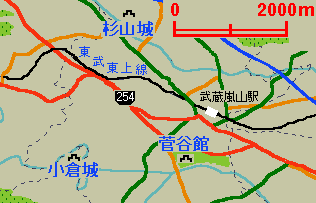
埼玉県比企郡付近は、西北から東南にかけての丘陵地帯で、関東平野の中心部へ続く鎌倉街道が古くから通っており、古代から栄えた場所です。
鎌倉時代には菅谷館、戦国時代には松山城の支城が点在しており、中世の城が数多く存在する地帯で、現在でも関越自動車道や東武東上線が走っている交通の要所です。(関係ないか!)
| 1つ前に戻る | ホームへ戻る |
埼玉比企の城
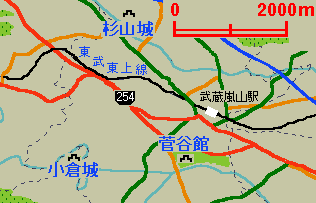
埼玉県比企郡付近は、西北から東南にかけての丘陵地帯で、関東平野の中心部へ続く鎌倉街道が古くから通っており、古代から栄えた場所です。
鎌倉時代には菅谷館、戦国時代には松山城の支城が点在しており、中世の城が数多く存在する地帯で、現在でも関越自動車道や東武東上線が走っている交通の要所です。(関係ないか!)
1つ前に戻る ホームへ戻る
菅谷館
|
所 在:埼玉県 比企郡嵐山町大字
地図[MapFanWeb] 交 通:東武東上線 武蔵嵐山駅 徒歩15分 種 別:中世 平城 鎌倉時代に畠山重忠の館としての記録が、吾妻鏡に残されています。畠山重忠は有能な武士で、頼朝の信頼も厚く、側近の一人として活躍しますが、北条氏が実権を握った後は謀殺されています。 戦国時代の前半には、太田道灌の息子資康が住居していた記録もあります。 その後は、北条氏により現在の城郭に整備されたとされていますが、詳細は不明です。 写真は本郭の掘で、かなり大型なものです。 城内は完全に公園化され、真新しい埼玉県立歴史資料館が三の郭内にあります。館内では菅谷館自身を始め、比企地方の城関連の展示がありました。 |
小倉城
|
所 在:埼玉県 比企郡玉川村
地図[MapFanWeb] 交 通:東武東上線 武蔵嵐山駅 徒歩60分 種 別:中世 山城 北条に属していた遠山氏の居城で、松山城落城と運命をともにしました。 城は、標高130mの南北に突き出た丘陵にあり、山の東側は嵐山渓谷、北側は槻川の断崖の要害ですが、展望はあまりきかないので、物見の機能は低かったようです。 西側の本郭と東側の二の郭が深い掘切で連結されて、両郭の南側に大小の郭が配置されています。 大手は、二の丸の東北に、小さな郭が列状に構成されている付近で、二の丸付近の一段下がったところに比較的大きな郭があり、隠郭とされています。上から眺めただけなので、その効果は把握していませんが、たぶん下からの敵にとって、いきなり現れる郭なんでしょう。(疲れていたので降りる気になれなかったのだ。) 上写真は、本郭の土塁の上にある碑です。このような土塁がぐるりと取り囲んでいて、本郭、二の郭ともかなりの広さを誇っています。 本郭西側にある帯郭の南端には、下写真の石垣の遺構があり、たぶん城門の遺構だと思います。 南隣の郭は、西側に枡形で口をあけているので、搦手の遺構になるようです。この城は、本郭と二の郭が逆の説もあるので、その説だったらこちらが大手になるのかな? その雰囲気は十分にあります。 遺構が良く残っている城ですが、整備はほとんどされてなく、看板は本郭しかありませんので、見学には縄張図が必要でしょう。 |
杉山城
|
所 在:埼玉県 比企郡嵐山町杉山字
地図[MapFanWeb] 交 通:東武東上線 武蔵嵐山駅 徒歩40分 種 別:中世 山城 杉山城は史料が乏しく、築城年代や正確の城主などは不明で、現在の遺構は戦国末期の築城のもので、北条氏と関東管領上杉氏の松山城攻防戦が激しくなった頃の築城とされています。その後は北条方の支城として機能し、北条攻めで松山城とともに落城しました。 南北に長い山で、標高100mの山頂に本郭が置かれ、西側の崖を除いて、南、東、北に郭が構成されています。 上図は日本城郭大系(新人物往来社)を参考にした杉山城の縄張図で、本郭を中心に各郭の連絡を良くした事、屏風折などの横矢を多用している事、馬出しがある事などの点で、中世の築城理念の縄張を、忠実に実現した教本の城として知られています。 杉山城へは、南麓の中学校横に寺があるので、裏の墓地あたりから山に入るとすぐ、南側の遺構にたどりつけます。公園としての整備がされてなく、看板は本郭にあるだけで、その他の指標は一切ありません。見学は縄張図を見ながらが良いでしょう。(北側、東側の登山口は確認してません) 南側の遺構には、大手、屏風折、喰い違いなどよく確認でき、杉山城の一番の見所です。東側もそれなりですが、南側ほどではありません。 中写真は本郭の掘で一番掘が深かったところです。上図だと”北1”の1の下あたりのコーナ部です。すぐ西側(写真とは反対方向)は土橋が直角に折れた構成になっていました。 下写真は北郭の小口で、これも直角方向に折れた枡形になってます。上図だと”北1”、”北2”の間の通路になります。 非常に良い城ですが、個人的にはもう少し”馬出し”が確認できればと思いました。木をすべて切れば良く確認出来るとは思いますが、そういうわけにはいかないでしょう。 ”遺構を保存するのは、現状維持が一番”という話をどこかで聞きましたので... |