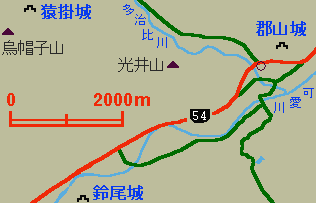
吉田町にある残りの城を紹介しましょう。吉田盆地は、広島県で唯一日本海側に流れる可愛川(えのかわ)と、それに注ぐ多治比川の合流点があり、川沿いの山々に郡山城を守る支城がたくさんありました。 猿掛城や鈴尾城もその一つで、他にもたくさんの城があるみたいです。郡山城をこのコーナーで紹介するのは心苦しいのですが、大河ドラマも終わったことなのでいいでしょう。(^O^)
| 1つ前に戻る | ホームへ戻る |
安芸毛利の城2
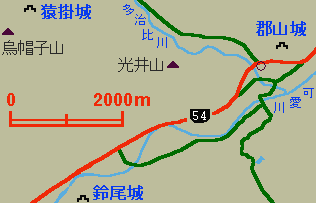
吉田町にある残りの城を紹介しましょう。吉田盆地は、広島県で唯一日本海側に流れる可愛川(えのかわ)と、それに注ぐ多治比川の合流点があり、川沿いの山々に郡山城を守る支城がたくさんありました。 猿掛城や鈴尾城もその一つで、他にもたくさんの城があるみたいです。郡山城をこのコーナーで紹介するのは心苦しいのですが、大河ドラマも終わったことなのでいいでしょう。(^O^)
1つ前に戻る ホームへ戻る
猿掛城
|
所 在:広島県 高田郡吉田町多治比
地図[MapFanWeb] 交 通:JR芸備線 吉田口下車 車で30分 種 別:中世 山城 築城や廃城の詳細は不明ですが、元就が27歳で郡山城に入城するまで、この城に居たことで知られる城です。 上写真は標高376mの猿掛山です。それほど高く見えないのは、麓で標高256mになるので、事実上は120mの山ですね。 麓には元就の父弘元と夫人の墓があり、少し東に行った登山口から10分ほどで寺屋敷曲輪に到着します。文字どおり寺があったところで、平坦部が確認できる以外はこれといった遺構もありません。 さらに10分ほど登ると頂上の本丸に至ります。 本丸は50m×20mほどの平坦部で、ここから東に4km離れた郡山城を望むことができます。本丸の北端には下写真の櫓台があり、10m四方の高さ3mで、なかなか立派な櫓台です。 麓の墓の裏から南へに50分ほど登山すると、標高529mの烏帽子山の山頂で物見丸があるようですが、さすがに登山する気力はありませんでした。 また、猿掛山の北西の山麓に出丸の遺構があったようですが、これも見逃しています。 |
鈴尾城
|
所 在:広島県 高田郡吉田町郷野寺福原
地図[MapFanWeb] 交 通:JR芸備線 吉田口下車 車で30分 種 別:中世 山城 福原城ともいいます。毛利の親類で重臣でもある福原氏の居城です。 可愛川沿いの標高316m、比高110mの盆地内に半島状に突き出た山で、西は入江方面、東は吉田盆地が見渡せる要所となっています。 写真は山頂から見た吉田盆地で、左端の山が直線で6km離れた郡山城です。(たぶん) 山頂の郭の中央には櫓跡と思われる小さな石塁があり、東側の中腹には大きな郭には元就生誕の碑が立っていました。 |
郡山城
|
所 在:広島県 高田郡 吉田町
地図[MapFanWeb] 交 通:JR芸備線 吉田口下車 車で20分 種 別:中世 山城 南北朝時代の1336年に、毛利時親が郡山東南麓に本丸(現在は旧本丸)を築いたのが最初で、以後戦国期に元就が山全体を要塞化、輝元の大改修を経て最大規模になりました。 1591年の広島城の築城後に廃城となり、関ヶ原後の防長移封を経て、1615年の一国一城令の破壊と、1637年の島原の乱での切支丹宗徒の籠城を恐れ、再度破壊が行われています。 上写真は歴史民俗資料館裏の登山口からみた郡山城で標高390m、比高190mの山です。やや縦方向になるので小ぶりに見えています。 遺構は、山頂の本丸を中心に6本の尾根に曲輪が展開しており、大小合わせて120以上あるらしいです。 私が見学した曲輪(見学コースそのものです(^O^))だけでも釣井の壇、御蔵屋敷跡、三の丸、二の丸、本丸を経て、満願寺跡、尾崎丸で、その他、名もない曲輪がごろごろあります。 本丸は二段で構成され中写真は櫓台とされている上段部分を、下段から撮ったものです。上段部分は10m×20m四方で、本丸の碑がありました。文字どおり最高位です。 その他、二の丸には若干ですが石垣が確認できました。満願寺跡から尾崎丸あたりの左側は、ものすごい急な斜面になってます。 尾崎丸には三段ほどの曲輪の列があり、その先200mほどには旧本丸が存在しますが、道はありません。 大河ドラマでもクライマックスのひとつだった郡山合戦で、元就は郡山城に軍兵、領民合わせて八千人で立て籠もり、城下でゲリラ戦を展開し尼子軍を撃退しましたが、尼子晴久率いる三万の兵が陣取ったのが、下写真の青光井山尼子陣所で、郡山城からすぐ目と鼻の先に位置します。 左が青山、右が光井山で、山中にはたくさんの曲輪があるようです。山間の台地が古戦場となっています。 |