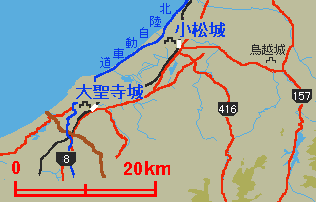
石川県で能登半島の根元部分が、加賀国にあたります。戦国期には織田軍を迎え撃つため、一向一揆軍が築城した砦、城郭がありますが、別のカテゴリで紹介するとして、近世の前田家の城を紹介しましょう。
前田家本城の金沢城以外には、藩主の隠居城である小松城、支藩の城(陣屋)の大聖寺城があります。ちなみに越中の富山藩も、加賀藩の支藩にあたります。
| 1つ前に戻る | ホームへ戻る |
加賀の城
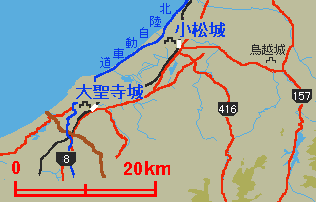
石川県で能登半島の根元部分が、加賀国にあたります。戦国期には織田軍を迎え撃つため、一向一揆軍が築城した砦、城郭がありますが、別のカテゴリで紹介するとして、近世の前田家の城を紹介しましょう。
前田家本城の金沢城以外には、藩主の隠居城である小松城、支藩の城(陣屋)の大聖寺城があります。ちなみに越中の富山藩も、加賀藩の支藩にあたります。
1つ前に戻る ホームへ戻る
小松城
|
所 在:石川県 小松市 丸ノ内二ノ丸
地図[MapFanWeb] 交 通:JR北陸本線 小松駅下車 徒歩20分 種 別:近世 平城 1576年には一向一揆の武将で、本願寺の家臣の若林長門が城主で、柴田勝家により攻略された後は、村上氏、丹羽氏と城主が移り関ヶ原を迎えます。 関ヶ原後は前田氏の領地となり城代が置かれました。1639年、江戸幕府は一国一城令の例外として、利家から三代目の利常の隠居城として小松の居城を認め、城として近世城郭の再構築がなされたようです。 利常は19年間小松城で隠居生活をおくり、その後は小松城番が置かれ、維新を迎えています。 明治の初めに掘はすべて埋められ、本丸、二の丸跡は高校の敷地になっており、三の丸は公園として日本庭園や公共施設などがあります。 上写真は、高校のグランドの南端にある櫓台の石垣で、打ち込みハギによる、ほとんど垂直に積まれた完成度の高いものです。 この辺は若干ですが高台になっていて、籠城の時は、北にある梯川から水を掘に引入れ、周辺を湖にして浮城にする構想だったようで、この櫓台の北側の下には舟着き場と推測される遺構もあります。 下写真は旧三の丸で、現在は芦城公園となっています。西側入口にほんの少しですが、城門跡の石垣と古木が残っています。 城下も良く残っており、古い家並や大きな寺など、周辺に残ります。 |
大聖寺城
|
所 在:石川県 加賀市 大聖寺地方町
地図[MapFanWeb] 交 通:JR北陸本線 大聖寺下車 徒歩20分で登山口 種 別:中世山城 近世陣屋 1335年、北条残党の名越時兼が、北陸の兵を引き連れ京に向かう途中、狩野一門の土豪がこの城で迎え撃ったと、太平記にあるのが一番古い記録で、のち一向一揆の拠点となり、一時は朝倉の所領となる時代を経て、柴田勝家の加賀侵攻により、織田、豊臣の武将が城主となっています。 関ヶ原後の1639年、加賀藩主の前田利常は、支藩として三男利治に七万石を分け与え、大聖寺藩が誕生し、以後維新まで続きました。 遺構は標高60mの錦城山に、本丸、二の丸、西の丸、東の丸、鐘ケ丸とそれぞれ独立した曲輪が存在します。 現状は、それぞれの曲輪の平坦部に公園、休憩所などあり、土塁なども確認できます。 上写真は、本丸と西の丸の間にある馬洗池で、このあたりが一番の見所でしょう。 大聖寺藩は、この錦城山に城を築いたのではなく、山の東側に陣屋を営んだようです。 下写真は、三代藩主利直が別邸として建てた長流亭で、国の重要文化財に指定されています。背後にある山は錦城山です。 |