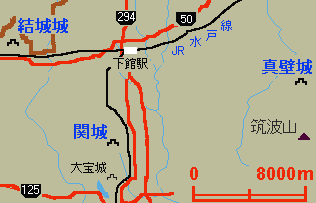
手ごろな家の近くの茨城県西部の城です。 このHPを作るまでは気にもしなかった名も無い城ですが改めて調べると、南北朝初期に南朝の主要拠点になった古城や、室町初期には幕府を敵にまわし籠城戦を行った城などがあり、石岡城や小田城などとあわせ常陸国には由緒正しい古城があります。
| 1つ前に戻る | ホームへ戻る |
茨城西部の城
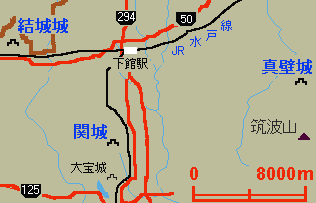
手ごろな家の近くの茨城県西部の城です。 このHPを作るまでは気にもしなかった名も無い城ですが改めて調べると、南北朝初期に南朝の主要拠点になった古城や、室町初期には幕府を敵にまわし籠城戦を行った城などがあり、石岡城や小田城などとあわせ常陸国には由緒正しい古城があります。
1つ前に戻る ホームへ戻る
結城城
|
所 在:茨城県 結城市 本町
地図[MapFanWeb] 交 通:JR水戸線 結城駅下車 徒歩30分 種 別:近世 平城 隣町の豪族小山政光の三男朝光が、鎌倉時代の黎明期に結城家を名乗り、結城秀康が越前に移封までの間、結城家の居城でした。 1440年、11代氏朝は、足利幕府間の争いで滅びた、関東公方足利持氏の遺児を奉り、幕府軍を敵にまわし結城城に籠城、のちに結城合戦と呼ばれ、全国にその名を轟かせることになります。 写真はわずかに残っている三の丸で公園になっています。この城には、家康の実子(秀康)を養子に迎える前に、結城家に伝わるお宝を城下に埋めた埋蔵金伝説が残り、公園のすぐ前の橋の下は、明治時代に掘り起こした跡といわれています。 |
関城
|
所 在:茨城県 真壁郡関城町
地図[MapFanWeb] 交 通:関東鉄道 常総線 騰波ノ江(とばのえ)駅下車 徒歩20分 種 別:中世 平城 結城家二代朝広の四男朝泰が、結城家の領地の一部を相続、地頭となり関氏を名乗ったのが始まりで、南北朝時代の初期、常陸における南朝の中心となった城です。 関城主の関宗祐は、1338年、吉野から海路で常陸に上陸した南朝方の北畠親房に協力し、1341年小田城(関城から西南20km)が落城すると、北畠親房を関城に迎え、関城は、南朝方の重要拠点として機能します。 2年後の1343年、北朝との籠城戦を経て落城。関宗祐、宗政親子は討死、北畠親房は吉野に戻っています。 上写真は関城城跡にある関宗祐の墓と城跡の説明看板です。 関城は、南を先端にした舌状の台地にある城で、かつての台地の下は大宝沼が広がり、それなりの要害であったようです。 中写真はその舌状の先端部分で、わずかですが高台になっているのが今でも分かります。 遺構は、本丸跡、二の丸跡といったまとまった遺構でなく、雑木林の中に土塁が確認できる場所がいくつかあります。 下写真は北朝方が、関城の物見矢倉を攻撃するために掘ったとされる坑道跡で、上記の関城城跡から東北に200mほどの田んぼの真ん中にあります。現在でも5mほど中に入れますが、それ以降は暗くて狭いのであきらめました。この作戦は途中で地盤が崩れたため失敗に終わっています。 関城の南4kmほど行くと、かつての大宝沼南限の高台があり、関氏とともに北朝と戦った下妻氏の大宝城があり、現在は大宝八幡宮になっています。 なんと、この関城から大宝城までの広範囲に渡り、昭和9年の早々に国指定史跡になっています。 |
真壁城
|
所 在:茨城県 真壁郡真壁町古町
地図[MapFanWeb] 交 通:JR水戸線 岩瀬駅 車20分 種 別:中世 平城 最初の築城は1172年、真壁長幹により築城されたといわれています。 初代の長幹は源平抗争、六代幹重は南朝に担架し落城、七代高幹が復興、12代慶幹は鎌倉公方との戦に敗れ、13代朝幹で再び復興、戦国期の17代久幹、18代氏幹と戦乱に明け暮れ、1602年に19代房幹が、佐竹氏に従い角館に移封になるまでの400年間、波乱に満ちた真壁氏による支配が続きました。 その後は浅野氏、稲葉氏と相次いで入封し、1622年に天領となっています。 遺構は本丸こそ町立体育館になっていますが、東側には田んぼの中に、二の丸、中城、外城、と展開していて、掘、館跡、櫓台?等、よく遺構が残っています。 上写真は本丸と二の丸の間にある掘の遺構で、写真右が体育館、すぐ後の山は筑波山です。 下写真は二の丸の最高位から東側を撮った写真で、中央の田んぼの中に、土塁が走っているのが分かると思います。櫓台跡のような遺構も確認できますね? 土塁の下には掘があり、さらにその向うの木が茂っているところが鹿島神社で、この裏には外堀の遺構も良く確認出来ます。 |