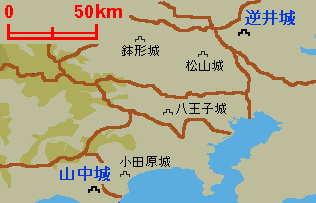
北条の城の第2弾です。逆井城は、佐竹氏との最前線の城として築城されたようで、広大な飯沼を背にした横矢、二重土塁を用いた平城です。 山中城は、小田原防衛のために箱根の天険を利用した山城で、畝掘、障子掘の遺構が整備されている城として有名です。
ともに、当時の北条流築城技術をフルに活用した城ですが、秀吉の北条攻めであっけなく落城しました。北条流築城理念は、近世の築城理念に大きく貢献したと勝手に思っています。
| 1つ前に戻る | ホームへ戻る |
北条の城2
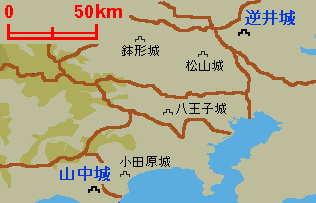
北条の城の第2弾です。逆井城は、佐竹氏との最前線の城として築城されたようで、広大な飯沼を背にした横矢、二重土塁を用いた平城です。 山中城は、小田原防衛のために箱根の天険を利用した山城で、畝掘、障子掘の遺構が整備されている城として有名です。
ともに、当時の北条流築城技術をフルに活用した城ですが、秀吉の北条攻めであっけなく落城しました。北条流築城理念は、近世の築城理念に大きく貢献したと勝手に思っています。
1つ前に戻る ホームへ戻る
逆井城
|
所 在:茨城県 猿島郡 猿島町逆井
地図[MapFanWeb] 交 通:JR宇都宮線 古河駅下車 車で40分 種 別:中世 平城 もともとは逆井氏の居城で、1575年に北条氏が攻略し落城。1577年北条氏繁が再構築しました。南北30kmにわたる飯沼(江戸時代に埋め立てられる)を要害として、常陸佐竹氏、その他の諸侯へ備える最前線の城として、重要な城であったようです。 1590年の秀吉の北条攻めで廃城になってますが、城の攻略戦の有無などくわしいことは分かっていません。 遺構は、一曲輪(本丸)、西二曲輪、東二曲輪、三曲輪があり、現在は塀、門、二重櫓、櫓門、井楼、主殿などの模擬建造物が建てられ整備の行き届いた公園となってます。(行き届きすぎという感もあるが...) 遺構の見所は、一曲輪の鐘掘り池の手前の外桝形がよく確認できる点と、本丸東側の二重土塁が良いです。 当然といえばそれまでですが、この二重土塁は内側土塁が外側より高くなっていて、比高二重土塁と紹介があり、北条氏の建築法の特徴のようです。 上写真は西二曲輪に建てられた模擬主殿の庭で、背後に模擬二重櫓も写ってます。 下写真は一曲輪を北側にある西仁連川を挟んで、撮ったものです。一曲輪の内部はあまり整備されてなく草木が生えていますが、周辺の土塁はよく確認できます。 左側に写っている模擬井楼に登ると、一曲輪の横矢掛りがよく確認できます。 |
山中城
|
所 在:静岡県 三島市 山中新田地内
地図[MapFanWeb] 交 通:JR東海道本線 三島駅 バス30分 種 別:中世 山城 北条氏康が小田原防衛のために、箱根の天険を利用し築城した箱根十城の一つで、その中でも、城内に東海道を取り込んだもっとも主要な城だったようです。 北条氏勝を城主、北条家三家老の松田康長が城代で、秀吉の小田原征伐を直前にして大規模な改修、拡張が行われたようです。 1590年3月、秀吉軍の箱根攻めの主将には徳川家康があたり、山中城攻めの総大将は豊臣秀次で、これに掘尾吉春、山内一豊らの合計七万の兵で攻撃したとされています。一方北条側は、松田康長はじめ四千の兵で籠城しますが、さずがに堅城でも兵の数が圧倒的に違えば、ひとたまりもないようで、わずか半日で落城しています。 遺構は良く整備保存されていて、障子掘、畝掘の遺構がある城として良く知られています。城の縄張は、西側に口をあけた三日月型に曲輪の列をなしていて、南側から岱崎出丸、国道1号線(旧東海道)をはさんで、三の丸、本丸、二の丸(北条丸)、北の丸と続き、二の丸から西側へ無名曲輪(元西櫓)、西の丸、西櫓の構成になっています。 上写真は岱崎出丸の北側にある畝掘です。 岱崎出丸には最南端が、すり鉢状にくり貫かれているすり鉢曲輪があり、その目的が理解できなかったのですが、看板には武者だまりであると考えられると説明がありました。その他岱崎出丸には御馬場曲輪があり、南側の薬研掘が見事です。 豊臣軍はこの岱崎出丸から攻撃して、これを攻略後陣所にし三の丸、二の丸、本丸を落したとされています。 中上写真は西の丸から撮った障子掘で、写真右側は西櫓です。この西櫓は最西端に位置しており、東側は障子掘、残り3方向に畝掘が放射状に造られており、山中城一番の見所でしょう。 中下写真は二の丸(別名北条丸)にある櫓台に上がって撮った虎口方向の写真で、通路の両側に土塁が整備されているのが良く分かります。 下写真は北の丸から撮った、本丸の東端にある天守台で、写真の左側が山中城内で最高位の天守台です。いわゆる天守閣はなく井楼、もしくは簡素な櫓がせいぜいのようです。掘の底は雪のおかげて、若干ですが畝掘が確認できます。 写真奥には見にくいですが、本丸から北の丸への架橋が復元されています。北の丸は、本丸の南側をのぞき三方を土塁で囲まれた広大な曲輪で、土塁の下には城内で一番深そうな空掘がありますが、整備はされていません。 このように山中城は見所もたくさんあり、説明看板も豊富でよく整備もされていますが、東海道を取り込んだ縄張のおかげで、国道1号線が城内を分断しており、トラックがビュンビュン走っているので、閑散とした雰囲気はありません。 |