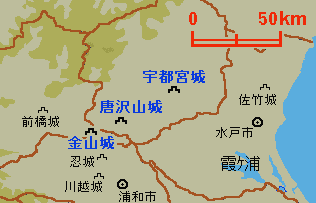
関東七名城と呼ばれている城があります。
いつ誰が選んだか不明ですが、江戸の藩城からの選択ではなく、戦国時代に難攻不落として名高い城の選択のような気がします。(勝手に思っているだけです。江戸の藩城の選択だと、佐倉城、古河城、館林城など、他も良い城があると思うのです。)
でも、なぜこのような選択になったのか不思議ですね? 残念ながら保存状態の良い城は、皮肉にも江戸時代初期に廃城になった、唐沢山城、金山城の中世山城のみです。
| 1つ前に戻る | ホームへ戻る |
関東七名城
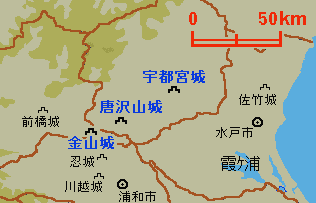
関東七名城と呼ばれている城があります。
佐竹城、宇都宮城、唐沢山城、金山城、前橋城、忍城、川越城 このうち、佐竹城、唐沢山城、金山城は中世の城であり、近世には廃城になっています。
いつ誰が選んだか不明ですが、江戸の藩城からの選択ではなく、戦国時代に難攻不落として名高い城の選択のような気がします。(勝手に思っているだけです。江戸の藩城の選択だと、佐倉城、古河城、館林城など、他も良い城があると思うのです。)
でも、なぜこのような選択になったのか不思議ですね? 残念ながら保存状態の良い城は、皮肉にも江戸時代初期に廃城になった、唐沢山城、金山城の中世山城のみです。
1つ前に戻る ホームへ戻る
宇都宮城
|
所 在:栃木県 宇都宮市 本丸町
地図[MapFanWeb] 交 通:東武宇都宮駅から徒歩15分 種 別:近世 平城 最初の築城は、藤原秀郷といわれていますが定かではなく、1062年、宇都宮氏の初代となる藤原宗円が、本格的な城郭を構えたのが始まりといわれています。 以来、22代に渡り宇都宮氏の居城となり、小田原攻めにも豊臣方に味方したのですが、太閤検地で宇都宮領内での所領の不正が発覚したため、宇都宮氏は所領を取り上げられてしまいます。(こうなるまでにいろいろ経緯があるのですが...) その後は城主が数家入れ替わり、本多正純が城主となって有名?な釣り天井事件が起こります。 釣り天井は伝説に過ぎないようですが、正純が幕府の許可なく城郭の大修復工事を行なったため、日光参拝で宇都宮城に立ち寄る将軍家を、暗殺するための釣り天井があるとウワサが流れたようです。 真相はよくある権力争いの陰謀にはまったのでしょう。 正純は宇都宮城を、日光口を守るふさわしい城にしたかったようです。 正純の後は譜代大名が数家入り、最後は戸田氏に収まり維新を迎えます。戊辰の役で建造物はほとんど燃えてしまい、その後の都市開発もあって遺構はほとんどありません。 上写真は本丸公園の土塁です。本丸はずいぶん昔から空き地になっており、藩兵の訓練場だったようです。 下写真は旧百間掘りにある樹齢380年の大銀杏の木です。(隣のビルと比べてみましょう) |
唐沢山城
|
所 在:栃木県 佐野市 富士見町
地図[MapFanWeb] 交 通:東武佐野線 田沼駅 徒歩1時間 種 別:中世 山城 この山城も平安中期に藤原秀郷が築城したといわれています。一時廃城になった後、1180年に藤原有綱が佐野氏を興し唐沢山城を再建しました。 戦国時代の1559年、27代昌綱が城主の時、小田原の北条氏政が大軍を率いて唐沢山城を攻めますが、上杉謙信の援軍もあって勝利しています。 28代宗綱のときには上杉家との仲が悪化し、1567年に謙信が攻めますが、この時も落城はしませんでした。 小田原征伐時、佐野氏は北条方だったのですが、宗綱の弟房綱のとりなしで領土を安堵されています。家康の天下になってから、江戸から20里以内の山城禁止令?により、唐沢山城は廃城になり春日岡城(佐野城)に移っています。 遺構は良くのこっています。上写真は大手門とされるところで、右横にある天狗岩に登って上から撮ったものです。枡形の喰い違いの遺構が良く残っています。 中写真は大炊の井で今でも十分に水があります。横の大きな空掘りには橋が掛かっていて、かつては曳き橋だったようです。 その他、三の丸、二の丸、とも良く遺構が残っていますが、所々で道が舗装されており、本丸北側は一般車も通っているようなので少し残念ですね。 下写真は本丸の石垣で、秀郷を祭っている唐沢山神社の回りを取り囲んでいます。また、本丸南側と南城には、関東の山城では珍しい規模の大きな石垣が見れます。 山城禁止令とは別の理由で廃城となった伝承があります。江戸が大火事になった時、唐沢山でいち早く発見した佐野信吉が江戸に駆け付け、家康に拝謁してこのことを説明すると、「江戸を見下ろすとはなにごとだぁ」で廃城になったということです。 |
金山城
|
所 在:群馬県 太田市 金山
地図[MapFanWeb] 交 通:東武伊勢崎線 太田駅 車で15分 種 別:中世 山城 平安時代には砦があったようで、鎌倉時代に新田義重が城郭として整備します。その後一時的に廃城になり新田一族の岩松氏が再入城しました。戦国時代初期に下剋上により横瀬氏が主となり、改築を繰りかえし大城郭として構えることになります。 戦国期の横瀬氏の立場は微妙で、最初は古河公方に組し北条とのつながりも強かったようですが、上杉政虎(謙信)が関東管領についた頃には、上杉方となり小田原攻めにも参陣しています。 1563年ごろ横瀬成繁は、姓を由良とあらため、66年頃に上杉に背いてからは、数度に渡り越後勢に金山城を攻撃されています。しかし金山城は一度も落ちることなく、難攻不落の城として名を馳せますが、北条氏と運命を共にして廃城になりました。 山全体に曲輪や出丸が尾根づたいに散乱しており、かなり大規模な山城であることが縄張図で分かりますが、詳細は見ておりません。 上写真は三の丸付近で発掘、復元されている石垣で住居跡みたいです。もう少し西の方へ行くと、馬場とされている細長い曲輪がありますが、大きなシートがかぶっており発掘調査の真っ最中でした。 下写真は水ノ手郭にある大きな貯水池できれいに復元されています。 推測ですがオリジナルの石は取り除かれているようです。石を取り除くのであれば、復元はしなくても良いと思うのですが皆さんはどう思いますか? 本丸は天守曲輪とも呼ばれ、新田神社が鎮座しています。北西側には石垣が残っているようですが、場所がよく分かりませんでした。もう一度よく見たい城ですね。 |