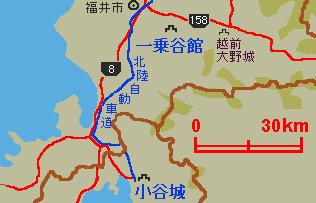
浅井、朝倉両家が、織田信長に滅ぼされる経緯は割愛して、両家の城を中心に見てみましょう。
浅井家の方は小谷城、朝倉家は一乗谷館で、共にそのまま廃城となってしまい、今は辺鄙なところになっているのですが、それが幸いしてか当時の遺構が良く残る中世城郭が見られます。
共に有力の戦国大名として、恥ずかしくない規模の城で、城下も栄えたことでしょう。それゆえかつての反映が見られない現在の状況や遺構を見ていると、まさに滅ぼされたという感じです。
現在、一乗谷館跡の方はそれなりに観光地になっているようですが、小谷城は今一つかな?城好きであれば、どちらの城も見て損はないでしょう!
| 1つ前に戻る | ホームへ戻る |





