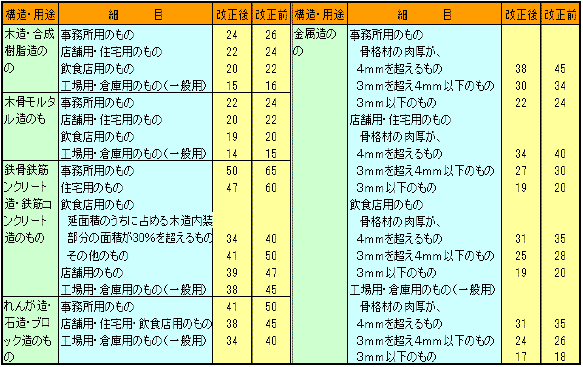
| 平成10年度所得税に関する改正点 |
平成10年度税制改正において、法人税制の抜本的見直しが行われたことに伴い、個人の事業所得等に係る課税制度についても見直しが行われました。所得税に関する主な改正は次のとおりです。
- 平成10年分所得税の特別減税
- 所得控除額の引き上げ
- 住宅取得等特別控除の改正
- 通勤手当の非課税限度額の引き上げ
- 事業所得等に係る改正
平成11年分の所得税から適用される改正
少額減価償却資産 割賦基準
退職給与引当金 製品保証引当金 特別修繕引当金
| TAXに戻る |
平成10年分の所得税について、特別減税が実施されることになりました。
なお特別減税額の合計が平成10年分の所得税額を超える場合は、その税額が限度とされます。
特別減税額 本 人 38,000円 控除対象配偶者又は扶養親族1人につき 19,000円
次の所得控除額が、それぞれ次のように引き上げられました。
控除の種類 区 分 改 正 前 改 正 後 配偶者控除 同居特別障害者である一般控除対象配偶者 680,000円 730,000円 同居特別障害者である老人控除対象配偶者 780,000円 830,000円 扶養控除 同居特別障害者である一般扶養親族 680,000円 730,000円 同居特別障害者である特定扶養親族 830,000円 930,000円 上記以外の特定扶養親族 530,000円 580,000円 同居特別障害者である同居老親等 880,000円 930,000円 同居特別障害者である老人扶養親族 780,000円 830,000円 障害者控除 特別障害者 350,000円 400,000円
この特例の控除を受けられる人の合計所得金額要件が3,000万円以下(改正前2,000万円以下)に引き上げられました。この改正は、平成10年1月1日以後に居住の用に供するものから適用されます。
平成10年1月1日から平成12年12月31日までの間に居住の用に供した場合の控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高1,000万円以下の部分に適用される控除率が改正されました。住宅取得等特別控除額は、住宅を居住の用に供した年により次のとおりです。
住宅を居住の
用に供した年控除期間 1,000万円以下
の部分1,000万円超
2,000万円以下
の部分2,000万円超
3,000万円以下
の部分控除限度額 平成10年 当初3年間 2% 1% 0.5% 35万円 残り3年間 1% 25万円 平成11年 当初2年間 2% 1% 0.5% 35万円 残り4年間 1% 25万円 平成12年 当初2年間 1.5% 1% 0.5% 30万円 残り4年間 1% 25万円 平成13年 6年間 1% 1% 0.5% 25万円
給与所得者が支給を受ける通勤手当の1月当たりの非課税限度額の最高額が10万円(改正前5万円)に引き上げられました。この改正は平成平成10年1月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者(現金主義によることを選択している人を除きます)でこれらの所得の金額に係る取引を正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則に従って記帳している人がその記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに期限内提出の確定申告書に添付している場合の青色申告特別控除額が、最高45万円(改正前35万円)に引き上げられました。
平成9年分の改正で、簡易な簿記の方法により記帳している人(現金主義によることを選択している人を除きます)が所定の帳簿書類その他の書類に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに期限内提出の確定申告書に添付することにより最高45万円(改正前35万円)の青色申告特別控除額の適用が受けられる経過措置の適用期限が平成14年分まで5年延長されました。
平成10年4月1日以後に新たに取得する建物及び営業権の償却方法は定額法とされました。
建物の耐用年数がおおむね10%から20%程度短縮され、最長のものでも50年を限度とされました。この改正による主な建物の耐用年数は次のとおりです。
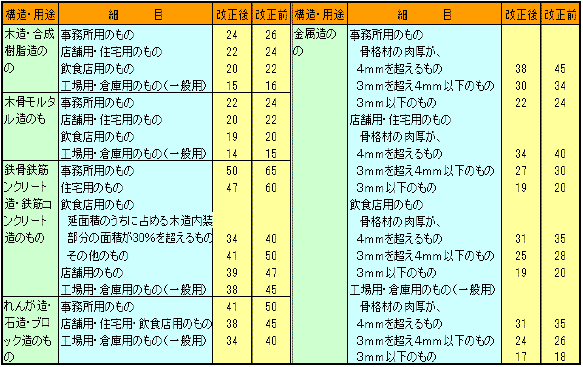
年の中途で業務の用に供した機械装置、器具備品、車両等に認められている初年2分の1簡便償却制度が廃止されました。
平成10年10月1日以後に締結される契約のリース取引の目的とされている減価償却資産で、非居住者または外国法人の国外において行われる業務の用に供される資産の償却方法が、リース期間定額法とされました。
「電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除の特例」の適用対象となる電子機器利用設備の範囲に、一定の電子計算機でその年に指定事業の用に供したものの取得価額の合計額が160万円以上のものが加えられるとともに、適用期限が2年延長されました。
「機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除の特例」が設けられました。 青色申告者である中小企業者が平成10年6月1日から平成11年5月31日までの期間内に、新品の(1)取得価額が230万円以上の機械装置、(2)事務処理の能率化等に資する100万円以上の一定の器具備品、(3)長距離輸送の効率化等に資する一定の車両運搬具、(4)海上運送業の用に供される船舶で一定のものを取得等して、同期間内に事業の用に供した場合には、その事業の用に供した年については、
イ.取得価額(船舶については取得価額の75%相当額)の30%相当額の特別償却を受けるか、
ロ.取得価額の7%相当額の特別控除(事業所得に係る所得税額の20%相当額を限度)を受けることができます。新品の(1)から(3)までの減価償却資産を物品賃貸業者からリース契約により賃貸して事業の用に供した場合には、その事業の用に供した年については、その費用の総額((1)については300万円以上、(2)については140万円以上のもの)の60%相当額に対して7%相当額の特別控除(事業所得に係る所得税額の20%相当額を限度)を受けることができます。
従来の債権償却特別勘定が貸倒引当金制度に含められ、繰入限度額の計算が期末貸金を個別に評価する債権(その一部につき貸倒が見込まれるものに限ります)と一括して評価するその他の債権とに区分して計算する方式に改正されました。
平成10年4月1日以後に締結する請負契約からは、「工事期間が2年以上でかつ請負金額50億円以上の長期大規模請負工事(製造を含みます)」については工事進行基準により各年分の収入金額及び費用の額を計算しなければならないこととされました。(経過措置)平成10年4月1日から平成13年3月31日までの間に締結した契約については150億円以上、平成13年4月1日から平成16年3月31日までの間に締結した契約については100億円以上の工事に限って工事進行基準が強制適用されます。
平成10年分の改正事項のうち、平成11年分の所得税から適用される主な改正は次のとおりです。
- 少額減価償却資産の取得価額基準の引き下げ
必要経費算入の対象となる小額減価償却資産の取得価額基準が10万円未満(改正前20万円未満)に引き下げられます。
ただし10万円以上20万円未満の資産については、通常の償却方法に代えてその業務の用に供した年毎に一括して3年間で均等償却する方法も認められます。
- 割賦基準の方法の廃止
割賦販売等に係る割賦基準による損益の計上が所要の経過措置を講じた上、廃止されます。この改正により原則として、商品の販売等を行った年の収入金額及び費用の額に算入されることになります。
ただし、賦払期間が2年以上であるなど一定の要件を満たす割賦販売については、延払基準の適用が認められます。
- 退職給与引当金の累積限度額の引き下げ
現行の退職給与引当金の累積限度額が期末要支給額の20%(改正前40%)に引き下げられます。
(経過措置)平成11年分から平成15年分までの各年分については、累積限度額に乗ずる率が年毎に斬減され最終的に20%に引き下げられます。
一 定 の 率 平 成 11 年 分 37% 平 成 12 年 分 33% 平 成 13 年 分 30% 平 成 14 年 分 27% 平 成 15 年 分 23%
- 製品保証引当金制度の廃止
製品保証引当金制度が廃止されます。
(経過措置)平成11年分から平成15年分までの各年分については、現行の繰入限度額に対して年度毎に6分の1ずつ減少する引当てが認められます。
一 定 割 合 平 成 11 年 分 6分の5 平 成 12 年 分 6分の4 平 成 13 年 分 6分の3 平 成 14 年 分 6分の2 平 成 15 年 分 6分の1
- 特別修繕引当金制度の廃止
特別修繕引当金制度が、所要の経過措置を講じた上、廃止されます。なお、船舶、溶鉱炉等特定の固定資産については特別の修繕に要する支出に備えるための特別修繕準備金の積立てが認められます
| TAXに戻る |