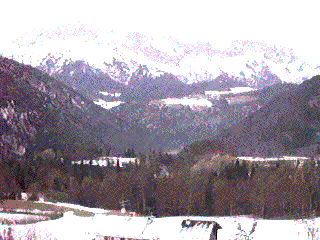カント「判断力批判」読了。これで三批判書読破ですが、予想に反してこれが一番読みにくい本でした。ゲーテがこの本をえらく推してましたが、詩を音楽よりも上の最高位の芸術として捉えていたところがお気に召したのでしょう。(12/28)
「チェリビダッケの庭」鑑賞。冗長。2時間半も文字通り禅問答そのものの巨匠(マエストロ)のモノローグにつきあわされるのはかないません。やたらと「現象学」を引用するのも困ったもの。ただしふんだんに出てくるリハーサル・シーンで実際に紬だされる音楽には説得力がありました。ブルックナーの九番を聞き直してしまった。(12/27)
「デジタル小津安二郎展−キャメラマン厚田雄春の視」(東京大学総合研究博物館)に行ってきました。厚田カメラマンの膨大な遺品に含まれる「捨てカット」から「東京物語」の本来の色調をコンピュータにより再現した5分間の映像の美しさが確認できました。坂本龍一が音楽をつけた無声映画「その夜の妻」(1930年)の特別上映も楽しめました。(12/20)
「梅沢由香里の平成棋院2」購入。プレイステーション用ソフトですが、囲碁思考ルーチン・アルゴリズムの世界的権威ケン陳博士が作成した実戦対局編はなかなかの腕前です。かつてパソコン用ソフトの弱さにがっかりしたものですが、進歩の度合いに感心しました。由香里二段は戦術戦略編の解説と実戦対局編での対局者の声で出演してます。(12/19)
山下洋輔Winter Jazz Night(原宿クエスト)今村監督作品「カンゾー先生」のサントラの為に編成されたカンゾー・バンド全員によるライブを聞きました。小山彰太(Ds)とのかつての山下トリオを彷彿とさせるノスタルジックな演奏やバイオリンの調べが美しいJ.G.BIrd等、ゴージャスなフルメンバーでの演奏を堪能。(12/15)
柳美里「ゴールドラッシュ」読了。父殺し以降の展開は、独特の閉塞感を生み出しながらも、主人公がそれまで生きてきた狭い生活空間を離れて物語のスケールを自ら拡げていくには幼すぎるという限界に阻まれて尻すぼみの印象を受けますが、この小説の一番の魅力はそうしたプロットにかかわる部分ではなくて、才気あふれるハードボイルドな文体そのものでしょう。居間に戻ったとき、少年は奇妙な意志の力が伸びてきて自分をとり囲むのを感じた。ふるえがぴたりと止まり、深部から涌き上がる力、逆らうことができない力、その力によって前に押し出され、静けさのなかにすべり落ち、花瓶をつかみとった瞬間、少年を押し止めていた力が決壊した。(12/12)
ドイツロマン派絵画展(静岡県立美術館)鑑賞。ライプツィヒ美術館、ケルン市立ヴァルラフ=リヒャルツ美術館より提供されたベートーヴェン、ゲーテの時代に生きたドイツの画家たちの作品展ですが、ゲーテの肖像や「雪の中の樫の木」が印象的。図らずも県立美術館巡り第二弾になってしまいましたが、ここは常設ロダン展に力を入れてる美術館です。(12/12)
浜松MUSIC ACT Togashi Meets His Friends(アクトシティ浜松・大ホール)を聞いてきました。富樫雅彦をリーダーに、およそ30年ぶりに集結した日野、山下、佐藤、峰、井野各氏の豪華メンバーによるステージです。山下洋輔さんと佐藤允彦さんのピアノ・デュオも70年代にレコードで共演以来の貴重なステージでした。二台のグランドピアノから豊饒な響きが会場いっぱいに広がりました。今夜の演奏は来年3月に二枚組CD(予価五千円)として発売されるそうです。(12/11)
森高千里TOUR 1998"SAVA SAVA"(東京国際フォーラム)最終公演に行きました。20代最後のステージを堪能。3曲目「二人は恋人」の途中で咳こんでストップというアクシデントがあったり、ツアー30公演の千秋楽ということもあって、よくしゃべる千里さん。紅白落選については、事務所の後輩モーニング娘に譲ったとか、やたらMCが長い。お陰で終電になってしまいました。(12/8)
ゲーテ「鉄の手のゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン」読了。執筆当時24才のゲーテの出世作ですが、フランスによる文化支配からドイツ文化を解放したとまで言われた戯曲です。福田和也が「ヨーロッパの死」の中で指摘しているのは、啓蒙思想の全盛期の中でなぜゲーテが封建的権利としての「自由」をこの作品の中で語らなければならなかったか、ということですが、単一の筋、単一の場面の中で話が完結する古典的ドラマトゥルギーの規則を破壊し自由なスタイルで描いたということが何よりも画期的なことだったのでしょう。(12/7)
「筒井伸輔展」に行ってきました。今回の目玉は「バッタの足」です。ガラス・ケースに納められたこの巨大な足は、ボタンを押すと空気圧送ポンプによって大きな唸り音と共に可動します。ぎゃははははと笑うのが正しい反応でしょう。値段がちゃんとあって、もし買い手がついたらアクリル・ケースに作りなおしてくれると画伯がおっしゃってました。金七拾伍萬円也。(ミヅマアートギャラリー12/26まで)(12/5)
ZARD「GOOD DAY」「新しいドア」今日同時発売の二枚ですが、一曲づつ二枚に分けたものでお値段も一枚五百円という趣向。青いほうは、ビューティラボのCM曲。暗い曲だけど、サビの部分でいやに馬力だして歌ってるのが印象的。先に曲があって後から詞をつけるのがいつものパターンらしいけれど、ちょっと字余り部分が目立つ感じ。緑のほうは、サッポロ冬物語のCM曲。こちらのほうがいつもの泉水節で親しみやすい。(12/2)
「ワイマルのロッテ」一年がかりでやっと読了。「文学界」に福田和也が連載している「ヨーロッパの死−トーマス・マンとフルトヴェングラー」にも引用が出てくるけれど、この小説が発表された時(1939年)、本国では非難の声があがったそうです。偉大な人物(ゲーテ)は民族の誇りであると同時に禍でもある、というトーマス・マンの主張にはナチズムへの非難がこめられており、そうした背景なしにはこの小説は語れないのかもしれませんが、この作品で描かれている数日の出来事(老年のゲーテと「若きウェルテルの悩み」のヒロイン、ロッテの再会)には、一年がかりで味わうに足る中身の濃さがありました。(12/1)
「ミュージック・フェア」見ました。松たか子と石井竜也の共演。「君がいるだけで」のデュオは秀逸。「サクラ・フラリ」はてっぺいちゃんが歌うと米米ソング。松たか子は口がゆがんでいる。(11/29)
「プルガサリ伝説の大怪獣PULGASARI」をビデオで鑑賞。金正日将軍の総指揮下で制作された北朝鮮版ゴジラ又は大魔人です。特撮部分は日本のゴジラのスタッフが担当。怪獣の中に入ってる人もゴジラをやってた人だそうです。大エキストラ動員が全体主義国家の映画の特徴ですが、ゲッペルスが撮らせた歴史映画「コルベルク」のほうが数段質が高いです。単調さにただただ退屈しました。円谷プロの定番シリーズに遠く及ばない出来。(11/26)
高野史緒「ヴァスラフ」読了。仮想と現実の狭間で跳躍する伝説のダンサー、ヴァスラフ。戯曲形式で描かれたヴァーチャル絵巻ですが、映画「トロン」などでお馴染みの舞台設定でありながら斬新に感じられるのは、著者が後段で比較しているように共時性を持つユングとニジンスキーへの思い入れがうまく作品に反映されているからかもしれません。著者が高校時代に書いた習作の第八稿にあたるというこの作品の出版を叱咤激励して促したのは、皆川博子、佐藤亜紀両女史だそうです。(11/25)
「自然に帰れミレーと農民画の伝統」(山梨県立美術館)「落ち穂拾い」のヴァリエーションをはじめとしたミレーの農民画を鑑賞しました。濃い緑色に見える水辺の色調が鮮やかな「鵞鳥番の少女」は、個人蔵と表示されていましたが、提供者は知る人ぞ知る筒井康隆さん。かつて「スタア」の舞台道具として一般にお披露目されて以来の公開です。二つ右に掛かっていた姉妹作「鵞鳥を追う少女」との違いは歴然としていました。隣接する県立文学館にこの作品を夏目漱石が模写した水彩画があったのが面白かったです。(11/22)
皆川博子「死の泉」読了。第32回吉川英治文学賞を受賞したこの作品を通して感じられる迫力は、丁寧に散りばめられたナチ文化のディテールが産み出すものでしょう。主要な舞台であるオーバーザルツベルクやベルヒテスガーデンのヒトラーやゲーリングの別荘、現存するホテル・テュルケン、ヒムラーの黒いカメロット、映画「コルベルク」等々の正確な描写は、実際にそれを見てきた私をうならせました。後半の展開がいかにも類型的ミステリーのそれで、ちょっと大味に感じましたが。(11/20)
獅子座流星群ウオッチしました。午前3時から4時の間、東の空に位置する獅子座から放射状に流れる流星群を見ました。時おり1等星ぐらいの明るさで長く尾をひく大物も見えましたが、それほど頻繁に登場する訳でもなく、寒さにがまんできなくなって4時前に引き上げました。ちょうど獅子座にぶら下がるような形で輝いていた火星も綺麗でした。(11/18)
「ハーフアチャンス1CHANCEsur2」鑑賞。アラン・ドロンとジャン=ポール・ベルモンドの28年ぶりの共演作です。大スターの共演が売りの映画なんてあざといという印象が先立つのですが、この作品も例外ではありません。作品中の登場人物ではなくて、ドロンとベルモンドだという目で見てしまうからですが、二人とも歳をとりました。ヘリコプターからたらした縄梯子を昔同様ベルモンドがスタントマンなしで昇るシーンは感涙ものです。二人が昔の顔に戻ってガンを手にする時にクロード・ボラン作曲の「ボルサリーノ」のメロディーがちらっと流れるのがしゃれてました。そういえば、ラストの高飛び先も「ボルサリーノ」と同じだなあ。(11/15)
パリ・オランジュリー美術館展ORANGERIE(Bunkamuraザ・ミュージアム)に行ってきました。モネの連作「睡蓮」で有名なパリの同美術館の老朽化建物改修中の引っ越し公開です。「オレンジの温室」が名前の由来とのこと。ルノワール、セザンヌの油彩がまとまって見れるのが売り物ですが、モネの「アルジャントゥイユ」(1875)も見事な色彩のバランスで目をひきました。(11/15)
山本周五郎「雨あがる」読了。黒澤監督の遺稿となった脚本の原作です。ファースト・シーン。「どん底」の舞台に似た木賃宿。外は「羅生門」の冒頭を思わす雨。山田五十鈴演じる三十年増が悲鳴のような声をあげて喚く。「またあの女だ」三船敏郎演じる主人公三沢伊兵衛が寝ころんだまま気づかわしそうにうす目をあけて香川京子演じる妻おたよを見る。おたよは縫い物を続けている。どこから切ってもこれは黒澤ワールドそのもの。撮ってほしかったなあ。(11/13)
「ヴォルテール回想録」読了。フリードリヒ大王とヴォルテールは親交があったどころか、秀吉と利休の関係に似た愛憎関係にあったことがよくわかりました。ヴォルテールはフランス国王の密使として大王と政治的な接触をもったことがありますし、また熱心な招聘にこたえて侍従として仕え修辞学を教授したこともありました。この本の中で、ある時は辛辣な悪口をまじえて風刺的に、またある時は素直に賛辞を惜しまずに描かれている大王の日常の描写はとても興味深いものです。同時代人カントが大王に心服していたと同時にヴォルテールにも多大な影響を受けていたことは著書での様々な引用からもあきらかですが、「筆が笑っている」と評されたヴォルテールの文章の面白さは、カントの退屈な文章とは正に対照的です。佐藤亜紀女史はヴォルテールの頭のよさには本を読んでいてうっとりするとまで言ってました。「私は(フランス)宮廷で最も無益な種族に属する一侍従が、ベルリンで無益な一侍従になったところで、ヴェルサイユに衝撃を与えようとは想像もしていなかった。私はフランス国王に非常に悪い心象を与えた。といって、その分だけプロシア王に喜ばれたわけでもなかった。プロシア王は心の奥では私を馬鹿にしていた」(11/12)
村岡暫「フリードリヒ大王 啓蒙専制君主とドイツ」読了。18世紀プロイセンのフリードリヒ二世の伝記を読みました。ひたすら無謀とも思える戦争の日々。ヨーロッパのほとんどの強国を敵にまわした七年戦争を戦いぬき、ドイツ統一の基礎をかためた人物ですが、ナチ第三帝国の領袖たちが崇拝していたのも頷けます。SS長官ヒムラーは配下のSS部隊を騎士団になぞらえて、ヴェヴェルスブルクに城まで作り大王を祭っていましたし、ルドルフ・ヘスがシュパンダウの刑務所で自殺したのは大王の誕生日だったと記憶しています。フリードリヒ大王にとってはフランス文化が生活の規範であり、ヴォルテールと親交があったことに啓蒙君主としての精神性の背景を見た気がしました。(11/10)
カント「実践理性批判」読了。幸福と道徳性という相反するものが必然的に結合する最高善においては、心の不死、自由、そして神の現存という三つの必然的条件が要求される。う〜ん、難しい。倫理学史上に輝く古典ですが、一番有名なのは結びにおける次のくだりでしょう。「私の上なる星をちりばめた空と私のうちなる道徳的法則」同時代人だったベートーヴェンがこれを会話帳に書き取ってます。(11/7)
「小説家の時間」文句のある奴は前に出ろ 渋谷の周辺2KMしか電波の届かないFM RADIO STATION XP (88mhz)の公開生放送を聞いてきました。作家佐藤亜紀さんと評論家小池真理さんのトークでしたが、夜中の10時半にスタートして終電のなくなる時間までの第一部が終わっても居残る熱心な聴衆を前にして、お二人は二本目の赤ワインに突入。第二ラウンドは、ドストエフスキーの「悪霊」論や笠井潔批判などの後、ついには筆者にも飛び入り質問のご指名がかかり、大蟻食党首に「私のファンクラブの会長のジャン・ポールさん」と紹介されてしまいました。次作として伝記を執筆中の「メッテルニヒは、めめしい男だから好き」という話から、「モンタイユー」(アナール派)の歴史観を自作に反映させてみたかったという執筆動機を語り、次いで「プライベート・ライアン」とホメロスの描いた戦闘シーンの比較をきっかけにお得意の戦争論へと話がすすみました。更に小池さんの訴訟の顛末が小一時間続き、最後に現代文学論に移ったところでやっとお開きになりました。実に4時間の長丁場でした。疲れた〜。(11/3〜4)
「ダイヤルM」鑑賞。ヒッチコック版を観たことがハンデにならずに楽しめる出来になってます。いかにも目鼻が利きそうな刑事が出てくるのにほとんど活躍しないで、あくまで夫婦の問題として事件が解決するところが気に入りました。ヒロインをグレース・ケリーと比較するのは酷。(11/3)
F1日本GP決勝。青ランプ直前にシューマッハ痛恨のエンジン・ストール。クラッチが焼き切れた模様。よく最後列から一時3位まで盛り返しましたが、88年のセナの再現はならず。今年はハッキネンの年だったのでしょう。KEIKOの「君が代」独唱は音程がはずれていたなあ。(11/1)
F1日本GP鈴鹿に行ってきました。不況の世の中を反映してかスポンサー広告やサーキットの華レース・クイーンの姿も少なく寂しい会場風景でしたが、観客動員数についていえばあいかわらずの盛況。公式予選はシューマッハ怒涛のポール・ポジション・ゲット。決勝の好勝負が期待されたのですが。(10/31)
森山威男PIT INN 2daysを聞いてきました。怪物ドラマー健在。田中信正のピアノがモダンかつパワフルで好感がもてました。森山さんのMCは面白い。「久々の新宿なので何か感慨があるかと思ったけど、何もないんですね。休憩の間、何か思いついたら次のセットで話します」とか「自分はドラマーに向いてないと思います」という発言に爆笑。「親父が三日前に亡くなりました」という発言にも冗談だと思ったのか、笑い声をたててる人がいました。(10/30)
森高千里「サファリ東京」プレステ版を入手しました。エアロスミスが先駆けた楽器演奏ゲームもしっかりと取り込んであります。モリタカの場合はもちろんドラムス。他にもライブビデオの編集ゲームや曲名合わせの神経衰弱ゲームなど盛り沢山ですが、熱烈ファンを除けばゲームとしての対象年齢は小学生までだろうなあ。(10/24)
阿佐ヶ谷ジャズストリート'98に行ってきました。神明殿(神楽殿)で行われた薪能的味わいの山下洋輔プラス津上研太の熱演を堪能しました。「カンゾー先生」のテーマ曲もデュオで聞くと曲の真水の構成が浮き彫りになって新鮮でした。また、アンコール「J.G.Bird」では「MILESTONE」の引用があったりとひと味違う仕上がりでした。(10/23)
ホメロス「イリアス」読了。古代ギリシアの騎士道的戦いを描いた英雄叙事詩ですが、写実的な戦闘描写に驚きました。このまま忠実に映画化したら、「プライベート・ライアン」どころか、巷にあふれるスプラッタ・ホラーまっさおの傑作残酷映画になることまちがいなし。黒澤明は「乱」を神の視点で描いたと言ってましたが、この叙事詩では神々が地上に積極的に介入して双方に加勢しますので「乱」以上の乱れぶりと言えましょう。(10/22)
「ソムリエ」第二回見ました。吾郎ちゃんはともかく、菅野美穂が重要な役まわりですね。弟子になるんですね。カリフォルニア・ワインで乾杯。(10/20)
「タブロイド」第一回見ました。テンポがよくて快調な出だし。日刊紙の社会部からタブロイド夕刊紙に異動させられた記者、常盤貴子の決め科白「人間への好奇心、真実への冒険心があれば新聞は生き延びます」「女は顔よ」がかっこよかった。ともさかりえもいい味だしてます。(10/14)
エクトール・フェリシアーノ「ナチの絵画略奪作戦」を読みました。第二次世界大戦中、ナチによってフランス占領後に組織的に略奪された数々の名画の行方を追った本です。ヒトラーの命により計画されたリンツ美術館やゲーリング国家元帥の個人別荘カーリン・ハルに向けて軍用列車に詰まれ運ばれていった略奪美術品は、戦後運良く元の持ち主に戻ったもの、行方不明のもの、暫定的に預けられたルーブルなどの美術館に返還者不明のまま今も所蔵されているものなど様々な運命を辿って今日に至っています。本書では触れられていませんが、一昨年私が訪れたカーリン・ハルに面した湖にゲーリングが脱出間際に沈めた作品もあったと聞いています。(10/13)
ジェームズ・タレル展(世田谷美術館)観てきました。光と知覚の関係をテーマにした現代アメリカ作家の本格的個展です。展示室そのものが壮大な光のオブジェである作品群を堪能しました。20分間一人で暗闇の中、道を選んですすんでいくブラインドサイトやCTスキャナー(ガスワークス)、電話ボックス(テレホンブース)、美容院のパーマ(ライトサロン)を思わせる個別体験型の作品はいずれも人気で予約順番待ち。「Orca」(1968年)など制作年度を見てその先進性に驚かされました。(10/11)
横濱JAZZプロムナード '98に行ってきました。ベイスターズのリーグ優勝の余韻さめやらぬ横浜は一転ジャズの街になってました。メインのランドマークホールにこの日まず登場したのは、坂田明ハルパクチコイダとゲストの小室等。坂田さんが「おどれ〜竿竹〜」と絶叫し場内一体となった後、お目当てのカンゾー先生バンドが登場。オープニングの10TH THEMEからカンゾー先生の映画音楽を含めてラストのクルディッシュ・ダンスまでジャズの醍醐味を満喫しました。(10/10)
村上“ポンタ”秀一Welcome to My Life聞きました。デビュー25周年を記念するこのアルバム完成でハイになった酒乱ポンタ氏に先日遭遇しましたが、その気持ちが伝わってくるような楽しいアルバムに仕上がってます。豪華ゲストがすごい。ボーカルだけでも泉谷しげる、井上陽水、EPO、大貫妙子、桑田佳祐、沢田研二、NOKKO、矢野顕子、山下達郎、吉田美奈子。圧巻はラストのWELCOME TO MY RHYTHMのドラム・メドレー。構成がちょっとビートルズの「アビー・ロード」を思わせます。森高千里と森山威男が共演しちゃうなんて正に夢の顔合わせ。(10/10)
甲子園の横浜優勝シーンに続いて、新番組「眠れる森」見ました。野村尚の脚本によるミステリー。謎のストーカーキムタクはともかくとして、中山美穂と仲村トオルの共演は「ビーバップ・ハイスクール」以来ではないか。懐かしい。ミポリンがちゃんと列車の中で麒麟麦酒を飲んでいたのに苦笑。(10/8)
松たか子「アイノトビラ」彼女の二枚目のアルバムです。オープニング曲を除く14曲のうち9曲が彼女の作詞。映画音楽風のインストゥルメンタルのオープニング曲は、松たか子作曲だというのだからかっこいい。わずか45秒の曲なのでもったいない気がしながらずっと通して聞いてみたら、最後にやってくれました。この曲に自作の詞をつけてピアノで弾き語りしています。子守歌なんだけど、ポール・マッカートニーの中位の出来のバラードみたいでいい雰囲気。残りのほとんどを書いてる武部聡志のメロディ−は総じて野暮ったい。(10/6)
木戸衛一編著「ベルリン過去・現在・未来」読了。異分野の五氏による学際的ベルリン論です。第1章では旧東独の集合団地マルツァーンの現状が、第2章ではギュンター・グラスの問題作「広野(Ein weites Fed)」で象徴的に描かれている西側主導のドイツ統一の功罪が、第3章ではベルリン・フンボルト大学の「清算」問題に視点を当て、旧西側の教育学が旧東側を駆逐している実態が、第4章ではプロテスタント教会の統一問題が、そして第5章では時の為政者の思惑によってころころ変わる「道路名に見るベルリン史」が論じられてます。「広野」はまだ邦訳がでてないのかな。読みたくなりました。(10/4)
ディドロ「ラモーの甥」読了。ゲーテやヘーゲルを魅了した18世紀フランス風刺文学の傑作ですが、私(哲学者)と彼(大作曲家ラモーの甥)が4月のある日の午後、パレ・ロワイヤル広場に面したカフェでオペラ座が始まる5時半までの間、様々なテーマについて語り合うという話です。ゲーテは自ら独訳して自国へ紹介してますし、「ファウスト」のメフィストフェレスとファウストの対話はこの小説がモデルになっているという説もあるそうです。またヘーゲルは大著「精神現象学」の中で3箇所にわたって引用しています。私(真正直な意識)の即自的な単調さに較べて、彼(自堕落な意識)の方が混乱と分裂を自覚(対自化)しているというところが、正にヘーゲルの弁証法に適ったスタイルだったのでしょう。(10/3)
森高千里TOUR 1998"SAVA SAVA"(中野サンプラザ)を聞いてきました。NEW ALBUMの中の曲を中心に構成されたステージでしたが、大きな「蒲焼き・うなぎ」の暖簾が登場した「ザルで水くむ恋心」では、ご自慢のドラムをたっぷり披露。これビートルズの「ヘルター・スケルター」のつもりなんだろうな。「気分爽快」のイントロは「ユー・キャント・ドゥ・ザット」だし。「17才」もアダルトなアレンジになっていたし、ご本人も二十代最後のツアーであることを意識したステージであったと言えましょう。(10/1)
「ガーシュウイン生誕百年バースデイ・コンサート」(かつしかシンフォニーヒルズ)を聞いてきました。ピアノ山下洋輔、井上道義指揮新日本フィルの「ラプソディ・イン・ブルー」は迫力満点。ぶっぱやいテンポのカデンツアは練習中に流して弾いたのがマエストロのお気に召して、本番でも採用された模様。(9/26)
小林信彦「怪物がめざめる夜」を読みました。タモリを思わせる無名の芸人がラジオでカルト的人気を得て、育ての恩人たちを攻撃しだすというモダン・ホラー小説。これで東京三部作読破。(9/25)
「カンゾー先生」今村昌平監督の最新作を観ました。坂口安吾の原作の舞台、伊東を瀬戸内に移して撮った作品です。音楽はもちろん山下洋輔。筒井さん、山下さん御臨席の試写会でブラックな笑いを満喫。(9/24)
ガルシア=マルケス「族長の秋」読みました。新聞に載った黒澤明追悼文のひとつに、マルケス自身がこの小説を黒澤監督に映画化してもらいたくて来日時に会っていろいろと話し合ったということが書かれてました。孤独な独裁者の最期を様々な登場人物によって語らせるこの作品独特のスタイルには、映画「羅生門」の影響があきらかに感じられました。六つの章に分かれていますが、全編改行なしの文章の途中で固有名詞が出たとたんにその人物に瞬間的に語り手が変わるという禁じ手も慣れるとリズムが心地よく、その語り口の妙を堪能しました。(9/23)
カント「純粋理性批判」
読了。ニュートン力学に代表される近代的世界了解の認識論を定礎した書といえ
ましょうが、さすがに難解で、ただ字面を追って読み飛ばすだけでも一月かかり
ました。主観と客観(存在論的には主体と客体)の一致を三項図式(意識対象−意識
内容−意識作用)の構図でとらえようとした訳ですが、この図式で考える以上、神の
存在、非存在とも否定できるアンチノミー(自己矛盾)に陥る訳で、カントもそ
うとう苦しんでこの本を書き上げたようです。後半の方で自分は地球外生物の存
在を信じるという件がありましたが、総じてユーモア感覚の乏しい本でした。講
談社現代新書の近刊「カントの人間学」を読むとご本人はなかなかユーモラスな
人生を送ったようですが。(9/21)
THE JASON BONHAM BAND聞いてきました。日本ツアーの最終公演で、新宿リキッドルームでのライブです。一言で言えば、史上最強のコピーバンドでしょう。ジミー・ペイジがレッドツェッペリン=ジョン・ボーナムであると言っていたのがはからずも証明されたステージでした。「ロックンロール」「移民の歌」「コミュニケーション・ブレイクダウン」「ブラック・ドック」「天国への階段」そのほかそのほか。おとっつぁんそっくりの風貌も感慨深いですが、なによりボンゾ直伝のパワフルなドラムは、言ってみれば伝統芸能みたいなものですから、文化遺産としてぜひ次の世代(息子がいるってMCで言ってました)に伝承していってほしいと思います。(9/19)
小林信彦「ドリーム・ハウス」今日も読んでしまいました。東京三部作の一作めですが、この小説では謎や伏線らしきものが放置されたまま終わるのが心地よいですね。アントニオーニの「欲望」みたいで。作中で主人公が書いてるエッセイの中に「(小学生の時に)新人・黒澤明の「姿三四郎」の絵コンテを描いた」という件がありましたが、今週号の週刊文春の連載エッセイでも触れてました。カラー作品になってからの黒澤明は「画家」に戻ってしまったという意見に同感。(9/18)
小林信彦「イーストサイド・ワルツ」読みました。「ムーン・リヴァーの向こう側」の姉妹編、というよりは正編にあたる作品です。実際、重要な場面で両作品共そっくり同じ科白がでてきます。この作品を読む気になったのは、東映Vシネマ「イーストサイド・ワルツ悦楽の園」というタイトルで映画化されているのを見つけたからです。主演は石橋蓮司、大竹一重。ほぼ原作に忠実な脚本ですが、R指定になってるだけあって二人の絡みシーンにやたら力こぶが入った作品でした。(9/17)
プルタルコス「プルターク英雄伝」セルトリアス伝読みました。ベートーヴェンはじめ、ナポレオン、シェークスピアまで魅了したこの英雄伝ですが、ベートーヴェンは「日記帳」にこのセルトリアス伝から抜き書きしています。セルトリアスが山国を通った時に住民が通行税を要求したのに対して、随行者達は激怒したが、彼は「凡そ大事を企つる者は時間を得るを以て最も急務とするが故に、余等は今其時間を買ひ取るのである」と言って諭したというくだり。印象的です。(9/16)
小林信彦「ムーン・リヴァーの向こう側」読みました。性的悩みを抱える39歳のコラムニストと27歳の謎多き女性との東京を舞台にした恋愛小説です。東京の街の描写がとてもリアル。東急文化会館の屋上に古本屋があったなんて、思わず確認しにいきたくなってしまいました。ヒロインの挙動不審な振る舞いもあとの「謎解き」でなるほどと思いました。主人公に関係する東京の裏面史にあたる事件の設定が見事。小説の世界とはいえ、この世に起こることで自分に無関係のことなんてないんですね。(9/15)
ハンス・クナッパーツブッシュ指揮ワーグナー「ニュルンベルクのマイスタージンガー」全曲聞きました。1950〜51年、巨匠62歳の時にウィーンのムジークフェラインで録音された世界初の全曲録音盤です。「筆記体」と呼ばれる遅いテンポで有名な指揮者ですが、晩年のミュンヘン・フィルとの序曲集で聞かれる演奏と違って、きびきびとした若々しい演奏です。一般的に晩年になるほど指揮者のテンポが遅くなるというのは肉体的な問題も大きく影響しているようで、クナも若い頃はむしろ早いテンポでぐいぐい圧すタイプの指揮者だったようです。(9/15)
「永井豪世紀末展」見てきました。30年にわたる全作品の原画、原稿、スケッチ、フィギュア、ビデオなど450点に及ぶ大展示会でした。「ハレンチ学園」「キューティーハニー」「デビルマン」などのビデオの前に座り込んで一日中会場で過ごしているのではと思われる熱心な若者ばかり。記念グッズ購入にも長蛇の列。やはり世紀末という時代が永井豪を待っていたのでしょう。先日読んだ「ダンテ神曲」の生原稿を見れて大満足でした。(9/12)
「金日成のパレード」東欧の見た“赤い王朝”観てきました。右翼の妨害にそなえて劇場前には警察の車が待機するというものものしさでしたが、場内は満員。ポーランドのアンジェイ・フィディック監督の視点は、努めて主観を排して、被写体を提供されるままに淡々とキャメラにとらえています。それだけに巨大なマス・ゲームと一糸乱れぬ行進、そして全てに「偉大なる首領様のおかげで」という枕言葉がつく人々の発言の不気味さが際立ちます。本番前に待機する人たちのいわば日常的な顔を写しとっているところは好感が持てました。当たり前ですが、始まる前はみんな座ってくつろいで待ってる訳です。レニ・リーフェンシュタールが「意志の勝利」の前年の党大会を撮った習作にもそういう「乱れた」場面があったように思います。(9/12)
森高千里New Album「Sava Sava」聞きました。いつもの森高節なんだけど、なにかパンチが足りない。ジャケットもおもいきりシック、というか地味。同時発売のビデオ・クリップ集「MORITAKA VIDEO CLIPS'FIVE'」も見ましたが、こちらはグー。「二人は恋人」のカラー・バージョンが気に入りました。もうすぐ始まるライブが楽しみです。(9/11)
「ファウスト」四態読了。言わずと知れたゲーテの代表作ですが、手塚治虫が生涯三回にわたってこの作品を漫画化しています。一作めの「ファウスト」は20歳の時の作品で、第一部と第二部を一緒にしてオーソドックスに描いた作品。二作目は「百物語」というタイトルで42歳の時の作品。こちらは戦国時代の日本を舞台にしたものですが、少年ジャンプ連載時にリアルタイムで読んでいながらこれが「ファウスト」だとは知りませんでした。そして遺作となった「ネオ・ファウスト」。70年代の日本を舞台にした第一部が見事な出来映えだけに、第二部が連載第二回で終わってしまったのはかえすがえすも残念です。(9/10)
「L.A.コンフィデンシャル」を観ました。面白い。終わってみれば登場人物ほとんどみんな悪い奴だったけど、ひとくせありそうな連中ばかりの中で、オスカーもらったキム・ベイシンガーは紅一点でもうけ役でしたね。(9/6)
「ヴァーグナー家の黄昏」を読みました。リヒャルト・ヴァーグナーの曾孫であり、本来なら現当主ヴォルフガングの息子としてバイロイト音楽祭を引き継ぐ人間であるはずの著者ゴットフリートがヴァーグナーの思想・音楽とナチズム、ホロコーストにつながる歴史的関連を暴き、ドイツで一大センセーションを巻き起こすことになるまでの半生が描かれています。それにしても父ヴォルフガングとの確執のすさまじさ。息子を許さない父がおふれを出すことによって、実際に世界中の劇場で仕事ができなくなってしまうというバイロイトの威光の力にも驚きます。かつてのベストセラー「ある愛の詩」をちょっと思い出しました。(9/5)
劇場版「ビーン」をビデオで見ました。主人公の設定は美術館の監視員でしたが、先日監視員のいない美術館(大塚国際美術館:徳島県鳴門市)に行きました。実際に名画にさわってしまっても誰も怒らないという緊張感の弛むシチュエーションですが、それもそのはず、古今東西1000点の名画を全部陶板で再現したという世界初の美術館でした。(8/26)
「フェイス/オフ」をビデオで見ました。腕利きのFBI捜査官(J.トラボルタ)が息子の命を奪った凶悪犯(N.ケイジ)と顔を入れ替えるという実におぞましい設定。途中でやめようかと思いましたが、我慢して手術シーンを通過したら面白くなってきました。考えてみたらこれは「王子と乞食」と同じ古典的な設定な訳で、二人の正反対な人物をめぐる人間模様の厚みのおかげで、水準的なアクション映画を超える出来映えに仕上がりました。(8/25)
ゲーテ「ヴィルヘルム・マイスターの演劇的使命」を読みました。「原マイスター」と呼ばれる「修行時代」「遍歴時代」の原型にあたる作品です。長谷川宏氏が「新しいヘーゲル」(講談社現代新書)の中で、ヘーゲルの「精神現象学」と「ヴィルヘルム・マイスター」との相似を指摘していますが、「意識」という名の主人公がさまざまな境遇に投げ込まれて経験を重ね、精神的に成長していく過程が似ているという訳です。面白い相似だと思いました。(8/24)
佐渡裕「僕はいかにして指揮者になったのか」を読みました。レナード・バーンスタインの最後の弟子であり、気鋭の若手指揮者である著者の半生記です。彼がいわゆる小澤征爾・斉藤秀雄の教条的指揮法とは一線をかくす、天性の指揮者だったバーンスタインの直弟子であることがよくわかりました。レニーが大阪弁を話してるかのように書いているのが面白い。最近出たショスタコーヴィチの交響曲第5番のビデオ(本とセットの指揮者ハウトゥー物)は、彼の現在の仕事ぶりがうかがえて面白いです。コンサートマスターも「佐渡さんならここまでやってくれるだろう、という期待通りオケを鳴らしてくれるのが嬉しい」というようなことを言ってました。(8/21)
草稿完全復元版「ドイツ・イデオロギー」(渋谷正編・訳)を読みました。モスクワに現存する序文、アムステルダムに現存するオリジナル草稿を日本で初めて子細に調査・研究した成果で、草稿紙面をありのままに再現するため見開き頁を使用しています。従来、廣松版が画期的なクリティーク版ということになっていましたが、訳者がこれまでの底本は全て誤りと言い切る自信は、「あんたそこまでやる」と言いたくなるような地道な筆写と解明の裏付けがあってのことでしょう。(8/21)
ワーグナー「トリスタンとイゾルデ」をビデオで観みました。近年のバイロイトでのライブで、指揮はバレンボイム。以前ヨハンナ・マイヤーがイゾルデを演じた舞台がビデオになってましたが、こちらのイゾルデは評判のワルトラウト・マイヤー。ヒラリー・クリントンみたいなヘア・スタイル、コスチュームがモダンといえばモダン。(8/20)
A.シュニッツラー「夢小説」を読みました。今世紀前半のウィーンを舞台にしたこの小説を、現代のニューヨークに置き換えて、トム・クルーズ主演で現在製作中なのがスタンリー・キューブリック監督の新作「EYES WIDE SHUT」です。クライマックスの秘密仮面舞踏会シーンが「時計じかけのオレンジ」をしのぐエロチックかつ幻想的な絵になることは間違いないと思いますが、本来は短篇であるこの原作をどうやって肉づけて映画化するのか楽しみです。公開は遅れに遅れて来年2月。(8/15)
George Martin「In My Life」を聞きました。ビートルズの名プロデューサーの引退記念アルバムで、ゆかりの人たちのビートルズ・カバー集ですが、ジェフ・ベック、ゴールディ・ホーン、ショーン・コネリーといった顔ぶれがゴーシャス。アレンジは御本家だけあって、オリジナル・アルバムと同じ香りがただよってます。一番の驚きは、ビリー・コノリーの「Being For The Benefit Of Mr.Kite」です。正にサーカスの呼び出しのおっさんそのもの。ジョンが生きていたら絶賛していたでしょう。(8/8)
「勇気をだして」かとうれいこ主演の30回連作の昼メロですが、今日が15回め。密室殺人事件の容疑者で、かつ被害者の妻、そして不治の病に蝕まれる身というヒロイン。もっぱら下田を舞台した人情物という感じで前半が終わりましたが、これから殺人事件の謎のほうも進展していくのでしょう。私は主治医が怪しいのではないかと思ってます。(8/7)
冨田恭彦「哲学の最前線 ハーバードより愛をこめて」を読了。現代アメリカ哲学を小説形式で手際よく紹介しています。佐藤亜紀さんに薦められて読みました。中でも紹介されているリチャード・ローティの「哲学と自然の鏡」を続けて読みたくなりました。新書づいて「マルクス遺稿物語」なんていうのも一気に読んでしまった。(8/2)
「オースティン・パワーズ」AUSTIN POWERS観ました。60年代ファッションと007のパロディてんこ盛り。劇場前は長蛇の列。みんな笑いに飢えているのか。エリザベス・ハーレーが可愛い。(8/2)
相川七瀬「crimson」は相変わらずの七瀬節。ジャケットが秀逸。ドリカム「SING OR DIE」は米国進出を狙った国際バージョン。名刺代わりにここぞとばかり声域の広さを見せつけてるところがいい。角松敏生「REALIZE」はB面の「Splendid Love」がお目当てでしたが、Sala盤の魅力に遠く及ばず。彼女どうしてるんだろう。山下洋輔「DR.KANZO」は、NYトリオとの旧作「WIND OF THE AGE」の中にテーマの原型がありました。(8/1)
「富樫雅彦トリオ」を新宿ピットインで聞きました。山下洋輔(P)、井上信義(B)の好サポートを得て富樫の繊細かつ鋭利なブラシさばきが光ってました。ビル・エヴァンスの名曲「MY FOOLISH HEART」では、山下さんのピアノに応えてドラムでメロディーを奏でてました。あとで山下さんもこれには驚いたと言ってました。この顔ぶれでバラード集をライブ・レコーディングするそうですが、とても楽しみです。(8/1)
「ダンテ神曲」永井豪(講談社文庫)を読みました。19世紀の天才版画家ギュスターヴ・ドレの作品をモチーフに、ダンテの大作を漫画化した力作です。佐藤亜紀さんが解説で書かれているように、「語り得ないものを敢えて語ろうとする」斬新な試みという意味で、豪チャンの力技はけしてドレに劣るものではないでしょう。いい仕事してますね。ただ、地獄編の冒頭でフィレンツェの街並みが描かれているんですが、ダンテの時代にはまだ大聖堂はできてなかったはずですよ。(7/31)
「MIB(メン・イン・ブラック)」をビデオで見ました。頻繁に使われる特殊技術が全く違和感なく絵になっていて見事。(7/30)
「百年の孤独」G.G.マルケスの傑作。今頃読んでるのもなさけないですが、ひじょうに疲れました。最初、ながったらしい登場人物名が句読点の役目をはたすように感じて、すいすい読めるような気がしたのですが、読了まで6日かかりました。(7/29)
「モンティ・パイソン・アット・ハリウッドボウル」をBSで見ました。おなじみのメンバーが舞台で大活躍。哲学者をネタにした替え歌やあぶない人種差別ジョークにインテリ層中心の観客がよく反応していました。(7/28)
「オデュセイア」ホメロスの傑作。あらゆる遍歴物のお手本でしょう。ぶっとんだストーリーが快感。(7/23)
「GODZILLA」見たんですが、だいたい評判通りの映画ですね。ゴジラだと思わないで見れば面白いという意見もありますが、いかんせんゴジラが幕間にひっこんでる間の人間さまのドラマに見るべきものがなく、キャストも魅力なし。エンディングの「カシミール」のカバーはかっこよかった。フューチャリング・ジミー・ペイジというのが泣かせます。(7/19)
「カンディード」ヴォルテールの傑作。あらゆる遍歴物のお手本でしょう。ぶっとんだストーリーが快感。バーンスタインのオペラ版も有名ですね。(7/12)
「哲学者の密室」笠井潔の本格推理長篇ですが、筒井さんも「本の森の狩人」で指摘しているように重厚な推理とハイデガー哲学の出会いが画期的。(7/11)
楽茶碗の四○○年/伝統と創造(サントリー美術館)に行ってきました。初代長次郎から当代(15代)楽吉左衛門までの歴代作品を一挙に展示してヨーロッパで好評を博した展覧会の凱旋です。初代と当代のぶっとび方が両極端で面白かったです。以前、天問という当代の展示会があった時に、会場の近くで当時出たばっかりの黒いNSXを見つけて、こっちのほうが当代の作品よりよっぽど黒楽らしいと思ったことがあります。(7/5)
「魔の山」(1981年西独映画、日本未公開ビデオ版)見ました。トーマス・マンの代表作の映画化ですが、ロッド・スタイガー、シャルル・アズナブールと言ったベテランが脇を固め、主人公ハンス・カストルプ役の若手俳優を盛り立てていました。原作のダイジェスト版の域を脱しえないのはこの手の映画化の常ですが、実際にあのサナトリウムや個性的な登場人物たちを絵にして見せてくれただけで満足。(6/28)
吉行和子一人芝居「ミツコ 世紀末の伯爵夫人」(国立劇場小劇場)観劇しました。実在した明治のシンデレラ一代記ですけど、吉行さんの円熟して堂々とした演技を堪能しました。(6/23)
「タイタニック」見ました。この作品は大画面で見ないとだめでしょうね。映画よりも細野晴臣のおじいちゃんの話のほうが面白かった。(5/19)
綾辻行人「十角館の殺人」読了。あっと驚くトリックの本作で本格推理界に鮮烈デビューした著者。その後プレステのソフトにもなった「館シリーズ」の第一作です。映像化できないトリックという意味では筒井さんの「ロートレック荘事件」と共通するものがあります。(5/10)
コーディ「イエスの遺伝子」読了。欧米で爆発的に売れた本で、脱サラの著者の第一作ですが、キリスト教圏の人たちの吟線に触れるアイデアだけが売りの大味な近未来ミステリー。(5/9)
北野武監督「HANA−BI」鑑賞。私は「ソナチネ」の方が面白かったです。なにか賞狙いを最初から意識してるあざとさが感じられました。(5/6)
「ヒットラーを狙え!独裁者 運命の7分間SEVEN MINUTES」を見ました。クラウス・マリア・ブラウンダウワー、ゲオルク・エルザー出演。時限爆弾の設定時刻の7分の遅れでヒトラー暗殺に失敗する主人公の物語。ダッハウ収容所に収容された彼は、終戦間近に処刑されました。合掌。(5/5)
「ソナチネ」鑑賞。北野作品を見たのは初めてです。自分の型を持ってることが強みですね。理屈なきに面白いエンターテイメント。(5/5)
ヘーゲル「精神現象学」読了。難解な哲学用語を平易な日本語に置き換えた、読みやすさに定評のある長谷川新訳版です。本書は「精神」の冒険遍歴の物語です。どうやって「精神」が究極的な「真理」に達したかを証明する手だてがはっきりしないという弱点を持つ本書ですが、同時代のディドロの著書の引用があったり、カントよりはずっと親しみやすい魅力的な哲学書だと思いました。昨年暮れにベルリンのヘーゲルの墓参りをしました。(5/4)
B.ウィリス主演「ジャッカル」鑑賞。フォーサイスの原作ではターゲットはドゴールでしたが、こちらはアメリカ大統領夫人。どう作っても基本プロットがしっかりしていれば面白くなるという見本。(4/28)
話題の郷ひろみ「ダディ」読みました。ワイドショーで紹介されてない部分もなかなか面白い。結構むちゃくちゃをやってますね、芸能人って。しかし、友里恵のお父さんも言ってるように女性問題だけが「別れる(唯一の)理由」ではないんでしょう。(4/12)
「めぐり逢い」第一回を見ました。常盤貴子は石井竜也監督の第一作「河童」の試写会で実物を見かけたことがあります。山口智子の長期休養が話題になったりする中、とぎれなくTV連ドラの常連というのはすごいことですね。(4/10)
ペイジ&プラントの新作「WALKING INTO CLARKSDALE」聞きました。ツェッペリンから起算すると19年ぶりのスタジオ録音になるという期待作ですが、オッと思ったのは一曲目のアコースティック曲だけ。音の録り方がなにかチープでなじめませんでした。(3/31)
石井竜也「H」聞きました。てっぺいちゃん初のソロ・アルバムですが、例えばここ2年くらい海外で生活などしてきて事情知らない人にこれそのまま米米の新作と言って聞かせたら素直に信じるだろうなあというのが感想です。ロバート・プラントのソロ一枚目のアルバムを聞いた時の印象と一緒。彼のメロディ−・メーカーとしてのセンスはたいへんなものですね。(3/28)
小林恭二「カブキの日」読みました。これは一言で評すれば「宮崎アニメの世界」だと思いました。上質のエンターテイメントでありながら伝統芸能であるカブキの世界をきちんと描いてフレームが骨太なところも似てますし、またキャラクター設定の多彩さも似てます。主人公の蕪(かぶら)は、もののけ姫だし、あやめは、エボシさまでしょう。蕪を松たか子が演じて映画化しないかな。(3/26)
佐藤亜紀「フリードリヒ・Sのドナウへの旅」読みました。女史久々の短篇ですが、「1809」では最小限の描写にとどめていた実際に起こったナポレオン暗殺未遂事件の犯人の調書とボナパルトの事件についての反応を描いてます。(3/21)
福島次郎「三島由紀夫−剣と寒紅」読みました。同好の士だからこそ知りえた文豪の実像に圧倒されました。特に後半、神風連の取材で熊本を訪れた際の三島の生き生きとした描写は、旅に同行してるように感じられるほどの臨場感でした。(3/14)
「ジャズ大名スーパー・セッション」柿田川チャリティ・コンサートを聞いてきました。渡辺香津美、山下洋輔、筒井康隆のお三方による楽しい演奏でした。(3/6)
「筒井ワールド6」を観てきました。今回は絶対のお奨めです。「さなぎ」の舞台演出の見事さ、「おれは裸だ」の衝撃的演技、「ウィークエンド・シャッフル」の濃縮された密度の濃さ。お見逃しなく。(2/8)
 来月の16日で閉館になる鎌倉シネマ・ワールドに行ってきました。小津安二郎監督のコーナーに再現された「東京物語」のセットで、独特のロー・アングルのカメラを実際に覗くことができて感激しました。これだけでも存在価値があるのに残念です。(11/14)
来月の16日で閉館になる鎌倉シネマ・ワールドに行ってきました。小津安二郎監督のコーナーに再現された「東京物語」のセットで、独特のロー・アングルのカメラを実際に覗くことができて感激しました。これだけでも存在価値があるのに残念です。(11/14) 「プライベート・ライアン」観てきました。冒頭30分間のノルマンディー上陸作戦の最激戦地オマハ・ビーチでの壮絶な戦闘シーンからして「史上最大の作戦」で描かれた口笛(ポール・アンカ作曲)まじりの上陸とは全く違い、観客は天才スピルバーグによっていやおうなしに最前線に放り込まれます。現在戦場をここまで臨場感たっぷりに描ける監督は他にいないでしょう。これを観てしまうと「フルメタル・ジャケット」がすごく淡泊に感じられます。カメラのぶれを嫌うキューブリックの美意識とは対照的に、スピルバーグのカメラは対角線に鋭く切り返し、スピード感あふれる絵造りを実現してます。まんねりジョン・ウィリアムズのテーマは「JFK」そっくり。(9/19)
「プライベート・ライアン」観てきました。冒頭30分間のノルマンディー上陸作戦の最激戦地オマハ・ビーチでの壮絶な戦闘シーンからして「史上最大の作戦」で描かれた口笛(ポール・アンカ作曲)まじりの上陸とは全く違い、観客は天才スピルバーグによっていやおうなしに最前線に放り込まれます。現在戦場をここまで臨場感たっぷりに描ける監督は他にいないでしょう。これを観てしまうと「フルメタル・ジャケット」がすごく淡泊に感じられます。カメラのぶれを嫌うキューブリックの美意識とは対照的に、スピルバーグのカメラは対角線に鋭く切り返し、スピード感あふれる絵造りを実現してます。まんねりジョン・ウィリアムズのテーマは「JFK」そっくり。(9/19)