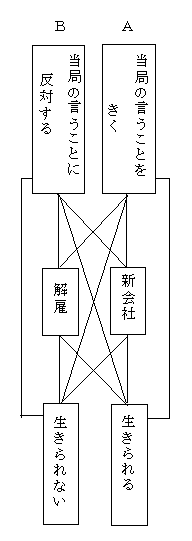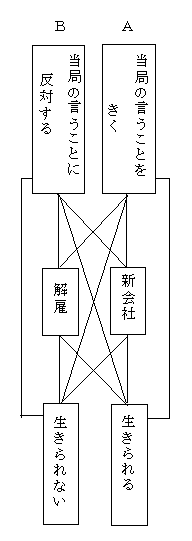婫曬桞暔榑尋媶 42崋 1992.6.1 強廂
乽擔杮偺<曐庣>傪揘妛偡傞乿 戝嶃揘妛妛峑曇挊 嶰堦彂朳 1994姧 強廂
幏昅1989擭12寧
丂
乽屬梡乿偲偄偆尵愢傪傔偖偭偰
乚亅崙揝暘妱柉塩壔斀懳摤憟偐傜亅亅
丂
丂乽摤偄乿偲偄傢傟傞帪丄乽揋乿偲偄偆偺偼偄偭偨偄壗側偺偩傠偆偐丅尰嵼偦傟偑帺柧偵巚傢傟偰偄傞強偱偼丄傓偟傠乽摤偄乿偼戅攑偺暿柤偵偡偓側偔側偭偰偄傞偺偱偼側偄偐丅
丂媽棃偺懳棫偺峔惉偑婓敄壔偟偰偄傞偲偄偆姶庴偑怴偨側乽恀偺乿懳棫揰傪尒偄偩偣偸傑傑丄媽宆偺弅彫嵞惗嶻偐尰忬峬掕偟偐摴偑側偄偲偄偆傛偆側丄悐庛姶偵楢側偭偰偄側偄偩傠偆偐丅
丂巹偨偪偼嬶懱揑偵壗偲摤偭偰偄傞偺偐丅崙揝偺暘妱丒柉塩偵帄傞夁掱傪宱偰偒偨崱丄巹偵傕傛偆傗偔偔偭偒傝偲偦偺巔偑尒偊偰偒偨傛偆偵巚偊傞丅偦傟偼丄恖傪巟攝偟傛偆偲偄偆帺屓堄幆偺宍懺偦偺傕偺傪丄帺夡丄柍岠壔偝偣傞曽岦惈偙偦偑変乆偺摤偄偱偁偭偨丄偲偄偆偙偲偩丅懳洺偡傞擇崁偺偆偪偙偪傜懁偵乽巹乿偺恎懱偑偁傝丄岦偙偆懁偵丄摤偄偺懳徾偲偟偰偺乽憡庤乿偺懱偑偁傞丄偲偄偆峔惉姶偼傕偼傗幐傢傟偰偄偨丅偦偙偵偼丄惗偒傛偆偲偡傞偙偲帺懱偑丄掞怗偟偰偔傞傕偺偲偁傜備傞椞堟丄宍懺偱奿摤偡傞偦偺峴掱丄傂偲偮偺懱姶丄懱惃偩偗偑偁偭偨丅
丂側偤乽偁偺偙偲乿偵擺摼偑偄偐側偄偺偐丄側偤乽偙偺偙偲乿偵搟傝偑偍偝偊傜傟側偄偺偐丄偦傟傜偵偮偄偰峫偊偸偔巚峫偺銸椡偵傛偭偰偙偦丄変乆偼帺傜偵偝偝偊傜傟偨偺偩丅偡側傢偪丄帺棫偟偨偺偩丅偦偺偙偲偵傛偭偰偙偦変乆偼丄屒撈抧崠偐傜尰忬峬掕偦偟偰堊偝傟傞偑傑傑偵恎傪傑偐偣傞丄偲偄偆揟宆揑側暵嵡僐乕僗偐傜摝傟傞偙偲偑偱偒偨偺偩丅
丂堦嬨敧幍擭巐寧偵峴傢傟偨崙揝暘妱柉塩壔偺妀怱傪偮偐傓偵偼丄偦偺帒嶻張暘傗丄岞嫟岎捠懱宯偲偟偰偺栤戣傕傕偪傠傫廳梫側偙偲偲偟偰偁傞偑丄崙揝怑堳偱偁偭偨巹偵偲偭偰偼丄怑応撪偺娭學偲偟偰廤栺揑偵尰傟偨條乆側椡偺憡屳嶌梡偺揥奐偵偮偄偰峫偊傞偙偲偑丄傕偭偲傕杮幙揑偱偁傞傛偆偵巚偊傞丅
丂偦偙偵偼丄尃椡偺彅憡丄愴棯丄掞峈偲攕杒偺僷僞乕儞丄偦傟傜傪挻偊傞摴偺擖岥側偳偁傜備傞傕偺偑偁偭偨傛偆偵巚偊傞丅
丂偙偙偱偼丄乽慡堳傪夝屬偟丄怴夛幮偲偟偰偦偺撪偺堦晹偺恖娫傪嵦梡偡傞乿偦偟偰乽偩傟傪嵦梡偡傞偐偼変乆偑寛傔傞乿乽偝偁丄偍傑偊偼偳偆峴摦偡傞偺偐丠乿偲偄偆峔憿偺尃椡嶌梡偵偝傜偝傟偨拞偱偳偺傛偆側曐庣揑側変乆偺巔偐晜傃忋偑偭偰偒偨偐丄偳偺傛偆側巚峫偲峴摦偑壜擻偱偁偭偨偐丄傑偨丄偙偆偟偨嬻娫傪偳偺傛偆側宱楬偑柍岠壔偱偒傞偺偐丄偵偮偄偰峫偊偨偄丅
丂
侾 乽屬梡乿偲偄偆恄榖
丂
丂乽婇嬈乿偲偼丄寛偟偰乽宱嵪岠棪乿偲偄偆扨撈偺尨棟偵廬懏偡傞婡夿偱偼側偔丄傂偲偮偺堄巙偺娧揙丄傂偲偮偺巟攝丄傂偲偮偺悽奅擣幆妋棫傊偺堄巙丄偦傟傜偺愴棯憤懱傪巜偡偙偲偽偩偲巚偊偰偔傞丅斵傜偑岅傞傛偆偵丄乽暘妱丒柉塩壔乿偼妋偐偵乽堄幆曄妚乿傪傔偞偡愴棯懱宯偱偁偭偨丅偦傟傜偵偮偄偰偼徻嵶偵帪嬻宯楍偵揥奐偟偨僎乕儉偺尒庢恾偝偊嶌惉壜擻偩傠偆丅
丂楯摥慻崌傪徚柵偝偣傞偙偲偱偼側偔丄乽暘妱丒柉塩乿斀懳偺慻崌偐傜丄巀惉偺慻崌傊楯摥幰傪堏偡偙偲偵捈愙揑側栚昗傪斵傜偑偍偄偰偄偨偺偼丄摉慠偺峴摦偱偁偭偨丅乽慻崌乿偲乽宱塩幰乿偲偄偆擇崁偺憡屳嶌梡偑偁偭偰偙偦丄埨掕揑偱丄廮擃偱丄怺偔乽帺屓堄幆乿偵崻偞偟偨乽巟攝乿偑峔抸偝傟傞偐傜偱偁傞丅偦偙偵偼丄帺傜傪堦斒揑側堄巙偱偁傞偲妋怣偟偰偄傞乽巟攝幰乿偲丄帺傜傪乽巟攝幰乿偵峈偟乽戝廜乿傪巜摫偡傞堄巙偱偁傞偲妋怣偟偰偄傞乽慻崌巜摫晹乿偑偄偨丅
丂儅僗僐儈偲偼丄婯奿壔偝傟偨暋悢偺棫応偲堄尒偵傛傞懳棫峔惉傪嶌傝忋偘丄偦傟傜偑怐傝惉偡摦懺傗忣摦偙偦丄偙偺悽奅偦偺傕偺偱偁傞偲庡挘偟懕偗傞僀僨僆儘僊乕憰抲偺偙偲偱偁傞丅偦傟偼婯奿壔偵傛偭偰怴偨側棫応傗堄尒傪慻崬傒丄嵞傃偙傟偑悽奅偩偲庡挘偟巒傔傞丅偩偐傜儅僗僐儈僿偺斸敾偼丄偦偙偵傕偆堦偮怴偨側乮恀惓偺乯棫応傗堄尒傪壛偊傛偲偄偆梫媮偱偼側偔丄偦偙偵搊応偟偰偄傞條乆側棫応傗堄尒偺婯奿壔偺偝傟曽丄偦傟傜偺堄枴偺宍惉峔憿帺懱丄傪夝懱偟偰偟傑偆僥僉僗僩斸昡丄偁傞偄偼丄捈愙偦偺尵愢偵幙栤偟偨傝懳榖傪媮傔偰偟傑偆偲偄偆懺搙偦偺傕偺丄偙偦偑桳岠偲側傞丅
丂偦偺條側忬嫷偺拞偱丄巟攝偺偨傔偺尵愢偺僉乕儚乕僪偼乽屬梡乿偱偁偭偨丅巟攝偲偄偆偺偼丄榑棟偺惼庛偵埶嫆偟偨偁偄傑偄偝傪娷傫偱丄斵巟攝幰偵帺屓婯掕憸傪嶌傜偣傞偙偲偱弶傔偰惉棫偡傞丅偦偺尨棟偵傕偪傠傫乽屬梡乿傕偁偰偼傑偭偰偄傞丅
丂暘妱丒柉塩寁夋偱偼丄崙揝怑堳偺嶰丄巐恖偵堦恖偑崙揝傪捛傢傟傞偙偲偵側偭偰偄偨丅偡傋偰偼偙偺榞慻傒偐傜敪偟偰偔傞丅屬梡妋曐偲偄偆偲偒丄懡偔偺崙揝怑堳偵偲偭偰偦傟偼揝摴偱摥偒懕偗傞偙偲傪堄枴偡傞丅偦傟偼丄崱偺巇帠傊偺垽拝傗丄尰忬偺堐帩偲偄偆堄枴偱丄帺傜傊偺曄壔偺嫮惂傪嵟彫尷偵杊偓偨偄偲偄偆堄巙偺昞尰偱偁傞丅偟偐偟婏柇側偙偲偵乽屬梡妋曐乿偲偄偆僗儘乕僈儞偼偦偺撪梕偑丄揝摴偺巇帠偺妋曐偲偄偆偙偲側偺偐丄偲偵偐偔廇怑偱偒傞偙偲偑乽屬梡妋曐乿偲偄偆偙偲側偺偐丄忢偵偁偄傑偄偵偝傟偨傑傑丄偦傟側偺偵偦偺僗儘乕僈儞傪庴偗偲傔傞幰偵偼揝摴偱偺巇帠傪妋曐偡傞偲庴偗偲傜傟傞傛偆偵嶌傜傟偰偄偨丅嵦梡梫堳榞傪峀偘丄慖暿屬梡傪偝偣偡丄婓朷幰慡堳傪偲傝偁偊偢怴夛幮偵嵦梡偡傞偲偄偆梫媮傪弌偡偺偱側偗傟偽丄乽屬梡妋曐乿偲偄偭偰傕偦傟偼慖暿偝傟傞偙偲傪慜採偲偟偨傕偺偵偡偓偢丄楯摥慻崌偲偟偰偼丄偒傢傔偰廳戝側栤戣偺偼偡側偺偵丄暘妱柉塩巀惉偺慻崌偼傓偟傠愊嬌揑偵慖暿傪庡挘偟偨丅儅僗僐儈傕乽屬梡妋曐乿傪丄偁偄傑偄側傑傑丄偩偐傜偙偦偙偲偝傜惡崅偵巊偄懕偗傞偙偲偱慖暿傪慜採偲偟偨敾抐嬻娫傪嶌傝忋偘傞梫慺偲偟偰婡擻偟偨丅
丂
偄偭偨偄偳傫側巇帠側偺偐丄偦偺撪幚偑栤傢傟偸傑傑丄乽屬梡乿偼傕偭偲傕廳梫偱偟偐偟柍撪梕側丄偦傟屘丄壙抣偵寢傃偮偄偨僉乕奣擮偲偟偰堦恖曕偒偟偰偄偔丅摉嬊偐傜偟偐偗傜傟偨寖曄偐傜尰忬偺帺恎傪庣傝偨偄偲偄偆晄埨偑丄巇帠偲偟偰偺撪梕傪扙怓偟偰丄乽屬梡乿偲偄偆壙抣偵寢徎偟偰偄偭偨偺偱偁傞丅
乽巇帠乿偲偄偆偺偼丄嬶懱揑側嶌嬈撪梕傪傕偪丄嬶懱揑側搚抧傗恖娫偲偺偮側偑傝偺拞偱峔抸偝傟傞丅偩偐傜丄惗傟堢偭偨搚抧傗桭恖偲偺娭學丄帺暘偺擻椡偺奐敪偺棜楌偲揥奐丄傑偨丄尰偵傗偭偰偄傞巇帠偑帺慠偺堦晹偲偟偰偼偳偆偄偆堄枴傪傕偮偺偐丄幮夛揑偵偼偳偆偄偆塭嬁傪梌偊偰偄傞偺偐丄摍乆偵偮偄偰丄忢偵偳傫側巇帠傪偟偰偄傞幰偱傕丄帺恎偺乽巇帠乿傪擖岥偲偟偰丄峫偊曕傒弌偡偙偲偑偱偒傞丅
丂偟偐偟丄乽屬梡乿偼屬梡偡傞幰偲偝傟傞幰偲偄偆丄摉帠幰娫偺娭學惈撪偵弞娐偣偞傞傪摼側偄丅乽屬梡乿偼乽恖偑恖偵傗偲傢傟傞偙偲乿偲偄偆埲忋偺堄枴偼傕偰側偄丅偦傟偑乽惗偒傜傟傞乿偲乽惗偒傜傟側偄乿偲偄偆壙抣敾抐偵寢崌偝偣傜傟偰偄傟偽偄傞傎偳丄乽屬梡乿偼拪徾揑側乽帺屓堄幆乿偺僪儔儅偲偟偰揥奐偟偰偄偔乮偦偟偰偙偺乽帺屓堄幆乿偙偦変乆偑奐偆傋偒傕偭偲傕曪妵揑側乽揋乿偺乽巔乿側偺偱偁傞乯丅
丂尰幚偵偼丄乽巇帠乿偲乽屬梡乿偼暘妱偟偰峫偊傜傟傞偙偲側偔偁偄傑偄側寢崌偺傑傑棳捠偟偰偄傞丅偦偺宍懺偵偍偄偰壙抣偼乽屬梡乿偺曽偵寢傃偮偄偰偄傞丅偩偐傜傎傫偲偆偼丄條乆側婇嬈偱乽壓偐傜偺乿昳幙娗棟塣摦側偳偑妶敪偵峴傢傟偰偄偰傕丄恖乆偼帺暘帺恎偺巇帠偵偮偄偰丄幮夛揑側堄枴側偳幚姶偟偰偼偄側偄丅偄偄偐偊傟偽懠幰傪偔傝偙傫偩帺屓愑擟偲偟偰偼丄偦偺婌傃偲偟偰偼丄巇帠側偳峫偊傞偙偲偑偱偒側偄丅廳梫側偺偼乽屬梡乿偱偁傝丄偦偺宯偱偁傞偲偙傠偺乽夛幮偺嬈愌乿偱偁傝丄乽廂擖乿偱偁傞丅偙偺夁掱偼偪傚偆偳丄婇嬈宱塩幰偵偲偭偰廳梫側偺偼乽帠嬈撪梕乿偱側偔乽嬈愌偺奼戝乿偱偁傝丄斵傜偐傜偼丄楯摥幰偼偁偔傑偱乽恖娫揑娗棟乿偺懳徾暔偲偟偰偟偐惉棫偟側偄偺偲懳徧揑偵側偭偰偄傞丅
丂乽屬梡乿偲偄偆奣擮傪娷傓恖娫椆夝偺嬻娫偼丄恖偑恖偲帺傜偺榬偱偮側偑傞偙偲偐傜墦偞偗丄偦偺嬻娫偵惗偒傞尷傝丄変乆偼捓嬥傪摼傜傟傞偐摼傜傟側偄偐偩偗偵尷掕偝傟傞懚嵼傊偲帺傜傪捛偄偙傫偱偄偔丅
丂偁偄傑偄偵寢戸偟偰偄傞乽巇帠乿偲乽屬梡乿傪愗抐偡傞偙偲丅乽巇帠乿偼妋偐偵乽幮夛傪巟偊偰偄傞乿偐傕偟傟側偄偑丄乽屬梡乿側偟偱傕乽巇帠乿偼壜擻側偺偩丅偲偡傟偽乽屬梡乿偝傟側偄乽巇帠乿偺偁傝曽偱暿偺幮夛傪峔惉偡傞偙偲傕壜擻側偺偱偁傞丅乽屬梡乿偲偄偆恖偺慻怐宍懺傪偲傜偢偵恖偼嫟摨偺椡傪敪婗偡傞偙偲傕壜擻側偺偱偁傞丅乽屬梡妋曐乿偲偄偆僗儘乕僈儞偼偙偆偄偆揰偐傜傕揙掙揑偵乽曐庣乿揑側傕偺偱偁傞丅
丂偙偺乽屬梡乿偲偄偆娭學傪傔偖傞懺搙偲偟偰偼丄乽屬梡妋曐乿偲偄偆僗儘乕僈儞偲丄乽慡堳偺屬梡妋曐乿偲偄偆僗儘乕僈儞偺娫偺嵎堎偙偦偑丄寛掕揑側懳棫傪惉棫偝偣傞慄暘偦偺傕偺偱偁偭偨丅乽慡堳偺乧乧乿偲尵偭偨帪丄変乆偼丄慡堳偱側偔偝偣傞傕偺偲摤傢偞傞傪摼側偄丅変乆偼丄乽慡堳偺屬梡乿偲偄偆僗儘乕僈儞傪偐偐偘傞尷傝丄傓偟傠屄暿揑帠懺偲偟偰偺乽屬梡乿偱偼側偔丄変乆傪昗揑偵偟偰慻惉偝傟傞丄乽惌晎傗摉嬊偺巤嶔乿丄偲偄偆柤偺巟攝偺暘愡偦偺傕偺偲丄偦偆偄偆丄変乆傪憖嶌懳徾偲偟偰埵抲偯偗傞巚憐偦偺傕偺偲丄摤傢偞傞傪摼側偄丅偦傟偼丄乽変乆乿偵傛偭偰扴傢傟傞乽塣摦乿偲側傜偞傞傪摼側偄丅
丂堦曽丄慡堳偺偲偄偆堄枴傪娷傑偢乽屬梡妋曐乿偲偄偭偨帪丄乽偩傟偺乿屬梡傪庣傞偺偐丠丂偲偄偆栤偼丄擟堄偺慄暘偱偐偙傑傟偨乽恎撪乿傪巜岦偡傞偙偲偟偐偱偒側偄丅偦傟偼乽恎撪乿偱側偄乽儎僣儔乿傪奜偵憂弌偟懕偗偰偟偐懚懕偱偒側偄峔憿偲側偭偰偄傞丅乽屬梡乿偑宱塩幰偲楯摥幰偲偺娫偱堦懳堦懳偱寢偽傟傞尰徾偲偝傟傞埲忋丄乽宊栺乿偑乽摉帠幰乿娫偱峴傢傟傞傕偺偱偁傞埲忋丄偦偺傛偆側嬤戙揑屄恖丒恖娫奣擮偑巟攝偡傞嬻娫撪偺宯偲偟偰乽屬梡奣擮乿偑偁傞埲忋丄乽屬梡妋曐乿偲偄偆僗儘乕僈儞偼忢偵丄乽偩傟偺乿偲偄偆栤偵懳偟丄媶嬌揑偵偼丄乽撈棫偟偨屄恖乿傪扨埵偲偡傞嬻娫撪偱丄乽巹乿偺丄偲偄偆乽帺屓堄幆乿偵偺傒廂澥偡傞偟偐側偄偐傜偱偁傞丅偦偺乽巹乿偼丄乽巹乿傪乽屬梡偡傞乿宱塩幰偲偄偆懚嵼傪慜採偲偟丄偦傟傪慜採偲偟偰惉棫偟偰偄傞乽巹乿傪媈傢側偄偲偄偆堄枴偱丄尰忬傪嵞惗嶻偡傞曐庣揑堄幆偱偁傞丅偝傜偵偦偆偟偨峔憿帺懱傪栤戣偵偡傞偙偲側偔丄傓偟傠乽尰忬傪嵞惗嶻偡傞堄幆乿亖乽帺屓堄幆乿傪偒傢偩偨偣嫮挷偡傞傕偺偲偟偰乽屬梡妋曐乿偲偄偆僗儘乕僈儞偼曐庣斀摦揑側偺偱偁傞丅
丂乽変乆偼崱偺巇帠傪懕偗偨偄丅偦傟偑偩傔側傜偳傫側巇帠偱傕尰嵼偺捓嬥偑曐徹偝傟傟偽偄偄丅変乆偼惗偒傞偨傔偵偼屬梡偝傟偹偽側傜偸偺偩丅屬梡傪幐偆偙偲偼偁偰偺側偄枹棃偺晄埨姶偵壠懓傕傠偲傕側偘偙傑傟傞偙偲側偺偩丅偄偐偵偟偰巹偺屬梡傪庣傞偺偐丄巹偼偳偆峴摦偡傋偒側偺偐丅乿
丂巇帠偺撪梕偲偐丄楯摥忦審偱側偔丄偨偩拪徾揑側乽屬梡乿偲偄偆偙偲偽偺傒偑廳偔廳偔妀偲壔偟偰偄偔偙偺娫偺慗堏偼丄帺暵偟堦恖堦恖偺恖娫偑屒棫偟偰偄偔峴掱偱傕偁偭偨丅偙偆偟偨屄恖偺乽妀乿偲側偭偰偟傑偭偨奣擮丄壙抣傪媈偄偩偡偺偼傓偢偐偟偄偙偲偱丄帺暵偡傞偙偺乽帺屓堄幆乿傪忢偵曄梕偝偣偵朘傟傞撪奜偺尰幚偩偗偑偦傟傪壜擻偵偝偣傞丅
丂偐偮偰堦恖偱栭偢偭偲峫偊偙傫偱偄偨偙偲偑偁偭偨傛偆偵巚偆丅傑偩暘妱柉塩偺惡傕側偔丄偨偩偔傝曉偡擔乆偑丄怱偺側偐偱蹇偔徴敆偺傛偆側傕偺偵偲偭偰偼慳傑偟偄瀪瀲偲偟偐姶偠傜傟偢丄偲偵偐偔壗偐偐傜扙偗弌偟偨偐偭偨丄偦傫側乽庒乿偐偭偨崰偩丅崙揝傪戅怑偟偨偲偟偨傜丄偳偆傗偭偰惗偒偰偄偗傞偩傠偆偐丅偲傏偟偄挋嬥丄壠捓丅偳傫側巇帠傪偟偨偄偺偩偲偄偆栚昗傕側偔丄戅怑偩偗偟偨偄偲偄偆婥帩偪偲偄偆偺偼丄帺暘偑幮夛揑偵枙嶦偝傟偰偄偔摴峴偺擖岥偵棫偭偨傛偆偵怱嵶偔埫偄暘婒姶偱偁偭偨丅廤拞偟偰尰傢傟傞偺偼偙偙偱傕丄偳偆傗偭偰乽怘偆乿偐偳偆傗偭偰廂擖傪摼傞偐偲偄偆偙偲偩偭偨丅
丂廂擖傪摼傞偲偄偆偙偲偲丄帺暘偑庤偛偨偊偺偁傞惗偒曽傪偡傞偲偄偆偙偲偲偼懡偔偺応崌懳棫偡傜偡傞傛偆偵巚偊偰偄偨丅寢嬊偦偺帪巹偼戅怑偟側偐偭偨偑丄崱偵偟偰巚偊偽丄偦偆偄偆婡夛偺朘傟偲偄偆偺偼丄恖偑巚嶕傪恑傔偰偄偔忋偱偺暻傪帺夡偝偣傞傋偔丄乽尰幚乿偑昁慠揑偵憲偭偰偔傟傞傕偺偺傛偆偵姶偠傞丅幚嵺偵戅怑偡傞偐偟側偄偐偱側偔丄偦偺朘傟傪偳偺傛偆偵徚壔偟偨偐偩偗偑丄堄枴偺偁傞堘偄偲側傞丅
丂巹偼師偺傛偆偵峫偊偨偲巚偆丅
丂崱寛抐偟傛偆偲偟偰偄傞帺暘偺彨棃傊偺懅嬯偟偄晄埨姶偵傕偐偐傢傜偢丄夛幮傪戅怑偟偨偲偄偆偙偲偺傒傪傕偭偰丄巰傫偱偟傑偭偨偲偄偆恖偼偄側偄偺偱偼側偄偐丅傕偆偩傔偩偲偄偆巚偄擖傟偵傕偐偐傢傜偢丄偳傫側応崌偱傕恖娫偼偦偙偱側傫傜偐偺曽朄偱丄偨偲偊偐偭傁傜偄傪偟偰偱傕惗偒偰偄偭偰偟傑偆偺偱偼側偄偐丅昦婥偱摦偗側偔側偭偨偲偟偰傕丄偨偲偊攑毿偵堦恖巆偝傟偨偲偟偰傕丄恖偼偦偺尰幚傪惗偒偰偄偔偩傠偆丅婏柇側偙偲偵丄巹偑婥偵偟偰偄傞乽廂擖乿偵傛偭偰偱偼側偔丄惗暔偲偟偰偺惗巰偼暷傪怘傋傞偐怘傋側偄偐偲偄偆偙偲偵偺傒嵟廔揑偵廬懏偟偰偄傞偺偱偼側偄偐丅
丂偲偡傟偽丄巹偑乽廂擖乿偑偲偩偊傞偙偲偵懳偟偰姶偠傞乽惗丒巰乿偺暘婒姶偲偄偆偺偼偄偭偨偄壗偺乽惗丒巰乿側偺偩傠偆偐丅乽廂擖乿丒乽捓嬥乿丒乽偍嬥乿偲乽暷傪怘偆偙偲乿偺儗儀儖偺娫偵偼柧妋側抐愨偑偁傞偼偢偩丅偦傟側偺偵丄偦傟傜偑捈愙揑偵楢摦偟偰岅傜傟偰偄傞偺偼慡偔晄巚媍側偙偲偱偼側偄偺偐丅恖偺巚偄崬傒傗晄埨偲偄偆偺偼傂傚偭偲偟偨傜偁偰偵側傜側偄傕偺側偺偐傕偟傟側偄丅偦偆偄偆丄恖偺巚偄崬傒傗晄埨偼偦偺帪戙偺楌巎揑偵宍惉偝傟偰偒偨憌偵偡偓側偄偺偐傕偟傟側偄丅
丂枹棃偲偄偆傕偺傪丄傕偟曐徹偝傟偨傕偺偲偟偰峫偊傜傟側偗傟偼晄埨偩偲偄偆偺側傜丄偨偲偊埨掕偟偨怑偵偮偄偰偄偰傕丄柧擔壗偐婲傞偐傢偐傜側偄偲偄偆堄枴偱偼晄埨偱側偗傟偽側傜側偄偺偵丄廇怑偟偰偄傞偲偄偆偙偲偼側偤偦偺晄埨傪傎偲傫偳姶偠偝偣偢丄戅怑偡傞偲偄偆偙偲偑晄埨傪偐偒偨偰傞偺偩傠偆偐丅埨掕揑偵捓嬥傪巟媼偡傞偲偄偆栺懇偑埨掕揑側惗妶偵楢寢偟偰峫偊傜傟偰偄傞偲偄偆偺偼傂傚偭偲偟偨傜偒傢傔偰摿庩側忬嫷側偺偐傕偟傟側偄丄偄偭偨偄偙傟偼側偤側偺偩傠偆丅
丂幮夛偑恖娫偺椶偲偟偰偺嫟摨惈偺妋怣偱偁傞丄偲偟偰丄偱偼丄崱偁偰傕側偔夛幮傪傗傔傛偆偲偟偰偄傞巹偺怱偺傆傞偊偼丄偦偺椶偲偟偰偺嫟摨偺椡偐傜帺恎偑捛曻偝傟傞偍偺偺偒側偺偱偁傠偆偐丅偄傗偦傫側偽偐側偙偲偼偁傝摼側偄丅乽夛幮乿偲偐乽巇帠乿偲偐傪挻偊偨傕偭偲峀戝側偲偙傠偱丄椶偱偁傞偙偲偺妋徹偨傞幮夛偲偄偆偺偼偁傞偼偢偱偼側偄偐丅昦恖傕恎懱忈奞幰傕惗傟偨偽偐傝偺愒傫朧傕奆娷傫偱偦偙偵丄崱偨偩偙偙偵偡偱偵尰懚偟偰偄傞偺偑幮夛偱偁偭偰丄偦偙偐傜捛曻偝傟偨傝丄偦偙偵壛傢偭偨傝偼丄尨棟揑偵偱偒側偄傕偺偱偼側偄偺偐丅偙偺幮夛偲丄変乆偑偦偙偐傜敳偗弌傞偙偲偵乽惗丒巰乿偺晄埨傪偡傜姶偠傞傂偲偮偺峔抸暔偲偼慡偔暿側傕偺偱偼側偄偐丅屻幰傪側傫傜偐偺乽惂搙乿偲屇傋偽丄偦偺乽惂搙乿偼嶌傝偁偘傜傟偨傕偺偱偁傝丄偦傟偵娭傢偭偰変乆偑姶偠傞晄埨傗埨掕姶傕偦偺乽惂搙乿偺撪晹偺傕偺偲偟偰丄乽惂搙乿偲摨條丄夝懱偝傟摼傞傕偺偱偼側偄偺偐丅
丂偦偺乽惂搙乿偲偼乽夛幮乿偲偐乽楯摥幰乿偲偐乽媼椏乿偲偐乽惗偒傞偨傔乿偲偐條乆側奣擮偱峔抸偝傟偨懱宯偱丄偦傟偑変乆偵廳嬯偟偄椡傪壛偊懕偗偰偄傞偺偩丅乽廂擖乿傪摼傞偲偄偆偙偲偱偟偐丄乽惗偒傞偙偲乿偵偮側偑傜側偄僐乕僪偺懇偑丄敪憐傗恎懱偺摦偒偺壜擻惈偝偊傕堔弅偝偣偰偄傞丅偟偐偟乽変乆乿偼忢偵偦偆偟偨乽惂搙(僐乕僪)乿傛傝偼傞偐偵峀戝側懚嵼偱偁傞偙偲傪塣柦偯偗傜傟偰偄傞偺偱偼側偄偐乧乧丅
丂寢嬊丄晄埨帺懱偼夝徚偝傟傞偙偲偼側偐偭偨傛偆偵巚偆丅偟偐偟丄偦偆偄偆晄埨偲偄偆傕偺偑夝懱壜擻側崻嫆偵婎偯偄偰偄傞偲偄偆妋怣揑椆夝偼妋幚偵変乆傪曄偊傞丄偲偄偆偙偲偼尵偊偨偲巚偆丅
丂偦偺壗擭屻偐丄崙揝暘妱柉塩壔偺偡偝傑偠偄楯摥幰傊偺暘抐峌寕偺拞偱巹偑傎偲傫偳昁慠偺傛偆偵姶偠側偑傜崙楯偺暘夛挿傪堷偒庴偗偨偺偼丄偙偆偟偨偙偲偵傛偭偰偄偨偐傕偟傟側偄丅
丂
俀丂峌寕偺暥懱
丂
丂偱偼嬶懱揑側崙揝暘妱柉塩壔偺夁掱偵偍偗傞乽屬梡乿傪傔偖傞尵愢偼偳傫側傕偺偱偁傝丄偳偆偦傟傪夝懱偱偒傞偩傠偆偐丅
丂堦嬨敧榋擭堦乑寧堦乑擔偺崙楯椪帪戝夛偱幏峴晹埬偐斲寛偝傟暘妱柉塩斀懳偑寴帩偝傟偨帪丄怴暦偼師偺傛偆偵彂偄偰偄偨乮朤揰堷梡幰乯丅
丂
嘆丂偟偐偟丄嶐擭廫堦寧枛偵丄崙揝摉嬊偐傜巜柤夝屬偵帟巭傔傪偐偗傞乽屬梡埨掕嫤栺乿偺嵞掲寢丂傪嫅傑傟偨偙偲傗摉嬊偐傜媮傔傜傟偨僗僩帺弆傪娷傓乽楯巊嫟摨愰尵乿偺掲寢傪嫅斲偟偨偙偲偐傜屬梡晄埨偑峀偑傝丄偙偙悢僇寧偼堦偐寧偵堦枩恖埲忋偺扙戅幰偑懕弌偟偰偄偨丅
86丒10丒11丂撉攧怴暦
嘇丂乧乧堦曽丄乽戝抇側懨嫤乿傪巟帩偟偰偄偨庡棳攈僌儖乕僾偼乧乧乽幏峴晹採埬傪摨偠幮夛搣搣丂堳嫤媍夛偺堦堳偱偁傝側偑傜丄妚摨乮嫟嶻搣宯乯偲庤傪寢傫偱棤愗偭偨摿掕僀僨僆儘僊乕廤抍乮嫤夛宯乯偺朶嫇傪嫋偡偙偲偼偱偒側偄乿偲偡傞惡柧傪敪昞丅崱屻丄幮夛搣偲憤昡偺巜摫傪庴偗側偑傜丄崙楯偺慻怐撪偱丄屬梡偺妋曐偲慖暿攔彍偵椡傪拲偖曽恓傪柧傜偐偵偟偨丅
86丒10丒11丂撉攧怴暦
嘊丂帺柉搣丄崙揝摉嬊丄懠慻崌偐傜偺峌寕偑偙傟傑偱埲忋偵嫮傑傞偺偼昁帄丅偦傟偩偗偵丄偄偐偵丂屬梡偲慻怐傪庣偭偰偄偔偺偐丄怴幏峴晹偺僇僕庢傝偑拲栚偝傟傞丅
86丒10丒侾侾丂挬擔怴暦
丂
丂偙傟傜偺婰帠偺拞偺乽幮夛搣乿偲偐乽嫟嶻搣乿偲偐乽庡棳攈乿側偳偲偄偆崁栚偼偙偺昅幰偨偪偵偼桳堄枴側曎暿峔惉姶傪傕偨傜偟偰偄傞偺偩傠偆偑丄変乆偵偼壗偺堄枴傕峔惉偡傞偙偲偑偱偒偢丄扨怓偱偁傞丅
丂撉攧偺婰帠嘆偵偄偆乽屬梡埨掕嫤栺乿偲偄偆偺傕丄幚偼丄乽崙揝偵偍偗傞崌棟壔偵偁偨偭偰偼柶怑丄崀怑偼偟側偄乿偲偄偆丄崌棟壔傪慻崌偑擣傔傞偨傔偺忦審嫤掕偱偁偭偰丄暘妱柉塩帪偺怴夛幮傊偺嵦梡偑徟揰偵側偭偰偄傞偙偺応崌偺乽屬梡乿偲偼榑棟揑偵偼柍娭學側偺偱偁傞偑丄側傑偠乽屬梡乿偲偄偆僉乕儚乕僪偑擖偭偰偟傑偭偰偄偨偽偐傝偵丄乮偦偺忋丄側傫偲偄偭偰傕屬梡傪乽埨掕乿偝偣偰偟傑偆偺偩偐傜両乯摴嬶偲偟偰廫暘妶梡偝傟偨傕偺偺傂偲偮偱偁傞丅
丂偟偐偟丄偙偺撉攧嘆偼丄偙偺屬梡奣擮偺慺婄傪幚偵揑妋偵帵偟偰傕偄傞丅乽崙揝摉嬊偐傜××傪嫅傑傟偨乿乽摉嬊偐傜媮傔傜傟偨××傪嫅斲偟偨乿偙偲偐傜乽屬梡晄埨偑峀偑偭偨乿偲弎傋偰偄傞丅屬梡偲偄偆岅偵撪梕偑梌偊傜傟偰偄傞丅偡側傢偪丄乽屬梡乿偲偼乽摉嬊乿偵嫅傑傟偨傝丄乽摉嬊乿傪嫅傫偩傝偡傞偙偲丄尵偄姺偊傟偽丄摉嬊偺乽堄乿偵斀偡傞偲丄乽晄埨乿偵側傝丄婋偆偔側傞傕偺偺偙偲側偺偱偁傞丅惓妋偵偄偊偽丄摉嬊偲偺娭學堄幆偺拞偱丄摉嬊傊偺廬懏揑懚嵼偲偟偰偺帺屓婯掕丄偦傟偑崙揝暘妱柉塩夁掱偺拞偱廤抍偲偟偰惗偒傜傟偨奣擮偲偟偰偺乽屬梡乿側偺偱偁傞乮傕偪傠傫朄妛幰偼暿偺懳徾壔偝傟偨乽屬梡乿奣擮傪偄偔傜偱傕尒偄偩偡偙偲偑偱偒傞乯丅
丂
嘆丂偄傑丄崙揝偵摥偔拠娫偺偩傟傕偑帺暘偺屬梡偵偮偄偰擸傫偱偄傑偡丅偲偔偵崙楯偺慻崌堳偱偁丂傞傒側偝傫偺応崌偼堦抜偲怺崗偱偁傞偲巚偄傑偡丅側偤側傜偽崙楯偼丄崅偄慻崌旓傪庢傞偩偗偱丄屬梡懳嶔傪偨偰傞偙偲傕幚峴偡傞偙偲傕壗傂偲偮偱偒偢丄張暘偑忋愊傒偝傟傞偩偗偺乽摤偄乿偵慻崌堳傪堷偒夞偡偲偄偆嬸偐側峴堊傪偔傝偐偊偟偰偍傝丄偄偔傜巇帠傪傑偠傔偵傗偭偰傕崙楯偵強懏偟偰偄傞偩偗偱媽崙揝丒巜柤夝屬偺懳徾偵側偭偰偟傑偆偺偼昁帄偩偐傜偱偡丅
嘇丂乽恀崙楯偺恖偺偄偭偰偄傞偙偲偼傢偐傞傛丅偩偗偳傕偆壗傪傗偭偰傕抶偄傛丅壌偼偳偆側偭偰傕偄偄傫偩丅僋價偵側偭偨傜幚壠偱昐惄傪傗傞傫偩乿偲偮傇傗偄偰偄傞偁側偨両丂杮摉偵偁側偨偼偦偆巚偭偰偄傞傫偱偡偐両丂偁側偨偺嵢傗巕嫙丄椉恊傕乽偳偆側偭偰傕偄偄乿偺偱偡偐丠丂杮摉偵壠懓傪怘傋偝偣偰偄偔傾僥偼偁傞偺偱偡偐丠丂壠懓偲偦偺偙偲偵偮偄偰榖偟崌偭偰偄傑偡偐丠
丂偦偆偱偼側偄偱偟傚偆丅偁側偨偼帺暘偺婥帩偪偵恀惓柺偐傜傓偐偄偁偭偰偄側偄偱偼側偄偱偡偐丅偩傟傕偑崙揝偵巆傝偨偄偺偱偡丅偦傟埲奜偵壠懓傪怘傋偝偣偰偄偔傾僥側偳側偄偺偱偡丅惗偒巆傞偨傔偵峫偊幚峴偡傞偺偼嬯偟偄偙偲偵偼堘偄偁傝傑偣傫丅偗傟偳傕丄嬯偟偄偐傜偲偄偭偰栚傪偦傓偗偨傝搳偘傗傝偵側傞偺偱偼側偔丄堦曕傪摜傒弌偡偙偲偑崱偁側偨偵栤傢傟偰偄傞偺偱偡丅
丂
丂偙偺暥懱偺偹偽傝偮偔傛偆側懅嬯偟偝偼偳偙偐傜棃傞偺偩傠偆偐丅偍偦傜偔丄偦傟偼偙偺昅幰偑丄憐掕偟偰偄傞乽楯摥幰乿偺媰偒偳偙傠傪僺僞儕偲偍偝偊偰偄傞偮傕傝偱偦傟偵岦偭偰彂偄偰偄傞偐傜偱偁傞丅偦偺懳徾偲偺嫍棧嬻娫偑丄乽懚嵼傪婯掕偟偮偔偡乿偲偱傕偄偆丄懳徾傊偺巟攝偺廳椡偵傛偭偰惉棫偟偰偄傞偐傜偱偁傞丅屇傃偐偗傞懳徾偲偝傟偨丄偙偺暥懱傪撉傓幰偼丄帺暘偑丄偍傑偊偼偙偆側偺偩丄偙偆側偺偩丄偲彑庤偵寛傔傜傟偰丄懱傪側傔傑傢偝傟傞傛偆側婥帩偪埆偝傪姶偠傞偩傠偆丅
丂暿偺尵偄曽傪偡傞偲丄偙偺暥懱偼丄斵傜偑憐掕偟偨乽楯摥幰乿憸偐傜棧扙偟偰偟傑偄偦偆側慻崌堳傗楯摥幰傪昁巰偱斵傜偺楯摥幰憸偵暵偠偙傔傞傋偔嶌傜傟偨惌帯愰揱偺暥懱側偺偱偁傞丅
丂偙偺乽楯摥幰乿偼師偺傛偆偵婯掕偝傟偰偄傞丅屬梡偝傟偰偟偐惗偒傜傟側偄懚嵼亖楯摥幰丄偲偄偆帺屓椆夝丄崙揝埲奜偱偺巇帠傪偡傞擻椡丄壜擻惈偺斲掕丄晇偼嵢巕傪梴傢側偗傟偽側傜側偄偲偄偆壠懓憸偺嬥宆偱偺埑敆亖壠懓傊偺巟攝幰偲偟偰偺弌尰丅偦偟偰丄摉嬊偺梫堳榞丄怴夛幮偺嵦梡榞偼晄摦偺愭尡揑慜採偲偟偰丄偙偺乽楯摥幰乿偲偄偆僔僗僥儉傪摦偐偡塀偟僼傽僀儖偺傛偆偵愽傑偝傟偰偄傞丅傓偟傠偦傟傪曄偊偰偼偄偗側偄偲偄偆傛偆偵丅
丂偙偺暥懱偺閌愩側峌寕惈偼丄偙偺暥復偑乽堦慻崌堳乿偺傕偺偱偼側偔丄乽戝廜傪巜摫偡傞乿悽奅娤傪恎偵偮偗偨乮偦傟偑妚柦揑偱傕恑曕揑偱傕曐庣揑偱傕摨偠偙偲偩乯慻崌巜摫幰偺傕偺偱偁傞偙偲偺報偱偁傞丅乽戝廜乿偑丄乽帺恎乿偲偺幚懱揑曎暿榝偱惉棫偟偰偄傞偲偄偆堦揰偵偍偄偰丄乽帺恎乿偐斵傜乽戝廜乿傪僐儞僩儘乕儖丄傑偨偼摫偐偹偼側傜偸偲峫偊傞偙偲偱丄乽慻崌塣摦巜摫幰乿傕乽摉嬊乿傕摨偠曐庣惈乮恖偑恖傪巟攝偟傛偆偲偡傞乯傪懱尰偟偰偄傞偲偄偆偙偲偑偁傝偆傞偺偱偁傞丅
丂偝偰丄偙偺暥懱偺拞偺曐庣揑側乽楯摥幰乿憸偺傑傑偱傕丄傕偟怴夛幮偺嵦梡悎偑晄摦偺傕偺偱偼側偄偲峫偊偨偲偡傟偽丄慡偔斀懳偺丄掞峈偺曽岦偑峫偊傜傟傞偼偢偱偼側偄偺偐丠
丂乽屬梡偝傟偰偟偐惗偒傜傟偢丄崙揝偱偟偐惗偒傜傟偢丄嵢巕傪梴傢偹偽側傜側偄乿偐傜偙偦丄怴夛幮偺嵦梡悎傪峀偘傞偨傔偵摤偆傋偒偩丄偲丅
丂偟偐偟丄尰幚偵偼偦傟偼偩傟偵傕暦偐傟偨掞峈偺抂弿偵偡偒偢丄偙偺曐庣揑側楯摥幰憸傪曐帩偟偨傑傑偱偼掞峈偼帩懕偡傞偙偲偼偱偒側偄丅側偤側傜尰偵嵦梡悎偑偁傝丄摉嬊偼偦傟傪娧揙偟傛偆偲偟偰偄偨偐傜偱偁傝丄摤偄偺拞偱偺尵愢偺拞偱丄変乆偼忢偵丄乽嵦梡悎偼曄偊側偄丄偍傑偊偼偳偆峴摦偡傞偺偐乿偲敆傜傟懕偗偨偐傜偱偁傝丄傑偝偵丄乽屬梡偝傟偰偟偐惗偒傜傟偡丄崙揝偱偟偐惗偒傜傟偢丄嵢巕傪梴傢側偗傟偽側傜側偄乿偲偄偆楯摥幰偲偟偰偺帺屓婯掕憸傪曄梕偝偣偢偵偼掞峈偺崻嫆傪尒偄偩偣側偐偭偨偐傜偱偁傞丅偄偄偐偊傟偽偙偺慡偔偺曐庣揑側乽楯摥幰乿偐傜巒傔偰丄偼偘偟偄摤偄偺夁掱偱丄偦傟傪偳偆曄梕偝偣偰偄偔偺偐丄偳傟偩偗丄崱傑偱偺擔忢惗妶偺拞偱偁偄傑偄偵偟偰偄偨奣擮傪弒暿偟丄朙晉側尵愢傪丄峴摦偺偟偐偨傪丄敪尒偟偰偄偔偺偐丄偦偺巚憐揑側摤偄偙偦偑丄変乆偵偲偭偰偺崙揝暘妱柉塩壔斀懳摤憟偱偁偭偨丅
丂偝傜偵偄偔偮偐偺丄崙楯扙戅傪偣傑傞懠偺慻崌偐傜偺尵愢傪尒偨偄丅傕偪傠傫偙偆偟偨尵愢偼丄摉嬊丄崙楯丄儅僗僐儈偺尵愢傗峴摦攝抲偵楢寢偡傞傕偺偲偟偰偦偺帪乆偵丄敪偣傜傟偰偄傞丅
嘆丂慖暿偼崙楯栶堳偐傜慻崌堳傊
丂偮偄偵丄梋忚恖堳偺慖暿偑奐巒偝傟偨偺偐丠丂崙楯栶堳偼側偵傂偲偮乽摤偆乿偙偲側偔師乆偲恖嵽妶梡僙儞僞乕僿憲傝崬傑傟偰偄傑偡丅
丂崙揝摉嬊偼廫堦寧傑偱偵屲枩屲愮恖傪恖嵽妶梡僙儞僞乕偵攝懏偡傞偲偄偭偰偄傑偡丅崙楯栶堳偵偩傑偝傟偰乽摤偄乿偵傂偒傑傢偝傟偰偒偨崙楯慻崌堳傕丄偙偺傑傑偱偼栶堳偲摨偠摴傪偨偳傞偙偲偼壩傪尒傞傛傝柧傜偐偱偡丅乧乧拞棯乧乧栶堳偼怑応偐傜偄側偔側偭偰偟傑偄傑偡丅
丂崙楯偼慻崌堳傪庣傞曽朄傕椡傕姰慡偵幐偭偰偟傑偭偨偺偱偡丅
丂崙楯偵偄傞偩偗偱丂慖暿偝傟傞偐傕乧乧丠
丂乽恖嵽妶梡僙儞僞乕偲偄偆柤偺丄嶌嬈偺側偄廂梕強偵攝懏偡傞偲尵偭偰偄傞摉嬊偲丄偦傟偵楢摦偟偰偙偆偄偆價儔傪攝傞慻崌乿偲偄偆峔惉偑丄傂偲偮偺巟攝偺宍懺側偺偱偁傞丅傂偲偮偺堄巙偺娧揙乮巟攝乯偺偨傔偺揟宆揑僷僞乕儞偱偁傝丄搊応偡傞栶幰傪擖傟姺偊傟偽奺抧偺峴惌偲廧柉偺懳棫応柺丄偡側傢偪丄尰幚悽奅偺嬶懱揑曽嶔偺傎偲傫偳傪愯桳偟偰偄傞乽峴惌乿偵懳偟偰巀惉丒斀懳偳偪傜偑乽摼乿偐丄偲偄偆揥奐偲摨宆偵側傞丅巟攝偡傞幰偺堄巙偼偦傟傪撉傒偲傞幰傪昁梫偲偟偰偍傝丄斵傜偵傛偭偰巟攝幰偺堄巙偼庴摦宍偱撪柺壔偝傟丄乽斵巟攝幰乿偑惉棫偡傞偺偱偁傞丅
嘇丂崙楯娵偼偁偰偺側偄峲奀偵椃棫偲偆偲偟偰偄傞丅乧乧拞棯乧乧
丂恀柺栚側崙楯慻崌堳偺奆偝傫両
丂巆偝傟偨帪娫偼丄偁偲傢偢偐偱偁傞丅偩偑丄偄傑側傜傑偩娫偵崌偆丅乽妶惈壔偟偨揝摴帠嬈懱乿傪偮偔傝偁偘傞偙偲傪偲偍偟偰丄帺暘偲垽偡傞壠懓偺偦偺婸偐偟偄枹棃傪愗傝奐偄偰偄偙偆丅傢偑摦楯偲偲傕偵両
丂丂堦嬨敧榋擭幍寧擇廫榋擔
崙揝摦椡幵楯摥慻崌搶嫗抧曽杮晹
嘊丂偲傝傢偗斀懳攈偺婙摢丄傢偑崙楯搶嫗偺乽巰摫(乮儅儅乯)乿偵偄偮傑偱傕偮偒廬偆偙偲偼丄乽偒傢傔偰晄岾側帠懺乿傪彽棃偝偣傞偙偲偵側傞丅傕偪傠傫偦偆偟偨偄恖偵偼偦偺帺桼偑偁傞偙偲偼偄偆傑偱傕側偄丅巆偝傟偨帪娫偼尷傜傟偰偄傞丅偦偟偰丄偡偱偵崙楯偺慻怐棪偼夁敿悢傪妱偭偨丅乽偙偺傑傑偱傕側傫偲偐側傞乿偲偄偆丄偝偝傗偐側乽婜懸乿傗乽婓朷乿偵恎傪傑偐偣傞偙偲偼丄乽嵟屻偺僠儍儞僗乿傪堩偭偟偨崙楯偲怱拞偡傞摴傪慖傇偙偲偱偁傞丅
丂偝偰巆偝傟偨乽嵟屻偺僠儍儞僗乿偼婱曽帺恎偺乽寛抐乿偱偁傞丅
丂
丂堦擔傕憗偔丄傢偑摦楯偺婙偺傕偲偵両
堦嬨敧榋擭廫寧嬨擔
崙揝摦椡幵楯摥慻崌搶嫗抧曽杮晹
丂偙傟傜偺扙戅傪偣傑傞尵愢偵偍偄偰岅傝偐偗傜傟偰偄傞崙揝楯摥幰偼丄
俙丂摉嬊偺尵偆偙偲傪偒偄偰怴夛幮傊偄偔亖惗偒傜傟傞
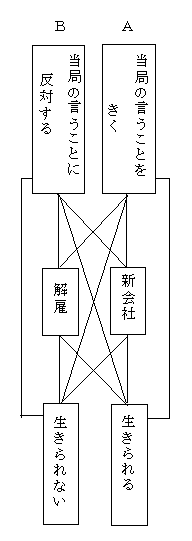
俛丂摉嬊偺尵偆偙偲偵斀懳偟偰夝屬偝傟傞亖惗偒傜傟側偄
丂偺乽擇幰戰堦乿偟偐側偄嬻娫偵婯掕偝傟偰偄傞丅偙偙偱偼丄暘妱柉塩埬偺梫堳悢偼丄偩傟偐偑慖暿偝傟傞偲偄偆偙偲偩偗偑堄枴傪傕偪丄嬶懱揑側悢偼柍帇偝傟偰偄傞丅側偤側傜丄慡崙揝怑堳偑丄俙偺乽摉嬊偺尵偆偙偲傪偒偄偰怴夛幮傊偄偔乿傪慖傫偱偟傑偆偲丄偦偺柦戣帺懱偑柍岠偵側偭偰偟傑偆偐傜偱偁傞丅
丂榑棟揑偵尒傞偲柦戣傪峔惉偡傞嶰偮偺儗儀儖偼撈棫偱偁傞丅
丂俙丒俛偳偪傜偐傜巒傔偰傕丄偳偺崁栚偲傕楢寢壜擻偺偼偢偱偼側偄偺偐丅
丂偦傟傜偺擇幰戰堦偑偦傕偦傕惉棫偟側偄帠忣偑柧傜偐偱偁傝側偑傜丄側偍俙楍丒俛楍偺擇幰戰堦傪敆傞偲偄偆偺偼偳偆偄偆堄枴偑偁傞偺偩傠偆偐丅
丂偙偺丄崙楯扙戅偺僾儘僷僈儞僟偺堄枴偼丄乽楯摥幰偼屬梡偝傟偰偟偐惗偒傜傟側偄乿乽屬梡偼丄摉嬊偺堄巙偑寛掕偡傞傕偺偱偁傞乿乽偙偺忬嫷偼愨懳偵曄偊傜傟側偄乿乽偦偟偰巹偼楯摥幰偩乿偲偄偭偨帺屓婯掕偺弞娐宯傪偟偭偐傝崗報偡傞偙偲丄側偺偱偁傞丅
丂偦偟偰丄偙偺丄摉嬊偺尵偆偙偲傪偒偔偐丄偒偐側偄偐偺擇幰戰堦偺愝栤傪彸擣偡傞偙偲偼丄乽偩傟偐偑慖暿攔彍偝傟傞偑丄偦偺偩傟偐偵巹偼側傜側偄乿丄偲偄偆偙偲傪慖戰偟偨偺偱偁傞偐傜丄摉慠偦傟埲崀乽拠娫乿偲偄偆楢懷偼惉棫偟側偄丅
丂偙偆偟偰尒偰偄偔尷傝丄崙揝暘妱柉塩偺夁掱偵偍偗傞丄摉嬊丄暘妱柉塩悇恑偺楯摥慻崌丄儅僗僐儈偺暥懱偼偡傋偰丄偙偆偟偨乽暵偠偨楯摥幰憸乿偺偍偟偮偗偱偁傝丄偦偙偐傜帺暘偺摢偱峫偊傛偆偲偡傞傕偺丄偦偙偐傜敳偗弌傛偆偲偡傞幰偵丄偍傑偊偨偪偼偙偆偟偰偟偐惗偒傜傟側偄偲墴偟偮偗傞傕偺偱偁偭偨丅乽戝廜偺巜摫幰乿偨偪偑丄偄偐偵曐庣揑側偦傟傜偺乽楯摥幰憸乿偵幏怱偟偰偄傞偐傕変乆偼巚偄抦傜偝傟偨丅
丂
俁丂乽楯摥幰乿偺夝懱
丂
丂師乆偲丄摉嬊丄儅僗僐儈丄暘妱柉塩悇恑偺楯慻偑偔傝弌偟偰偔傞丄乽屬梡乿傪暘婒偲偡傞丄恖乆傪暘抐屌掕偡傞愴棯偵偝傜偝傟偰丄傂偲傝傂偲傝偼丄惗傟偰偐傜偙偺偐偨梴偭偰偒偨偁傜備傞奣擮傪梙偝傇傜傟傞偲偄偆橣岕偵弌夛偆偙偲偲側偭偨丅崱傑偱媈偆偙偲側偔丄惗偒傜傟偰偒偨條乆側奣擮偑偼偘偟偔攇偆偪丄岾塣側応崌偵偼丄偦傟傪媈偄丄懳徾壔偡傞偲偄偆偙偲偑偱偒偨丅
丂乽楯摥慻崌乿偲偄偆偺偑傢偢傜傢偟偄傕偺偲姶偠傜傟傞偺偼側偤偐丅偦傟偼丄慻崌堳傪巜摫偝傟傞傕偺偲偟偰偺憸偵偲偠偙傔傞慻怐偺偙偲傪偝偟偰偄傞応崌偱偁傞丅巜摫幰偼乽慻崌堳乿偵丄偙傟偵廬傢側偗傟偽偍慜偺偙偲偼曐徹偟側偄偲偄偄丄慻崌堳偼乽巜摫幰乿偵丄壌偨偪傪偳偆偟偰偔傟傞偲巕嫙偺傛偆偵僟僟傪偙偹傞偙偲偑屳偄傊偺椡偺媦傏偟曽偱偁傞傛偆側娭學偺慻怐偺応崌偱偁傞丅
丂乽暘夛挿偼摤偆摤偆偭偰尵偆偗偳丄壌偺屬梡偼庣偭偰偔傟傞偺偐乿乽慻崌偑壌偨偪傪庣偭偰偔傟傞偺偐乿
丂擔栭慡崙偺崙楯偺暘夛偱偔傝曉偝傟偰偄偨偵偪偑偄側偄偙偺媗栤偵巹偼偳偆摎偊偰偄偨偩傠偆偐丅偙偺愝栤偵揔崌偡傞夞摎側偳偁傝摼側偐偭偨丅偙偺愝栤帺懱傪夝懱偡傞偲偄偆偲偙傠偵偟偐変乆偑惗偒傞摴偼側偐偭偨偺偩丅
丂乽慻崌偲偄偆拪徾揑側傕偺偑壌偨偪偵壗偐傗偭偰偔傟傞偲偐丄偔傟側偄偲偐偄偆偙偲偼側偄傛丅崱傑偱壌偨偪偼摨偠忔柋堳偲偟偰堦弿偵儊僔傪怘偄丄屳偄偵彆偗偁偄丄堦弿偵巇帠傪偟偰偒偨丅偩偗偳崱丄摉嬊偼偦偺壌偨偪偵丄摉嬊偺偄偆側傝偵側傟偽怴夛幮偵峴偐偣傞偗偳丄偦偆偱側偗傟偽僋價偩偲偄偭偰偄傞傫偩丅偟偐傕恖悢惂尷傪偟偰偩丅偦傫側傆偆偵拠娫傪棤愗傟傞偐偄丅帺暘偩偗偼丄偭偰峫偊偨偲偟偨傜丄崱傑偱偺壌偨偪偺丄拠娫偲偐桭忣偲偐偄偆偺偼偄偭偨偄壗偩偭偨偺偐偄丅慻崌偩壗偩偼傎偲傫偳娭學側偄傛丅崱丄壌偨偪帺恎偑丄偙偆偄偆丄摉嬊傗戞擇慻崌偺楢拞偺偄偆偙偲偵偳偆巚偆偺偐丄偦傟偑帺慠偵壌偨偪偺峴摦傪寛傔偰偄偔傫偩丅偦偺寢壥偑丄慻崌偺堊偟偨偙偲偩傛丅
丂彮側偔偲傕壌偼丄傒傫側傪棤愗傝偨偔側偄傛丄偦傫側傫偩偭偨傜崙揝側傫偐傗傔偨傎偆偑傑偟偩乿
丂愢摼偡傞儅僯儏傾儖側偳偁傝摼側偄偺偩丅巹帺恎偑崙楯偺暘夛挿偱偁傞偲偄偆偙偲傕娭學側偄偺偩丅偨偩丄偙偺崱丄偙偺弖娫丄変乆偼摨偠乽惗乿傪惗偒偰偄傞偺偩偲偱傕偄偆幚姶偲嫟偵丄巹偺岥偐傜丄巹偱偡傜弶傔偰娫偔偙偲偽偑偁傆傟偰備偔丅偦傟偼偁傞堄枴偱壗偲偄偆岾暉側帪娫偩偭偨偐偲丄崱偼巚偆丅 偦偺帪乆丄偦偺憡庤偵傛偭偰丄偦偺応強偵傛偭偰変乆偺夛榖偼傂偲偮偲偟偰摨偠偙偲偽傪敪偡傞偙偲偼側偐偭偨丅偦偺応偱尵傢傟丄偦偟偰徚偊偰偄偔丄柍悢偺偙偲偽丄偦傟傜偑傂偲偮偺乽変乆乿偲偄偆傕偺傪峔惉偟巒傔偰偄偨偺偩丅
丂偍偦傜偔丄巹偑尵偭偰偄偨偙偲偽傪暥帤偵彂偒偲傔撉傒曉偣偽丄偦偺堦尵堦嬪偵斀榑偼壜擻偩偭偨偼偢偱偁傞丅偄傢偔丄拠娫偩側傫偩偐傫偩尵偭偰傕寢嬊偼帺暘堦恖偠傖側偄偐丄偄傢偔丄偒傟偄偛偲尵偄側偑傜棤偠傖傒傫側偄傠傫側偙偲傗偭偰傫偩丄偄傢偔丄帺暘偺恖惗偼帺暘偱戱偔偟偐側偄丄壌偼摉嬊傕慻崌傕娭學側偄丄帺暘偺敾抐偱惗偒偰偄偔乮偲尵偄偮偮側偤偐戞擇慻崌偵壛擖偡傞乯偲偄偭偨傛偆偵丅偙偆偟偨庡挘偺偦傟偧傟偺僶儕僄乕僔儑儞偼柍尷偵峫偊傜傟偨丅偟偐偟丄寢嬊偼偨偩堦揰偵廂懇偡傞偙偲偑尒偊偰偄偨丅偦傟偼丄乽帺暘偼帺暘乿偱偁傝丄愨懳晄壜怤偲偟偰摝偘偙傔傞壙抣偲偟偰偺乽巹乿丄乽屄恖乿丄乽帺屓乿偲偄偆椆夝偱偁偭偨丅偦傟偼拠娫偲偮側偘傞擏懱偺榬傪傕偨偢丄偨偩丄嬀偺傛偆偵壗偱傕塮偟弌偡偙偲偑偱偒傞婯斖惈偲偺傒丄堦懳偲側偭偰岦偄崌偭偰偄傞柍撪梕側帇慄偱偁偭偨丅偦偺帪偺懱偼丄嬀偱偁傞乽婯斖惈乿偐傜偺帇慄偵傛偭偰帺桼側摦偒傪嶦偝傟丄堦曽岦偵偺傒愗敆偟偰堌弅偟偰偄偨丅偦偟偰丄懳榖傪廔傢傜偣傞媶嬌揑側偣傝傆丄乽偍屳偄偺壙抣娤偺憡堘乿丄偲丄摨偠偔媶嬌偺偡偰偤傝傆乽壌偺恖惗偼壌偑寛傔傞乿丄偵夛偭偨帪丄変乆偼暿傟傞偟偐側偐偭偨丅
丂偙偆偟偰乽帺屓乿偲偄偆堄幆偼丄敪揥傗曄梕傊偺摴傪帺傜偲偞偟丄偩傟傕丄偳傫側榑棟傕擖傝偙傔側偄傂偲偮偺姰寢偟偨悽奅偲偟偰丄婏柇側偙偲偵帺桼傗帺庡偲偟偰偺乽帺屓乿偱側偔丄傓偟傠偦傟偲惓斀懳偺丄惂搙傗嫼敆偺惓摉壔乮偦傟傊偺廬懏壔乯偺偨傔偵乽帺屓庡挘乿偟偼偠傔傞偺偱偁偭偨丅惓妋偵尵偊偽丄乽帺屓乿傗乽屄恖乿偺宯偱偁傞偲偙傠偺帺桼傗帺庡偼丄帺傜偺廬懏揑敾抐偺惓摉壔丒愨懳壔偺偨傔偵乽懠幰偐傜偺晄壜怤偺壙抣乿偲偟偰巊梡偝傟傞偦偺傛偆側傕偺偲偟偰丄傓偟傠傂偲偮偺丄乽惂搙乿偺峔惉梫慺偦偺傕偺偩偲偄偆傋偒側偺偱偁傞丅偙傟傜偺偙偲偼丄乽帺屓乿偲偄偆堄幆偺宍懺偑丄傂偲偮偺摦偐偟摼側偄慜採偱偼側偔傓偟傠丄懠偺乽楯摥幰乿傗乽屬梡乿側偳偲偄偆奣擮偲摨條丄楌巎揑側憌偺拞偺扨側傞傂偲偮偱偁傞偙偲傪妋怣偝偣偰偔傟傞丅偙偲偽偑丄偙偆偟偨丄屒棫偟偨丄懠偲嫟桳寢崌偡傞扨埵傪傕偨側偄乽帺屓乿偲偄偆帺屓婯掕丄帺屓弞娐偺儚僫偵偼傑偭偨帪丄偳傫側偙偲偽傕恖乆偺屳偄偺娫偵丄怣棅偲偄偆夝曻傗揥奐傪婲偙偡偙偲偼偱偒側偔側傞丅偦偙偱偼懠偲偺乽娭學乿偼屒棫偲偄偆嫟怳傪屳偄偵堷偒婲偙偡偙偲偵偍偄偰惉棫偡傞偩偗偩丅偦偺拞偱恖乆傪摨偠峴摦傊偐傝偨偰傞偺偼乽帺屓乿偵傛偭偰惓摉壔偝傟偨嫟捠偺嫲晐偩偗偱偁偭偰丄屒棫偟偨棻巕偑摨偠椡偵傛偭偰摨偠曽岦偵摦偄偰偄傞偺偱丄乽嫟摨乿偟偰偄傞傛偆偵尒偊傞偩偗偩丅偦偺傛偆側強偱偼恖乆偼崻嫆傪幐偄丄偦偺帪偺惂搙偺婯斖椡偺巜偡曽岦偵塃偱傕嵍偱傕側偩傟傪偆偭偰偄偔丅
丂愭掱丄変乆偺偙偲偽偼偦偺帪乆偺尰幚偺帪娫偺拞偱堦夞尷傝変乆偺娫傪偮側偓丄変乆傪宍嶌傝丄傑偨暿偺偙偲偽丄峴摦偑偦傟傜傪揥奐偟偰偄偭偨偲尵偭偨丅偦偺傛偆偵丄帺屓弞娐偟側偄偙偲偽傗峴堊偵傛偭偰偙偦恖偼惗偒偰偄傞偙偺尰幚偺柍尷偺壜擻惈傪尒幐傢側偄偙偲偑偱偒傞丅拠娫偲偄偆偙偲偺捈愙惈偵惗偒傞偙偲偑偱偒傞丅偦傟偼條乆偵惂搙偑偟偐偗偰偔傞擇幰戰堦傗壗傗傜丄変乆偺巚憐傪昻偟偔姞傝崬傓奣擮傪柍岠壔偟偰偔傟傞丅
丂偙傟傜偺偙偲偼丄恖偑丄慖暿偵斀懳偡傞慻崌偐傜扙戅偟偰慖暿傪庡挘偡傞慻崌偵壛擖偟偨偐丄偦偆偟側偐偭偨偐偼丄偦偺恖屄恖偺愑擟偲偟偰徧偊傜傟偨傝棤愗偲偟偰斱偟傔傜傟偨傝偡傋偒偙偲偱偼側偔丄偦偺恖偑偄偨応強偱偳傟偩偗廤抍揑偵憡屳怣棅偑抸偐傟偨偐丄媡偵乽帺屓乿偵暘抐偝傟偰偟傑偭偨偐偺寢壥偵偡偓側偄偙偲傪堄枴偡傞丅偦傟偼丄扙戅偟傛偆偲偟偰偄傞恖偵丄偦傟偼棤愗偵側傞偺偩偲愢摼偡傞偙偲偲柕弬偟側偄丅偦偆偄偆愢摼偑丄偦傟傪偟偰偄傞変乆偑丄斵傜偲怣棅傪嶌傝摼側偐偭偨帪丄帠懺偼寛偣傜傟傞偺偩偐傜丄変乆偼斵傜偲怣棅傪嶌傝摼側偐偭偨偙偲傪丄偦偺側偤偩偭偨偐傪徣傒側偗傟偽側傜側偄偺偩丅扨偵丄屄恖偺乽桬婥乿傪徧偊偨傝乽棤愗乿傪旕擄偡傞塣摦偱偁偭偨偲偡傟偽丄偦傟偼偦偆偟偰偄傞変乆帺恎偑傑偩丄乽屄恖乿乽帺屓乿偺愨懳惈偲偄偆嫊峔偵偲傜傢傟偨攕杒傊偺摴傪曕傫偱偄傞偙偲偵側傞偺偩丅
丂変乆偼丄傂偲偮偺塣摦偺拞偱丄乽変乆乿偲偟偰拠娫傪妋怣偡傞丅偙偺乽変乆乿偲偄偆傕偺偙偦丄乽巹乿傗乽帺屓乿偑偨偲偊偳傫側晄栄偺愨朷姶偵偝偄側傑傟偨栭傪夁偛偟偰傕丄梻挬丄偍偼傛偆偲尵偭偰奆偲惡傪偁傢偣偨弖娫偐傜丄嵞傃姼慠偲悽奅偺拞傊摜傒弌偝偣偰偔傟傞尨摦椡側偺偱偁傞丅偦偟偰丄棳捠偟偰偄傞條乆側奣擮傪媈偄怴偟偄悽奅椆夝傊偮傟偰偄偭偰偔傟傞曣懱側偺偱偁傞丅傂偲偮偺怑応偺拞偱偦偺拞偺偛偔偝偝偄側擔忢偺弌棃帠偺暘愅偑丄変乆傪悽奅揑側晛曊惈偵傑偱楢傟偰峴偭偰偔傟傞丄崱偼偦偆偄偆帪戙偵撍擖偟偨偺偩偲巚傢傟傞丅
丂
偦偺帪丄偙偺乽変乆乿偺偙偲傪丄変乆偼側傫偲屇傇傋偒偩傠偆偐丄乽楯摥幰乿丠乽巗柉乿丠 傕偼傗偄偢傟偺屇傃柤傕傆偝傢偟偔側偄丅側偤側傜丄乽変乆乿偼丄傑偝偵偦傟傜偺奣擮傪偺傝偙偊傞夁掱偱惉棫偟偰偄傞偺偩偐傜丅
仸2020/09/23丗1師帒椏傊偺儕儞僋嶌惉
彅榑峫偺栚師傊栠傞