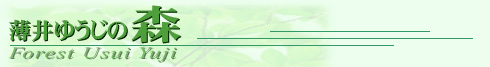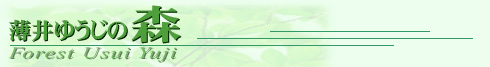|
 あとがき あとがき
早朝、五時半にラスベガス近郊のモーテルを出た。まだ薄暗い。すこしずつ地平が明るんできて、バックミラーに朝日がまぶしく映りはじめる。僕はフォード・サンダーバードで西へ向かっている。時速六十五マイル。地平線の彼方までどこまでもつづく一直線の道路に対向車はなく、ミラーにも車の影はない。このまま、どこまでも走ろうと思う。
*
何度目のアメリカだろうか。格安の航空チケットを買ってレンタカーを借り、モーテルを泊まりながら気ままに荒野を走る。アメリカの大地は果てしない。見えるのは地平線だけ。ときおり僕は車を停めて荒野に一人降り立つ。三百六十度すべてが荒野で、すべてが地平線だ。そんななかにじっと身を置いていると、自分がいまどんな場所にいるのかを把握しきれなくてかるい目眩のようなものを感じる。あの地平線まで行けば何かがある、そう思いながら僕はまた車を走らせる。そうして地平線までたどり着いたとき、前方にあるのはまた新たな地平なのだ。
*
ノン・ジャンル。どんなジャンルにも含まれない、境界線ぎりぎりの小説を書きつづけてきたつもりだった。この境界線上の旅は、アメリカの荒野の旅に似ている。果てしのない境界線に囲まれながら、僕はたどり着くことのない旅をしている。
ここに収録された一連の短篇は、怖い小説なのだと思う。だが、怖さというものに区切りなどはなく、どこからどこまでを書けば怖さなのかわからない。そして気がついたことがある。怖さを書かないこともひとつの怖さなのではないかと。
*
表題作の短篇『枕時計の女』は、十五年以上も前に書いたものに加筆したものだ。そのころの僕は発表するあてのない小説をたくさん書いていて、それらはいま押入の奥で眠っているけれど、この一篇だけがこうして活字になった。昔の通信簿を見せられているみたいで妙な感じがするけれど、僕はあのころから曖昧な、境界線上の物語を書こうとしていたらしい。
*
果てしのない荒野を走りつづけて僕は小さな村にたどり着いた。シュショーニというその村には民家が数件と、郵便局とカフェとガソリンスタンドとモーテルが一軒ずつしかない。僕は「赤い馬車」という名の小さなカフェに入り、朝食をとった。トーストと卵焼きを運んできたカフェの女主人に、「日本から来たのか」と話しかけられた。その通りだと答えると彼女は信じられないというような顔をした。「なにも日本からずっと車で走って来たわけじゃないんだけど」僕は笑って答えた。そして彼女は訊いた「どこへ行くのか」と。「地平線まで」僕がそう答えると彼女はおおらかに笑った。ここには地平線以外、行き先などないのだ。
------------------------------------------------
一九九六年五月 カリフォルニア州シュショーニの村で 薄井ゆうじ |
|