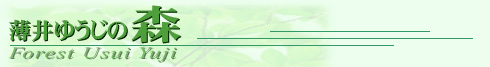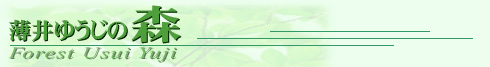|
 あとがき あとがき
夕刻の都会を抜けて、川崎から約十キロもつづく長いトンネルをくぐると、ぽつんと海の上に出た。そのむこうは木更津まで長い橋になっている。東京湾アクアライン。東京湾を横切るこの長いトンネルと橋との繋ぎ目には海から塔がにょきりと突き出ていて、「海ほたる」と名付けられたレストエリアがある。僕はいま、そのなかにあるレストランの窓際の席で、暮れていく海を見ている。彼方には遠く、沈む夕陽を待ち構えるみたいに富士山が黒々と横たわっている。
*
僕の仕事場は東京の下町にあって、そこへ行く途中、小さなトンネルを抜ける。歩行者しか通れない、背を屈めながら通るような狭いトンネルで、昼間も薄暗く、蛍光灯がいつも灯っている。そのトンネルの先にはいきなり踏切があって、雨の日はトンネルのなかで雨宿りしながら踏切が開くのを待っていたりする。仕事場へ行くためにそこを通るとき、僕の頭のなかにはいつも、「異界」という言葉がぶら下がる。これから小説を書く場へ行くのだ。そこは異界に違いない。そんなふうに思うのだが、仕事を終えて町へ出るためにそのトンネルを戻るとき、こんどは町という名の異界へ出るのだ、という気持にとらわれる。異界から見れば日常こそが異界なのだと、当たり前のことに気付かされるのもこのトンネルのなかだ。東京湾の下を通る長いトンネルを車で走りながら僕は仕事場近くの小さなトンネルのことを思い、そしてこの物語に出てくる人物たちが通過する様々なトンネルのことを思った。ひとはなぜ、異界に焦がれるのだろう。
*
この小説を書きはじめたころ、東京湾横断道はまだ建設中だった。物語のなかに木更津と川崎を繋ぐ長い橋が出てくるが、もちろん東京湾横断道のことだ。まだ完成していないものを小説に書く不安から、僕は執筆の合間を縫って横断橋建設現場近くまで行って、どんなものができるのかを確かめたりした。だが海岸から眺めても橋の完成形がどんなものになるのか、よくわからなかった。そして橋が開通した直後、すぐ確認のために橋を渡ってみようと思ったのだが、この小説の執筆に追われて時間がままならず、はじめて来たのが、ゲラを読み終えた今日になってしまった。不思議なことに橋は僕が想像していたものと、ほぼ同じだった。そこから見える景色も想像通りだった。もしかしたら僕は遠い昔、完成前のこの『海ほたる』へ来たことがあるのではないだろうか。もちろん、そんなことはあり得ない。僕のなかの何かが、未来のイメージを逆デジャ・ビュのように先取りして映像化していただけなのだろう。
*
近未来を小説に描くことはいままでにもあったが、この小説のようなかたちで衣食住、都市交通、行政から物流に至るまでの一切の世界を構築したのは、はじめての経験だった。小さなもの、たとえば電話機ひとつを描くにしても、それはその世界のすべての象徴であり縮図でもあるわけで、細かい部分をおろそかにすれば、たちまち全体が崩れてしまう。すべてをつくるのだ、そういう思いで書きつづけた結果、森羅万象、原子から宇宙までを僕独自の感性で再構築する羽目になった。当初は、三百五十枚程度で書き上げる予定で取りかかったのだが、小説の場を構築する――それはとても楽しい作業だった――必要性から、七百七十七枚という僕にとっては驚異的な数字になった。777。ビンゴである。
*
僕はこの小説を、未来小説としては捉えていない。未来は現在の延長であるし、完成する前の橋を描かねばならないように、見えないはずの未来を架空の目で見て描き切るということも小説という作業の重要な一面ではないかと思っているからだ。どんなに小さなものでも、未来の断片には必ず現在が包含されている。
*
かつて僕は、電子ペット飼育ゲームを扱った『天使猫のいる部屋』という長編小説を書いた。あれから七年後にそういう商品が大流行したとき、何人かから「あの電子ペットは薄井さんのアイデアですか」と訊かれたけれど、僕は商標登録も実用新案登録もしていない。すべてのものは、同時多発的に複数の人間が考えつくものだと思っている。あの小説を書いた時点では将来電子ペットが登場するだろうという予感があっただけで、自分が描くものを未来の先取りなどとは考えていなかった。小説は、書いた時点で現在になるのだから。僕はこう思っている。小説という作業もそうだけれど、生きるという作業も、未来をひとつずつ丁寧に確定していく作業に他ならないのではないだろうか。次々と容赦なく迫ってくる未来という時間を、根気よく現実のものとして確定していく作業の連続においては、自分という森羅万象体の個性を信じるしかないのだ。
*
こうしているうちに窓の外の夕陽は富士山のむこう側に落ちて、海は暗くなり、遠く川崎や千葉の灯が美しく見えはじめた。都会を抜け出し、長いトンネルを通って僕はここへ来た。ここは僕にとって、ドームの外なのか。あるいは遠い都会の灯が、ドームの外側なのか。僕はたぶん、小説を書きつづけるだろう。混沌として掴みどころのないように見えるこの世界で、未来を文字というかたちに置き換えて、根気よく、ひとつずつ物事を物語に固定していく作業を繰り返していくのだろうと思う。『海ほたる』のレストランは、二十四時間営業している。深夜も暗い海の真ん中で、ぽつりと明かりをともして営業しつづけるのだ。僕と同じだ。
*
余談だけれど僕はかつて、『たの・かえる』というペンネームで週刊誌などにイラストを長年描いていた。下手くそな絵だったけれど、そんな僕になぜ仕事が十三年間も途切れずにあったのか不思議でならない。そのころ、僕に限らず若者は誰もがある人物を神様のように思っていた。横尾忠則氏である。いま、この本の装丁を横尾氏に引き受けていただいて、僕にとっても『狩人たち』という物語にとっても、本当に幸せなことだと思う。僕は二十数年前、横尾忠則氏が週刊プレイボーイ誌にカラーの大きな挿し絵を連載していたとき、その裏側のページに小さなカラーのカットを描いていたことがある。そのころの僕はただ、横尾氏の裏のページにたまたまカットを描いてるだけなのに、「むふふ」と思った記憶がある。だから今回、僕の小説の装丁を神様に手がけていただいたりして、僕はもう、「むふふふふふふ」なのである。なお、この物語を書くにあたって、フィールドワイの鈴木誠二氏に未来雑学考証とでもいうべき知識についてご協力をいただきました。明記して感謝の意を表します。
------------------------------------------------
一九九八年三月・東京湾アクアライン『海ほたる』のレストランにて 薄井ゆうじ |
|