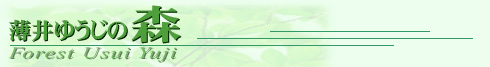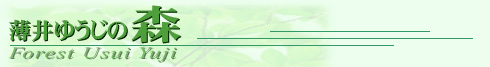|
 あとがき あとがき
長編小説を書きはじめると、僕の睡眠時間は極端に短くなる。起きている時間のほとんど−−、一日十八時間以上もワープロの前にすわっている日がつづく。キーボードを叩く作業というのは指と腕が動く程度のわずかな運動量しかないわけで、これでは運動不足にならないほうがおかしい。なんとかしなければ。そう考えていたとき、あることを思いついた。
書くこと自体が運動になればいいのではないだろうか。そのためには、キーボードを巨大なものにするのである。ひとつのキーが一メートル角ぐらいのキーボードをつくるのだ。打つときは両手と両足で、しかもジャンプしながらキーからキーへと渡り歩いていく。以前、そういう室内ゲームが流行ったことがある。赤を右足で踏みながら青は左手で触るというやつ。あれに似た、もっとスポーティな感じの巨大なキーボードをつくれば、世の作家の運動不足は即座に解決するのではないだろうか。名案である。
*
しかし、そんな巨大なキーボードを、どこに置けばいいのだろう。ざっと計算してみても、長辺が四十メートル、短辺が十五メートルほどのキーボードになる。いまの仕事場に、そんなものは入りきれない。どうしたらいいのだ。そこで次の手を考えた。僕は幸い、団地に住んでいる。ここには四百戸入っているから、その一軒一軒にお願いして、キーを預かってもらうのだ。たとえばお隣さんには「A」を、そのお隣さんには「B」のキーを。こうしてすべてのキーを各戸に分散しておいて、文章を書くときは団地内を走りまわり、各戸のキーを叩いてまわるのだ。これはかなりの運動になる。しかも楽しい。
「ぴんぽーん。すみません、キーを押しに来ました」
「あれえ、しばらくお見えにならなかったけど」
「ええ、Wの文字はこのところ、ぜんぜん使わないもので」
「たまには使ってくださいよ」
「はいはい。またWのときは、よろしくね」
などと会話は弾み、都会の団地のコミュニケーションも完璧に保たれることになる。ここに書いた「あとがき」くらいの文章の量を打ちこめば、終わるころには各戸でいただいた、田舎から届いた野菜やらお菓子やらで、両手がいっぱいになってしまうにちがいない。今後ワープロは、そういう方向へ進むと僕は信じている。
*
さて。巨大なキーボード。そういうものをイメージしただけでも、大きさというものが、ときには質までも変えてしまうことがあることに気がつく。そのことを、なんとか小説に書けないものだろうか。そう思って書きはじめたのが、この『星の感触』だった。大きさの変化は、質の変化をも意味する。いまはダウンサイジングの時代だけれど、もしかしたらそういう時代にこそ、巨大化する悲しさのようなものが書けるのではないか。あるいはだからこそ、大きさというものに左右されない何かが書けるのではないかと考えたのだった。
*
「すみませーん、お宅、取り消しキーでしたっけ?」
「そうですけど。あなたこのごろ、うちにばっかり来るじゃないの。ちゃんと書けてんの?」
「いやあ、このところ書き直してばっかりなんです」
「がんばってね、期待してるんだから」
「はーい」
こうしてこの長編は書き上がったのである。その間、僕は団地内を走りまわり、延べ十六万回ものチャイムを鳴らしたことになる。ああ、しんど。−−と、そんなことを考えてみたくなるほど、僕の指はキーボートの上を走りまわった。書いているとき、ひとつひとつのキーの下には、ちっぽけな山本さんや、ちっぽけな岡田さんや、ちっぽけな橋本さんが住んでいるのではないかという気分にもなった。みなさん、その節はお邪魔いたしました。
*
大きさというものは不思議なものだなと思う。記憶にはないけれど僕は、ちっちゃな赤ん坊として生まれてきたはずだ。それがいつの間にか、母親の身長を超えた。ひとは誰だって、ちっぽけだった時代を持っている。そのことを忘れてはならないはずだし、逆に、大きくなることを恐れてもいけない。久しぶりに実家へ帰って母親の小さな背中を見ながら、僕はそう思った。
------------------------------------------------
一九九四年一月一日 僕の誕生日・茨城後台にて 薄井ゆうじ |
|