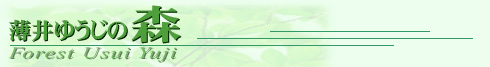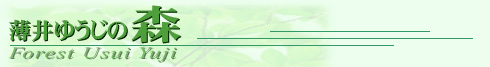|
 あとがき あとがき
桜が満開の季節。静かな春の午後だ。僕はいま地下鉄東銀座駅近くの近代的な明るいビルの二階にあるラウンジにすわって、コーヒーを飲んでいる。目の前のテーブルの上にはノート型のパソコンがあって、その液晶画面がキー入力を待っている。そこに僕は文字を書こうとしている。この二年間、僕は『鳩よ!』という月刊誌に短い小説を連載してきた。その二十二本の短篇小説が単行本にまとめられることになったので、そのあとがきを書こうと思うのだ。
マガジンハウス。ここはその出版社の打合せ用のロビーだ。FM放送だろうか、気持のいい音楽が目立たないくらいの音量でラウンジに流れている。広いフロアに配置された洒落たデザインのテーブルと椅子はほとんどが空席で、二、三組の編集者らしい人物をまじえた客が小声で打ち合わせをしている。時間は、穏やかに流れている。
*
いまから二十年以上も前のことになる。この出版社がまだ『平凡パンチ』という男性週刊誌を発行していたころ、僕はイラストを抱えてこのあたりを歩いていた。そのころの僕はまだ駆け出しのイラストレーターで、雑誌社から依頼される埋め草用のイラストレーションをぽつぽつと描いて暮らしていた。徹夜で描き上げた挿し絵用のイラストを届けるために僕は睡眠不足の頭を抱えながら地下鉄に乗った。そのころ平凡出版という名だったこの出版社の、お世辞にも綺麗とはいえない編集室に通っていた。『平凡パンチ』の編集部は木造の、ぎしぎしと音を立てる狭い階段を昇ったところにあった。世の中の混沌がすべて凝縮したみたいな編集室だった。汚くて猥雑な場所だったけれど、そこは当時の若者の文化や情報を、そして新しい時代の予感を牽引していたエンジンルームでもあった。
*
編集部にイラストを届けたあと、僕はその足で銀座の街へ出た。クラシックレコードを聴かせる静かな喫茶店があったのだ。『らんぶる』。その店で、いまにして思えばお世辞にも旨いとは言えない、それでもあのころは香ばしくて贅沢なコーヒーを飲みながら、僕は暗い店内で何時間も本を読んだ。そしてすこし眠った。夕方近くになると喫茶店を出て、東中野にある三畳一間のアパートへ、とぼとぼと帰っていった。イラストレーターなんて、決して派手な職業ではなかった。黙々と絵を描き、その褒美に僕は一杯のコーヒーを自分におごり、そして肩をすくめながら三畳間に帰って泥のように眠ってしまう。そうした日々が二十年くらい前の僕には確かにあったのだ。
その喫茶店もいまはなく、『平凡パンチ』は休刊して、平凡出版はマガジンハウスと社名を変えた。あの古びていまにも壊れそうな木造の階段とその奥にあったカオスのような混沌とした編集室もいまはない。建物は取り壊され、その跡地には空港のロビーかと思うような近代的でおしゃれなビルが建った。マガジンハウス。僕はいま、そのかつて『平凡パンチ』の編集室があったはずの二階の空間の清潔なラウンジに、いまは作家としてすわっている。時間というものがこんなふうにあわただしく過ぎていくなんて、想像もつかなかった。僕はあのころ、小説を書きたかったイラストレーターだったのだ。
*
僕はいまそのロビーで、短篇集のあとがきに何を書こうかと呻吟している。大きく切り取られた明るいガラス窓のむこうに路地が見える。ぼんやりとそれを眺めていると、もしかしたらあの路地を、かつての僕がイラストの入った紙袋を抱えていまにも通りそうな気がする。その「僕」に対して、いま僕はいったい何を書けばいいのだろう。これは、きみの物語だ。そう書けばいいのだろうか。それは照れ臭いような気がする。イラストの仕事だけでは食えないために、それと平行して日雇いの日々を送っていたきみに対して、こんなおしゃれなビルのラウンジでふんぞり返って、「これはきみの物語だ」などと偉そうにはとても言えない。
それでもこれは、きみの物語なのだ。なぜそう思うのだろう。この短篇のなかに登場する人物は、かつての僕ではないし、現在の僕でもない。僕に似た、あるいは僕の友人や知り合いの誰かによく似た人物たちの点描でしかない。そんなものを「きみだ」と言われたら、きみはとても迷惑そうな顔をするにちがいない。
*
もしその路地を通りがかったら、ここへ来ないか。ここへ来て一緒にコーヒーを飲まないか。こんな静かで綺麗なラウンジに腰をおろすことをきみはためらうだろうけれど、それでもここはとりあえず僕の、いまいる場所なんだ。もちろん、僕はいつまでもここにすわっているわけではない。きみとすこしだけ話をして、コーヒーを飲み終えたら僕もここから立ち上がって歩き出そうかと思っている。
思いだした。きみのイラストレーター時代のペンネームはたしか「たの・かえる」といった。きみは『平凡パンチ』ですこし仕事をしたあと、『週刊プレイボーイ』で五年間くらい毎週イラストを描きつづけることになる。どうしてそんなことを知っているのかって? どうしてかな。その後、『夕刊フジ』のイラストなどを描いて、それから……。聞きたくないんだろうな、そんな話。きみが僕になるまでの話なんて、きみには関係ないんだから。
*
外は雨が降ってきたみたいだね。僕も傘なんて持っていない。きみも相変わらず、傘を差すのが嫌いなようだね。相変わらず、という言葉はきみにではなく僕に使うべきだろうけれど。とにかく雨が小降りになるまで、もうすこしここにいようか。コーヒー、もう一杯どうかな。遠慮しなくてもいいんだ、コーヒー代くらいなら持っているから。こういう言い方は気に入らないかもしれないけれど、一杯六十円のコーヒーで半日もクラシック音楽を聴いていたきみが懐かしい。きみのポケットには帰りの電車賃が新宿までのぶんしかなくて、あとは東中野まで歩いたんだよね。それでも音楽が聴きたくて喫茶店に入ってしまうんだ。妙な時代だった。はじめてタクシーという贅沢なものに乗ったのもあのころだった。終電車がなくなる時間を過ぎても編集室でイラストを描いていると、出版社がチケットを切ってくれて、きみは深夜のタクシーで部屋に帰った。ああ、このタクシー代さえあればあと半月くらいは腹一杯何かが食べられるのに、ときみは思ったよね。こんな話はやめよう。いまのきみには関係ないんだから。きみは、きみでありつづけていればいい。
*
きみはコーヒーを飲み終えて、僕に挨拶もしないでこのラウンジを出ていく。妙な男に出会ってしまったというような表情をして。こつこつ、ときみが遠ざかる足音が路地のほうから聞こえてくる。雨はまだ止まない。僕はそのまましばらくじっとしている。いまでもあの木造の、オンボロの階段はあるのだろうか。その奥には若者を熱狂させた週刊誌の編集室がいまもあって、きみはそこでイラストを描きつづけているのだろうか。だとすれば、この明るいラウンジで阿呆のようにすわっている僕は、いったい何なのだろう。きみが遠ざかってからずいぶん多くの時が過ぎた。きみに出会えただけでも奇蹟なのだろう。
きみの飲みかけのコーヒーはもう、すっかり冷めてしまった。気がつくとテーブルの上に、きみが置いていった小銭がレシートの上に、きちんと並べられている。きみは自分のコーヒー代を黙って置いていった。僕は深い溜め息をつく。僕はきみに何もしてあげられない。たった一杯のコーヒーをおごってあげることさえできないのだ。
*
きみはきみの路地を歩いている。そして僕は、僕のために「あとがき」を書く。そうしていつかまた、たとえば十年後に僕は、きみという名の「僕」に出会うだろう。それをいったい何度繰り返せば僕はきみになれるのだろうか。目の前にはいま、冷めたコーヒーカップとワープロがある。そして僕は、もう一杯熱いコーヒーを注文しようかどうか、さっきから迷っている。
------------------------------------------------
一九九六年四月十一日 マガジンハウスのラウンジにて 薄井ゆうじ |
|