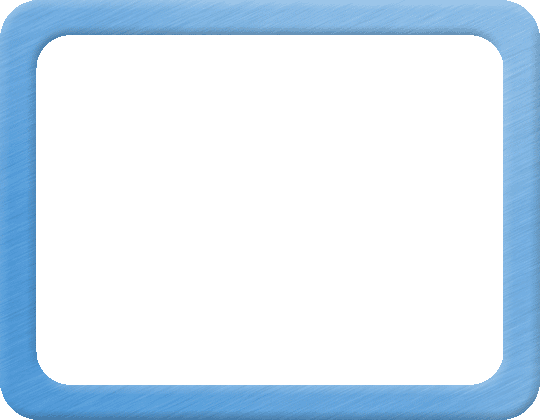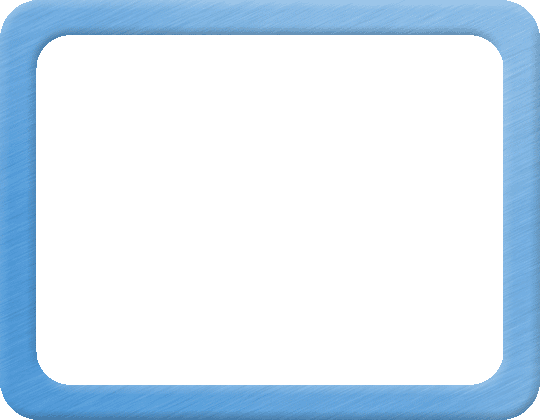ジョン・ダワー『敗北を抱きしめて 増補版』
(岩波書店) 上巻 Page 1
(済みません、まだ上巻しかありません)
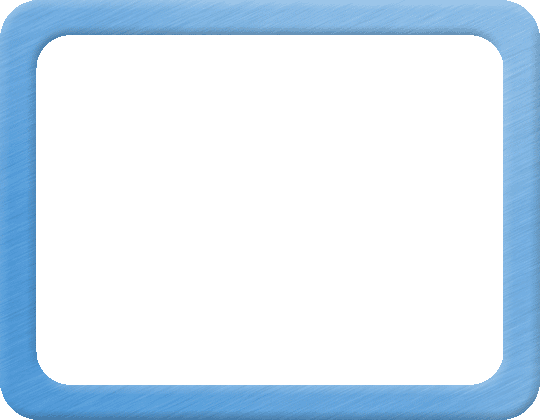
序
黒船以来、日本の近代国家としての興隆ぶりは凄まじいものだった。折しも西欧列強が植民地権益をめぐってしのぎを削っていた時代、突然アジアの一角から姿を現したこの小国は、日清、日露、第一次大戦などでヨーロッパの強国と肩を並べて戦い、勝者として獲物の分け前に与った。
やがて世界的な恐慌と動揺の時代に入ると、日本は単独でアジアの市場と資源を支配しようと、破竹の勢いで領土拡大を続けた。その国家戦略を支えたのは、天皇をふくむ指導部による、国民に対する徹底した思想統制、洗脳である。だが野望がもたらした結果は、まれに見る徹底した敗北であった。
こうして史上に例のない、「上からの」、軍事独裁機関による一国の「非軍事化、民主化」という事態が始まった。勝者に対する敗戦直後の日本人の対応は、まったく事前の予想を裏切るものだった。狂信的な天皇崇拝者による徹底抗戦を予期して日本へ上陸したアメリカの軍隊は、なんとも平和的で友好的な日本民衆に迎えられたのである。かつての命知らずで残忍な敵の姿はなく、ただただ荒廃と破壊に打ちのめされ、厭戦気分に浸り、過去を忘れたがっている惨めな敗者の姿だった。
勝利は圧倒的だったので、勝者のなすことだけに注目が集まるのも無理はなかった。だがここには、単に勝者の弱者に対する征服、支配、統制があっただけでなく、「抱擁embrace」ともいうべき事態、いいかえれば敗者の側からの占領者に対する影響、関与があった(レジメ作成者注: embraceという英語には、物理的に抱きしめるという意味意外に、次のような含意がある。①考え・コンセプト・計画・申し出などを喜んで応じる、快諾する、これ幸いと受け容れる ② ~を見て取る、悟る、包括的にとらえる ③ (主義・思想などを)受け容れる、採用する)
本書においては、日本人の敗北の体験を、「内側から」、民衆意識のレベルで、つまり社会のすべての人々の声を聞き取るよう努力した。敗戦について、何か日本人全体として一律の体験があったわけではない。彼らの敗北への反応がどれほど多様で活発なものになるか、日米双方の誰も予想できなかった。
たとえば、生まれたばかりの労働運動の爆発的エネルギー、売春婦や闇市の出現、カストリ文化やデカダンス、占領軍への膨大な手紙、米国流の豊かさへの憧れ、こういうことはアメリカ側はもちろん、日本人自身でさえ予想しなかった現象だった。混乱した状態だったが、同時に活気と解放感に満ちた時代だった。
そこから占領軍を解放軍とする発想も出てきた。たしかに占領軍が導入したのは、ニューディールのリベラル思想、社会改良主義、権利章典的な理想主義に影響された、当時としては例外的なほど革新的な改革だった。それはアメリカ本国ではすでに否定、または無視されていた姿勢だった。
だが、この理想主義的な色彩がもっとも濃かった占領初期でさえ、占領政策は自己矛盾を抱えていた。ここまでの過激な「民主化」を、厳格な権威主義的支配を貫徹しつつ実行しなければならなかったからである。その結果、白人支配の占領政策のため、帝国日本からもっとも被害を受けたアジアの人々が、この敗戦国で指導的役割を果たせなくなってしまったこと、GHQと日本政府による二重の官僚支配、天皇制の温存による戦争責任の曖昧化など、将来に大きな禍根を残した。
功罪いずれにしても、戦後日本を形成した大きな要素が、じつは征服者と被征服者との複雑な相互影響から生まれたのである。
日本の敗戦体験を日本の特殊性と結びつけて語ることは、外国人のみならず、日本人自身によっても好んで行われる。だがそのようなとらえ方は一面的でしかない。むしろ、この敗北と占領はすべての人間の生にとって最も基本的な問題との闘いであり、そうした問題と取り組む日本人の姿は世界全体に訴えかける力をもっていたというべきだろう。たとえば叩き込まれた軍国主義をいとも簡単に捨てた点では、イデオロギーの脆さというものを示唆しているし、苦難に際して民族や集団のアイデンティティがいかに被害者意識に染まりやすいかをも物語っている。
現代の日本には、この敗北と占領を外国モデルの一方的押しつけの時代、圧倒的な屈辱の時代ととらえるネオナショナリズム的な主張があるが、私(ジョン・ダワー)自身は、この時代がもっていた活力と、日本の戦後意識の形成において日本人自身が果たした役割の創造性とを、このような見方より積極的に評価している。大切なことは、当時、そしてその後、敗戦というみずからの経験から、日本人自身が何を作り上げたかということである。
第一部 勝者と敗者
第一章 破壊された人生
日本の敗戦は天皇の放送(玉音放送)とともにやってきた。天皇裕仁は満州侵略を黙認し、その名において中国との全面戦争を開始し、合衆国と欧州に宣戦を布告した当の人物であったにもかかわらず、「彼個人はなんら責任を問われないようなやり方で、負け戦を終わらさなければならなかった」(p.21)。
詔勅は、今次の戦争は侵略目的からではなく日本の生存とアジアの安定を確保するために行われたが、原爆投下を含め凶暴な敵の行為による人類の滅亡を防ぐために終結を決意した、という言い方で巧みに敗北についての言及を回避し、降伏を美化していた。
天皇とその周辺(そして米国)が恐れたのは、敗戦日本における革命反乱の可能性であり、この放送は「敗戦国家の社会的・政治的安定を図ると同時に、天皇の支配を維持するための緊急キャンペーン」(p.25)として行われた。実際それは、天皇が放送を通じて直接国民に語りかけるという前代未聞の手法(裕仁自身が考えたといわれる)と、天皇自身を無類の国難の体現者、犠牲者に仕立て上げた細心の文言により、降伏時点での反乱や混乱を防ぐ上で多大な効果をあげたと思われる。
戦艦ミズーリ号上での降伏文書調印式にも、本来出席すべき天皇やその側近は出席を免れた。当時は皇室派のアメリカ人官僚でさえ、天皇は当然出席して降伏文書に署名するだろうと考えていたので、この連合国側の譲歩に驚いたほどである。
その後の数週間、敗戦日本に乗り込んできた勝者は、この国のすさまじい荒廃ぶりに驚くばかりであった。この状態で日本があれだけ抵抗を長引かせたこと自体、驚嘆すべきこととされた。広島長崎をふくむ66の大都市は空襲で全市街地の40パーセントが破壊され(東京では60パーセント)廃墟になった(ただし、後に占領軍が接収することになる高級住宅地や金持ちの家は焼かれずに残されたが)。戦争で死亡した戦闘員・非戦闘員は270万人。その他負傷者・罹病者が数百万人。戦争による物的被害は全国の富の三分の一にのぼり、全所得の三~二分の一を失った。
数百万の人々が中国、台湾、朝鮮、東南アジアとフィリピンなどの外地に残され、満州だけでも17万9000人の一般市民と6万6000の軍人が命を落とした。170万の人々がソビエトに捕らえられて使役され、そのうち30万人は完全に消息を絶った。
国内でも数知れぬ女、子ども、老人、そして復員してきた傷病兵や引揚者が家も身内もなく路頭をさまよい、相当数が栄養失調で死亡した。あとにも先にもないほど、社会的弱者に対して冷酷な弱肉強食社会が出現した。
しかし瓦礫の中に立つ人々に解放感や希望がないわけではなかった。「完全な敗北という認識があったから、目前で古い世界が破壊され、新しい世界を想像するほかなくなった人間にだけありうるような、すばらしい回復力と創造性と理想主義が発揮されることになった」(p.35)
第二章 天降る贈り物
敗戦後の恐るべき混乱(激しいインフレ、食料不足、闇市、政府の無能…)のなかで、占領軍は神の手のように日本を解放し、自由を与えた。ポツダム体制は連合国による占領といわれているが、実際には「占領の全側面について基本政策を決定し、最大の命令権を行使したのは、アメリカ合衆国ただ一国であった」(p.73)。マッカーサーは単独指揮権を与えられておりそれを隠そうともしなかった。
占領軍は日本の民主化、非軍事化を達成するために驚くほど大胆な改革を行った。日本をアジアの悪の根源にした「戦争の意志」を取り除き、侵略の根源を「根絶やしにする」ことが必要とされた。「戦争の勝者がこのような大胆な企てに乗り出すことは、法的にも歴史的にも前例がなかった。……一般大衆のものの考え方そのものを変革するという、多国を占領した軍隊がかつてしたことのないような企てにとりかかったのである」(p.72)。このような改革は、ひとつには、戦争終結前に米国内部で、日本占領に関して保守の知日派とニューディーラーなどのリベラリストのあいだに意見の相違とヘゲモニー争いがあり、リベラル派が勝利したために実現したのである(詳しくは後述)。
また日本は「マッカーサー式 MacArthesqu」の支配下におかれたが、これは「ひとりの人物の個性が歴史に明確な刻印を残した、めずらしい出来事であった」(p.81) 戦後日本の零落した姿は、「ドイツに対しては考えられないような、民族的優越感にもとづく宣教師のような情熱をかきたてた」(p.81)のである。
このようなかつてない占領政策を正当化したのは、「第二次世界大戦が先例のない破壊力による悲劇であった以上、過去のやり方を踏襲していたのでは、安定した世界秩序はとうてい実現できないという主張……国際社会における新しい行動規範を創造しようとする明確な意識」(p.82)があった。
軍事独裁や新植民地主義的独裁A neocolonial military dictatorship.から民主主義革命が生まれたことなどかつでなかったが、マッカーサーの軍事支配はまさにそのことをめざしたのである。多くの急進派アメリカ人はこの矛盾を意識していたがひるまなかった。保守日本政府の抵抗をきっぱりと退け、治安維持法の撤廃、政治犯の解放、婦人参政権の導入、労働組合運動の促進、教育の自由化、財閥解体、農地改革、国家神道の国家からの分離、公職追放など次々と改革が断行された。
1946年11月には新憲法が公布。「改革計画にとっては王冠に輝く宝石のような存在だった」(p.85)。
一方保守派の国家エリートにとって、降伏後最優先の課題は、社会の激変を避け、天皇中心の「国体」を不変のままに維持し、日本経済を立ち直らせることであった。彼らは戦争の根本的原因を究明することは避け、軍内部の一部による逸脱だったのだから構造的制度的改革は不要だと主張した。彼らに戦後を任せたとすれば、「実行されたのは、軍指導部の穏便な追放や、将来極端な軍事的行為に走らないようにするための小規模な改革であったろう」(p.86)
このような占領軍について、1947年までは、共産党やその他の左翼も含め、ほとんどの日本人が占領軍を解放軍と考え、ナイーヴにその政策を支持した。
だが時間がたつにつれ、「上からの革命」という発想そのものに内在する主体性のなさと内容のなさに注意を喚起する言論人が多くなっていった。たとえば南原繁は、明治時代は近代国家の「外観」をつくりあげたにすぎず、個人の人格が確立していない日本では「政治上の民主主義は、いまだ真の生命的存在となっていない」と訴えた。

哲学・思想書レジュメ4