|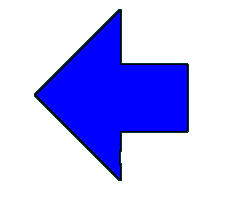 (独身者の....)|
(独身者の....)|
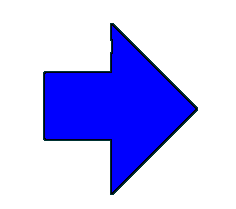 (スウカイナ7 目次)|
(スウカイナ7 目次)|
コラム
●荒木悠之
美しい景色
本を読んだり、書類を作ったりといった机仕事の折に、不意にある風景が脳裏に浮かぶことがある。黄昏時にコウモリの舞う秋の聖蹟桜ケ丘の川原の景色や、ランチタイムの虎ノ門界隈の様子、水銀灯で新緑を照らす甲州道のケヤキ並木・・・ いずれも何の脈絡もなく唐突に、頭が勝手に描き出すといった感じであり、またそれらは極めて美しく表象されるので、しばし仕事の手を休めて恍惚としてしまう。特に仕事が忙しく、時間に追われている時にこの恍惚感にとらわれると、焦る心のなかにおいては甘美さは二倍にも三倍にも増幅する。単なる目先の課題からの逃避であり、弱気から来るなまけ心が集中力の欠如状態をもたらしているに過ぎないと自覚しているのだが、それにしてもなにかを美しいと感じる心性には頽落を愉しむ心が潜んでいるような気がしてならない。
今年は今までになくたくさんの風景を見た。鹿児島に転居したことに加えて、自転車競技部のクラブ顧問をしたためだ。春から夏にかけて、週末の大隅半島方面でする練習を皮切りに、学生のロードレーサーをくくりつけたサポートカーを運転しては、佐賀、大分、鳥取、広島などを転戦した。壇ノ浦を流れる速い潮や、松の点在する鳥取の海岸の黄色っぽい砂、などなどを眺める機会を得て、自分がこの目で探勝した風景の数は大いに増えた。砂礫を吹き上げる桜島や霧島山系のなだらかな稜線は日常的に目に入る。けれどもこうした風景には、脳裏に生ずる風景と違い、なぜか美的対象としてのアウラをなかなか感じ取れないでいる。美的興奮がない時、リアリティも感じられない。本物の風景を見ているのに、360 度に展開する絵はがきを眺めているような気になることもある。仕事や日常生活を通して接した風景であるためかもしれない。生命力旺盛な季節の陽光のもとで見たせいかもしれない。いずれもが「死」や「崩壊」、「堕落」といった、自虐的なイメージとは結びつかない健全な対象物として、目に映っているのである。
南ア・鳳凰三山の薬師小屋に泊まり、雨の中、夜叉神峠まで歩いたのはちょうど一年前の11月だが、荒涼たる岩と砂と冷気に取り囲まれ、この世ならぬ場所にいるという気分に浸されて眺める稜線上からの景色は、神々しいまでに美しかった。あるいは府中市側から関戸橋方面を望んだときの、多摩川河川敷のススキの群生も美しい。落日を背景にして、穂波が赤みがかった白に輝くさまは、誕生し、成長し、開花していくのとは対極の指向性を暗示している。土手のサイクリングロードを走ってススキを見に行こうと思い立っただけで、気持ちが昂ぶったものだ。
名声高まるばかりである荒木経惟の『沖縄烈情』を、鹿児島市内天文館(南九州随一の繁華街と言われる)の本屋で発見した。彼の写真集を見て感心しなかったことはまずない。アラーキー氏はなぜ性的な対象にこだわるのだろう。仮に風景を写した写真であっても、その像がもたらす叙情性は、撮る者と見る者が共有している(かもしれない)自虐的意識と結びついているようにぼくの目には映る。凡百のポルノグラフィーと見比べると、彼の写真における性は秘密のなく、姑息なところも微塵もない肯定の相のもとに発現しているが、どのように肯定されようとも、快楽と自虐意識とはそもそも不可分ということだろうか。彼の風景写真は、傷を想起させる性的な対象とないまぜになり、美であることを主張している。想起されるのは、決して脳天気ではない、欺瞞のない明るい傷で、美に至る頽落は「本当は私を認めてください」と上目遣いに哀願する自己否定とは違っている。
自己否定という劣情と、自己肯定という劣情、どちらの劣情も「美」と名指されたつるつるの身体を愛でようとするのには変わりはないのだが・・・ それにしても「死」や「崩壊」や「自虐」・・・ 美について考えるといかにも青春的なイメージが湧出し、贋物くさい趣が醸し出される。自己を肯定してその贋物性を強調することでリアリティが生ずるというのは、なんだか不可思議である。
●塚田高行
手紙
Iさん、
東京でもひとつふたつと木の葉の色がかわりはじめ、ようやく秋も深まりをみせてまいりましたね。
その後いかがおすごしですか。
先日はたいへんうつくしい舞台「星の牧場」をみせていただきありがとうございました。
星の牧場というタイトルにふさわしく、照明もきれいだし衣装もはなやかだった。もちろんIさん、あなたも。
おそらく秋にこどもたちにおくるのに、ふさわしい舞台だったでしょう。ただ、(これ以後すこし辛口になりますが)あなたの所属する劇団ではあまり手なれていないミュージカル性を全面にだそうとしたためか、役者の語るせりふがどうもよわくなってしまった、役者の語ることばが、ちょうど動体に対する空気抵抗の実験の空気のようにわたしのからだの表面をすりぬけて、わたしの内部には入ってこなかった、いわばことばがうわ滑りしているような気がしたのです。
なぜそうなってしまったのか、わたしなりに考えてみましたが、せりふにズレがなかった、語法的にも内容的にもあまりに整いすぎていて、みている者が自分を入れるすきまがなかった、これがもっとも大きな要因だとおもうのです。それと、同じような意味の観念語を三つも四つもならべたせりふが多すぎた。ようするに脚本家とか演出家が、この劇で訴えようとすることを劇のはじめからおわりまですきまなくならべすぎていて(ということは役者も自分の個性を出しにくいのではないかとおもいますが)、観客を静かに劇のなかに引き入れようとする姿勢に欠けていた、すくなくともその配慮が十分ではなかったという気がするのです。これは静かな場面を多くつくればすむという次元の問題ではありません。舞台から客席への(すこし乱暴なことばをつかいますが)脅迫的な一方向性をうすめよ、ということなのです。あまりにも訴えようとする姿勢が強く出すぎている、それだけで終始しようとする演劇では失敗作だとおもうのです。たとえばせりふとおどりとの間に、なんていうかあるトーンのへだたりがあってもおもしろいとおもうのですが。
Iさん、あなたの所属する劇団は、日本ではもっともことばを大切にする、特に語りとしてのことばを大切にする劇団だという定説がありますね。その語りとしてのことばを十分に生かしたミュージカルを、わたしとしては観てみたいです。
以上取り急ぎ感想めいたことを書きました。今度会ったときがこわいけど、おてやわらかに。
では。かぜなどひかぬよう。
1995.10.25 T・T
M・Iさま
●小林弘明
書評
岩成達也『私の詩論大全』
『私の詩論大全』は、岩成詩学による新体詩以降の詩論の批判的通史と、岩成詩学の基礎たる『詩的関係の基礎についての覚書』の補足で構成されている。
岩成達也は『覚書』で詩的関係を<私達:言葉>:世界という記述で示される言葉を介在して世界と関係し同時把握する認識と、<表現形相:内容形相>で充足しないコノテーションという言語論的アプローチで定義している。そして、この著作の特徴は、「幾何学的秩序に従って論証されたエチカ」の記述のように、---ただし論証するのではなく構造にならぬ構造化といったもので---定義とその前提条件、そしてそこから導かれる公式とその系から成り立ち、数学基礎論的な厳密さと抽象化にある。だから静的な構造に詩的関係を押し込む記述ではなく---北山透が批判しているような階層化され閉ざされた詩学ではなく---固有値を得るときの演算子のような多分に言語の機能が議論されているわけであり、階層化といったいわば<表現:内容>が充足して見え易い構造ではなく、詩的関係のいわば微細な言語の運動性、そしてそこに重なっている私達(内部)と世界(外部)との間の運動性が記述されている。この意味で開放系の詩学であり、内部と外部の反転や滲み、そしてそれを実践する言語の機能(コノテーション)は、脱中心化の運動であり、主観性批判になっている。と書いてしまうとなんだということになってしまうが、岩成達也がマチネ・ポエティクの詩理解を「詩を内側から捉える語句というよりは、それを外側から捉える語句ではなかろうか‥‥‥マラルメとは言語と主体との未曾有の危機に直面した男のことではないかという視点」が決定的に欠落していると批判するように、岩成詩学の特異さとしての、詩学の内側から詩という形式が内在する悪意への危機意識あるいは緊迫感を見落としてはならない。
『私の詩論大全』の第一部は、『覚書』に対する以上のような補足と誤解に対する弁明がなされ、第二部では新体詩以降の詩論の批判的検討がなされる。新体詩創始期での韻律をめぐる外山正一と島村抱月の論争、有明に代表される「諸官能の刷新とそれらの間のコレスポンダンス」という象徴詩の詩論、そして、詩的精神を感情の意味をもつ主観的態度と結論づけ、詩の本質とする朔太郎の「詩の原理」、「超自然主義」の西脇順三郎、韻律のメタフィジックを散文に意味の意味として取り込み成り立つポエジイの春山行夫、詩・モンタージュ論の半谷詩論、そして小林秀雄の詩人論、荒地派の詩論にいたるのである。結局ここで批判的に検討されるのは、小林秀雄で完成される詩=純粋言語に向かうことのできる特殊な「詩精神」という考え方である。ここで純粋言語とは「言語からその伝達機能や社会性を除いて、「画家にとっての色、音楽家にとっての音」のごとき極端に唯物論的に扱われる言葉」であり、そうした「言葉の裸形の洞見」に向かいうるのはランボオや実朝、モオツアルトの驚くべき「無垢」つまりは「天才」なのであるという小林秀雄の詩人論が議論されている。朔太郎から続く感覚と主観によって、物を押しつぶして中身を出すという表現をなすことが詩の行為であり、古典主義が成立した形式を乗り越えてゆくこの運動は、「特殊風景に対する誠実」であり、詩的精神の謎あるいは奇跡によってなされるというものだ。岩成達也は、「詩人の存在がその作品の唯一の根拠」とか、「「非人称の闇」が天才達に遭遇するとき、闇はその謎と神秘の核を「詩魂」として形成する」という主観的で詩的精神に偏った詩に対する姿勢を批判し、先に述べたようにコノテーションという言語の構造と機能、「私達の世界認識の構造とそれを反映している私達の言葉の構造」による詩的関係を小林秀雄の「詩人論」にも見いだそうとしている。
浪漫主義の頂点に位置するかのような「詩魂」に依然として影を落としている形式に内在する悪意を、私達は、『私の詩論大全』の悪戦苦闘ぶりに同じように、しかし倒錯した形で目撃するだろう。
|目次|
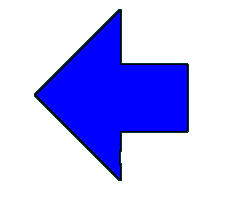 (独身者の.....)|
(独身者の.....)|
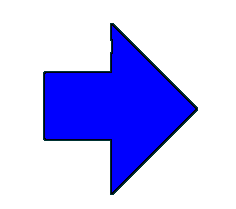 (スウカイナ7 目次)|
(スウカイナ7 目次)|