鏡像とネットワーク
|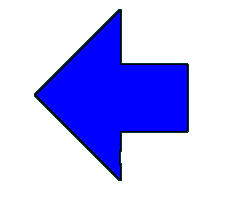 (分子状基質の張力)|
(分子状基質の張力)|
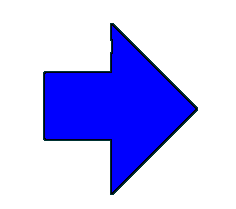 (スウカイナ8 目次)|
(スウカイナ8 目次)|
鏡像とネットワーク
小林弘明
HTMLはネットワーク(コンピュータ)上のさまざまな言語で書かれた無数のテキストと画像を相互に結びつけてハイパーテキストにする記述言語であり、コンピュータ間のコミニュケーション手段である。
タグと呼ばれる記号だけで(括弧でくくる)、ハイパーテキストを作ることができるのは、8BIT単線の通信から情報をパケットにして一気に送る階層化されたプロトコルの採用そしてブラウダ(閲覧ソフト)という発想によっているのであり、この手軽さが端末のパソコンをワークステーションにまで持ち上げ、情報の流れを増殖させまさにWORLD WIDE WEBに変化させた。
これは、テキストとテキストを引用という概念で結んでいることで特徴づけられる。ひとつのテキストには別のテキストにつながる引用タグ(リンク)を反映している言葉があって、その言葉をクリックすることでその言葉に反映されている「引用」テキストへと一気に移動する。反映された言葉には特定のテキストの階層と場所を示す内容が付加されている。こうしてテキストとテキストは次々とリンクされ仮想空間をつくることになる。ネットワークではテキストからテキストへの流れが発生していると言えるかもしれない。パソコン通信が、いわば広場であってそこを通り過ぎるネット加入者の人と、その広場はそれらの人々が置いていった言葉で作られ、ホストコンピュータへと集まってゆく言葉の組織体と言えるならば、インターネットは気まぐれなリンクとテキストからテキストへの取り留めのない流れと言えるかも知れない。あるいはひとつのネットでの階層化ということと、階層を交差して、少なくとも垂直軸をなし崩す線分の発生との間で、それぞれが独立し区分されたテキストを撹乱し、テキストの部分と部分を連結して別のテキストに到るようにして、引用の織物というべきものに近いだろう。
さらに、ここで注目すべきことは、言葉にメタ言語的にタグが反映していることである。テキストモードでは言葉の間に引用符タグとコマンドが挿入されて、ブラウザで見るとタグで指定された書式とレイアウトに再構成されているのである。ブラウダを通すことでタグはテキストに反映される。ブラウダはまさに電脳プロジェクターであって、実際インターネットのWebのサイトを見ることは、端末のディスプレイにワークステーション上の画像を投影する手続きを行うのである。パソコン通信の電子掲示板や電子会議室はいわば大きなファイルであって、私達はそこを開いて読み込んだり、書き込んだりしているのである。私達はファイルという部屋の中から読み込んだり、そこに書き込んだりの作業ができるだけで、端末の私たちは、その部屋を大きくしたり、新たに作ったり、あるいは外との関係をいじるわけにはいかないのである。一方、インターネットのホームページはいろんな部屋を増殖させるようなもので、ほとんど制約を受けないで、つまりインスタントに私達は無数の部屋というより正確にはページ(すべて見ることができ、常に開かれうる---公的な場に私的なものが流れ込む境界にもなっている)の設計をすることができる。これがタグでありHTMLなのであり、これによって錯綜したページのアレンジメントに別のページを加え、別の通路や線分をひくことができるのである。ひとつのページから他のページへの移動コマンドである「リンク」を随時文字やイメージに反映させることができる。これらの設定とホームページが個人の端末でインスタントにできることが重要なのである。言語形態に与える要因は、文字とイメージを混在して扱えることで、---パソコン通信では文字記号しか扱えない---このことは、ただ単にページという概念をコンピュータ上で成立させただけでなく、あるいはフレームによって作られる仮想的な場所だけでもなく、文字のイメージ化を加速させているのである。
私達は、ワープロでディスプレイ上の文字には親しく接している。紙に書き付ける手の労働からキーボードでの作業になったり、カナ漢字変換が介在して、言葉は幾分私達から距離をとることになるが、そこには直接書かれた言葉の鏡像を認めている。その距離は皮膜で隔てられた、限りなく近い距離であるだろう。実際、原稿用紙に書くこと以上に言葉を個人的なファイルに封じる意味合いが強い。
ワープロでの文字が鏡像とするなら、インターネット上のそれは松浦寿輝のいう「蝟集空間」のイメージー---名前を失った群衆として機能する---なのである。そのイメージは再現性と等距離によって特徴づけられ、一回性を構成しない世俗と反復に属するものであり、イメージを送る人も、受け取る人も顔のない群衆であることを要請するのだ。オリジナルなきイメージの蔓延であるとか、べきぺらぺらしたイメージの遍在という表現で語られるべき世界なのである。したがって、「私」という概念は消耗してしてゆき、均一な距離のもとで見られ、松浦がいうような「それであってそれでない」イメージに、「私」が書いた言葉が脱色されるのである。言葉が記号から画像イメージのひとつになることは、象形文字的な身体を持つのではなく、あるいはイコン的な表徴となるのでもなく、言葉の熱気、つまり亀裂を出来させうる身体の喪失なのである。
一方もし「蝟集空間」での群衆として機能していることが、そこでのイメージの圧制のすぐ近傍で、身体の亀裂さえも遍在させる執拗さと仮想空間をもっているなら、もはやネットワークの問題ではなく、境界としての文学を形成することになる。そして間隙を覆って蔓延するイメージに対するゲリラ戦すなわち差異の流れは、等距離性のフレームを撹乱するだろう。
「帝国は無意識の裾野に拡がる世界である。そこは懐しさに満ちみちている」という忘れられた帝国は、島田雅彦がまさに少年だったときの外の世界を、ひねくれた子供の目で見いだしたものである。「帝国は前世や来世も含む四次元の世界を流れる川のようなもので、ぼくは未生以前からそのほとりで遊んでいたのだ」という帝国を流れるTM川は、地理関係、洪水の話があるにもかかわらず、現実の多摩川からずれてしまうのは、ただ単に作者の思い入れのある回想であるためではなく、逆にそういった回想から除かれる不協和音である個人的で交換不可能な身体や事物が流れるのがTM川であり、トイレであり茶の間というわけなのだ。河原とか裏山、茶の間といった世の中に蔓延っていたイメージ---某友人はファシズムとよぶが---もはや古きイメージしか引き起こさないにしても││それゆえいっそう作者の無意識が権力関係に操作されがちなのであるが、つまり茶の間、裏山といった思考を停止させる何かであって、現実に霞をかける権力関係が与えるイメージなり意味と戦い、亀裂を与え、その差異を生きることが、結局無意識の裾野に拡がる世界であり、表象の平面を差異化するひとつの運動なのである。「なぜなら、ぼくの体も魂も帝国の一部なのだ」。この帝国とは、超越的シニフィアンの支配する無意識でありながら、ノマド的運動が発生している過渡的であり、政治的な帝国なのだ。
それゆえにイメージのなかに体と魂が見い出され、表象ならざるもの=現実の上で想像力が作動するという懐かしさに満ちみちているのである。
イメージの等距離性を亀裂としての存在により過剰に引き寄せ、記号と身体との間で折り畳んでしまう。TM川の向こうには芸者がいて、黒竜江の向こうには敵がいて、そのあいだを行き来するものがいた。右岸と左岸を結ぶ船は、無意識の波間に消えることもあるのだった。危険な領域はトイレにもあったし、帝国の森にも学校にもあったのだ。ここにイメージは折り畳まれ、身体と記号が遭遇することになるのだ。
島田雅彦の小説の登場人物は、着せ替え人形のように、表情を欠いている。身体的な誇張と妄想的な行動が、等距離性が捏造する表情という風景から逃走させるというべきであろう。「あの頃、ぼくたちが無邪気でいられたのは何もかもが始まったばかりだったからだ。何をするにも暗闇の中の手探りゆえの黄金時代だった。権力闘争のさなかで‥‥‥少しずつ帝国の掟や法則を学んできたが、全て自分の体を実験台に使ったのである。‥‥‥時間はうんざりするほどあり、その気になれば、やり直しも効いた」無意識という過剰な沃野で、無意識の掟を身体が学んでゆくのである。顔は無意識のざわめきに埋没して、まだ見いだされていない。身体の形成過程で、あるいは身体の傷栱亀裂として言葉が行動している。だから無意識の学校のカリスマ的エミコの巨大なおっぱいに蹂躙されるのであり、幽霊屋敷でミナコは黙示録的な言葉をまとったりするのである。
「物事には必ず入口と出口がなくてはならない。そういうことだ。」
風の歌を聴け、1973年のピンボール、羊をめぐる冒険まで、小説は僕と鼠によって進行する。「イエローページ村上春樹」で述べられているように、僕=現実と鼠=異界という領域の往復を構造として、たとえばピンボールでは金星生まれの話と土星生まれの話、あるいは208と209と区別されることになる双子の女の子、ピンボールの向かい合う2対のフリッパー、僕と僕の友人が経営する翻訳事務所の部屋の配置などが、小説を多重構造にするとともに、僕=現実を出口と入口というような2極の間の運動として特徴ずけ、ラバーソール、カリフォルニア・ガールズに増幅されて時間を構成してゆくことになる。
一方の鼠の世界は「1973年の秋には、なにかしら底意地の悪いものが秘められているようでもあった。まるで靴の中の小石のように鼠にははっきりとそれを感じ取ることができた。‥‥‥
鼠にとっての時の流れは、まるでどこかでプツンと断ち切られてしまったように見える。
何故そんなことになってしまったのか、鼠にはわからない。切り口をみつけることさえできない。‥‥‥鼠は無力であり、孤独であった。何処かで悪い風が吹き始め、‥‥‥」
出口のない世界と描かれ、死の静寂しかない冷えきった世界には、双子のような対になったものは出てこない。死に傾斜してゆくとさえわからない行き止まり感が重くあたりをおおっている。
風の歌を聴けではジェイスバー、1973年では双子の女の子がこの二つの世界の境界に位置していて、死んでゆく鼠の、あるいは直子の外側を形成している。鼠はネガティブな内面であるというより無意識と呼ばれるべきものなのである。なぜなら鼠の世界は、あまりにも遠いと同時にすぐ後ろに接していて、広大な拡がりであり、「懐かしさに満ちみちている」からである。村上春樹の小説はこの無意識栱死をテーマに展開しているのである。
「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」の世界の終りでは、影をなくした僕は世界のおわりで死んでいった獣の頭骨から夢を読み取りながらしだいに弱ってゆく。夢読みは「彼女が説明してくれたほど楽な仕事ではなかった‥‥‥明確なメッセージとして把握することはできなかった」夢読みは指を介在として光に目を晒すことであり、生が凝集したもので、後にねじまき鳥の井戸で体験される光である。しかし後者の光は突然あたえられるものであるに対し、前者は読み取るべきものである。夢読みは古い夢しかない図書館でなされる。図書館という装置で無意識を知として見える形にする作業をするのである。というのはこの「世界のおわり」とは、ラカンの鏡像段階にも似た幽閉された無意識なのであり、無意識は光のもとで分類され読み込まれねばならない。一方、光は生という欲望でもあるので、光を外に放出して無意識を生から死への時間の秩序に一致させねばならなかった。光は超越的シニフィアンと運動としての欲望のカップルなのである。影が失われることには、単に象徴界への移行ではなく、このような2重の機能の間の薄暗い無意識の彷徨を見る必要がある。
無意識では言語は厚みをもち、とめどもない抵抗と欲望に事物のパースペクティブは変形する。内面によって幽閉されたのは個以前の欲望と不透明な言説であり、具体的には「鼠」と「僕」「影」と「僕」という鏡像関係に村上春樹の無意識は内面化され、再構成されるのである。「忘れられた帝国」が、非人称的で個と個の間を移動するノマドとして定義される群集の力学からなっているに対して、村上春樹は鏡像関係の答えのない死の意味を探索するのである。本来的な意味での無意識は指で探られる光なのだ。
「ねじまき鳥」は鏡像関係の破綻後の物語であるととりあえずは言えるだろう。
岡田とおるは、「ピンボール」の「僕」に所有欲のなさと一風変わった物事へのこだわりは似ているものの、早急さと投げやりさを見せることのない、つまり過去に罪を犯していない人物と言えよう。したがってこの物語は受難の物語なのである。岡田とおるはマルタ、クレタ姉妹、シナモンといった人たちに夢読みの能力を気づかされる。他者の無意識を肩代わりできうる能力のために、満州蒙古国境での出来事を体験することになるのである。世界のおわりという幽閉された無意識の世界と現実の世界とが鏡像関係にあったのであるが、「ねじまき鳥」は同一の平面上で展開しているのである。もはや岡田とおるの鏡像は存在しない。彼の影の部分は、猫「わたやのぼる」や顔にできたシミとかに断片化されたのであろうか? 1938年満州国境から世田谷の露地裏までの一本の糸がつながっていて、彼は期せずして蒙古の井戸を影とせざるおえなかったのか? 構造化された言語が彼と鼠を表裏の関係に縫い合わせたことに対して、今までの作品の主題を反映した言説を繰り込む戦略的なリアリズムが、内容的には幾分錯綜しているにもかかわらず、均質な空間を構成しているのである。つまり彼とその影は超越的シニフィアンに吊り下げられて、まったく鏡像関係の揺らぎを失う一方で、効果的に同一平面に重ねられて投影されているのである。
「物事には必ず入口と出口がなくてはならない。そういうことだ」と諦観した声こそが表面には現れぬ超越的シニフィアンなのである。これは村上春樹的ウィットが効いた悲しみなのかもしれない。しかし「そういうことだ」という悪意さえ感じられる断定こそが、鼠を死に追いやる悪い風を吹かせていたのである。そして、いままで出口がない行き止まりであった井戸が出口を持つにいたった「ねじまき鳥クロニクル」は、その予言の成就に向けて動かされているように見えるのである。予言の成就は神秘とか啓示といった機構ではなく、その新しさはおそらく反映という機構にこそあるのだ。
|目次|
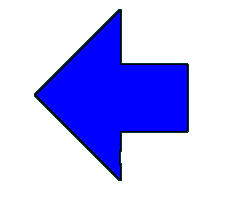 (分子状基質の張力)|
(分子状基質の張力)|
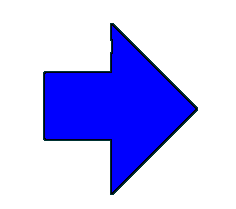 (スウカイナ8 目次)|
(スウカイナ8 目次)|