唯
心
(
ゆいしん ) 
第一章

秋の陽が、だいぶ西に傾いていた。紅葉した山々の輝きに、深い陰が増してきてい
る。やがて、その暗い谷へ降りていくと、寒々とした。
西住正一は、谷底を流れる川で、愛用のザックを下ろした。中から、ウインド・ブレーカ
ーを出す。それを、ベストの上に羽織った。例年だと、西住はここで水筒に水をつめる。
が、今年はその必要もなさそうだった。
西住は、尾根の陽射しを見上げながら、石の上に腰を下ろした。銀紙をむいてチョコレ
ートをかじり、ぼんやりと川のせせらぎを眺めた。点々と落葉が流れてくる。その川の水
を、西住は手ですくって飲んだ。それから、ザックのベルトを持ち上げ、また肩に掛けた。
もう一方の腕を通す。そして、飛び石を渡り、谷川を越えた。
西住は、再びサラサラと落葉を蹴散らし、谷の登りにかかった。急な深い谷を、ジグザ
グに登っていく。ようやく、陽の射す尾根に出ると、体が汗ばんでいた。
尾根を少し下った所に、小さなホコラある。中に石仏が納めてあった。道祖神である。
西住は、その前でザックを下ろした。それから、ポケットから、谷川で拾ってきた小石を出
した。ホコラの前の、小石の山に積み上げるために持ってきたのだ。西住は、その丸い
小石を、山の一番てっぺんにのせ、両手を合せた。
時計を見た。三時を少し回っていた。例年だと、午前中にここに到着している。今年
は、三時間以上も遅くなったわけである。しかし、おかげで、午後の紅葉を見ることが出
来た。
このホコラの場所からは、広々とした南西方向の谷が一望できる。西住の目的地であ
る鹿村も、この谷にあった。山陰で、ここからは見えなかったが、もうすぐそこにあった。
西住は、ホコラの横の草むらに、どっかりと腰を下ろした。まだ、足腰や肩が、ズキズ
キと痛む。彼は、ウインド・ブレーカーのチャックを切り下ろし、空を見上げた。山々は、豊
かな実りの季節だったが、鳥の影もなく、静かだった。
しばらく休むと、西住は、陽の当るのどかな山道を下った。紅葉が日射しに透け、下界
には杉や竹薮が緑の斑に見える。山ブドウのツルや、アケビの密生したツルも見える。
が、もう時期は遅いようだった。二つに割れたアケビの実などは、中身がすっかり小鳥に
食べられてしまっている。
鹿村には、一番高台に、曹洞宗の清安寺がある。その清安寺境内に、西住は裏山の
方から入っていった。境内は、強い秋の夕日を受け、シンと静まり返っていた。しなび
た、山村の山寺である。しかし、落葉はきれいに掃き清められてあった。戦争前までは、
修業の厳しさで、近隣に知れ渡っていた禅寺である。
西住は、古い僧坊から鐘突き堂の方へ回り、本堂の前へ出た。すると、本堂の縁側
で、数人が座禅に入っていた。良安、一真、そして玄海の後ろ姿も見えた。その他の
四、五人は、鹿村や下の町の青年たちである。
住職の、玄信和尚の姿はなかった。西住は、縁側の隅の方へ行ってザックを下ろし、
山靴を脱いだ。風雨に晒されて白くなった縁側に上がった。そして、まず、本堂の中の本
尊に両手を合せた。それから、座布を持ってきて、一同と並んで座禅に入った。
この清安寺の住職玄信は、西住の遠縁にあたる。西住は子供の頃の数年間を、この
山寺で過ごしていたのである。小学四年生の、二学期からだ。その当時、彼は手のつけ
られない悪ガキというレッテルを張られていた。もっとも、彼自身の記憶では、それほど
のワルとは思っていなかった。ただ、誰も彼を理解しなかったのだ。が、いずれにして
も、周囲の意見は一致していた。それで、中学校を卒業するまでの約六年間、彼はこの
清安寺に預けられたのだった。
本堂の縁側で座禅を組んでいると、いつしか陽が陰った。それから、あたりは急速に
夕闇の中に沈んだ。座禅の終わりを告げたのは、年長の良安だった。一同、それでゆっ
くりと禅定をといた。
「やあ、正一さん」良安が、西住の後ろにやってきて、なつかしそうに声をかけた。
「やあ、またやっかいになります」
「どうぞ。またにぎやかになるなあ」
「今年も山越ですか?」一真が聞いた。
「ああ」西住は、口もとを弛めた。「やあ、玄海、元気にしてたか?」
「ええ。夏、盲腸をやったけど、」
「ほう、」西住は、薄暗がりの中で、玄海の姿を見つめた。
玄海は、住職玄真の孫で、中学二年生である。一真は、東京近郊で高校を卒業し、仏
縁あって、この清安寺で修業に入っている。良安も、仏縁でこの寺に来、今は玄信和尚
の法嗣と決まっている。
「痛かったか?」西住は、玄海の肩に手を置いて聞いた。
「あんなの、」
「はっ、はっ、はっ、」一真が、大声で笑った。「もう、こっちの方が痛くなりましたよ。良安
さんがバイクの尻に乗せて、町まで下ったんですよ。夜中の二時でした。それで、何かあ
るといけないってんで、わたしもバイクで追いかけたんですよ」
「軽トラックで行かなかったのか?」西住が聞いた。
「ああ...あれ、」一真は、手を振った。また、クッ、クッ、と笑った。「あれは、良安さん
が、黒井沢におっことしました」
「黒井沢だって?どうして?」
良安が、薄暗がりの中で首を振り、白い歯をこぼした。
「雨でスリップしたんです。そして、いつの間にか傾いてきて、あれよあれよと思っている
間でした。それで、急いでドアを開けて、飛び下りて...」
西住は、あきれた。黒井沢は、下の谷川まで、五十メートルもある崖っ縁である。その
時の良安の様子が、目に見えるようだった。
「良安さんは、運動神経がにぶいから」玄海がからかった。
「あそこでは、」良安が言った。「もう、絶対に左側へは寄りません」
「怖くて、もう一緒に乗れないですよ」一真が言った。
「バカめ!御仏がちゃんと守って下さるわ!」
「で、軽トラックは、下まで落ちたんですか?」西住が聞いた。
「いや、」良安が言った。「二十メートルほどで止りました。薮にひっかかったんです。しか
し、危ないってんで、次の日、川原まで落としました」
「まったく、」一真が言った。「恥ずかしくて、しばらく村を歩けなかったですよ。中沢でも、
町中が知ってますよ」
「とにかく、」良安が、咳払いをした。「怪我が無くて幸いでした」
「おい、正一、」夕闇の中で、誰かが呼んだ。「後で遊びに来いや」
「哲治か?」西住は、夕闇を透かして言った。
「ああ。久しぶりだな」
「もう、取入れはすんだのか?」
「畑が少し残ってるだけだ」
「電話するよ」
「ああ、そうしてくれや。じゃ、な」
「ああ」
青年たちは、寺の者に挨拶をし、暗い中を帰っていった。境内の一段低い所に、駐車
場がある。そこに車を止めてあるのだ。
西住は、山靴を拾い、それからザックを肩に引っ掛けた。そして、良安と一緒に、庫裏
(くり/寺の家族の住んでいる所)の方へ回った。一真と玄海は、本尊に灯明をともし、戸締りにかかっ
た。
「すぐ、月が昇るな、」西住は言った。
「ええ...和尚は、今年は雪が早いって言ってます。例年にない大雪だそうです」
「そうか、大雪か。大屋根の雪降ろしが大変だな」
「ええ...ところで、正一さん、ついに教わりましたよ。“観雪”を、」
「ほう、清安寺“観雪”が伝授されたか、」
「ええ...まあ、聞いてみれば、たわいもないことです。しかし、よく当りますからね。むし
ろ、そんな関連性を発見したことの方に、頭が下がります」
「ふうん...」
「和尚も、先代から聞いて、色々工夫を加えたり、記録を取ったりしています。わたしも、
それを引継ぎました」
「そうか、そいつはおめでとう」
「ええ、」
「大雪といえば、おれが中学一年の時、良安さんが三年の時でしたか...」
「ええ、あの冬は大変でした。色々ありましたね」
「和尚が大屋根から落ちたのも、あの冬だったでしょう」
「ええ、あの冬でした。あの時は、町の病院まで下りるのが、ひと苦労でした。吹雪はだ
んだん激しくなるし、暗くなってくるし、」
「清玄さんが、鬼神のようにソリを引っ張りましたね」
「...」
「清玄さんにも、ずいぶん会ってないな、」
「時々手紙が来ますが、むこうで元気にやってます」
「そうですか。ところで、良安さん、今晩の晩飯は何ですか?」
「ふむ...キノコ汁を作りましょう。シシタケがたくさんありますから」
「ほう、シシタケですか。久しぶりだなあ」西住は、肩のザックをグイと持ち上げた。「シシ
タケは、東京では売ってませんからね。誰からもらったんです?」
「川西の富三さん」
「ああ、キノコとりの名人か。相変わらず元気そうだな」
「ええ、元気でやってます。もう、七十になるはずですが」
良安は、台所の方へ行った。
西住は、山靴を玄関の方に置いた。そして、居間の障子を引いた。すると、玄信和尚
が、ひとり炉端で晩酌をやっていた。井炉裏の真ん中に、なつかしいブリキ製のストーブ
が見えた。それが、真っ赤に焼けただれている。上に載せてある鉄瓶のフタから、蒸気
が吹き上がっている。ここは、二十年前と少しも変っていなかった。宇宙基地、核融合、
知能ロボットと、文明社会が目まぐるしく変化している中で、この部屋だけは、昔のまま
に残っている。
玄信和尚は、すでに七十五歳を越えていた。頭もすっかり禿げ上がり、痩せさらばえ
ている。が、陽気で、かくしゃくとしていて、今でも一合の晩酌は欠かさない酒好きであ
る。若い頃は永平寺で学び、その後、道元禅師の足跡を慕い、中国にまで旅をした人で
ある。
「和尚、」西住は、廊下で正座して言った。「ただ今帰りました」
「おう!正一か!」和尚は、杯を置き、顔を輝かせた。「よく来た、よく来た、」
西住は、ザックを手に持ち、炉端まで運んだ。
「また、山越えか?」
「ええ。今年は、午後になってしまいました」
「うむ。山はどうじゃった?」
「今年は、紅葉がきれいでした。よく晴れていたし」西住は、和尚の左手の炉端に腰を下
ろした。客人の場所である。
「和尚、約束の物を持ってきましたよ」西住は、満面に笑みを浮かべて言った。
「約束?はて、何じゃ?」
「酒です。上等の洋酒を持ってくると言ったでしょう」
西住は、ザックのヒモを解いた。荷物のほとんどが、皆への土産だった。和尚には、コ
ニャック。良安には、頼まれていた本が三巻。一真には、永平寺やその他の寺の写真集
全二巻。これら全てが、山越えには重い荷物だった。そして玄海には、上等なアノラック
と、スキー帽子を買ってきてあった。
西住は、ザックの真ん中あたりから、四角い紙包みを取り出した。包装紙を取り、箱の
フタを開け、コニャックの瓶を抜出した。西住は、それを和尚の方にさしだした。
「ほう・・・」和尚は、首の長いビンを受け取り、しげしげと眺めた。
「レミー・マルタンという酒です。フランスの、最高級のコニャックです」
「ウィスキーか?」
「いえ、ブランデーです。飲んだことがありますか?」
「はて...覚えがないのう。ふむ、これは、コルク栓じゃな」
「ええ」
「どうやって開けるんじゃ?」
西住は、一緒に入っていた栓抜を取った。それで、ゆっくりと、慎重にコルク栓を抜き
取った。和尚は、杯に残っていた酒を、口に放り込んだ。西住は、その杯に、コニャックを
なみなみと注いだ。和尚は、目を閉じ、コニャックに一礼した。それから、杯を口へ運び、
しばらく香りを味わい、チビリとなめた。
「ほう...」和尚は、びっくりし、しばらく口の中のコニャックの感触を味わっていた。「うー
む...これは、いい酒じゃ。異国の文化の香りがするのう...」
西住は、微笑してうなずいた。
和尚は、さらに、小さく一口飲んだ。
「これは、フランスのコニャック地方というところで出来る、極上のブランデーです」
「ふむ...こいつは、いくらでも飲めそうな酒じゃのう」
「口当たりはいいですが、強い酒です」
「ふむ...」和尚は、もう一口小さく飲むと、杯を炉端に下ろした。
西住は、少年の頃から、和尚が酒を飲んでいるのを見ているのが好きだった。ムダも
スキもなく、極めつくされた一つの芸域に達した飲みっぷりだった。それも、茶道のような
わざとらしさもなく、自由気ままに、ただ酒を飲んでいる。西住が、今でも、とてもかなわ
ぬと思うことのひとつである。
「正一、」和尚が、首を傾けて言った。「嫁は、まだもらわぬか?」
「ええ、」
「何故じゃ?」
「色々と。仕事もありますし、」
「ふむ...いったい、心理学というのは、それほど面白いものか?」
西住は、ただ微笑した。
「おまえに、そんなものが必要とは思えんがのう」
「これは、仕事ですから。それに、“解脱”、“悟り”、“唯心”と言うだけでは、現代人の全
てを納得させることは出来ません。現代人を納得させるには、人間の意識進化の流れ
を、文明共通の認識形態で、論理的に解明していく必要があるんです。時代は、大きく
動いています。それも、加速度的に変化しています。一刻も猶予のない状況です」
「ふーむ...」和尚は、杯を取り上げた。
「もっとも、科学が万能でないことは、しだいに分ってきています。しかし、イギリスで始ま
った産業革命以後、現在の宇宙開発に至るまで、我々の文明の屋台骨を形成している
のは、依然科学技術です。こうした、現代人共通の意識状況を、無視するわけにはいか
んでしょう。かってのような、宗教や占い中心の社会は、もう戻っては来ないんですか
ら、」
「なるほど...」
「現在、人間は、地球生態系から溢れんばかりです。こうした人間が、みんな、毎日何を
考え、何を求めて生きているか...」
「うむ。途方もない時代がきたものじゃて、」
西住は、膝を立て、ゆっくりと炉端から立ち上がった。
「じゃあ、良安さんを手伝ってきます」
「うむ」
西住は、清安寺に帰ってくると、すぐに少年時代の寺の生活に戻った。ここでは、彼は
今でも客人でないのが有難かった。
第二章
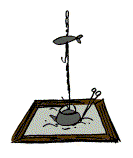
玄信和尚は、夕食の後、いつも炉端で話を一つ聞かせてくれる。話といっても、たいが
いは公案(禅宗で、参禅者に示し、座禅工夫させる課題)や教典の講義である。また、時には、昔の偉
い僧侶の話をしたりした。これは、清安寺の伝統になっている。あたたかい春の宵や夏
の晩などは、この話を聞きに、近在の人々が清安寺に登ってくる。人が多い時には、場
所が本堂に移される。
「さて、良安、」和尚が、座布団の上に腰を下ろしながら言った。「今夜は何の話じゃ?」
「『無門関』(禅の公案集)の第二十三則です」良安が、すでに開いてある本を、和尚に手渡し
た。
「『無門関』第二十三則か。“不思善悪(ふしぜんあく)”じゃな」和尚は、パラリ、パラリ、と次
のページをめくった。
玄海が最後に居間に入ってきて、一真と並んで炉端に腰を下ろした。
「玄海、いいか?」
「はい」
「うむ。この、『無門関』第二十三則は、六祖・慧能(えのう)の話じゃ。慧能は、何度も話し
たことがあるな。覚えておるかの?頓悟(とんご)の慧能じゃ。この六祖・慧能の話は、禅の
歴史の上でも、最も有名な話じゃ。
よいか、“悟り”に至るには、二つの流れがある。修業の段階を経ずに、一 挙に悟りを
開くことを“頓悟(とんご)”という。これに対し、長い修業を経て、しだ いに悟りを開いていく
ことを、“漸悟(ざんご)”という」
「はい」一真がうなづいた。
「さて、禅宗は、インドから中国に渡った、菩提達摩(ぼだいだるま)を初祖とする。インドで釈
尊が入滅し、何百年かたった頃のことじゃ。この頃、全インドに広がった仏教も、いよい
よその絶頂を極め、下降期に入っておった。インドでは、再び、急速にヒンズー教が復活
し始めておったのじゃ。
何故か?理由は、仏教の教えは、無学な一般の人々には、あまりにも難しかったから
じゃ。働かずに、ただいちずに学ぶほどの者でなければ、なかなか悟りに至ることは出
来なかった。これでは、貧しい大衆はついてはゆけぬ。
こうして、インドでは、仏教の行く末は見えてきておったのじゃ。そこで...世界四大文
明発祥地の一つ、インダス川流域の文明が、もう一つの黄河流域の文明に移植される
ことになる。つまり、インド大陸では行く末の見えてきた仏教が、布教の新天地を求め、
菩提達摩(ぼだいだるま)を中国大陸に送り出したと言っていいじゃろう。似たようなことは、
後にヨーロッパ大陸のキリスト教でも起こっておる。新教との争いに破れたカトリックが、
布教の新天地を求め、世界の海に船出した。フランシスコ・ザビエルが、日本にまで布教
にやってきたのも、そうした背景があったのじゃ。
もっとも、菩提達摩の場合、とてもそんな大仕掛のものじゃあなかった。ダルマさん
は、一粒の麦にたとえられておる。インドの一粒の麦が、中国の大地にまかれたのじゃ。
それは、はたして、うまく芽が出るかどうかさえも分らぬものじゃった...」
「和尚、」良安が口を開いた。「菩提達摩は、どうして中国を選んだのでしょうか?仏教
は、隣接した東南アジアにも広がっていたのに、」
「いや、いや、良安、中国を選んだのは、菩提達摩ではない。彼の師、ハンニャタラという
者じゃ。ハンニャタラは、菩提達摩に、こう言ったといわれておる」
「ダルマよ、わしが没して六十七年がたったら、東の方のシナという国に行くが
よい。よいか、シナでも、決して文化の低い南方に留ってはならぬ。北方へ行
くのじゃ。そこに、おまえを待っている者がおるであろう」
「こうして、インドから中国の大地に、一人の人間が送り込まれたのじゃ。その時、菩提
達摩はすでに、百五十歳の高齢に達していたと言われておる。師ハンニャタラが没し、
六十七年後じゃからのう。ともかく、菩提達摩は、師の言われたとおり、ちょうど六十七年
後に、海路シナに渡ったのじゃ。そして、北方中国、当時で言う“魏(ぎ)”の国に入った。
そして、崇山(すうざん)の少林寺にとどまり、そこで一日中壁に向かって座禅をしておった。
この奇妙な異国人を、人々は“壁観(へきかん)バラモン”と呼んでいたという。まさに、手も
足も使わんダルマさんのように座っておった。そうやって、菩提達摩は、少林寺で面壁す
ること九年、よわい百六十余歳で没しておる。壮絶な大冒険じゃ。
むろん、この菩提達摩以前にも、仏教はさまざまな形で、中国に伝わっておった。が、
菩提達摩が渡来するまでは、真の仏法は伝わっておらなかったのじゃ。菩提達摩が渡
来し、中国に禅宗が興るまではのう。それまでは、金のピカピカの仏像を拝むようなこと
をやっておったのじゃ。が、仏教の本質は、伽藍(がらん)や仏像にあるのではない。それは
形であり、単なる器じゃ。仏教の本質は、釈尊の悟られた心、“解脱(げだつ)”体験にある
のじゃ。その、かんじんの心が伝わっておらなかった。ま...いずれにしても、仏教は、
その後の歴史を見ても分るように、東南アジア、チベット、中国、そして日本において完
成されたのじゃ。
さて禅宗の初祖・菩提達摩が、海路中国に渡来したのは、六世紀初めのことじゃ。そ
して、その菩提達摩の弟子、慧可(えか)が二祖となる。さらに、三祖・僧粲(そうさん)、四祖・
道信、五祖・弘忍(こうにん/ぐにん)、六祖・慧能(えのう)と続くのじゃ。この六祖慧能の時代に
なって、禅はようやくインド仏教の体臭を消し去ったと言われておる。真に、黄河流域に
発生した中国文化に溶け込み、中国の大地と同化したのじゃ。そして、この中国独自の
ものとなった禅宗が、再び海を渡り、日本にも渡来したのじゃ」
和尚は、キセルにきざみタバコを詰めた。それを、真っ赤に焼けたストーブに押し当
て、火をつけた。そして、カチリ、とキセルをくわえ、目をしょぼつかせながら、ぷかりと煙
りを吐き出した。
「さて、話を、慧能(えのう)にもどそうかの、」和尚は、キセルを手に持って言った。「六祖・
慧能禅師は、南方中国は広東省新州の生まれじゃ。家は貧しかったという。はるかな
昔...唐の時代のことじゃ。日本の遣唐使、阿部仲磨(あべのなかまろ)が海を渡ったのは、
慧能の生きた時代より、ほんの少し後のことになるかの。玄海、阿部仲磨は知っておる
か?」
和尚は、キセルを口にくわえ、玄海を眺めた。
「はい...ええと、唐で宮中につかえ、日本に帰らなかった人、」
「そうじゃ」和尚は、深くうなずいた。「その時代の話じゃ。記録によれば、慧能は街で薪
を売って歩き、それで細々と母を養っていたという。ところが、ある日のことじゃ。ふと、あ
る家の前にくると、中からお経を読誦(どくず)している声が聞こえてきた。今まで、聞いたこ
ともないお経じゃった。慧能は、つい立ち止まって、聞き入った。そして、聞いているうち
に、強く心を揺り動かされる言葉があった。
人には、一生を決めるような、巡り合わせというものがあるものじゃ。誰にでものう。慧
能の場合、まさにこの時だったのじゃろう。慧能は、そのお経を読誦している家の前を、
そのまま立ち去ることが出来なかったのじゃ。それで、ついに中へ入っていった。そし
て、そのお経は何というものかと尋ねた。すると、主人が、これは『金剛般若経』である、
と教えてくれた。出所は、北方中国の黄梅山(おうばいさん)におられる、禅宗の第五祖、弘
忍(ぐにん)禅師だと言った。慧能は、それで、北方中国の、黄梅山へ旅することを決意した
のじゃ。『金剛般若経』は、若い慧能の心に、よほど強い衝撃を与えたのじゃろう。このよ
うにして、五祖・弘忍と、六祖・慧能の仏縁が結ばれたのじゃ。
慧能は、ともかく、まず母親が何とか食べて行けるようにした。それから、ひとり黄梅山
へ向かって旅立ったのじゃ。そして、ようやく、北方中国の黄梅山にたどり着いた時、慧
能は二十四歳じゃったという。長旅に疲れた、風采の上がらない、ひとりの小男だったそ
うじゃ。唐のこの時代、貧しい一人の青年が、南方中国から北方中国に旅するということ
は、言語に絶する困難じゃ。地図もなければ、ろくな道もない。今のような宿があるわけ
でもない。しかも、山には山族が多く、トラも出没した。むろん、毒ヘビや毒虫、病気やケ
ガも心配せねばならなかった。しかも、今のような薬もなかった。ちょっとしたことでも、人
はすぐに命を落とした。昔は、旅をするとは、これほど命がけのことじゃったのじゃ。今の
ように、ちょっと電車か車で行ってくるのとは、わけがちがう」
良安が、茶を入れた。それを、炉端に順送りに送った。
「ま、ともかく慧能は、身ひとつで、黄梅山(おうばいさん)にたどり着いた。そして、五祖・弘忍
禅師に参謁(さんえつ)した。この時、二人の間で、このような禅問答が交わされたのじゃ」
「おまえは、どこから来たのか」弘忍禅師が聞いた。
「嶺南(れいなん)から来ました」慧能が答えた。
「何を求めているのか」
「仏になりたいと思います」
すると、弘忍禅師は、こう言ったのじゃ。
「おまえたち、嶺南の猿どもには、仏性はない。それが、どうして仏になれよう
か」
すると、慧能はこう答えた。
「人には、南北の別があります。仏性に、どうしてそのような差別があり得まし
ょうか」
「この問答で、弘忍禅師は、慧能のなみなみならぬ天分を見抜いたのじゃ。人には南北
の別はあるが、仏性にはそれがないという。これが分るか、一真?」
「はい。仏性は...“空(くう)”ですから、」
「ふーむ...」和尚は茶を取り上げ、一口飲んだ。「で...慧能はじゃ、そこで弘忍禅師
から、米つきの仕事を与えられたのじゃ。つまり、黄梅山で修業することをゆるされ、仕
事まで世話してもらった。しかし、僧侶になったわけではない。ただ、黄梅山で、米つき
の仕事をもらっただけじゃ。
この時期、中国では、禅宗はまさに興隆期じゃった。そして、その禅宗の五祖・弘忍禅
師のもとには、常時七百人からの修業僧が集まっておった。黄梅山とは、そういう所じゃ
った。そんな禅宗の総本山へ、慧能は、フラフラと身ひとつでやって来た。そして五祖・
弘忍禅師から、そうした修業僧たちが食う、米をつく仕事を与えられたわけじゃ。モミの
殻を取り、白米にする仕事じゃな。こうした黄梅山での修業生活が、どんなものか、おま
えたちにも想像はつくじゃろう。のう、一真?」
「はい」
「もっとも、慧能は、その黄梅山で、ほとんど一日中米つきをしておった。米つきバッタと
いって、両脚でバッタン、バッタン、とハネを踏み、臼の中の米をつくのじゃ。ところが、慧
能がやってきて、八ヶ月ほどが過ぎた頃じゃ。五祖・弘忍禅師は、全黄梅山の修業僧た
ちに、こう布告を出した」
“正法を学ぶには、いたずらにわしの言う言葉を写し、それでよしとするべきで
はない。各自、自分の自覚体験を表す偈(げ/ 詩)を作り、正法を嗣ぐに足る力
量を示せ。”
「この布告には、まず神秀(じんしゅう)が答えた。この神秀は、黄梅山において最上席にあ
り、皆からも深く敬愛されておった。そこで、まずそういう運びになったのじゃろう。その神
秀の偈は、こうじゃ」
身はこれ菩提樹(ぼだいじゅ)であり
心は明鏡の台のようである
一刻一刻心して拭い清めよ
塵埃(じんあい)をとどめてはならない
「神秀は、この偈(げ/ 詩)を、僧堂の壁に張り出した。ま、悪くはない。神秀という人物の、
真面目に精進する性格が、よく出ておる。
全黄梅山が注目しておるから、慧能も当然この偈を見た。そこで、自分も一句作る気
になったのじゃ。ところが、慧能は、字が書けなかった。貧しくて、そんな教養も無かった
からじゃ。そこで、一緒に仕事をしている童(わらべ)に書いてもらった。童とは、子供のうち
から寺に入っている、小僧のことじゃ。その、小僧に書いてもらった。そして、その偈を、
僧堂の壁に張り出したのじゃ。その慧能の偈は、こうじゃ」
菩提(ぼだい)は本来樹ではない
明鏡にもまた台はない
本来無一物
どこに塵埃(じんあい)がつき得ようか
「この慧能の偈と、神秀の偈には、歴然とした差があった。慧能の偈の方が、“悟り”とい
うことに関しては、はるかに高い透徹性を示しておる。これは、見識のある者ならば、誰
にでも分ったことじゃ。ところがじゃ、では、その慧能とはどういう人物かとなると、最近嶺
南から迷い込んできた、米つき行者(あんじゃ/禅宗で、寺院にあって、諸種の用務に従事する給仕)じゃ。
まだ、剃髪(ていはつ/頭髪をそり下ろすこと)もしておらず、僧侶ですらない。したがって、この慧
能が、いかに大悟していようとも、いきなり法嗣(ほっす/法を嗣ぐこと。この場合、五祖の法を嗣ぎ、六祖と
なること)とするわけにはいかない。これでは、誰もが受け入れがたい。
五祖・弘忍(ぐにん)禅師は、これ以後、しばしば慧能と接する機会を持ったと思う。そし
て、ある夜、ひそかに慧能を自室に呼んだのじゃ。そこで弘忍禅師は、慧能を確かに私
の法を嗣ぐ者だとして、自分の衣(ころも/僧衣)と鉢(はち)を与えたのじゃ。(衣鉢は、法を嗣いだ証拠
として、師僧から弟子に伝える、袈裟と鉢)
それから弘忍禅師は、慧能を、ただちに黄梅山から立ち去らせた。期の熟するまで身
を潜め、禅境をさらに深めよと指示してのう。五祖・弘忍は、ここで全てを六祖・慧能に託
したのじゃ。ま、慧能とは、それほどの器だったと言うことじゃな。
弘忍禅師が、神秀(じんしゅう)なり、智諠(ちせん)なり、義方(ぎほう)なり、他の誰かに衣鉢(い
はつ)を与えることは、たやすいことじゃった。しかし、弘忍禅師は、そうした人事的な配慮
はしなかったのじゃ。仏法の伝統を守り、真理の体験的伝承をとり、大悟しておる慧能に
与えたのじゃ。いかにもすがすがしい、良き時代じゃった。まさに、禅宗の興隆期だった
のじゃ。これは、学僧として中国に渡った空海(弘法大師)が、密教の正統を受け継ぎ、それ
を日本に持ち帰ってしまった大事件とよく似ておる」
「面白いですね。空海の場合も、アッ、という間でしたね」西住は言った。
「うむ。いずれも、興隆期の、純朴な情熱が溢れておるわい。おお、そうじゃ...一方の
神秀じゃが、この方も後に大悟し、大禅匠になっておる。慧能の南宗禅に対し、神秀の
北宗禅といわれる時代が来るのじゃ。したがって、神秀も、慧能と同じく、六祖といわれ
ておる。しかし、衣鉢(いはつ)を受け継いだのは、慧能じゃ。
これを見ても分るように、慧能は“頓悟(とんご)”じゃ。一方、神秀は“漸悟(ざんご)”じゃ。
神秀は、長い修業を経て、しだいに悟っていったのじゃ。そして、それぞれ二人の指導す
る禅風も、そのように分れていったのじゃ。こうしたことから、南宗禅は“頓悟”、北宗禅
は“漸悟”とするようじゃ。しかし、いちがいに、そうと割り切れるものでもないのじゃ」
「和尚、」一真が言った。
「うむ、何じゃ?」
「さっきの神秀と慧能の偈を、書いてもらえませんか、」
「うむ」
玄海が、サッと立ち上がった。和尚の硯箱と、紙ばさみを持ってきた。
和尚は、紙ばさみを手に持ち、さらさらと二つの偈を書きつけた。それを良安に渡し
た。良安が、それを一真と玄海の方に差し出した。
「神秀の偈は、いってみれば、倫理的じゃ、」和尚が、硯箱に蓋をかけながら言った。「一
方、慧能は、天性の感の鋭さで、“悟り”という仏法の本質を、グイとつかんでおる。
この、我々の住む世界の真相というものは、ホレ、“即、ここ”にあるのじゃ。まさに、ソ
レ、今ここに現前しておるのじゃ。が、ソレを見つけるのに、何十年とかかる者がおる。あ
るいは、仏道を歩みながら、一生涯ソレを見つけることができぬ者もおる。ところが、慧能
のように、アッ、とソレを見つけ、ヒョイとつかんでしまう者もおるわけじゃ。悟ってしまえ
ば、後は弘忍禅師が慧能に示したように、その禅の境涯を深めてゆけばよい。
しかし、言っておくがの...神秀のような“漸悟”と、慧能のような“頓悟”は、どちらが
良いと言うものではないのじゃ。悟ってしまえば、“無門の関”を通ってしまえば、あとは
一つじゃ。同じ一つの世界じゃ。“漸悟”となるか、“頓悟”となるかは、それはその人の
性格にもよる。じゃが、頭の良し悪しで決まるものではない。また、頭が良いからといっ
て、必ず悟れるというものでもないのじゃ。
人間、生まれてきて、死ぬわけじゃ。みんなそうじゃ。その間に、悟ればええ。人の一
生は修業じゃ。本来、修業という行為、修業という姿そのものが、悟りの風景なのじゃ
が...」
良安は、赤く焼けたストーブを見つめていた。
西住は、和尚が最後に言った、“修業の姿そのものが、悟りの風景なのだ”、という言
葉の意味を眺めていた。
和尚は、キセルにきざみタバコを詰め、また一服つけた。
「さて、」と和尚は、口から煙りを吐き出して言った。「『歴代法宝記』によれば、慧能が黄
梅山を去った後、弘忍禅師は説法を聞きに集まった僧たちに、こう言った」
「みなの者、もうわしに話すことは何も無い。それぞれ、何処へでも、好きな所
へ行くが良い」
これを聞いた僧たちは、口々に、一体何のことですかと聞いた。すると、弘
忍禅師は、こう言った。
「ここにはもう、仏法は残ってはおらぬ。わしの仏法は、はるか南方へ行ってし
まった」
僧たちは、皆びっくりした。
「南方へ行ってしまったですって!」
「あんな未開な南方に、そんな立派な大禅匠がおられるんでしょうか?」
僧たちはざわめいた。騒ぎは益々大きくなった。
すると、弘忍禅師のそばで、それまで黙って聞いておった法如(ほうにょ)という
者が、静かに言ったのじゃ。
「今まで黄梅山にいた、慧能行者(あんじゃ)です。慧能行者が、師の仏法を嗣(つ)
いで、南方へ帰ったのです」
「ところで、この法如じゃが、この男も弘忍禅師に師事すること十六年という。学問、人
格、修業、ともに優れておったという。最上席の神秀しかり、弘忍禅師のもとには、この
ような優れた者たちが山ほどおった。が、こと、仏法の真髄、“悟り”という一点において
のみ、慧能に遠く及ばなかったのじゃ。誰一人、慧能の天分に追いつけなかった。中国
全土から、優れた者たちが集まってきて、何年も修業をしておってのう...
しかし、これこそが、まさに、“頓悟”の出現だったのじゃ。慧能が五祖・弘忍に参謁し
た時から、五祖は慧能の天分を見抜いておった。しかし、それからわずか八ヶ月であり、こ
れほどとは思わなかったかも知れぬのう。いずれにせよ、五祖は、新しい悟りの形態“頓
悟”に、禅宗の将来を託す事を決したのじゃ。米つき行者の慧能を、初祖・菩提達磨以来
の、真理の体験的伝承を引き継ぐ第六祖と決したのじゃ。これは、並並ならぬ惚れ込み
ようだったはずじゃ。
つまり、慧能の“頓悟”は、それほど優れた大輪の花の蕾だったと言うことじゃ。この慧
能の時代から、禅宗はインド臭さが抜け、真に中国文化の大地に根付き、大きく開花して
いくのじゃ。むろん、この歴史的な開花があってこそ、禅は現在のように、日本をはじめ世
界で認められる文化となったのじゃ」
玄海が、目を輝かせていた。
「どうしてかなあ、」一真が言った。「どうして慧能は、“頓悟”ができたのかなあ、」
「天分としか、言いようがあるまいのう、」
「米つき修業八ヶ月ですか、」一真が言った。
「一真は、もうじき二年になるのう」和尚は、温かい皮肉をこめて言い放った。
一真は、頭をかいた。
「分ったじゃろう。普通はそんなもんじゃ。が、“光陰矢の如し”、一刻一刻、気を許すまい
ぞ。“漸悟”とて、のんびりとかまえておっては、ラチも開かぬ。神秀のように、常に精進
に精進を重ねておらねばならぬ」
「はい!」一真は、膝頭を両手で押さえた。
「さて...それで、黄梅山は大騒ぎになった。大混乱した。何百人もおる僧の中には、
激怒した者もおった。まさに、興隆期の禅宗にとって、この上もなく大事な五祖・弘忍禅
師の衣鉢(いはつ)じゃ。これは黄梅山の至宝でもあった。一部の者たちは、祖師の衣鉢を
取り返さんものと、慧能に追っ手をかけた。
この時、慧能を追った僧たちの中に、慧明(えみょう)という者がおった。前身は、ひとかど
の武将じゃったという偉丈夫じゃ。本題の『無門関』第二十三則は、この慧明が、大庾嶺
(だいゆれい)という山の峠道で、ようやく慧能に追いついた時の話じゃ。
慧能は、ついに慧明が追いついたのを知った。前にも言ったように、慧能は小男じゃ。
一方、慧明は、武将だったほどの偉丈夫じゃ。そこで慧能は、師の衣鉢をかたわらの石
の上に置き、慧明が近づいてくるのを待った。おそらく、いきりたっておった慧明は、こん
なことを言ったのじゃろう」
「やい、慧能。おまえのような無学な行者(あんじゃ)ごときに、黄梅山の宝を持っ
て行かれては、一山はたまったものではない。その、弘忍禅師の衣と鉢は、
黄梅山に返してもらいたい」とな。
そこで、慧能は、こう答えた。
「慧明上座...この衣鉢は、正法伝授の信を表すものです。力ずくで、どうこう
できるものではないでしょう。しかし、それでも、あえてあなたがそうするという
のなら、そうするがよいでしょう」
「ま、慧能としては、もっともなことを言ったわけじゃ。そこで慧明は、それでは...と、石
の上の衣鉢を持ち上げようとしたのじゃ。ところがどうじゃ。衣鉢はまるで、山のように動
かなかったのじゃ。これはどうしたことか。人間とは、不思議なものじゃ。そんなものを、
偉丈夫の慧明が、持ち上げることができなかったのじゃ。どうしてだと思う?」
「神通力ですか?」玄海が聞いた。
「はて、さて、わしにも分らぬわい。しかし、慧明には、まるで大岩のようであった。どうし
ても、持ち上げることができなかったのじゃ。それが、神通力か、心理的なためらいか、
もっと他のものかは、わしらには分らぬ。が、慧明は、恐れ、ためらい、おののいてしまっ
た。
激怒して、慧能に追いうちをかけ、いよいよ迫ってはみたものの、さあ進むも引くも出
来なくなってしまった。よいか、ここが、この公案の大事なところじゃ。慧明も、バカではな
い。いちずではあるが、ひとかどの人物じゃ。そして、その慧明が、さてもバカなことをし
たと気づき、心から恥じ、感きわまってしまった。そして、慧明は、素直な気持ちに立ち返
り、ただひたすらに、慧能に道を求めたのじゃ。おそらく、こんなことを言った。
「確かに、わたしは、法を求めてきたのでした。衣鉢を追いかけてきたのでは
ありませんでした。慧能行者、どうかわたしに、正法を教示して下さい」
そこで慧能は、感きわまっている慧明に対し、こう言ったのじゃ。
「善を思い、また悪を思うことを止めるがよいでしょう。そうした時、慧明上座、
あなたの本来の自己とは、どの様なものでしょうか」
この一言で、慧明は大悟したのじゃ。“頓悟(とんご)”じゃ。ドッ、と全身から汗が吹き出
したという。武将の身分を捨てて禅宗に飛込み、長年苦労して捜し求めておった“悟り”
じゃ。それが、慧能の一言で、ハッ、と分ったのじゃからのう。どうじゃ、こう聞いて、おま
えたちに大悟できたか?」
誰も、何も言わなかった。
「まず、無理じゃろうて。しかし、慧明はそれが出来た。そして、こうした『無門関』第二十
三則/“不思善悪(ふしぜんあく)”という立派な公案として残っておる。何故じゃ...よいか、
それは慧明が、長年修業を重ね、機が熟しておったからじゃ。また、真に、ギリギリの所
まで追いつめられたからじゃ。むろん、これは、慧明の事情じゃがのう、」
和尚は、硯箱に手を伸ばし、紙ばさみと筆を取った。そして、さらさらと書きつけた。そ
れを良安に渡した。良安がそれを読み上げた。
「“善を思い、悪を思うことをやめよ...この時、慧明上座の本来の面目と
は、どの様なものか...”」
良安は、紙を一真と玄海の方に回した。
「よいか、“善を思い、悪を思うことをやめよ”とは、善悪、美醜、損得というような、二元論
的なものの考え方を捨てよということじゃ。
慧能は五祖に参謁した時、仏性に東西南北の別はないといったが、本来この世の何
処にも、東西南北などの別は無いのじゃ。善を思うから、悪があるのであり、東西を思う
から、南北が生じてくるのじゃ。何も無い所で、左と指差すから、その対極として右が生
まれてくるのじゃ。こうしたことを、二元性といい、二元論的なものの考え方というのじゃ。
慧能は、このような考えを一切放下し、真の自己を見つめよ、と慧明に言っておるのじゃ」
「じゃ、どうて人は、そんな二元論的な考え方を身につけたのかなあ、」一真が、つぶやく
ように言った。
「うーむ、いい質問じゃ。よいか...人は成長するにつれて、しだいに自己というものが
明確になってくるのじゃ。そして、自己、すなわち主体があり、その対極に客体があると
認識するようになってくるのじゃ。しかし、よいか、慧能が慧明上座に言ったのは、そのよ
うな二元対立的な善や悪を思うことを、やめよと言ったのじゃ。そして、その時、慧明上
座の本来の面目とはどのようなものか、と言っておる。さあ、一真、どうじゃ!そこが脱落
すると、後に何が残る!」
「...」一真は、じっと炉端を見つめていた。
「よいか...それは、心を“無”にせよということじゃ。この公案は、“無”とはこのようなも
のじゃと教えておる。そして、心を“無”にした時、自己も世界もどこにもない。ただ目の
前に、“内外打成一片”の何者かが、静かに現前しておる。我も世界も“1”と響く...
これが、この世の真相なのじゃ...」
一真と玄海は、和尚が話し終わると、また紙の方を見入った。その二人に、良安が二
言三言つぶやいた。それから、火箸を使い、ストーブの外に掻き出した灰の中から、栗を
取り出した。焦げた皮をほぐし、手の中でもみながら、一つ割って食べた。
「焼けてるな、」良安は、残りの半分も口に入れた。
良安は、灰の中から栗を全部出した。そしてまず、二つ手に拾い上げ、両手でこね、
和尚の前に置いた。それから、玄海たちと、西住の方にも送ってよこした。
「山栗か。どこの栗じゃ?」
「一本松の下です。玄海が、学校の帰りに拾ってきました」
「うむ。あそこの栗は、小粒だが、うまい栗じゃ」
「正一さん」良安が言った。「あの一本松の下の栗の木が、今年、台風で一本倒れまし
たよ」
「ほう、どの木が?」
「一番下の木です。岩清水の方へ下った所の、」
「ああ、あれか...」
「もったいないことをしました」
「ここも、少しづつ変っていくな、」
「ええ。わたしたちが、あそこで栗を拾ったのは、もう二十年も前ですから、」
「そうだな、」
玄海と一真は、栗もそっちのけで、ボソボソと真剣に何か言合っていた。
「何か?」良安が二人に聞いた。
「いや、いいです」一真が、笑ってごまかした。
栗を二つ食べ終わると、和尚は立ち上がった。それから、しばらくして、また居間に戻
ってきた。
「いい月じゃった」和尚は、炉端に腰を下ろし、手をあぶった。「弘忍も、慧能も、道元も、
みーんな、この同じ秋月を見たじゃろう。しかし、今じゃ、その上を人が歩きよるわい」
「一句できますね」良安が微笑した。
「いい句にゃならぬわ。ケチがついておる」
「玄海」良安が言った。「勉強はいいのか?」
「ええ。今日はもう」
「それじゃあ、」和尚が言った。「『無門関』第二十九則を話してやろうかの。この話の続
きじゃ」
「はい!」玄海は、顔を輝かせた。
「正一さん、もっと栗を焼きますか?」良安が言った。「ああ、そうそう、山ブドウがありま
すよ」
「ほう、山ブドウか、」
「ええ。富三さんが、キノコと一緒に置いていきました」良安は立ち上がり、台所の方の
障子を開けた。
「アケビはないのか?」
「ええ。アケビなら、明日玄海が取ってきますよ」良安は、台所の方で言った。それから、
山ブドウの大きな房を、二つ持ってきた。
西住は、その山ブドウを受け取った。山ブドウは、珍しいほどの大粒で、黒く良く熟し、
すでに茎がしなびかけていた。が、口に入れると、さすがに酸味が強かった。もっとも西
住には、昔なつかしい山の幸の味だった。子供の頃は、ブドウと言えば、この山ブドウの
ことだった。
「さて、慧能は、」和尚は、本を片手に持って話し始めた。「そうして黄梅山を去った後、
十五年間ほど、消息が不明になっておる。禅宗史の中に、どこにも現れてこんのじゃ。お
そらくは、弘忍禅師の諭したとおり、ひとり禅の境涯を深めておったのじゃろう。
そして、歴史に再び登場してくるのが、広州の法性寺(ほっしょうじ)においてじゃ。四十歳
前後のことじゃった。この時の話が、『無門関』第二十九則“非風非幡(ひふうひばん)”じゃ。
慧能はその頃、法性寺の印宗のもとに、涅槃経の講義を聞きに行っておった。むろ
ん、まだ剃髪しておらず、行者のままじゃ。そうしたある夜のことじゃ。慧能は、一緒に後
ろの方で講義を聞いていた僧たちが、何やらザワザワ言合っているのを耳にしていた。
寺の幡(ばん/はた)が、ハタハタと風に揺らいでいるのを議論しておったのじゃ。幡とは、
ほれ、旗竿の先に吊るす、長い布のことじゃ。それが、風が出てきて、ハタハタと揺れて
おった。後ろの方で、気の緩んだ者たちが、こんなことを話しておったのじゃろう。
「少し風が出てきたな...」
「うむ...幡が揺れ動いているな」
「おい、」
「なんだ?」
「それは、少し違うぞ...幡が揺れ動いているんじゃない。風が動いているん
だ」
「バカなことを言う...幡が揺れ動いているじゃあないか」
「いや、動いているのは、風の方だ」
「風が動くだと?バカなことを言う。それは、そもそも風の働きというものだ」
すると、別の一人が話に加わって言った。
「何が風で、何が風の働きなのか?」
さらに、別の一人が口を出した。
「風といえば、すでに吹いているものだ」
「じゃあ、何故、風が吹くと言うのか?」
こんな議論に始まり、まわりの僧たちも、動いているのは、幡だ、いや風だ、
と言い始めた。そして、後ろの方が、しだいにザワザワとしてきた。そこで、そ
れまで黙って議論を聞いていた慧能が、一言、こう言ったのじゃ。
「皆さん...幡が動いた、風が動いたと、何をバカなことを言っておられる。
幡が動いたのでも、風が動いたのでもない。あなた方の、心が動いたので
す」
慧能のこの一言を聞き、今まで議論しておった僧たちは、ハッ、とした。
さて...『無門関』第二十九則、“非風非幡”じゃ。どうじゃ、一真?どうじゃ、玄海?」
「心が動いたんですか...」玄海が、考え込みながらつぶやいた。
「よいか、二人とも...これは禅問答じゃ。いわゆる、理性で理解できることではないの
じゃ。したがって、幡が動いたのでも、風が動いたのでも、まして心が動いたのでもない
のじゃ。慧能が、真に言わんとしたことは、別の所にある。さあ、何のことじゃ!」
「すると...」一真が、口をすべらせた。
「おう、すると...すると、何じゃ?」
「...」
「よいか...残るのは、“這箇”(しゃこ/仏教用語で、“この”、“これらの”を表す)だけじゃ。元来、ただ
これ、“這箇”だけじゃ...」
「和尚、どうしてそんなことになるんですか?」玄海が聞いた。
「よいか。ここに、言葉や文字の限界を越えた、真実があるのじゃ。理性や計算で理解で
きることなら、修業はいらぬ。この世界の真実、真理、真相は、“これ”、“ここに”、“即
今”、の上にあるのじゃ。わかるか?
この、“即今”、“即、目の前に現前している巨大な真実”を差し示すために、祖師たち
は、大変な苦労をされてきたわけじゃ。それが、禅宗の歴史であった。言葉で言って分ら
ぬから、棒で叩く祖師があった。言葉で言って分らぬから、嬌声を発する祖師があった。
言葉で言って分らぬから、黙って拳を立て、あるいは黙って指を立てる祖師があった。
いずれも、何を示そうとしておったのか。みな、この、“即今”じゃ。“即、目の前に現前
している巨大な真実”じゃ。あまりに近すぎて、見ることも、聞くことも出来ぬ真実じゃ。そ
して、よいか、それでも分らぬから、座禅を組む修業者たちがおったのじゃ。また、そうし
た修業者たちの道標のために、『無門関』や『碧巌録』のような、すぐれた公案集が編集
されてきたのじゃ...
しかし、この“即今”、“即、眼前している巨大な真実”は、いかようにも直接説明できぬ
ものじゃ。手を取り、そこを棒で叩いて示し、それでも分らぬ時は、痛棒を喰らわせた。そ
の行為、その痛みが、“即今”なのじゃからのう。そうやって、それを教え、示してやること
は出来る。が、結局は、その真実に自分が気付き、自分自身の力で、悟る以外はない
のじゃ...」
「それでは、和尚...」一真が言った。「それは、どこにあるんですか?」
「そうさな...今の言葉で言えば...それは、主体と客体を共に超越した所にある。よ
いか、主体とは、いわゆる自分じゃ。客体とは、その自分以外の全てじゃ。それは、人ば
かりではないぞ。囲炉裏も、ストーブも、山も月も星も、全て客体じゃ。分るな?」
「はい、」玄海が答えた。
一真は黙ってうなずいた。
「その主体と客体、その双方を超越した所に、“無心の心”がある。心を“無”にすると
は、そういうことを言うのじゃ。それは、何者かだけが、ただ現前している世界じゃ。自分
もなければ、他人もない。善も無ければ、悪も無い。美も無ければ、醜も無い。その“無
心の心”に、“悟り”への無門の関がある。そこに、この世界の真実、真理、真相が見え
てくるのじゃ。
よいか、これは覚えておくがよい。“無心”とは、別の角度から見れば、絶対主体である
己が、絶対主体である世界を見つめている姿じゃ。つまり、世界が世界を見つめている。
その時、本来の面目とは、どのようなものか...」
「...科学とは、」西住が、一真たちの方を向いて口を開いた。「物事を主体と客体に分
けて考えることを言う。つまり、観察する主体と、観察される客体に分離し、きちんと整理
し、体系化していく。しかし、和尚が言ったように、この我々の住む世界の“真実”は、主
体の側にあるあるわけでもないし、客体の側にあるわけでもない。その主体と客体双方
を超越した所に存在する。
科学を越えた所、あるいは、科学や理性のメスが入る以前...つまり、“人間の領域”
にあるのだ。これは、我々が“人間”であるということと深く関係している」
「それじゃあ、」一真が言った。「科学って何ですか?正一さんは、一種の科学者でしょ
う。科学って、何のためにあるんですか?」
「うむ...」西住はうなづいた。「そうだな...まず、科学は何かというと、それは真実の
影絵といったところだ...つまり、影絵はあくまでも影であって、本物ではない。それか
ら、科学は何のためにあるのかと言うことだな。まあ、それは、“方便”(ほうべん/目的を果たす
ために使う、その時だけのうまい方法)だ。科学も、総合的に突き詰めて行けば、根本的な矛盾に突
き当たる。が、“方便”としては、近似値的には、素晴らしい威力をもつ。人類の物質文
明が、このような形で今日まで発展してきたのも、いわゆる科学の力だ。したがって、科
学は“方便”として、真実の影として使いこなすことが必要だ」
「じゃ、主体と客体を越えるって、どういうことですか?」玄海が、同じことをもう一度聞い
た。
西住は、和尚の方を見た。
「それはじゃ...」和尚が、宙を見上げて言った。「自分が、それらのものと、一つになる
ということじゃ。主体である自分を越え、客体である周りのものも越え、そうした一切すべ
てが一つになる。それが、いわゆる、“絶対主体”といわれるものじゃ」
ストーブが、赤々と照り返っていた。鉄瓶から、蒸気が吹き上がっている。和尚、良
安、一真、玄海、そして西住は、静かな“今”の上に在った。不生不滅の“今”、不生不滅
の“唯心”の超次元座標で、彼等は同じ一つの囲炉裏端という船に座し、方向のない旅
をしていた。次元や座標という、空間的な方向のない旅。また、過去未来という、時間的
な方向のない旅でもあった。あるのは、ただ“即今”の、一枚の絵...その一枚の絵
の、自由な流れである。
この世界は、“唯心”...ただ一つの心...それ以外のものは、どのようなものも存
在しない。そうした中で、人は皆、自我という仮面をつけ、二元論的な喜怒哀楽の夢の
中を歩む。それが、誕生し、そして死に至る、発達心理学的な人間意識の必然である。
そして、ある時、“超意識/悟り”にたどり着き...夢から目覚めてみれば、大いなる
真実は、ただ一つと知る。それは、何者かが、自ら静かに現前している風景である。時
が時を見、空間が空間を見、光が光を見、ただそれのみが光り輝いている。やがて、あ
らゆる形態が消え失せ、あるのはただ光りとなる。ここに至れば、もはや主体も客体もな
く、“人”も“法(刹那滅における法・・・事物、存在、現象)”も無い。全てが一つに溶けてしまう。
あるのは、ただ一つの心...そのただ一つの心による、自らの超越的な目撃のみで
ある。それを“唯心”という。
第三章

清安寺の朝は早かった。まだ薄暗いうちに起き、本堂や境内の掃除を始める。それが
終わる頃、人々がぽつぽつと集まってくる。朝は、老人が多い。老人は暇な上に、朝が
早いからだった。中には、参禅ではなく、ただ遊びに来る者もあった。が、みんな大事な
信者たちである。
それから、この時期だと、六時に座禅に入り、七時に終わる。その後、朝粥(あさがゆ)にな
る。これらの世話は、良安と一真がやった。この朝粥が終わると、和尚が出てきて、三十
分ほど話をする。時には、一時間を越えることもあった。こうした清安寺の朝は、昔も今も
少しも変っていない。
朝粥が終わり、和尚が人々と話をしている間、西住たちは境内の下の方にある大根
畑へ出た。畑につくと、良安は近所へ軽トラックを借りに行った。西住と一真が大根を抜
き、だいぶ積み上げた頃、良安が軽トラックを畑に乗りつけた。大根は、軽トラックで、五
回運び上げた。それから、その大根の山を水場で洗い、二本づつワラで結び、竿に掛け
た。タクアン漬けにする大根である。雪深いこの地方では、タクアン漬けは貴重な冬の食
料である。この作務に、たっぷり三時間かかった。
朝の一仕事を終えると、三人は居間に戻った。玄海は学校へ行ったし、和尚の姿も見
えなかった。和尚は、檀家まわりである。檀家まわりは、和尚の足腰には一番良かっ
た。
良安が、ポットの湯で茶を入れた。一真が、台所から、サツマイモを蒸かしたのを持っ
てきた。三人は茶を飲み、冷たいサツマイモを食べた。
「鳴沢まで入りますか?」良安が、西住に聞いた。
「ええ。良安さんも、一緒に行きませんか?」
「寺を、留守にするわけにもいかんでしょう」
「じゃあ、一真は?」
良安は、黙ってうなづいた。
「行っていいんですか?」一真が聞いた。
「いいだろう。仕事はいっぱいあるが、正一さんが手伝ってくれるしな」
西住と一真は、良安の作ってくれた弁当を持ち、鳴沢へ向かった。細い山道を、バイク
を連ね、一時間以上も登った。もともとバイクで登れる道ではなかったが、何ヶ所かの難
所を越えれば、歩くよりはバイクの方がはるかに楽だった。彼等は、落葉の積もったジメ
ジメした山道を進み、ようやく鳴沢池のほとりでバイクを止めた。
うっそうとした樹林の中に、突然出現する原始の池である。この密林の池まで来る村
人は、めったにいない。巨大な杉の倒木が、池のほとりから沈み、こぼれ日が水面に射
していた。あたりは、死のような静寂が支配している。
この鳴沢まで来れば、キノコは必ずあった。もっとも、一真の言うとおり、誰かがすでに
取ったあとが幾つもあった。この鳴沢と呼ばれている一帯では、木々の葉も、すでに半
分以上が落ちていた。それが、山々の大地に厚く降り積もっている。この、深山の樹木
の香り、乾燥した落葉の臭い、それに山々の大地の体臭が、西住にはなつかしかった。
鳴沢には、まだブナの巨木が残っている。そうした倒れた自然の朽ち木に、色々なキ
ノコが生えている。二人は、朽ち木に生えたキノコの群生を見つけ、ポリ袋に摘み取って
いった。キノコは、できるだけ種類別にポリ袋に入れた。そして、それが手に重くなると、
背中のリックサックに詰めた。が、小さなキノコは、そのまま残しておいた。次に来る人の
ためであり、また来年のためでもあった。
「“人はみな、夢の中を歩む...”か、」西住は、弾力のある山の斜面を歩きながら、一
人つぶやいた。
「何か言いましたか?」沢の下の方で、一真が聞き返した。
「いや、何でもない」西住は、下薮で姿の見えない一真に言った。「独り言だ。道元禅師
の詩を思い出した、」
「詩ですか?」
「うむ...道元禅師は、“人はみな、夢の中を歩む”と言っている」
「“夢の中を歩む”ですか...どういう偈(げ/詩)ですか」一真が、ザワザワと下薮をかき分
けながら登って来た。
「うむ...こうだ...」
この穏やかに漂う雲は哀れなり
人はみな夢の中を歩む
目覚めれば、大いなる真実は一つ
寺の屋根を打つ黒き雨
「いい詩だろう」
「“目覚めれば...大いなる真実は一つ...”ですか...」
「うむ...悟ってみれば、大いなる真実は一つ...そして、その大いなる真実とは、常
に目の前に現前している...こういうのもあるぞ」
今ここに見られる山水は、
諸仏の方々の悟った境地を表されている
山は山になりきっており、水は水になりきっている
その他の何者でもない
それは、あらゆる時を越えた山水であるから
今ここに実現している
あらゆる時を越えた自己であるから、
自己であることを解脱している
「それは、『山水経』ですね」一真が言った。「『正法眼蔵』の中の、」
「うむ、そうだ。文語体を、口語体に訳したものだ」
「暗記したんですか?」
「いや、そういうつもりはなかった。いつの間にか、覚えてしまったのさ。道元禅師の言葉
として、」
「そうですか...」
西住は、ブナの巨木にナイフで刻みつけてある、人の名前を眺めた。ずいぶん古いも
のだった。明治という元号と、年月日が入っている。
「そうやって、」一真が言った。「悟れますか?」
「さて、どうかな...」
「正一さんは、自分で、何かを悟っていると思いますか?」
「和尚は何も言わん...ま、どのみち、悟り切ってはいまい。だから、2、3年もしたら、
帰って来いと言うわけだ」
「そうかあ。そうすりゃあ、ものになると?」
「多分、そういうことだろう...」
「ふーん...悟ったと思っても、なかなか悟っていないって言いますからねえ」
「しかしな、一真...こういう“悟り”の詩は、いいなあ、と感じることだ。深く共鳴してみる
ことだ。そうすれば、わずかずつでも、道元禅師の心に近づいていく...『正法眼蔵』の
真髄をかいま見ることが出来るのだ...」
「はい...」
「...“人はみな夢の中を歩む”という...この一つの言葉でも、修業していくにつれ、
道元禅師の深い心が分ってくる。折に触れ、益々深く分るようになる。もっとも、今のおれ
には、道元禅師の心は、ただ奈落の底のように深い。深く、透き通って、広く、カラッポ
で、何も見えない感じだ。しかし、ただ、この詩はいいなあ、と共感することは出来る。道
元禅師の投げかけてくれた心を、わずかにではあるが、共感することが出来る」
「そういうものですか、」
「うむ...ま、道元禅師は道元禅師だ...」
「はい、」
二人は、沢を登りつめた所の、日当たりのいい場所でリックサックを下ろした。乾いた
倒木に腰を下ろし、昼食のオニギリを開いた。
「正一さん、さっき、二元論と非二元論と言いましたね。それは、どんなことなんです
か?」一真が、漬物の入ったプラスチックの箱を開きながら聞いた。
「うむ...」西住は、オニギリを一つ掴んで言った。「いわゆる、我々の知識というものに
は、二つの形式がある。一つは二元論的知識、もう一つは非二元論的知識だ...まだ
他にも、分類の仕方はさまざまあるが、」
一真は、漬物の箱を、二人の間に置いた。西住は、オニギリをかじった。それをモグモ
グやり、それからラッキョウの酢漬けを一つ、口に放り込んだ。
「それは、どういうことかというとだ...」西住は、ラッキョウを噛み砕きながら言った。「ま
ず、二元論的知識の方は、リアリティー(真実)であるこの世界を、ことごとく二つに分断す
ることによって認識していく。
つまり、リアリティーを、まず主体と客体に分断することから、この認識は始まる。そし
て、およそこの世の全ての名詞、動詞、形容詞等によって、無限に差別化し、個別化し、
部分化して行くわけだ。分断していくことによって、理解が深められていく。
しかし、分断で、本来のものが破壊されて行くものもある。機械の部品が寄せ集めら
れて、機械になるわけではない。そこには、組み立てや、設計図というものがあるはずな
のだ。全体が、単なる部分の総合ではないということだ」
「しかし...どうして、そんな分断が、無限に続くんですか?」
「うむ、いい質問だ...何故、こうした細胞分裂のような、二元論的認識が始まるのか。
これは、“認識”というものの宿命だからだ。
いいか...人間の意識は、赤ん坊の状態から、しだいに進化していく。誕生した時の
意識は、自己と物質的宇宙とが、まだ未分化の状態にある。自己と宇宙とが、一つの状
態だ。これは“悟り”の風景に極めて近いといわれる。
そして、次に赤ん坊の意識は、食物ウロボロス(食欲が現れる)と呼ばれるステージに上が
る。すると、この“食欲”から、やがて自我らしきものが目覚める。この自我の覚醒こそ、
いわゆる自我である主体と、それ以外のものである客体との最初の分断を生み出す。
ま、最初は、かなり漠然としたものだが、自分と、自分以外のものとの分断をし始めるわ
けだ。
なんと言っても、この食欲と言うのは、自分以外のものを、自分の中に呑み込むもの
だからな。しかし、この時から、自分以外の他者が発生するわけだ。そして、他者のある
所には、“恐怖”が発生する。が、この最初の恐怖は、ウロボロス的恐怖と言って、漠然
と他者に呑み込まれる恐怖だ。この関係はわかるだろう?」
「はい、なんとなく...」
「うむ...しかし、この最初の分断は、実に決定的なことなのだ。受精卵の最初の卵割
と同じように、我々人間の意識も、必然的にこの道を歩んでいくことになるわけだから
な。そしてそこに、人類の持つ文化や文明という、既存の歴史的な言語的亜空間が重な
っていく...
つまり、“人生”とは、自分という主体と、それと接する他者との物語であり...言語的
亜空世界の超座標の中を、直接的知識と象徴的知識を合成して、時間的認識の中で旅
をしていくことになる...」
「うーん、言葉が難しいですよ、正一さん」一真は、首を横にした。
「そうか...これは、言っておきたかったのだがな。まあ、要するに...ここから、自己と
他者との壮大なストーリイが流れ出していくということだ。こうして、しだいに周囲に二元
論的知識や、それに類する概念が増え...ホモサピエンス独自の、そして共通の言語
的虚構世界が形成されていくわけだ...
コレとソレ、アレとムコウを区別するために、名前を付け、地図を作り...この壮大な
眼前する世界を学んでいく。ま、こうした膨大な言語的虚構世界を背負い込んでいくだけ
に、他の動物にはない学習の苦労が伴うわけだ。しかし、そこがまた、人類の知性や豊
かな情緒世界を醸し出しているわけでもある...」
「要するに、二元論的知識というのは、具体的にはどんなものなんですか?」
「そうだな...たとえば、我々はリアリティーであるこの世界を、上と下、左と右、光と影
というように、分断することによって、その切り口を認識していく。こういう二元対立的な認
識形態を、二元論というのだ。客観性に基盤をおく科学的知識などは、まさにこの二元
論の典型的なものだ。
科学は、“今”というこの世界の巨大なリアリティーを、“心の領域”と“物の領域”に分
け、“物の領域”に限定している。その上で、まず時間と空間に分断している。したがって
科学は、この時間座標と空間座標によって、マクロ的な大宇宙を作り上げた。また、ミク
ロの方では、リアリティーである“光”を、粒子と波に分断している。もちろん、これは悪い
ことではない。科学とは、そうやって分断することによって理解を深め、体系を構築して行
く学問だからだ」
西住は、手に持っていたオニギリをかじった。それから、水筒の水を一口飲んだ。
「じゃあ、時間と空間は、元々は一つのものなんですか?」一真が聞いた。
「そういうことだ。もっとも、それが科学的に証明されたのは、アインシュタインの相対性
理論でだ。相対性理論では、時間と空間が、一つの関係式で結ばれている。“光”の粒
子と波への分断は、量子力学の問題になるな...
まあ、これは分断したというよりも、そういう方法論、認識形式で進めた結果、観測的
に見つかってきたということだ...」
西住は、ナスの塩漬けを口に入れた。そして、それを噛み砕きながら、高いブナの梢
に射す、淡い秋の陽射しを見上げた。
「量子力学ですか、」
「うむ...よく、“光”は、波の性質と粒子の性質の、二面性を持っていると言うだろう」
「はい。聞いたことはあります。しかし、どういうことだかは、」
「うむ...リアリティーとしての“光”は、波として観測すれば、確かに波の性質を示す。
また、粒子として観測すれば、これもまた粒子としてだけの性質を示す。しかも、この二
つの性質を、同時に観測することは不可能だ。時間と空間を、同時に測定するのが不可
能なようにな・・・
このあたりから、話がややこしくなる。こういう関係を“相補性”というが...互いに支
えあっていて、切っても切れない関係という意味だ。つまり、科学が、リアリティーの核心
に迫っているとも言える」
「うーん・・・」
「しかし、これが核心だ」
「はい」
「つまり...“光”の性質とは、どんなものかと聞かれたら、粒子と波の二種類のメニュー
がございます・・・どちらに調理いたしましょうか?と、聞き返される。粒子か波かは、注
文次第というわけだ。つまり、ここは、完全に観測者の主体性にまかされてくる。これ
は、奇妙な話だろう。少なくとも、観測者の主体性にまかせるような科学は...」
一真は、小さく首を振ってみせた。
「話が少し脱線してしまったな、」西住は、空を見上げ、ラッキョウの酢漬けを口に放り込
んだ。「ようするにだ、二元論とは、今言ったように、リアリティーを分断することによって
得られる知識体系だということだ。科学や理性、それに、いわゆる言語もそうだが、こと
ごとく、こうした二元論的な思考形式で体系化されている。二進法で記述されるコンピュ
ーターなどは、その究極的なものだ」
「しかし、それが、全部ではないということですか?」
「まあ、そうだ。一見、ほとんど全部がそう見える」
「そんな...」
西住は、もう一つ、ラッキョウの酢漬けを口に入れた。そして、それを噛み砕きながら
言った。
「まあ、聞け...そうした二元論的知識に対し、非二元論的知識とはどういうものか。い
いか、非二元論的知識とは、リアリティーの分断や分析を、いっさい行わない知識のこと
を言う。つまり、直接リアリティーを把握する知覚だ。これが、文字どおり、非二元論的知
識なのだ」
「直接、リアリティーを把握するんですか?」
「うむ。むずかしいことじゃない。具体的な例をあげれば、“直感”がそうだ。インスピレー
ションとか、第六感とか...推理や理屈抜きに、突然何かがひらめく時があるだろう?」
「はい、」
「そういう種類の知覚だ。いわゆるテレパシー、透視、予知なども、理屈抜きにそうしたも
のが見えてくる。もっとも、我々の視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚などの五感もそうだ。理
屈や推理抜きで、見えたり、聞こえたり、感じたりする」
「はい、」
「しかし、ここが肝心な所だ。いいか...たとえば、視覚で目の前に現前しているものを
見、そこにもしブナの木という固有のものを認識したら...その時点で、それは二元論
的知識になる。なぜなら、リアリティーからブナの木を分離分断し、同時にそれを対象化
することによって、主体と客対をも作り出しているからだ。
ただ視覚でとらえているのなら、それは理屈抜きのものであり、非二元論的な知識だ。
しかし、そこで、ブナの木という分類を始めると、そこから二元論的認識の世界に入る」
「あ、そうですね、」
「あるいは、こういうことも言える。いい音楽が流れていて、それに聞き入っているまでは
いい。しかし、それが、ドボルザークの『新世界』だと認識する。すると、そこから二元論
的認識の世界に入る...分るか?そこからは、純粋な聴覚や、純粋な視覚ではなくなる
からだ」
「ええ、分ります...ようするに、直感や五感のようなものが、非二元論的知識と思って
いいわけですね」
「うむ、」西住はうなずいた。「何故こんなことを話したかと言うと、そうした、二元性を問題
としない超越的知覚が、非二元的知識であり、いわゆる真の知識なのだ。上下、左右、
南北、裏表といった、二元論的な構造化は、幻想に幻想を重ねることでしかない。そうし
た二元論的構造知識では、この世界の真理は把握できない...」
「どうしてですか?」
「二元論は、リアリティーを分断することによって、その切り口を見ているに過ぎないから
だ。したがって、それによって形成されるのは、影の世界であり、夢の世界なのだ...」
「どうして、そうなるんですか?どうして、理性ではなく、直感でなくてはいけないんです
か?」
「うーむ...それは...」
西住は、オニギリをかじり、それをもぐもぐやりながら考えた。鳴沢の秋の空や、樹木を
眺め回した。向こうのホウの木のてっぺんに、鳶か鷹のような、大きな鳥が止っているの
が見えた。
「それは...」西住は、慎重に言葉をさがしながら言った。「心というものの、本質と関係
している。心とは、あらゆるものから分離されずに、この世界のあらゆるものを目撃する
ものだからだ。
たとえば...このオニギリにしても、心とオニギリとは、分離されていないということ
だ。鏡に映したオニギリが、鏡とは分離されていないようにな。しかも、オニギリは見える
が、鏡自体はどこにも見えない。心とは、この鏡のようなものなのだ...
つまり、この鳴沢の樹木と心とは、互いに分離された存在ではないということだ。さら
に言えば、この我々の住む世界と、心とは、本質的に分離されていない。自己が宇宙と
一体のものとは、こうしたことを言う...」
「...」
「また逆に...自分の心を...物事や世界から切り離して考えるということ(“自我”の目覚
め)は、二元論的幻想世界を生み出す結果になる。言いかえれば、世界を主体と客体に
分離して考えるということは、リアリティーを失い、“煩悩”への道を歩むことになる。
むろん、これはさっき話したように、赤ん坊からの意識成長...意識の細胞分裂の流
れになるわけであり...自我の成長と共に、煩悩もやって来るわけだ...」
「うん...」一真は、うなづいた。
「いいか、我々は一刻も早く...この煩悩の世界から目覚め、真に人間としての道に踏
出さなければいけない...いや、そればかりではない。和尚の言うように、衆生を導いて
いくという、もっと大事な仕事もあるだろう」
「はい!」 一真は、唇をギュッと結んだ。
「いいか、一真...この世界の真実の姿は、こうした非二元論的方法でしか知覚するこ
とができない。客観性に基盤をおく科学や理性では、この世界の真実の姿は、知ること
が出来ないのだ。
なぜなら、リアリティーを分断して影を調べていく二元論的方法では、“心”を見失って
しまうからだ。“人間”を分断していって、最終的に原子や素粒子にまで還元していき、そ
こに“人間”の真実を見ることが出来るか?出来はしまい」
「...」
「話は少しズレるが...ここで大事なのは、究極にある原子や素粒子ではない。肝心な
のは、そこに流れている膨大な量の“関係性”にあるのだ。“物”ではなく、“関係性”が大
事なのだ。これは、“即、眼前している巨大な真実”を知る上で、一つの重要なカギにな
る。
ま...“物”も“関係性”も、禅的な風景から言えば、“内外打成一片”の同じものだ
が、あえて、こういう視点もあると言うことだ...」
「関係性ですか?」
「システムと言ってもいい」
「システムですか...」
「そうだ...」
一真は、考え込んだ。西住も、それ以上は何も言わず、オニギリを食べた。そして、そ
れぞれの分を食べ終わると、一真が言った。
「正一さん...『無門関』第二十九則が分らんのですが、」
「公案は、簡単に理解しようとする方がおかしいのだ。理屈で考えようとしては、ダメだ」
「まあ、そうですが...」一真は、頭に手をやった。
「...『無門関』第二十九則“非風非幡”で問うている所の...“風が動いたか、幡(ばん/
はた)が動いたか、心が動いたか”...これは、科学や理屈でどうとか、国語のテストのよ
うな解答をさがしていては話にならん。
昔、六祖・慧能の聞いた、夜の闇の中でハタハタとなびく幡の音を、自分も聞いてみる
ことだ。時を越え、非二元論的な知覚でな...」
「...」
「それは、慧能と共に、今も、ハタハタ、ハタハタ、となびいている。慧能が時を越えて、
ハタハタ、ハタハタ、となびいている。慧能が、永遠の世界でなびいている。いいか・・・
永遠とは、無限に続く直線的な時間のことではない。ここで言う永遠とは、“時が無い”と
いうことだ。“時の無い世界”ということだ。そういう世界を、考えたことはあるか?」
「いえ、」
「この世界が、まさにそうなのだ。我々の存在している、この世界がな。時間や空間は、
“今”の二元論的な影に過ぎない...我々は、時間を見極めようとすれば、空間が霞ん
でしまう。また、空間を見極めようとすれば、今度は時間の方が霞む。つまり、そのいず
れもが、幻想だということだ」
「それは、“永遠の今”ですか?」
「そうだ...そうした世界で、慧能は、今も幡の音を聞いている。ハタハタ、ハタハタ、と
風に揺れている音をな。永遠の動、動、動...永遠の静、静、静...そして、永遠の
今、今、今...そうした、時を越えた人間の真実...“唯心”の世界...そうした中に、
自分も飛込んでみることだ。ためらわずにな...」
「はい、」
話し込んでいると、空がだいぶ曇ってきた。青空も、ほとんど見えなくなってきている。
「ひと雨来ますかね」一真が言った。
「さあ、どうかな...いずれにしろ、すぐには降り出さんだろう」
「秋の天気は変りやすいですよ」
「うむ、」
一真は、昼飯の後始末をした。
「このあたりも、来月の今頃は、もうすっかり雪の下ですね」
「冬、この辺りまで来たことがあるのか?」
「ええ。良安さんと。雪山は、本当にきれいですね」
「ああ。何月頃来た?」
「さあ...雪が硬く凍みわたった頃でした」
「ふーむ、二月の末ごろだな。じゃあ、スキーの方も、だいぶ上達したわけか」
「はい。うまくなりました。山を歩くと、スキーが体に馴染むって、良安さんが言ってまし
た」
「特に、練習したことはないわけか?」
「はい。正一さん、その頃、また来ませんか?」
「そうだな...スキー・ツアーでもやりたくなったな。暇ができたら、来てみるか」
「はい。そいつは、楽しみですね」
第四章

その翌朝、まだ暗い寺の境内に、ザーザーと雨の音がしていた。気温が急に下がり、
寒い朝だった。西住は、持ってきたセーターを出した。良安たちは、僧衣の下に、肌着の
チョッキを着込んだ。
雨は、それから三日間降り続いた。シワシワとした、晩秋の長雨だった。境内の樹木
の幹も、落葉も、長い石段も、連日の雨を吸って黒々と濡れた。ようやく四日目の昼、雨
が上がると、山々はすっかり灰色にくすんでいた。これで、紅葉の季節も終わったのが
分った。この地方も、いよいよ立冬の季節に入ったのである。
清安寺も、冬備えで忙しくなった。ストーブで焚く薪も、今のうちに集めておかなければ
ならない。畑の中に穴を掘り、冬野菜も囲っておかなければならない。それから、根雪が
来るまでに、本堂や鐘つき堂、古い僧坊にも、雪よけのハメ板や、ヨシズを立てなければ
ならない。清安寺建立の時に植えた、樹齢二百年を越える松などにも、コモを捲き、竿を
立てなければ、雪の重さで枝が折れてしまう。野山がすっかり雪の下に埋まる冬に備
え、やることは幾らでもあった。
その、雨の上がった日の午後、西住は一真と一緒に、寺の裏山へ作務に出た。それ
ぞれ古い梯子を担ぎ、カギの付いた棒を持った。串柿にする、シブ柿の収穫である。裏
山には、大きな柿の木が何本もある。二人が梯子を掛け、カギの付いた棒で柿を落とし
ていると、和尚が坂道を登ってくるのが見えた。後ろで両手を組み、とぼとぼと登ってく
る。
「和尚...」一真が、ニヤリと笑って言った。「綿入れハンテンを出したな」
「寒がりだからな」
「酒飲みのくせに、」一真は、まだからかい調子だった。
西住は、梯子の上から寺の方を眺めた。この、裏山の柿の木の上からだと、清安寺の
境内全体が一望できる。道元禅師の詩の、“寺の屋根を打つ黒き雨”の寺の屋根が、黒
く重く沈んでいる。
「どうじゃ...少し熟し過ぎたか?」和尚が、二人を見上げて聞いた。
「こんなもんです」一真が答えた。
「そうか...みんな取るでないぞ。どの木も、少し残しておけ」
「はい。分ってます」
「ホレ、一真...木の方には足を掛けるな。濡れていて滑るぞ。柿の木は、折れやすい
ぞ」
「はい」
「ところで、正一...今度はいつまで居られる?」
「来週の水曜日に、帰ろうと思ってます」
「今日は何曜日じゃ?」
「今日は、金曜日です」一真が言った。
「うむ...それまでに、一度薪集めをするかの、」
「そうですね」西住は言った。
「川上部落の、内田正三郎の杉林が分るか?」
「内田さんの杉林ですか...?」
「ホレ、鳴沢へ行く途中に、清水の方へ登る道があるじゃろう、」
「ええ、」
「あそこを登って、清水の少し上へ行った所じゃ。いい杉林があるじゃろう」
「ああ、ありますね...スラリとした、手入れのいい、」
「うむ。あの杉林が、この夏枝打ちをした。それが、もらえることになってる。焚き付けにな
るじゃろう。どうじゃ、あそこまで軽トラックが入れるか?」
「清水まで、タイヤの跡がついてますよ」一真が言った。
「ほう。じゃあ、大丈夫じゃろう。どれくらいあるかのう...」
「ああ、そうだ、和尚、」西住は、ふと思い出して言った。「三の沢に、雷に打たれたカラ
松がありました。でかいカラ松でした。あれを持ってきますか?」
「ほう、どんなじゃ?」
「バラバラに砕けて、吹っ飛んでました。まるで、大砲の直撃を喰らったようでした」
「ほう、ほう、」
「この間の、アレかなあ...」一真が言った。「夕方、でかい雷が落ちたでしょう」
「ふーむ...三の沢のどのあたりじゃ?」
「大岩の下の方です。でかい花崗岩の岩があるでしょう。あそこから、五十メートルほど
山道を下ったあたりです」
「はて、すると、五助の山かな...清次郎の山かもしれんのう。清次郎の山なら、もらえ
るじゃろう。明日、寄って聞いてみるか、」
「清次郎というと、中村さんですか?」
「うむ。代がかわっておるでのう」
西住と一真は、地面に落としたシブ柿を、ポリ・バケツに拾い集めた。それを、寺の水
場まで運んだ。全部の柿の木から集めると、ポリ・バケツに三十二杯あった。木にも、ま
だだいぶ残っている。足場の悪い所は、ほとんど取ってない木もある。しかし、あとは柿
の木のものだった。これは、放っておくと、やがて完熟し、真っ赤になる。それを、根雪の
頃まで、小鳥たちがついばむ。
一方、水場に集めたシブ柿の山は、一つ一つ丁寧に皮をむき、カヤの串に刺す。そし
て、できたものから、僧坊の壁に吊るしていく。これも、古くから、冬の清安寺の貴重な食
料だった。タクアン漬けもそうだが、クシ柿も、十分すぎるほどの量を作る。寺には来客
が多いし、クシ柿などは、村の子供たちが喜ぶからである。
その日の夕餉(ゆうげ/夕食)の後、和尚は良安の渡した本をパタリと閉じた。
「正一」
「はい?」
「今夜は、お前が何かを話せ。何でもええ」
「さて...」西住は、拳を口に当てた。
和尚は、きざみタバコを丸め、キセルの先に詰めた。それをストーブに押し当て、火を
つけた。
「何が聞きたい?」西住は、玄海と一真に聞いた。
「それじゃ、正一さん」玄海が言った。「“心が動いた”って、どういうことですか?『無門
関』第二十九則で、慧能の言った...」
「うむ」西住はうなずいた。「そこが、よく問題になるようだな...じゃあ、玄海、まず、そ
の動いたと言う“心”は、どこにある。最初に、それをはっきりさせておく必要があるな」
「場所ですか?」
「うむ。まず場所だ。初祖・菩提達摩(ぼだいだるま)が、二祖の慧可に、“心”を持って来いと
言った話がある。『無門関』第四十一則、“達磨安心”だ...まず、その動いたという、
“心”とはどこにある?」
「それは...頭の中ですか?」
「頭の中というと...?」
「脳の中...」
「本当にそう思っているのか?だったら、それを見せられるか?」
「それは...」
「脳細胞が“心”だと言うなら、それは脳細胞のどのあたりだ?」
「それは...どことは、限定は出来ません...」
「じゃ、どうして脳細胞だと断定できる?どうして頭だと断定できる?人間は、体全体が
一つのシステムだぞ。五感は体全体に張り巡らされているぞ」
「...」
一真が笑い出した。
「そもそも、“心”とは何なのだ?これをはっきりさせる方が、先決かもしれんな。さあ、玄
海、一真、“心”とは何だと思う?これをはっきりさせなければ、場所がどうの、動いた動
かないのと言ってみても、話が進まん」
良安が、ストーブの横のフタを開けた。薪を一本入れ、またフタを閉めた。それから、ス
トーブの上に置いてある、鉄鍋のフタを取った。モウモウと湯気が上がり、煮豆の香りが
フワッと広がった。
玄海と一真は、顔を突き合せ、ボソボソと何か言合っている。それから玄海が二度うな
づき、顔を上げた。
「“心”とは、」玄海が、西住の方を向いて言った。「“自我”のことです」
「ふむ、なるほど。“自我”か。で、その“自我”を、玄海は感じたことがあるわけだな?」
「はい。いつも感じています」玄海は、自分の胸をドンとたたいて見せた。
「ほう、そうか...」西住は、微笑した。「“自我”を感じたことがあるわけか。それじゃ、
玄海、一つ聞く...」
「はい、」
「その“自我”を、感じたのは一体誰だ?」
「は?」玄海は怪訝な顔をし、一真の方を振り返った。
また、二人でボソボソと話し合った。今度は長かった。一真が、玄海の頭を小突き、二
人で笑った。
「“自我”を感じたのは、もう一つ別の“自我”か?」西住は、話し込んでいる二人に言っ
た。「そうだとしたら、“自我”が二つあることになるぞ。“自我”とは、二つも三つも、入れ
子細工のようにあるものなのか?」
今度は、二人は小声で鋭く言合い始めた。玄海が、一真の肩を指でつついた。そのう
ち、一真の方が考え込んでしまった。さらにだいぶたってから、西住が言った。
「いいか、玄海、一真...自分の右手で、自分の右手を掴むことが出来るか?火が、火
自身を燃やすことが出来るか?自分の目が、自分の目を見ることが出来るか?どうだ、
出来はすまい...
いいか、自分の目で見ることが出来るのは、自分の目以外の全てだ。自分の右手で
掴むことが出来るのは、自分の右手以外の全てだ。たとえば...鏡に映った自分の目
は、それは自分の本当の目ではない。左右が逆になった、客体化した虚像の自分の目
だ。こうしたことと同じ様に、自分の“心”が、自分の“心”を、客観的に見ることは出来な
いのだ」
「...」
「...」
「玄海が、さっき感じたと言った“自我”は...鏡に映った自分の目を指し、あれが自分
の目だと言ったようなものだ。その時、自分の本当の目は、何処にある?あるいは、写
真に映った自分の目を指し、友達に、“おれの本当の目はここにあるんだ”と言ったよう
なものだ。
そんなことを、友達が信用するか?玄海の目は、ちゃんと別の所にあるのを、友達は
みんな知っている」
「それじゃあ...」
「いいか、玄海...玄海の言った“自我”は、自分の心に映った客体化した“自我”なの
だ。それを、“心”...本物の純粋な意識である“心”が見ている。問題は、“自我”では
なく、こっちの本物の純粋意識...本物の“心”の方だ...これは、一体、どこにあるの
だ?」
「...」
「いいか、一真、『無門関』第二十三則、“不思善悪”は、このことを問ただしている。大庾
嶺(だいゆれい)という山の峠道で、慧能が、追いかけてきた慧明に聞いている。“善悪にも
とづいて考えるもの、見るもの、聞くものは何者か”と...何者だと思う?」
「...」
「その正体は、いわゆる玄海の言ったような“自我”なのだ...客体化した、偽りの“心”
なのだ...そして、慧能はこう言ってる。“そうした、物事を善悪に分断するような、二元
論的な考え方はやめよ”、そして、“そのような、二元論的に作り出された偽りの自我を
越えた時、そこに残る純粋意識...純粋な心とは...どの様なものか”とな...この言
葉を聞いて、慧明は大悟した」
玄海は、何か言おうとしたが、口をつぐんだ。
「いいか...人はみんな、自分を感じながら、毎日毎日を生きている。人生における喜
怒哀楽も、みんなその“自我”を中心に揺れ動いている。しかし、“自我”をそこに据え置
き、その喜怒哀楽を目撃しているのは何者なのか?そうした、人の世の喜怒哀楽の振
幅を映し出している、背景座標とは、何者なのか?そうやって、まさに“自我”を客体化
し、それを目撃している純粋意識/“心”は、何処にあるのか...」
「それは、何処にあるんですか?」一真が聞いた。
「こう言っている禅師がいる・・・」
わたしの体は幽霊のようなもの
小川のあぶくのようなもの
心そのものを見つめる心は
空っぽの空間のように形がない
が、その中のどこかで、音が知覚される
聞いているのは誰か...
「さあ、玄海...誰だと思う?どの様なものだと思う?」
「...」
「これを聞いている者こそが、不生不滅の“心”...“真我”なのだ」
「“心”とは、世界そのものだと言うんですね」一真が言った。
「うむ。一真、この間、鳴沢でこう言っただろう...“心とは、あらゆるものから分離されず
に、この世界のあらゆるものを目撃するもの”だと。“心”とオニギリ、“心”とブナの木は、
分離されたものではないと...」
「はい...」
「では...“心”は、何処にあるのだ?」
「さあ...それは、“唯心”ということですか?」
「そうだな...有名な物理学者の言っている言葉を話そう。参考になる。“波動方程式”
の発見者であるシュレーディンガーは、こう言っている...
主体と客体は、一つのものである。外界と意識とは、一つの
同じものである。それら双方の境界が、最近の物理科学の成果
で、壊れたのではない。そんな境界など、最初から存在していな
かったのだ。
これは、ノーベル賞をもらった、偉大な物理学者の言葉だ。実際、こうした問題が、素
粒子の世界でも大問題になっている。それから、有名な“不確定性原理”を発見したハイ
ゼンベルクも、こう言っている...
自然を扱う科学にとって、研究の主体は、もはや“自然それ自
体”ではない。人間の諮問に委ねられた自然である...
この言葉も、結局、観察する主体と、観察される客体が、切り離せないということを言
ってる。こうしたことは、単に禅の公案や、仏教哲学の問題だけではなくなってきていると
いうことだ。広く、科学世界全般をも捲き込み始めている。これが、どういうことかは分る
な。つまり、この世界のリアリティーが、何処にあるかという問題だ...」
「正一さん、」玄海が、膝を進めて言った。「さっきの詩を書いて下さい。それから、今の
物理学者の言葉も、」
「うむ、」
玄海が立っていき、和尚の硯箱と、紙ばさみを持ってきた。西住は、和尚の筆を使い、
それらを丁寧に書き上げた。それを玄海に渡した。
「多少言葉が違ってるかもしれんが、意味は同じだ...」
「はい、」玄海がうなずいた。
それから、玄海と一真は、声をそろえ、詩と物理学者の言葉を、くり返し読んだ。
「釈尊が...」しばらくして和尚が、おもむろに口を開いた。「悟りの中で認識した“心”と
は、生きとし生けるもの、すべての心じゃ...存在するもの、すべての心じゃ。それが何
か、今分ったじゃろう...
よいか...月の心、山の心、水の心、囲炉裏の心を...ひとり静かに、見つめてみる
ことじゃ...」
しばらくして、良安が鉄鍋のフタを取った。湯気と煮豆の香りが、部屋いっぱいに広が
った。良安は、木のシャモジで豆を幾つかすくい、それを吹き冷ました。それから、それを
掌に落とし、口に入れた。
「うむ・・・煮えたぞ。一真、皿を持って来い」
「はい」
第五章

西住が鹿村にやってきて、十日ほどが過ぎた。彼が越えてきた晩秋の山々も、今はも
う雪を待つばかりだった。清安寺の境内も、広葉樹がガラッと透け、遠くの南の山々が見
えた。また、日中になると、下の水田や畑から、細い紫煙が立ち昇のが見えるようになっ
た。
西住は、朝晩座禅に励み、日中は寺の作務に汗を流した。が、その他の時間は、一
人で山道を歩いた。西住は少年の頃から、山道を歩くのが好きだった。この山野の跋渉
は、鹿村での楽しいことの一つである。
こうして西住は、清安寺でののどかな休暇を過ごし、しだいに自分の心が澄んでいく
のを感じていた。しかし、あと何日かで、また都会の雑踏へ戻っていかなければならなか
った。それを思うと、坊主になるべきではなかったか、とさえ思った。
西住が、東京へ発つ前日の晩、和尚は炉端でこう言った。
「よいか、正一...物欲を断つことが出来たなら、あとは理屈はあまり考えぬがよい」
西住は、和尚の言葉にうなずき、唇を引きしめた。
「ただ、座禅することじゃ。その方が早いじゃろう」
「はい」
「ま...」和尚はキセルを取り上げた。「おまえに、考えぬがよいと言っても、仕事がら、
無理かも知れんのう。ともかく、座禅は欠かさぬことじゃ」
「はい」
「どうじゃ、正月は帰れぬか?」
「ええ。むこうでも、色々と用事がありますから、」
「うむ」
「しかし、二月の末頃、二、三日ほど帰れればと思っています」
「うむ...二月の末頃のう...」
「都合がつけばですが。ずいぶん雪も見てないですし、」
「うーむ...その頃は、大変じゃぞ。バスも不通になるかも知れんて、」
「ええ。その頃になったら、また電話します」
「うーむ。スキーで、山にでも登りたいか?」
「そんなとこです」西住は、微笑した。
「ほっ、ほっ、ほっ、」
「楽しみにしてますよ、正一さん」一真が言った。
「日曜日なら、一緒に行きたいなあ」玄海が言った。
翌朝、西住は座禅の後、寺での最後の朝粥を食べた。それから、ザックに荷物をまと
めた。梅干や漬物、ギンナン、クルミ、穀物などで、ザックがいっぱいになった。この他、
串柿やタクアン漬けなどは、折を見て、毎年小荷物で送ってくれている。
西住は、和尚、良安、一真と、別れの挨拶をした。それから、そのズッシリと重いザッ
クを、肩に掛けた。みんなは、境内のはずれの石段まで見送った。西住は、町の中学校
へ行く玄海と一緒に、石段を下りた。その百八段の石段の下で、もう一度三人を見上
げ、手を振った。玄海とは、バス停で別れた。西住は、下の町まで、歩いて下ることにし
ていたのだ。
南の渓谷ぞいに下って行くと、虹マスの養殖場がある。それをやっているのが、少年
時代の友人の一人だった。今、イワナの養殖実験をやっているので、是非寄っていけと
言っていた。西住は、行くと約束してあった。
どんよりとした冬空の下で、裸の樹木や薮が寒々としていた。西住は、両肩にくい込
むザックのベルトをしごき、のんびりと歩いた。そして、冬空を見上げながら、いつもの道
元禅師の詩を口づさんだ。
この穏やかに漂う雲は哀れなり
人はみな夢の中を歩む...
目覚めれば、大いなる真実は一つ
寺の屋根を打つ、黒き雨...
この四行の詩のうち、三行目以下は説明的である...人はみな、二元論的な夢の幻
想世界を旅し、修業して悟ってみれば、この世界の真実は一つと知る、という意味であ
る。
四行目は、その真実とは、どの様なものかという説明である。“寺の屋根を打つ黒き
雨”とは...何者かが、自ら現前している“即今”の風景...という意味だろう。
では、“この穏やかに漂う雲は哀れなり”という、一行目は何だろうか...この、一行
目こそは、道元禅師の心ではないのか...と、西住は思った。
西住は、もともと俳句や和歌や詩には、ほとんど素養がなかった。むろん、自分で作っ
たこともない。が、いつの頃からか、仏や悟りについてのものを読むことが多くなってい
た。それは、読んでいれば、おのずとその“心”が分るからである。また、年々、時々、そ
の“心”の深さも分ってくるからである。
この穏やかに漂う雲は哀れなり...
この一行目は、しかし、本当に道元禅師の“心”なのだろうか...西住には、むろん道
元禅師の“心”の深さは、知るよしもない。しかし、この一行目にしても、多少なりとも分る
ところはある。
それは、非二元論的に、直接感性に共鳴してくる、この世界の穏やかなものの哀れで
ある。もっともそれは、世界が世界自身を見ている、超越的風景である。しかも、常に、
すでに現前している何者かである。それを道元禅師は、哀れなり、と突き放して眺めてい
る。
この、“哀れなり”とは、一見客観的に眺めている感性である。しかしそれは、超越した
客観性である。いったんは、主観・客観をはるかに超越し、その上で、ほのかな人間的
な香りをつけている。
この、リアリティーに対する、ほのかなものの哀れ...これが、悟りの上に悟りを極め
た、道元禅師の“心”なのだろうか。いずれ、時がたてば、さらに深い禅師の“心”が分っ
てくるだろう。しかし、それは、どんなものなのだろうか...
西住は、霜の降りた農道を歩きながら、繰り返し、この道元禅師の詩をつぶやいた。
そして、どんよりとした立冬の空に、無心にその“心”を見つめた...
その西住の姿は、やがて渓谷のカラ松林の中へ消えた。葉のすっかり落ちたカラ松林
の梢に、風が吹き渡っていく...
・・・〔 完 〕・・・
