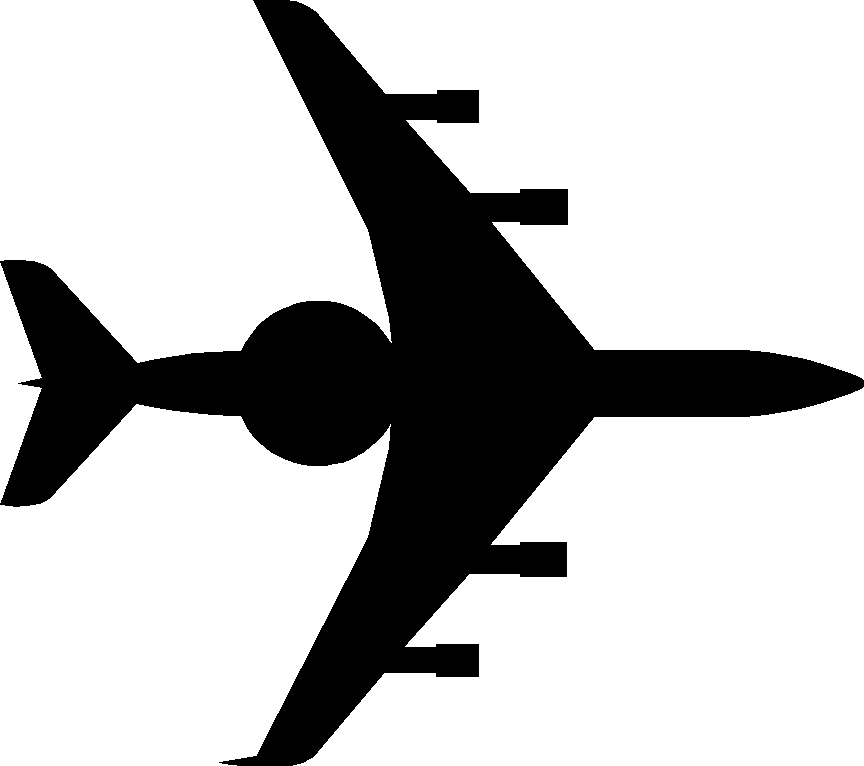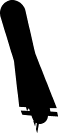![]()
人 間 の 座 標
![]()
早春の午後の日射しが、砂嵐の奥で白く散っていた。下界には、数十
キロに及ぶ廃墟の都市が広がっている。大震災と内乱によるものだが、ビ
ルはおよそその半数が倒壊している。また、広い平野の中の河川はいた
る所で氾濫し、洪水はいくつもの湖沼を形成している。それらの都市の中
に散在する湖水が、砂嵐の下で白く光っていた。
内乱は、平野の東部へ拡大した。そして現在、膠着状態に入っている。
ただ、この巨大都市の南東部の前線でのみ、いぜんとして消耗戦が続い
ている。
4月28日。午後。
その南東部における最前線の、崩れたビルの谷間の一画で、数台の民
間車両が砂塵をしのいでいた。灰色に迷彩された箱型の二トン車が三
台、そして大型ジープのランドクルーザーが二台である。その五台は、砂
塵の舞う中で、ひっそりと路地のガレキの上に乗り上げられてあった。
短機関銃で武装した男たちの何人かが、そこを中心に周囲の見張りに
出ていた。が、南の方だけは、豊に水をたたえた洪水地帯が、延々と広が
っていた。遠く、水面にちょんちょんと岩礁帯のように突出したビルの頭
が、吹き寄せる白波に洗われていた。
強い西風にのって、時々男たちの耳に、雷鳴のような爆撃の音が伝わ
ってきている。
「いやな音ですね」無線士の添島が、文化局のジープの中から言った。
「あれは、味方の爆撃だ」輸送班々長の砂山が、たしなめた。砂山は、わ
きあがる砂塵に目を細めながら、風のうなる天空を見上げている。
「また、味方の頭の上を爆撃してるんでなきゃいいですがね」輸送班の中
島が、ペッ、とツバを吐き捨てた。この男は、ヘルメットに付いている防塵
用のゴーグルを、目の位置まで引き下ろしている。
「そんな死に方はいやですね」添島が、重そうに首を振った。
「じゃあ、どんな死に方ならいい?」砂山が、投げ返すように聞いた。「死ん
でしまえば、みんな同じだろうが、」
「そりゃあ、そうです。しかし、その課程が問題ですよ」
「隊長、」と、輸送班の森本が、ガレキに寄りかかってタバコを吹かしてい
る青年に声をかけた。「隊長は、死ぬことについて、どう思われますか?」
彼等は、くすんだ色のヘルメットに、ネズミ色の迷彩服姿で、てんでの格
好で体を休めていたが、みんな隊長の方に顔を向けた。
彼等は誰もが、この回収部隊の指揮を取っている、文化局第三十二回
収班々長を信頼していた。掴みどころの無い隊長だったが、何よりも公平
であり、何となく万事がうまくいくのであり、それで信頼しきっていた。
その、文化局第三十二回収班々長は、名前を北里と言った。北里は、
激しい野外任務で浅黒く日焼けした顔を、静かにくずした。そして、
「死ぬことか?」と、よく通る声で聞き返した。
「そうです」
北里は、何と答えていいか、タバコを一服して考えた。それから、さらに
考えるようにして言った。
「死も、人間の一生の経験のうちのひとつとして考えることだな。人間の一
生は、生まれること、生きること、死ぬことの三つからなってる。しかし、そ
れらの経験の中で、どれが良い、どれが悪いということはない。どれもみ
んな、真実の結晶の流れだ」
「しかし、後方で、うまくやっている連中もいます」中島が言った。
「それも、同じだ」北里は、この単純な言葉に、重みと深みを込めて言っ
た。「何処にいようと、何をしていようとだ」
「本当にそう思いますか?」砂山が聞いた。
「ああ、」北里は、砂山を眺めやってうなずいた。それからゆっくりと、鍛え
上げられた体を、ガレキの塊から起こした。「さて、屋上の連中を見てくる
か。ここをたのむぞ、砂山。何時でも出発できるようにしておいてくれ。も
う、じきだと思う」
「はい!」砂山は、サッ、と挙手を切った。
北里は、上着のポケットから出した、ネズミ色の軍手をはめた。そして、
西側のガレキの山によじ登っている、竜造寺の方を見上げた。ひとりの青
年が、てっぺん近くのガレキの陰で身をこごめ、油断なく双眼鏡を使ってい
る。この回収部隊の中では、北里は判断力においては、この竜造寺を最も
信頼していた。文化局第三十二回収班の、副班長の任務にある。もともと
肌が黒く、万能のスポーツマンであり、大震災以前は弁護士の卵だった男
だ。
文化局々員は、北里と、この竜造寺の他に、無線を担当している添島、
そして北側のビルの屋上で見張りをしている、浜田と菊村老人の五人が
いた。輸送班の方は、三両の二トントラックに、それぞれ二人づつが乗込
んでいる。それから、この回収部隊にはあと一人、財務局から派遣されて
いる丸山がいた。今日の仕事は、財務局を支援してのものだったからだ。
「竜造寺!」と、北里は呼んだ。
竜造寺は、双眼鏡を膝の上におろし、日焼けした精悍な顔を下の方に
向けた。
北里は、北側のビルの方を指し示した。
竜造寺はうなずき、サッ、と投げるように挙手を切った。
北里は、タバコをガレキの陰でもみ潰した。そして、吸い殻を、上着の胸
のポケットの中に落とした。この広大な廃墟の中でも、タバコの吸い殻や
マッチ棒は、意外なほど人の目につくからだ。それが、新しいとなればなお
さらである。彼等の仕事では、行動の痕跡は、およそどんものであれ、可
能な限り残すべきではなかった。仮に、タバコの吸い殻やマッチ棒が、誰
かの目に止るとしよう。すると、その数や散らかりぐあいから、人数や休息
時間が判断され、さらにタイヤの痕跡から、車種や目的が判断されるとい
った具合である。むろん、長期的には、ルートや行動パターンまで、全て統
計的に分析されていくことになる。
北里は、腰の軍用自動拳銃を、少し後ろの方へ押しやった。そして、一
歩一歩踏みしめるように、北側のビルの方へ歩いた。腰の布ベルトの左
側には、ナイフと、液晶ディスプレイ解析盤付きの、高性能無線機が付い
ている。
北里は、窓ガラスの抜け落ちた、今にも倒れかかってくるような北側の
ビルを見上げた。古い小さなビルだが、このあたりでは唯一原形を残して
いる。中に踏み入ると、薄暗かった。所かまわず、ゴミやガレキが散乱して
いた。廊下には、段差のある旧式な防火帯があった。ドアの抜けた部屋
の中に目をやると、焚火の燃えかすがあった。大震災後、生き残った人々
が暖を取った跡である。
北里は、立ち止まって、ボンヤリとそこを眺めた。そして、人間の、“命”
の営みの跡を見つめた。
・・・定まりのない、人間の実態・・・と、北里は、心の中でつぶやい
た。・・・ここにありと確信したら、それはすでにここにはなく、過去に流れ
去っている世界・・・そして、常に新たな何かが、新たな何かの上に現出し
てくる世界・・・喜びと、悲しみが、この時空世界に溢れ出し、その全てが
一夜の花火のように散っていく人間の営み・・・そして、常に、つぎなる今
と、つぎなる孤独を描き出していく、人間の座標・・・
三階の踊場の窓から、南の洪水地帯が見渡せた。さっきまでいた自衛
隊の小型観測ヘリは、風に吹き飛ばされたように、湖面の上空から消えて
いた。
そのビルの屋上では、浜田と菊村老人が、腹這いに並んで双眼鏡を使
っていた。そして、たった今、ヘルメットを拾い上げて体をごろりと横にし、
肘を使って少し後ずさった方が、菊村老人である。この老人は、かって銀
行の大型金庫を制作してきた知識と技術を買われ、この回収の仕事に特
別に参加していた。すでに七十歳を越え、ふさふさした髪も見事なほど真
白に枯れている。妻子を失い、また自分の生まれ育った大地でもあるこの
東京に、老人は自分の骨をも捨てるつもりでいたのである。
老人は、痩せていて、物静かで、今ようやく人生のほとんどを終えようと
していた。しかし、老人は、これまで幾多の激動の時代を、この東京の大
地の上で過ごしてきた。若い時代の太平洋戦争。敗戦の屈辱。焼夷弾
で、一面焦土と化した中での、盲目のような再出発。そして、朝鮮動乱が
あり、ベトナム特需があり、復興の時代があった。また、東京オリンピック
の熱狂の時代もあった。そしてさらに、世界の工業大国、世界の技術大国
への飛躍の時代も経験した。かって、アジアの最果ての辺境の島国から、
急激にヨーロッパの列強に参入した、あの明治の富国強兵時代につぐ、
日本の第二の奇跡とうたわれた時代である。そうした、民族の挫折と栄光
の時代を、老人もまた、大股で歩いてきたのである。そして、いよいよその
人生の終末近くに見たものが、この巨大都市における、史上未曾有の大
惨劇だった。
マグニチュード8の強烈な直下型地震は、わずか数分間の出来事だっ
た。そのわずかな時間の地殻の異変が、営々と築き上げてきた、一千万
都市の大半を崩壊させたのだ。激震に続く、大火災の焼熱地獄。そのつ
ど、風向きによって変る、有毒ガスによる大パニック。そして、つぎつぎに
大暴動が起こっていった・・・
見渡す限りの、空を焦がす大火災。ゴウゴウとわきあがる黒煙と火柱。
そして、その後、激しい雨が降った。そのザーザーと降りしきる雨の中で
始まった、自衛隊と米軍の大救助作戦。各師団の、陸海空からの関東へ
の集中。港湾封鎖、海上封鎖、日本全土でたて続けに発進していく、スク
ランブル戦闘機群。自衛隊機構そのものが大混乱の中にありながら、ディ
フェンス・コンディションがいっきにはね上がり、臨戦体勢に突入していっ
た。陸上、海上、航空、全自衛隊の防衛出動待機体勢であり、そのまま交
戦段階に突入していく体勢である。
そして一方では、日本の主都壊滅と同時に、世界の軍事情勢がいっき
に緊迫した。東西の主力が対峙するNATO正面、中東、北極、中ソ国境。
また、日本の主都壊滅に雪崩現象の兆候を見せ始めた、朝鮮半島の三
十八度戦。そうした緊迫下にある一千万余の兵士が、そして数十億の人
類の全てが、日本の刻々の情勢を、衛星中継で固唾をのんで見守ってい
た。が、すでに世界経済の大混乱は、免れようもない現実の問題として差
迫っていた。
こうした状況に加え、シベリヤ沿海州方面で、ソ連軍の総合軍事演習
が、一週間早めて実施された。規模も、遠距離航空部隊のTu26バックフ
ァイヤー爆撃機を加え、五倍以上にふくれ上がったものになっていた。
また、こうした世界戦略の流れと連動し、東西両陣営の偵察衛星、軍事
通信衛星、海洋監視衛星等が、この緊張下の極東アジア監視のために、
続々と打ち上げられていった。さらにそれらに加え、アメリカのスペースシ
ャトル一機が、カリフォルニア州バンデンバーグ空軍基地から、地球極軌
道へ打ち上げられている。オービターの搭載貨物、宇宙空間での任務等、
一切不明である。しかし、世界戦略における、宇宙優勢確保の一環であっ
たことは、誰の目にも明白だった。
そして、そうした頃にはすでに、極左武装グループに扇動された組織的
な謀略と抗争が、この関東平野の大惨劇の中で、着々と進行していた。
誕生して、わずか数カ月しかたっていない革新連立内閣は、大震災と大
パニックの中で、実質的に壊滅した。それには、極左武装グループのテロ
があったとも言われる。しかし、その究明もされないまま、治安出動部隊と
極左武装グループとの対立だけがエスカレートしていった。
パニックと混乱の中で、破壊とテロが続発し、生活物資や援助物資の
輸送が組織的に妨害され、大衆が扇動され、デモが各地で同時多発的に
起こった。また、そうした中で、生き延びたと言われる閣僚一名を含め、数
名の政務次官が、極左武装グループに合流した。そして、彼等のやった
最初の仕事は、米軍の介入を牽制し、ソ連に正式な支援を仰いだことだっ
た。むろん、この要請は、即時に受理されたといわれる。そして、フルコー
スの軍事援助物資が、密かに、間髪を入れずに、各地に停泊中の貨物船
から揚陸が開始されたといわれる。いずれにせよ、これで内乱は決定的と
なったのである。
しかし、強力な治安部隊が包囲布陣する中で、内乱がこれほどまでに
拡大した最大の要因は、紛糾した衆議院解散後の、熾烈な選挙戦にあっ
たと言われる。その感情的なシコリが、国民を分裂させてしまったのだと
言う。スキャンダラスな事件によって、保守政権が退き、もう一方の、受皿
の整わない不安定な連立のヤグラの上に、歴史的な政変が乗ってしまっ
た。そのために、政治不安の心理的パルスが、社会の深層にまで、利害
対立の幻影をくい込ませてしまっていた。そして、まさにその上に、史上未
曾有の大惨劇が降りかかってきたのである。
そうした大暴動と大パニックの中で、首都圏を脱出する巨大な難民の流
れが出来るのに、さして時間はかからなかった。そして、この数百万人の
難民の流れは、自衛隊ではもはや押し止めようもなかったのである。
菊村老人は、こうした全体的ないきさつは、新聞やテレビのニュースで
知った。が、一面の焦土や、メガトン級の核攻撃を受けたような破壊され
た都市は、自分の目で見、自分の肌で感じ取ってきた。
しかし、目的達成のためには手段を選ばぬ一握りの人間たちにも、無
差別なテロや暴動の風景に対しても、老人にはもはや怒りの心は湧かな
かった。老人には、ただ、その全てを自分の目で見てきたという自覚だけ
があった。それは、自分の人生と、国家と、この巨大都市の変遷の風景だ
った。
北里が登っていく少し前のことだ。老人は両手でかげを作り、風をさけて
タバコに火を付けていた。強く吸込みながら、ようやくのことで火を付けた
のだが、風でタバコを半分も吸込めなかった。それでも、老人は、長い人
生の中で手慣れた、いっときの休息を味わっていた。老人はタバコを吸い
ながら、頭の中ではほとんど何も考えていなかった。そして無意識に、自
分のしわがれた掌の中のライターを、しみ入るように見つめていた。
この象牙細工をほどこしたライターは、大震災の前年、アメリカから帰国
した、孫の一人が贈ってくれたものだった。溢れるほどあった身の回りの
物、大勢の家族、自分が手掛けてきた会社、不動産や友人や様々な人生
の保証。そうしたものは、今は何も無かった。全ては、あの運命的な地殻
の変動とともに、大地へ還っていった。そして今あるのは、年老いた自分
自身の肉体と、掌の中の一個のライターだけだった。このライターを贈って
くれた孫も、あの大震災のさ中で、この世を去っている。しかし老人は、今
はもうそうしたことを悲しいとは思わなかった。自分も、虫ケラや鳥や動物
と同じように、この大地から生まれたことを悟っていた。そして、みな、やが
てまた大地へ還っていくのを納得していた。結局、そうしたものだと、老人
は思っていた。
老人は、ボンヤリとした頭の中で、いつものようにかすかな記憶をたどり
ながら、疲れた頭を水槽の鉄柱にもたせかけた。鉄がひんやりと冷たかっ
た。それで老人は、首に差込んでいたタオルを半分引き抜き、頭の横に当
てた。そうやって、細く痩せたうなじを凹ませ、大きくタバコの煙を吸込ん
だ。そして、タバコの味が薄いようだな、とまた思った。そう思いながら、午
後の淡い日射しが、黄砂の奥で白く散っているのを見ていた。風の中で、
あるか無しかのかすかな温もりを、老人は額に感じていた。そうやって、早
春の陽光をボンヤリと眺めていると、いよいよ自分の死期の迫っているの
が、老人には分るのだった。が、死を恐れる気持ちは、とうの昔に無かっ
た。かといって、死を望んでいるわけでもなかった。死は、ただ死であり、
この風と陽光のように、この一服のタバコのように、ごく自然なもののよう
に老人には思えた。それは、焚火の残り火が、すっかり灰になって冷めて
いくのにも似ていた。
「菊村さん!」と、一緒にいた浜田が、老人の様子が心配になって声をか
けた。「大丈夫ですか?」
「ああ・・・わしは心配ないて、」
「そうですかね、」
「まあ、何かあったら、わしをここに置いていってくれればいいさ」
浜田は、ぽってりと肉のついた顔を苦笑させ、首を二度振った。
「まあ、かってにどうぞ」浜田は、元気よく言い捨てた。
「もう、このあたりの景色は見たでしょう。下へ降りてもいいですよ。誰か、
代りの者をよこしてくれれば、」
「まあ、もう少しいますかな、」
菊村老人は、それから、腹這いになって双眼鏡を使っている浜田の背
中を、見るともなしに眺めていた。若々しく、大柄で、丸々とよく肥えた青年
だて、と老人は思った。また、野放図で、かって気ままな青年だとも思っ
た。
老人に悪気はなかった。老人は、今一緒に働いている青年たちが、皆
好きだった。もちろん、この浜田と呼ばれている青年も好きだった。それか
ら、老人は、この回収部隊を指揮している、文化局第三十二回収班々長
のことを思った。今はその班長を、老人は自分の孫のように思っていた。
老人は、できうる限り、生きている限り、その青年のために働こうと考えて
いた。そして、それが、お国への最後の御奉公だと思っていた。
老人は、ひとしきり激しくむせび、大きなタンを吐き捨てた。それからま
た、気を取り直し、ヘルメットを頭の上にのせ、金網の方へにじり寄った。
そして、浜田の横で腹這いになり、ゆっくりと両手で双眼鏡を覗き込んだ。
屋上へ出た北里は、強風に身をこごめながら、素早く東側の幹道を観
察した。空が明るく、ゴウゴウと天空に黄砂が流れていた。地上は、湧き
立つ砂塵で、ボウボウと霞んでいる。が、大地が埃っぽいのであり、それ
ほど風が強いわけではない。
それから北里は、首に掛けている双眼鏡を片手でつかみ、風の中を二
人のいる水槽の方へ走った。ジャケットが、バタバタと風をうった。北里は
目を細め、唇を引き結んだ。浜田のユーモラスな背中を見やり、ほくそえん
だ。
この浜田は、一風変った男だった。何処にいても、何をやらせても、全て
が枯れ木の賑いといった感じがするのだ。が、そうかといって、自主性が
無いというわけでは全くなかった。それどころか、浜田は回収本部でも貴
重な、第一級のコンピューター技師なのだ。しかし、それでいて、そうした
知性を全く感じさせない男だった。
「やあ、どんな様子だ?」北里は、水槽の陰に駆込みながら、二人に声を
かけた。
「べつに変った動きはないようですな」菊村老人が、防塵用ゴーグルをヘ
ルメットの上にあげながら言った。
「で、」浜田が、姿勢を低くし、後ろの方へ下がりながら言った。「ガンシップ
は来るのかい?」
「ああ。もうこっちへ向かってるそうだ」
「この風でもか?」
「ああ。最新のヤツは、すごい馬力だ」
「それに、」菊村老人も、後ろにさがりながら言った。「これは、でかい回収
ですて、」
「その通りだ」北里は言って、唇を引き結んだ。
「ああ、」浜田もうなずいた。
下の路地にある三両の二トントラックのうち、二両には、まさに地下金庫
室から回収した宝の山がつまっている。大震災時に永久ロックされ、その
まま未処理になっていたものだ。そして残りの一両には、その金庫を開け
るのに必要な、最新の機材や爆薬や雷管の類が積み込まれてある。
北里は、浜田と菊村老人に代わり、北側の幹道周辺を見張った。この
北の風景も、見渡す限りの廃墟である。しだいに雑草が芽吹き、その上を
ボウボウと砂塵が流れている。
北里は、目を細めながら、首に掛けている双眼鏡のツルを巻いた。そし
て、軍手をはめた両手で、双眼鏡のレンズを握り込むようにし、回収地図
の上に記憶している幹道を覗き込んだ。焦点を絞っていくと、その砂塵の
踊っている幹道が、急に目の前に迫った。そして、そのやや手前には、ち
ょうど海に浮かぶ小島のように、若葉の萌える樹林がくっきりと見えた。ケ
ヤキの若葉が、透けるように淡い。
「すると、」と、北里は、廃墟の大地を覗きながら、後ろにいる二人に聞い
た。「赤十字の車両が通ったのは、あの林の向こうだな?」
「そうですな・・・」菊村老人が、のんびりと言った。「ちょうど林の向こう、十
字路と水溜まりの間を抜けて行きましたな」
「十字路から水溜まりの方へだな?」北里は、双眼鏡を覗きながら、正確
に聞いた。
「さよう」
「他には?」
「確認したのは、それだけでした」浜田が言った。
「そうか・・・」
「そうですな、あの辺りは、ちょうど駅だったです」菊村老人は、懐かしそう
に言った。「線路が曲りながら、駅のホームに入っていく辺りでしてな。そ
の、看板の並んでいた、鉄道線路の手前の道路でしょうな」
「うむ・・・後でチェックした方がよさそうだな」
しばらくすると、ビルの屋上に、淡い陰が落ちた。見上げると、三機のヘ
リが、かなり近くまで迫っていた。その機体が、太陽をかすめたのだ。彼等
は、日の陰っている水槽の裏側までさがった。シルエットで、敵側の最強
のガンシップ、ミル24ハインドとは違うのが分る。もし、ミル24に本気で狙
われたら、全てを放棄し、身を隠すのが精一杯だろう。
見上げていると、一機が、風に大きく流されるように降下してきた。北里
は、太陽をレンズに入れないように日陰を確かめ、慎重に双眼鏡を使っ
た。ヘリは、ネズミ色に迷彩された、第一空中機動師団の最新型ガンシッ
プだった。胴体から、翼のようにウエポン・ベイが張り出している。そこに、
左右対称に二個のロケット弾ポッドと、TOW対戦車ミサイル8発を吊り下
げていた。この他に、20ミリ・バルカン砲を、標準装備として持っている。
中型輸送ヘリの大きなペイロードを生かし、装甲化した上に、一機で爆撃
機なみの火力を機動させている。
「一機だな、」ドン、と水槽の錆びた鉄柱をたたき、浜田が残念そうに言っ
た。
「あれなら、一機で十分だ」北里は、腰の無線機に手を掛けた。「さあ、行
こう!」
「ああ!」浜田は、自分の短機関銃を片手で拾い上げた。そして、二人よ
りも先に、階段を駆け降りていった。
北里と菊村老人が、ビルの外へ出た時は、ガンシップは地上数メートル
の所まで降下してきていた。ゴウゴウと細かいガレキを吹き上げながら、
周囲から身を隠すようにホバーリングしている。しかし、まるで怪物が出現
したような、圧倒的な感じだった。その、うなりを上げて回転している四枚
のブレードは、23ミリ対空機関砲弾にも耐えるものだ。
輸送班々長の砂山をのぞき、全員がすでにそれぞれの車両に乗込ん
でいた。二トン車には、輸送隊員が二名づつ。そして、財務局の丸山のジ
ープには、助手席に竜造寺が乗込んでいた。文化局のジープでは、浜田
がすでにハンドルを握っていて、エンジンを吹かしていた。一番若い添島
は、最後部にある無線席についていた。
菊村老人が後部シートに乗込むと、北里はヘリの風防ガラスの中へ手
を振り上げた。それから彼は、助手席に乗込み、防弾マットの入った重い
ドアを、バン、と閉めた。
「よし、行こう!」北里は、浜田に言った。
「ああ!」浜田は、サイドブレーキを落とした。
ザザーッ、とジープが発進した。ガレキの山を踏み砕き、いっきに道路
へ出た。その後に、三両の低い箱型の二トン車が続いた。しんがりに、財
務局の丸山のジープが回り込んだ。
五台の車両は、ガレキを踏み、高々と砂塵を巻き上げ、今にも崩れかか
ってくるようなビルの谷間を突進した。ぶっ潰れた橋をひとつ迂回した。日
の陰ったジメジメした所を、ザーッ、と水をはじいて進んだ。そこを抜ける
と、ようやく幹道に出た。幹道は、広い洪水地帯を左に見下ろした。十字
路があり、そこから左へ下った道路が、洪水の中に没していた。が、やが
て幹道を離れ、再び細い道に入り、彼等は北西へ向かった。
「班長、ガンシップからです!」添島が言った。
北里は、ヘルメットの上に、自分用の送受信機を付けた。
突然、頭の中に、エンジンとローターのうなる音が響いた。
「文化局!第三十二回収班!」北里は、声を張り上げて言った。「班長の
北里です!」
「空中機動師団、第三攻撃大隊の、朝倉だ。覚えているか、北里君?」
「ええ。もちろんです。よく覚えてます」
エンジンとローターの唸る音に加え、ザーッ、ザーッ、とノイズが入った。
無線にスクランブルがかかっている上、戦域一帯に妨害電波が乱れ飛ん
でいるのだ。が、ガンシップの方は、ドップラー航法装置、全天候型火器管
制装置から、秘話装置にいたるまで、全てが完備している。
「すると、君とは、例の品川撤収作戦以来だな」
「そうですね。また、世話になります」
「ま、よろしくたのむ。いいかね、まず、あと五、六キロで、我々の設定して
いる交戦域に入る。一番手薄なところを突破する。いつもの通りだ」
「ええ。了解です」
「では、まず、前線空中指令部の管制下に入ってもらおう。コールサイン
は、分っているな?」
「分っています」
「よし。それじゃあ、始めてくれ」
前線空中指令部というのは、重輸送ヘリに強力な無線管制システム
と、指令部機能を搭載したものであり、最前線で空中機動している。
回収部隊は、やがてその戦域情報が集中する、空中指令部の管制下
に入った。オペレーターが一名ついた。それから彼等は、直衛のガンシッ
プと共にその管制を受けながら、味方の散布地雷原の間隙を縫い、ビル
の間の裏道に入り、待機し、爆走した。大地が、ビリビリと振動していた。
多連装ロケット弾が射ち込まれているのだ。その連続的な炸裂音と、遠い
間欠的な砲声が聞こえた。そして、一瞬、煙幕のモウモウと上がっている
交差点から、北の空が一望できた。幾筋かの黒煙が、黄砂の舞う砂塵の
空にのみ込まれていた。そして、そのさらに上空に、小さな黒い点・・・無
人偵察機らしい影が流れていくのが見えた。
一度、彼等は待機している間に、数機の味方のガンシップが、廃墟のビ
ルの谷間を突進していくのを目撃した。凄じい空中機動戦の迫力だった
が、彼等が戦闘らしきものを直接見たのは、結局それだけだった。この戦
場は、まさに核兵器戦なみに、戦力が異常に希薄になっているといわれ
る。空中機動力の展開と、廃墟の都市という器が、ベトナムのジャングル
戦のような様相を作り出しているのだ。が、実質的な装甲ヘリによる超低
空域の戦略化は、この戊辰戦争(明治維新の官軍対幕府軍の戦争)以来
の、日本の内乱の中で確立さつつあった。
![]()


![]()
文化局の第三十二回収班が、第三前進基地の勢力圏に入った時は、
すでに風もだいぶ落ちていた。大きな春の夕日が、西の空の砂塵の中
に、ぽっかりと浮かんでいた。
基地近くのビルは、激しく撃ち砕かれている。その一面のガレキの上
に、ブルドーザや戦車が、黒いシルエットを作っていた。その中を進んで行
くと、錆びた鉄骨材や、折れた木材や、崩れた土嚢が、いたる所に散乱し
た。高台の裏側に、十榴陣地があった。牽引式の、105ミリ榴弾砲であ
る。その上に張られた破れたネットが、風に揺れていた。
そのさらに右の方の、半壊したビルの屋上の鉄柵に、戦闘服が一枚ひ
っかかっていた。そこには、12.7ミリ・ブローニング重機関銃があった
が、つい最近、陣地変換になっている。
「さあ、もうすぐだ!」北里は、後ろの三人を振返って言った。「“戦士の歌”
を合唱しよう」
「凱旋歌ですね」添島が言った。
「そうだ」
彼等は、歌をうたいながら、敵の砲弾が作った摺鉢状の穴をよけ、砂塵
を巻き上げながら前進した。半壊したビルが、資材置場に使われているの
が見えた。その脇の方で、二台のフォークリフトが、パレット積の砲弾をトラ
ックから降ろしている。ひしゃげた鉄塔の下に、土嚢で囲まれた休憩所が
あった。そこで数人の自衛隊員が、立ってお茶を飲んでいた。帰還してき
た彼等に、手を振った。彼等も、車の中から手を振り返した。
それから、次ぎの検問所で、コーヒーの缶詰を一個づつ渡された。彼等
はコーヒーで喉を湿らせ、また歌をうたいながら進んだ。最後の検問を通
過し、基地の第一フィールドに着いた時には、あたりはすでに薄闇が広が
っていた。全員が、ぐったりと疲れ果てていた。同じ五キロ、十キロを走る
のでも、かって道路が完備していた頃とは、比較にならないほど時間がか
かった。
この、第三前進基地の約二十キロ後方には、第二包囲環が敷かれて
いる。この、革命軍側の聖域を囲む第一・第二の二重包囲環は、東京湾
から関東北部の丘陵地帯にまで達し、ゆるい弧を描きながら、茨城県最
北部の太平洋岸へ抜けている。
また、沿海州のウラジオストックからの補給ルートのある日立港、鹿島
港一帯に対しては、自衛艦隊、米空母機動部隊、米強襲揚陸艦部隊が、
海上から包囲していた。しかし、日米両艦隊と、ソ連太平洋艦隊との確執
は、さらに北のオホーツク海から、ベーリング海にまで及んでいる。この、
荒れ狂う北太平洋の戦略海域は、海底、海中、海上、上空、宇宙空間に
までわたり、すでに実践に等しい電子戦が展開している。ベーリング海峡
をはさんで、地球上で唯一アメリカ本土とソ連本土が直接対峙し、日本の
北海道がその一角を占める北太平洋海域は、現在世界大戦勃発の、巨
大な火薬庫に発展してきているのである。
夜の会食は、前進基地で働く男達にとっては、楽しい時間だった。第三
前進基地で働く、約三百人の回収本部局員が、一堂に集まるのもこの時
だった。そのために、食堂は人息と食事の熱気とざわめきで蒸れかえっ
た。そうした中で、その日の回収報告、統計報告、指導、演説が行われ
た。時によると、負傷者や殉職者の報告もあった。が、今夜は幸い、食欲
が少しでも減退するような報告は一つも無かった。かわりに、テレビのニュ
ース報道カメラが一組入り込んでいた。そして、例のスズメ・タイプの女ニ
ュース・レポーターが、前の方で騒ぎをいっそう盛り上げていた。
文化局は、この第三前進基地に、二つの回収班を残留させている。第
三十二回収班と、第四十五回収班の合計十名である。彼等は正面の演
壇から一番遠い、窓際の一つのテーブルを占領し、食事をとっていた。全
員、風呂に入ってサッパリとしていたが、深い疲労が溜まっていた。特に、
最前線のCー70地区で回収をしてきた、第三十二回収班の方は疲れきっ
ていた。菊村老人は、ハシを置き、腹の上で両手を組み、椅子からズリ落
ちそうにして眠り込んでしまっている。
「明日は休ませよう」北里は、菊村老人を見やって言った。
「その方がいいな」第四十五回収班々長の、外山が言った。
「菊村さんにはきつかったな」
「ああ」北里は、ため息をついた。「おい、浜田、ヤカンをこっちに回してく
れ」
「あいよ、」浜田はヤカンに手を伸ばし、それをドンと北里の前に置いた。
北里は、前の方の騒ぎに目を投げた。そして、自分の茶碗と外山の茶
碗に、茶を注いだ。それから茶を一口飲み、鶏の唐揚げを一つ口に放り込
んだ。
この鶏の唐揚げは、一日に一度は食事のメニューに加えられている。す
でに、食料政策が効を奏しているのだ。魚は近海もののイワシが多くな
り、肉類も飼料効率の悪い牛肉などは、すっかり姿を消してしまっている。
そして、代わりに、この鶏肉がはばをきかせ始めているのだ。
「よう、北里・・・」後ろのテーブルから、鈴木が声をかけた。財務局の支局
長だった。
「何ですか?」北里は、肩越しに振り返って言った。
「今日は、すまなかったなあ、」鈴木は、パチッ、と指を弾いて笑った。
「なに、こっちは不死身ですからね」北里も笑い返した。
「じゃあ、明日もCー70を頼むとするかな。ハッハッハッ・・・冗談だ。明日
は、Dー35の方へ回ってもらうよ。ところで、今夜はヒマか?」
「いえ。原田禅師と約束があるんです。何ですか?」
「うむ。いや、いいんだ。べつに急ぐ問題じゃあない。上野の東部総局へ
帰還してからの話だ」
「じゃあ、どうせなら、特別休暇の後にしてもらいたいですね」
「ま、それでもいい」
「一体、何ですか?」
「そのうち話す」
正面の壇上に、海上幕僚部から来た若い将校が上がった。前の方から
拍手がわきおこり、食堂の中のざわめきもようやく鎮まった。シワひとつ無
いネイビー・ブルーの制服に身を固めた将校は、“環太平洋海運計画委員
会からのシーレーン・レポート”と題し、よく通る鋭い声で話を切りだした。
会食が終わると、北里は外山と一緒に、菊村老人を三階まで連れて上
がった。部屋は、浜田と添島が同室だった。菊村老人は、タバコを一本吸
い、すぐにベッドに入った。北里と外山も、部屋を出た。二人は何も話さ
ず、宿舎の薄暗い階段を下りた。ガラスの割れ落ちた踊場の窓から、南側
の広々としたヘリ・フィールドの明りが見えた。すでに、風はすっかり落ち
ている。静かな春の宵で、車のヘッドライトが、基地の南側の丘を登って行
くのが見えた。
「一緒に来ないか?」北里は、資料室のある二階まで下りると、外山に言
った。北里はそこで、原田禅師と会う約束になっていた。
「いや、」外山は、笑って首を振った。「このつぎにしよう」
北里は、黙ってうなずき、手を上げた。
外山は、二次回で討論会の始まる食堂へ下りていった。
外山は、大学院で、ずっと理論物理学を勉強していた青年である。が、
あの大震災で、大学そのものが無くなってしまった。それで、東京芸術大
学が中心になって進めていた、文化財の回収事業に参加してきたのだ。
北里は、外山とはその時以来の仲間だった。外山は、今ではこの最前線
の回収事業が終了しようとしているのを、最も喜んでいる一人だった。
北里は、重い鉄扉を切って、資料室に入った。原田禅師は、すでに新聞
を読みながら待っていた。黒いトックリ首のセーターに、褐色のコールテン
のズボンをはいている。
北里を見ると、ソファーから立ち上がった。新聞を新聞掛けに戻した。ツ
ルリと剃り上げた形のいい頭をし、何処か陽気な、乾いた深いまなざしを
していた。かって、科学技術庁の役人から、一転して禅門に入ったという
経歴の持ち主である。基地では、遺体回収局の幹部だった。また、あらゆ
る意味で、基地幕僚達の信頼も厚かった。
「遅くなりました」北里は言った。
「ああ、かまわんよ。だいぶ疲れとるようだな」
「ええ。Cー70まで出たもので」
「うむ、」
北里は、本を一冊持っている禅師の後から、広い資料室を奥の方のテ
ーブルへ歩いた。部屋の中では、幾つものグループが打合せをしたり、地
図や資料を調べたりしていた。が、奥の方は誰も居なかった。窓にヘリ・フ
ィールドの明りが見え、天井の明りも半分に落とされている。
「ところで、」と、窓ぎわの、菜の花の差した花瓶の置いてあるテーブルに
腰を落ちつけ、原田禅師は北里を見上げた。
「撤収まで、あとどのくらいあるかね?」
「我々の方は、あと残り六日と言われてます」
「うむ。では、もういくらもないわけだな」
「ええ」北里も、椅子を引いて腰を下ろした。
北里は、原田禅師からはずっと、『正法眼蔵』の講義を受けていた。が、
今日は、原田禅師は考え深げに顔を上げたかと思うと、まるで別なことを
言った。
「北里君、君は“アビダルマ”の時間論をどう思うかね?」
「はあ、」
「うむ・・・具体的に言って、“法”については、どうだな?」
「ええ・・・“法”というものが、率直に言って、素粒子のような感じがしまし
た。三次元空間の素粒子を、時間的に積分していけば、四次元世界線と
いうことになりますが、そういうものかなと思いました」
(“法”: アビダルマにおける“刹那滅”の概念。ここでは、時間の最小単位で
ある刹那ごとに、法は生じ且つ滅びていくという考え。“法”という語は、サン
スクリット語で“ダルマ”といい、保つとか、支えるというほどの意味である。ま
た、仏教用語としては、教えるという意味を持ち、さらに、事物、存在、現象
などの意味も持つ。)
(“アビダルマ”: アビとは、対するという意味であり、これは“釈尊の教えに
対する議論”という意味である。)
「“法”と素粒子とはまるで違うが、」と、原田禅師は微笑して言った。「ま
あ、それは、君自身が考えてみるが良かろう」
「時間を、密度をともなうような、粒子の集合体のように考えるというのは、
どう思われますか?」
「うむ。わしには何とも言えん。が、わしも、そうしたことを色々と考えたこと
があった。あるいは、この科学時代が、そうさせるのかもしれん。時間空
間の、絶対主義、相対主義といったようにな、」
「ええ。ニュートンと、ライプニッツですね」
「そうだ。だから、こうはわしにも言える。今、我々二人がこうして話し合っ
ているのも、厳然たる時間の流れの中においてだということだとな。時を
語るも認識するも、そして我々の存在すらも、全て時の流れの中において
成立する。その我々が、時を知るには、おのずと限界があるとは思わぬか
な。客観的であり得るかな。逆に、全てが、主観に陥っているとは言えま
いか。ならば、時間というものが何であるかを知るには、この絶対主観の
立場より他に道はないと、わしは思うが、」
北里は、テーブルの上の、黄色い菜の花に目を当てていた。そして、自
分の心の中の理解を眺めながら、黙ってうなずいた。
「相対性理論は、時間と空間の関係式を、光速度の不変性に置いた。時
間と空間の状態がどう変化しようと、その二つの関係から導き出される光
速度は、一定不変だという所に座標を定めた。しかし、禅においては、そ
れを絶対主観、つまり絶対主体性に置いておる。その絶対主体である己
にとって、この時間的風景が一体何であるかを知ることだ。全てを、幻と思
うもよかろう。全てを、夢のまた夢と思うもよかろう。いずれ、科学にせよ、
哲学にせよ、そして宗教にしてもだが、その基盤はしっかりと据えておか
ねばならぬ。そうは思わぬかな、北里君?」
「ええ。そうだと思います」北里はうなずいた。
「また、そうでなければ、何も解決はすまい。ただ、迷いの上に迷いを重ね
るだけの結果になってしまう」
「この宇宙が、数学的な側面から観察されているのは、どう思われます
か?」
「うむ・・・わしも、かっては、科学技術庁の人間だった。科学を信奉する者
のはしくれだった。だから、数学の威力は知っておるつもりだよ。数学は、
確かにこの宇宙の共通語と言えるだろう。この宇宙が、分割可能な物質
と、意味の構成からなっているとすれば、それらを結びつけている力学が
ある。意味付けている哲学がある。プランクの定数・・・不確定性原理・・・
重力定数。エネルギー保存則。エントロピーの増大と、重力熱力学的カタ
ストロフィー。そして、大統一場理論の展開。こうした方向から、宇宙の探
索はどんどん続くだろう。その意味で、数学は宇宙の謎を解く一つのカギと
言えるかもしれん。しかしだ、数学は、あくまでも数の学問でしかない。究
極ではあるまい。小川の流れを、流体力学的に極限まで把握したとして、
それが一体何になろう。その、膨大な資料の山を受入れる我々は、人間
なのだ。人間にとって、小川はサラサラ流れる。それでいい。大きくもなけ
れば、小さすぎもしない。それは人間にとっての、完全な姿の小川なの
だ。いいかな?」
「はい、」
「うむ。逆に言えば、小川のパーソナリティーなのだ。我々は主体であり、
人間だという事実は・・・何と言ったらいいか・・・北里君の言う物質世界、
精神世界、情報世界、意味世界かな。そうした全てが、いわゆる人間にと
っての世界だということだ。そうした世界において、一つ二つという数の関
連の学問が、主体である人間を凌駕することはあるまいと、わしは思う
が、」
北里は、原田禅師の言葉にうなずきながら、“ラプラスの魔”という言葉
を思った。その概念は、全宇宙の物質について、素粒子の一個一個につ
いてだが、その森羅万象の世界を、重力場方程式や運動方程式によっ
て、究極まで解明するといったような意味だ。しかし、禅師の言われるよう
に、ここから一体、人間にとっての何が導き出されるだろうか・・・
「ひとつ、わしの昔話を話そう」原田禅師は、乾いた深いまなざしを細めな
がら、首をやや傾けた。「わしは昔、こう考えたことがあった。時間にせよ、
空間にせよ、宇宙にせよ、そこにはおのずと人間としての側面があると
な。人間の方を向いておる、顔があるとな。つまり、我々の五感の全てが、
この世界の事物事象の人間的な側面だということだ。仏の教えはともか
く、その当時は、自分なりにそう考えたものだった。我々の目に映る現象
は、明らかに、人間的に変形されたものだと思った。だいいち、昆虫の複
眼で見る世界や、魚の魚眼レンズで見る世界は、人間の目で見る世界と
はかなり違うものだそうだ」
「そうですね、」北里は言った。「個人個人によっても、全て異なりますが、」
「そのとおりだ。そしてまた、人間の感覚というのは、人間の都合のいいよ
うにこの世界を再構成し、それを認識しておる。そうしたもので、ひとつの
虚構世界を作っておる。視覚の事例をあげれば、距離の問題と、形の問
題と、色彩の問題がある。色彩について言えば、物質そのものに色彩など
というものが無いのは、画家の君なら知っておろう。物質界の本当の色
は、まるで電子顕微鏡で覗いた世界のようだと聞いておる。昔の白黒映画
の世界のようだと、」
「ええ。物質に電磁波があたり、その反射吸収の微妙な変化が、人間の
目の網膜に感知されます。その信号が、神経をつたって脳に入ります。そ
して、その脳の中で初めて、様々な色彩世界が構成されます。ですが、あ
る波長の電磁波が、なぜ赤や黄色や緑に対応するのかは、分りません
が、」
「つまり、可視光の七色だな、」
「ええ。人間にとっては、」
「ふーむ、」原田禅師は唇を引き結び、それから愉快そうに唇をなごませ
た。「北里君も、そうしたことを考えたことがあるわけだな?」
「いえ、ぼくはただ、授業で習っただけです」
「それでいい。そして考える。人間とは、そうしたものだ。それからさらに、
自分とは一体何か、世界とは一体何か、生きるとは一体何か、じっくりと
考えてみることだな」
「はい」
「禅とは、この宇宙における、絶対一元的な主体性を悟ることだ。一切を捨
てきって、無になりきることだ。無になりきるとは、一切のこだわりを捨てる
ことだ。相対的な欲得の、自己を捨てることだ。この宇宙における、唯一の
主体になりきってみることだ。いいな?」
「はい」
「絶対主体性とは、自我の拡大ではない。自我を捨てること
だ。いいな?」
「はい」
北里は、そこに、“人間の座標”を直感した。そして、深い“命”の深淵
と、張り巡らされた人間の根の深さと、ボウボウと流れる宇宙の底流を感
じた。“時”が単なるパラメーターにしても、あるいは、この宇宙の存在その
ものが“時”だとしても、絶対主体性はその一切を呑みつくしてしまう。孫
悟空のガキが、釈迦の掌から、絶対に外に出られなかった道理だ。時空
間をも含め、生も、孤独も、死も、あらゆるものが、その絶対主体性の中に
呑みつくされているからである。
九時過ぎになって、北里は原田禅師を外まで送り出した。回収本部の
傘下にありながら、遺体回収局だけは全てが別だった。宿舎も施設も、特
別の独立したエリアにある。そして、そのエリアにある冷凍倉庫だけでも、
まだ何万体とも知れない回収遺体が保管されていた。その遺体を荼毘(だ
び)にふす細い紫煙が、今もこの風のない夜空に高く立ち昇っている。
北里は、原田禅師が錆びた鉄道線路を渡っていくのを見送った。線路
の枕木の間に、早春の雑草が伸びている。北里は、春がまた巡ってきた
のが嬉しかった。全てが、こうして経歴していくのが嬉しかった。その春の
星明りの下で、原田禅師の後ろ姿は、やがてブルドーザが作ったガレキの
山陰に消えた。
北里は、少しヘリ・フィールドの方へ歩き出してみた。風が落ち、なまあ
たたかい春の宵だった。夜空が澄み、空気がいつになくうるおっていた。
星辰が、うるんだ光を、廃墟の大地にふりそそいでいる。北里は今、それ
らの現象の一つ一つを検討した。そして、人間的側面から、あらためて光
りを当てた。
北里は、あらゆる現象、あらゆる存在、こうした一切全てが、自己の主
体性の発現と認識した。その現象界の真理の海に、北里は、静かにその
真理の一片である自我を沈めていった。限りない深淵の、海底を目指し
て。人間の根源へ。真理の流れへ。そして、永劫の時の世界に、人間原
理の解を求めて・・・
基地も、いつになく物音が絶えていた。虫も、風も、素粒子も、一切のも
のが、彼のためにそっと息をひそめていた。そして、この次元座標の基地
は、ひとときの平安と、真理の夜を描いて流れていた。
北里は、いつしか立ち止まっていた。そして、またゆっくりと歩み出しな
がら、心の底でつぶやいた。
・・・色空間には、およそ750万色にのぼる色彩世界が展開する。が、
その絢爛たる色彩の流れる世界も、それは人間にとっての感覚であり・・・
自我の結晶世界であり・・・この主体にとっての感覚であり・・・唯一の認識
であり・・・
・・・宇宙を突き抜けて無量に漂う、七色のシャボン玉のような閉鎖情報
系・・・シャボン玉どうしが、何の妨げもなく通り抜け合う、相互主体性の世
界・・・
ひとつ向こうの道路を、基地パトロール隊のジープが走っていった。この
星明りの中で、北里の姿を認めたはずだった。が、ジープは、ゆっくりと動
いていった。北里は、深呼吸し、星明りが影を映している雑草を見つめた。
その光と影が美しかった。
彼は、ヘリ・フィールドの端に立ち止まり、深い夜のしじまを見上げた。
その、おそるべき静寂と、宇宙の深淵の彼方に、かなわぬ自我の真相と、
その真の波動を見つめようとした。
そうやって、じっと立ちつくしていると、彼は心のうちに、どこからともなく
満ち溢れてくる、あたたかい存在の波動を感じた。存在することの、静か
な喜びを、全身で感じた。無条件な、おどろくべき安定した波動だった。
・・・一体、これは何だろうか・・・これは、何処から来るのだろうか・・・こ
れは、“命”の中に発現しているのだろうか・・・
が、そうした思いすらも、たちまち包み込んでしまった。そして彼は、た
だ唖然として、それを受入れ、見つめていた。
![]()

![]()


北の空から、ゴウーン、ゴウーン、とかすかな爆音が聞こえてきた。が、
やがてそれは、沖から押し寄せてくる大波のように、基地の夜空全体を圧
し始めた。その割れるような豪音の響きを切り裂き、キーン、と鋭いジェット
音が流れた。第一空中機動師団、一個攻撃大隊の増援兵力である。おそ
らく、ソ連の沿海州と対峙している、新潟方面の部隊だろう。
やがて、重輸送ヘリや電子戦ヘリを含む、総合戦闘ヘリ集団の航行灯
が、夜空の中にパラパラと見えてきた。星空を背景に、夜行虫のようにひ
しめいて光っている。強力な夜間兵装システムを誇示し、この第三前進基
地の助っ人に乗込んできたのである。大隊を護衛してきたのは、国産新型
機種のCCV支援戦闘機のようだった。空中機動師団では、この一個大隊
が、一つの総合戦闘集団を形成している。
空中機動師団としては、この関東配備の第一空中機動師団の他に、北
部方面隊の北海道に、第二空中機動師団が展開している。
北里は、一波、二波、三波と飛来してくる航行灯を見上げながら、宿舎
の方へ引き返した。宿舎の半壊したホテルの中に入ると、ようやく騒音が
遠のいた。
宿舎の中は、すでに寝静まっていた。北里は、誰もいない薄暗い廊下を
歩いた。何も考えなかった。それから、ふと、一つの概念が、心の表面に
浮び上がってきた。
・・・人の一生においては、何が良く、何が悪いということはない・・・菊村
老人の言うように、全てはあるがままの現実が、真実なのだと・・・それ
が、真実の結晶なのだと・・・
壁には、回収スローガンや、ニュース写真が、びっしりと張り出してあっ
た。それもこれも、みな真実の結晶の姿だった。それから北里は、廊下の
天井に張ってある、問題のポスター写真を見上げた。素肌の美しい娘が、
片方の乳房をツンと立て、肩越しに振り向いて優しく笑っていた。
むろん、公衆の面前に、こんなものを張り出すのは厳禁だった。基地で
は、マリファナや覚醒剤はむろんだが、アルコールさえも厳しく制限されて
いる。またタバコにしても、ヤニ取り用のパイプが、無料で支給されている
ほどだった。しかし、天井が公衆の面前であるかどうかはともかく、このポ
スターを知らない者は、おそらく一人もいないだろう。
北里は、写真の中にいる、娘の真実の意味に笑いかけた。そして、“画
餅”ならぬ写真の中に、娘の真実の命を見つめていた。全ての理解は、
“絵”である、と道元禅師は言っている。北里は、娘の真の命を見つめつ
つ、そしてそれを見つめている自分自身の真実をも、“一枚の絵”として眺
めていた。
やがて北里は、その“絵”の中の廊下を歩き始めながら思った。“絵”
は、喜びも悲しみも、生も死も、美も醜も、みな同じパレットの中の絵の具
で描かれる。そこには、価値なるものは本来存在しない。しいて言えば、
醜も死も、同じ一筆の絵の具で描かれていく価値である。つまり、“人間の
心”とは、本来そうしたものなのだろう。そして、さらに言えば、その“絵全
体”にこそ、価値があるのかもしれないのだが・・・
過去も現在も、距離的に遠いものも近いものもだが、みな同じその“一
枚の絵”の中に、等しく人間的に描かれていく。宇宙の地平面近くにあるク
ェーサーOQ172の光も、太陽からごく近い恒星系の光も、同じ“今”という
一枚の網膜の上に実現する。また、はるか少年の頃の思い出も、つい今
しがたの攻撃ヘリ大隊の到着も、何の区別も無しに“今”の脳裏に実現
し、現在を形成していく人間の原理。こうして一切世界を構成し、意味づけ
ていく、情報系としての人間の姿を、いったい何と把握したらいいのだろう
か・・・
ポケットに手を突っ込み、食堂の前を通ると、ふと浜田の声が耳に入っ
た。北里は、開け放されている戸口から、中を眺めた。明りの消された食
堂テーブルに、数人が居残っていた。いつもの、札付きの連中だった。食
堂の一番奥の方は、光々と明りが灯っている。そこでは、ラジオのボリュ
ームをしぼり、明日の仕込をやっていた。
北里は、浜田に関してはいつものように捨ておいた。そして、ぶらりと階
段を登った。あの、充実した気分は、まだ残っていた。上の方から、回収
計画部長が、厚いバインダーを抱えて下りてきた。北里は、黙って頭を下
げた。部長も、しぶい生真面目な顔で、頭を下げた。髪に白いものが幾筋
か混じり、それをてかてかに撫でつけていた。が、頬はげっそりと痩せ落
ち、何処から見ても疲れきっていた。ここの環境から、任務にいたる全て
が、あまりにも頽廃的だった。それが、神経質な計画部長には、よほどこ
たえているようだった。
北里は、すれちがって、数段登った所で呼び止められた。
「ああ・・・北里君、」
「はあ、」
「文化局の撤収は、何時になる予定かね?」
「我々としては、今日を含めて一週間と見込んでいますが、」
「なるほど。ふむ、一週間か・・・」部長は、コブシを口の上に当てた。「場合
によっては、少し早まるかもしれんな。そう思っていてくれたまえ」
「はい。歓迎しますよ。そういう話なら、」
「ハッハッ、じゃあ、お休み」
「部長も、早くどうぞ」
翌、四月十九日。
その朝、北里は、風のうなる音で目を覚ました。開け放された窓から、冷
たい風がいっぱいに吹込んでいた。窓の外を眺めると、空が暗くどんより
としていた。が、すでに夜が明けているのが分った。
「低気圧が来てますね」ほの暗い部屋の向こう側から、竜造寺が言った。
ベッドの上で、タバコの火が風に流れている。
「じきに降りだしそうだな」北里は言った。
「そう願いたいですね」
「うむ。今日の回収は、中止か・・・」
「北里さんは、今度の休暇は山へでも行くんですか?」
「いや、まだ決めてない」
「上野にいても、しょうがないでしょう」竜造寺のタバコの火が、強く光っ
た。また、赤い火の粉が風に流れた。
「まあ、そのうちに考えておくさ」北里は、ドサッ、とベッドの上で仰向けに
なった。そして、枕の上で、薄暗い天井を見上げた。窓から強く吹込んでく
る朝の風が、冷たく、気持ち良かった。北里は、そうやって、朝の風の音を
聞いていると、少年の頃の山小屋の朝を思い出した。
その山小屋では、朝目を覚ますと、風の音と川瀬の音が聞こえてきたも
のだった。そして、夜中に目を覚ました時は、その明け放してある窓から、
月と星と雑木林が見えた。今、北里は、そうした頃の月や星が懐かしかっ
た。その雑木林は、晩秋の頃になると、すっかり葉が枯れ落ちたのを、鮮
やかに覚えている。そして、その透けるような細い梢の中を、白い月が昇
った。が、夏には雑木の葉が鬱蒼と茂り、山ブドウやアケビのつるが厚く
からみあった。下薮には、ハシバミのよくなる茂みがあった。
北里は、その頃の事を思い浮べると、何時も心がなごんだ。そうした時
空の全てが、“真実の結晶”が経歴してきた姿である。そして、彼は今、荒
廃した主都東京の大地の上に経歴し、砲弾で射ち砕かれた半壊したホテ
ルの一室にあった。そして、あの少年の頃と同じように、朝の風の音に耳
を傾けていた。こうした、おどろくべき人の一生が経歴していく姿を、いった
い何と表現したらいいのだろう・・・
竜造寺は、あおむけになって雑誌を眺めていた。北里は、蒲団をはね返
し、ベッドから起上がった。ズボンをはき、灰色のカッターシャツを着、班長
を示す濃い褐色のネクタイを結んだ。それから、窓へ行き、外を眺めた。
外は、厚い雨雲が低くたれ込めていた。その下で、基地はまるで晩秋
のような風景だった。吹きつけてくる風が重く、湿気を含んでいた。風を受
けて立っていると、肌寒かった。北里は、自分の机の椅子に掛けてあるジ
ャケットを取り、ゆっくりと腕を通した。
それから北里は、机に向かって六時まで書類の整理をした。その後、竜
造寺と一緒に、朝食をとりに下へおりた。食堂はまだガランとしていた。東
側の窓から射す明りの中で、幾つかの回収班が、てんでに朝食をとってい
た。
北里は、カウンターの隅に置いてあるステンレスのミルク・タンクから、
熱いミルクコーヒーをカップに注いだ。回収本部の、不死鳥のエンブレム入
りのカップだ。それをグイと一息に飲み、カップを水の入ったバケツの中に
沈めた。
いつの間にか、竜造寺の姿が見えなくなった。それに、今日は回収は
中止と決め込んだらしく、文化局々員の姿は一人もなかった。外山の姿も
ない。
北里は、調査局の榊原と、窓辺でタバコを吹かしながら立ち話をした。
榊原は、大震災以前からの友人である。二本目のタバコに火を付けてい
ると、窓ガラスに、ピシッ、ピシッ、と雨が当たり出した。雨はたちまち、ザ
ーッ、と強く吹きつけた。遠くの方が、白い雨糸でかすんだ。
土嚢で幾つにも仕切られた駐車場には、百両近いトラック、ジープ、トレ
ーラーが並んでいる。それらが、あっという間に、すっかり濡れた。そして、
そんな中で、あわただしく紫煙をまき散らしながら、ジープやトラックがつぎ
つぎと発進していく。工場撤収部隊の車両だ。トレーラー、コンテナー車、
クレーン車等が、ワイパーをせわしく動かしながら、続々と周回道路へ出
ていく。
しばらくして、どこかのエリアでサイレンが鳴り出した。すると、続いて食
堂の中でも、はじけるようにサイレンが鳴った。基地警戒レーダーか、どこ
かの対砲レーダーに、長距離砲弾かミサイルが補足されたのだ。やが
て、二段目のサイレンの間隔も無く、ズーン、ズーン、と着弾の振動が伝
わってきた。外は、ますます風雨が強くなってきている。今日は、どうやら
春の嵐になる様相だった。
九時少し前に、北里はひとり部屋へ上がった。自分のベッドで、十一時
まで眠った。疲労を取るには、とにかく眠れる時に眠っておくのが一番だっ
た。
目を覚ました時、外は激しい嵐になっていた。ゴウゴウと風のうなる音
が聞こえる。窓から駐車場を見下ろすと、すでにかなりの車両が帰還して
きていた。
北里は、机の椅子を引き、そこに腰を落とした。両足を、ドッカリと机の
上に投出した。そうやって北里は、ボンヤリと部屋の一点を見ていた。そし
て、自分自身という概念と、部屋という概念が一つに重なり、そこに静かな
“時”が満ちていくのを感じていた。
やがて、北里は、心の中でつぶやいた。
・・・こうやって、今も、刻一刻と、それぞれの事物が互いにからみあいな
がら、一つの壮大な歴史が刻印されていく・・・この流れを、神による“人類
救済史ストーリイ”ととるべきか・・・あるいは、何の意味も含まない、“空な
る相”ととるべきか・・・キリスト教的な直線的時間概念と、仏教的な平面的
時間概念の対比になるが・・・
・・・まるで、綿のように絡み合った、未来永劫へ流れる因果律の糸・・・
自ら、その意味を知らずに生み出されてくる、波動関数の世界・・・その多
世界的解釈、パラレル・ワールド(平行的世界)の相・・・そして、ライプニッツの
“最適性”による、選択的世界の摘出・・・その世界の、局所銀河群、銀河
団、超銀河集団への階層的構造・・・が、いずれにせよ、この宇宙の主体
性は、今まさにこの“自我”の上にある・・・これもまた、まぎれもない真実
なのだ・・・
ドアにノックがあった。
「どうぞ!」北里は、机から足を下ろし、ドアの方を眺めた。
菊村老人が入ってきた。午前中に散髪したらしく、髪をきちんと刈り揃
え、つるりとした顔をしていた。
「こりゃあ、ひどい荒れになりましたなあ、」
「ああ、」北里は、テーブルの上のタバコの箱を引き寄せ、一本抜出した。
「手紙を預ってきました」
「ああ。みんなはどうしてます?」北里は、手紙を受け取り、ライターでタバ
コに火をつけた。
「浜田さんが、ポーカーでだいぶやられてますな。添島さんは、まわりのパ
トロールに出ました」
「外山はどうしてます?」
「外山班長は、多分、PX(Post Exchange)でしょう。最前線で、かなり
動きがあるようでしてな、」
「サービス・エリアが、一番情報が早いか、」
「でしょうな、」菊村老人は、自分で納得してうなずいた。
北里は、菊村老人から渡された手紙を眺めた。それから、裏をひっくり
返してみた。“ニシガミ・カオリ”と、カタカナで打ち込まれてある。上野の国
連事務局の中にある、WHO(世界保健機構)で働いている女だ。北里
は、封を切り、プリントアウトされた、真新しい便箋を取り出した。
手紙は、かなり検閲を意識して書かれてあった。内容は、最近の上野
の町の様子や、仕事のことや、髪を切ろうかと考えていることや、休暇の
事などだった。そして、そうした中にも、彼の身をしきりに案じているのが
感じられた。が、北里は、そうした女の匂や優しさは、無視した。そうした
ものは、やりきれなかった。それから、さらに読み進んでいくと、彼女がす
でにひとりの人間として、孤独に絶えきれなくなっている様子が分った。そ
れが、どうやらこの手紙の真の意味だと、北里は悟った。
あの、しっかり者が、いったいどうしたのだろう、と北里は思った。が、と
にかく、上野に帰ったら、優しくしようと思った。彼女には、それが必要だっ
た。いずれにしても、あと数日で、回収本部東部総局へ帰還になる。
北里は、便箋を封筒に戻した。そして、その封筒の角に、ライターで火
をつけた。火が大きくなると、灰皿の中に置いた。北里は、それがすっかり
燃え尽きるまで、その情報というものを含んだ赤い素粒子の流れを、ジッ
と見つめていた。情報が人を動かし、社会を動かし、この戦争を動かして
いる。北里は、情報の根源にある価値、価値の根源である意味を見つめ
ながら、ふと菊村老人の方に顔を向けた。
「我々も、PXへ行ってみますか?」
「そうですな、」菊村老人の顔に、微笑が広がった。「久しぶりに、向こうで
昼飯でも食べますかな」
「じゃあ、特上の寿司といこうか。チケットも、もう必要無くなる」
「いいですな。ハッハッハッハッハッ、」菊村老人は、わけもなく笑った。
北里もつられて笑いながら、自動拳銃の付いた太い布バンドを腰にま
わした。それを、回収本部のエンブレム入りのバックルで、カチ、と結ん
だ。それから、ズシッと重い自動拳銃を引き抜き、弾倉を確かめた。そし
て、弾倉をまたグリップにたたき込み、拳銃を鞘め、パチッ、と留めた。班
長は、治安維持のために、基地の中でも自動拳銃の携行が義務付けられ
ているのだ。
北里は、それから防水シガレット・ケースにタバコを詰め、ボールペンと
一緒に胸のポケットに差し込んだ。
「さて、行きますかな、」菊村老人が、上機嫌で言った。
「うむ、」北里は、腕時計を見た。十一時四十分を刻んでいた。
窓に、相変わらず、ザッ、ザッ、と激しく雨が打ちつけている。フィールド
の方では、パトロール隊のジープが、雨しぶきの中をヘッドライトをつけて
走っていた。
四月二十二日。雨は、今日で四日続いている。
この日、午後二時十分。文化局第三十二回収班は、第三前進基地にお
ける全任務を完了した。そして最後の回収物資を、第一フィールド管理隊
詰所で、トラックごと輸送隊に移管した。
その引き渡しが終わると、北里はずぶ濡れの仲間を基地巡回バスに乗
せ、先に宿舎へ帰した。北里は、これまで一緒に仕事をしてきた輸送班の
一人一人に対し、ねぎらいの言葉をかけ、握手を交わした。やがてバスが
動き出すと、北里は雨の中で手を振った。
それから北里は、帰還の事務手続きを取るために、また詰所の中に入
った。申請を済ませると、ジープ装備の暗号通信回路や、識別信号関係
の電子部品の取りはずしを始めた。回収本部の技術部員が手伝ってくれ
た。自衛隊の下士官が一人、彼等に一緒に立合った。こうした電子部品
は、全てブラック・ボックス化されていた。つまり、破壊することは出来て
も、分解したり、中を調べたりすることは不可能になっている。部品は、一
つ一つ電子的に照合され、慎重に収納された。それが終わると、北里は
無線機の上で何枚かの書類にサインし、コード番号を記入した。
北里は、また詰所の中に戻った。そして、ストーブの前で体を暖めなが
ら、撤収許可の書類が回ってくるのを待った。紙コップのコーヒーを飲み、
タバコを吹かし、窓の外の第一フィールドの風景を眺めた。全身ぐっしょり
に濡れていて、寒かった。が、それはべつに彼一人ではなかった。フィー
ルドに溢れている、全自衛隊員がそうだった。また、今も交戦中の、全て
の部隊がそうだった。
正門あたりでは、撤退してくる部隊と、出撃していく部隊が、降りしきる
雨の中で、あわただしく噛み合っている。野戦テントが張られ、迷彩色の
バスが並び、ジープが何台も突っ込んでいる。ゲート内に流れ込んできた
トラックからは、軽機関銃や小銃や無反動砲を抱いた自衛隊員が、続々と
飛び降りている。シュラフに包まれた負傷者が降ろされ、同じ手で81ミリ
迫撃砲が降ろされる。衛生隊、警務隊、基地管理隊が活発に動き、第一
フィールドは基地開設以来のごった返しようだった。南東部の方、かって
江東、江戸川、浦安と呼ばれていた方面から、大規模な撤退が始まって
いるのだ。
戦車戦、ゲリラ掃討戦での苦戦が大きかったといわれる。また、敵側
の、予想を上回る対空火力の展開、新型対ヘリ弾の実践配備、それに空
中機動戦に不利な悪天候が重なったともいわれる。むろん、その他にも、
圧倒された戦術的要因はさまざまにあった。しかし、結果として、レーザ
ー・ビームのように集中してきた、敵戦車部隊の圧力を阻止できなかった
ことにある。これが結果であり、事実だった。むろん、研究はしつくしてきた
のだ。コンピューターによるシミュレーション、全包囲部隊の連動、補給、
火力の集中量、空中機動と超低空域の戦略・・・が、その上で、まさにして
やられたのだった。
その問題の付近は、もともと国道十四号ギャップとしてマークされてい
た。が、自衛隊の布陣は、圧倒的なものだったのだ。しかし、かってベトナ
ム戦争で、ミスター・コンピューターと言われたマクナマラ国防長官が、あ
の熱帯雨林とゲリラに敗退している。あれほどの、圧倒的な兵力と物資を
投入してだ。が、結局、今回の作戦でも、そうした過去の幾多の劇的な逆
転を、もう一度証明して見せたわけだった。しかし、考えてみれば、闘争や
戦争の歴史は、むしろこうした意外性や逆転のドラマそのものである。そし
て、その意外性も、つきつめていけば、意外でも何でもないことを教訓とし
てきた。
ところで、この劣性については、もうひとつ最もらしい別な見方があっ
た。それは、この敗退の最大の原因は、圧倒的な兵力で包囲している自
衛隊側の、戦略的な甘さだという意見である。そして、その自衛隊の戦略
的な甘さは、西側自由主義陣営全体の甘さだという。言い換えれば、豊な
側の国々の、世界大戦勃発回避への分別であり、潜在的譲歩であるとい
う。しかし、これでいいというわけではむろんなかった。これは、幾度となく
民族開放闘争の名のもとにくり返されてきた、敗戦のパターンだからであ
る。また、このタガの緩みこそが、戦争という巨大な組織的行為において
は、最も危険なものだからである。そして、これもまた有史以来の数々の
戦史が、劇的に証明してきている事柄なのだ。
しかし、それはそれとして、いずれ雨が上がりしだい、本格的な爆撃が
再開されるはずである。さらにまた、アソルト・ブレーカー・システムが使わ
れるとか、レーザー・ビーム・ライディングのカッパーヘッド誘導砲弾が大量
に投入されるとか、新兵器投入の話もしきりだった。が、こうした勇ましい
話も、目前の敗戦の風景の中では、どこか白々しかった。いづれにせよ、
戦争は本来ハングリーなものであるはずである。テーブルの上にメニュー
を並べて見せるなどは、負け戦における、オオカミの遠吠えでしかなかっ
た。
北里は、ストーブの前で体をあぶりながら、西住大尉とそんなことを話し
合っていた。濡れているジャケットと、ズボンの前から、もうもうと湯気が立
ち上がっている。
「ほう、」と、西住大尉は、正門の方を眺めながら、ボンヤリと言った。「あ
れは、30ミリ対空機関砲だな」
「どうやら、捕獲品のようですね」北里も、今ゲートを入ってきた、六銃身の
自走対空機関砲を眺めながら言った。ZSU23−4にかわる、新型のソ連
製対空機関砲だ。
「一両捕獲したという話は聞いていたが・・・」西住大尉は、砲弾の破片で
負傷している左の脇腹を、ゆっくりとさすりながら言った。
その、無傷で捕獲した自走対空機関砲の後から、74式戦車が二両入
ってきた。二両とも、回転砲塔のまわりに数人の兵がよじ登り、雨に打た
れていた。
そのゲートの向こう、大雑把に土嚢で仕切られているエリアには、20榴
(203ミリ自走榴弾砲)、多連装ロケット・ランチャー、戦車架橋、回収され
てきた各種戦車等が、雨の中でゴミの山のように折り重なって見える。し
かし、このゴミの山は、また何百億円というカネの山でもあった。今は故障
しているが、かってはどの車両も、すべて数億円単位のものである。これ
が、戦闘機や新型対戦車ヘリともなれば、一機数十億円から百億円以上
にはねあがる。そして、こうしたものを、大量に、いともあっさりと消耗して
いくのが、戦争経済である。戦争はまさに、人間をも含めたあらゆる価値
を、雑然とかき回してしまっているのだ。
・・・それにしても、人間にとって、価値とはいったい何だろうか・・・その
前にはまず、人間を定義しなければならないのだが、しかし、人間を取り
巻いている価値という抽象もまた、分らないしろものだ・・・戦争、金銭、兵
器、食料、友情・・・そうした意味の流れ、価値の流れ、そして主体性の流
れ・・・
・・・主体性を取り巻くように流れる価値とは、情報なのか、物質なのか、
感情なのか、あるいは“命”というものの本能に分類されるようなものなの
だろうか・・・つまり、時間が運動や変化とは完全に切り放しては認識され
得ないように、価値というものもまた、その実態は極めて不透明なものな
のだろうか・・・むろん、すべて、この時空間を経歴している、一枚の“人間
原理”の絵でしかないわけだが・・・
「失敬するよ」西住大尉が言った。そしてカウンターを回り、奥の方へ入っ
ていった。
北里は、もうもうと湯気の立つ太腿をこすりながら、今度は背中をあぶっ
た。そうやって、降りしきる雨の真実と、雨と寒さの中でごった返している
戦争の真実を、一枚の“絵”の中に広がる夢として眺めていた。
敗退、恐怖、仲間、味方、安心感、そして戦争という重圧・・・人間の抱
えるそうした真理が、軍事的単純さで、的確に処理されていく姿。考えて
みれば、これは非情な場景だった。また、それを眺めている彼の心も、非
情なものと言えた。北里は、自分がいつしか、こうした環境にとっぷりとつ
かっているのを感じた。軍事機構のもつ、斬新と能率と非情、命令と責任
の厳正、兵たちの人間としての単純さ。そうしたものが、北里は、わけもな
く好きになっていた。また、そうした一方で、複雑な感情の動物としての人
間は、何故か手にもてあまし始めていた。
「北里班長!」フロントが呼んだ。
「できたのか?」
「はい。ワッペンの方が品切れだったもので、時間がかかりました」
北里は、白い湯気の上がる服を両手でたたきながら、カウンターへ歩い
た。北里は、コンピューターからプリントアウトされた書類を、自分の身分
証明カードと一緒に受け取った。それから、封筒に入れられた、五組の記
念メダルとワッペンをもらった。第三前進基地で勤務していた記念である。
メダルの裏には、日付と、それぞれの所属、そして名前が打ち込まれてあ
った。
「御苦労様でした」フロントの小尉が、挙手を切った。
「ありがとう」北里は、挙手を返しながら言った。
「それじゃあ、気をつけて、北里君」脇の方から、回収計画部長が言った。
計画部長は、今日も髪をてかてかに撫でつけていた。
「お世話になりました」
他に、五、六人の者が、北里に別れを言った。北里はそれに答え、それ
から西住大尉の姿を捜した。奥のファクシミリの所にいた。北里に気ずき、
挙手を投げてよこした。
管理隊詰所を出ると、北里はジープの運転席の方に乗込んだ。深々と
シートに腰を沈めた。全身が、ぐったりとしていた。膝が、ガクガクだった。
北里は、またシガレット・ケースを取り出し、タバコを一本つまんで口にくわ
えた。マッチをすって火をつけた。そして、ゆっくりと煙を吐き出しながら、た
め息をついた。
上野へ帰還したら、タバコは止めるつもりだった。そして、座禅を始める
つもりだ。結局、いずれその道に、踏込んで行かなければならないのだ。
人間の真実の道、そのためにこそこの世に生を受けた、永劫の“命”の修
業の道である。
北里は、タバコをはさんだ重い手を動かし、ハンドルの上に回収日誌を
開いた。日誌を濡らさないように、袖をまくりあげた。そしてまず、基地帰還
の時間と、回収物資移管の時間、封緘のナンバーを記入した。
任務完遂・・・
事故ナシ・・・
北里は、すでに書込んである箇所を読み拾いながら、回収のだいたい
の経過、回収物資の概要等を書込んでいった。また、現在進行中の撤退
についても、自分の見聞した状況を書き添えた。いずれ後の時代に、この
動乱を語る資料になるものだ。
そこまで書込んだ時、ザーッ、とまた雨の音が激しくなった。北里は腕
時計を見た。それから、ジープのエンジンをかけた。ワイパーを動かし、ヒ
ーターを回した。フィールドの北側の方に、すさまじい爆音をたたきつけな
がら、タンディム・ローターの重輸送ヘリが降下してくるのが見えた。負傷
者を、直接後方へ送り込んでいるヘリだ。北里は、ボンヤリとそれを眺めな
がら、ゾクリと体を震わせた。ファンから吐き出されてくる、ヒーターの風が
暖かかった。そう思っていると、ゲートの外の第二十四対空陣地の方か
ら、モウモウと白煙が湧き上がるのが見えた。白煙の頂点に、白い迎撃ミ
サイルが上昇した。それは斜に、祈るように、厚い雨雲の中に吸込まれて
いった。 北里は、タバコを灰皿に置き、ボールペンを取り直した。そして、
最後のまとめを書いた。
文化局第三十二回収班は、今日、C−75地区の回
収をもって、全任務を完了とする。今、この焦土と洪水
の大地に、二度目の春が訪れ、二度目の戦火 が拡
大しつつある・・・
北里は、回収日誌を閉じた。硬表紙の上にかけてあるヒモを、かたく結
んだ。それをビニール・ケースに入れ、ダッシュボードの中に放り込んだ。
北里は、ブレーキを落とし、ギヤを入れ、ゆっくりとジープを発進させた。
ごった返している車両をさけ、雨の中で動いている将校や兵をさけ、ソロソ
ロと周回道路をまわった。フィールドの一番奥手に、朝にはなかった巨大
な穴があった。大型トレーラーが、すっぽりと落込むような穴だ。穴の縁
に、オレンジ色の旗竿が立ててあり、中に泥水が流れ込んでいた。
その第一フィールドを離れると、基地はいつもの風景とあまり変りなかっ
た。ただ、車両の数が多く、この長雨で濡れ、黒ずんでいた。回収本部輸
送隊のエリアでは、何台もの十トン・フォークリフトが動き、コンテナーをトラ
ックに積み込んでいるのが見えた。
北里は、タバコを吹かしながら、片手でジープのハンドルを切った。そし
て、この基地も見納めだなと思った。あと、彼に残された任務といえば、四
人の仲間を、無事に上野まで引き連れて行くということだけだった。第三
十二回収班々長としての任務も、それで完了するわけである。
北里は、宿舎の正面玄関にジープを乗りつけた。そこの張り出した屋根
の下に、荷物の山があった。五人分の標準個人装備と、アルミニウムのト
ランクが二個、あとは小さなダンボール箱が二、三個あった。菊村老人
が、そのそばで二人の男と立ち話をしながら、タバコを吹かしていた。
「ごくろうさん」北里は、ヘルメットを頭に乗せながら、ジープをおりた。「み
んなは?」
「さて、食堂ですかな、」
北里は、宿舎の中に入った。シンとしていた。濡れた靴の跡が、ずっと
奥まで続いていた。食堂を覗いてみた。浜田と添島がいた。差し向かい
で、ミルクコーヒーを飲んでいる。二人とも、風呂に入ってさっぱりとしてい
た。
竜造寺の姿は、食堂の中には見当たらなかった。北里は、浜田と添島
に、ジープを整備し、ガソリンを規定量入れておくように言いつけた。それ
から彼は、三階へかけ上がった。部屋の中は、ひどく殺風景になってい
た。彼が朝用意しておいた着替え一式だけが、ベッドの上にそのまま放り
投げてある。万事、竜造寺が片ずけたのだ。
北里は、その着替えの衣服を片手で丸め、わしずかみにした。そして、
もう一度部屋の中を見回した。何の感慨もなかった。しかし、真実の結晶
世界としての輝きは感じられた。北里は、それで満足だった。
共同浴場は、まだすいていた。湯気の中に、二、三人の人影が見える
だけだった。北里は、壁に掛けてある時計を眺めながら、広々とした湯槽
の中で、冷えきった体を温めた。そうやっていると、いい気持ちだった。風
呂というヤツは、とにかく悪くはなかった。それから、上がって乾いた衣服
を身につけると、さっぱりとした。
食堂を覗くと、今度は誰もいなかった。シンとしていて、雨が窓ガラスを
たたいていた。壁の古い鳩時計が、二時四十分を指している。上野へ向
かう最終輸送部隊の出発は、四時である。が、この混乱した状況下で、そ
れが早まるのは確実だった。
北里は、一人食堂の中に立っていた。そして、静けさと、戦時下の張り
つめたような緊張感を眺めていた。師団規模の撤退であり、敗軍の緊張
感が漂っていた。北里は、ヤカンから冷めた茶を注ぎ、サンドイッチを腹に
つめた。雨が、ザーッ、と時おり強く窓に吹きつけてくる。
菊村老人が、食堂を覗きに来た。北里は、壁の鳩時計に目をやり、残っ
たサンドイッチをつかんで立ち上がった。それから、口の中にほおばってい
るサンドイッチを、茶で胃に流し込んだ。
「お世話になりました」北里は、サンドイッチを出してくれた給仕頭に言い、
挙手を切った。
「お元気で」給仕頭が、厨房の中で言った。
廊下へ出ると、菊村老人が言った。
「雨は、上がりそうもないですな」
「期待してないさ」
七、八人が、玄関まで見送りに出ていた。彼等は、それぞれと握手を交
わし、今後の無事を誓い合った。それからジープに乗込み、輸送隊の出発
ゲートである、北面の第五フィールドに向かった。




出発は、定刻より三十分早まった。40ミリ擲弾機関砲を搭載した、装甲
歩兵戦闘車が先頭にたった。それから、自走連装無反動砲、自走迫撃砲
等が続き、バーの上がった第五ゲートを出ていった。その後に、数十両に
及ぶ非戦闘車両が、豪音をたてて流れ始めた。回収物資を満載した大型
トラックや、コンテナー運搬車がほとんどだった。そして、それらに挟まっ
て、定期連絡バスや、燃料運搬車が出た。文化局第三十二回収班のジー
プは、縦隊のほぼ真ん中あたりに入った。
北門を出て十分ほどで、155ミリ・カノン砲陣地に達した。そこで、第二
監視網ラインを抜けた。するとまもなく、C型ガンシップが三機、斜に頭上を
越えて進出した。C型は、左右のウエポン・ラックに、二本づつのロケット
弾・ポッドを吊り下げている。武装は、その都合七十六発のロケット弾と、
7.62ミリ弾・ミニバルカン砲、そして40ミリ擲弾機関砲を搭載してい
る。40ミリ擲弾機関砲は、何割かが徹甲弾になっている。
(徹甲弾: 堅固な目標や装甲を撃ち抜くための砲弾。ニッケル鉱やクロム鉱
などの特殊鋼で造る。)
さらに数分後、ぶっ潰れた橋を踏み越えた時、卵型の小型ヘリが一機、
雨空の中へかすんでいった。豆粒のようだが、勇ましく、左右のウエポン・
ラックに、スティンガー対空ミサイルか、TOW対戦車ミサイルを、四発装着
していた。輸送部隊に、これほどの護衛がついたのは初めてだった。戦線
が、よほど流動化していると考えるべきだろう。
しかし、コンボイは、味方部隊とも遭遇しなかった。ただ、荒れ果てた主
都の大地を、北へ巡航速度で走り続けた。輸送回廊の風景は、この連日
の雨の中で、いっそう寂れきって見えた。
「北里さん、」添島が口を開いた。「歌をうたっていいですか?」
「よし。楽しく行くか、」
添島が、今前線ではやっている、“戦士の歌”をソロで歌った。それか
ら、同じ歌の二番と三番を、添島と竜造寺がデュエットでうたった。その
後、菊村老人が、古い軍歌をうたった。
北里は、“故郷の廃家”をうたった。竜造寺が、その歌の題は、“廃墟の
故郷”だと言い張った。が、やはり、“故郷の廃家”だということで、他のみ
んなの意見が落ち着いた。
その後、浜田がハーモニかを取り出して、片手でハンドルを握りながら、
“おぼろ月夜”を吹いた。彼等は、みんなでそれを合唱した。いい詩だっ
た。それから、“赤トンボ”と、“夕やけこやけ”と、“いつか来た道”を合唱し
た。どれも、古い唱歌だった。誰もが、そうした子供時代や、古い時代が
懐かしかった。しかし、もう二度とかえってくることのない、失われた世界
だった。むろんそれが、経歴し熟成していく、この世界の姿だった。
「浜田さん、あれを吹いて下さい。歌いますから」添島が、無線機の上で歌
詞の本をめくりながら言った。
「何だい?」
「“銀色の道”、」
「よしきた」
北里は、浜田のハーモニカと、みんなの合唱を聞きながら、指で回収地
図の上の輸送回廊をたどった。菊村老人が、みんなにコーヒーの缶詰を
配った。北里は、その缶の口を切ってコーヒーを飲みながら、残り物のサ
ンドイッチを腹につめた。サンドイッチを食べ終わると、北里はダッシュボー
ドを開き、一番下から数冊の小冊子を引きぬいた。基地管理隊広報部が、
毎月一回刊行しているものだ。第三前進基地周辺や、この管区の最前線
の最も新しい状況が、かなり詳しく掲載されていた。むろん、機密の事項
は全てカットしてある。
最新の四月一日刊行のもに、初めて、敵聖域内の精鋭三個師団につ
いての考察がある。この公開されている資料を見る限りでは、その三個師
団は編成こそ違うが、火力・機動力で、ソ連地上軍の自動車化狙撃師団
に匹敵するものだった。圧倒的な装甲化に加え、対空戦闘と超低空域戦
闘が重視され、精強な兵が選抜的に投入されていると推定している。ま
さに、実験兵団の観があった。現在、問題の国道十四号ギャップに出現し
ている部隊は、この“重装甲ファランクス”と呼ばれている師団ではないか
と言われている。
小冊子はまた、革命軍聖域についても、一番新しい資料を示している。
兵力の戦略的展開を示した地図だが、それによると革命軍聖域の版図
は、ほぼ茨城県全土を含み、千葉県北西部、栃木県南東部に及んでい
る。また、その軍事組織は、事実上プロレタリア同盟が掌握したと判断を
下している。これは、“赤軍”への実質的な移行を意味した。自衛隊の“日
本国防軍”への改変の流れと、好対称を示している。
北里は窓を開け、ジープの中に新鮮な空気を入れた。雨の中で、夕暮
れがせまっていた。道端の緑の雑草が、とっぷりと水に浸かっている。そ
れらが所々で、ちょんちょんと水の中から頭を出していた。
「戦闘準備の要請です!」添島が、緊張した声で言った。
「よし、準備だ!」北里は、タバコをもみつぶした。
回収本部各班においては、武器の使用は、自己防衛目的に限られてい
た。また、それは、班長の判断と責任において許可されていた。
北里は、シートの横にある自分の短機関銃を取り外し、安全装置を確か
め、膝の上に横たえた。それから、予備挿弾子を二本、上着のポケットの
中に落とした。ポケットが、ずっしりと重くなった。後ろの座席で、竜造寺と
添島も、それぞれ自分の銃を準備した。
短機関銃という銃は、いわゆる軽機関銃や重機関銃とは、まるで違うも
のだ。使用する弾丸も、9ミリ・パラベラム弾であり、軍用自動拳銃のもの
と供用である。また、歴史的にもこの銃は、もともとが戦車兵や偵察兵の
護身用のものだった。しかし、構造が単純でプレス加工がきき、安価で大
量生産向きなこともあり、この動乱勃発と同時に生産ラインが動き出した
と言われる。射程と命中制度ではやや難点はあるものの、接近した市街
戦や、森林戦には適した銃である。
北里は、その短機関銃を膝の上に置いて、片足を踏ん張るようにし、双
眼鏡を使った。この雨の中で、ゲリラの潜みそうな所を、注意深く点検して
いった。やがて、沿道に、一群のくすんだビルが近づいてきた。北里は、
双眼鏡を下ろし、短機関銃をかまえた。そして、油断なく、銃口で目標を捜
していった。
所々に、遺棄されたおびただしい量の車両がかためられてあった。ブル
ドーザで押し潰され、赤錆が浮き、黒々と厚い埃をかぶっていた。これら
も、いずれはスクラップとして回収されていくはずである。今の日本には、
無駄にしていい資源は何もないのだ。国力が衰え、経済が失速してしまっ
ては、全てが暗澹たるものになってしまう。そしてそれは、日本だけにとど
まる問題ではなかった。おそらく、そのシワ寄せは、世界の最も弱い部分
に、飢餓として押し寄せて行くはずである。
「明るいうちに、ポイント38を越えたいですね」竜造寺が言った。
「F−38か、」浜田が、のめり込むように、ハンドルに片腕をかけながら言
った。それから、北里の方を向いた。「あのあたりはどうですか?」
「侵入していると、考えるべきだろう。しかし、トラップ・ラインのセンサーを、
探知されずに越えるのは難しい」
今度は、輸送回廊の両側に、黒く高いビルが林立してきた。雨空も、い
ちだんと暗くなった。頭上で、時々ヘリの爆音がした。が、ヘリの機影は見
えなかった。遠くのビルの間に、所々陥落した高架の主都高速道路が見
えた。が、そこも、かっての面影はなく、この都市の敗北の象徴のようだっ
た。
ビルの間をしばらく進むと、輸送部隊は新しくできた洪水地帯に突き当
たった。そこから、迂回路がとられた。が、迂回路も水が浸していた。どん
どん増水しているのだ。輸送部隊は、浅い泥水の中を進んだ。泥水の中
に、オレンジ色の旗竿が点々と立っていた。防弾チョッキを着た重武装の
拠点防衛隊が、ずぶ濡れで輸送隊の誘導に当たっていた。が、それでも、
一面水の中というのは、いい気持ちのものではなかった。そう思っている
と、広い水の上に、ぽっかりとコンクリートの橋のらんかんが見えた。どう
やら、そこに川があるようだった。
「このクソいまいましい洪水は、この川がネックだぜ!」浜田が、ハンドル
をたたいて言った。
「川に当たってもしょうがないさ」竜造寺が、後ろから茶化すように言った。
「まあな、」浜田は、首を振った。「しかし、何でこんな所に川を堀やがった
のかな」
ジープが、ちょうど橋のらんかんを抜けようとした時、大地が水面ごと、
グラリ、グラリ、と大きく揺れ出した。右手の方のビルの間で、ゴゴゴッ、ゴ
ゴゴッ、とコンクリートの崩れ落ちる音がした。地震は、すぐにおさまった。
が、水面の大きな揺れ戻しが続いた。ビルの間で、ザプン、ザプン、と水
音がしている。
大震災以来、いまだに続いている群発地震だ。が、この震源は、東京
の直下ではなく、日本海溝の太平洋プレートの沈下だと言われている。い
ずれにしろ、地殻の深い所でどの様な異変が連鎖したかは、地表では知
るよしもなかった。しかも、世界に誇った地震予知のシステムも、この動乱
で崩壊してしまい、一部の学者が細々と続けているのみである。
「何か見えるか?」北里は、浜田に言った。
「いや、」浜田は、小さく首を振った。
「どんどん崩れていくな、」
「ああ、」
北里は、暗いビルの林立を眺めながら、心の中でつぶやいた。
・・・この大地の上の人間の思い出が、ひとつひとつ消滅していく・・・こ
の時空に析出した、真実の結晶が・・・意味あるものが、いっとき静かに波
動し、その存在を誇示し、そして謎は謎を残したまま、再び謎の深淵の世
界へ沈んでいく姿・・・
ジープは、ザーザーと、揺れ動く暗い水面を推し進んだ。鼻の先に、ぐ
んぐんと山のような水面がうねっていく。こうやって、一切世界の存在が、
刻々と未来へ押し上げられていくのだ。
・・・何故、こんな世界があるのだろうか・・・北里は、息を押し殺し、鋭く
心の中でつぶやいた。
・・・あるよりは、むしろ無い方が自然だ・・・しかし、あるからには、そこ
に何らかの強い意志が存在するのではあるまいか・・・
北里は、ジープに揺られながら、暗い水面のうねりをボンヤリと見つめて
いた。彼は、これから一週間の休暇の間、こうした個人的に山積した問題
を、じっくりと考えられるのが嬉しかった。人間としての、ささやかな、ほの
ぼのとした、確かな喜びである。
対戦車ヘリが二機、暗くなりかけた雨空の中を、東の方へ横切った。そ
の機影が雨に霞んでしばらくすると、東の空に赤い光が炸裂した。さら
に、鋭い飛跡がはしるのが見えた。20ミリ・バルカン砲の発射らしかった。
高エネルギー弾を、超高密度で発射した飛跡だ。それが、薄暗い空の中
で、さらに、バッ、バッ、と光った。
が、輸送部隊は、同じ速度で前進を続けた。やがて、すっかり暗くなった
ビルの間から、泊撃砲弾の曲射飛跡が幾筋も上がるのが見えた。輸送回
廊の拠点が、ゲリラの攻撃にさらされているのだ。ゲリラ側の総攻撃が始
まっているようだった。
さらに進んでいくと、夕暮れの中で、鉄骨で組んだ大きな橋がボンヤリ
と見えてきた。輸送部隊は、その橋の方へ向かって進んでいた。が、やが
て、橋のすぐ近くで左に折れた。そこは、川の堤防の下の道路だった。そ
こからは、車両はライトを消し、自衛隊員の合図で、とぎれとぎれに進ん
だ。
ピィィィーッ、ピィィィーッ、と空気を切るロケット弾の音が聞こえてきた。
が、飛跡は見えなかった。道路の左側の方は、工場地帯だった。その辺り
から、味方の迫撃砲弾の飛跡が上がっている。そして、そのポイントへ、
正確に敵の迫撃砲弾が吸い込まれて行くのも見えた。かなり低い弾道だ
が、対砲レーダーで弾道放物線を補足し、正確に発射地点を割出してい
るようだ。そしてそれが、バーン、ドーン、と炸裂し、サーッ、と一帯の工場
に、照明弾のような光と影を映した。ガーン、ガララーン、ゴーン、と鉄骨材
がぶつかり合う音が響いた。
自衛隊員の誘導で、順次トラックが進んで行った。が、こんな所でジッと
止っているというのは、いい気持ちのものではなかった。
するとまた、シュルッ、シュルッ、シュルッ、シュルッ、と空気をこすって、
迫撃砲弾が突進してきた。神経をすり減らすようなその音が、極限まで広
がったかと思うと、フッ、と頭上を越えた。体を固くし、歯をくいしばっている
と、ドシーン、と炸裂した。ビルの間が白熱し、サーッ、と稲妻のような光
が、目の下に溢れた。それがグングン広がってきたかと思うと、やがて、
ザーッ、と土砂が降ってきた。至近弾だった。さらに、もう一発近くに来た。
また、一発が、鉄骨の橋に命中した。それは、ガシーン、と派手な音を立
てて、大きな火花を散らした。ソ連製の、82ミリ迫撃砲弾だ。
ライトを落とした輸送車両が、つぎつぎに進んでいく。ようやく彼等のジ
ープが一番前に出た。そこでは、土手から下の方に、ジープのヘッドライト
が向けられていた。その明りの中で、タバコをくわえた自衛隊員が、ずぶ
濡れで手旗を降っていた。すでに、あたりがすっかり夕闇に包まれている
のが分った。やがて、迫撃砲弾の炸裂する明りで、前の方に定期バスが
止っているのが見えた。担架が幾つも運び込まれている。バスは、文化局
のジープの前で、再び輸送部隊の列に加わった。ようやくその修羅場を過
ぎると、彼等は周囲のかすかな明りを頼りに、暗い道をノロノロと前進し
た。一度、道路が堤防の上に出た時、広々とした水面が一望できた。この
あたりは、川は対岸で氾濫している。しかも、この長雨でさらに増水してい
る。その、雨にけむる灰色の湖面に、閃光が映り、硝煙が霧のように落
ち、機関銃弾や小銃弾が水平に流れている。その眺望を最後に、道路は
しだいに川から離れた。すると、やがて前の方から、順次ヘッドライトが灯
った。
夜空に照明弾が上がり始めたのは、ポイントF−38の検問を通過して
からだった。高い夜空の一方が、にわかにボーッと明るくなった。その明り
の中で、降りしきる雨が白く映った。光源の方は、ゆっくりと東の方へそれ
て沈んでいく。この照明弾は、上野の回収本部防衛隊が、105ミリ榴弾砲
で打ち上げているものだ。すでに、このあたりの輸送回廊は、回収本部防
衛隊が布陣しているという証である。
輸送部隊は、つぎつぎに上がる照明弾を右舷前方に見ながら、巡航速
度で走った。やがて、ちいさな村を幾つか抜けた。上野周辺で操業を再開
している、中小工場群である。住民たちが、村のゲートに明りを灯し、輸送
部隊の通過を歓迎した。
最終輸送部隊が、上野の町の絶対防衛圏に入ったのは、すでに六時
半近かった。その検問を通過すると、夜空の中に、ボンヤリと赤い航空識
別灯が見えた。照明弾は、すでにはるか後方へ去っている。そして、かわ
りに強力な探照灯の光が、雨の闇を切り裂き、サーッ、と流れてきた。北
里は、雨に濡れそぼった輸送部隊が、一瞬その光で現実の世界に浮び
上がり、再び闇の世界に沈んでいく様を、ボンヤリと眺めた。
ところで、この動乱の始まる前までは、北里はこの上野の街に住む、素
朴な画家の卵だった。その貧困と情熱の時代こそ、楽しい時間だった。
今、上野に帰還してきて、あらためてそうした時代の平和が、如何に偉大
なものであったかが分る。当時は、社会のあらゆるものが保護され、気づ
われていた。また、どんな人々であれ、それぞれに希望をもって生きてい
た。悪いこと、インチキなこと、腹のたつこと、そうしたものさえ、どこか愉
快だった。必然的に不平等である人間社会の功罪が、そこには如実にあ
った。また、そうした不平等の自由な揺れが、社会に活気を与え、経済を
発展させ、文化や芸術を生み出してきたのである。勝者と敗者があり、富
者と貧者があり、賢者と愚者があり、そこにさまざまな価値の世界が形成
され、人々と同じ数だけのストーリイがあった。誰のためでもない、彼等自
身が、彼等自身のために描くストーリイがあった。また、人間原理の底に、
オリのように沈んでいく邪な心が、そのストーリイと社会に、影と断層と倫
理を加えてきた。北里は、そうした街のさまざまな風景を、白いキャンパス
の上に、繰り返し繰り返し描いてきたものだった。
しかし、この史上未曾有の大艱難を生き抜いてきた今、北里はもうそう
した考え方はしなかった。天災と、動乱と、人間を見つめながら、人間がよ
り本質的に平等なものであると認識したからである。全ての人々が、それ
ぞれ独立的に、同一の座標系の同一の一点に、極めてきわどい形で存在
していると分ったからである。
東京は今、この激動の時代の始まりとなったマグニチュード8の直下型
大地震から、一年と十一箇月が過ぎようとしていた。
輸送回廊の最終検問所で、輸送部隊は拳銃とナイフだけを残し、全武
装を解除された。そして、いったん車両も引き渡し、金網と土嚢で囲まれ
たプレハブの建物に入った。中には、電話ボックスと呼ばれている、箱型
のゲートがずらりと並んでいた。上野に出入りする人間の、総合管理シス
テムの端末である。身分照明カード、手形、指紋、声紋等がチェックされ
る。
そのボックスを抜けると、数人一組で、荒っぽい消毒を受けた。それで
ようやく通過できた。短機関銃で武装した数名の回収本部防衛隊員が、
北里たちにねぎらいの言葉をかけた。北里も、二、三人は顔を見知ってい
た。ベニヤ張りの床の上に、軍用犬が二匹いた。が、軍用犬は床にうずく
まり、おとなしく彼等を眺めていた。
プレハブの建物を出ると、最後の有刺鉄線と土嚢の壁を抜けた。監視
塔から、探照灯の光が落ちていた。その雨にけむる明りの中に、ジープと
バスだけが回されてきてあった。文化局のジープを運んできた若い回収本
部防衛隊員は、北里を確認すると、挙手を切って立ち去った。
最終検問所から数十メートルも走ると、整地された広いフィールドに出
た。出発ゲートに面していて、輸送部隊の編成に使われている場所であ
る。最近たてられた街灯が、雨の中に点々と灯っていた。
その、フィールドのはずれの方に、プレハブ式の事務所と、食堂が何軒
か並んでいた。そこだけが、ミニ・カーやジープやマイクロバスで混雑して
いた。輸送部隊のための店だった。が、夜はもっぱら、この防衛管区の防
衛隊員の休憩所に使われている。
彼等も、そこへジープを乗りつけた。北里は、特別に缶ビールを出しても
らい、それを四人に配った。それで、上野への無事帰還を祝って乾杯し
た。それから北里は、食堂の電話を使い、文化局々長に帰還の報告を入
れた。そしてもう一件、WHO(世界保健機構)の事務局を呼出し、二子神
香織の所在を尋ねた。若い女の声が、彼女は防疫センターにいると教え
てくれた。そこへ電話を入れると、今度は男の声が、彼女は重要な会議中
だと言った。急用なのかと聞いた。北里は、いや、そうではないと言った。
北里は、彼女へ伝言を一言頼み、電話を切った。帰還したことを知らせて
おけば、それで良かった。
小休止を取ると、彼等は回収物資集積所のある上野公園へジープを向
けた。公園の森が近づくと、しだいに雨の闇が濃くなった。浜田は、震災
後に出来た迂回路の方を、ゆっくりと進んだ。ここは彼等全員にとって、そ
れぞれに感慨深い場所だった。
やがて、ヘッドライトに映し出されてきた上野の森は、無残に荒れ果て
ていた。砲弾の直撃を喰らって、バラバラに砕けた樹木。焼け焦げて、芯
だけが点々と立っている林。そして、無数の焼け焦げたバスやトラックや
バリケードの残骸が見えた。ヘッドライトに映し出されていく全てが、避難
民をも巻き込んだ凄じかった戦場を、今も無言で物語っている。しかし、秋
にはここも、一面にコスモスの花の群生でおおわれる。そして、今年はさら
に回収本部防衛隊の手によって、主都全域に、数十トンに及ぶ草花の種
の空中散布が計画されている。
「北里さんは、暴動の時は、最後までここに居たんですか?」浜田が聞い
た。
「ああ・・・」北里は、唇を引き結び、深くうなずいた。
「すまんがな、浜田さん、」菊村老人が言った。「ちょいと止めてもらえませ
んかな」
「どうしたんですか?」
「拝みたいものでな、」
浜田はジープを止めた。
菊村老人は、ドアを外へ押し開けた。そして、雨の闇に向かって、深々
と手を合せた。
北里の方は、無言で、雨の降りしきる闇を見ていた。今は、過去の怒り
や悲しみは、何も考えまいとした。彼にとって、頭の中をカラッポにしておく
ことは、たやすいことだった。が、水が音も無くしみ出すように、彼自身の
心の中に、しだいに悲しみと虚しさが広くしみわたっていった。それで北里
は、もう一つの自分自身の心の中で、知性と煩悩が無益なシミュレーショ
ンを励起していく様子を、静かに見つめていた。
・・・どうして人間の心は、こうしてまるで無益なことを考えるのだろう
か・・・自分自身の意志に反して・・・これは生命体を維持するためのフェイ
ル・セイフ機構でもなく、豊な感情の奔流でもない・・・ただ、無益な不安や
不満といった、煩悩を鬱積していくだけだ・・・考えなければそれでいいも
のを、考え、ただひたすらに考えて・・・存在すること、それ自体を恐怖と思
い・・・消滅すること、それ自体を恐怖と思い・・・そしてまた、恐怖が恐怖
そのものの幻想を描いていく人間の心・・・人間に、この様なことをさせるも
のは、一体何なのだろうか・・・人間の存在と、はりめぐらされた人間の根
の深さ、その座標系の余りにも複雑なるがゆえだろうか・・・
・・・いったい、生命の維持と進化を、宇宙の熱力学的カタストロフィーの
観点から考えれば、エントロピーの増大は死を意味する・・・してみると、こ
うした秩序に逆行する煩悩は、生命の“生”としての要素ではなく、生命活
動に制動と枠をはめる、“死”の要素に入るのだろうか・・・
・・・しかし、考えるに、“自我”や“生命体”には、なぜ死がやってくるの
だろうか・・・なぜ、常に新しく生まれ変わるという、新陳代謝の形式が取ら
れるのだろうか・・・波動関数と人間原理の謎、生と死を映す認識という
鏡、その“命”のリズム、そして宇宙の膨張と進化という風景・・・一連のこ
うした中に、いったい存在における、どんな意義があると言うのだろう
か・・・この宇宙の終焉が、エントロピー増大による熱的な死か、ブラックホ
ールによる死か、あるいは神による、意志的な死かは知らないが・・・
・・・しかし、何故とも知らずに生み出されてきた、幾千億の魂、幾千兆
の悲しみや絶望・・・それらは、いったい何処から来、この宇宙の何処へ去
って行ったのだろうか・・・そして、結局、このエネルギーはいったい何なの
だろうか・・・
・・・しかし、それにしてもだ、この何時果てるとも知れない波動世界が、
“命”の座標の上を流れていく姿は、いったい何なのだろう・・・この宇宙の
観測者たる“知能”が生み出した、二律背反の幻影・・・その論法が生み
出してきた、喜怒哀楽の相・・・そして、全てが再び無化の深淵へと沈んで
いく波動の世界・・・何時果てるとも知れない永遠の修業の道のみが、こ
の謎の世界の存在に、一つの解を与えてくれるのだろうか・・・
ドアが、バン、と閉った。ジープが再び動き出した。
「北里さん、」と、添島が声をかけた。「会食の前に、ちょっと時間をあけて
いいですか?」
「ああ。会食には、間に合わせろよ」
「大丈夫です」
「うむ。菊村さんは、会食には出られますか?」
「そうですな・・・」菊村老人は、ボソリと言った。
「無理に出なくていいですよ。明日もありますから、」
菊村老人がグッタリとしているのは、誰の目にも明らかだった。すでに
上野に入った今、北里はどの様な形であれ、菊村老人を束縛する気はな
かった。ただ、文化局では、帰還した日は、夜の会食には必ず出席する慣
例になっていたのだ。
「明日の会食にしますか?」少ししてから、北里は言った。
「そうさせてもらいますかな・・・」
「功労者が欠けて残念ですが」竜造寺が、菊村老人の膝をたたいて言っ
た。
「いや、」菊村老人は、弱々しく笑った。
焼け残った樹林の向こうに、回収物資集積所の明りが見えた。明りの
下に、コンテナーの列があった。さらに、反対側に倉庫式の大型テントが
立ち並び、その先の方に二階建てのプレハブ式の事務所があった。その
窓の明りの列が、かっての街の灯のようだった。これらは全部、一般回収
局の回収物資集積所だった。コンテナーや倉庫群には、一般家屋や店舗
等からローラー式に回収されてきた、さまざまな回収物資がつまってい
る。日用雑貨、衣類、小型電気製品、機械工具類をはじめ、化学薬品、I
C、はてはかなり大型の数値制御ロボットまで含まれていた。大工場のロ
ボットはともかく、小さな町工場のものは、全て一般回収局の仕事である。
これらの物資はほとんど、ここから北にある埼玉県岩槻市の、第一輸送
中継基地へ運ばれていく。そして、日用雑貨等に関しては、その中継基地
から、北関東の百六十八箇所の難民キャンプへと送り込まれている。ま
た、さらにその何割かは、二重包囲環を越えて、敵勢力下の難民キャンプ
にも送られている。首都圏をのがれた膨大な数の難民は、こうした回収物
資と援助物資で、二度の冬を乗り越えてきたのである。
一方、主都の第二包囲環の西側の地域では、スラム化と産業の復興
が、同時に急速に進行していた。その一帯に、自衛隊基地と米軍基地が
集中していることもあり、まるで主都が数十キロ西へ移動した観さえあっ
た。そして、この主都西部地域こそが、今後の日本の将来を決する策源
地になるといわれている。
ジープは、一般回収局の明りの中を抜け、半壊した国立美術館の方へ
出た。その国立美術館が、文化局の回収物資集積所である。荒れすさん
だ美術館の前に、街灯が一つ灯っていた。光の輪が、雨と潅木と石畳を
照していた。その右手の方は、ヘリポートと接している。土嚢で仕切られた
ヘリポートには、点々とわびしげな明りが、雨にかすんでいた。
文化局のエリアの中に入ると、トラックもコンテナーも無く、ただガランと
していた。かっては文化局を中心に、この膨大な回収事業が始められた
のである。が、当時のその目まぐるしかった場所に、今は孤独な時間がよ
どんでいた。しかし、いずれにせよ、彼等がここに送り込んだ全ての文化
財は、すでに日本の各地で厳重に管理されている。また、特別に重要なも
のに関しては、日光の地下数十メートルの岩盤の中に作られた、耐核地
下貯蔵施設に運び込まれているはずである。
こうした全ての文化財は、日本民族の経歴の姿だった。また、日本民族
再統一のシンボルであり、和解への象徴でもあった。むろん北里は、そう
した平和で豊な時代が、再びやってくることを信じていた。歴史や、民族の
団結や、文明の精華といったものは、人間にとってはきわめて重いもので
ある。そして人間は、そうした限られた、耕された過去のストーリイの上に
生きている存在である。そうした、経歴の上に発現している形式なのであ
る。
浜田は、ジープを国立美術館の裏手の方へ回した。雨を吸った土嚢
が、ごっそりと崩れていた。やがて、対戦車用の80ミリ・ロケット弾で射ち
抜かれた壁の下に、テントの張ってある所があった。そこにも、すでに警
備員の姿はなかった。テントの下に、裸電球が一つ吊るされていた。テン
トの裂け目から漏れる雨水が、下の水溜まりでバシャバシャと音を立てて
いた。浜田は、その奥の方までジープを突っ込んだ。
「さあ!」北里は、ドアを押し開けながら言った。「トランクを頼むぞ!」
「しかし、ひどく荒れたな・・・」竜造寺が、あきれたように言った。
「まるで、化物屋敷だなあ」浜田も、裸電球に照し出された周囲を見回しな
がら言った。
「で、おれたちは、そこへ帰ってきた化物か?」
「ちがいねえ」
みんなが笑った。
「さあ、いくぞ」北里は、いつもの調子で言った。「菊村さん、大丈夫です
か?」
「ああ。わしは大丈夫、」
添島と竜造寺が、アルミニウムのトランクを一個づつ担いだ。菊村老人
は、アルミニウムのカメラ・ボックスを、肩に吊るした。それを浜田が取り上
げ、自分の肩に掛けた。北里は、回収日誌と、D−52地区の特別調査資
料を脇に抱えた。特別調査資料は、局長から個人的に調査を依頼されて
いたものだった。
暗い廊下の窓の下に、雨の吹込んだあとがあった。廊下の角を二つ曲
ると、その先に光々と明りが見えた。ラジオのジャズ音楽が流れていた。
そこまで行くと、ホールで五、六人が梱包作業をしていた。短機関銃が二
丁、壁に立てかけてある。
「やあ!」竜造寺が声をかけた。
「やあ、御帰還か!」
「元気かい?」
「みんな無事か?」
「全員無事だ!」北里は言った。「外山の班は、無事に到着したか?」
「ああ。一時ごろ着いた」
彼等は、荷物を床の上に下ろし、一人一人と固い握手を交わした。
「局長は、上かい?」
「ああ。君たちをお待ちかねだ」
北里は、荷物をつかみ上げた。そして、階段を登った。菊村老人と、添
島が一緒についてきた。浜田と竜造寺は、下で話し込んでいた。
「北里さん」フェルトのツバ付帽子をかぶった安藤が、階段を見上げて言っ
た。「シリウスで待ってますよ。あそこには、新しい娘がいっぱいです」
「その話は、」北里は、口もとを弛めながら言った。「向こうでも聞かされて
る」
「シリウスには、今じゃ、シリアスな尻軽女がいっぱいですよ」
「連中は、特別バスを仕立ててやってくるんです」
「そして、上野の金を、みんなハンドバッグに詰めて帰っちまいます」
「ハッハッハッ、上野が干上がってますよ」
「いったい、男は何をやってるのかと思いますね」
「ハッハッハッハッ」
「ハッハッハッハッ」
「ハッハッハッハッ、バカな話ですが、ホントの話ですよ」
「じゃあ、待ってます」安藤が言った。
「会食の後だ」北里は言った。
「懐かしい連中を、大勢集めておきますよ。今じゃ、かなり上野に帰還して
きてます」
「うむ」
五人は、二階の局長室に入った。局長は、帰り支度で彼等を待ってい
た。東京芸術大学教授であり、北里にとっては恩師でもあった。が、その
教授にも、今はもう二年前までの、エネルギッシュな陽気さはなかった。銀
縁の眼鏡の奥の目が、どことなくボンヤリとしていた。髪も、急に白いもの
が多くなったようだ。
「とにかく、君たちが、無事に帰ってきてくれたことが、なによりです」
局長は、一人一人と握手をしていった。北里は、あらためてそれぞれの
名前を紹介した。
「みなさん、よく、頑張って下さいましたな」局長は、カタコトのように繰り返
して言い、感激していた。
「先生も、お元気なのでホッとしました」北里は、改めて言った。
「うむ。これで、わしの仕事も終わったね」
「いえ、先生にはこれから、」
「いや、いや、自分でよく分る・・・まあ、北里君は、切り抜けてくれると思っ
ておった。しかし、小島君を死なせてしまったな・・・」
小島啓介は、教授が最も期待をかけていた学生だった。
「小島が殉職したのは、ぼくの班の下条が殉職した三日後でした」
「そうか、そうか、」教授は、目をしょぼしょぼさせ、涙を浮かべた。「そうだ
ったなあ・・・」
教授はうつむいたきり、しばらくは口もきけないように、おし黙ってしまっ
た。どこかしら、ボケがきていて、そのうえ涙もろくなっていた。
一方、教授を見ている北里の方は、心が白々と乾燥し、全てが乾ききっ
てしまっていた。親友の死に遭遇しても、一滴の涙も湧いてこなかったの
だ。また、聞くところによれば、心が白けてしまい、もはや女をも愛せなくな
ってしまうこともあるという。北里は、自分がそうなのかどうかは分からな
かった。ただ、これもまた、未曾有の死線を越えてきた男の姿だった。
教授は、気を取り直すようにして、他の四人に向かって言った。
「さあ、話は会食の時に、ゆっくりと聞きましょう。とにかく、宿舎で風呂に
入って、ゆっくりとくつろいでください」
「それでは、」と、北里は言った。「会食の時に、」
「うむ。わしもすぐに下っていくよ」
彼等は、またジープに乗込んだ。そして、公園の高台を下った。やが
て、町の明りのにぎやかな繁華街に入った。そこに入ると、ようやく上野に
帰ってきたのだという実感がわいた。
最前線の町の上野には、現在約二万人の人口が集中している。回収
本部東部総局がその中心で、人口の約半数を占めている。また、回収本
部防衛隊が別にあり、以下は街の女や商人、それに特殊技能者グループ
が、その専門技術を売物に集まっていた。しかし、この上野の町を最も特
徴づけているのは、ここに双方の代表からなる、和平委員会が常設されて
いることだろう。この事が、上野の町を中立的な性格に位置付けていた。
そして、中立的な回収本部防衛隊の創設となり、回収物資の一部割譲に
まで至っている。
しかし、最前線に位置する上野の町自体は、必然的に戦略的な町だっ
た。また、内外の報道機関、及び軍事情報機関が集中した。そして、情報
戦や謀略戦やテロが、歓楽街の裏側で、常に火花を散らしている町でもあ
った。
文化局の会食は、七時半に始まった。事務局の方の幹部も含め、それ
でも五十人前後が集まった。それと、方面隊幕僚の小佐が一人、また韓
国の観戦武官と情報将校が一人づつ、そしてイギリスのBBC放送のニュ
ース・レポーターが一人加わっていた。彼等は全員が、最前線のC−83
方面の戦闘と、この大規模な撤退について、ナマの詳しい状況を知りたが
っていた。
質問には、北里と外山が、交互に答えた。が、C−83方面に関しては、
第三十二回収班の全員が、あらゆる角度から詳しく検討しながら話した。
「うむ・・・よく分った、」だいたいの話が終わると、小佐は椅子から立ち上
がった。
「役に立てればよかったのですが、」北里は、ビールのコップをテーブルの
上におろしながら言った。
「大いに参考になった。ありがとう、諸君。それじゃあ、急ぐので、失敬する
よ」小佐は、軽く挙手を切った。そして帽子を受け取って、早々に食堂を出
ていった。
やがて、その会食も終わりに近くなった頃、北里は玄関に面会人が来
ていると告げられた。中座し、湿った薄暗い廊下を歩き、玄関まで出てみ
た。すると、髪をショートカットにした二子神香織が、ぽつりと電灯の下に立
っていた。彼女は、思っていたより元気だった。WHO(世界保健機構)のマーク
の入った軍服風のオリーブ色のジャケットを着、きちんと腰バンドを締めて
いる。
彼女は、細面で、おとなしい顔だちだった。が、気は強く、気持ちのいい
身のこなしをしている。
「やあ、」北里は歩きながら言い、口もとで笑って見せた。
「元気そうだね」
「ええ。あなたもね、俊一」二子神香織は、楽しそうにまばたきをして笑って
見せた。 北里は、両手で彼女の肩をつかみ、接吻し、抱きしめた。パン、
パン、と彼女の背中をたたいた。そうやって、大きく息をし、玄関の外を眺
めていた。そとは、あいかわらず、かなり激しく雨が降っているようだった。
北里は、そうやって、玄関の明りに映る雨を眺め、ボンヤリとしていた。
「疲れているわね、俊一」
「ああ・・・今になって、ドッと疲れが出たよ。しかし、みんな終わった。そこ
へ座ろうか、」
「ええ。あたしはまだ勤務中だけど。多分、九時半までには終わると思う
わ」
「忙しいんだな」北里は、どっかりとソファーに腰を下ろした。彼女をみ上げ
ながら、タバコを口にくわえた。
「また、コレラが動き出しているの」二子神香織も、ソファーに腰を下ろし、
膝の上で細い指を組んだ。
話がそうした問題になると、彼女は知的な印象を与えた。しばらくする
と、彼女はまた雨の中を、防疫センターへ帰っていった。北里も、食堂へ
戻った。が、すでに会食は終わっていた。食堂のドアが開いていて、ガヤ
ガヤとした話し声が聞こえてきた。
「さあ、北里、街へくりだそう」誰かが言った。
「シリウスへいこう。女たちが、首を長くして待ってるぜ」
四月二十五日。上野に帰還して三日目。
その日は、午後も遅くなると、またシワシワと雨がぶり返した。その雨の
中で、回収本部防衛隊の灰色の軍用車両が、いつになくせわしく町の中
を動き回っていた。それに加え、自衛隊の車両もしばしば目に入った。こう
した自衛隊の車両から、かなりの部隊が、この上野周辺に展開し始めて
いるのが分った。空中機動師団の武装攻撃ヘリも、頻繁に発着をくりかえ
している。
こんなことは、これまで一度もなかったことだった。しかし、確かに、上
野の町に開放軍の軍事的な圧力がかかり始めていた。湖水の向こうに、
濃密な対空火器で防御された、かりの戦車が目撃されているという。これ
が、単なる形式的な圧力だけなのか、本格的な攻略を目指したものなの
か、北里にも判断がつきかねた。
北里は、新聞を二つに折たたみ、その上に手を置いていた。そして、長
い間、スナックの窓から、人々や軍用車両の流れを眺めていた。それから
また、長い間、窓辺に置いてあるプランターのチュウリップの花を眺めた。
しかし彼は、ただそれらを眺めていたのではなかった。チューリップの花
や、軍用車両や、人々を、自分と一体化して眺めていたのである。つまり、
自我を拡大し、それらの事物と一体化し、同じ一人称の存在になろうと試
みていたのだ。主観と客観を超越し、宇宙と一体化できるものかと・・・
北里は、やがてウィスキーのグラスに手をかけ、ひとりボソリとつぶやい
た。
「・・・花は、花であり・・・限りなく花であり、永遠に花である・・・その花は、
人間にとって、美しいものであるべきだったのだろう・・・いや、それとも、
人間にとっての“美”が、花という対象を形成したのだろうか・・・この、人間
的に形成された世界の、必要条件としての“美”という概念を満たすため
に・・・」
北里は、ため息をつき、静かに顔を上げた。グラスを口に当て、ゆっくり
と傾けた。それから、今まで見つめていたチュウリップと同じように、しだい
に暮れていくこぬか雨の街路を見つめた。そして北里は、自分自身も、
“一期一会”のこぬか雨の中に溶け込んでいった。
・・・すべては、自我と共にあり、自我と共に流れ、自我と共に降ってい
た。街路は自分であり、人々は自分であり、大地も空も宇宙も、全て自分
だった。そうした全てが、真実の結晶世界だった。すると、自我は、それそ
のものの全体として消えてなくなる。そして、一切全てが、ただ一切全ての
ものになりきっている風景になった・・・
どこを見るともなしに、窓の外を眺めていると、ポッ、ポッ、と街灯に明り
が灯っていった。すると、こぬか雨の中に沈んでいた往来の風景が、また
明るくはずんで動き出した。北里は、この次元座標の無量の深淵を歩む、
武装した男たちや、街の女たちの風景に溶け込んでいった。そして、彼自
身が雨になり、雨に濡れて光る回収本部防衛隊のジープになり、ジープ搭
載の機関銃になり、それを埋める空間となった。
その、すべてが、真実の結晶が経歴していく、“永遠の絵”だった。しば
らくして、その“絵”の中に、二子神香織がフラリと姿を見せた。彼女はコウ
モリ傘を高くさしあげて、自衛隊の指揮通信車をやり過ごした。そして、往
来を渡ってきた。それから、パレット積みの土嚢の壁にそって、北里のいる
スナックの方へ歩いてきた。
「ここだ!」北里は、窓から声をかけた。
彼女は、うなずいて、足早に近づいてきた。北里は、そうした時の彼女
の仕草が好きだった。
「夕食は、外でする?」彼女が、窓から中を覗いて言った。
「うむ、」
「そう、」彼女はまばたきし、チューリップのプランターに、コウモリ傘を立て
かけた。
「だいぶ疲れてるな、」北里は、二子神香織の手首をつかんで言った。彼
女の手はひんやりとしていた。
「コレラがとまらないの。どうやら、ばらまかれているみたい」
「細菌攻撃か?」
彼女は、黙ってうなずいた。
「特殊な菌か?」
彼女は首を振った。
「でも、他のもあるの、」
「ほう、」
「わたしにも、コーヒーを一杯もらえない」
「ああ、うむ、」北里は、奥の薄暗い方を眺め、給仕の女に手を上げた。
「コーヒーをもう一つ頼む」
「モカを」二子神香織が言った。
「モカだ」
「はい」
その時、空気を切り裂く音がし、ドーン、と何かが炸裂した。続いて、もう
二つ、どこかで炸裂する音がした。攻撃が始まったようだった。
「どうなるのかしら?」彼女は、ギュッ、と北里の手を握りしめた。
「どうともなりはしないよ。ただ、全てが流れていくだけだ・・・」
北里は、暮れてきた灰色の雨空を見つめた。雨空が、限りなく美しく見
えた。
〔 完 〕