(1)
カオスの中で動く生体分子モーター 

「ええ、外山さん...ここまで、シアノバクテリアや光合成、ATPなど、原始地球に発
現した生命体と、ナノテクノロジーの風景を考察してきました。おそらく、その原初の
命とナノテクノロジーの中に、この生体分子モーターというのも、含まれていたのだと
思います...
そこでまず、生体分子モーターとは、どのようなものなのか、そのおおよその概念
を伺っておきたいのですが、」
「そうですねえ...
まず、生物体の中にあって、大きさは分子サイズということですね。それから、この
ような“ナノ・サイズ”の機械だと、その存在そのものが、嵐の様な“ブラウン運動”に
晒されているわけです。ところが、最近の仮説では、このブラウン運動を逆に利用し
ているというモデルが、有力になって来ています」
「うーん...ちょっと感覚的に、難しいわねえ...あ、ミミちゃんの方、準備が出来て
いるのかしら?」
「うん!」ミミちゃんは、コクリとうなづいて、唾(つば)をのんだ。
「そう、じゃあ、お願いね」
 《ミミちゃんガイド...No.2》
《ミミちゃんガイド...No.2》 


<ブラウン運動
> 
「ええと...
“ブラウン運動”というのは、微粒子に、熱運動をしているまわりの分子が、不規則に
衝突するために起こる、“ゆらぎ現象”の1つです。分子の熱運動効果が、直接目撃でき
る現象として有名です。
例えば、タバコの煙が空気中で拡散していく現象や、水の中にインクを1滴たらした時
に起こる、美しい拡散の風景です。
ここでは、ナノサイズの生体分子モーターなどの微粒子は、このブラウン運動の嵐で、
もみくちゃにされているということです。つまり、生体の中のナノサイズのマシンというもの
は、つねにこのような量子力学的な影響を受けているということです...
あ、それから、純粋に量子力学の影響下にあるのかと言うと、アミノ酸で構成されるタ
ンパク質ですから、そうした量子世界よりも、少しスケールが大きいです。
うーん...あえて言えば、ちょうどマクロとミクロの中間ぐらいの、難しいサイズです。
後で、また説明することになると思いますが、このあたりは“メゾスコピック”と呼ばれる
特異な領域で、古典力学(マクロ的力学)と量子力学の、奇妙な連携に支配されています」



「はい。ミミちゃん、どうもありがとうございました」響子は、パンパンと手を叩いた。
「うん!」
「ま、ともかく...」外山が言った。「今、ミミ君も言ったように、このような生体内の分
子モーターいうのは、私達が日頃よく知っているモーターとは、およそかけ離れたも
のだということですね。まず、回転子も接極子もなく、周りの部品というものが全くな
いモーターです...おそらく...」
「うーん...そんなモーターが、本当に存在するのでしょうか?」
「まあ、モデルを考察している段階と言っておきましょう。しかし、全く架空の話でもあ
りません...
想定されているのは、ベンゼン環平面や水酸基、アミノ基等で構成される、羽根車
とラチェット機構を組み合わせた様なモーターですね。実際のところ、最先端の研究
領域であり、今も様々な仮説が飛び交っている状況です。また、こうした様々なモデ
ルも、実際に作られ、研究されているわけです...」
「それで...その分子サイズのモーターというのは、生体内で、どのような仕事をし
ているのでしょうか?」
「ああ。それは、非常に広範囲にわたっていますね。筋肉の収縮、ATPの合成、DN
Aの二重ラセンの開閉、細胞膜を介しての物質の運搬...等々...様々なタイプ
の、膨大な数量の分子モーターが機能していると考えられます。
しかも、体液の中のミクロ世界は、“熱揺らぎ”や“量子ゆらぎ”が支配し、化学物質
や酵素が流れ、ブラウン運動の嵐が吹きまくっています。
しかし、より重要なことは、そのような中で、分子モーターは、きっちりと確かな仕
事をこなしているという事実です。しかも、体液の中で仕事をしているのは、1種類の
分子モーターだけではないのです。そのような“複雑系”の中で、様々な仕事が複合
的に行われ、情報交換がなされ、完璧な仕事が永続的に遂行されているということ
です。ナノテクノロジーの入口に立っている我々にとっては、まさに神業としか言いよ
うのない世界を覗いているわけですね」
「はい...」響子は、深くうつむいた。「何故...そんなことが出来るのでしょうか?」
「うーむ...まあ、分子モーターに関して言えば、ようやく最近、そのメカニズムが分
かりかけて来たという所ですね。つまり、その基本となっているのが、ランダムなノイ
ズをうまく利用するメカニズムだということです。
それは、具体的には、“ブラウン運動を使った、ラチェット(爪車/つめぐるま)の原理”の
様だということです。ラチェットというのは、分りますか?」
「はい...どこかで、聞いたことがあるとは思うんですけど、」
「ラチェットというのは、爪車(つめぐるま)のことです。切り替えで、一方だけに回るラチェ
ット式のドライバーや、ラチェット式のスパナというのがあるでしょう。あれは、一方向
の力だけを加えていける仕掛けになっています。逆回りの時は、空転して、」
「あ、はい。分りました。そういうドライバーを、一本持ってます」
「うむ、」外山は、笑ってうなづいた。「そこで、いいですか...生体分子モーターとい
うのは、体液というブラウン運動の海における“ラチェット機構付きの羽根車”の様な
ものではないかというわけです。ブラウン運動は、四方八方から、無数の粒子がラン
ダムにぶつかって来ますが、このような“ラチェット機構付きの羽根車”に当たると、回
転方向の力だけが加算されていく。つまり、これだけで、モーターが回転するわけで
す。ブラウン運動がエネルギー源なら、エネルギーさえ必要ないわけです」
「うーん...ブラウン運動を、エネルギーとして利用しているわけですか。すると、エ
ネルギーを必要としないわけですか?」
「しかし、ところが、響子さん、」外山は、指を立てた。「奇妙なことに、このモーター
は、動きを止める時にエネルギーを必要とするのです」
「うーん...よく分りませんが、」
「まあ、詳しい説明は省きますが、現在想定されている有力な生体分子モーターのモ
デルというのは、そのようなものです。止まる時に、エネルギーが必要なのです。ま
あ、徐々に説明していきますがね、」
「あの...このような分子モーターというのは、非常にたくさんあるのでしょうか?」
「そのようですね。生体内ではごくありふれたもので、細胞内でのあらゆる運動を支え
ていると言われます。これは、“カオスやノイズから秩序を取り出す、整流器”と考える
といいかも知れません」
「はい。でも...本当かしら...?」響子は、顔をくずし、首をひねって見せた。
「まあ、途方もないシステムが、存在していることは確かです。それから、何故今、ナ
ノテクノロジーに研究が集中して来ているかというと、生物学、医学、化学、物理学等
の、これまでの研究成果があるからです。その20世紀に積み上げられてきた研究成
果の土台の上で、ようやく今、ナノテクノロジーの科学がその扉を開こうとしているわ
けです。まあ、単なる直感で、生体分子モーターなどと言っているのではないというこ
とですね」
「はい。もちろん、本当だとは思います。でも、これまで私たちの知っているモーターと
は、あまりにもかけ離れていますわ」
「しかし、響子さん、この生体分子モーターの方が、はるか36億年の昔からあるわけ
です。シアノバクテリアの光合成工場も、そうです。誰が図面を引いたかは知りませ
んが、ちゃんとモチベーションもあり、さらに地球生命圏の進化も視野に入っていたよ
うです。まあ、私はそう見ていますがね、」
「すると、最初の生命体は、地球以外の所からやってきたものだと...?」
「いや、そうは断定していない。しかし...深い意味での受け入れ態勢が、すでに
あったと言うか...生命体が、非常に発現しやすい“場”となっていたと言うか...
まあ、高杉・塾長と似たようなスタンスです」
「“宇宙の初期条件”ですか...」
「私は天文学の方はやらないので、この方面はあまり深くは考えませんがね」
「はい...」響子は、コクリとうなづいた。「ええと...このラチェット型の分子モータ
ーのモデルについて...他に、何か言っておく事はあるでしょうか?」
「そうですねえ...このモデルは、ブラウン運動から無限のエネルギーを得ているの
で、第二種の永久機関(熱力学の第2法則を破る“永久機関”)が実現してしまうように見えます。
しかし、これに対してリチャード・ファインマンは、このシステムは外部からのエネルギ
ー供給が無ければ、仕事が出来ないことを示し、“熱力学の第2法則”にも違反して
いないことを証明しましています」
「はい...」
「この他にも、“光で動く分子モーター”などの研究報告もあります。いずれにしても、
この方面の研究は、まだ入り口に立ったばかりといった所ですね」
「はい、」





外山は、横にやってきたタマの頭をなでた。タマは見た目も立派だが、柔らかな毛
並も、たいしたものだった。外山は、人差し指で、タマのノドを小さく撫でた。タマは、
もっそりとノドを伸ばし、気持ちよさそうに目を細めた。響子も、タマの様子を眺め、口
もとを崩した。
「さてと...」外山が言った。「ここまで、ラチェット型の生体分子モーターのモデルに
ついて考察してきましたが、今度は、“生体エンジン”のようなものについて、考えて
みたいと思います。
まあ、ここで言うモーターとエンジンがどう違うかというと、回転力を生み出している
モーターに対し、エンジンというのは、まずピストンがあるわけですね。車などは、内
燃機関によるピストンの上下運動を、クランクによって回転運動に変えているわけで
す。つまり、ここでは、ピストンというよりは、“ポンプの様なもの”と考えてもらいましょ
うか」
「はい。ええと...その“生体エンジン”の1例として、細胞膜にある“イオンポンプ”を
取り上げるわけですね。このイオンポンプも、ラチェット(爪車/つめぐるま)のような機構が
働いているのでしょうか?」
「はい。まさに、そのとおりです」外山は、タマの頭を、背中の方へ撫で下ろした。「こ
のイオンポンプというのも、先程述べた生体分子モーターと同様に、“イオンチャンネ
ル”という、ごく単純な装置が中心になっています。
まあ、生体というのは、こうした単純かつ無限の複雑さを秘めたものを、それこそ、
膨大な数量を生滅させているわけです。我々には想像を絶するようなものを、あっさ
りと作り上げ、平気で廃棄していくのです」
「はい...」
「生体にとって重要なのは、その活動のプロセス性なのだと思いますがね...その
プロセス性こそ、私が私でありつづけ、命が命であり続けている姿なのです...
つまり、命の本質は、物質的なメカニズムにあるのではなく、時間と空間を統合し
た、“リアリティーの流れ”にこそあるのだということですね...」
「あの、外山さんも、そうした禅的な考えを持っておられるのでしょうか?私は、高杉
塾長から、よくそういう話を聞きますが、」
「なるほど...しかし、私は科学者として言っているのです。生命体というものを理解
する、方法論として、」
「はい...」
「まあ、そうは言っても、、確かに還元主義的な機械論的風景というものも、現実に目
の前に展開しているわけです。この、まさに、私たちの文明のパラダイムとして...」
「はい、」
「...山々の木々は、春に一斉には芽吹き、秋にはみな葉を落としますね。そして、
毎年それを繰り返す。そして数十年もたてば、古い樹木と新しい樹木が入れ替わり、
さらにそれが延々と繰り返されていくわけです。これは、むろん樹木に限らず、この地
球生命圏の全ての種が、営々と繰り返している生命活動の本質なのです...
まあ、あえて今回のテーマに関して言えば、これは我々にはまだ理解できないに
しても、全体が途方もない、精緻なナノテクノロジーの風景だということです。おそら
く...この巨大な地球生命圏を創出できた者が、もしいたとしたら...それはまさ
に、“神”そのものなのかも知れません。なんとも、想像を絶する世界が展開していま
すね。日々、刻々と...」
「うーん...知れば知るほど、驚きが益々深まるということですね...」
「まさに...我々はもっと、この“存在”と、“命”の深さを知るべきですね...」
「はい...ええ、話を進めたいと思います。それで、外山さん...細胞膜にあるので
すね、このイオンポンプというのは、」
「はい」
「ふーん...」響子は、椅子から立ち上がって、腕組みをした。「生命体の最小単位
が、細胞というのは、よく分ります。そして、この細胞膜というものにも、実に様々な機
能があり、様々な種類があるのも分ります。
それから、この細胞の塊が、さらに上位のヒエラルキー(ピラミッド型の階層制度)を形成
し、筋肉や臓器などとなり、さらに全体が描かれていくと...細胞というのは、まさに
キーポイントですが、まるでブラックボックスの様でもありますね」
「まあ、昔から、植物や動物の細胞が図解されていますが、この細胞の中で動く生体
分子モーターや、生体エンジン、“情報伝達のメカニズム”などは、これまで全く分って
いなかったわけです。最近、ヒトゲノムをはじめ、様々なゲノムの解読が進んでいま
すが、それだけで生命体を理解したとは言えないわけです。それはあくまでも設計図
であって、生体やタンパク質そのものではないのです。まあ、生命体を理解するに
は、まだまだ程遠いという状況ですね」
「はい。そうした中で、とりあえず、細胞膜の機能というものが出てくるわけですね。こ
こも、実に、ナノテクノロジーの宝庫のようなのですが、」
「まさに、そうですねえ...病原菌が攻撃してくるのも、この細胞膜ですし、抗体が反
応して防御しているのも、この細胞膜なのです。まあ、細胞というのは、典型的な“開
放系システム”ですから、入ってくるものは拒まないし、出て行くものも自由です。そ
れが、一定のルールに従っている限りはですね。
ただし、異物、有害物に対しては、非常に厳しいチェックしています。それが、免疫
反応であり、移植手術などで見られる拒絶反応です。また、神経細胞や、脳細胞など
では、情報が典型的に細胞から細胞へ伝達されていきます。相当に複雑な信号や
脳内麻薬物質などが、細胞から細胞へ伝達されていくわけです。これがどのようなメ
カニズムなのかは、今まさに研究が進んでいるわけですね。
まあ、しかし、今回は、そうした細胞膜の働きの中の1つ、“イオンポンプ”に話を絞
りましょう。そうでないと、とてもまとまりませんから、」
「はい...」響子は、コクリとうなづいた。「ええと、それじゃ、ミミちゃん...まず、そ
の“イオン”というものについて、おさらいをしてくれる?」
「うん!」ミミちゃんが、うなづいた。
 《ミミちゃんガイド...No.3》
《ミミちゃんガイド...No.3》 


イオン 


「ええと...だいたい分っていると思うけど、おさらいをしておきます...
“イオン”というのは、物質を作っている原子、または原子団が、電気を帯びているもの
を言います。酸やアルカリや塩などを水に溶かすと、イオンを生じます。プラスの電気を
帯びたものを“陽イオン”といい、マイナスの電気を帯びたものを“陰イオン”と言います。
この“陽イオン”と“陰イオン”は、互いに引き合う性質を持っていて、これらが結合した
ものを、イオン結合と言います。簡単な例をあげると、食塩の“NaCl”は、プラスの電気を
帯びたナトリウム原子と、マイナスのイオンを帯びた塩素原子が結合したもので、電気的
には中性になります...」
 (ミミちゃんは、旅先の鹿村から、ハイパーリンクで来ています)
(ミミちゃんは、旅先の鹿村から、ハイパーリンクで来ています) 

「はい。ミミちゃん、どうもありがとう。ひと休みして、次の準備をお願いね」
「うん!コーヒーをご馳走になるね!」
「どうぞ。鹿村にいたのに、本当に、ご苦労様!」
「さてと、いいかな?」
「はい」
「では...ミミ君が今説明した、この各種イオンですが、通常これらは、電気化学ポ
テンシャルの勾配にしたがって移動します。まあ、イオンとは、そうしたものですか
ら。ここは、分ると思います」
「はい、」響子は、唇を結んでうなづいた。「抽象的なミクロの世界ですが、何となく分
ります」
「結構、」外山は、小さくうなづいた。「ところが...生体内では、この細胞膜のイオン
ポンプが、そのポテンシャルの勾配に逆らってイオンを輸送します。このようにして、
“一定の電気化学ポテンシャルを維持すること”が、生命体にとっては不可欠だから
です...」
「はい...それで、外山さん、その細胞膜のイオンポンプというのは、実際にはどの
ようなものなのでしょうか?」
「はい...先程も、少し触れましたように、イオンポンプというのは、“イオンチャンネ
ル”という、比較的単純な装置が中心になっています。これは生体がもつ整流器で、
電流が一方向にのみ流れるように制御しているものです」
「...」
「典型的なイオンチャンネルは、漏斗(ろうと)の形をしていて、大きさは10nm(ナノメートル
/
1nmは、10億分の1m=100万分の1mm)程度のようですね。イオンは、この漏斗の広口部分
から先端部分へ流れ、逆流はしないわけです...
ええ...生命体の構造はみな一様にそうですが、単純そうに見えていて、奥が深
い。まあ、実にうまく出来ているわけです。つまり、これだけで、イオンポンプとして機
能しているわけですね...
実際には、イオンチャンネルは、先端付近の原子構造が少し変化するだけで、広
口部分の構造が大きく変わり、開閉する仕掛けになっているようです。そして、広口
部分が開閉することによって、漏斗の先端から、イオンを外へ運び出せるわけです
ね...
これはラチェットと同様に不可逆的であり、つまりイオンポンプとして機能している
わけです...さらに研究していけば、もっと深い領域があるのですが、とりあえず
は、簡略化して、全体のスケッチを見ていくことにしましょう」
「はい。このイオンチャンネルのエネルギーも、分子モーターと同様に、ブラウン運動
から来ているのでしょうか?」
「いえ、このイオンチャンネルは、ATPの加水分解エネルギーで動いています。つま
り、生命体の共通エネルギー通貨で作動しているということですね」
「ああ、なるほど。ATPのエネルギーというのは、このように使われているわけです
か...」
「そうですね。まあ、このATPの反応については、この次の項で詳しく考察します」
「はい...
ええ、さて、ここでは、生体分子モーターと、イオンポンプを取り上げたわけです
が、あらゆる領域で研究が進行しています。そこで次は、生体分子モーターとして最
も研究が進んでいるミオシンについて、さらに具体的に考察していこうと思います。外
山さん、このミオシンというのは、筋肉のタンパク質なのでしょうか?」
「はい、そうですね。詳しくは、そちらの方で説明します」
「はい。ええ、どうぞ、ご期待ください!」




 ナノ・テクノロジーへの道
ナノ・テクノロジーへの道 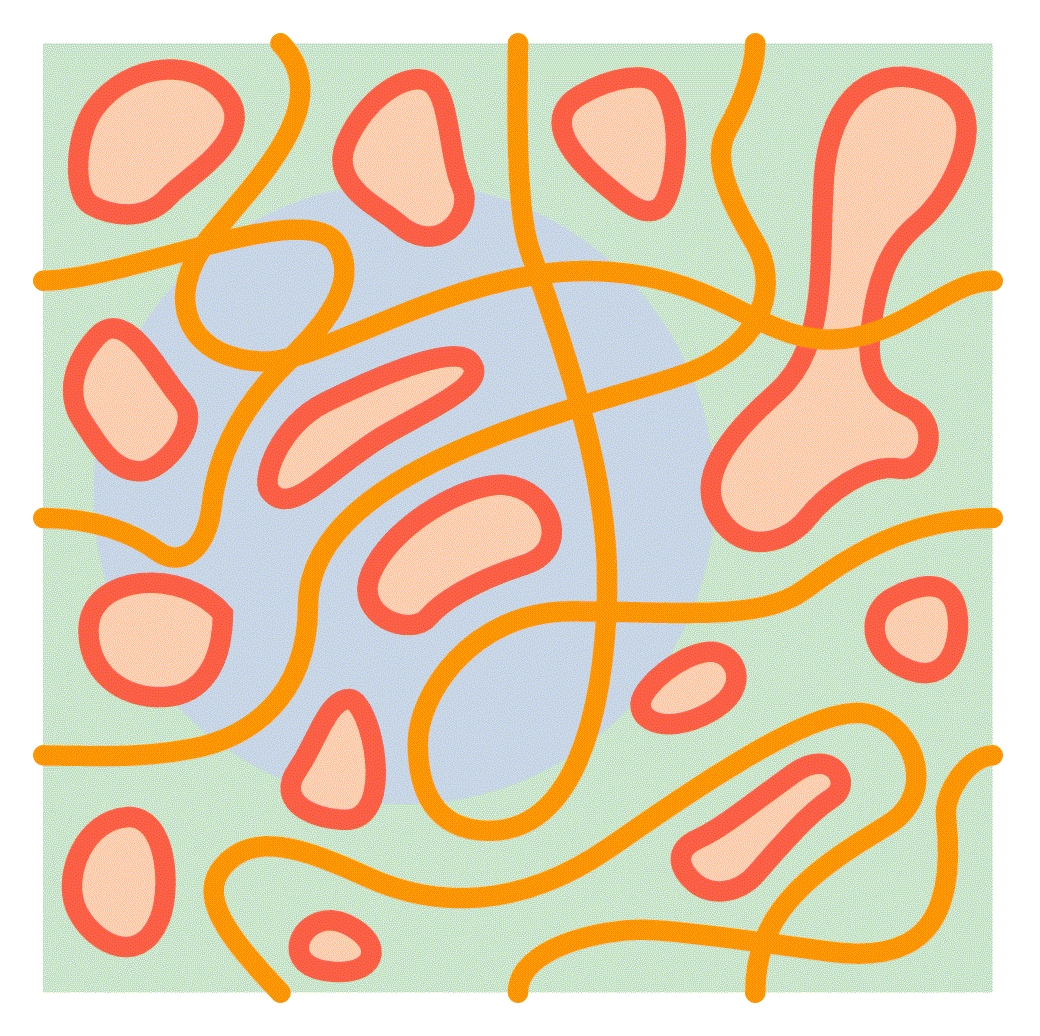
![]() <生 物 系>
<生 物 系> ![]()






![]() INDEX
INDEX 
![]()
![]()
 軽井沢基地
軽井沢基地 ![]()