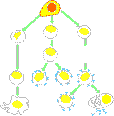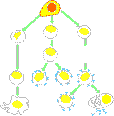



「ええ...」アンが、自分のモニターに目を移した。「まず...
近代生物学の衝撃と言えば...ワトソンとクリックが、DNAの二重らせん構造を突き
止めたことに始まります。これは、1953年のことですね。第2次世界大戦が終了してか
ら、8年後のことになります。2人は、このことで、ノーベル賞を受賞しています。この発見
は、それ以後の生物学に、革命を引き起こしました。
それから、半世紀後/2003年4月14日...“ヒトゲノムの解読”が完了しました。
“ヒトゲノム計画”で、“30億塩基の全配列の決定”に、ほぼ15年の歳月がかかってい
ます。このビッグ・サイエンスは、国際協力で取り組んだ、文明史上に残る巨大事業でし
た。
ええと...現在/2008年ですから...“ヒトゲノムの解読完了”は、5年前のことで
すね。それから、もうずいぶん時間がたっているように感じますわ。でも、わずか5年前
のことなのです。それだけ、以後の爆発的な影響力が、各方面に波及しているということ
ですね」
「そうですねえ...」外山が言った。「ヒトゲノムの解読以後...ゲノムの解読は、非常
にスピーディーになりました。コンピューター技術の成果でしょう。現在では、DNA鑑定
は、犯罪捜査や親子関係の鑑定にまで、幅広く応用されています。
“ヒトゲノム計画”の影響は、分子生物学の分野を越え、人類文明の社会性や、文化
面にまで波及しています」
「大勢の震災犠牲者も...」響子が言った。「DNA鑑定で、個人特定が行われています
ね。これまでは、遺体や遺骨の個人特定は、困難だったのですが...」
「そうですねえ...」外山が言った。「中国/四川大地震でも、遺体の腐乱が激しいとい
うことで、とりあえず遺体を処分し、後でDNA鑑定が行われているようですね」
「うーん...」響子が、口に手を当てた。「四川大地震の後は...いよいよ、日本の太平
洋ベルト地帯かしら...東京直下型地震...東海地震...東南海地震...それから
南海地震...などですね。
世界最大のメガロポリス(巨帯都市)群が、こうした地震ベルトと重なっています。この太
平洋ベルト工業地域で、これらの大地震が連動して起こった場合、日本は壊滅的状況
になります。
これらのメガロポリス群に、一刻でも早い、〔人間の巣型・災害対策拠点〕の展開が
必要ですわ...メガロポリスを安定化することが、まさに喫緊の急務となっています。こ
うした〔強固な対策拠点〕を、事前に展開しておく必要があります...日本は、先進国
なのですから...」
「そうですね...」アンが、響子の方に顔をかしげた。「《危機管理センター》としては、
当面の、最大の心配事ですね、」
「はい...」響子が、両手を握りしめた。「高速道路や新幹線よりも、こちらの方に予算
配分するべきですわ...それが、戦略的な対処です...」
「でも...」アンが言った。「日本の政治・行政は...そうした対策よりも、道路を整備し
たいようですわ...そして、“少子化対策”で人口も増やしたい様子です。全てが、的を
外れた、トンチンカンなものになっていますね...統治能力を疑いますわ」
響子が、黙ってうなづいた。
「政治・行政に...」アンが言った。「〔人間の巣型・災害対策拠点〕を展開して、メガロ
ポリスを安定化するという考えは、全く無いのかしら...それこそが、日本の生命線です
わ。それよりも、“天下り”が大事なのかしら...」
「アンも...」外山が、からかうように言った。「すっかり、《危機管理センター》の仕事が
板についてきましたねえ...口調も、響子さんに似てきましたねえ、」
「そうかしら...」アンが笑った。
「うーん...」響子が、口に手を当てた。「ともかく、強固な...“万能型・防護力”/〔人
間の巣型・災害対策拠点〕が展開していれば...メガロポリスは安定化しますわ...
理論研究員の秋月茜さんも、くり返し提唱していることですが...」
「政治家も官僚も...」アンが、響子の方を見た。「“国家のことは考えていない”と言わ
れますね...これはマスコミでも広く言われていることですが...本当にそうなのでしょ
うか?」
「うーん...」響子が、口をすぼめた。「そうは考えたくはないのですが...でも、実際に
何も進んでいませんね...
“新型インフルエンザのパンデミック”も心配ですし、“地球温暖化”も心配です。“巨大
危機が輻輳”
し、津波のように押し寄せてきています...でも、日本の当局は、年金や
保健や天下り行政のことで政局になっていますわ...今回のテーマとは、関係のない
事ですが...」
「いや...」外山が、首を振った。「“文明の破局”がやって来ては、再生医療もなにも、
あったものではないでしょう。まさに、何百万人もの命がかかっていることです」
「はい...」響子が、深くうなづいた。「そうですね...」
「ええと...」アンが、頭をかしげた。「いいかしら...本題に戻りましょう...」
「はい、」響子が顔を上げた。
「ええ...ヒトゲノムの解読以外では...
最近の医学・生物学の分野で、“衝撃的なニュース”というと...10年ほど前の、“ク
ローン羊ドリーの誕生(1997年/英ロスリン研究所/ウィルムット博士)”と、今回の“iPS細胞/人工
多能性幹細胞の成功(2006年/京都大学/中山伸弥・教授)”だと言われます...
“クローン羊ドリーの誕生”は、大きな衝撃だったのですが、一方で、反対や戸惑いも
ありました。理論的に、同じ手法で“クローン人間”が可能になるからですね。でも“iPS
細胞”では、世界中が大歓迎しています...まさに、歓迎一色の様相ですわ...
2006年に、“マウスiPS細胞(京都大学/中山伸弥・教授)”がつくられ...翌2007年に、
“ヒトiPS細胞(京都大学/中山伸弥・教授・・・及び、米/ウィスコンシン大学/ジェームズ・トムソン・教授)”が、別々
に開発に成功すると...“ヒトES細胞”の使用に反対の立場を取っていた、米/ホワイ
トハウスやローマ教皇庁/バチカンも、これを歓迎するコメントを発表していますね...」
「そのニュースは聞きました...」響子が、明るい顔にもどり、指を組み合わせた。「一般
的には、難しい内容ですが...ホワイトハウスやバチカンでは、しっかりとウオッチして
いるのですね、」
「そうですね...」アンが、眼鏡を押し上げた。「専門的な内容も含め、しっかりとウオッ
チしていた、ということですわ」
「日本では...」外山が言った。「宗教的に、あまり問題視されませんが、キリスト教で
は大問題なのでしょう。宗教のことは、よく分かりませんが...」
「それで...」響子が、外山の方に顔を向けた。「外山さん...
ES細胞と、iPS細胞は、そもそもどのように違うのでしょうか...極めて専門的な、ミ
クロの命の分野で...いったい、何が起こっているのでしょうか?」
「まあ...」外山が、顎をしぼった。「このニュースの衝撃というのは...
“ES細胞で発現している遺伝子”を導入すれば...“分化した体細胞”でも、“脱分化
/リプログラミング”が可能であることを証明したことです...
“体細胞核移植によるクローン技術”...“ES細胞と体細胞の融合技術”...“特定
遺伝子の強制発現によるiPS細胞の誘導技術”...これらを用いることによって、“分化
した体細胞”から、“未分化な細胞”をつくり出することが可能になったことです...」
「うーん...やっぱり、難しい話ですわ...」響子が、首をかしげて見せた。
「ま、とりあえず、一応説明しておきましょう。後で、くり返し、説明を加えて行きます」
「はい、そうですね。お願いします」
「まず...
“分化した細胞/機能分化した細胞”が...どのようにして“脱分化/リプログラミン
グ”され...分化多能性を再獲得するかについては...そのメカニズムは、まだ不明と
いうことですねえ...ともかく、iPS細胞/人工多能性幹細胞が、可能であることが示さ
れたわけです...
こうしたことは、医学・医療ではよくあることです。ここが、機械工学や電子工学とは違
うところでしょう。生命体とは、そもそもがすでに完成されている、究極のシステムなので
す。人間の科学技術をはるかに超えた、大自然の真理なのです...それを、人間が読
み説いているわけですね、」
「うーん...
“脱分化/リプログラミング”というのは...そもそも、細胞が機能的に分化してくベク
トル...各臓器や、血液などの成分組織になって行くベクトルとは...“逆の流れ”にな
るわけですね...“分化が逆流”するということですね?」
「その通りです...そして、再び、多能性を得るということです...
通常では、1つ受精卵から卵割が始まり、ヒトの成人で約60兆個の細胞に分かれて
行きます。単細胞細菌に見られるように、生命の最小単位は細胞なのです。そして、1つ
の細胞が60兆個に分割した、多細胞生命のダイナミックな波動が、ヒトの個体というこ
とになります...
こうした、多様化・複雑化が...生命潮流のベクトル/力と方向なのです...ところ
が、“脱分化/リプログラミング”というのは、こうした方向とは逆になるわけですね。ただ
し、熱力学の第2法則/エントロピーの増大のように...完全な非可逆性ということでは
ないようです。ここが進化・構造化する生命体の、特異な側面になるのかも知れません」
「つまり...
DNA機能が逆流し...分化した1個の細胞が、元の受精卵にまで戻るということか
しら?」
「いや、受精卵にまで戻ることはありません。しかし、分化は逆流するということです...
まあ、この過程で起こる...DNAのメチル化や、ヒストンタンパクのアセチル化・メチ
ル化といった...“DNA塩基配列の変化を伴わない=エピジェネティックな変化”...こ
れを、これから明らかにして行く必要があるようです...
つまり、“細胞分化の制御機構”を解明して行くことが...今後の課題になる様です」
「うーん...
様々な道具/技術がそろってきた上で...その、“脱分化/リプログラミング”も...
可能になってきたということですね?」
「その通りです...
クローンを可能にする“卵の不思議な力”は...卵/卵子だけでなく、ES細胞の中に
も存在していたということです...マウスの全遺伝子の公開データベースから...ES
細胞だけで発現している遺伝子を探したようです。
そして、まさに“卵の不思議な力”の遺伝子...その有力候補の遺伝子を、特定でき
たようです...それを、分化した細胞に導入し、成功したのが、iPS細胞ということのよ
うです」
「うーん...
つまり、その4つの遺伝子を、大人の皮膚細胞に導入したわけですね...導入する
のに、ガン遺伝子などに組み込んで導入したわけですね...それで、ガン化してしまう
危険があるということですの?」
「まあ、そうです...そのあたりのことは、《掲示板》を見て下さい」
「あの、外山さん...」響子が、顎に人差し指を当てた。「iPS細胞をつくるのに、ES細
胞の遺伝子を使うのなら...やはり、難しいのではないかしら?ES細胞を必要とするわ
けですよね、」
「いや...
卵は、動物の雌から採取しなくてはならないのですが...ES細胞は、“細胞株”とし
て樹立されています。入手も簡単で、実験もしやすくなっています...それに、遺伝子や
DNAは、PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)法で、いくらでも増やせるわけです」
「あ、そうですね...うーん...色々と事情があるわけですね...私たちには分からな
いような事情が...」
「まあ、その通りでしょう...論文として、私たちの目に触れるのは、ほんの表面的な成
果だけなのでしょう」
「はい、」
<
“ES細胞” と
“iPS細胞” の違いは・・・>





「ええと...」アンが言った。「《人工万能細胞・掲示板》でも説明しているのですが、そ
のあたりのことを...周辺情報も含め、もう一度説明しておきましょう...
時間的経緯や、詳しい解説もありますので、《掲示板》の方も是非お読みください。こ
こでは、重複を避け、概略を説明をします」
「はい、」響子がうなづいた。「《掲示板》も、お二人でされているわけですね、」
「いや、」外山が、笑って首を振った。「《掲示板》の方は、アンがやっています。私は、一
度呼ばれただけですね。ま、呼ばれた時に顔を出すだけですよ。コメントだけの時は、二
人でやるほどのことはありません、」
「あ、はい...私も、一通りは、目を通しているのですが、」
「ふふ...担当は、私になっていますわ」
「ええと...」アンが、手慣れた手つきでマウスを動かした。「いいかしら...
“iPS細胞(人工多能性・幹細胞)”は...“ES細胞(胚性・幹細胞)”と同じように...“無限の自
己増殖能力”と、“身体を構成する全ての細胞に分化する多能性”を、持っています。こ
の多能性という言葉ですが、これは全能性と区別される言葉です。この言葉について、
まず説明しておきましょう...
ええ...“全能性”というのは、“あらゆる種類の細胞に分化する全能性”のことです。
これは、哺乳類では、受精卵と、そこから2~3回分裂した細胞だけが持つと考えられて
います。一方、“多能性”というのは、“胎盤を除く、すべての細胞に分化する多能性”の
ことです...」
「うーん...
つまり...“脱分化/リプログラミング”でも...胎盤にまでは、逆流することができな
いわけですね...ES細胞でも、iPS細胞でも...」
「そうですね...
胎盤にも、もちろん受精卵にも、遡ることはできません。くり返しますが、全能性は、受
精卵と、そこから2~3回分裂した細胞だけが持つと考えられています。つまり、胎盤を
つくり、自然界の中で、真に個体を増殖する能力があります...自己増殖能力は、生命
体の最大の特徴の1つです」
「はい...
そして、この多能性・細胞に相当するのが、ES細胞であり、iPS細胞なのですね。胎
盤を除く、全ての細胞に分化する能力があるのですね...そして、iPS細胞の場合は、
分化した大人の細胞を、“脱分化/リプログラミング”で、分化を逆流させてつくるわけで
すね...」
アンが、うなづいた。
「iPS細胞では...」響子が言った。「そんな、“脱分化/リプログラミング”が可能な事を
示したわけですね...それで、スタートの轟音が響き...世界中の研究者が、一斉に
研究競争に走り出したわけですね...
“マウスiPS細胞”でそれが始まり...翌年の“ヒトiPS細胞”の成功では...京都大
学/中山伸弥・教授たちと、米/ウィスコンシン大学/ジェームズ・トムソン・教授たちと
が、別々に成功したわけですね...熾烈な研究競争のようですね、」
「そうですね...
もともと、それだけの研究の土台が、すでにあったということですわ。だから、すぐに追
いついたのです。そうした意味では、世界中で研究体制が整っています。日本はむしろ
遅れているようですわ。そこで、文部科学省などがあわてているようです。競争原理/莫
大な経済的利権が絡んでいます...」
「うーん...」響子が、ゆっくりとうなづいた。「そういうことには、敏感なのかしら」
「はは...」外山が笑った。
「ええ...」アンが、マウスでモニターをスクロールさせた。「ともかく...
“ES細胞”と、“ntES細胞(核移植ES細胞/体細胞クローン胚由来ES細胞)”、“iPS細胞”が、この
多能性を持ちます...多能性とは、胎盤を除く、全ての細胞に分化する能力のことです
ね...」
「アン...ntES細胞というのは、どういうものなのかしら。何度も聞いているのですが、
どうもよく分からないのですが、」
「あ...これは、ES細胞の1種ということになります...
再生医療で移植する場合...患者本人のES細胞なら...異物と認識されることも
なく、免疫系の問題はないのです。でも、患者本人のES細胞というのは、そもそも不可
能なのです。
そこで...患者の細胞から、“体細胞核移植”で“クローン胚”をつくり...そこから、
“患者と同じゲノムを持つES細胞/・・・成長すればクローン人間となる”が...考えら
れたわけです。この処理を行ったものは、普通のES細胞とは区別して、ntES細胞/核
移植ES細胞と呼んでいます...」
「うーん...それが、いわゆる...クローン人間にもなるということですね?」
「そうですね...
このクローン技術は、羊やマウスやサルでは成功しています...クローン牛もありま
すね...でも、ヒトでの成功例はまだありません...ヒトの卵/卵子を使う点や、ヒト・ク
ローン胚をつくる所に...技術以前の、倫理的問題があります...
全く同じヒトゲノムを持つクローン人間を、何人もつくることが可能になるわけです。こ
れは、今までに存在しなかった、大変な問題になりますわ...自然の摂理に反していま
す」
「それは...」外山が言った。「クローン牛でも同じことですね...トウモロコシや大豆で
も、同じことです」
「うーん...ともかく...iPS細胞では、これらのややこしい問題は、クリアされるわけで
すね?」
「そうです...」アンがうなづいた。「iPS細胞は、患者の体細胞からつくることが可能で
すので、ES細胞や、ntES細胞の抱えている問題は、あっさりとクリアできますわ」
「はい...」
「再生医療にとっては...」外山が言った。「まさに、衝撃的なニュースでしょう...
臨床で応用されるには、まだ課題があるということですが、基礎生物学の面からも、
非常に興味深いものがあるようです。“細胞分化の制御機構”を解明して行くことが、今
後の課題になるようです」
「話を戻しますが...」アンが、響子に言った。「ES細胞と、iPS細胞の違いは...そ
の、つくり方にあります。
ES細胞を得るには、初期胚を壊さなければなりません。この初期胚は、母体に戻せ
ば、赤ちゃんに成長するものですね。つまり、赤ちゃんに成長するものを、殺してしまうこ
とになるわけです...ここがまず、倫理的に問題になる所です。
でも、iPS細胞の方は、大人の細胞に、特定の遺伝子を導入することでつくります。こ
こが、決定的に違う所です。このことは《掲示板》の方で、ニュースとして詳しく説明して
います」
「はい、」
「文部科学省は...
“ヒトの初期胚”を“生命の萌芽”としています...そして、そこから得られるヒトES細
胞は、“人の尊厳を侵すことのないよう・・・誠実かつ慎重に扱う”ということを...文部省
の指針で求めています。
つまり、ヒトES細胞は、“つくること”はもちろん...“研究目的で使うこと”も、厳しい
条件が定められています。国/行政機関や、研究機関の審査が必要になるのです」
「はい...」
「でも、iPS細胞なら...
大人の分化した細胞からつくることが可能ですから、こうした問題というのは無いわけ
ですね...もちろん、初期胚を壊すという、倫理問題に抵触することもありません...ま
た、ヒト・クローン胚をつくる必要もありませんわ...」
「まあ...」外山が言った。「将来...再生医療に応用する場合でも、ES細胞の問題点
を、iPS細胞ならクリアできます。わざわざ、問題のあるntES細胞をつくる必要もないわ
けです」
「はい...」
「そもそも...」外山が言った。「再生医療というのは...
機能不全になった細胞や組織や臓器などを、培養細胞などで置き換えようというもの
です。多能性のES細胞は、1998年に発見されたわけですが、それ以来、再生医療の
担い手として、大いに期待されてきました。
ところが、ES細胞には...“生命の萌芽”を潰してしまうという倫理的問題の他にも、
技術的な面での、免疫系の問題がありました。それで、状況を非常に複雑にしてきたの
です。
つまりES細胞では、患者に異物を導入することになるわけです。その拒絶反応をクリ
アしなければならず、しかも、胚性幹細胞(ES細胞)ですから...発生という源流に近い所
の、拒絶反応になるわけです...」
「iPS細胞では...」響子が言った。「ともかく、こうした基本的な難問は、クリアされたわ
けですね」
「そうです...さて...その源流に近い所の、拒絶反応について、少し話ましょうか、」
「あ、はい...」響子が、肩をかしげた。
<マイクロキメリズム>




「ヒトの個体には...」外山が、モニターから頭を上げて響子に言った。「意外なことです
が...他者の細胞が混ざっている場合があります...
どの程度混ざっているのかは、まだ不明ですが、臓器移植などとは別のレベルで、自
分以外の細胞が混ざっているということです。これを、“マイクロキメリズム”と言います。
まあ、私にはあまり詳しいことは分かりませんが...胎盤の中に流れ込んでくる、母
親の細胞というものが、比較的よく知られているようです。この、子供の体内に母親の細
胞が存在する現象は、“母系マイクロキメリズム”と言います」
「はい...」響子が、手を組んで頭をかしげた。
「しかし...」外山が、脚を組み上げた。「大概の、外来の細胞は...いわゆる異物で
あり、死んでしまうようです...ところが、外来の細胞でも、“幹細胞”の場合は、生き残
ることがある様です...
免疫系をクリアして、胎児の中で根付くようですねえ...それが、“母系マイクロキメリ
ズム”です」
「細菌でも、善玉菌というのがありますものね、」
「まあ...そうですね...
ところで、この“マイクロキメリズム”というのは、両刃の剣のようなものだと言います。
有害なこともあれば、有益なこともあるようです...まあ、幹細胞というものが、いかに
強力なものであるか、ということでしょう...また、生命の神秘・・・免疫系の神秘のよう
なものを感じます...」
「はい...」
「この...“他人の細胞が混ざっている”ということ自体は...実は、かなり古くから知ら
れています。ただ最近、また注目されるようになりました。
“母系マイクロキメリズム”は、新生児ループス症候群などにも関与しているようです。
それから、インスリン依存性・1型糖尿病などの“自己免疫疾患”でも、これが関与してい
るようなのです」
「うーん...
1型糖尿病の原因は...その住み着いた母親の細胞が...子供の中で、異物とし
て免疫系の攻撃を受けているということかしら?」
「なかなか鋭いですねえ...」外山が、ほくそ笑んだ。「当然、そういう推測が可能なわ
けですが...実際は、どうも違うようです」
「と、いうと...?」
「母親由来の膵臓のβ細胞が...免疫系の攻撃対象になっている証拠は...どうも見
つかっていないようなのです...それなら、話としては分かりやすいのですがね」
「どういうことかしら?」
「逆に...膵臓の中にある母親由来の細胞が、臓器を再生しようとして働いているらし
いのです」
「じゃ...有益に働いているわけですね?」
「そういうことです...
まあ...こうした研究は最新のもので、今後どういう方向へ行くかは分かりません。し
かし、この現象は、治療に利用できるかも知れないと言われています。ともかく、今後、
研究が進んで行くでしょう...」
「うーん...でも、それは救われる話ですわ...母親の細胞が、子供を苦しめていると
いうのでは、たまりませんもの、」
「しかし、先ほども言ったように...“マイクロキメリズム”は、両刃の剣なのです...悪
い影響を与えているものもあるのです」
「はい、」響子がうなづいた。
「“母系マイクロキメリズム”とは逆に...母親に、胎児の細胞が逆流している現象もあ
ります。これは、“胎児マイクロキメリズム”と呼ばれています。胎児の細胞が、母親に定
着している場合ですね...
私は知らないのですが...妊婦の体調というのは、不思議なことがある様ですねえ。
色々と...」
「そうですね...」アンが、微笑し、眼鏡の真ん中を押した。「本題とは外れますが、“マ
イクロキメリズム”のことを、簡単にコメントしておきましょう...最近、注目されている分
野です...」
「はい...」響子が、アンにうなづいた。「私の知らないことばかりですわ」
「おそらく...」アンが、響子に言った。「誰の体内にも...“本人以外の人の細胞”が潜
んでいるようですわ...
子宮内の双子の間では、細胞が交換されているらしいですし...兄弟での“マイクロ
キメリズム”の可能性もあるようです。これは、母親を通してということですね。あと、性交
渉での“マイクロキメリズム”の起こる可能性は、まだ分かっていないと言われます。それ
から、乳児の授乳によって、母親の細胞が乳児に移行することは、あるようですわ、」
「そんなに、あるのですか?」
「まだまだありますよ...
治療行為によるものは、“医原生マイクロキメリズム”と呼ばれています。輸血や臓器
移植などですね...今後、研究が進んで行くと思います...
ともかく、分かっているのは、まだ胎児だった時に...胎盤を通して母親からもらった
細胞が、ずっと住みつくことはあるようです。これが“母系マイクロキメリズム”ですね。そ
れから、妊娠経験のある女性なら、胎児由来の細胞を持っているようです。これが、“胎
児マイクロキメリズム”です」
「はい...」
「母親由来の細胞であれ、胎児由来の細胞であれ...免疫系から見れば、“非自己/
他者”の細胞ということになりますわ...」
「何故...免疫系は、そうした他者を受け入れるのでしょうか?」
「それは、分かりません...
母子間で交流した細胞は、ともかく何十年も生き延びて、組織の中にすみ着くようです
わ。そしてそれは、体内の臓器から切り離せなくなって行きます。この現象を“マイクロキ
メリズム”というわけですね。
“マイクロキメリズム”は、“自己免疫疾患”の一因にもなるのですが、外山さんの言わ
れたように、“自己の身体を治す”のにも役立っているようです」
「うーん...つまり、両刃の剣ということですね...」
「そうです...
でも、今後の研究と開発で...“自己免疫抑制”や、“傷ついた臓器の再生促進”な
ど...“新しい魅力的な治療法”...に、つながって行く可能性があると言われていま
す。これも、今後、再生医療の1つになるかも知れませんわ...」
「はい...」 <参考文献:
日経サイエンス/2008-05/
マイクロキメリズム・・・あなたの身体に潜む“他者”の細胞>
「雨が降り続いますね...」アンが、窓を眺めた。窓辺の紫陽花(あじさい)が、雨に激しく打
たれていた。「ええ、さて...話を進めましょうか...
これまで、簡単に概略を話してきましたが、さらに考察を進めます。くり返しになる部分
もあると思いますが、別の角度から考察することで、理解も深まると思います」
「私には、」響子が言った。「まだまだ理解できない所が沢山ありますわ」
「そうですね...
研究者ではないのですから、当然ですわ。私たちの考察も、研究者を対象としたもの
ではなく、ごく一般の人を対象として話を進めています。その意味では、参考文献の“日
経サイエンス”の論文も、一般人でも理解できるものとなっていますね」
「いいですか...」外山が、自分のモニターを眺めた。「うーむ...
再生医療への期待が膨らむiPS細胞ですが、研究の流れとしては、クローン動物と深
いつながりがあるのです...クローン羊・ドリーが誕生したのは、1997年ですから、もう
10年以上がたつわけです。
メディアでも盛んに騒がれましたが、これは“クローン人間の可能性”を示唆するもの
でした。その観点で、倫理問題が浮上し、世界中が騒然となりました...米/ホワイト
ハウスや、ローマ教皇庁/バチカンも、これに神経をとがらせて来ました。日本/文部省
も、ES細胞の扱いには、非常に慎重な立場を取って来ました。
しかしこの問題は、生物学的には、衝撃は別の所にあったのです。それは...“不可
能と思われていた哺乳類の細胞でも・・・プログラムの書き直しが可能だった”...とい
うことが、証明されたことです」
「はい...」響子が、手をすり合わせた。
「受精卵から、多細胞体/個体に成長するまでの...
その、発生のプロセスというものは、まるでオーケストラのような趣があります。場所・
時間・音色/座標・プロセス・色彩...が、指揮者のタクトで絶妙に調整され...遺伝
子が、次々とピアノの鍵盤をたたくように発現し...また、自らその環境と対話しつつ、
壮大な芸術作品/生命体という波動プロセス性を形成して行くわけです...」
「ものすごい光景ですね...」響子が言った。「まるで...パソコンでWindows
を立ち
上げる時のような、壮大な動因がかかって行くわけですね...」
「動因ですか...」外山が、顎に手をかけた。「そう...確かに、強力な動因がかかって
います...生きること・・・/存続すること・・・/増殖すること・・・への、壮大な動因がか
かって行きます...」
「発達心理学的にも...」アンが言った。「その方向で、動因がかかって行きますわ。こ
れは、母親との臍の緒が切れ、個体として分離されてからですが...それ以前にも、無
意識のレベルでの、増殖への動因がかかっていますわ」
「はい...」響子が、アンにうなづいた。
「この光景は...」外山が言った。「イギリスの発生生物学者/コンラッド・ウォディントン
(1905~1975年)の、後成学的風景/エピジェネティック・ランドスケープの概念になります
ね...ウォディントンによれば、発生の特性は、その運河化/カナリーゼイションにある
とされます...
分水嶺に降った雨水が、しだいに地形を削って行くような...壮大なオーケストラのよ
うな...遺伝情報発現の光景ですねえ...先ほども言ったように...“DNA塩基配列
の変化を伴わない変化・・・エピジェネティックな変化”...この、“細胞分化の制御機構”
を解明して行くことが、今後の課題になるようです」
「うーん...」響子が、頭を振った。「高杉さんから...何時だったか、そんな話を聞いた
ことがありますわ、」
「そうですか...塾長なら、知っているでしょう...
ウォディントンによれば...情報は“発見”するものでも、“発明”するものでもなく、“発
現”するもの...だそうです。これは、なかなか含蓄のある言葉ですねえ。“この世界/
この世”の、構造自体の問題としてです...はは...これは、塾長に言葉が移ってしま
いましたねえ」
「はい...」響子が、沈んだ顔でまばたきし、口元を崩した。
「ともかく...」外山が言った。「いいですか...
“プロセス性の重力・・・”のようなものが...ヒトの60兆個の多細胞体/個体を作り
出して行くようですね。それも、複雑系を間違えることなく...まさに奇跡的に、複製・増
殖して行くわけです。しかも、絶妙な誤差を引き起こし...そこから、進化を引き出して
行きます。
この自然界のシステムでは、そもそも間違いというものは存在しないのです...その
微妙な誤謬(ごびゅう)や袋小路さえ、さらに道を開拓し、あるいは圧力となり、それが進化
のベクトルとなるわけです...」
「うーん...」響子が、斜めにうなづいた。「そうですね...
時間を区切り...あるいは、個別目的で眺めれば...膨大な誤謬が浮かび上がって
来るわけですが、それでも時間は続いて行くわけですね...リアリティーは不可分のも
のであって、局所原因というものは成立しませんわ...これは、【ベルの定理】ですね」
「これは...」外山が、微笑した。「そうした方面は、響子さんの方が詳しいわけですね」
「外山さんは...」響子が、指を立てた。「その...オーケストラのタクトを振っているの
は、どのようなものだと考えているのでしょうか?」
「さて...
ウォディントンも、そのことは言っていないのかも知れません...しいて言えば、エリッ
ヒ・ヤンツ(1929~1980年)の、『自己組織化する宇宙』のような概念でしょうか...“神”と
いうものを抜きにして考えれば...」
「高杉・塾長に言わせれば...」アンが、響子の方に肩をかしげた。「それは、“36億年
の彼”なのかも知れませんね...?」
「うーん...そうかも知れません...
高杉さんは、“生命体の条件の1つ”として...“36億年の彼”との、リンクを考えて
いますわ。ヒトの60兆個の細胞が、ヒトゲノムとリンクしているように...上位システム
では“命の全体性/36億年の命の広がり”と、不可分のものとみているようですわ...
その“36億年の命の全体性”に、人格を与えたのが“36億年の彼”です。
“36億年の彼”の“意識”が、膨大な発生の動因を送り込んでいるのでしょうか。そし
て、生命全体のタクトを振っているのでしょうか...小説/『人間原理空間』は、そのこ
とも、1つのテーマにしていると聞いていますが...」
「それは...」アンが言った。「今後...明らかになって行くでしょうね...“文明の第3
ステージ/意識・情報革命”の時代の進展とともにです...
でも、それほど単純明快なものではないと思いますわ...この世界の複雑性は、常
に次の逃げ道や...確率論的不確実性や...カオスあいまいさの壁に突き当たります
わ...そのために“神の座標”があるのでしょうが...でも、1つの考え方としては、い
いのではないでしょうか、」
「はい...」
「まあ...」外山が言った。「ウォディントンが亡くなって、すでに久しいわけですが、最先
端の生物学では、どのような概念になっているのでしょうかねえ...実際にこれから、こ
の“細胞分化の制御機構”の解明に取り組んでいくわけですが...」
「そうですね...」響子が、首を伸ばし、両手を組んだ。「装置/ハードウェアーの方は解
明できたとしても、ソフトウェアーの解明は、難しいことになりそうですね。これは、生物学
全体に言えることですが...」
「ともかく...」アンが、上体をのり出した。「個体のスタートである受精卵には、全てのカ
ギになるものが含まれています...それは、間違いありません...
そこで、指揮者のタクトが振られ、壮大なオーケストラが波動を開始します。しかも生
態系では、こうした発生は、それこそ無尽蔵に、やたらに起こっています。生態系や生命
圏そのものが、凶暴なほどの発現を爆発させ、惑星の風景を変貌させています...これ
は、凶暴という以上のものですわ...」
「エントロピーの増大に...」響子が言った。「まさに、拮抗しているわけですね...宇
宙の膨張が、莫大な真空のエネルギーを生み出しているように、そうした類のエネルギ
ーなのでしょうか...
高杉さんは、“生命”や“意識”というものを、“この世”の最も基本的なものとしていま
すが...」
「そうですね...“生命は、自然の法則に書き込まれている”ということなら...“宇宙の
初期条件”に入っているのかも知れませんわ、」
「あ、アンは今...高杉さんと、《影の生物圏の考察》を担当しているのでしたね、」
「そうです...」アンが、口のほころびを押さえてうなづいた。「ともかく...
こうした、潮流のような膨大な事象は、コンピューターの並列処理で対処できる限界を
超えています。しかも、生命潮流のベクトルは、複雑化・多様化の中で進化しています。
ヒト/人間も、まさにこうした中にあり...何者かによって発現させられ、生かされてい
ます...
さあ...この謎を解いていくわけですが、構造的に言って、私たちに解ける謎なので
しょうか...」
「高杉さんは...」響子が肩を引き、腕を背もたれに掛けた。「生命体の情報処理は、コ
ンピューターの並列処理ではなく...“36億年の彼”にリンクした、“意識”ではないか
と言っています。でも、それも確かに単純な風景ではないようですわ。“生命体”とは、そ
して“主体的・認識”とは、いったい何なのでしょうか...」
「響子さんが...」アンが、からかうように言った。「それが、分かっていないとは思えま
せんわ、」
「あら...禅的な覚醒ではなく、生物学的な意味でです...それに、簡単に答えの出る
ものではありませんわ」
「それなら、人生は非常に単純になりますものね...」
「そうですわ」
「うーむ...」外山が、深く頭を傾げた。「塾長の言う、“新しい生命観”ですねえ...
人類文明は、“文明の第3ステージ/意識・情報革命”に突入し...現在、そのステ
ージの端に立っているわけですねえ。そうした意味で、“細胞分化の制御機構”を明らか
にして行くというのは...単なる、基礎生物学や再生医療の領域を超えた、時代的な要
求かも知れませんねえ...」
「はい...」響子が言った。「“巨大で粗野な熱的エネルギー/・・・核爆弾や核エネ
ルギー”を振り回している時代は、すでに終わりが近づいていますわ。21世紀はもう、
“稠密な情報エネルギー”の時代に入って来ています...」
「うーむ...そうなのでしょうねえ...今は、まさに、産みの苦しみの時なのでしょう」
「はい」
「ええと、いいかしら...」アンが言った。「話を進めましょう...
ES細胞は多能性ですが、受精卵の全能性を持つのですね...この全能性というの
は、全ての細胞と胎盤になる能力を持っています...
受精卵から卵割が始まり、分裂して細胞の数が増えて行くにつれて、細胞の機能分
化/役割分担が始まります。これが、いわゆる“分化”ですね...多細胞生物の、“細胞
の機能分化”です...くり返しますが、ES細胞やiPS細胞には、“胎盤”になる能力はな
く、多能性という言います」
響子がうなづいた。
「ええ...単細胞生物には、寿命がないと言われます...
でも、多細胞生物は機能分化し、生物体として高度に、複雑に進化することにより、寿
命という大きな悲劇を背負い込むことになります。
でも、それは個体として...時間を区切ることによって、固有の価値観が生じる所か
ら来ているわけですね...逆にいえば、寿命があることにより、価値観が生まれ、そこ
から豊かな感情のあふれる、無限のストーリイ性が生み出されて来るわけですね...こ
の間、響子さんがお話してくれたことですが...」
「はい...」響子がうなづいた。「リアリティー/巨大なカオスの中では...
そもそも、時間・空間の概念も消滅します...“リアリティー/・・・切れ目のない真実
の結晶世界”では、部分/局所性というものはなく...したがって、固有の価値というも
のは存在しません。全ては“巨大な全体”です。それは不可分であり、1つのものです」
「それに覚醒するのが、禅的な“悟り”ということでしょうか?」
「うーん...簡単にいえば、そういうことですね...でも、言葉で表現できない所に、真
の意味での“悟り”があるのですわ、」
「はい、」アンが、瞬きしてうなづいた。
「ええと...」響子が、宙を見た。「うーん...
ヒトは言語を持つようになり...“意識”が発達・進化して...明確な時間認識や空間
認識を持つようになったのだと思います...そして、歴史性や、個体の寿命という、時間
概念を導入し...ストーリイとして認識し、相互主体性社会を共有するることにより...
“言語的・亜空間世界”に、多様な人間風景が刻印されるのだと思います...
その独特な亜空間座標に、“豊かでしなやかな情感世界”が生まれます...この、意
識の複雑化・多様化の方向に、文化・文明の意味があるのかも知れませんわ...人類
文明が、構造化を進めている“言語的・亜空間世界”というのは...そうですね、奇跡的
な芸術世界なのかも知れません...
それは、“この世”に発現した...“何者”かの、“夢のバリエーション”なのかも知れま
せんね...“夢の夢の、またその夢”なのかも知れませんわ...」
「そういうものかしら...」アンが、ゆっくりと腕組みをした。
「さすがに、響子さんですねえ...」外山が、宙を見上げた。「“この世”とは、そういうも
のですか...」
「あ...高杉さんが、そんな事を言っていました、」
「あら...みんな、高杉さんのせいにしていますね?」
「ふふ...」響子が、はにかんで、口に手を当てた。
<脱分化/リプログラミング>
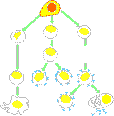




アンが、モニターに目を戻した。
「えーと...“分化”の話に戻りますが...
受精卵から始まる“機能分化”は、最初は3つの機能に大別されます...外胚葉、中
胚葉、内胚葉ですね...
それから、例えば...外胚葉は、さらに表皮系、神経系などに分化して行き...表皮
系ではさらに、皮膚の表皮、口の粘膜、目の角膜などに細胞分化が進みます。全ての
細胞の種類としては、200を超えると言われています...
これらの細胞は、機能分化が進むにつれて、必要のない遺伝子には、順次に“ロック”
がかかって行きます...この“遺伝子のロック”を全部外し...分化の流れを逆行させ
ることを、“脱分化”、“再プログラム化”、“リプログラミング”、あるいは“初期化”などと呼
びます」
「はい、」響子が、軽くうなづいた。
「“分化の最終段階まで進んだ哺乳類の細胞”でも...“脱分化/リプログラミング”が
可能であることを実証したのが、クローン羊・ドリーの誕生でした...1997年のドリー
誕生は、そうした意味で、大きな衝撃でした」
「そして、それは、“ヒトのクローンの可能性”を示唆した瞬間でもありますね、」
「そうですね...そこで、ヒトのクローンに、どのような意味があるのかという、倫理問題
が浮上したわけです」
「クローン羊・ドリーは...」外山が、響子に言った。「核を取り除いた未受精卵に、羊の
体細胞の核を移植することでつくられました...つまり、未受精卵の核を、成長した羊の
核と入れ替えたわけですね...そして、ドリーが誕生しました...」
「はい。それが、ヒトの場合...“ヒト・クローン胚”になるわけですね」
「そうです...
2005年の末に発覚した、“ヒト胚性幹細胞・捏造事件”(ES細胞論文の捏造・研究費等横領・卵子
提供における倫理問題)が起こったのも、このあたりの話ですねえ...」
「はい、」
「しかし...」外山が、手を組合わせた。「この、未受精卵への体細胞核移植で...何
故、体細胞の核が、“脱分化/リプログラミング”されたのかは、分かっていなかったと言
います...卵(/この場合は未受精卵)に存在する何らかの因子の働きによるはずですが、完
全には突き止められていないようです」
「はい...」響子が、唇に指を当てた。
「さて、一方...
山中伸弥・教授(/京都大学)のiPS細胞は、体細胞に4つの遺伝子を導入(/後に3つの遺伝
子でも成功)することで、“脱分化/リプログラミング”に成功しています。しかし、この“導入
した遺伝子のタンパク質”と...ドリーの体細胞核移植で、“脱分化/リプログラミング”
させた“卵由来の因子”が...同一のものかは、まだ不明なようです...」
「うーん...“初期化”...“脱分化/リプログラミング”のメカニズムは、謎が多いわけ
ですね、」
「そのようですねえ...
山中・教授のiPS細胞づくりは...導入すべき24個の候補遺伝子を、片っ端から試
す手法を取ったようです。しかし、その候補遺伝子の1つ1つの機能が、詳しく分かって
いたわけではなかったと言います。
これは、他のクローン動物での、“脱分化/リプログラミング”でも事情は同じようです
ね。羊、牛、マウス、ウサギなどで、クローン動物が誕生していますが、その成功率とい
うのは、実は非常に低いようです。動物種によって異なるようですが、その成功率は数%
程度のようです。
それから、霊長類でもクローンが試みられているわけですが、まだ誕生には至ってい
ません。“サルのクローン胚”からES細胞をつくることには成功しているようですが、誕生
までは至っていないようです...もちろん、ヒトでも成功していません」
「外山さん...」響子が頭を傾げた。「それはつまり...“種によって差”があるという事
でしょうか?」
「そういうことですねえ...
したがって、種によって細かな手法/やり方に差があるようです...クローンをつくる
には、未受精卵に核移植をした後、電気刺激などを加えて活性化させます。クローン羊・
ドリーを誕生させたウィルムット博士によると...“移植と同時に刺激”を加えるか、“刺
激を遅らせるか”でも...結果/成功率に違いがあるようなのです」
「はい、」
「羊では差はないようですが...牛では、“遅らせた方”が成功率は高いようです。それ
からマウスでは、“遅らせることが不可欠”のようですね...しかし、何故、こうした違い
が生じるかは、まだ分ってないといいます」
「うーん...」響子が、頭をひねった。「まるで...職人芸の領域ですね...」
「うーむ...」外山も、頭をひねった。「そうですねえ...
何故、うまくいかないか...このクローン動物づくりの成功率の低さは...“脱分化/
リプログラミング”の失敗かも知れないと見られています」
「うまく、“再プログラム化”ができなかったということでしょうか?」
「まあ...原因を探って行けば、そういうことになるのでしょう...
世界で最初のクローン・マウスに成功した、若山照彦(理化学研究所/発生・再生科学総合研究セン
ター/チームリーダー)によれば...マウスの場合、クローン技術を使って、成体まで育つ成功
率というのは、最適条件でも6%程度だと言うことです...
しかし、“胚盤胞”と呼ばれる初期胚まで発育させ...そこからES細胞を樹立するな
ら...成功率は30%と、格段に高くなると言います...つまり、この差は、どこから生じ
るのかということです」
「うーん...」響子が、体をのり出した。「話が難しくなりましたわ...よく分からないので
すが...」
「ま...要するに、こういうことです...
“ES細胞は、全ての細胞になれる多能性”を備えているはずです...そこで、クロー
ン動物の成功率の低さが、“脱分化/リプログラミング”の失敗にあるのなら...“クロ
ーン胚からのES細胞/ntES細胞”は、“普通のES細胞”と、何か違いはあるのかとい
うことです」
「あ...そういうことですか...
“ntES細胞”と、“普通のES細胞”は、何か違いはあるのでしょうか?」
「まあ...詳しく解析しているようです。しかし今のところ、その違いの部分というのは、
確認はされていないようです」
「うーん...そうですか...」
<クローン羊・ドリーの死・・・>
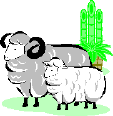

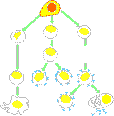


「ES細胞は...」アンが、肩をかしげた。「“機能分化の多能性”の他にも...“無限の
自己増殖能力”を持つわけですね...
この、自己増殖能力ですが...普通の細胞では、細胞が分裂するたびに、染色体の
端末にあるテロメアという反復配列が、短くなっていきます。細胞は数十回ほど分裂しま
すが、このテロメアがある長さ以下になると、細胞は分裂を止めたり、アポトーシス(プログラ
ム細胞死)を起こしたりします。
つまりテロメアとは、“細胞分裂の回数券”のような働きをしていることが知られていま
す。このことが、老化具合を刻み込み、細胞の寿命を決めています。このため、“細胞寿
命時計”とも言われます。
逆に...細胞が異常に増殖してしまうガン細胞も、このテロメアが関与していることが
分かってきています。テロメラーゼという特殊な酵素が働いていて、どうやら、無限の増
殖能力を維持しているらしいのです」
「はい...」響子がうなづいた。「テロメアというのは、聞いたことがありますわ」
「クローン羊・ドリーは...
子供を産んで、生殖能力があることを示しましたが、ドリー自身は、この“テロメアが短
かった”ことが報告されていますわ...羊の寿命というのは、だいたい15歳ぐらいのも
のです。でも、ドリーの場合は、6歳の時に回復の見込みのない肺の病気にかかり、安
楽死させています」
「安楽死ですか?」
「そうです...」アンがうなづいた。「この時...ドリーは...
高齢の羊に見られるような、関節炎の症状を示していたと言われます...ドリーは、
どうやら、ゲノムの“脱分化/リプログラミング”はうまくいっていたようなのですが、“細胞
分裂の回数券”であるテロメアの方は、うまく元に戻らなかったようですね...」
「うーん...」響子が、深くうなづいた。
「先ほどの...」外山が、響子を見て言った。「CDB(理化学研究所/発生・再生科学総合研究センタ
ー)の若山照彦・チームリーダーによれば...
ドリー以外のクローン動物では...調べられた限りにおいて...テロメアは“短くはな
っていない”ということです...さて、この違いは、どこから来るのかということですが、こ
れもまだ分かってはいないようです」
「そうですね...」アンが言った。「人為的な“脱分化/リプログラミング”は、まだ謎だら
けのようです。これから、本格的な研究が始まるのだと思います」
「はい...」
<エピジェネティクス>





「さて...」外山が、チラリとモニターを眺めた。「ええと...
“脱分化/リプログラミング”と、エピジェネティクスについて...別の角度から説明し
ましょう...」
「あ、お願いします...」響子が、顎を突き出した。
「エピジェネティクス(英語:epigenetics)の定義は...
クロマチン(染色質/
DNAとヒストンの複合体が主成分)への後天的な修飾により...遺伝子発現
が制御されることに起因する...遺伝学/分子生物学の研究分野ということになります
か...」
「うーん...難しい定義ですね」
「いや、そうでもありません...
エピジェネティクスという言葉は...“遺伝子/gene”の、“表面や外側/epe”の
変化であることから...この名前があるようです」
「ああ...」響子がうなづいた。「“epe”が“gene”の頭の方にくっつくわけですね...そ
れで“epigenetics”ですか...」
「そうですね...
詳しいことは分かりませんが、イギリス/発生生物学者/コンラッド・ウォディントン
(1905~1975)の、“エピジェネティック・ランドスケープ(後成学的風景)”の概念でしょう。かなり
前に亡くなっていますが、この造語はそこに出てきます。発生生物学者ですから、まず間
違いはないでしょう...
ウォディントンによれば...発生の特性は、その運河化/カナリーゼイションにあると
しています...分水嶺に降った1粒の雨水が、しだいに地形を削って行くように...そ
の小さな受精卵から出発し、環境と対話しつつ...壮大なオーケストラのような遺伝情
報発現の光景が展開して行くわけです...」
「その非常にダイナミックな活動は...」響子が言った。「命の続く限り...営々と継続
して行くわけですね...ヒトの60兆個の細胞において...そして、数百万年の世代を
超えて...さらに、“36億年の彼”として...」
「まあ、そういうことですねえ...個体レベルでは、何らかの原因で、その活動が停止し
た時、いわゆる死が訪れるわけです」
「その過程...プロセス性の影が...いわゆる“人間”ということなのですね...?」
「さて...そういう哲学的なことは、響子さんの方がお詳しいでしょう...具体的に話を
進めましょう...」
「はい、」響子が姿勢を正した。
「多細胞生物の個体を形成する、全細胞は...」外山が言った。「同じゲノム/全遺伝
情報の、複製を持っています...細胞分裂の時に、まず最初に核が2つに分裂し、コピ
ーがつくられます。それから細胞全体が2つに分裂して行きます。そうした中で、細胞の
機能分化も始まるわけですね...
細胞の種類によって、形も機能も様々に異なりますが...唾液や、血液から採取され
るDNAにも、全遺伝情報が含まれているわけです。だから、犯罪捜査などで、人物の特
定ができるわけです。DNAはまさに、究極的な個人情報になります...」
「個人差は...」響子が、微笑しながら言った。「SNP(スニップ / 単一塩基変異多型 )から来る
のでしたね...外山さんとご一緒に、《大戦略DNAの攻防》を考察したのは...確か
2000年の夏ですから...もう、8年前になりますわ...」
「そうですねえ...」外山が、懐かしそうに天井を見上げた。「もう、ずいぶん昔のことに
なってしまいました...」
「どの人も...ヒトゲノムの配列は、99.9%が一致するのだったかしら...残り1%が
個人差というのは、変わっていないのでしょうか?」
「さて...詳細な状況はよく分かりませんが、大きく変わってはいないでしょう...
しかし、コンピューター技術の発達で...DNAからの個人特定は、非常に速く、正確
になっているようですねえ...テーラーメイド医療も、進んでいるようですから、」
「はい...
8年前は、まだヒトゲノムの解読も完了していない頃でしたわ...5年前に解読が完
了(/2003年4月14日に解読完了)したということは...それよりも、3年前の話ですわ...」
「そうですねえ...さて、話を進めましょう...
ヒトゲノムは、個体/個人の設計図にたとえられます...ヒトゲノムは、30億塩基対
の2重らせん構造になっているわけですね。それが、ヒストン(塩基性単純タンパク質の一群の総称/
DNAと結合して、ヌクレオヒストンになる)という、糸車のようなものに巻きつけられ、染色体の中に納
まっているわけです。
この中に、人体を形成したり、メンテナンスの担い手となる、2万~3万種類の部品(/
タンパク質)のつくり方が書かれているわけです...響子さんも、よくご存知のように...」
「はい...」
「さて...
細胞は必要に応じて、部品の設計書を、DNAから1文字づつコピーします。そして、そ
のコピーをもとに、細胞内の別の場所で、部品/タンパク質を組み立てるわけです」
「mRNA(メッセンジャーRNA)などの仕事ですね...」
「そうです...
“遺伝子のスイッチが入る”というのは...遺伝子の文字列/塩基配列をなぞって行
く、“コピー装置のスタート台”が、“遺伝子のすぐ前にピタリとくっつくこと”だと例えられま
す...この“スタート台”のことを、“転写因子”と呼びます...」
「うーん...それで、コピーが開始できるわけですね...」
「さて、ここからが...」外山が、モニターに目を投げた。「エピジェネティクスの本題で
す...
生物体というのは複雑系の極みですが...これがキッチリと健康に過ごすには...
個々の細胞が、それぞれ必要なタンパク質を、キッチリとつくり出すことが大事になりま
す。別な言い方をすれば、“不要なタンパク質はつくらない”ということです。
もし、脳細胞が胃の消化酵素などをつくり出したとしたら、それこそ大変なことになりま
す。脳が消化されてなくなってしまいますからねえ...しかし、生物体では、そんな事は
絶対に起こらないわけです...」
「そうですね、」響子が微笑した。
「つまり...
そうした、“不要なタンパク質をつくりださないための装置”が、エピジェネティクスと呼
ばれる仕組みなのでしょう...つまりつ、細胞の機能分化です。ま、奥の深いものです
が、分かっている概略を説明しましょう」
「はい、」
「先ほどの設計図のアナロジー(類推)になりますが...
ゲノムDNAには、“覆(おお)い”が付いていていて...隠されている箇所が多くありま
す...この“覆い”があると、“コピー装置のスタート台”が結合できなくなるのです...
さらに、この“覆い”が多くなると...そのページは開かれないように、“糊づけ”されてし
まうのです」
「つまり...遺伝子に、“ロック”がかかって行くわけですね?」
「その通りです...
具体的には...DNAを構成する“文字/・・・塩基”にメチル基(CH3)がくっつき、“メ
チル化”されるのです。このメチル基が、つまり“覆い”なのです。そして、DNAはヒストン
という糸車に巻きついているわけですが、メチル基が多くなると、ヒストンの化学修飾が
変わり、“隣のヒストンとギュッと凝縮”してしまうのです。これが、“ページが糊づけ”され
たアナロジーです」
「うーん...そんなことになっているのですか...」
「ここで、大事なことは...
ゲノムDNAの、書き換えや削除が起こっているのではないということです。ゲノムはそ
のままで保存され、“メチル化で修飾”されたり、“ヒストンがギュッと詰って・・・ページが
閉じられている”だけだということです」
「だから...細胞分化の“初期化”も、可能になるわけですか...」
「そうですね...」アンが言った。「つまり...
“遺伝子/gene”の...“表面や外側/epe”の変化であることから、エピジェネティ
クスというわけですね、」
「そういうことですか...」響子がうなづいた。
<DNAのメチル化について・・・> 






「DNAの“メチル化”について...」アンが言った。「私の方からも少し話ましょう...」
「はい、」響子が、アンの方に肩を回した。
「哺乳類の受精卵では...
一度、DNAのメチル基(CH3)が外れた後、母胎の子宮に着床するところから...再
メチル化が始まるようですね...胚から発生が進行するにつれて、つまり機能分化が進
行するにつれて...個々の細胞では、“不要な遺伝子のメチル化”と、その部分の“ヒス
トンの凝縮”が進んで行くと考えられています...」
「その“メチル化”は...」響子が言った。「細胞分裂の過程で、引き継がれて行くわけで
すね?」
「そうですね...
細胞分裂の前に、核の分裂があるわけですが、そこでDNAの複製が行われます。そ
の時に、メチル基も娘細胞に引き継がれて行きます」
「はい、」
「ええと...」アンが、モニターに目を移した。「どこだったかしら...そうそう...
あらかじめ、核を取り除いた未受精卵に...体細胞や核を移植すると、クローン動物
として育ちます...そこで卵/卵子には、メチル基を外す、“脱メチル因子”があると考
えられています...
クローン羊・ドリーの例でも見られるように...ここに...“脱分化/リプログラミング”
の因子の、少なくとも1つはあるはずですわ...」
「うーん...」
「DNAのメチル化研究は...
ガン研究の分野でも活発になってきているようです...ガンは、そもそも、遺伝子が
変異を起こすことで生じると考えられています。ところが最近になって、“DNAのメチル化
異常”によって、ガンが生じることを示すような研究結果というものも、出てきているようで
すわ」
「DNAのメチル化の異常が、ガンになるのですか...これも、テロメアが関係しているの
かしら?」
「ともかく...これから研究が進んで行くでしょう...
分子生物学の流れとしては...まず、ヒトゲノムの解読が行われ...それから、エビ
ジェネティクスの解明へと進んできたわけですね。したがって、ゲノムの全景を調べたり、
個々の遺伝子の塩基配列に応じて、メチル化を調べるといった研究は、そもそも歴史が
浅いのですわ...21世紀に入ってから、本格的な研究が始まったようですから...」
「はい...」響子が言った。「タンパク質や糖鎖の研究なども、一斉に始まりましたわ」
「そうですね...
こうした研究/・・・DNAのメチル化研究を行う専用機器というものも、すでに開発され
ているようですわ。つまり、“試料からデータ解析まで行うための専用機器”ですね...
この種の機器を提供している、アプライド・バイオシステムズ・ジャパンによれば...ラ
イバル社の製品と合わせると、すでに世界で、2000~3000台が使われているという
ことです」
「うーん...そういうシステムが開発されることで、研究にも拍車がかかるわけですね」
「そうですね...でも、非常に高価な装置だということですわ...
文部科学省の科学研究費補助金/科研費などの助成がないと、購入はなかなか難
しいようですね。関係者によれば、“日本での導入は遅れ気味”ということです。“最近
は、中国からの問い合わせが多い”のだそうです」
「うーん...時代の勢いということでしょうか...
でも、本質的な意味で...経済原理下の競争原理が働くというのは、どうなのでしょう
か。純粋な意味での再生医療が発展するのは、大歓迎なのですが...」
「でも...」アンが響子を見て、明るい顔で言った。「第一線の研究者は、純粋な情熱で
やっているのだと思います...そうでないと、研究生活など続きませんものね...」
「そういうものかしら...」
アンがうなづいた。
「現在は...」外山が言った。「大資本の投入が、研究開発を盛り上げているのは事実
でしょう...資本主義の原理下では、やはり資本の投入がなけれは、何も物事が進み
ませんねえ。
響子さんの気持ちは分かりますが、社会体制のパラダイムシフトは、再生医療とは別
の課題ということでしょう」
「はい...」

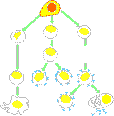




「ええ、厨川アンです。
長くなりましたので、以降は、《iPS細胞時代のスタート(Ⅱ)》の方へ移行
します。引き続き、よろしくお願いします...」
 iPS細胞時代のスタート
(Ⅰ)
iPS細胞時代のスタート
(Ⅰ) ![]()