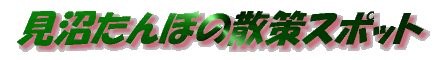
【大谷ホタルの里】
(おおやほたるのさと)
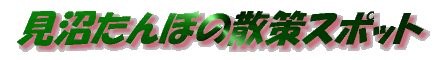
|
西福寺の東側斜面林のふもとに、大谷ホタルの里があります。大谷ホタルの里は、景観ゾーン、生態系ゾーン、ふれあいゾーンにわかれています。 6月中旬からはゲンジボタル、7月からはヘイケボタルの光を見ることが出来ます。 昔、見沼はゲンジボタルの名産地で、源平蛍合戦伝説が生まれたり、江戸時代には「大宮の螢狩」の版画が有名になったりしたそうです。また明治以降は、宮中への献上蛍でも、見沼は有名だったそうです。ですが1950年代にはゲンジボタルが絶滅し、ヘイケボタルも激減してしまいました。こういった人工の地区でしか蛍が殆ど見られなくなってしまったのはとても残念ですが、ぜひ蛍が住めるような環境を復活させたいですね。 平成9年4月29日には、テントウムシも見られました。 |
 |
 |  |
 |
|
【解説】 昔は大宮市内のいたる所で見ることが出来たホタルも、急激な都市化による環境の悪化により、現在ではほとんど見ることができなくなりました。 ホタルは水のきれいな川にしか住むことが出来ないため河川環境のバロメーターとなります。ホタルがすんでいるということは、人間にとっても住みよい環境なのです。 大宮市ではホタルを通じて、自然と親しみ清流を復元するモデル事業として、このホタルの里をつくりました。 景観ゾーンは、ヘイケボタルの生息に適した環境にしています。7月から8月にかけてヘイケボタルが見られるように、水路や池にはヘイケボタルの幼虫と餌になるカワニナやタニシがいます。とらないで下さい。 自然状態の湿地に近づけるために、池は傾斜をつけ、水深によって、植生も変化をもたせてあります。 生態系ゾーンは、斜面林に生息する生物への配慮から、斜面林と通路の距離を広くとって人間と自然との間に間隔をもたせてあります。 水辺林の植生もハンノキ、オニグルミ、ヤナギ、エゴノキを中心に、クヌギ、コナラ、シラカシ、等の自然木を配置しています。 また、このゾーンには、ゲンジボタルのために人工水路をつくってあります。6月中旬には、ゲンジボタルの光も見ることが可能です。 手前の池はトンボ池、奥の池は水鳥のためにつくりました。ホタルだけではなく、トンボを含めた全体としての生態系を考慮しています。 ふれあいゾーンは水辺で親しめるように、山側には、(相木石)だけを積み上げた空石積みになっています。 また水際には、階段護岸や緩傾斜護岸を配置してあります。石や土や木という自然素材を使って昔どこにでもあったような水路をイメージして整備しました。 ザリガニやメダカ等の水生生物が住みやすい水路です。 水路にものを投げ込まないようにしましょう。 (大谷ホタルの里の掲示板から) |