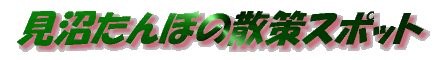
【見沼通船堀】
(みぬまつうせんぼり)
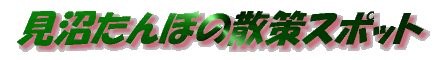
|
武蔵野線の東浦和駅を下車し、右手に2〜3分歩くと見沼通船堀公園にでます。 この公園の裏側に見沼通船堀(西縁)があります。通船堀に沿って進むと芝川に突き当たり、さらに橋を渡って見沼通船堀(東縁)を進むと見沼代用水に出ます。 この見沼代用水に沿って「緑のヘルシーロード」というハイキングコースがあり、川口自然公園、大崎公園方面へ抜けることができます。 |
 |  |
 |  |
|
【歴史】 見沼通船堀は、享保16年(1731)に幕府勘定吟味役井沢弥惣兵衛為永によってつくられた我が国最古とされる閘門式運河です。通船堀は代用水路縁辺の村々から江戸へ、主に年貢米を輸送することを目的として、東西の代用水路と芝川を結ぶかたちで八丁堤の北側につくられたものです。東縁路が約390m、西縁路が約654mありますが、代用水路と芝川との間に水位差が約3mもあったため、それぞれ関を設け、水位を調節して船を上下させました。関と関の間が閘室となり、これが閘門式運河と呼ばれる理由です。この閘門をもつことが見沼通船堀の大きな特長となっており、技術的にも高く評価されています。 通船堀を通って江戸に運ばれたものは、年貢米の他野菜、薪炭、酒、魚類、醤油、荒物などが運ばれました。 通船を行うのは、田に水を使わない時期で、初め秋の彼岸から春の彼岸まででしたが後に冬場の2ヶ月程と短くなりました。通船は明治時代にも盛んに行われましたが、陸上交通の発達によってすたれ、大正時代の終わり頃には行われなくなり、昭和6年の通船許可の期限切れとともに幕をおろしました。 |
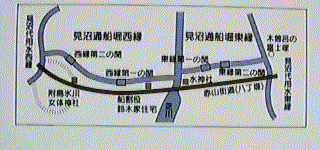 |
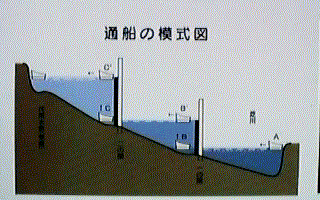 |