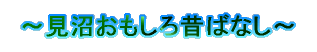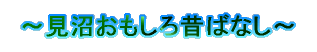| 第1回 太田道灌(おおたどうかん)に会いに行くの巻 |
華固(かこ)ちゃんは、見沼に近い小学校の5年生です。
若葉のかおる初夏の日曜日の朝、身支度をととのえた華固ちゃんは、庭の奥にある『護摩堂(ごまどう)』という建物の前で、同級生の未来(みらい)くんの来るのを待っていました。きょうは、見沼に関係の深い人で、五百年ほど前に活躍した"太田道灌(どうかん)"という武将に会いに行くのです。お父さんの不思議な祈祷(きとう)の術によって、過去の世界へ連れていってもらうのです。
しばらくすると、未来くんが走って来ました。野球帽をかぶり、リュックを背負い、首から双眼鏡を下げています。
「おそいじゃないの。気が気じゃなかったわ」
「ごめん、ごめん。お母さんのおにぎり作りがおくれたんだ」
「お母さんのせいにしない方がいいわ」
「だけどさ。ぼくの言うこと、信用してくれないんだもの。"太田道灌に会うなんて、できるはずないでしょ"って言うんだ」
「それは仕方がないわ。私でさえ、お父さんの言うこと、本気にできなかったもの」
「そうか…。華固ちゃんも初めてなんだ。どんなふうに過去の世界に入っていくんだろう?」
「なんだか、こわくなってきたわ」
そう言っているところへお父さんが出てきました。
華固ちゃんのお父さんは、『修験道(しゅげんどう)』という宗教の『行者(ぎょうじゃ)』なのです。白装束(しょうぞく)に身を固めたその姿は、映画やテレビに出てくる『山伏(やまぶし)』そっくりです。名は『夢幻坊(むげんぼう)』といいます。
「おう、おう!来ていたな。さあ、入れ!」
夢幻坊は、さっさと護摩堂に入っていきます。二人は、こわごわ後につづきました。
護摩堂の中は暗く、ひんやりとしていました。二人は夢幻坊の後ろに坐りました。
目が慣れてくると、正面に青鬼のような像が見えてきました。きば牙をむき出し、大きな目でこちらをにら睨んでいます。ぞうっと寒気がして、身も心もこお凍りついたように感じました。
二人とも、下を向いてふるえていると、パチパチと音がして、急に明るくなりました。
ローソクがともされ、薪(たきぎ)に火がつけられたのです。青鬼の目が光り、いちだんとすごみが増してきたようで、華固ちゃんは未来くんにしがみつきました。とたんに夢幻坊の声が飛びました。
「動くな!目をつむれ!」
二人はびくっとして、目を閉じて固くなっていました。
お経のような声、つぶやくような声、怒っているような声と、次々に調子のちがう声が流れました。それは、未来くんにはもちろん、華固ちゃんにも初めての、不思議な祈りの声でした。
薪がパチパチとはじけ、煙が広がって、息苦しくなりました。じっとがまんをしていた二人でしたが、華固ちゃんが悲鳴(ひめい)をあげました。
「やめてぇ! 死にそうよ、お父さん!」
「だまれ! この煙では死なん!」
夢幻坊が叱(しか)りました。こらえていた未来くんが、くっ、くっとせきこみました。
「こらえろ!息をとめろ!」
きびしい声が飛んできました。
「はい!」
返事をしたとたん、頭がもうろうとしてきて、未来くんは、何もかも分からなくなりました。華固ちゃんも、ほとんど同時に気を失ってしまいました。夢幻坊の声だけが、高く低く、長く短く、強く弱く、しばらくの間ひびいていたのでした。
気がつくと、いつの間にか、三人は暗いトンネルの中を歩いていました。聞こえるのは、足音と、水のしたたる音だけでした。
二キロぐらい歩いたでしょうか、いきなり「止まれ!」と声がかかりました。『先達(せんだつ)』としての夢幻坊の声でした。
「さ、しっかり目を開けてみなさい。そこの出口から外界が見えているぞ」
「あっ、山だ!山が見えるわ」
華固ちゃんが驚きの声をあげました。
「あ、川も見える!橋がかかっているよ」
未来くんが目をこすりながら言いました。
「お父さん。ここ、どこ? 見沼じゃないわね」
「まあ、落ちつけ。これから話すぞ。未来もそばに寄れ。ここからはおまえたち二人だけで行くのじゃ。よく聞けよ」
夢幻坊は、二人をトンネルの出口の方へ向けて立たせ、後ろから肩を押さえて話し始めました。
「正面に見える橋を渡って、川に沿った道を登って行け。五百メートルぐらいの所に大きな寺がある。"龍穏寺(りゅうおんじ)"という寺だ。太田道灌公はそこで待っているのだ」
「どうしてこんな山の中なの?」
「ここにお墓があるんだ。五百年もの間、"道真(どうしん)"というお父さんといっしょに、そこに眠っているんだ。今は起き出して、顔を洗っているかな? あははは…」
「なんだか、こわいわ」
「ぼくもこわいよ。死んだ人が起きて待ってるなんて…」
華固ちゃんも未来くんも、急に元気がなくなってきました。
「歴史上の人物に会いたかったんだろう。そんな意気地なしでは、研究は進まん! さ、行け! 午後3時に迎えに来るからな」
夢幻坊は二人の肩を強く押して外へ突き出し、姿を消してしまいました。振り返るとトンネルの穴さえなくなっていたのでした。
そこは越生(おごせ)という奥武蔵の山裾(やますそ)の町でした。
二人は元気を出して山道を登っていきました。
龍穏寺の山門をくぐると、正面の奥に、大きな本堂が見えました。左手には、少し小さなお堂が二つほど建っています。そして、その陰で、白い装束の男が、しきりに手招きしています。
「あれ、お父さんかしら?」
華固ちゃんが言いました。双眼鏡でのぞいていた未来くんが、叫ぶように言いました。
「ちがうよ! おさむらいだ! 白装束のおさむらい…あ、太田道灌だ! 顔が日本歴史事典に出ていたのとそっくりだ!」
「どれ、見せて!」
華固ちゃんが双眼鏡を借りてのぞきました。
色白で、にこにこして手をあげているその顔は、昨日調べた日本歴史事典の顔とそっくりでした。
「道灌さん。こんにちは…」
二人は、一年生のころの担任の先生にあったような感じで、手をふりながらか駆け寄っていきました。
それは、確かに太田道灌でした。白装束は死んだ人が着せられる着物です。道灌さんは、あの世から起きて来て、二人を迎えてくれたのです。
二人は、お堂に上がり、お茶やお菓子のもてなしを受けました。
「さて、あまり時間は取れないので、質問を聞こうかのう」
道灌さんはあぐらをかいて、ゆったりとした口調で切り出しました。
「見沼のことだったのう。すっかり変わってしまったようだが、わしには、思い出がいろいろあるのじゃよ」
「ぼくが聞きたいのは、竜の話なんです」
「私は、砂(すな)町という名前と、 砂金(さきん)についての伝説が知りたいのです」「ほう、ほう。ほかにはどうかな」
「はい、道灌さんは、どうして岩槻(いわつき)という町に城を築いたのですか?その訳や、吉野原合戦の話を聞かせてください」
「私は、見沼でハスを作らないわけと、道灌さんとの関係が知りたいです」
「ほほう。そんな話もあったかのう。では、一つずつ片づけていこうか。」
道灌さんは立ち上がって、本や、地図や、いろいろな書き付けを持ってきました。
華固ちゃんと未来くんは、リュックからノートや筆箱を取り出し、記録の用意をしました。いよいよ本番の昔ばなしの始まりです。
「まず、竜の話じゃが、見沼には伝説がいくつもあったのう。もう調べてあるのかな?」
「はい。竜の話は七つも八つもあるのですが、そのことよりも、道灌さんは竜に出会ったことがあるのかどうか…と」
「うむ。あるぞ。昔は大沼だったので、竜は何匹もいたのじゃ。嵐のときとか、沼が荒れる直前とかに、よく天に昇っていったものじゃった」
「それは"たつまき"じゃないのですか」
「そうじゃ。たつまきじゃ。竜は天に昇るとき、黒雲を呼んで、たつまきを起こすのじゃ」
「それでは竜を見たことにならないです」
「あははは。竜は神じゃ。神様をはっきり見ることなどできぬ。神様とは、姿を見せないものなのじゃ」
「でも、竜の姿は、お寺や神社に…」
「うむ。人間が想像して創ったわけじゃ。姿を見せないのじゃから、自由な姿でいいのじゃよ」
未来くんは、分かったような分からないような変な気分で、ノートに書き始めました。
道灌さんは、華固ちゃんに笑顔を向けました。
「そなたは、行者"夢幻坊"の娘だから聞いておるじゃろう。この寺の小林住職が、『見沼の竜はうちから行ったのだ』としきりに申しておる」
「ほんとうですか?初めてです」
「この寺の伝説じゃ。昔、この場所は、人を寄せつけないほど険しい山中の湖だったそうじゃ。ここを見つけた第五代の住職で、雲崗(うんこう)という和尚(おしょう)が"こここそお寺を建てるのにふさわしい地だ。ここをゆずってくれ"と山の神に祈ったのだそうじゃ。すると湖の主だった竜は、嵐と雷を呼んで天に昇り、一夜のうちに平地になった。そこですぐに寺を建てる工事にかかり、龍穏寺はここに引っ越してきたということじゃ」
「その時の竜が、見沼に引っ越してきたのですね」
「古い本には『 名栗(な ぐり)の有馬山(ありまやま)に去って池をなした』と書いてあるが、小林住職は見沼へ行ったと言っておる。国昌寺(こくしょうじ)や万年寺(ばんねんじ)に、見沼の竜の伝説もあるが、どちらも曹洞宗(そうとうしゅう)であり、ここの末寺のようなものだから、つながりがあるとな」
「はじめて聞いたわ。道灌さん、ありがとう」
華固ちゃんは"来てよかった"と心からのお礼を言いました。未来くんも、おもしろい話に筆記を忘れて聞き入っていました。
「さて、次は"砂町の地名"の話だったかな?」
「お願いいたします」
華固ちゃんは鉛筆を持ちなおしました。
「あれは驚きだったな。わしの直感がぴたり当たったのじゃからのう」
「どういうことですか?」
「そもそも砂町というのは、元は砂村、その前は山田村、その前は三沼村じゃ。三沼村を上州(じょうしゅう)(群馬県)の山田七郎という者が大きく開拓して山田村とした。わしは、岩槻城ができてまもなく、見沼を見てまわった。その時、山田村で大きな塚を見つけた。形はよいが、一部くず崩れかけていて、頂上の祠(ほこら)は傾いていた。わしは考えた。"荒れてはいるが、ふつうの塚とはちがう。古代の有力な首長(しゅちょう)の墓にちがいない。村人の心のよりどころとして修築してやろう"とな。わしは頂上に登って祠をのぞいた。"稲荷(いなり)の神だった。このとき、わしは不思議な霊気(れいき)を感じた。"この神は、必ずわしのお味方になってくださる"とな。わしは、手を合わせて言った。"この塚をなおさせていただきます。お宮も建てかえさせていただきます。しばらくわきでお休みください"とな。すると、どうだ。何が起こったと思う?」
「さあ?」
「分かりません」
華固ちゃんにも、未来くんにも、見当がつきません。
「光ったのだよ、祠の奥が! ピカッと光ったと思うと、おごそかな声がかすかに聞こえた。『汝(なんじ)のなすがままに委せよう。塚の奥にて光る物は、汝に与えることとする』と。わしは直ちに工事を命じた。くず崩れをなおし、草を刈り、木の枝を切って眺(なが)めをよくした。道を開いて人々が通りやすくした」
「塚の中には砂金があったのですか?」
「その通りじゃ。わしは、あのお告げを信じて、その砂金をいただいた。工事の費用に使うとともに、軍資金にもした。その後、あの村は"砂村"と呼ばれるようになったのじゃ」
「よく分かりました。ありがとうございました」
華固ちゃんはていねいにお礼を言いました。
未来くんは、塚とお宮の絵を、夢中で描いていました。
このあと、しばらくきゅうけい休憩と言うことになりました。皆さんも一休みしてください。
「さて、今度は、城や合戦の話じゃな。歴史というと戦の話になりがちだが、何故だろうかのう? それはともあれ、質問に答えねばならんが、二つともむずかしい話になるので、簡単な説明だけにしておこう。
岩槻城を築いたのは、『応仁(おうにん)の乱(らん)』という十年も続いた大戦の起こる少し前じゃ。既(すで)に、関東でも、次々と戦いが起こり、少しの油断も許されなかった。これは都の足利幕府の力が弱くなったためで、関東では、鎌倉公方(かまくらくぼう)や関東管領(かんれい)を始め、地方の豪族(ごうぞく)たちが勢力争いばかり続けていたのじゃ。
太田家は、関東管領の上杉氏に仕えていたので、 武蔵(む さし)・相模(さがみ)両国(埼玉・東京・神奈川)を守るため、たくさんの城を築いた。江戸城・川越城・岩槻城などじゃ。
岩槻は古くから交通の要所であり、水運の便もよかった。荒川の本流が台地を包むように曲がって流れており、その台地に城を築けば、どんな名将にも攻め落とせなかろうと、わしは考えて造った。この岩槻城の攻防戦は何度もあるので、大きくなったら調べてみるとよかろう。
さて、次の「吉野原合戦」の話じゃが、あれは、孫の資高(すけたか)がやったことじゃ。わしはもう殺されていた。
「え! 道灌さん、殺されたんですか?」
「そうじゃ。主君上杉定正(さだまさ)公によってだましう討ちにあった。昔はよくあったことじゃ。詳しくは夢幻坊に聞きなさい」
道灌さんは平気な顔で話を進めました。
「あれは享禄(きょうろく)2年のこと、川越城には敵方の上杉憲房(のりふさ)がいたが、いきなり三千の兵を率(ひき)いて攻めてきた。そこで資高は千二百ほどの兵を連れて岩槻城を出た。両軍は、吉野原で、見沼を挟んで対陣したのじゃ。降り続く雨で見沼は増水していたが、岩槻軍は全員で見沼を押し渡り、川越軍を攻め散らした。孫の資高が勝ったんじゃよ。これが「吉野原合戦」の話じゃ」
「ありがとうございました。それで、今、何か残っているでしょうか?」
「何もないな。原っぱは、住宅や公園や工場に変わり、見沼は、草ぼうぼうの中に、小川のように細い芝川が流れているだけじゃ。『つわもの兵どもが夢の跡』という言葉があるが、それさえ消えてしまっておる」
道灌さんの顔は、とてもさび淋しそうでした。
「長くなったが、いよいよ最後の話じゃな」
道灌さんは茶をすすり、華固ちゃんと未来くんにも、すすめました。
「見沼でハスを作らないわけは、三つあるようじゃな。氷川女体神社の女神の話と、見沼の竜のためだとする話と、も一つは、わしが原因だとする話の三つが語り継がれていたようじゃな」
「はい。その中の、道灌さんの話が本当かどうか、教えていただきたいのです」
華固ちゃんが、はっきりとした言葉づかいでお願いしました。
「おかしな話が生まれて、よく今まで伝えられてきたものよのう」
道灌さんはそう言って笑ったあと、ていねいに話してくれたのでした。
「見沼は、ハス作りには向かなかったようじゃな。一部で作ったところもあったようじゃが、やめてしまったのだ。水の増減の激しい暴れ沼だったことや、場所によっては底知れぬ泥沼であるため、取り入れが容易でなかったからであろう。
わしが戦に敗れて、ハス田に逃げ込んだ時、雨の音が鉄砲の玉の音に聞こえてこわ怖い思いをした。それから後はハスを作らなくなったと言うのじゃが、岩槻城主のわしを思ってくれるのはうれしいが、わしは、そのような負け戦は一度もしておらん。それに、わしの生きていた頃は、まだ鉄砲はなかったのじゃ。鉄砲が使われるようになったのは、百年以上経ってからのことじゃ」
これには華固ちゃんはもちろんのこと、未来くんもびっくりでした。鉄砲が、ポルトガル人によって日本に伝えられる話は、まだ、誰からも聞いていなかったのです。
こうして、道灌さんの長い話が終わりました。二人はノートがいっぱいになるほど書き込み、お礼を言って立ち上がりました。
道灌さんは、戦国時代の武将の中で、いちばん立派な武将だったと、お父さんから聞いていたので、また会いに来る約束もして帰途についたのでした。