86�@��g�{�̌���
 |
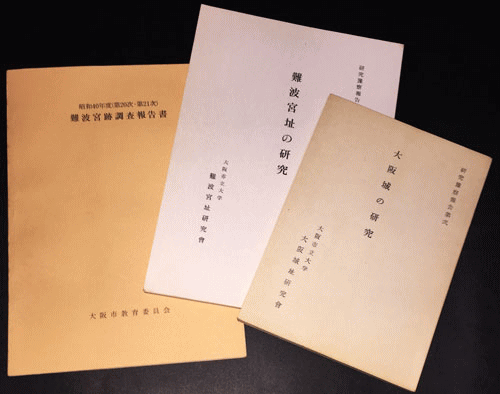 |
�����V��2016�N12��1�����Ɂu�����g�{�����Ղ��v�Ƃ����L�����łĂ܂��B
��g�{�̏��݂𖾂炩�ɂ����́E�R�������Y�搶�̈̋Ƃ��Ȃ���A�������̕ӂ�͍��w�r���ɂ���Ĕj��Ă����ł��傤�B���{�̃V�����[�}���ƌ����A�����1954�N�́u����̌����v��́u���隬�̕����I�����v�_�������Łu����̓M���V���j�̃g�����ł���B�v�ƋL����Ă���悤�ɁA���̈�Ղ͓I�ɏI�����@�������ꂽ�������ō����̌��ʂ�����킯�ł�����A�L���ɂ͂����O���Ȃ��̂ł����ɋL���Ă����܂��B
�����Đ搶�Ǝ��̕��͋���݊w��������̉��ŁA���̓�g�{�̔��@���������s�̂���`���������Ă��������A��6��1970�N�܂�16�N�ȏ�ɂ킽���ďo�ł������܂����B�����̍��͕��̗\�Z���Ȃ��A�搶�������q�̊�Ƃ�����Ċ�t����A���̕��ւ̎x�����ɏ[�ĂĂ��������܂����B�掵���ȍ~�͑��s���s������Ǝ҂ł���Ƃ������ƂɂȂ�A������̎�𗣂�܂����B�[���̂����Ȃ��d�ł��ƂȂ�܂����B�ҏW����o�Ō����Ȃ�������ɂ�����̂��ƍ����v���Ă��܂��B
���ĎR���搶�͑f���炵�����ł����B�����������̓�̂���ɊĂ��炤�ƁA���̂悤�Ȏᑢ�ɂ��e�����ڂ��Ă��������A���l�Ƃ��ǂ��������Ă��������܂����B��������Ƒ싅���ėV���Ƃ�����܂����B
��������ŕ����ł������R���搶���͂��߁A���i��v�搶�╟�R�q�j�搶�����I�����|�ɂ������������������ƍ��ł����ӂ������Ă���܂��B�ŋ߂͏o�ł͂��܂�ł��Ȃ��Ȃ�܂������A�l�Êw�⌚�z�j�ɑ���ȋƐт��c���ꂽ���X�ɏ����̊Ԃł��g�߂ɐڂ���ꂽ���Ƃ͂Ƃ��Ă����������Ƃł��B
�E�̃R�s�[�́u����̌����i�������@���j�v�i���隬������@���a29�N���s�j���Y�ɔ[�̏����]�ځB |
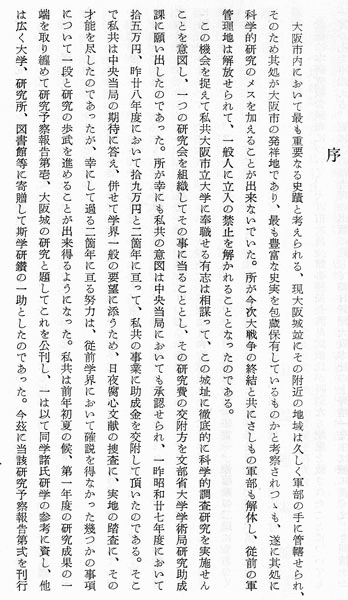 |
85�@�O���⎖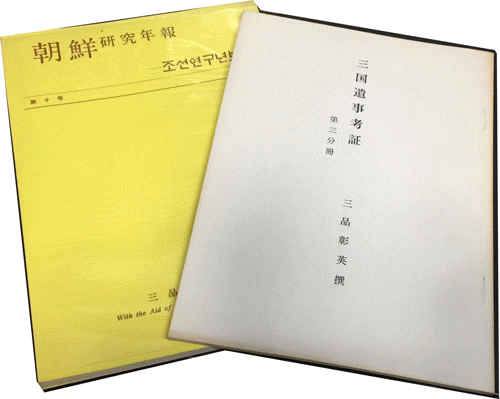
�u�O���j�L�v�͎O������i�V���E�����E�S�ρj���瓝��V�������܂ł�ΏۂƂ���I�`�̗̂��j���B���N�����Ɍ�������ŌÂ̗��j���ŁA1145�N�����A�S50���B�����āu�O���⎖�v�́w�O���j�L�x�Ɏ������N�Ñ�̗��j����13���I�������B�w�O���j�L�x�ɂ��ꂽ���������^�����B���N�ɂ�����w�O���j�L�x�Ɓw�O���⎖�x�Ƃ́A�قړ��{�ɂ�����w���{���I�x�Ɓw�Î��L�x�Ƃɑ�������A�Ñ�j�̊�{�����ł��B
���|�ɂ͒��N�j�̌����ҁE�O�i���p�搶�̒m�Ȃ����āA�u���N�����N��v�Ɓu�O���⎖�l�v��1958�N����n�[�o�[�h�E��������������̌�����ŏo�ł��܂����B�i�g�o��{�E�f�[�^�j
84�@���{�̕��@���ƂŃI�[�v���Ɠ���
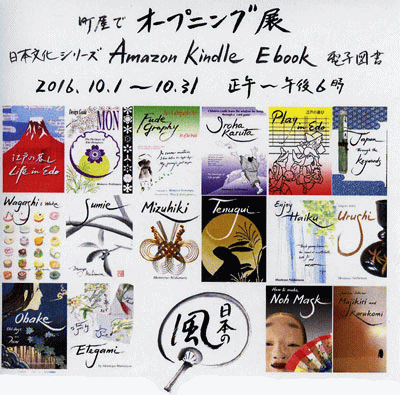 4 4 |
�u���{�̕��v�Ƃ������{�̕������C�O�ɏЉ��O���[�v������܂��B���[���Ɠ����̐^�Ŋ�������Ă����܂������A�a�͋��I�Ƃ������ƂŁA�������Ɋ����ꏊ���ڂ���A�I�[�v������܂����B
�����Ď�Â̐��W��������[�_�[�ɃC�M���X�ɓ��{�������Љ�銈���ɎQ���������ŁA�������s�i�o�̂���`���������Ă��������܂����B
�I�[�v�j���O�Ɏ��̏������镽�ƕ���̕����`�����Z�Ȉ�o�̛������������݂܂������A�傫�����Ĕ��o��u���Ă��炢�܂����B�܂����A���̓��т����������܂����B |
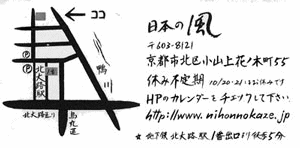 |
 |
 |
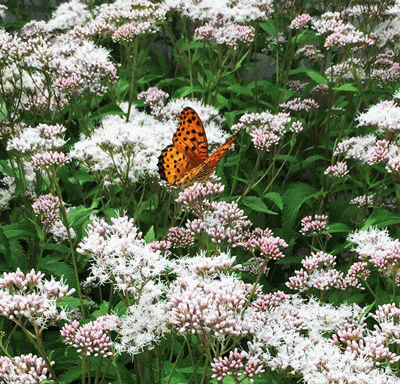 |
 |
����
1998�N�A���s�s������匴��̌Òr�̒�h�Ŕ������ꂽ���т̖쐶���匴��_�Ђ̋����ƒ������s�E�������߂��̔��ň�Ă��Ă��܂����B���̐�Ŋ뜜�A�����j�a�r�̓v���W�F�N�g�𗧂��グ�A�H�̍������s���ɉԂ��炩���Ă��܂��B���N���~���H�����⋞�s�䏊�A�����ʓ��ɉ��S����u���ӏ܂ł��܂��B���т͕������ォ��͌����ӂɍ炭�R�쑐�Ƃ��Đe���܂�A�������������т͍����Ƃ��Ă��p�����A�����̏����B�͓��т����܂ɓ���A�\��P�ɂ��̂��Ă����悤�ł��B
�I�єV��
�u��ǂ肹�� �l�̂����݂� ���� �킷��ꂪ���� ���ɂɂق��v
�Ɖ̂��Ă��܂��B�܂��w��������x�\�l���̑�30�̓��т̊��ł͋�顂�z���[�����r��
�u������̘I�ɂ��铡�т��͂�͂����悩���Ƃ�����v
�Ɖr��ł��܂��B
�ʐ^�͂j�a�r�~�n���ŎB�e�A�����ς����X�������Ă��܂����B�ǂ����Ă����ɉԂ�����Ƃ킩���ł��傤���B��͂�[���̂悤�ɓ����ɗU��ꂽ�̂ł��傤�ˁB�i161010�j |
83�@��S���q�ƃ��b�P�i��
 |
�������������قŌ��J����Ă����u��S���q�v�i����j�͌㔒�͖@�c�i�������㖖���j���O�\�O�ԓ��ɔ[�߂��u�Z���G�v�̈ꕔ�̒��̉�S�҂ł��̊G�͐H����S�ł��B����H���Ă��܂��B
�Ƃ���Ō㔒�͖@�c�͌��o�����l���ł������A�n���Ɋy���������炱�������G�����[�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�������m���p���ɂ��s���܂����B�����ł̓h�C�c�����ʼn�ƃ��b�P�i���̍�i���W������Ă��܂��B���̒��Ŗڂ��������̂��u��l�����Ԃ邤���������̃I�[�i�����g�i��p�����فj�ł��B�����͎��ł�����E�T�M�B�̔����ł��B��l�����Ԃ�A�����ςĂ��܂��B�ɉ��ł��ˁB������Љ�h�ł��B�i2018.8.8�j
|
 |
82 ���̊C�̂Â��̊C��
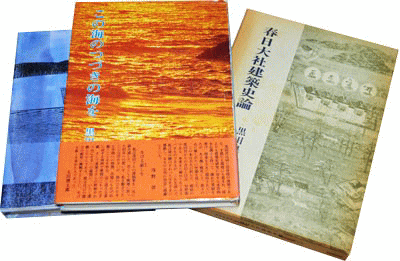 |
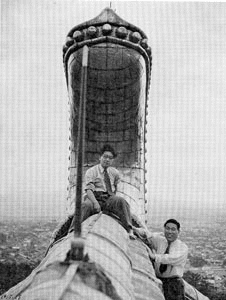
���厛�啧�a�剮���Ɍׂ鍕�c�f�` |
�߂����ւ肪���q����͂��܂����B���ɂ���o�ł����u���̊C�̑����̊C���v���o���ꂽ���c�N�q�i�������j�����N�\���S�ŖS���Ȃ�ꂽ�Ƃ�����������̕ւ�ł��B��\���炢�܂Ŗ��N�I��L�O���ɖ����_�Ђɍs���A�푈���̊���������Ă��܂����B����͐푈�Ƃ����\�͂��V���Ԃ��Ȃ����c�v�Ȃ������A�O�r�m�X�̎Ⴋ�w�҂��A��ʐl�Ƃ��Ă��܂�������ł��B
���c�f�`�i�̂�悵�j����͑吳�O�N�i1914�j�É������܂�A���a��Z�N�i1945�j�t�B���b�s���Ő펀�B���É������H�Ɗw�Z���z�ȁi���E���É��H�Ƒ�w�j���ƌ�A�ޗnj��ÎЎ��C�����Ζ��ƂȂ�Z���Ƃ��Ē����������A���ɋ���������������̒����畧�������A���ꂪ�̂��ɔ̎R�c�����P���Ƃ킩�荑��ƂȂ�܂����B�܂��t����Ќ��z�̌����͏����̔��m�_���Ƃ̎v���ŏ�����܂�������̑��ʼn����A�����̂܂ܐ펀�B���e���̂��������喼�_�����E�̕��R�q�j�搶�ƓޗǑ�w�����E�̉��c�p�j�搶�͂��̘_���̑f���炵�����v���A���ɏo�Ȃ����Ƃ�ɂ��݁A�t����Ёi�t��������j�̉����āA�u�t����Ќ��z�j�_�v�Ƃ��ď��a�\�O�N�i1978�j���ɂŏo�ł���܂����B���肪�������ƂɊ������A���݂͐�łƂȂ�܂����B
���ĉ��l�E���c�N�q����͐���l���q������A����Ȓ����������A�v�N�̋Ɛт�ɂ��݁A���R�搶�≪�c�搶�ȂǑ����̉����Łu�t����Ќ��z�j�_�v���o���ꂽ��A���c�f�`����̂�����̍˔\�E�̂���r�W�Ƃ��āu���̊C�̑����̊C���v���Ăю��̂ق��ŏ��a�\�ܔN�i1980�j�o�ł���܂����B�J�o�[�ʐ^�͈⎙�E���c�j�v����B�c�O�Ȃ��炲�q���͂����Ԃ�O�ɂ��S���Ȃ�ɂȂ�A��������ɊŎ���Đ����ꂽ�����ł��B�v�N�Ƃ��q����l�̍����킹�ĖႢ�A�S�܂Ő�����ꂽ�̂ł��傤���B
���N�i�����N�j�ꌎ���A�V�c�c�@�É����t�B���b�s����K��A��v�ҕ�n�ɍs����܂����B���{�l��n�̋L�O��͐ō�����⍜���A�N�q����̐펀�̌���̂��ƁA���O�N��Ɉ⍜�����͂��܂��������͋�ł����B�i2016.2.2�j |
81 ��{�̍���
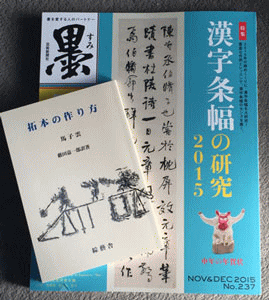
�G�����u�n�v�H�����u��{�̍����v���Љ��܂����B�u�n�v�ɂ�20�N�ȏ�O���炨�t������������A�����g�̏Љ��A�L�����ڂ��Ă��������܂����B�ߔN�����E�����q���ŏ������~�C���ł͂���܂����A�������ȃO���r�A�Ŋ撣���Ă����܂��B���ꂩ��������̊����ɂ܂��܂��̌��������F�肵�܂��B�i2015.11.11�j�@
80 �����l�Êw����
���Y�ɂ�1967�N�A�ҏW�E�̔������u�����l�Êw�����v�͋��s�����w�l�Êw������E���]�c�Y�������ŁA�����l�Êw�Ƃ������𐢂ɏo�������ЂƂȂ�܂����B���ꂩ�甼���I�A��������V���ŊC�m�����w�ҁE�╣���������グ���A���݂̐����l�Êw�̌��Љ��Ă��܂����B�����T�O�N�̋Z�p�̐i���Ő����̑����̈�Ղ�╨���������꒲������Ă��܂������A2001�N���l�X�R�Łu����������Y�ی���ň╨�̈����グ���֎~�ƂȂ�A�ߔN��B�Ŕ������ꂽ�����D�͈����グ���Ȃ������ł��B�����Ă͒n���C�̊C�ɒ��D���物���������グ��ׂ������Ȃ�Ă����͖̂��ɂȂ�܂��ˁB
�Ȃ��{���͎�ɔ��i�̐���̈�Ղ�╨�̌����ł��łɐ�łƂȂ��Ă��܂��B
�i2015.8.8�j
79�@���[�@�k��V���{
 |
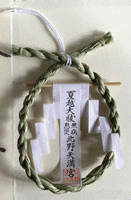 |
 |
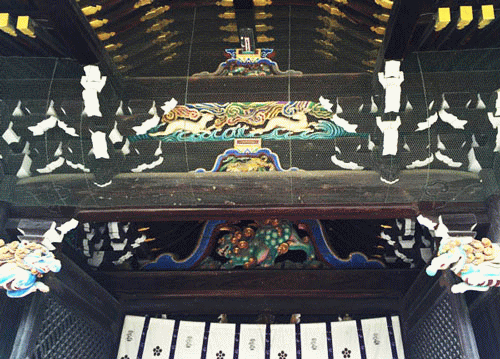 |
|
���N�̎��[�͂����ɂ��̉J�ł��B����k��V���{�̖{�a�ɂ��鎵�[����ɒZ�����Ԃ牺���Ă��܂����B�V�_����͐������^�������J�肵���_�ЂŁA�w��̐_�l�ł��B�����ĉz�̂��w�肵���̂ł����A�C�w���s���ł����ς��A�݂Ȃ����Q�q����Ă��ė��Ίw��̐_�l�ł��B�i�~�j���̗ւ����������܂����j
���Ė{�a�ɓ����͒���ŁA�����ł͎O����Ƃ������̂ł����ʖ��u�������̖�v�ƌĂ�܂��B�B�O����Ƃ͎O�̌��E�����Ɛ����w���܂����A���̖�ɂ͑��z�ƌ��ƎO�����̒���������܂����A��������܂���B����͕�������A�����̐^�k�ɂ����̏�ɖk�ɐ����P���Ă����̂ŁA�����͕s�v�Ƃ��ꂽ�ƌ����Ă��܂��B�J�̎��[�͐������̎��[�ł�����܂��B�i2015.7.7�j |
78�@���Ր_�`

|
 |
 |
���|�ɂ̒n��̎��_�l�͏���_�ЁA���Ղ̂R����P�W���ɍ�A���N�O����䏊���̒ʍs��������A��O�Ő_�`�S���ł��B�͓̂V�c�ȂǓa��l�ɂ����킢�͕��������̂ł��傤���B���������Ώ㐙�{�������O�}�ɂ����̍Ղ肪�`����Ă��邻���ł��B�����͉䂪�ɂ̑O�ōs�ʂ蔲���A�_�`����Ԃɍڂ��Đi�ނ����̍Ղ�Ȃ̂ł����A�䏊�ł͎O��̐_�`�����ꂼ��|�����Ō��ɒS���ŗ���܂��܂��B���o�������Ă̑呛���B���ɍŌ�̖��L��̐_�`�͂Ă���ɐ_�Ђ̉����Ɠ�������i�䂪�����ŏ��Ɋo�����Ì��z�p�ꂿ���j�����A�����͐_���˂��Ă���̂ŐԂ��z�ʼnB���āA�傫�ȗ��炵�Ȃ���u���炢�������I���炢�������I�v�ƒS���܂��܂��B���Ղ�Ƃ��Ă͋��s�ŌÂ������ł��B�O���l���������Ă����܂����B�ꎞ�͒S���肪�����Ȃ��Ă����̂ł����������Ċ������ł��ˁB
�Ō�͖k����A�������Ɠ��u�Б�w�̉���ʂ�Ђɖ߂�܂��B����_�Ђ͊����V�c����n�܂����_�Ђł����A�������m�̗��̒[���ɂȂ����Ƃ���ł�����܂��B�i15.6.6�j |
77�@��펛���ː�
 |
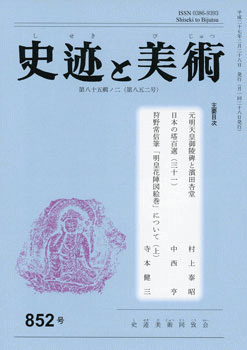 |
�j瑔��p������1010���͑�������˂đ�펛�ł����Ȃ��܂����B���͊Ď��Ƃ��čĔC����A���ꂩ����{��̂���`�������܂��B�����j�k�ł��q�ׂĂ��܂��悤�ɁA�{��̑n�ݎ҂ŐΑ����p�̖��t���e�E�쏟�����Y�搶�Ǝ��̕����c�È�Y�͒��w�̎�����̐e�F�ł��݂��ɐ����������ē��{�̔��p�A���j�̌��������Ă��܂����B���̉��Ŏ������͂Ȃ��炨��`�������Ă��܂��B�{��̉�u�j瑂Ɣ��p�v851�����炱�̈�N�A���̍̂����u�j�˔@�ӗ֊ω��Ε���{�v���\��������܂��B
����̌�͑�펛�O��@�A���ɓ��ʎj�ՁE�����̒뉀���C���Ɍg������{��̌���E��蔎������ƂƉ���E�g������̂��b�ƕ̂��ƌ��w���܂����B�{��͖L�b�G�g���c���O�N�i1598�j���̉Ԍ��̌�A�v���܌��Ɋ�������������ɏG�g�����A���̌��펛����`�o�y�@�ɂ���Z�N�����č��ꂽ�����œ��{�L���̃X�P�[���̑傫���₩�Ȓ�ł��B���ł���̒��S�ɂ���u���ːv�͊Ǘ̍א삩��M���A�G�g�A�ƍN�Ɠn�����e���̐ƌ�������̂ł��B���Ƃ͔\�E���˂Ō����悤�Ɍ������킩��̂����̂���ϋP�Ί�ł��B�߂��猩��Ƃ��̑��݊��͂��������̂ł��B
����3��8��1011����͖������ł��B�i2015.3.3�j |
76�@�����@�P����
 |
����26�N10���C���Ȃ����F�������@�ɍ��N1���j瑔��p������1009����Ƃ��ĎQ�����܂����B�܂��F����_�ЂŐ����Q�q�A��������N�������̏C�����I���A���{�ŌÂ̐_�Ќ��z�Ƃ��đh��܂����B�N�֔N�㑪�肩��1060�N�n���̍���{�a�Ɣq�a�A�{�a�͎O���Ђƕ�������Ȃ�A�����̂������œ��Ђ��Y��Ɏc���Ă��܂��B�܂��q�a��1215�N���z���ꂽ�Q�a���ŁA��������̏Z����\�Ƃ��Ă͗B��̂��̂ł��B���ɖK�ꂽ�̂͋����A�����́u��{�v�́u�ďH�Ƃ茾63�F�����f���v�ł������������B
���Čߌ�͐��E������Y�F�������@�ɎQ��܂����B�����@��1052�N�A���������̕ʑ��𗊓������@�ɁA���N�ɂ͈���ɔ@�������u����P���������āA�Ɋy��y���Č����܂����B���͍�����45�N�O���|�ɂŁu�Ì��z�ו���b�v���o�ł���ɂ�����A���҂ł����������c�È�Y�ƉF����_�Ђƕ����@�ɖK��B�e���A�{�Ɍf�ڂ��܂����B���̖{�͂��������܂Ń����O�Z���[�Ƃ��č�������Ă��܂��B����C�����ꂽ�P����������ƂƂ��Ă�������������F�i�O�y�j�ƍ������œ��{�̔��ӎ��ɂ��������̂ɂȂ��Ă��܂��B�����̓��m�N���ł̎ʐ^�ł�������ǂ��������̂̃J���[��������Ĕ̏o���Ȃ������ł��B�����Ă͊ՎU�Ƃ��Ă����F����_�Ђ��A�C���Ȃ����P�����������̐l�����Ă����ē�����Ă��܂����B �Ȃ��F����_�Ђ̔�富҂͓�������̋M�d�Ȉ�\�ł��B�Ȃ������@�����́u��{�v�̃M�������[���������������B
�����m�N���ʐ^�́u�Ì��z�ו���b�v���B |
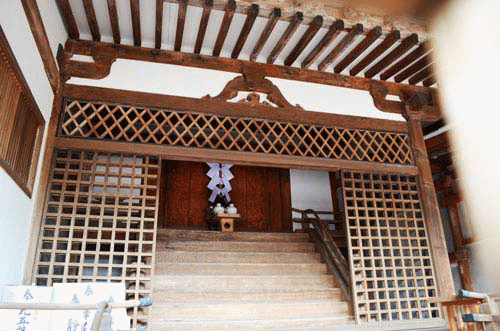 |
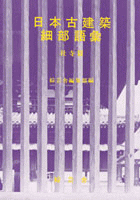 |
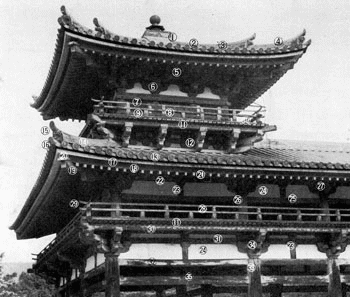 |
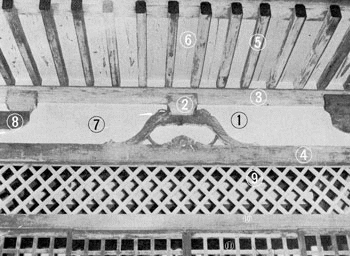 |
75�@My�����
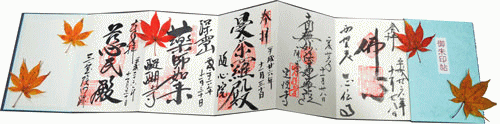 My����ł��B������ƑO�̂P���u���Ō��{�ɍ�������̂ł��B�H�̋��s�k�Ɠ�������܂����B My����ł��B������ƑO�̂P���u���Ō��{�ɍ�������̂ł��B�H�̋��s�k�Ɠ�������܂����B
�E���琼��̐��`���A����̌��x���A����̐��g�@�A�����đ�펛�{���ƎO��@�B���̍g�t��Y���āE�E�E�B
|

���k����ɂ��鐳�`���͗ՍϏ@��T���h�@�g�ˎR�@���`�썑�T���B�d���̕���Ə��x���B�̎��q�̎��n���̒뉀�ŗL���ŁA��b�R���،i�ɁA�͎R���ɐ�u���̂łȂ��T�c�L��z�u����Ƃ����a�V�Ȕ��z�ł��B |
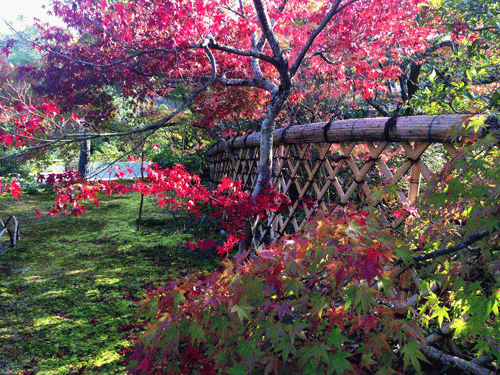
���k����̌��x���͖{������x�̂����ł��B�P�U�P�T�N����ƍN���炱�̕ӂ��q�̂��A���x�𒆐S�Ƃ���H�|���Ƃ��ĉh���܂����B�����動������芪�����x�_�ɂ��݂����f���܂��B
���ׂ̌������͍��NJR�́u���������s�ցv�̃|�X�^�[�ɂȂ������ߑ����̊ό��q�������܂����B
|
���s�R�Ȃƕ����̋��ɂ����펛�͍O�@��t�̑���q������t���W�V�S�N�n�������^���@�̑��{�R�ł��B���x���̍Č���ʂ��č����܂ő����Ă��܂��B�ƂɗL���Ȃ͖̂L�b�G�g�̑��̉Ԍ��ł����A�g�t���f���炵�����ł��B
�d���A�����͍���ł��B�܂������ɂ���O��@�̓���⏑�@������B�G�g�v�ƌ�����뉀�͍��̓��ʎj�ՁE�����ɂȂ��Ă��܂��B |

��펛�̉��ɍs���ƕٓV��������A�r�Ɏʂ�g�t�ɂ����Ƃ肵�܂��B |
 |
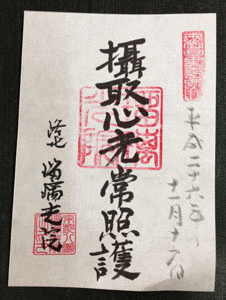 |
�ڗ����@�̂����
���s�����ɂ���ڗ����@�͏��a�̏��ߌ��z�ƒ����O��ƒ�t���쓡�E�q��ɂ���đ���ꂽ�����z�ƒ뉀�ł��B���Ă����͓��{�莛�n�̂����ł�����̂ł����A�l��s���Ȃ̂������͊e����������Ă��������Ƃ̂��ƁB
������ăX�^���v�����[�ł���ˁB������Ƃ�������B�������ł������������������X�ɂ����Ă���܂����B�L�������܂���B�i2014.12.12�j |
74�@�ۂ̉Y�E�����̕�����
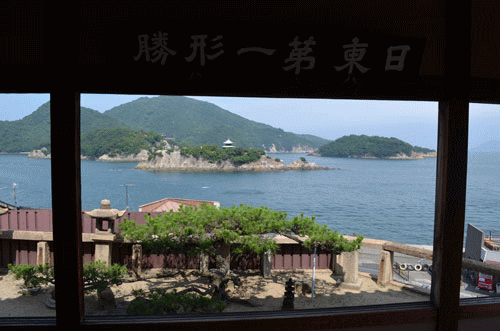
�j瑂Ɣ��p������1006����̂��m�点�B����͎����S�����܂��B�����̂�����A���߂��̕��͂��Q�����������B�ڂ����͂��₢���킹���������B������ߐ�܂����B�i141005�j
73�@�j瑂Ɣ��p
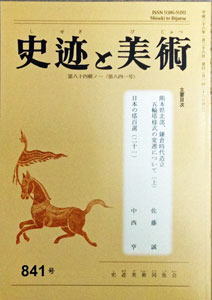
���M�c�È�Y�Ɛ̂���̗F�l�ł������̐쏟�����Y��̑n�������G���u�j瑂Ɣ��p�v�̍������s��841���ɁA��N�U�����R�̋S�̏�ɍs���������o���܂����B�܂������̎ʐ^���f�ڂ���܂����B
�����č�����S�O�N�قǑO������𗊂��đ喴�c���痈����B�j���A���N������ɏZ��ł��܂��������s�̋��͂܂����ƌ����Č̋��ɋA��A�����������̎d���ɏ]�����A���̂��і{���ɘ_�����f�ڂ���܂����B�i�m���ɓ����̋��s�̋��͂܂��������B
�u�F�{���k���A���q���㑢���@�ܗ֓��l���̕ϑJ�ɂ��āi��j�v�������j
�Ȃ��j瑂Ɣ��p������̗��͂S���łP�O�O�O����}���܂��B998��͋��s�q�ω@�ȂǁB
72 �X�_�ꂳ��
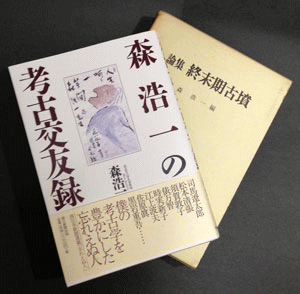
���܂��܉䂪�ɂ̃z�[���y�[�W�ҏW���A�k��B���{�����L�O�قŎn�܂����u���{�����Ǝהn�䍑�W�v�ɕ��Ƃ̉������Ȃ��o�Ă��邱�Ƃ������Ă�����A�j���[�X�œ��喼�_�����X�_�ꂳ��̂�������m��܂����B�����ĉ䂪�Ƃɂ����Ă��������A�u�I�����Õ��v�X�_��ҁi�����[�j�ł͕��̉v�c��D�l�̈�҂��ڂ��Ă�����Ă�����A�����ƊW������܂����B�ŋ߂ł́u�X�_��̍l�Ì�F�^�v���Ƃ��Ă������[���ǂ܂��Ă����������̂ł����A���Ƃ����i���N2���L�j��ǂނƉE���ؒf���ꂽ�Ƃ̂��ƃr�b�N���A�Ă��Ă���܂����B�[�������̈ӂ�\���܂��B�i20130809�j
71�@���ƃA���o��
70�@������
 |
 |
�\����{����ѐ��F�Ɏg�������т͎��̖тłł��Ă��܂��B ���ɓ~�т��Ėт̕����_��ł��B�т̒����ɂȂ��Ă��Ă��炩��������ێ����܂��B���тƂ��đ��鎞�����ǂ���Ȃ��悤�ɂ��邽�ߎ�Ԃ�������܂��B
���̍��т̖т͔����������肵�܂������̖т͔���������̂łȂ������邽�߃X�g���[�̂悤�ɐ܂�Ă��܂��܂��B�����h���̂ɂ͐��̒��ɂ��Ă��������킯�ł����A���܂ɂ����g��Ȃ��ꍇ�͍��x�͕�������܂��̂ł��������킯�ɂ��s���܂���B�g��Ȃ��Ƃ��͎��X���点�Ă��������B
�ʐ^�͔�r�I�V�������̂Ǝg���Â������̂��r���܂����B�Ȃ����ɍL�����Ă��邨�����ŁA��i�̂����L���Ă����̕����ł����߂鋰�ꂪ�Ȃ��A�܂����ɖ������Ȃ��̂łƂ��Ă��L���₷�����тł��B���ׂĒ����g���Ă���`���I�ȓ���ɂ͗��R������킯�ŁA���̂��̂ő�p���Ȃ����������ł��傤�B�i130503�j�����ђ��� |
69�@�A�L���@��F���m
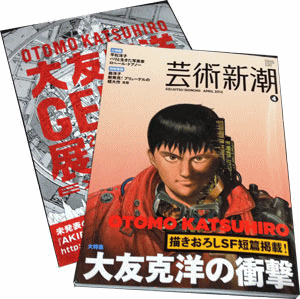 |
����Ƒ�F���m�͊C�O�ł͈��|�I�Ȏx�����Ă��܂��B���ɃA�j���ɂȂ����u�A�L���v���E�ɓ��{�̃A�j���[�V�����̐�삯�ƂȂ�����i�ł��B
�P�X�W�P�N�u�C���͂����푈�v�ł̕`�ʂ̑f���炵���Ŏ������ڂ��Ă��܂����B
�u�|�p�V���v�Q�O�P�Q�N�S�����ŕ\�����������̂����悪�A�[�g�Ƃ��F�߂�ꂽ����ł��傤�B
�T��23����H�t���̂R�R�R�P��������chiyoda�ł̌���W���ς܂����B�\�ɂ����̂͑����̃t�@�������邩��ł��傤�B�m���ɂقƂ�ǂ��Ⴂ�l�����ł����B
�W����Ƃ��Ă͕�����Ȃ����̂ł����B������l�̖���E�̗E�E���Y�F�́u�Ō�̃}���K�W�v���S�N�O�ɏ��̐X���p�قŊς܂������A������̕����W����Ƃ��Ă͗y���ɗǂ������Ƃ������܂��B
���Ƃ͐X�r���ŊJ�Ò��̔��c�h��YOnePiece�W���ς����ł��B�i2012.6.1�j |
 |
 |
| �u�����v�̈��� |
�W�����ɍ��ꂽ�� |
68�@One�@Piece
 |
�f�G�ȔN�ł������͂��̓e�N�I ���̔N�ł��������������N�A3.11�����{��k�ЂŖ����i���Y����Ȃ��߂����N�ɂȂ��Ă��܂��܂����B
���̓��͔߂��E�T�M���A�������̂Ƃ��̂��Ƃ̓��d�A���{�̑Ή��œ{��S���A�ŋ߂̖���}�����Ɗ����̌����ɓ{��͎��܂炸�A���̂Ƃ��ɂȂ��Ă������Ă��܂��B�������̒���ς��Ă���Ȃ�������I
�u�����s�[�X�v�͌���64��2��5�疜���A�ŐV������400�����Ƃ����������̂悤�Ȗ���A��Ƃ̔��c�h��Y�͎��Ɠ����u�e�N�v�A60���܂œǂݏI���܂����B�o�ŕs���̒���l�C��f���Ă��銴���ł��ˁB�Q���R���ɂ͂U�T�������A���ď��ŋL�^�X�V���H
���̍�i�͎q�ǂ��ȊO�ɂ���l�����Ɏx������A���낢��]����Ă����܂��B
���l�̎����q���g�������ł����A���ɂ̓M���V���_�b�́u�I�b�f�Z�C�v���v���N������܂����B�����V�[�Y�Ƃ�����ꂽ�p�Y�̑s��Ȗ`���k�A�f��ɂ��Ȃ��Ă܂��B
�����Ă������C���b�ł�����A�ŋ߂ł́u�p�C���[�c�E�I�u�E�J���r�A���v�����~���̂悤�ȋC�����܂��B
�Ƃ���ŏ����Ȃ���A���͊C������D���ł����B�G��`�����鐂�`���A���ɂ͒|�̌��������A��щ���Ă��܂����B�������f��͊C�����m�@�劈�I���A�C���D�����������Ă����A�����v�̖����肪�����Ă������X�g�V�[���ɐ�������Ă��܂����B
�Ȃ�Ƃ��ꂪ�����āA���Z����t�F���V���O���ɓ���A�Ȃ�ƂP�N�̗��K�ŁA�S�����s��\�Ƃ��ĐV���܂ł������قǂł����B���ʂ͎U�X�ł������B�i2012.2.1�j |
 |
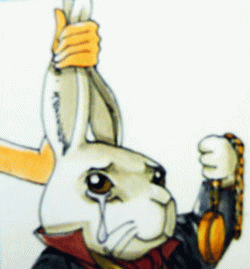 |
67�@���E���E��E�J
 |
 ��Light ��Light
|
| ���̓��j���A�Z�{�~�b�h�^�E���̃N���X�}�X�C���~�l�[�V���������ɍs���܂����B�N�X������Â炵�āA���N���f���炵�����̃y�[�W�F���g�B�S�K�̃C�^���A���X�g�����{�^�j�J�ł̐H���̌�A�C�P�����{�[�C����̈ē��Ńe���X����̃C���~�l�[�V�������ς��܂����B |
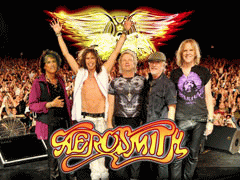 |
 ���@Sound ���@Sound |
|
���j���̖�́@�����h�[���Łu�G�A���X�~�X�v����40���N�I���Ȃ��I���W�i���E�����o�[�ŌN�Ղ��鐢�E�ō���̃��b�N�o���h�A7�N�U��ɗ����I�������ł��B�h�[���ɂ̓|�[���E�}�b�J�[�g�j�[���ɍs���Ă���20�N�Ԃ�A�����ȃ��b�N�Œ����̂����߂āA���܂��ɃA���[�i�Ȃ̕��䂩��10���[�g���A�قږ����̊ϋq�ȁB����A���o�͔�r�I�V���v���A�ł��X�e�B�[�u���E�^�C���[�͍ŏ�����Ō�܂łԂ�����A�ԃX�^���f�B���O�ŁA�V�e�ɂƂ��Ă͊y�������Ă�����Ƃ炢�E�E�E�Ƃ������Ƃō��������ɂ��B���{�ł͗L���ȃA���}�Q�h���̎��̂��̂��܂������A���̋Ȃ��悩�����ł��B�{���̃��b�N�͐����I
|
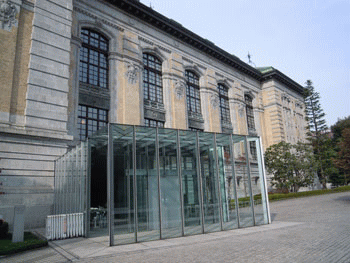 |
��@Silent
��閾��������́A���̍��ێq�ǂ��}�����A���Ƃ͒鍑�}���قƂ���1908�N���l�T���X�l���������ꂽ�����Ŗ������m�����z�A�ׂɂ͏��a�����̍��c���P�L�O�ق����艩�t�����ǂɉf���Ă��܂����B�����͌��ݓ������������ُ��L�ŁA�q�ǂ��}�����͍���}���ٕ��قł��B���Ă����œW�����Ă���u���B�N�g���A���̎q�ǂ��̖{�v�̃A���X�̖{���ς܂����B�Â��Ɋ����B
|
 |
�J�@Bonds
23���ɖK�ꂽ�������������فu�@�R�Ɛe�a�W�v�ɏo�Ă�������u���{�莛�{�O�\�Z�l�ƏW�v�����ꂽ�����̒����ȉ̐l���ƌÕM�ƁE�����������̂�������Ɛe�����Ȃ�܂����B
���s�͍����{�莛�����{�莛�������̐M�҂̃o�X�Ŗ��܂��Ă��܂��B���낢��ȕ��Ƃ��J�̒��ɐ����Ă��邱�Ƃ��������Ă��܂��B
�Ƃ���Ŕ����ق̍���i���r�c���~�E����ɂ���Ԗ�ƑΔ�j���J���Ă��Ē�����������̋�ǂ������܂����B�i2011.12.10�j
|
66�@��C�̔���
 |
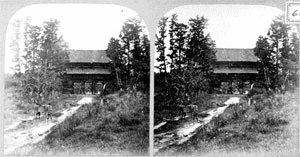 |
�����̋�C�W�u�W�ڎw�A�v�Ȃǂ̏����ς悤�ƒx�X�Ɛi�܂Ȃ��ŏ��̕��͂�����߂āA���̙֑ɗ���\�����W�����A�����̖{���Ɣ�ׂ悤���Ȃ��A��p�����ق̖����ɑ��āA����������ٗ��ɕs�����c���Ȃ���̊ϗ��ł������A��������_�@����u�@�؋���F�����v�_�쎛�i�X�b�j�̂��܂�̐_�X�����ɉ��Y��Ē��ߓ���܂����B
�����̂�����̓��ʓW�u�����Ɣ~�����g�v�i�N�����e�i�C�ʐ^�j���������̓��{�ƒ����̌i�F���ʂ��Ă��܂��B�����~�e�i�C�ʐ^�E���厛����̑O�����ڂ��ڂ��A�����悤�Ɍ̋{�̂Ȃ������ڂ��ڂ��A100�N�ő����̂��̂��ς�����悤�ł��B�}�^�ɂ͕ʔ��̂R�c�ዾ�����Ă݂�Ɨ��̂Ɍ�����ېV�O�̃X�e���I�ʐ^���ςĂ���ƁA�R�c���܂�ς���Ă��Ȃ��C�����Ă��܂����B
�܂��������Ԃ��������̂ŁA���m���p�ق́u�Ñ�M���V���W�v�ɂ����܂����B��p�����قł̓G�W�v�g�ƃA�b�V���A�Ŗ��������̂ŃM���V���͌��Ȃ������̂ł��B�ڋʂ́u�~�Փ����v�͎ʐ^�ƈ���Ă������������ς��A�j����̂Ȃ����`�ɂ͊������܂������A�����ƌ��Ă����肪�Ȃ��������悤�ȋC�����Ăǂ��ƂȂ������ۂ������Ă��܂��܂����B����Ȃ₳�����Ȏ�œ������邩�S�z�A��͂�����͎m���̂悤�ȑ̋�̕����D�݂ł��B�Ƃ���Ŏ��ɂƂ��ĐV�����͋I���O600�N����̍���������ł��B�{�Ȃǂł͍ו���������Ȃ������̂ł����A�f���炵�����`�ł��B���Ă��̔��p�ق����E��Y�ɓo�^�\�����ꂽ�Ƃ������Ƃ炵�����ǂ��������̂��킩��܂���B���E�R���r���W�G�v������Ȃ̂����������A���{�ɂ͂����Ɠo�^���������̂�����Ǝv�����E�E�E�B �i2011.10.22�j |
 |
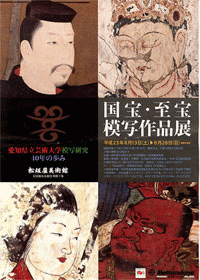 |
�Ȃ����É��ł͈��m�|��́u����E
����͎ʍ�i�W�v�����㉮�ł݂܂����B
�f���炵���͎ʍ�i�ł����B |
65�@��p������
 |
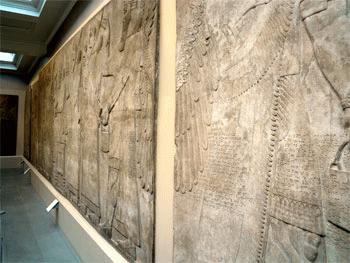 |
 |
��p�����قɓ����āA����̉~�`�����̍����̃h�A�����ƁA�K���X�P�[�X�ɓ��������[�b�^�X�g�[��������܂��B�����قł͈�ԍ��G����ꏊ�ł��B���̉��̓��\�|�^�~�A���A�b�V���A�̃R���N�V�����B�f���炵���I�ǖʂɊ���Ђ����Č����邵�A�ʐ^�̂����B���܂�l�����Ȃ��̂ł��[���ƌ��Ă��܂����B�I���O8���I�̍�i�Ȃ̂ɁA���C�I���̗Y�����т��������Ă������ł��B
�C���N�ɂ�������푈�Ŕj��Ă����ł��傤�ˁB
���̖��̓C���h�̃T�[���`�̕��Β��Ƃ��̃��\�|�^�~�A�̐Β��A�ǂ���ɂ�����̂ł���Ŏv���c�����Ƃ���܂���B
�i2011.0723�j |
64�@���s��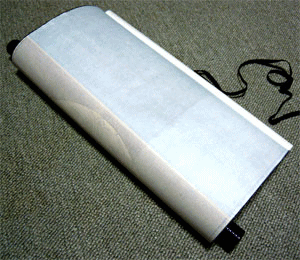
�����{��k�ЂŁA�����̂��̂��s�����܂����B�ŏ��͐��⋍���A�K�\�����ȂǁA�܂��d�͕s�����ǂ��ł��ł��B
����A�����̍u���ŁA����p�����s�����Ă��ă`���V������Ȃ��̂ŁA������̈���������o���Ȃ��Ȃ�܂����B
�����Ċ|���̗��ɂ���㊪���E�E�E����͕������얓���Y�n�ł��B���̂̋N�������������ɋ߂��̂Ŕ������o�Ă��܂��B���ꂩ��ǂ��Ȃ�̂ł��傤���B
���s�ɏZ��ł��Ă������Ɖe�����o�Ă��܂��B�����{�̕��͂ǂ�قǕs�ւȕ�炵������Ă���̂ł��傤���B�܂��������Y�ł��Ȃ���Ώ����̐������s���ł��B����������������邱�Ƃ��F��݂̂ł��B
���|���̗��̈�ԏ�̔��̌����㊪�i�������Ƃ��얓���j�A�����ꂽ�Ƃ��Ɏ��S�̂�ی삵�܂��B�֘A�L���u�|���ƛ����v�i2011.4.20�j
63�@�����ٌw��
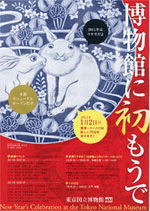 |
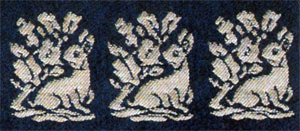 |
 |
| �Ƃ������ƂŒx�܂��Ȃ��琳���Q�U�����������قœe�̓W����ς܂����B����قǑ傫�ȓW���łȂ����Ďc�O�ł������A�e�̂��Ƃł����珬����܂�ł����B
�����ň�ԕ��ɂȂ������Ƃ́A��D���ȁu�ԓe�v���l���A���͒����̗��ɉ_�C���̃f�U�C�����Ԉ���āA�e�ɉԂƂ��Đ��܂ꂽ���l�������Ƃ������ƁB���{�l���e�D�����Ƃ������Ƃ̈�[�������ł��B�����D�ޒ����Ɠe����������{�A���{�l�͕��a��`�҂ł���B
���łƂ����ĂȂ�ł����u���R��v�ƕ������ی�v�W���ς܂����B���{�����łȂ��A�W�A�̕������ی�ɐs�͂��ꂽ���R����̋Ɛт͂������Ǝv���܂����A�`���ꂽ�G��䩗m�Ƃ��Ăǂ����s���g�̍���Ȃ����i��Ɏv���܂��B���i��Ȃ瓌�R�@�̕����V���[�v�����A�C���h�̊G�Ȃ�H��s�邳�������E�E�Ƃ������Ƃł��܂苻���͂���܂���B
���Ă������A�����H�������铌�m�ق͏C�����A�@�����ق̃��X�g�����ŐH���A�����ɗ���ƕK���K���̂������̒�ɂ���u���\�։@��a�v�A�����ς�ƍg���~���炢�Ă��܂����B
����ɂ��Ă��ŋ߂̔����ق���ςł��ˁB�����������c�ƁA�f�p�[�g�畉���I�i2011.02.20�j
|
62�@�ɕʁ@���R�l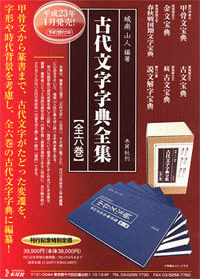
���ɂƂ��ėB��̒��l�������F�l���S���Ȃ�܂����B�ނƂ�2�N�قǂ����Ă��܂���ł����B�m�点���Ȃ��̂͌��C�ȏȂ�Č��ߍ���ł����̂ł����A�������l���烁�[���ŖS���Ȃ����Ƃ����m�点�E�E�E䩑R�����I
������30�N�قǑO�A���q����o��w���������̏Љ�ŏA�E�����ɗ��܂����B�����l���ق��قǂ̎d�������Ă��Ȃ������̂ł��f�肵���̂ł����A���܂��ܓW����̎�t���˗��A�����Ɏ�`���ɗ����F�l�Ƃ����ďЉ�A�������Č������邱�ƂɂȂ�A�Ԃ���莝�����������l�����������̂ł��B
�ނ͓������łɏ��ƂƂ��āA�܂����|�ƂƂ��Ċ������Ă��܂������A�d�x�̉ԕ��ǂ̂��ߓ��|�⏑�삪�������ꂽ���Ƃ������āA�����̌����ɖv�����Ă����܂����B���ʂ�1980�N�ォ�猻��A�������̏o�ŎЂ���Ñ㕶���̎��T�����o���悤�ɂȂ�A�N���������Ȃ��k���Ȏ��T�����X�o�ł��܂����B���̏W�听�ƂȂ�u�Ñ㕶�����T�S�W�v�S�U�������s����钼�O�ɋA��ʐl�ƂȂ�܂����B�{�l�����X�ɕ��{���ς��ʂ͎̂c�O�ł����A�������Ă̑��E�ŏ����͗ǂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
����ɂ��Ă��ɂ����l�������܂����B�ނ͐V���Ȏv���ŏ�����n�߂悤�Ƃ��Ă��������ł��B�܂��f���炵���̂��r��ł��܂��̂ł���炪���炩�̌`�Ő��ɂł�Ǝv���܂��B
�u�t���@�����o������ߒ����v�@�u���_�ƕn�R�_�ƉԂ̉��v�@�u�\���͌������邩�H�����v
�����P��@�u�s�`���d�ˁ@�����l��ʖ��O���ȁv�@�V�e�@�@�얳�I�@�@�@�i2011.1.1�j
61 ���t�@�O�쓹��搶
����m�l���A�u��ς����b�ɂȂ������w�Z�̐搶���A�l�ÂĂɖS���Ȃ��Ă����b���ăV���b�N�����v�ƕ����܂����B������ēˑR���̉��t�O�쓹��搶���v���o���܂����B���炭�����������Ă��܂����B�������C���^�[�l�b�g�ł킩�邩�Ȃƌ��Ă݂�ƁA6�����E���Ă����܂����B���u�Б�w�̖��_�����������̂ŋ��s�V���ɂ͏o�Ă��܂������A�w�ǂ��Ă��Ȃ��̂ł킩�炸�A���܂��ɖ{�l�̈ӎv�ő���������Ȃ��Ƃ������Ƃ����������ł��B
�s�`���ł��I��Ȃ��ł��I�\����Ȃ��ł��E�E�E����ɔ��ōs���āA���l�Ƃ���l�ɂ�����݂Ƃ��l�т����܂����B�����s����Ȃ�ǂ����Č䑶���̊Ԃɍs���Ȃ������̂��͜��Ɋ����܂���B�����ς��b���������Ƃ��������̂ɁB���Ƒ�����͂Ƃ��Ă��D�����Ή����Ă��������A�搶�͐��O�u�M�c����A�Ƃ��Ă��Z�����ˁv�Ƙb���Ă���ꂽ�ƕ����A�u�X�C�}�Z���I�Z���Z�C�v�A���Ƒ��ƎႫ���̐s���ʎv���o�����A�ʂ�ۂɂ͏����͏d�ׂ��Ƃ�܂����B
�搶�̋����q���������l�A�Ⴋ���h�C�c��̓�������������搶���V�тɗ��āA���ւɏo�����l�ɁA�u�����l�͂��ݑ�ł����H�v�Ƃ������b���قق��܂����v���o���܂����B
�搶�̓h�C�c���w�҂ŁA�w������h�C�c�����u���Ă������͂ł��̈������k�������̂ł����A���ƌ㉽���̉��ŁA���k�搶�̊W�łȂ��A�F�l�̂悤�ɐڂ��Ă��������A�o�Ől�Ƃ��Ďd�����n�߂�ƁA��w���ڂ�ꂽ�搶�͂����������e�������Ă��������A�o�łł��܂����B�����͐��ӋC�ɂ����̌����͓���̂ŏ����D������������Ȃ�Ă����āA���点���肵�܂����B
���̖{�����̊Ԃɂ���łƂȂ�܂����B�ł������̖{�u�h�C�c����w����v���H���ƂȂ�Aweb�T�C�g�u�����h�b�g�R���v�ŕ������Ăق����{�ɑI��A�Ï��ō��l���t���Ă���Ƃ�����Ԃł��B�搶�̑f���炵�����ĔF�����Ă��܂��B���������������{�ł��B
�o���b�N���y���D���ŁAFM�����Ɍ��e�������Ă���ꂽ�搶�A�V���Ńo���b�N���y�����Ȃ���A��D���Ȗ{�Ɉ͂܂�Ă����邱�Ƃł��傤�B�얳�I
�i�ǁj�Ȃ��Z��̑O�쐽�Y�����m���p�يْ����ꌎ�ɖS���Ȃ��Ă����܂��B�w���̎���勳���Ƃ��ċ��s�ɗ����Ď��Ƃ��܂����B�����˂����˂�����ݐ\���グ�܂��B�i2010.09.08�j
60 ����̗�

����Ƃ������t�͂��܂��ʓI�ł͂���܂���B���͑����i�u�b�N�f�U�C���j�̈ꕔ�ƍl���Ă��܂������A���̓W����ő���̂��Ƃ�^���ɍl���Ă݂܂����B�{���o�ł���Ƃ��A���ҁA�ҏW�ҁA����A���{��ʂ��Đ��܂�܂��B�{�̌`�����߂�f�U�C���͑����͕ҏW�҂̗̈�ł����A���݂͑��{�Ƃ�������āA�����e��\���A�l�̖ڂɂ��f�U�C�����{����܂��B���̈ꗃ��S���̂��A����Ƃ����킯�ł��B����̓u�b�N�J�o�[�̊G�������̓f�U�C���ƍl���Ă悢�ł��傤���A�����E�^�C�g���̓C���X�g���[�^�[�⏑�Ƃ��S������ꍇ������ł��傤�B
���������ďo�ł����{�̎����ōl�����������C�ɓ����ău�b�N�f�U�C���̌���W�ɏo�i�����Ƃ�����C�̎���I�v���o������܂��B
���č��s�݂₱�߂����i21�C22���͉�X�́u�Ђ傤�ق�W������܂��j��11������16���܂Łu����̗͓W�v���J�Â���Ă��܂��B�T�u�^�C�g���́u���ɁE������`���v�ł��B20���̃C���X�g���[�^�[���Q���������܂łɂȂ��{�̓W����ł��B
����������̒m�l�̖S���Ȃ�������l�̈��W�u�юR�E���i�W�v���_�ے��̞w��L�Ō����߂ɂ���܂������A��g���X�Ȃǂ̑���ƂƂ��Ċ��ꂽ�����ł��B�i2010/03/14�j
59�@�_�X�̗��S
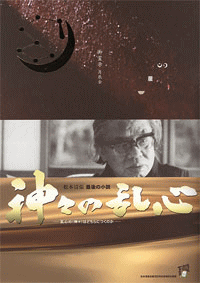
2010�N1��9���`3��31���܂Ŗk��B�s���q�̏��{�����L�O�قŊJ����Ă���u�_�X�̗��S�W�v�̐}�^�����������܂����B
�u�_�X�̗��S�v�͏��{�����Ō�̍�i��M�ł��B
���e��
���a�����A�V���@���ƓV�c�A�R��������荞�����Ƃ����j�̖�]��`�����b�ł��B
���������Α�q�b�g�́u�P�p�W�S�v���V���@�����e�[�}�ł����ˁB�������Ă������\��ɂȂ�����������܂���B�i2010/02/11�j
58 ����J�s1300�N

����������J�s�����̂�710�N�Ƃ������Ƃō��N��1300�N�ɂȂ�܂����A70�N�̒Z���݂₱�ł����B
�������ޗǂ̓s����s�Ƃ��āA�����̐_�Е��t�����̗��j������ł��܂��B
���|�ɂ��o�ł���̋Ɩ��Ƃ��Ă������a��͑��̓��Ӑ悪�قƂ�ǂ��ޗǂŁA���x���ޗǂɂ͒ʂ��܂����B
���ɒ��J���A�����A���ɂ͂����b�ɂȂ�A���V�����ɂ������b�ɂȂ�܂����B
�܂��ߋE���{�S���̕������ƂɎQ�����A�����̌������̍����u�ߋE���{�u�b�N�X�v�Ƃ������q���o�ł����̃u�[���̐�삯�ƂȂ�܂����B
�Ⴊ�~�����Ƃ����d�b�ŁA�������J���܂ŏd����^�J������w�����B�e������A���炭�g��R�����x���K��ĕ\���̎ʐ^���B��܂����B
��{���̂�悤�ɂȂ��Ă���A���厛���a��C���̂���`���ŁA�����̂قƂ�ǂ̂��̂��̑�A�����āu���厛�W�v�̏o�i��Ƃ��đS������ēW�����܂����B
���Ƃقlj��̂���ޗǂ̑J�s�Ղ�A�������F��܂��B
���̎ʐ^�̓I�[�v�j���O�C�x���g�����U�u�l�_�v�����F�ޗnj����A���F�������A���ՁF�M�M�R���쑷�q���A�鐝�F�����R���ōs����Ȃ��ŁA�Ղ̎��Ƃ��ėL���Ȓ��쑷�q���Ƃ�����荑��u�M�M�R���N�G���v�̂��̂������Љ�B
�]��ɂ������̂ŁA�����ДN�̍��N�̕����Ɣɉh���u�E�I�[�v�Ɣq��ł����܂��B�i2010.1.1�j
57 �Ƃ��
 |
���|�ɂ̂��ׂ̘V�ܗr㻂̌Չ����I�[�v������2�����o���܂����B�ٗ��̂����҂������܂łƂ̂��ƂŁA����悹�Ă��炢�܂����B�܂��Ƃ��Ă����邢���͋C�ŁA��k�Ƃ��ɃK���X����ŗ������������܂����B������A���{�뉀�łȂ�������ۂ����Ă�薾�邳����������Ă��܂��B
������x�̃X�y�[�X���Ƃ��āA�a�̍��ؖ{��A���s�W�̖{�A�a�َq�̖{�Ȃǂ��u���Ă���A���R�ɉ{���ł��܂��B
��D���Ȃ����X�i�݂j�����������܂����B�������������I
�a�َq�̓X�ɒj���̉��B�n�̃{�[�C������ꂽ���A������������ł��ˁB
�Չ������̒n�ɑn�Ƃ����̂�1628�N�ȑO�炵���B380�N�̘V�܂Ȃ�ł��ˁB1854�N�ɗ����͍�����C���ꂽ�����ł��B
���a13�N�̎ʐ^������܂����B�������Ɋo���Ă���Ƃ��낪�킽�����ۂ̐�����N��ɂȂ����̂�����H
���������ΐ��A�������z���̎���ɁA������b�ɂȂ�ꂽ���单�삳�A�ߏ��ɕ��ɍ�������ƌ����āA���ʂ肪���ւ̗����Ɛ��O�ꂪ�\���Ă��܂����B
��ԓ��̕��ƒ��ǂ�������͂��낢�남���b�ɂȂ����݂����ł��B
���Ė��͒��ԏ�A�䂪�ɂ̖k�ׂɌՉ��̒��ԏꂪ�I�[�v���A�r�C�K�X�Ƒ����ł��ꂩ�炪�v������܂��B
�ł͑��|�ɂɂ��z���̐߂́A�Չ��ٗ��őe�����₢�⍂�����َq�ňꕞ�������ł����H�@�@���ԏ���������܂��B�i2009.8.20�j |
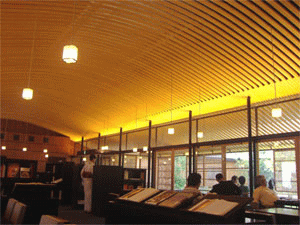 |
56 �ʔň��

�t�����f��Ɂu���̑��蕨�v�Ƃ����A�����J�f�悪����܂����B�܂������\���m�����Ȃ��A30�����炢�͋����߂�����܂������A�㔼�͗܂ŏ���ł��܂��܂����B
����́uSEVEN POUNDS�v�A�u���Ɂu�x�j�X�̏��l�v�́u���̂P�|�C���h�v���v���o���܂����B������������������̂ł��傤�ˁB
�b�̓E�C���X�~�X���������]���ɂ��ĉ������Ă����b�ł��B
���Ă����ł��������ꂵ�������̂́A�S���a�������Ă��鏗���Ƃ̘b�ł��B
�ޏ��͓ʔň���ŃJ�[�h������Ă���d�������Ă��܂��B �ޏ��͔ނɁu�����͓ʔň������D���Ȃ̂�B������˂��j�����A���ň���i�I�t�Z�b�g�j�����āA�ʔň���E�����́I�v�Ƃ����b�i���̐��̓��j�[�N�j�B
�����Ď����̍H�[�ɔނ�A��čs���܂��B����@�����A��͂Ԃ�Ă��ĒN�������Ȃ��A�����ЂƂ��g���Ă���̂ƌ����ē������܂��B
���̓��̈���@�悭�m���Ă��܂��B��͓��{�ł́u����܁v�Ƃ����鏬���̓ʔň���@�A������́u�n�C�f���v�Ƃ����h�C�c�̖��@�ł��B
�����ē����̂قƂ�ǂ̂͂�����J�^���O�͂���ō����Ă�����Ă��܂����B���܂����̈���H��ł͂��̋@�B���Ă��܂��B���s�ł͐����ɂȂ��Ă��܂��܂����B�������قƂ�ǂ��p�\�R���ōς܂��Ă��܂��̂ŁA�o�ŕ��̍Ĕł��炢�ł����g��Ȃ��Ȃ�܂����B������ʔł̉��ł����茸���Ă��āA�����_���ł��傤�ˁB
���ĉf��ł͎�l������ꂽ�n�C�f���@���C�����āA�ޏ����т����肳���A����@���K�`�����K�`�����Ɠ������ł̃��u�V�[���E�E�E�����Ȃ����ȋ@�B�̉��Ɏ����g�̐̂��v���N�����Ă��܂����B�����ł͖��̂ɂ����Ƌ@�B�̉��̒��ŁA�H��̎�l�ƍZ�������Ă�����A�F���킹�����Ă���p�ł��B���͂Ȃ��葢��̐��E�B
����̐V���ł́A���{�̏o�ŎЂ��Ƃ��Ƃ�4000�Ђ���������ł��B�Ĕł������Ȃ��Ȃ������|�ɂɂƂ��Ă��x������v���ł��B�ł����ꂩ���web�T�C�g��ʂ��āA���{�̕����������ł����M�������Ǝv���Ă��܂��B�撣��܂��I�i2009.07.05�j
55 �z������
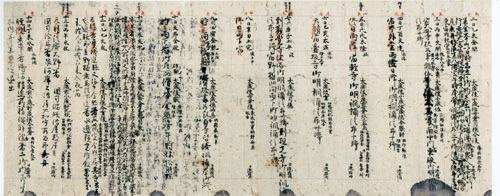

12��14�����j���́u�j瑂Ɣ��p������v��936��ڂ̗��A�����Ƃ��āu�z�����Ɂv�Ɓu�������v��47���̕���A��Ĕq�ς��܂����B
�����J���~���Ă����̂ł����A9���߂��ɂ͏オ���āA�ߌ�ɂ͐��V�ɂȂ�܂����B�W����10�������q�_�Ћ����B�S�������āu�z�����Ɂv�ցB���a�C���ɒ����A���ɂ̑O�ŕ��ɂɂ��Ă̐����B���̌�ɓ��ցA��K�ɓW����������܂��B
���̓��݂Ȃ���Ƀ}�X�N���Q���]���Y��A���ꂼ��n���J�`�A�}�t���[���Ō����Ă̌��w�B�J�o�����͈�K�ɒu���܂��B���ɂƋ��ɑ��ɃJ�M���������āA�O�ɂ͏o���Ȃ��Ƃ������d�ȊǗ��B��������R�ł��傤�ˁB����A�d����20���_���̂����ɂɔ[�܂��Ă���̂ł���ł��B��g�[����܂���̂ŏ������������ł��B47���̐l�������āA���C���C�ɂȂ����̂ł����A�����͊O�̓R���N�[�g���ł����A������5�����̋˂̔ŕ����Ă��܂��̂ŁA���x�����x�����܂�ω����Ȃ������ł��B�|���̋˔��⒅���̑��˂��ɓ����Ă���悤�Ȃ��̂ł��ˁB
���ĕ��ɒ��̐������Ȃ���̌��w�A�܂��K���X�P�[�X�ɓ���������u�䓰�֔��L�v�A�䓰�֔��Ƃ͕�������̓��������i966-1028�j�������܂��B
�u���̐����@�킪���Ƃ��v�Ӂ@�]���́@�������邱�Ƃ��@�Ȃ��Ǝv�ւv�Ɖr�����l�ł����A���w�������A����������[����삵�܂����B���N����1000�N�I�ƌ����Ă��܂����A���̐��E�I���w���ŏ��ɓǂ̂͂܂����������ŁA���e���Ñ������قǂł��B
���̓������M�̓��L���A�Ɏq�P�[�X���J���Ă�����āA����܂����ɂЂ����Č�����Ȃ�āE�E�E���Ƃ��Ƃ��̎���̓��L�͊����ɂ��āA�܂������Čr��������A���t��������Ă���A�����̓��p���L�̂悤�Ȃ��̂������̂ł��ˁB�����͂��̓����ɐ��s�������݂����Ă��܂��B���\�Ԉ�����ƌ����āA�ォ�珑���̂�����A��������̐l�Ԗ��̂�����̂ɂȂ��Ă��܂��B�܂��������݂������ꍇ�́A���ɂ��������ނƂ����|��������Ă��܂��B���̂��߂��̕����͗��ł�������Ă��܂���B
���̕����ɒ���������ƂЂ�����Ԃ��Č����Ă���܂����B���������ȂɊȒP�Ɏ�舵���Ă����Ȃ�āE�E�E�����قł͂��肦�Ȃ����Ƃł��傤�ˁB�i���Ɍ����邤������Ɖf���Ă��鏑�����w�����j
���ŁA���̓��������N���N���Ȃ���ǂu��������v�A�������̎��M�͐��ɓ`����Ă��܂��A�����ɂ͊��q����ʖ{�E�d���u��������v54��������A�W����̏�ɊJ����Ă��܂��B���F�����炢�̑傫���ŁA�ŏ��̕Łu���Â�̌䎞�ɂ��A����A�X�߂��܂����Ԃ�Ђ��܂Ђ���Ȃ��ɁE�E�E�v�����Ƃ��ǂ߂܂��B1000�N�̎���ʂ��āA�h�s�h���ɂ߂������Ɠ������͂܂����ɓǂ�ł���̂��Ǝv���ƃ]�N�b�Ƃ��܂��ˁB�M�����Ȃ��قǑf�G�Ȏ��Ԃ��߂����܂����B���̋M�d�ȕ������߉q�Ƃ�1000�N�̂������A���m�̗��▾���ېV�A�����m�푈�Ƃ�������Ȏ������A�����̍K�^���������ł��傤���A����Ɏc�����Ƃ��鋭���ӎ����A���̉�X�Ƀp���h���̔��E�Ƃ��Ă����炵�Ă��ꂽ�̂ł��ˁB�i2009.1.1�j
54�@�j瑂Ɣ��p������

�Α����p�Ƃ��������n�݂����쏟�����Y�搶�́A�e���̐e�F�ł���܂����B�ǂ�������͖S���Ȃ��Ă��܂����A�쏟�搶�́u�j瑂Ɣ��p������v�Ƃ����j�Ղ���p���������T�K�������c����A78�N�����A935��̌��w��Ɓu�j瑂Ɣ��p�v�Ƃ������788���܂Ŕ��s����A���s�ł͗ѐ�ƕC�G�����Ƃ��Ĕ��W���Ă��܂����B
���͂��̊Ԃ��[�Ɩ��Ȃ��������Ă��܂������A�����]�T���ł��܂����̂ōĂт���`�����邱�ƂƂȂ�܂����B
�ǂ������j��Ô��p�A������_�ЁA�������ՁA�����ċ��s���D���ȕ��A�Q�����܂��B
��ł͗��Ƃ���
11��9���@�哿���ʗщ@�A�^����ɂ܂���܂��B�����v���Ԃ�ɎQ�����܂��B���̗��͗\��Ȃ��ŒN�ł��Q���ł��܂��B
���ł킽�����S���ŁA12��14���@���s�F������z�����ɂƗ������ɂ܂���܂��B�z�����ɂ͖��Ԃ̐��q�@�Ƃ�����قǑ����̍���A�d���Ȃǂ�����܂����A�l�I�ɂ͂����Ȃ��Ƃ���ł��B������l���������Ă̌��w�ƂȂ�܂��̂ŁA���\��������Ǝv���܂��B
53�@���������
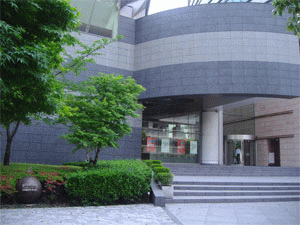 �S���̂��������̒��A����������ɂ����������فiPrinting�@museum�j�ɍs���܂����B������2000�N�ɓʔň��100���N���ƂƂ��Ă���ꂽ�A����̗��j�����قł��B�o����������s�����������̂ł����A����ƔO�肩�Ȃ��܂����B
�S���̂��������̒��A����������ɂ����������فiPrinting�@museum�j�ɍs���܂����B������2000�N�ɓʔň��100���N���ƂƂ��Ă���ꂽ�A����̗��j�����قł��B�o����������s�����������̂ł����A����ƔO�肩�Ȃ��܂����B
�����̐����烂�_���Ȕ��~���`�̍��w���z�������܂��̂Ō���ꂽ��������Ǝv���܂��B�ł������ɔ����ق����邱�Ƃ͌䑶���Ȃ��ł��傤�ˁB
��Ɣ����قƂ��Ă͖k��̉��q�����́u���̔����فv�̍s�������Ƃ���܂����A�������R�ɐV�������Ē�����Ă���͍s���Ă��܂���B���Ă����ďo�łɂ���������g���炷��ƁA���{�̓�����̓ʔň���Ƒ���{����ɂ͂Ȃ��݂�����܂����A�ŋ߂�IT�Y�ƂƂ��Ă����E�L���̉�Ђł��B
�����ق͂������ɑ��Ƃ̌��Ă����̂ł�����A�������f���炵���A�W�����Â��Ă��܂��B����̋N���Ƃ��Ă̔ʼn�ɂ͓��ɗ͂����Ă���݂����ł��B���j�[�N�Ȃ͔̂����ق̈�p�ɂ������H�[�ł��B�����ʂɂ͌��邱�Ƃ̂Ȃ��Ȃ����������g���ẮA�Â�����@�ł̈�������Ă���K���X�ň͂܂ꂽ����̉Ƃł��B
�悭���������{�݂ł́A���N���̐E�l���A���������ɂ���Ă�����̂ł����A�����ł͎Ⴂ�l�⒆�N�̐E�l���A���������Ɠ����Ă��܂��B�Ȃɂ��T�O�N�O������ɐ����Ԃ��������̕����ł��ꂵ���Ȃ�܂����B�����Ċ��W���A�u1950�N����{�̃O���t�B�b�N�v7���܂ł���Ă��܂��B������50�N�O�̂��̂Ȃ�ČÏL���I�Ȃ�Ďv���Ă͂����܂���B�f���炵�����́A�n���I�Ȃ��̂͂����Ƃ��Â��Ȃ���ł��ˁB����������i���Ƃ����Ă��[������͂������̍�i�ɂ͂���܂����B�i���ł���t�ł��ōւł��Â��Ȃ�Ċ����Ȃ��̂Ɠ����ł��B
���̔����ق̖��͌�ʂ̕ւł��B�ǂ�����s���ɂ��Ă��A���\�̋��������Ȃ���Ȃ�܂���B�ł����w���瓌�����������قⓌ���|��ɍs�������̏����������炢�ł��B
���Ĕ����ق���o�āA�n���S�֍s���r���ɁA�����Ė��N�V�����o�ł��Ă������A�V�����̌��{�������āA�ѓc������g�R�g�R�����Ă���Ă����u�g�[�n���v������܂����B�����͏o�őS���̎���ł��B�����o�Ŕ̔��i�g�[�n���j�̒S���ɁA���{�̖{��n���A�u1000�����肢���܂��v�Ƃ����ƁA������ƌ��āA�u500���Ђ��������[�v�Ȃ�Č����A���̓j�b�p���i���{�o�Ŕ̔��j�ɂ����ē������Ƃ������āA���������炢�A
�u���[�����3000�������邩��A�Ȃ�Ƃ��������ł����I�v���ꂩ�琔�J���A���s�̂킪�ЂɃg���b�N�����A�h�J�b�ƕԕi�̎R�E�E�E����͈ϑ��̔��Ƃ������x�������炵�����Q�ł��B���̂��납��o�ʼnߏ肪�n�܂�A�������ꂪ�N����A�o�ŎЂ�{�������������܂����B
�����Ď��́A�{�Ƃ�����ʐ��Y�̐��E���痣��āA��i��������̐��E�ɓ������̂ł��B
���������A��������قł́A�g�b�p���ƒ����̋������Łu���֏�v�Ƃ����o�[�`�������A���e�B�[�f������f���Ă��܂��B�c�O�Ȃ���A�y�������̏�f�ł����B�i2008.04.26�j
52�@�o���
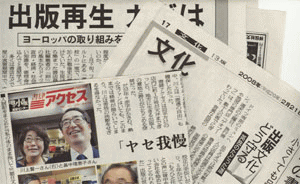 ���|�ɓ����X�u�\���M�������[��v������4�J���ɂȂ�܂��B���܂��ɁA�[���d�b����Ɓu��v�����
���|�ɓ����X�u�\���M�������[��v������4�J���ɂȂ�܂��B���܂��ɁA�[���d�b����Ɓu��v�����
�u�����͂��̕ӂŋA��܂��v
�Ƃ����X�^�b�t�̐����������Ă�����o���������܂��B
�����Ċ��l���̐l����A�c�O�ł��ˁA�܂��ĊJ�����̂ł����H�E�E
�Ƃ������t�������܂��B���̒n������l����ƂȂ��Ȃ���ςł��B
���Đ挎�A�����V���u�j�b�|���l�E���E�L�v�Ƃ����L���ɁA�Ǝ傳��ł������u�n���E���o�ŗ��ʃZ���^�[�v�̎В���㎁�Ɓu����A�N�Z�X�v�X���̔������o�Ă��܂����B
����������ɂ͑����̃t�@�������Ă��Ďc�O�����Ă����Ƃ��B
�_�ے��Ƃ������{�̖{�̒��S�n�ŁA��̕����]�[��������u�Ԃł������̂ł��B
�ŋ߁A�V���ł������o�łɂ��Ă̋L�����o�Ă��܂����B�o�ŕ��������Ƃ������ɓI�ŕێ�I�Ȃ��Ƃł����̂�������Ƌ^��Ɏv���܂��B���̃j�[�Y�ɍ������o�ł������ƐϋɓI�ɐ�`���A�Ǐ��̖ʔ�����`���邱�Ƃ���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�o�ł��班�������������A�a�̓`���Z�p�̌p���Ɣ��W�ɔ��͂ł͂���܂������g��ł���A���ɂ͂��炻���Ȃ��Ƃ͂����܂��E�E�E�E�B�i2008.3.16�j
51�@���l

2008�N����20�N��q�̔N���n�܂�܂����B�����Ȃ�ʍ��l�ō��N����L���ɂȂ����@�R�@�̖T�A�N�w�̓��ɂ����L�_�ЂɌ�Q�肵�܂����B
�����ȑ�L�_�Ђ̒��ɂ����ЂƂ����ȎЁA�����͑单�傪�J���A��������l�Y�~���A���݂̌`�łȂ��ł��܂��B
�U������z���āA�M�̔N�ɂ������@���|�Ɋ撣�肽�������܂��B�n�Ǝ҂̕��A�M�c�È�Y�R�T����A���̔N�Ɉ������߂Â�����܂��B���N�͐��܂��������s�̂��߂ɁA�����ł��`���Ɗ������Ȃ���d�������Ă�������Ǝv���܂��B
���n�߂Ɂu�a�̍H�|�V���[�Y�v���A���R�A���É��ŊJ���܂��̂ŁA���Ђ��z�����������B�i2008.1.1�j �֘A�L���@�u�|���ƛ����v�߂苴
50�@�Տ� �\���M�������[��@�X
 11��26���\���M�������[��E���|�ɓ����X��27�N�Ԃ̗��j���I���܂����B
11��26���\���M�������[��E���|�ɓ����X��27�N�Ԃ̗��j���I���܂����B
����͉Ǝ�̒n�������ʃZ���^�[�̏�������̏���A�N�Z�X���A�ߔN�̏��З���̉e���ŕX�����̂ɔ����A���̈ꕔ����Ă����䂪�u��v���X����������Ȃ��Ȃ�܂����B�Ƃ��Ă��c�O�ł��B
27�N�O1980�N�����A�S���Ȃ������̐Ղ��p�������|�ɁA�����o�ł����C���ł������̂ŁA�����ł������̐l�ɖ{�����Ă��炨���ƁA�n���̖{�������Ă���n�������ʃZ���^�[�ɎQ�����܂����B���炭���ăZ���^�[����A�X�̈ꕔ��݂��܂����������ł����Ƃ̘A�������܂����B
�����n�������ʃZ���^�[�͏x�͑䉺�ɂ������̂ŁA�{�̊X�̈�p�Ɂu��{�v�̃M�������[�Ǝ��Ђ̖{��u���Ă݂���ǂ����낤�E�E�E�Ƃ������ƂŗE�������ɏ�荞�݂܂����B
1�N�قǂ͒�������{�̑�{��W�����Ă��܂������A�v�����قǂ͐l�͗��܂���B
�����œ����e�n�ŋ����Ă�����{�Ɨ��ł��������鋳�����n�߂�ƁA�����͐l������悤�ɂȂ�܂����B
���炭���đ�{��藠�ł���\�����w�т����l�̕����������Ƃ��킩��܂����B
�����œ����ł́A���������đS���I�ɂ����܂�Ȃ������u�\���u���v���X�^�[�g�B���ꂪ�Ȃ��27�N�ɂ��y�Ԃ��ƂɂȂ낤�Ƃ͎v�������܂���ł����B
���N�̂��A�n�������ʃZ���^�[���̔������V���ɍ��A�_�ے��������ʂɓX�܂��ڂ�����A��K�̈�p���g��Ȃ����ƌ����A������������Ƃ��čL���g���邱�ƂɂȂ�A�M�������[�Ƃ�����肿������ȃJ���`���[�Z���^�[�ɕϐg���܂����B
���������āA�x�͑�ɂ����w�̗F�Ќo�c�̎�w�̗F�����Z���^�[�ŕ\���������邱�ƂɂȂ�܂����B
���ɗ�����Ȃ��u���A���ɋ��s���痈���搶���Ƃ������ƂŁA1�N���X�Ŏn�߂���A�Ȃ��40�l�ȏ�̎Q��������A�������A����̎�荇���E�E�E�Ȃ�Ă����ɂȂ�A�}篍u���𑝂₵�A�A���A�y6�N���X�ɑ����A����Ɨ��������ċ�������ɂȂ�܂����B
�����̎v���o�͓�K�̃��X�g�����ł̒��H���ɁA�������̃A�e�l�t�����Z�ōu���������Ă���ꂽ�A���쒷������Ɖ����b���ł������Ƃł��B
�܂������w�@�̂������������ȃ}���j�G�ʂ���������Ƃł��B
���̎�w�̗F�����Z���^�[���o�ŎЂ̓s����10�N�قǑO�ɕ�����A���͖{�ЂƂ��Ďg���Ă��܂��B
�p�~�ケ���̎�u���̉��l���́u��v�����ɎQ�����ꂽ�̂ł����A����̕����Ƃ��Ă��c�O�����Ă����܂����B
��������O�Ɏ�u���n�߂āA�q�������ꂽ���ɏ����x��܂��Q���A���̂��q�����⍂�Z���E�E�E�B
�܂��ʂ̕��́A���X�q�炪�Ă�ɘA��Ă��Ă���ꂽ���w���A�����̒[�Ŏ��Ƃ��I���̂�҂��Ă������q���A���͑�w���A���݂��ɒ������t�������ł����B
�Ȃ����́u��v���N�_�ɁA�����ł̍u���������A��t��V�h�A�r�܁A����A��q������A���R���u�Ȃǂɂ��i�o�A������10�����A�u����15�u���A150�l�ȏ�A25�N�łP���l�ȏ�̕��ɋ��\����������v�Z�ɂȂ�܂��B
���̕��X�̌��₨���A�d�������n���̂悤�ɕ�����ł��܂��B
���ɂ̓v���̕\��t�ɂȂ�������A�\���ƂɂȂ������ȂǁA�����q����������Ƃ͎��̍��Y�ł��B
����������B�����s�@�ŗ��Ă���ꂽ�����͍��͌F�{�Ő搶�A�k�C�����痈���Ă������͕\��t�ɂȂ��Ă����܂����ˁB
�܂��������n�߂�ƁA�����ޗ����K�v�ɂȂ�A�u��v�̓M�������[�Ƃ������\�������X�̔�d�������Ă����܂����B�����͑f�l�ɔ���X���Ȃ����āA���������̕��ɗ��Ă��������܂����B
�Ƃ��낪�o�u�����͂����A�\��̎��v�������āA�\��������āA�����̍ޗ��X���Ȃ�ӂ�\�킸�����ƂɎQ���A���͂Ƃ��Ă�����������ɂȂ��Ă��܂��B
���̂Q�O���N�A���͎��ʼn��W�𓌋}�S�ݓX�┵�����ł����Ă��炢�A������u��v�Ƃ������_�����������������Ǝv���Ă��܂��B
�����ԁA�\���M�������[��E���|�ɓ����x�ɂ����ۛ����������ėL��������܂����B�Q�O���N�̊Ԃɂ�����������̕��X�A�u��v�͖����Ȃ�܂����A���|�ɂ͋��s�̌䏊�̐��Ŋ撣���Ă����܂��B�܂������͓����𒆐S�ɂ܂��܂��[�������Ă����܂��B�킽�������Q��͓����ɂ܂���܂��̂ŁA���ꂩ�����낵�����肢���܂��B
�i�Ō�ɁA�X�⋳���̃A�V�X�^���g�Ƃ��ė��Ă������������������A�������Ďq�������܂�K���Ȃ��̂�A�������܂�Ă��[�����ɂȂ����l�A�����h���ŌW������˕Q��������L���Ȕޏ������A���j�̂��[�ł��ȁ[���[�ł��Ȃ������ɕt�������Ă���ėL��I
�����Ă��ꂩ�����낵���E�E�E�E�B�j�i2007.12.15�j
�S9�@�Տ� ���{���z�E�f�U�C���̊�b�m��
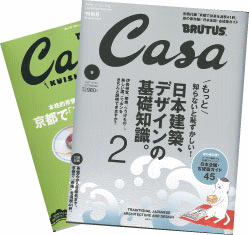 �}�K�W���n�E�X�Ђ̃��C�t�f�U�C���}�K�W���uCasa�@Brutus�v9�����ő��|�ɂ́u�Ì��z�ו���b�v���Љ��܂����B
�}�K�W���n�E�X�Ђ̃��C�t�f�U�C���}�K�W���uCasa�@Brutus�v9�����ő��|�ɂ́u�Ì��z�ו���b�v���Љ��܂����B
�u�����ɂ��r�r�邯�ǁA���z�Ƃ⌚�z�j�ƌ����łȂ��A�����܂ł���ʌ����B�Ì��z��K�ꂽ��A��发��ǂ肷��Ƃ��ɈЗ͂�����B����}�ʂ�r���A�e�L�X�g�݂̂̒��������B�v�ƏЉ��܂����B
�{����27�N�O�̔��s�ł����A�����O�Z���[�Ƃ��č����o�Ă���܂��B
�{���͑��|�ɏ���̖��c�È�Y���S�����A�ʐ^�͖��c�ďH���B�e���܂����B��l�œޗǂ⋞�s�̖����z���B�e�������Ƃ����ł��v���o����܂��B�����͒��^�Ƒ�^�̃J�����ŎB��A����Ō����A�����L�������A��������掆�ɒ��荞��ł����܂����B����ɂ��B�e�⌻���̋Z�p�w���Ɗw�ł�������̂ł�����A���s����̐��E�ł����B
������̖L�x�Ȓm���̏�ɐ��藧�����{���ł͂���܂����A�J�����}���łȂ����̎ʐ^�����܂ł��𗧂��Ă���Ǝv���Ƃ��ꂵ���Ȃ�܂��B�f�W�^���J�������g���悤�ɂȂ��āA���̃J����ꀂ��͂��Ă��邩������܂���ˁB�i2007.8.13�y���Z�E�X�����Q�̗������j
�S�W�@�Տ��@�_����
 |
 |
�V���P�P�����̒ʂ�ɖg�������n�߂܂����B�ؑg�݂ɓ�݂̂őg�ݗ��Ă�`���Z�p�A���̑g�ݗ��Ă̂������ŊX�����s���āA�䂳�䂳�h��Ă����邱�Ƃ�����܂���B�����w�r�����ϐk�\���ɏ_�\�����̗p���鐔�S�N�O�A���s�̒��O�͐�[�Z�p���g���Ă����̂ł��B
�D�g�̘a���݂₳��u���܂��v�����������܂����B����ŗ��N�܂ň��ׂł���������ł��ˁB
���N�͋��s��ɂ����f��⏬�����������o�܂����B
���̑�\���@�{������Y�r�{��
�u���WHaaaan!!!�v�@�쌀�f��̃G�|�b�N�ƂȂ��i�ł��B
�����������B
�u����z�����[�v
�@�@����ڊw���i�Y�ƕҏW�Z���^�[�j
���Ղ̓��A����̊w�������V��Ȑ��E�Ɋ������܂�A���镨��B�r���_���Ղ��o�Ă��܂��B
�u��͒Z�������扳���v
�@�@�X���o���F���i�p�쏑�X�j
����������ɁA�V�R�{�P�̂��킢�������ƁA�����ĂȐ�y�̗����ꂪ�A��l����Ö{�s��Ɋ��V��A�䕗�̂��Ƃ��X�s�[�h�œW�J���܂��B�Ȃ��ł��m�����̌Ö{����i�X�����łĂ��Ċ������Ȃ�܂��B
�Ƃ���ł��̓�l�̍�ƁA����@�w���Ɣ_�w���o�g�ł��B���w���łȂ��̂��~�\�ł��ˁB
���W�́[�[��̏��o���D�����s�o�ǂ����B
���č��N�̋_���ՁA�A�x�œ��₩�Ǝv���܂����A�䕗���������ł��B�i2007.7.12�j |
 |
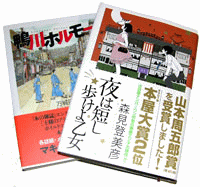 |
�S�V�@�Տ��@�|������
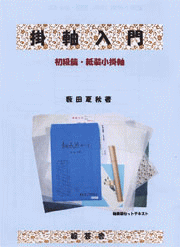 |
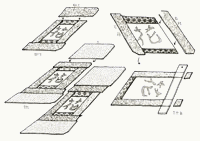 |
�P�X�W�Q�N������Q�T�N�܂��A�㓏�����{���́A�e�n�̉ďH�\�������̏����e�L�X�g�Ƃ��Ă����Ԃ�g���Ă��܂������A���N�ŕi��ɂȂ��Ă��܂��܂����B����A�ꕔ����������āA�I���f�}���h����ōĔ̂��܂����B
�a���̏����Ȋ|�������e�L�X�g�ł����A�S�҃C���X�g���g���č��ؒ��J�ɏ����Ă��܂��B
��̎���傫�Ȏ��ł���{�͓����ł��̂Ŗ𗧂��܂��B�i2007.5.20�j
|
�S�U�@�Տ��@�Q�P�Q�Q�PDESIGN SIGHT

�����͐V���p�قׂ̗ɂł����~�b�h�^�E���̒��́u�Q�P�Q�Q�P�v�f�U�C���T�C�g�ɍs���܂����B
�������Y�ƎO��ꐶ�̃f�U�C���ō��ꂽ�A�V�����f�U�C�����M�̏�Ƃ����G�ꍞ�݂ł��B
���̍��\���́A�Z�p�ƈӏ����Ȃ킿�e�N�j�b�N�ƃf�U�C�������ł��B
�Ƃ������ƂŊ��҂��Ă������̂ł����A�ꏊ�����܂�L���Ȃ��A���W���S�̏�ŁA�����ȃf�U�C����������A������}���ׂ���ł��Ȃ��A���҂��Ă������̂ł͂���܂���ł����B
�i2007.4.14�j
�Ƃ���ŐՏ�42�u��Ȃ̂ˁv����W������܂��B�R�R���N���b�N
45�@�Տ��@�V���p�قƋ��s���ۃ}���K�~���[�W�A��
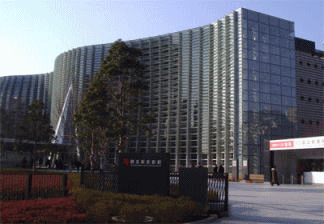 �P���Q�P���I�[�v�������Z�{�������V���p���ɍs���܂����B�����ő勉�̓W���X�y�[�X�̐V���p�فA�I�[�v�j���O�L�O�́u�Q�O���I���p�T���v�Ɓu���{�̕\���́v�Ƃ��̌����̐v�ҁu����I�͓W�v�A���ʂĂĈ�x�݂����悤�Ǝv�����̂ɁA����������J�t�F��X�g�����͖����ł��B�Ă����̂́u�A�[�g���C�u�����[�v���p���̐}���ق����ł���Ƌx�e�ł��܂����B�ł����̃A�[�g���C�u�����[�͖��ɗ��������ł��B
�P���Q�P���I�[�v�������Z�{�������V���p���ɍs���܂����B�����ő勉�̓W���X�y�[�X�̐V���p�فA�I�[�v�j���O�L�O�́u�Q�O���I���p�T���v�Ɓu���{�̕\���́v�Ƃ��̌����̐v�ҁu����I�͓W�v�A���ʂĂĈ�x�݂����悤�Ǝv�����̂ɁA����������J�t�F��X�g�����͖����ł��B�Ă����̂́u�A�[�g���C�u�����[�v���p���̐}���ق����ł���Ƌx�e�ł��܂����B�ł����̃A�[�g���C�u�����[�͖��ɗ��������ł��B
�W���X�y�[�X�Ƃ��ăI�[�v���������̔��p�قّ͊��i�������Ȃ��̂ŁA�S������͂����Ȓc�݂̂̑����ƂȂ�܂��̂ŁA����͍̂��̂������Ǝv�����̂ł��B
���O���猩���V���p�قƉ����B�O���ɂ̓T���g���[���p�ق��ׂ̌��h�q���ɃI�[�v���A�q���Y�̐X���p�قƕ��ׂăA�[�g�g���C�A���O���������ł��B

���s���ۃ}���K�~���[�W�A���͋��N11���I�[�v���A���Ƃ͗��r���w�Z�������̂ł������p���Ŕp�Z�A���z���ă~���[�W�A���ɂȂ����̂ł��B
�s�����͓̂y�j�Ȃ̂Ŏq�������ł����ς��ł��B�����̃}���K�݂͑��o�����R�ł��B��l���q�����֎q�ɍ�������A�K�i�ɍ�������A�Z��͎Ő����͂��Ă����āA�~�̒W�����𗁂тȂ���Q�����œǂ�ł���q�����܂��B����ȐÂ��ȃ~���[�W�A���͒������ł��ˁB
����20���_�}���K�����藈�N�ɂ�30���_�ɂȂ邻���ł��B���W�́u���E�̃}���K�W�v�A�܂�����Ƃɂ��u�S�l�̕��W�v������Ă��܂��B�����ł͐̉��������u���ŋ��v���������薞���ł����B
���N�̔N���Ɏg�킹�Ă�������u���b�Y��v�����{�}���K�̌��_�ł��B�����č��␢�E���ɓ��{�̖��悪�A�o����A�ǂ��̍��ł��u�l���������v�łƂ���܂��B�ő�̕����A�o�ł��B
�Տ��@44�@�u�쉤�_�Ђ̈�v
 �����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B���N�͕���19�N����̔N�ł��B
�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B���N�͕���19�N����̔N�ł��B
���|�ɂ��������10���������Ƃ���ɒ�������쉤�_�Ђ͈�̐_�Ђł��B
�Ƃ������Ƃ�12�N�Ɉ���Ă���K�^�����̊G�n���\���Ă��܂��B
���U���w�肢�����܂��āA���̃z�[���y�[�W��`���Ă����������̍K�������F�肢�����܂��B
�쉤�_�Ђɂ͘a�C�����C���J���Ă��܂��B�ޗǎ��㖖�A�����ɂ���ċ�B�ɗ��߂ɂ������܁A�h�q�ɏP��ꂽ���A�����̒��ɏ�����ꂽ���ƂŁA���̐_�ЂɂȂ��ƂƂ̂��Ƃł��B�����̂悤�ɂ����̍����͍���Ȃ�ł��ˁB�i2007.1.1�j


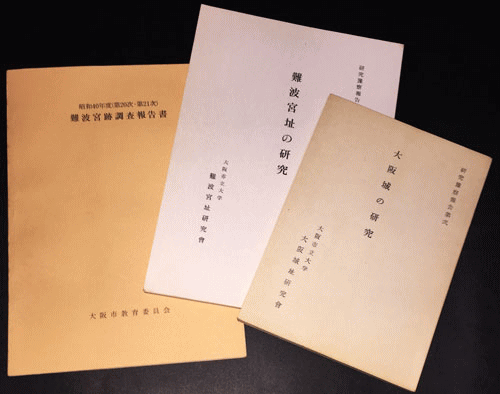
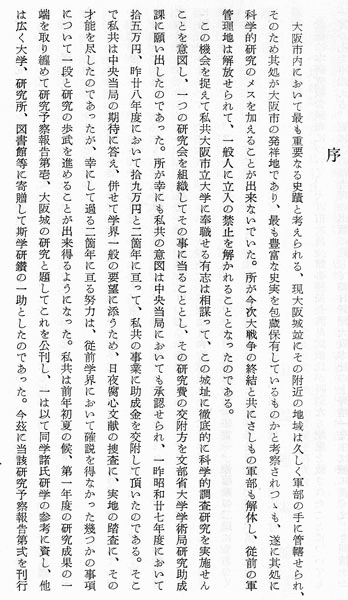
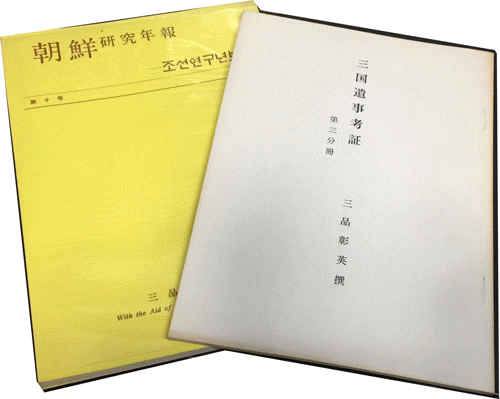
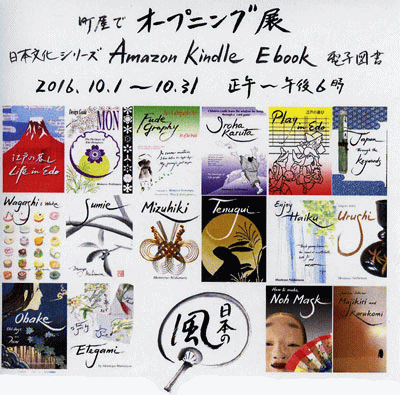 4
4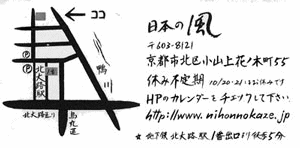


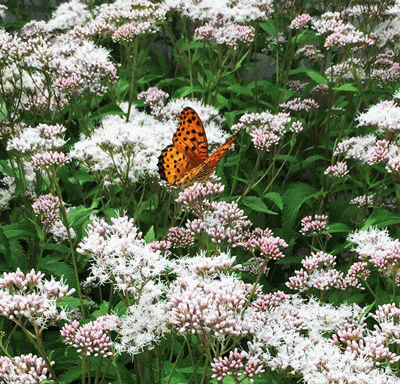



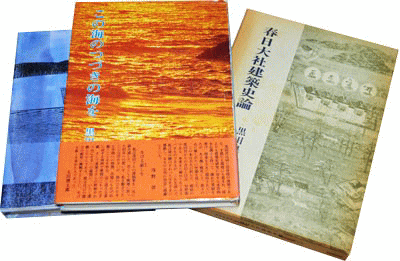
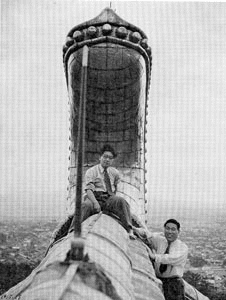
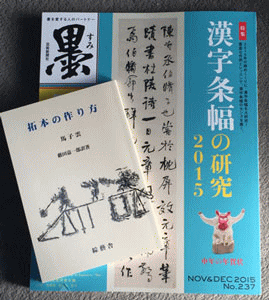


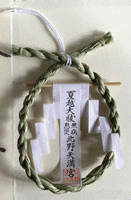

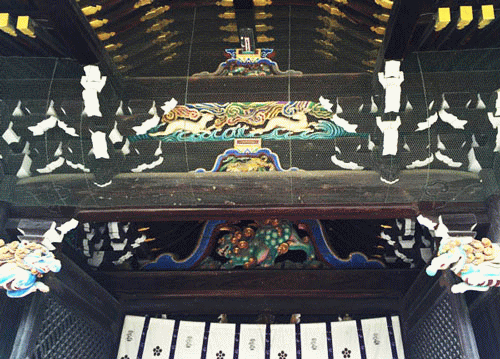




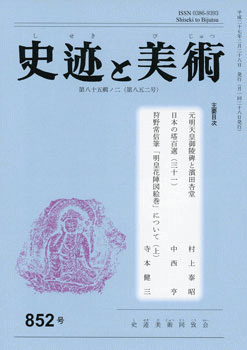

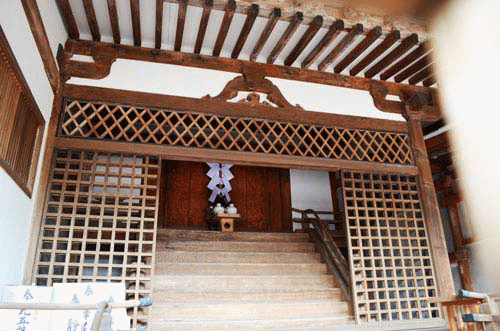
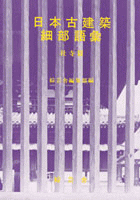
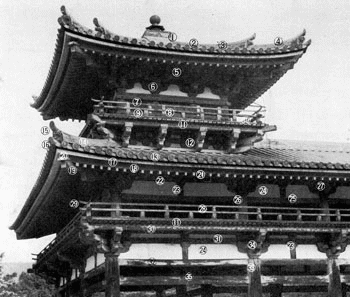
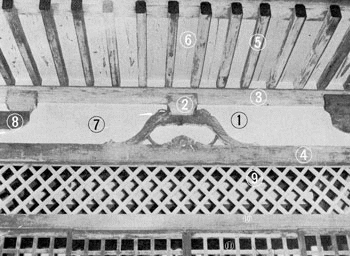
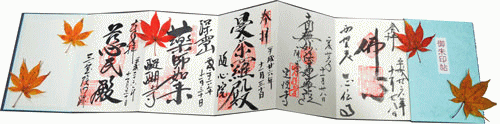 My����ł��B������ƑO�̂P���u���Ō��{�ɍ�������̂ł��B�H�̋��s�k�Ɠ�������܂����B
My����ł��B������ƑO�̂P���u���Ō��{�ɍ�������̂ł��B�H�̋��s�k�Ɠ�������܂����B
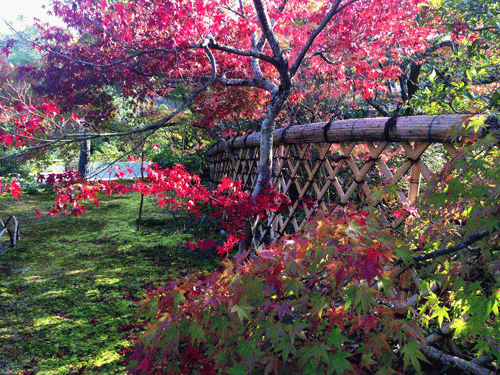


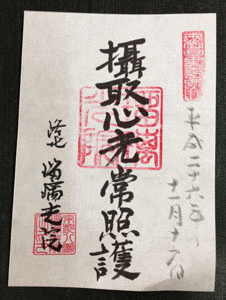
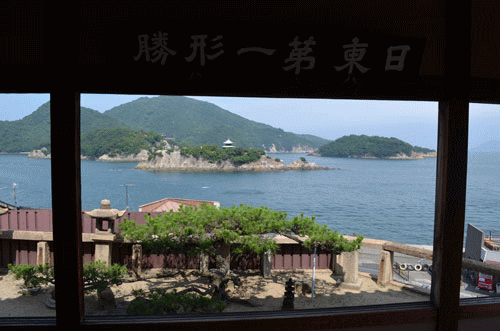
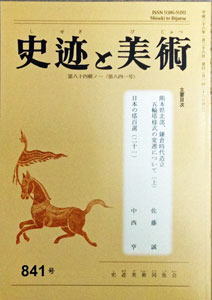
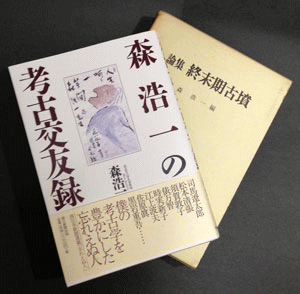
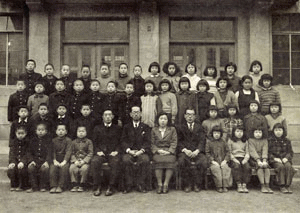
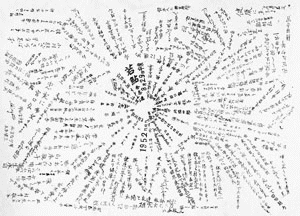
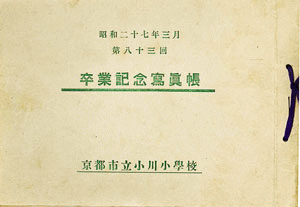


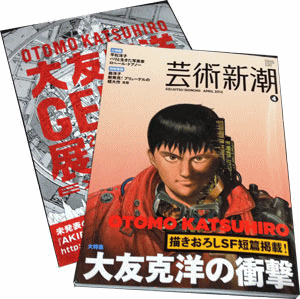




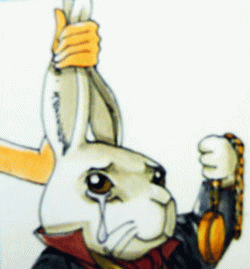


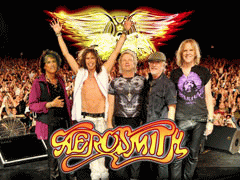

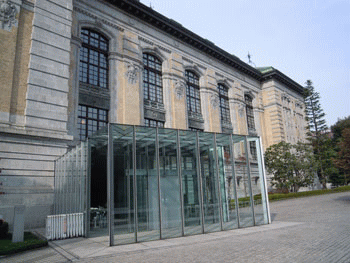


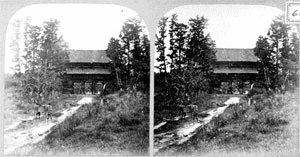

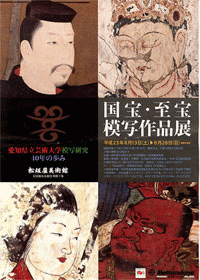

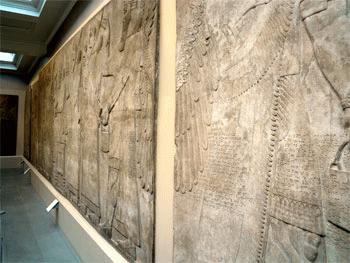

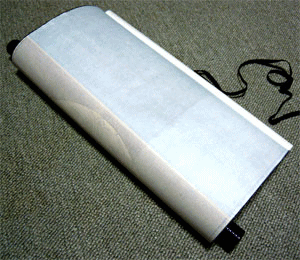
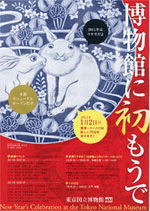
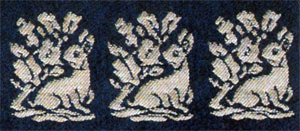

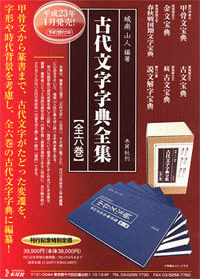


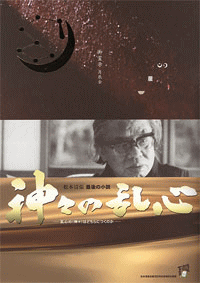


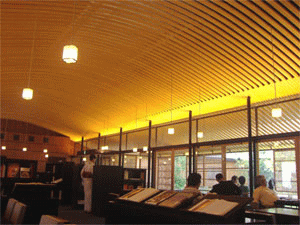

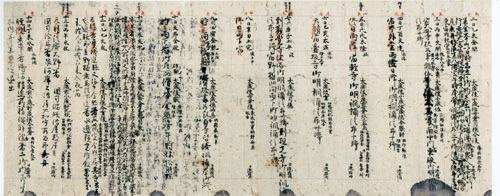


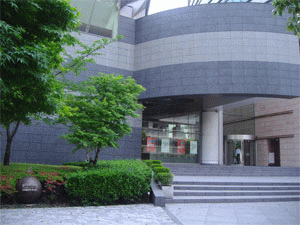
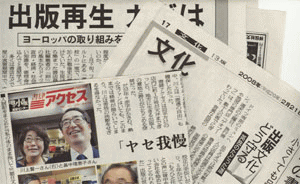 ���|�ɓ����X�u�\���M�������[��v������4�J���ɂȂ�܂��B���܂��ɁA�[���d�b����Ɓu��v�����
���|�ɓ����X�u�\���M�������[��v������4�J���ɂȂ�܂��B���܂��ɁA�[���d�b����Ɓu��v�����
 11��26���\���M�������[��E���|�ɓ����X��27�N�Ԃ̗��j���I���܂����B
11��26���\���M�������[��E���|�ɓ����X��27�N�Ԃ̗��j���I���܂����B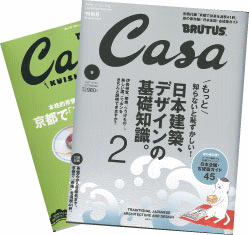 �}�K�W���n�E�X�Ђ̃��C�t�f�U�C���}�K�W���uCasa�@Brutus�v9�����ő��|�ɂ́u
�}�K�W���n�E�X�Ђ̃��C�t�f�U�C���}�K�W���uCasa�@Brutus�v9�����ő��|�ɂ́u


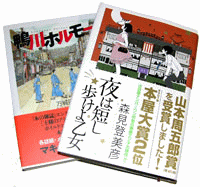
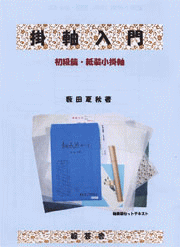
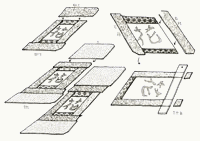

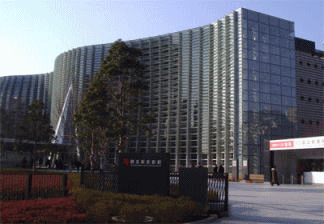 �P���Q�P���I�[�v�������Z�{�������V���p���ɍs���܂����B�����ő勉�̓W���X�y�[�X�̐V���p�فA�I�[�v�j���O�L�O�́u�Q�O���I���p�T���v�Ɓu���{�̕\���́v�Ƃ��̌����̐v�ҁu����I�͓W�v�A���ʂĂĈ�x�݂����悤�Ǝv�����̂ɁA����������J�t�F��X�g�����͖����ł��B�Ă����̂́u�A�[�g���C�u�����[�v���p���̐}���ق����ł���Ƌx�e�ł��܂����B�ł����̃A�[�g���C�u�����[�͖��ɗ��������ł��B
�P���Q�P���I�[�v�������Z�{�������V���p���ɍs���܂����B�����ő勉�̓W���X�y�[�X�̐V���p�فA�I�[�v�j���O�L�O�́u�Q�O���I���p�T���v�Ɓu���{�̕\���́v�Ƃ��̌����̐v�ҁu����I�͓W�v�A���ʂĂĈ�x�݂����悤�Ǝv�����̂ɁA����������J�t�F��X�g�����͖����ł��B�Ă����̂́u�A�[�g���C�u�����[�v���p���̐}���ق����ł���Ƌx�e�ł��܂����B�ł����̃A�[�g���C�u�����[�͖��ɗ��������ł��B
 �����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B���N�͕���19�N����̔N�ł��B
�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B���N�͕���19�N����̔N�ł��B