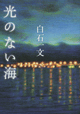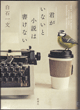| 1. | |
|
「どれくらいの愛情」 ★★ |
|
|
|
4篇の中篇ラブ・ストーリィを収録。 決して深刻で重苦しい内容、という訳ではありません。要は私の感じ方というだけのことなのですが、一篇一篇が長篇作品なみに独立した重みを備えている、と言ったら良いでしょうか。 「20年後の私へ」は、結婚するためにはどんな気持ちが必要であるかを。「たとえ真実を知っても彼は」は、結婚生活を守っていくためには何が必要であるのかを。「ダーウィンの法則」は、愛を貫くことの大切さを。そして表題作であり、唯一書下ろしである「どれくらいの愛情」は、相手を信じきることの大切さを。 「20年後の私へ」は比較的私の好みに近いストーリィですが、「たとえ真実を知っても彼は」はちょっとスリリングなストーリィ。隠された事情は容易に察することができますが、裏を深読みしようと思えば、所詮夫婦だろうとどんな駆け引きがあるのか油断はできない、という代物。 上記3作も読み応えありましたけれど、やはり表題作の「どれくらいの愛情」が圧巻です。どんな風に展開していくのか、ついつい先を飛ばすようにして読みふけりました。 20年後の私へ/たとえ真実を知っても彼は/ダーウィンの法則/どれくらいの愛情 |