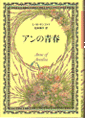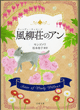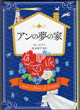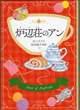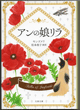|
|
|
|
|
2.アンの友達 3.アンをめぐる人々 4.赤毛のアン 松本侑子訳 5.アンの青春 松本侑子訳 6.アンの愛情 松本侑子訳 7.風柳荘(ウィンディ・ウィローズ)のアン 松本侑子訳 8.アンの夢の家 松本侑子訳 9.炉辺荘のアン 松本侑子訳 10.虹の谷のアン 松本侑子訳 11.アンの娘リラ 松本侑子訳 ※1.“アン・ブックス” |
果樹園のセレナーデ、ストーリー・ガール、黄金の道、青い城、もつれた蜘蛛の巣、銀の森のパット、パットの夢、丘の家のジェーン |
|
|
|
●「赤毛のアン」● ★★★ |
|
|
1954年07月
|
今更言うまでもなく、児童文学における
傑作! そして名作。 呆気にとられるほど空想力に充ちたおしゃべり(パレアナはとても及びません)、溌剌とした感情の豊かさ、明るく開けっぴろげな気性、そして自分の責任を認める勇気。アンのすることなすこと、いつも大騒ぎを引き起こすことばかり。そんなアンが全世界の人々を魅了したからといって、何の不思議もありません。 アンは、グリーンゲイブルスに引き取られて初めて自分の家を持てたのですが、引き取られて面倒をみられるという経験は既に2回もしている訳です。それにひきかえ、クスバート兄妹、とくにマリラにしてみれば、子供を我が家で養育するなどまるで初めての経験。アンがいろいろな失敗を重ねて派手に成長していく一方で、ひそかにマリラもアンへの愛情を育て、それ故に笑ったり嘆いたりする喜びを学んでいくのです。 その意味で、本作品はアンとマリラとマシュウという、偶然の縁で結びついた家族の物語であり、「アンの青春」以降の続編にはない要素を含んだ
作品であると言うことができると思います。 なお、初めて読んだ小学生の頃は、女の子の物語だと思った為か、夢中になることはありませんでした。中学生の頃にアンが好きになり、「アンの夢の家」までを、大学生の頃に以後の「炉辺荘のアン」「虹の谷のアン」「アンの娘リラ」を読みました。したがって、アン周辺の人々を描いた「アンの友達」「アンをめぐる人々」を読んだのは、ネット世界に入り込んでから。 |
|
●「アンの友達」● ★★ |
|
|
|
“アン”シリーズのうち、周辺人を描いた2冊については未読だったのですが、「赤毛のアン」後何人かの方から勧められて
読むに至りました。 奮い立ったルドヴィック/ロイド老淑女/めいめい自分の言葉で/小さなジョスリン/ルシンダ ついに語る/ショウ老人の娘/オリビア叔母さんの求婚者/隔離された家/競売狂/縁むすび/カーモディの奇蹟 /争いの果て |
|
●「アンをめぐる人々」● ★ |
|
|
1959年04月
|
本書は「アンの友達」に続く“続アヴァンリーの記録”。 前作同様に、長年にわたる恋が漸く実るというストーリィが大部分を占めています。しかし、その割に前作程の感動、面白さが感じられないのはどうした訳なのでしょうか。 その中では「シンシア叔母さんのペルシャ猫」がユーモラス、「偶然の一致」はO・ヘンリ的。また、「父の娘」と「ベティの教育」は出来すぎのストーリィですけれど、気持ち良さがありました。 シンシア叔母さんのペルシャ猫/偶然の一致/父の娘/ジェーンの母性愛/夢の子供/失敗した男 /ヘスターの幽霊/茶色の手帳/セーラの行く道/ひとり息子/ベティの教育/没我の精神/ディビッド・ベルの悩み /珍しくもない男/平原の美女タニス |
|
●「赤毛のアン」● ★★★ |
|
|
1993年04月 2000年05月 2019年07月
|
1ヶ月かけて、少しずつ、じっくりと読みました。 すると、これまでのように一気呵成に読んだ時とは、違ったものが見えてきます。つまり、本書の1章、1章それぞれにおいて、アンは何かしらの事件を引き起こしており、1章だけ読んでも十分に楽しめるということです。 それと、アンの言葉に、古典文学(主に英文学)からの引用が実に多いということ。これは松本侑子さんの指摘どおりです。それぞれに詳しい注釈が巻末につけられていますので、気分次第で引用の中味を知ることが出来ます。それによって、アンの物語を一層面白く読むことが出来ます。 松本新訳本の特徴は、この 100頁近くにも及ぶ注釈にあります。また、松本さんによると、村岡訳には省略された部分もある、とのことですが、冒頭のブラウニングの詩を除いてその違いはなかなか判りません。頁数の面では、それ程大きな開きはないのですが。 訳の面では、松本新訳の方が、すっきりと現代的な印象を受けます。幾場面か村岡訳と比べますと、後者の方が言葉をかなりまるめようとしてる気配を感じます。それと、文章における漢字の多寡に気付きます。村岡訳は比較的少なく(多分意識的に)、松本新訳は一般小説程度に多い。ただし、読んでいる最中、村岡訳と松本訳の違いなんて、まるで気になりませんでした。素直に読んで、楽しめました。 感想は前回のとおり。アンだけでなく、マシュウ・マリラ兄妹を含めた新たな家族の物語として読みました。また、アンの成長の様が著しいだけに、シリーズの中でもやはり格別の作品です。 |
|
|
追記 松本訳を読んだ時、一頁一頁村岡訳との違いを比べた訳ではありませんので、明確に村岡さんが省略した部分を知ることはできませんでした。 今般、松本侑子さんご本人からメールを貰い、大きな違いがある場所を教えて頂きました。第37章、第38章とのことです。(リンク先は「赤毛のアン電子図書館」の当該説明ページです) この2章は、マシューの死を含む、小説最後の2章です。村岡さんが省略された部分は、松本訳を読んだ時に強く印象に残った部分。記憶に無かった所為ということもあったかもしれませんが、アンとマリラの感情を深く描いた部分、アンが詩情溢れんばかりにアヴォンリーの土地を形容をする部分で、アン・ファンとしては捨て難い、貴重な部分です。 村岡さんが何故この部分を省略したかというと、児童が理解するには難しい部分だったからでしょう。村岡訳が松本訳に比べて劣るということでは決してありません。私としては、そのどちらも素敵な訳だと思っています。 ただ、訳本というのは所詮限界があるもの。ですから、アン・ファンの方には、村岡訳に留まることなく、松本訳も是非読んでみることをお薦めします。私と同様、きっと新たなアンの魅力を発見することでしょう。 |
|
●「アンの青春」● ★★★ |
|
|
2001年10月 2005年09月 2019年09月
|
シリーズ第2作である本書は、アヴォンリーの学校で教師となったアンの、16歳半からの2年間が描かれています。 第2作には、何を仕出かすか判らない、繰り返し事件を引き起こす活発な女の子はもういません。それ故、「赤毛のアン」的な面白さはなく、「赤毛のアン」、第3作の「アンの愛情」に比べると、本書におけるアン自身の印象は薄いものです。しかし、その代わりに、内面を成熟させつつあるアンがそこにいます。かつての想像好きは変わりませんが、すぐ口に出すということがなくなり、相手、時宜をわきまえて振る舞うことをアンは既に習得しています。本書中では、ポール・アーヴィング、ミス・ラヴェンダーが“心の同類”として登場します。 第2作で特徴的な出来事としては、アンたちが村の改善協会を立ち上げた事、マリラがディヴィとドーラという双子の子供を引き取ったこと、隣人ハリソン氏のこと、ミス・ラヴェンダーのことが挙げられるでしょう。また、第1作と違い、養育される側から養育する側へ、教わる立場から教える立場への変化があり、大人の愛情の在り方にも触れ、それらを糧としてアンは大人の女性への入り口に立とうとしています。 本書の最後で、アンは愛着ある教師生活に一旦終止符を打ち、慣れ親しんだアヴォンリーと親しい人々に別れを告げて、大学進学という新たな生活に踏み出すことを決意します。ダイアナだったら、そんなことはせず、アヴォンリーの穏やかな生活に満足してそこに留まることを選ぶでしょう。しかし、アンは新たな世界に飛び込む意義を信じ、かつての意欲を忘れることなく心を振るって大学への進学を選びます。そんなアンの、人生への前向きな姿勢に、どれだけ勇気付けられる人がいることでしょう。 以前のような突拍子もない行動で人々、読者を楽しませてくれる“赤毛のアン”に代わり、ここには、これからの日々に希望と夢を感じさせてくれるアンがいます。「赤毛のアン」とは異なる趣きですが、深い味わいのある、魅力に充ちた一冊です。 ※本書は訳者の松本侑子さんからプレゼントして頂き、読むに至りました。心からお礼申し上げます。(注:だからといって、ヨイショしていることは決してありません) |
|
●「アンの愛情」● ★★ |
|
|
2008年10月 2019年11月
|
久々に読んだ「アンの愛情」、松本侑子さんの新訳版です。 本巻でアンは、アヴォンリーや親友ダイアナから離れ、ギルバートらと共にカナダ本土の都会キングスポートへ渡り、レッドモンド大学に入学します。 「赤毛のアン」や「アンの青春」の時期を過ぎ、大学生になったアンが主人公ですから、少女時代のような溌剌さがストーリィから影をひそめているのは仕方ないことかもしれませんが、やはり寂しい。 つまり本書は、大学生のアンというより、自由な時間を得て娘から一人立ちした大人の女性へと成長を遂げていく、その孵化期間を描いた巻と言うべきなのでしょう。 松本侑子訳の特徴は、アンらが盛んに用いる英文学上の名詩選、聖書からの引用について、余すところなく注釈を付している点。こんなにも多かったのかと呆れ返る程ですが、それが判ってこその「アン」シリーズの味わいと思います。 なお、“アン”シリーズで欠かせないのは、主人公であるアンと共に、その盟友であるギルバート・ブライスの存在。 |
| 「風柳荘(ウィンディ・ウィローズ)のアン」 ★★ 原題:"Anne of Windy Willows" 訳:松本侑子 |
|
|
2020年01月
|
アン物語としては4巻目になりますが、執筆順序としては8冊中の7番目。モンゴメリ62歳の時の作品です。 ※私が最初に読んだ時は「アンの幸福」という題名でした(角川文庫は「アンの愛の手紙」だったかな)。 婚約が成った後、引き続き医学部で勉強を続けるギルバートと離れアン(22歳)は、アヴォンリーとは島の反対側(本土側)、港湾都市として栄えるサマーサイドの高校に学校長として赴任します。 アンの下宿先となったのは、2人の老婦人が暮らす風柳荘(ウィンディ・ウィローズ)という名の家。本作はサマーサイドでのアンの3年間が描かれます。 「アンの愛情」までの3作品と比較すると、本作はかなり落ち着いているという印象です。 作者の執筆年齢によるところもかなり大きいと思いますが、ギルバートとの婚約で身辺が落ち着いたこと、教師としてもベテランでその立場も安定していることもあるでしょう。 もっともそれは同時に、アンの成長ストーリィからは程遠くなっているということでもあり、刺激的な面白さは余りないなぁ。 ストーリィは、アンのギルバートに宛てた手紙+日常ストーリィ+登場人物幾人かの人生ドラマ、からなっています。 なお、冒頭では、町の有力者であるプリングル一族から何故か憎まれたらしく、アンの苦闘が描かれていて少々スリリング。 全体を通しては、下宿先の女中である個性的な人物レベッカ・デューと、隣家の常磐木荘(エヴァーグリーンズ)で老婦人に抑圧的に育てられている少女エリザベス・グレイソンの存在が印象に残ります。 本作は久しぶりに読みましたが、何だかんだといっても“アン”魅力に富んだシリーズです。 松本侑子さんの訳本は詳細な訳注が付されていることが特徴ですが、その分余計に“アン”を楽しめるというもの。 ファンとしては嬉しいことです。 一年目/二年目/三年目 |
| 「アンの夢の家」 ★★ 原題:"Anne's House of Dreams" 訳:松本侑子 |
|
|
2020年11月
|
“アン”シリーズ第5作。 松本侑子さんの新訳を機にした、久しぶりの再読です。 アンがギルバートと結婚、アヴォンリー、グリーン・ゲイブルズを離れてセント・ローレンス湾に面したフォー・ウィンズ、その海辺にある“夢の家”で新婚生活を始める巻です。 アン・シャーリーからアン・ブライスに姓が変わったからと言ってアン自身に変わりはない筈なのですが、やはりこれまでの巻とは変わったな、という印象を受けます。 ひとつは、アンにそれまでのような溌溂さが無くなった、ということ。元気がなくなったということではなく、そこは結婚した女性という抑制が働くようになった、ということでしょう。 また、「奥さん」と呼ばれる立場となり、交友関係が近所に住む大人ばかり、子どもの登場がないということもあります。 ・ジム・ボイド船長:老人で今は灯台守。マシューに似た存在観あり。マシューよりもっと交際上手ですが。 ・ミス・コーネリア:中年の独身女性。度々アンの家を訪れ、ストーリィにリズム感を与えている存在です。何かというと「男のやりそうなこと」と批判的に口にする等々がユーモラス。 ・レスリー・ムーア:アンより3歳年上のすこぶる美人女性。それが仇となって不幸な結婚をする羽目になり、今も苦しむ。 アン一人が突出した登場人物ということにならず、アンと上記3人(お互いにそれぞれ親しい)がグループで織りなすストーリィという観が強い。 ここまで来たのですから、次巻「炉辺荘のアン」が楽しみです。 1.グリーン・ゲイブルズの屋根裏で/2.夢の家/3.分かち合う夢の国/4.グリーン・ゲイブルズ初の花嫁/5.わが家へ/6.ジム船長/7.学校の先生の花嫁/8.ミス・コーネリア・ブライアント、訪ねて来る/9.フォー・ウィンズ岬の夕べ/10.レスリー・ムーア/11.レスリー・ムーアの物語/12.レスリー、来たる/13.幽霊の夜/14.十一月の日々/15.フォー・ウィンズのクリスマス/16.灯台の大晦日/17.フォー・ウィンズの冬/18.春の日々/19.夜明け、そして黄昏/20.いなくなったマーガレット/21.壁、消え去る/22.ミス・コーネリア、手配する/23.オーエン・フォード、来たる/24.ジム船長の人生録/25.本の執筆/26.オーエン・フォードの告白/27.砂州にて/28.種々様々/29.ギルバートとアン、意見の不一致/30.レスリー、決意する/31.真実は自由にする/32.ミス・コーネリア、仰天事を話し合う/33.レスリー、帰る/34.夢の船、内海に入る/35.フォー・ウィンズの政治運動/36.灰に代えて美を/37.ミス・コーネリア、驚きの発表をする/38.赤い薔薇/39.ジム船長、砂州を越える/40.さようなら、夢の家 |
| 「炉辺荘のアン」 ★★ 原題:"Anne of Ingleside" 訳:松本侑子 |
|
|
2021年11月
|
“アン”シリーズ第6作。 ただし、執筆されたのは最後、65歳の時の作品。 つまりは、晩年になって「アンの夢の家」と「虹の谷のアン」の間に挟み込む形で執筆された一冊、ということです。 冒頭、アンは長男のジェム(「夢の家」で誕生・7歳)を筆頭に3男2女の母親。そして本書中で末娘リラが誕生し、3男3女という子沢山の母親になります。 それでもすらっとした体つきは変わらず、子供たちも自慢の綺麗な母親というのは、アンのイメージを壊さず、ということでしょう。 本作は、母親であるアンとその子供たちの物語、といったストーリィ内容で、短編小説ともいえる「章」を繋いでひとつの物語にしているようです。その中では当然にして、アンの子供たち一人一人が主人公になっている章があります。 (ジェム、ウォルター、双子のナン&ダイ、シャーリー、リラ) なお、ギルバートは常に登場するものの、アンの背後に収まっているという感じで、医師業が多忙ということなのでしょう、子育ての役割は余り担っていないようです。 本作、1975年に村岡花子訳で一回読んだだけなので47年ぶりの再読ということになるのですが、改めて読んでみると「赤毛のアン」と対称的に描かれていると感じます。 まず冒頭、アヴォンリーに一時的滞在したアンが、親友ダイアナと2人で少女時代を思い出しながら、かつての馴染み場所を散策するところが描かれます。 そして最後は、「赤毛のアン」と同様、詩的情趣に溢れた幕切れとなっています。 晩年のモンゴメリが“アン・ブックス”を達観する気持ちで、最後を締めるつもりで執筆したからではないか、と想像します。 なお、最終章、いみじくもアンとギルバートの絆を再確認するような展開になっていますが、「アンの愛情」の最後を思い出させられる内容です。 結局、“アン”物語は、“アン&ギルバート”物語でもあったのだということでしょう。 |
| 「虹の谷のアン」 ★★ 原題:"Rainbow Valley" 訳:松本侑子 |
|
|
2022年11月
|
“アン”シリーズ第7作。 ただし、本巻での主人公は子供たち、特にやもめの牧師メレディスの4人の子供たちであって、アンは脇役にすぎません。 そもそも原題は単に「虹の谷」ですし、虹の谷は子供たちお気に入りの遊び場所であって、アンは無関係。それなのに題名に「アン」を付けたのは、“アン”シリーズであることを謳うためでしょう。 登場する子どもたちは、ブライス家の6人に、彼らと仲良くなる新しい牧師メレディス家の4人、そして引き取り手の扱いの酷さにそこを逃げ出してきた孤児のメアリ・ヴァンス。 ストーリィは常にこの三角関係の枠組みで進みますが、主役となるのはブライス家ではなく、メレディス家の4人という次第。 ジェリー、フェイス、ウーナ、カールという男女2人ずつの子供たち、4年前に母親を喪い、父親のメレディス牧師はいつもぼんやりしていて子供たちのことを何も気づかず、家事担当のマーサおばさんは耄碌している上に頑固とあって、食事も服等も惨めな状況。 基本的に善良で素直な子供たちなのですが、彼らを躾ける者は誰もおらず、彼らの行動は何かと教会の信者たちから非難の的。 そこにメアリ・ヴァンスの存在が加わることによって、さらに面白くなるのです。 メアリ自身も悪気はなく、助けてくれたメレディス家の子供たちのためを思っての言動なのですが、その度にメレディス家の子供たちに余計な騒ぎを起こさせてしまいます。 それらの事件がいつもアン、家政婦のスーザン・ベイカー、ミス・コーネリアの話題に上るのですが、終盤にはさすがのミス・コーネリアも、あの子たちを庇うのにももう疲れた、と嘆くのですから、想像しようがあるというもの。 ただ、最後にようやく、メレディス家の子供たちにも吉報がもたらされ、当人たちも周囲の大人たちも、やっと安心できることになります。やれやれ。 俯瞰すれば、子供たちが子供たちでいられる間の物語、と言えるでしょう。最終章がそう暗示しているように感じられます。 |
| 「アンの娘リラ」 ★★ 原題:"Rilla of Ingleside" 訳:松本侑子 |
|
|
2023年12月
|
松本侑子訳“アン”シリーズ第8作にして完結。 本作を読むのはこれで3回目。前回読んだのは1975年、新潮文庫の村岡花子訳ででした。 本作については同シリーズの他の巻と違い、単純に面白がってばかりいられない、暗く重苦しい雰囲気があったことを今でも忘れられません。 それもその筈、時代は第一次世界大戦勃発から4年間、三男三女のブライス家においても、ジェム、ウォルター、シャーリーと、次々に3人の息子全員が出征し、両親やリラ、そして家政婦のスーザンらも、一時も心安らかでいることはできません。 そうした中で、末っ子で甘ったれた処のあったリラが、兄たちが出征し、姉たちも家を離れた今、ただ一人炉辺荘に残り、しっかりして両親たちを支えるという役目を果たすことになります。 そうしたことを通じて、リラ15歳の時から始まり4年間に亘る日々の中、見事に成長していく姿が描かれます。 勿論これまでのように、幾人もの恋模様も描かれますが、男たちは出征していくという時代の中、浮かれた雰囲気はありません。 原題は「炉辺荘のリラ」であり、シリーズ第1作の「グリーンケイブルズのアン」と対比されているのでしょう。 アンの時代が、のどかで平穏なアヴォンリーの村で伸び伸びと育つことができたのに比べ、リラの時代は電話等々便利なことも増えたとはいえ逆に世界情勢によって日々の生活が脅かされるという、対照的な世界となっています。 なお、第6作は「炉辺荘のアン」であり、アンとリラがバトンタッチしたように感じられますが、刊行されたのは本作の18年後ですから、第1作と対比して味わうのが相応しいように思います。 本作は、第一次世界大戦当時の、銃後の女性たちの暮らしを敢えて描き、同時に若い娘リラの成長と恋を描いた物語、と言って良いのでしょう。 ※レマルク「西部戦線異状なし」を懐かしく思い出しました。 1.グレン村「通信」ほか/2.朝の露/3.月明かりの宴/4.笛吹き、笛を吹く/5.「行軍の音」/6.スーザン、リラ、犬のマンディ、決心する/7.戦争孤児とスープ入れ/8.リラ、決意する/9.博士、災難にあう/10.リラの悩み/11.暗と明/12.ランゲマルクの日々に/13.屈辱のパイ/14.裁きの谷/15.夜が明けるまで/16.現実とロマンス/17.過ぎ去っていく日々/18.戦時結婚/19.「奴らを通すな」/20.ノーマン・ダグラス、集会で意見する/21.「恋愛はむごい」/22.小さな犬のマンディは知っている/23.「それでは、お休み」/24.メアリ、間一髪で間に合う/25.シャーリー、出征する/26.スーザン、求婚される/27.待ち続ける/28.暗黒の日曜日/29.「負傷および行方不明」/30.潮の変わり目/31.マティルダ・ピットマン夫人/32.ジェムからのたより/33.勝利!/34.ハイド氏は自分の場所へ、スーザンは新婚休暇へ/35.「リラ・マイ・リラ!」 |
|
※1 |
|
|
“アン・ブックス” |
|
|
|
01.赤毛のアン Anne of Green
Gables |
|
「アンをめぐる人々」を最後に、アン・ブックス全冊を読み終えました。しかし、振り返って考えてみると、本当に面白かったのは「赤毛のアン」「アンの青春」までではなかったかと思います。少女時代とその延長期にあるアンがそこにいたからです。 |
|
| 「アン」物語は結局、「赤毛のアン」〜「アンの夢の家」で本来完結するものだろうなと思います。 邦題だとそう感じられないことも、原題からは強く感じられます。 「グリーンゲイブルズのアン」は、孤児のアンが居場所を得るという巻。そして「アヴォンリーのアン」、「島のアン」ではアンの世界が広がっていくことが謳われ、そして「アンの夢の家」に至り孤児だったアンがついに自分の家庭を手に入れるという流れ。 ですから、それ以降の巻は、率直に言って<付け足し>なのでしょう。 「虹の谷」は子供たちの物語、「風柳荘のアン」は書簡体小説の楽しさを味わえる巻。 「炉辺荘のアン」は、「グリーンゲイブルズのアン」と対称的。 そして邦題「アンの娘リラ」も、原題は「炉辺荘のリラ」で、やはり「グリーンゲイブルズのアン」、「炉辺荘のアン」と対称的な関係にあります。 なお、こうした整理をしようがしまいが、「アン」シリーズを読むのが楽しいことに変わりはありません。ですから上記は単なる自己満足。 (2023.01.27) |
|
※ 他作家によるアン物語 → バッジ・ウィルソン「こんにちはアン」
|
“アン”シリーズ執筆順序(松本侑子「誰も知らない赤毛のアン」より) |
|
|
|
1908(作者34歳) 赤毛のアン アン:11〜16歳 1936(作者62歳) アンの幸福(風柳荘のアン) アンの婚約時代 ※モンゴメリ自身がシリーズとして組んだ本は6冊だけだそうです。つまり、子供たちの本は除外されている、ということ。勿論、「アンの友達」と邦題のついている「アヴォンリー年代記」(正・続)は含まれません。 |