管球式NF−CR折衷型プリアンプの設計と製作
---- MJ 1988.9 所収 ----
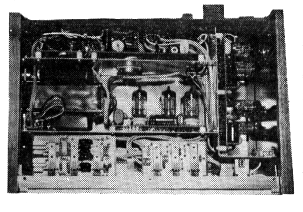
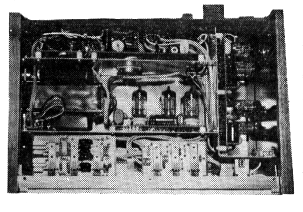
全段SRPPを採用し、ダイナミックレンジとSN比のバランスがよく、動作原理の単純なNF−CR折衷型のプリアンプです。イコライザーアンプの最大出力は80Vあります。
 次のページ
次のページ
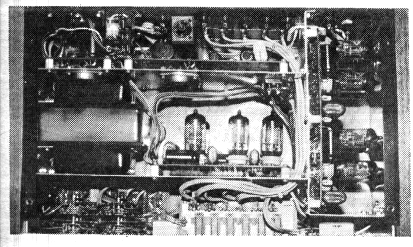
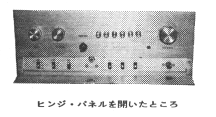
ディジタル化が進むオーディオ界では、自作派の活躍できる範囲もだんだんせばまりつつあるようです。しかし、欧米ではマニアの間で管球式アンプが一つの流行とか。真空管が製造停止になって久しい日本と比べると、趣味の世界にはいろいろな価値観が存在するのが自然だという考えがあるのでしょう。ところで最近の管球式アンプは、昔の銘機と言われたマランツ、マッキントッシュに比べて、技術的に進歩しているのでしょうか。管球式プリアンプの最近の傾向として、無帰還アンプによるCR型イコライザーを採用したものが多いようです。歴史的には最も古い方法ですが、以前NF型がもてはやされた頃に指摘されたCR型の欠点は克服されているのでしょうか。素子の進歩がない管球式の場合、必ずしもCR型が良いとは言い切れないようにも思えるのです。
この記事ではNF型とCR型の良さを合わせ持つNF−CR折衷型のイコライザー及びトーンコントロールを採用した管球式プリアンプについて紹介します。本機は昭和57年に一応完成して、その後改良を加えながら現在も使用中で、基本性能の点でも、また安定度の点でも問題ないことが確かめられています。
プリアンプの設計がパワーアンプの設計と大きく異なる点は、全体の構成を考える必要があることです。機能を必要最小限にとどめれば設計・製作は容易になります。しかし、一方で自分の欲しい機能はなんでも盛り込むことができるのも自作ならではの良さと言えます。このアンプを製作するにあたって、表1のような仕様を考えました。これがこのプリアンプの設計目標と言うことになります。順に少し詳しく説明してみましょう。
表1 プリアンプの仕様
| 入力切り換え | |
| フォノ | 1系統 |
| ハイレベル入力 | 3系統以上 |
| イコライザー段 | |
| 利得 | 40dB |
| SN比 | A補正で入力換算−120dBV |
| 許容入力 | 1kHzで500mVrms以上 |
| RIAA偏差 | ±0.5dB以内 |
| トーンコントロール段 | |
| 利得 | 20dB |
| 最大出力 | 20V以上 |
| 周波数特性 | 20〜20kHzで±0.5dB以内 |
| トーンコントロール特性 | |
| 周波数切り換え可能 | |
| 可変幅 | ±6dB程度 |
(1)入力切り換え・レベル調節等の機能
最近はCDプレーヤーを使うことも多いのですが、プリアンプの技術的テーマとしては、イコライザー・アンプを避けて通るわけには行きません。フォノ入力は配線の引き回しを避けるため1回路のみとし、入力端子のすぐそばに初段管を配置します。ハイレベルの入力は多い方が何かと便利なので、テープ入力2系統のほかに3系統用意したのですが、最近ではAV機器がつながるようになってこれでも足りないくらいです。使い勝手の点から入力切り換えはプッシュスイッチを使います。また、テープ入力はテープモニター・スイッチと入力切り換えのどちらからでも使えるようにしておき、普段使わないテープモニター・スイッチは前面のヒンジ・パネルの中に収めることにしました。モード切り替えは、モノラルとリバースにできるだけの簡単なものですが、機械の接続をチェックするときなどに重宝します。
高域特性を悪化させないためにはVOLUMEやBALANCEの抵抗値の選び方が重要です。管球式アンプでは負荷を軽くする意味から、通常250kΩ程度のことが多いようですが、これで配線の引き回しを行うと高域特性の劣化を招きます。それを防ぐには100kΩが限度でしょう。これでも最もインピーダンスの高くなる中点の状態では、対アース間容量を50pFとしてカットオフ周波数は120kHz程度となってしまいます。BALANCEはVOLUMEの前に続けて置かれるのが普通ですが、イコライザー段の負荷が重くなることを避ける意味で、トーンコントロール段の後へ持って行くことにしました。BALANCEはあまり調整することもないので、MN型を使い損失を防いでいます。最近のテープデッキは入力インピーダンスが低く、特に電源が入っていない状態では非常に低くなることがあります。REC OUTのON−OFF切り換えを付けたのも、イコライザー段にバッファーが付いていないので、負荷が重くならないようにするためです。従って通常はOFFにしておきます。
トーンコントロール段の後に10dBステップのレベル切り換えを設け、レベル調整のできないパワーアンプと組み合わせる時にSN比を悪化させないですむようにしてあります。バッファー段の出力にはスイッチONの時の雑音をカットするためにタイマーリレーを使ったミューティング回路を設けてあります。大体30秒程度で雑音は無くなるようです。
(2)イコライザー段
増幅度は少し大きめの方が使いやすいので40dBに設計し、雑音の点ではハムが無いことと、JIS・A補正を施して入力換算−120dBVを目標とします。許容入力は大きい方が良いわけですが、1kHzにおいて500mV程度(つまり最大出力50V)を目標としました。技術的には許容入力より最大出力の方が設計の目安になります。高域(10kHz程度)で殆ど最大出力が低下しないことが条件です。供給電圧はあまり高くしたくないので、電源利用効率の良い回路を工夫する必要があります。一般に電圧増幅管では、供給電圧の1/4程度の実効出力電圧が得られれば上出来と言えます。このため球数が多くなりますが、全段SRPPを用いることにしました。RIAA偏差は精度の良い測定が難しいのですが、少ない方が良いのは当然で、可聴帯域内では±0.5dB以内に収めたいものです。
(3)トーンコントロール段
トーンコントロールは使わない方も多いと思いますが、スピーカーや部屋の音響特性の補正が必要な場合、まずグラフィック・イコライザーを使ってトータルの伝送特性をフラットに近付け、ソースの帯域バランスを補正するためにトーンコントロールを使うのが良いと思っています。そのためには、変化量は少なくても良いのですが、ターンオーバー周波数を切り換えて微妙な調整ができることが望ましいのです。本当は中域も可変出来る方が良いのですが、回路が複雑になるので、普通に高域、低域のみとしました。変化量は±6dB程度あれば十分です。トーンコントロール段全体の増幅度は20dBとし、最大出力は20V以上欲しいところです。なお、出力側にトーンコントロールの素子が挿入されて出力インピーダンスが高くなるため、バッファーアンプを付けています。また全体に低インピーダンス化を図って、配線の浮遊容量による高域特性の悪化や誘導雑音を防ぐようにします。
高域フィルターは使わないので省略しました。超低域フィルターは必要なものなので、本機の場合ははじめから可聴帯域以下の超低域は減衰させています。

イコライザー方式には大きく分けて、NF型、CR型、NF−CR折衷型があります。以前は管球式、TR式を問わずNF型が多かったのですが、最近のアンプではCR型が主流です。TR式の場合には素子の性能向上により、十分なSN比が得られていますが、管球式の場合、CR型にはSN比か許容入力のどちらかを犠牲にしなければならないという欠点があります。図1にCR型の構成例を示しますが、前段で利得をかせぐとSN比では有利だが高域の許容入力の点で不利となります。逆に後段で利得をかせぐと、許容入力では有利だがSN比の点で不利となります。通常は共に30倍程度に設定し、EQ素子での1/10の減衰と合わせて全体の利得を100倍程度とすることが多いようです。
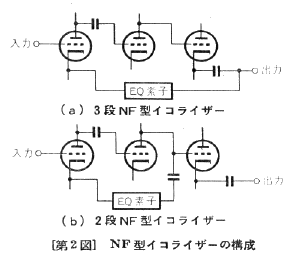
図2にNF型の構成例を二つ示します。マランツで有名な3段型は、バッファー段を強力にすれば相当良いデータが出せるため、いろいろ改良した回路が使われています。私もいろいろ作ってみましたが、測定してみると発振はしていなくても不安定なことが多く、NF技術に頼った設計と言えます。マッキントッシュが採用した2段型はNFの安定度の点では良いのですが、2段目の高域における負荷抵抗が低くなるために、高域の許容入力の点では不満が残ります。結局NF型に関しては随分研究されてはいますが、決定版と呼べるほどの回路はないようです。

NF−CR型は従来、図3(1)に示すように入力に高域のロールオフを置くのが普通でしたが、これはSN比の点で明らかに不利なので使いたくない回路です。(2)のようにNFアンプを2ユニット使い、前段で低域のターンオーバーをNF型で行い、ユニット間に高域のロールオフをCR型で置く構成をとると、利得のロスがないため、SN比、許容入力、動作の安定度と全ての点で一応満足のいく結果が得られます。1kHzでのそれぞれのユニットの利得を10倍ずつにしておけば全体では100倍の利得となります。NF型に比べ後段ユニットの高域雑音がそのまま出てくるという欠点はありますが、全帯域にわたって出力対歪み特性の変化が少なく、NFの動作解析が極めて簡単なのが特徴です。このアイディアは、以前本誌でも安井章氏によって発表され*1、メーカー製アンプにも採用されたことがありますが、もっと見直されて良いと思います。
*1 無線と実験、1976年8月号、9月号.
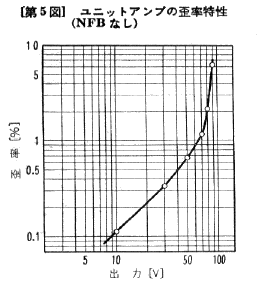
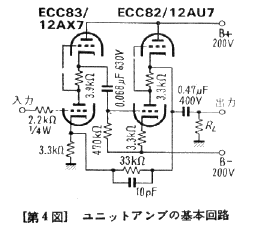
本機では、10倍程度の利得をもつユニットアンプを考え、イコライザー段に2個、トーンコントロール段に1個使用することにしました。このようにアンプを標準化することによって、充分に回路を煮つめることができます。ユニットアンプを設計するにあたっては、表2に示すような性能仕様を目標とします。基本的には裸特性を良くして、NFBはあまりかけずに安定度を重視する考えをとります。NFBなしで20kHzまでフラットとか歪率を低くすることは、従来の管球式NFアンプでは割合軽んじられていた要素と言えるでしょう。2段アンプを構成するのに、良く使われる12AX7−12AX7という構成では、利得が高過ぎ帯域も狭くなってしまいます。最大出力を大きく取るために2段目にSRPPを採用し、12AX7−12AU7の組み合わせで行くことにしました。SRPPについては、以前本誌に動作の解析が紹介されたことがありますが、結論を簡単にいうと、低μ管でカソード抵抗を大きめに選び、カソードのパスコンを外すと、プッシュプルのバランスが取れて極めて低歪みとすることが可能となります。また、インピーダンスを下げて高域特性を良くするため、1段目もSRPPとしました。図4にユニットアンプの基本回路を示しますが、この定数ではSRPPのバランスがかなり良く取れて低歪みとなります(図5参照)。ただこのバランスは出力負荷抵抗によって変わるので、あまり完全にバランスをとるのは無理です。もしバランスを完全にとるならば、バッファーアンプが必要でしょう。また2段目のカソードのパスコンを外したため、電流帰還がかかって利得が少なくなり、ミラー効果による高域の減衰がおきにくいという利点があります。実験機ではNFBなしでのカットオフ周波数が40kHz以上でしたが、実際に基板を起こしたところ、浮遊容量が増えて20kHzそこそこに留まったのは残念です。
もう一つ2段NFアンプに重要な問題点は、低域の時定数が2個となるため、NF量が多いとスタガー比を確保することが難しい点です。よく知られているように、過渡応答が振動解を含まないためにはNF量の4倍のスタガー比が必要です。しかしNF量が少なくない場合、4倍のスタガー比を確保することは困難です。本機の場合、裸利得が46dB、NF量が26dBで最終的に20dBの利得を得ているために、スタガー比は80必要です。一方を10Hzとしても他方は0.125Hzとなって、ちょっと難しいでしょう。これを解決するには、時定数を1個にするのが簡単です。2段目を正負両電源で駆動することにより、2段目出力のコンデンサーを取り除くことにしました。ただ、カソード抵抗が大きいため、2段目の出力点は0Vではないので、出力のカップリング・コンデンサーは必要です。また、容易に想像がつくように、直流NFBによって初段のバイアスにも影響が出ます。若干問題の残るところかも知れません。
表2 ユニットアンプの仕様
| 利得 | 20dB |
| 最大出力 | 50Vrms以上 |
| 周波数特性 | NFBなしで20〜20kHzで±3dB以内 |
| 歪率 | NFBなしで10V出力時0.1%以下 |

トーンコントロールについては使わないという人も多いかも知れませんが、きめ細かいコントロールができるものは有用です。スピーカーや部屋の音響状態を補正するには、グラフィックイコライザーが必要だと思いますが、それをフラットにした後、ソースの音を補正したくなることがあります。それにはなめらかな変化特性を持つトーンコントロールの方が使いやすいのです。そういう意味からあまり変化量を大きくせず、周波数を切り換えられる方が良いでしょう。今回は普通に高域、低域のコントロールを設けましたが、QUADのアンプに見られるように、全体をシーソー型に変化させるリニアイコライザーと低域のブーストを組み合わせるという方式も使いやすいと思います。音色を大きく変化させるには、中域のコントロールも欲しいところですが、回路が複雑になるので省略しました。
トーンコントロール段の構成としては、図6に示すように1段帰還型と2段帰還型が一般的です。BAX型に代表される1段帰還型は、構成が簡単で、トーンコントロール素子をグリッドに挿入するため特性がうまくでやすいという特徴があります。LUXのようにフラット時の周波数特性のうねりを取り除いたものや、中域のコントロールもできるタイプもあります。しかし私としては、トーンコントロールのために余計な増幅段が入るのが気に入らないところなのです。これに比べて2段帰還型は、利得を持つアンプのNF抵抗に選択特性を持たせるため無駄がないのですが、インピーダンスの低いカソードにトーンコントロール素子がつながるため、思ったような特性を出すのが難しいのです。
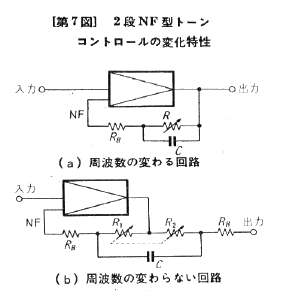
2段帰還型のもう一つの欠点は、周波数を切り換えるのが難しいことにあります。簡単な回路で切り換えるためには、特性を決めるコンデンサーを1個とすれば良いのですが、例えば低域上昇の場合、図7(1)に示すように単にコンデンサーの並列抵抗を変化させたのでは、変化量の少ない時と多い時とでターンオーバー周波数が変化してしまう結果となります。これを防ぐには(2)のようにパラメータをもう一つ増やして、周波数が変化しないようにすれば良いのです。もっともこうすると、出力が抵抗で分割されるため、最大出力電圧が低くなるという欠点があります。回路図でみて分かるように、高域でもパラメータを増やし、NFB回路と次段の抵抗値の等しい対称形としました。こうすると、上昇・下降の抵抗が共用できるようになります。また、フラット位置では完全にコンデンサーが回路から外れるようにしてあります。周波数特性の計算式はかなり複雑なので省略しますが、さらに直流をスイッチに流さないようにしたため、コンデンサーが入って回路が複雑になるとともに超低域の特性が不自然になってしまいました。スイッチの切り替え雑音を防ぐための処置なのですが、このあたりは少し凝りすぎたかも知れません。
バッファーアンプは12AX7のSRPPにより、低歪で大きな最大出力電圧が得られます。トーンコントロール段の最大出力はトーンコントロールの調整と、レベルコントロールの位置で変わりますが、結局パワーアンプの最大入力を越える電圧は必要ないはずですから、不足ということはないでしょう。
 目次
目次
 次のページ
次のページ