物語研究会九月例会・年間テーマ「物語学の限界」 1998.9.19 國學院大學
物語学の限界、さらには研究者個々人の、研究への立脚点と、その限界点とを見定める。
絶望の言説-限界の竹取学、文献学と物語世界の臨界線
僕の卒業論文は『竹取物語の研究』(1986)でした。数年後書いた修士論文もやはり『竹取物語の研究』(1990)で、古本本文(新井本)を底本に、伝後光厳院宸翰の古筆切本文数葉・『風葉集』所引の和歌本文・『海道記』本文等を以て本文批判を実施し、流布本に対置する古本系の 物語本文の宗本(アーキタイプ)を復原しようと企図したものです。その間、漢文体『竹取』先行説やら『斑竹姑娘』原本説などにも寄り道したりして、その頃の思考の残骸が『研究講座竹取物語の視界』(1998)に再録されてしまいました(初出1989)。今、あの頃の感慨を吐露すれば、文献学理論を厳密に突き詰めると、やはり『竹取物語』を以てしても、院政期はおろか、伝本状況の比較的良好な『風葉集』所引の和歌本文以前には遡れないのだ(もちろん大島本『源氏物語』絵合巻所引本文にも先行して)、と言う絶望感がありました。そして、そこから逃避しようとして、慣れない作品世界へと迷い込んだのが、先の論文だったのです。
つまり、現存の『竹取翁物語』は、どの本でも平安時代の言説として語る資格を有しません。しかし、これらのテクストを、世界文学に冠たる物語言説であると称揚するしかないことにこそ、欺瞞に満ちた、我々「物語研究者」の宿業であることを、直視・確認しつつ、それでも、そこから僕の物語学の臨界線を見つめ直したいと思っています。(8.31稿)
古本『竹取物語』とは何か
いまはむかし、たけとりのおきなといふものありけり。野山なるたけをとりてよろつの事につかひけり。名をは、さるきのみやつこと《なむ》いひける。そのたけの中に、もとひかる竹、ひとすちあり。あやしかりてよりて見るに、つゝの中ひかりたり。それをみれは、三すんはかりなる人、いとうつくしうてゐたり。おきないふやう、我あさことゆふへに、見るたけの中に、おはするにてしりぬ。子になり給へき人なんめり、とて、手にいれていゑにもてきぬ。めのをんなにあつけて、やしなはす。うつしきことかきりなし。いとおさなけれは、こにいれてやしなう。たけとりのおきな、なを竹をとるに、この子を見つけてのちとる竹に、ふしをへたてて、ことにこかねある竹見つくる事、かさなりぬ。かくておきな、やうーーゆるらかになり行。このちこやしなうほとに、すくーーと、おほきになりまさる。三月はかりやしなうほどによきほとなる人になりぬれは、かみあけなとさうして、かみあけさす。もきせ、ちやうのうちよりもいたさす、いつきやしなう。このちこのかたちの、けうらなる事世になく、屋のうちは、くらきところなく、ひかりみちたり。おきなの、心ちあしく、くるしき時も、この子を見れは、くるしきこともやみぬ。はらたゝしきことも、なくさみけり。おきな、竹をとる事、ひさしくなりぬ。いきをゐ、まことの物になりにけり。この子、いとおほきになりぬれは、この子の名を、みむろのあきたをよひてつけさす。あきた、なよたけのかくやひめとつけつ。
僕じしんの研究史の出発点であり、研究の立脚点でもあった、 古本『竹取物語』本文の冒頭部です。流布本では「野山に交じりて」とある本文が「野山なる」とあります。池田亀鑑『古典の文学研究の基礎と方法』(至文堂1968)「文献学における解釈と批判-異本はいかにして生ずるか(初出1931)」によれば、この本文の異同を「漢字と仮名との混同」の一類型として「『野山ニ交而竹ヲ』とあったのではないかとも想像される(大隅氏にこの説あり。)257頁」との本文転訛を想定していますが、とすれば、漢文体『竹取物語』先行説を認めて、さらに古本・流布本ともに漢文体物語の書き下し本文の伝流が前提になります。しかし、奥津春雄の一連の研究が示している通り、漢文体の物語がかな物語に書き改めらねばならない必然性に乏しく、やや無理があるでしょう「漢文体竹取先行説の問題点」(「平安朝文学研究」1983)。この点、池田亀鑑は、前掲書で「洛東隠士(似閑)の校合した異本竹取物語(この本の学術上の価値につきてはまだ世に紹介せられざるがごとし)」は、他本に比して単なる誤写と思われない相違があるが、あるいはこれは真名本か、または仮名交り本から写されたものではないかと思われる。256頁」と述べていました。
また、流布本に「そのたけの中に、もとひかる竹《なむ》、ひとすちあり《ける》」とある本文は、古本には「そのたけの中に、もとひかる竹、ひとすちあり」とあって係り結びが存在しません。ただし、『花鳥余情』の『竹取物語』梗概本文は同文なのでこちらが古態ではないかとも考えられます。しかし続く、「さるきのみやつこと《なむ》いひける。」とある本文のように、《なむ》を私に補っておいたのですが、平安前期の語法としては疑問符を付けたくなるようなところもあります。とはいうものの、そこで安易に平安文法の原則により本文を改訂するのは、文献学ではもっとも避けなければならない最終手段のはずです。「まず本文ありき」であって、「文法現象」はその現象から再構築されるべきものだからです。現在の辞書で構築された古語の世界は、平安語彙とは言い難い近世版本-活字本の語彙の世界にしかすぎないからです。しかし、活字本でばかり本文を読み慣れている研究者は、近代的論理と先入観で、すぐ文法的解釈に走りがちなことは言うまでもありません。ちなみに、この古本本文で「なむ」は三一例ありますが、第一中止(終止)形・第二中止(連体)形の語形が共通のものも多く、結びの不呼応そのものが明らかに確認できるのは、この「さるきのみやつこと《なむ》いひける」のみ、わずか一例です。
さて、このテクストの完本はひとつしかなく、後は絵入版本に校合した形の本文ばかりです。その完本の通称を「新井本」といいます。かつての所蔵者であり、『竹取物語の研究本文篇』(図書出版株式会社1944)一冊を残して早逝した、故新井信之氏にちなんで命名されました。今は、故人の実妹で、未完の『狭衣物語』の校本と、『竹取物語の研究校異篇・解説篇』(塙書房1960)を遺した、故中田剛直氏の夫人の所蔵に架かります。数年前、この本文の閲覧を願い出た僕に、「主人の亡くなった後、どなたにも見せておりません。兄にゆかりの本ですのでよくおぼえておりますが」と、丁寧に断られました。まだ今も、中田家にあるはずです。この本の来歴については、横山重の『書物探索』(角川書店・1978)の下巻にこのようにあります。
「文化十二年写本粗本『竹取』は大魚なりき」
わたしは、古活字版の十行本の『竹取物語』を二種もっていた。‥大阪に村井という古書店があった。…その村井が、金沢の旧家から買った本の中に『竹取』があったとて、それを送ってくれた。文化十二年の粗末な写本であった。こんなものを十二円としては相すまぬが、仕入れが意外に高いから、がまんしてくれとあった。…わたしは寄贈という文字を紙に書いて新井君のところへ送ってやった。…二、三日後に、新井君がやって来た。…彼は鞄の中から一枚の写真を出した。
△伝後光厳院宸筆名物裂 一枚
…この名物裂の本文と一致する本文のある『竹取物語』は今まで一度も見たことがないという。…最近は、もう、あきらめてしまったが、ふと、夢に見たことが、二、三度あるという。と、今度の本がそれだった。「この名物裂の本文と、本文が一致する本に行き当たった夢を見たのですか」私は感嘆してきいた。「ええ、賀茂の三手文庫に、今井似閑が、別本と校合した、元禄五年の板本がある。その別本を、似閑は『古本』と呼んでいる。その古本の文章が、この名物裂の本文(九行分で百二十二字)に、大体あっています。ですから、今井似閑の頃までには古本があったはずです。」…こういうことがあってから、半年の後に、新井君は発病したのであった。わたしは、直ちに新井君の『竹取物語』の『本文篇』を刊行せんと欲した。新井君の妹さんが、資料を運んできた。…(昭和)十八年から十九年にかけては印刷事情も最も悪いときであった。本は新井君の死後刊行された。84~93頁
かくして、故新井信之氏の博捜によって、その存在は知られていた古本本文は、かつて元禄時代の学僧・契沖と、その門下の高弟・今井似閑が絵入版本に校合したのちに命名したとおり、まさに「古本」と称する価値の本文を有するものなのであって、その古筆切本文の存在によって「古本」は真の「古本」であることが認定されたのでした。その後、一時、『竹取物語』は、この古本によって、細々と読まれていた時期もあったのでした。
・南波浩『校異古本竹取物語』(ミネルバア書房・1953)底本・新井本
・吉川理吉『古本竹取物語校註解説』(龍谷大学国文学会出版部・1954)底本・三手文庫本
・南波浩『竹取物語・伊勢物語』(日本古典全書/朝日新聞社・1959)底本・新井本
・中田剛直『古本竹取物語』(大修館書店・1968)底本・新井本
・中川浩文『竹取物語の国語学的研究』(思文閣出版・1984)底本・三手文庫本・未完
しかしながら、絵入版本などによって圧倒的に流布した本文である流布本が戦前の叢書のみならず、戦後の叢書にも採られることとなって、やがて『竹取物語』の本文として定着・席巻してゆくようになります。
・阪倉篤義『竹取物語・他』(日本古典文学大系/岩波書店・1957)底本・武藤本
・片桐洋一『竹取物語・他』(日本古典文学全集/小学館・1972)底本・古活字十行本
・片桐洋一『竹取物語・他』(完訳日本の古典/小学館・1983)底本・古活字十行本
・野口元大『竹取物語(新潮日本古典集成/新潮社・1984)底本・高松宮家本
・片桐洋一『竹取物語・他』(新編日本古典文学全集/小学館・1996)底本・古活字十行本
・堀内秀晃『竹取物語・他』(新日本古典文学大系/小学館・1997)底本・武藤本
このように大手出版社によつて流布本は完全にこの物語の基本テクストとして、認定されたかの感があり、現在では僕以外の研究者には全く省みられることなく、その存在すら知らない研究者がほとんどになりました。先年、それでも野口元大「竹取物語の本文」(「国文学」1993.4)・内田順子「偽玉の枝作りの工房-『竹取物語』の本文と解釈」(「国語国文」1996.1)によって拙論の批判、もしくは修正意見が提出され、やはり流布本に軍配を挙げる、もしくは古本と流布本を切り張りする本文再建案が提出されました。とくに前者、野口説は拙論に対する全面的な批判なのですが、古本本文を批判する論理は、また流布本の批判ともなり得るもので、循環論に陥っています。これは例えば、『枕草子』の三巻本・能因本優劣論争に似て泥仕合になる可能性もあります。しかし、僕には、『風葉和歌集』の和歌本文との一致から『うつほ物語』の前田家本に、版本以前の古態を求めた野口氏が、『竹取物語』では『風葉和歌集』本文が古本・流布本の混態本文であるにもかかわらず、この歌集の原本系である傍記本文(古本に近い本文)を認めず、本行本文(流布本説に有利な混態本文)からのみ比較して通行本系と認定している点からして、その検証過程および研究態度そのものを疑問と言う他ありません。また、内田論文は、古活字十行甲本「しらせ給たる限十六そをかみにくとをあけて」古本「しらせたまへるかきり十二方をあたきかみにくちをあけて」「玉の枝を作」った本文に対して、結論からすれば「しらせたまへるかきり十二方を」(古本)+「ふたき」+「かみにまとをあけて」『竹取物語伊左々米言』と本文をご都合主義的に合成するという噴飯ものの論文でした。言うまでもなく『竹取物語伊左々米言』は江戸時代の校訂意改本文です。こうした本文の成立背景を無視して本文批判?が行われ、しかも「国文学界」では屈指の学会誌にこうした「紙の無駄」的論文が掲載されたことに、僕はすくなからず衝撃を受けました。現在の「国文学」の水準とはこんなものなのでしょうか。
さて、これらの批判の対象となった僕の論文は以下の通りです。
・「<伝後光厳院宸翰『竹取物語』小六半切>本文に関する研究」「日本文学研究」1991.1
・「『海道記』『風葉和歌集』所引の『竹取物語』和歌本文の考察より鎌倉期流伝の物語古本系統の実在を論じ、流布本系統本文の批判に及ぶ」「日本文学論集」1991.3
・「『竹取物語』伝本の本文批判とその方法論的課題-求婚譚の人称規定を例として」「中古文学」1991.11
・「<伝後光厳院宸翰『竹取物語』小六半切>本文に関する研究・続」「ぐんしょ」1995.7
以上の諸論文に述べたように、断簡本文は脱文も確認できますが古本に先行します。また、古本本文ももちろん脱文や本文転訛を持ちますが、流布本に先行します。よって「古本」の命名を変更する必要はありません。ただし、「伝後光厳院宸翰『竹取物語』切 」を二葉所蔵している田中登の『古筆切の国文学的研究』(風間書房1997)「竹取物語の古写断簡」のように、時間的に書写年代の異なる断簡の持つ独自本文に対して、本文批判・本文系譜再建を一切行わずして、その相対的な異同のみから「異本」系統に分類する説などは参照に値しない、「ブルジョア的骨董趣味的」研究なのです。しかし、驚いたことに、稚拙で拙速なこの田中説に対して、鈴木日出男編『竹取物語・伊勢物語必携』(学灯社・1988)の「研究の現在」では「賛同してよかろう」と述べられています。田中氏の持つ⑤の切本文は明らかに「おほ」相互の目移りによる脱文であり古本系統に帰属せしめられる本文であるにもかかわらずです。この項の執筆者はどこに目をつけて研究史を眺めているのでしょうか。
結論として、僕の試論は本文系譜と本文史に集約されます。流布本はどんなに遡ってもその痕跡が『風葉和歌集』の二三本文箇所にとどまり、しかもそれは古本との混態本文であるのに対し、古本独自本文はすくなくとも『海道記』以前まで遡り得ます。つまり、鎌倉期流伝の『竹取物語』は圧倒的に古本であったわけです。さらに室町期に至っても一条兼良の『花鳥余情』所引の『竹取物語』まで古本であったことが実証できてもいるのです。近年古籍商の目録に紹介された二つの流布本本文も室町末期を遡るものではありませんでした。
なぜ流布本が普及したのか
ではなぜ、この物語は古本が流布本に取って代わられたのでしょうか?それは思うに印刷技術の普及による出版文化における物語文学の大衆化と連動しているようです。そうした、流布本『竹取物語』の普及が先入観となり、さらに近代にいたってマスメディアによる一般読書人への大量普及が本文の価値評価を潜在的に決定していると言うことは言えるのではないかと思います。 例えば、斯界の「最高権威」片桐洋一の所持する古活字十行甲本は、年記はありませんが慶長の上木であり、流布本の源流となった本です。したがって、江戸時代の写本はかなりの本がこの本の写しであるといってよいほどの影響力を持っていますが、奥付は「竹取物語秘本申請興行之者也」と見えるだけで素性の知られない明らかな校訂意改本文であり、中田剛直はこれを通行本系統の第三類に分類しています。地方の図書館に必ずといってよいほど所蔵されているいわゆる武家の必需品であった『絵入版本』もおなじ第三類ですから、その本文の通りの良さ、わかりやすさがわかるでしょう。それに加えじしんが大枚をはたいて手に入れたがゆえに、この版本が『全集本』『完訳日本の古典』『新編全集本』の底本となったのです。片桐氏によれば「(古本・流布本)共に問題がある限り、圧倒的に多くの人に愛されてきた通行本(流布本)によりながら、それを徹底的に読み解いてゆくべきではないかと思うのである。完訳104頁」と、この物語の研究の限界線を勝手に引いてしまいました。したがって、僕は『全集本』によって『竹取物語』を論じる研究者を「全集本的水準」と規定しています。とはいいながら、では、第二類の『集成本』、第一類の『大系』『新大系』はどうなのでしょう。第一類は武藤本そのものが本文として痛んでいるため、改訂しないと読めませんが、新旧校訂者の力量ゆえか、本文をほとんどいじっておらず、解釈のみ田中大秀の『竹取翁物語解』の解釈と古本本文の文脈を頼りに注釈していると言った状態です。これはすでに三谷栄一『竹取物語評解』(有精堂1956)、松尾聡『竹取物語全釈』(武蔵野書院1961)にみられる解釈スタイルです。そこで僕は『大系本』での竹取学を「大系本的水準」と呼んでおきましょう。第二類もさして変化はありません。『集成本』は他社版との新味を出しつつ、穏当なところで、といつた販売戦略から、中田剛直の校本に未収録の高松宮家蔵の『竹物語』によったのでしょう。影印を見ても「あなあなをくしりかいはみまとひあへり」などという稚拙な書写にかかる独自本文が、きれいに訂されて標準的な流布本となっています。
『竹取物語』の物語世界へのアプローチは可能か
結論から言えば、かなり危うく絶望的ですらありますけれども、可能性は数パーセント遺されています。 しかし、外部徴証はわずかで、僕が挙げた文献がすべてです。ですから、本文の優先順位は①断簡本文②古本③流布本と接ぎ当てしながら組み立てるしかありません。しかも断簡からして全き本文ではないので、主に「目移り」などによる脱文、字形相似による本文転訛などを本文批判してゆく必要があります。それゆえ、今回の発表のタイトルを「絶望の言説-限界の竹取学」としたのです。
では、こうした絶望を抱え込みながらこの物語世界との臨界線を示すこととしましょう。
そこで、物語の時間構造と、翁の年齢記述の齟齬というこの物語の基本問題について、語源譚にまつわるテクストを古本本文を基軸に考えておきます。
そこで、まず、この物語の時間記述の本文を摘出して検討してみましょう。
・三月はかりやしなうほどによきほとなる人になりぬれは、かみあけなとさうして、かみあけさす、もきせ、ちやうのうちよりもいたさす、いつきやしなう <生い立ち>
・しも月しはすのふりこほり、みな月のてりはたゝくにも、さはらすきけり <求婚>
・おきな、うれしくも、のたまふ物かな、おきな、とし七十にあまりぬ、けふあすともしらす<求婚>
・いつかたおほえす、ふねのゆくにまかせて、うみにたゝよひて五百日といふ、たつのときはかりに、うみの中に、わつかに山みゆ、 <蓬莱の玉の枝>
・ふねにのりて、おひかせふきて、四百よ日になん、まうてきにし、大くわんのちかえにやありけん、なにはにふきよせられて侍し、<蓬莱の玉の枝>
・玉のえだをつくりつかふまつりし事、五こくをたちて、千よ日にちからをつくしたること、すくなからす <蓬莱の玉の枝>
・文に申しけるやう、御子の君、千日いやしきたくみら、もろともにおなし所に、かくれゐて <蓬莱の玉の枝>
・かやうにて、御心をたかひになくさめ給ふほとに、みとせはかりありて、春のはしめより、かくやひめ、月をおも《し》ろうゐてみたるを見て<八月十五夜>
・おやをはしめて、何事ともしらす、八月十五日はかりの月に出ゐて、かくやひめ、いといたくなき給ふ、<八月十五夜>
・いまは、かへるへきほとになりにけれは、十五日に、かのもとのくにより、むかへに人ゝまうてこんとす、さらにまかりぬへけれは、おほしなけかんか、かなしき事を、この春より、おもひなけき侍るなりといひて、いみしくなくを、<八月十五夜>
・おきな、ことし五十はかりなりけれとも、物おもふには、かた時になん、おひになりにけると見ゆ、
<八月十五夜>
・おきなこたへて申、かくやひめを、やしなひたてまつること、廿よねんになりぬ、かた時とのたまふに、あやしく成侍ぬ、又こと所に、かくやひめと申人そ、おはす覧といふ、<八月十五夜>
『竹取物語』の時間構成は個々の求婚譚の中では一回完結型なのですが、物語を統一体としてとらえ返すと矛盾して括りきれなくなるという、摩訶不思議なテクストなのです。たとえば、「火鼠の皮衣」の段の、「もろこし舟の王けい」なる人物の舟での「もろこし-日本」の移動については、僕も考えたことがあり、片桐氏はこれを「本文を勝手に誤解し、必要のない説明を加えている感じである。全集本38頁」とし、野口氏もまた、実在の漢詩人・小野田守のパロディかと思われる「小野の草守(流布本・房守、田守-草守の連想か)」の行動を理由に古本を改訂本文と認定しています。これは循環論と言わざるをえませんが、すくなくとも古本本文の方が時間の流れに関して叙述が丁寧であることは確かです。
さてそこで、この物語全体の時間の流れについてなのですが、翁の月の天人への返答に「二十余年」と語られてはいるものの、実際には杉野恵子「竹取の翁と『二十余年』」(「平安文学研究」1985.12)の綿密な計算によって、都合「約十年」であるとする説が妥当であると東原伸明「竹取物語の引用と差異-<話型>のカタドリもしくは旧話型論批判」(「日本文学」1990.5)は認定しています。要するに、かぐや姫発見から垣間見三ヶ月+求婚者の名告りと脱落三年+難題物捜索三年+帝との交流三年+月への昇天八ヶ月=約十年という計算式の学説です。つまり、求婚譚は一斉に開始された「共時的な同時進行」であるという考え方になりましょう。しかし、高橋亨「竹取物語論」『物語文芸の表現史』(名古屋大学出版会・1987.初出1976)が指摘し、奥津春雄「『竹取物語』求婚譚の時間意識」(「まひる野」1984.9)が追認したように、例えば「火鼠の皮衣」の段で「このたひは、かならすあはせん、といひておんなの心にもおもひをり」とあって、はっきり「この度」と前段の求婚譚を受けており、さらに、五つの求婚譚すべてを受けて「御狩の御行」で帝が「おほくの人の身をいたつらになしてあはさなるかくやひめ」と述べてもいるところから、求婚譚は「事件そのものが配列順に継起して」行われ、それらの失敗を受けて帝が登場するという、二重構造があると考えるべきでしょう。つまり、翁が天人に述べた「かくやひめをやしなひたてまつること、廿よねんになりぬ」という物語の年月を正確に翁が把握していたことになります。すなわち、求婚譚をのべ十五年とカウントすることで、前後六・七年を加えて二十余年にぴったりと附合するからです。言い換えれば、『竹取物語』 の年立は二十数年を基軸に作られねばならないことになります。
つぎに、竹取の翁の年齢についても考えておきましょう。
さきの東原論文では、八月十五夜時点の地の文「五十ばかり」を起点として、杉野論文の十年年立て説を支持し、かぐや姫発見時の翁が「四十歳という年齢が、青年(中年)と老年のひとつの境界に相当」する記号であるとし、さらに「七十」という記号が『律令』のコードから「いちおう男性の範疇にあっても実質的には男ではなく『無性』に等しい存在」であるとして、これらから「<語り(=騙り)のディスクール>によって閉じられ、差異化された 」ものと読んでいます。同じく室伏信助「竹取物語の文体形成」『王朝物語史の研究』(角川書店・1996・初出1990)も七十歳を会話の「大げさな表現」の修辞で「人生七十、古来稀」(杜甫詩)の引用とみています。ぼくも七十歳は翁じしんの発話による、娘に結婚を勧めるための誇張と見る説には賛同します。ただし、年立二十年説とすれば翁は三十歳ということになります。そこで僕は、物語終末部時点では五十歳の翁を、一貫した人称とするために、冒頭部では年齢に先取りする形で「翁」としるされたものと見ておきたいのです。いうまでもなく、『竹取物語』は、五つの語源譚を語る本文と終末部の一文「いまたそのけふりくものなかへたちのほるとそいひつたへたる」だけが、<語り手の物語る現在の世界>なのです。つまり、「いまはむかし」から「ふしの山とはなつけゝる」まではおおよそ線状的、継起的に出来事を語る「物語世界」のこと゛たということです。
その傍証として、翁の妻の表記を挙げておきます。古本・流布本ともに冒頭部の表記は「めのをんな」であって「媼」ではありません。ただし『全集・完訳本』『集成本』ではこれを改訂して「翁-媼」とペアにしています(以下、二例も同様、新旧『大系本』改訂せず、「媼のこと」とする)。しかし古本では「妻のをんな」は他に<八月十五夜>に一例だけでこれも「をんなのいたきたるかくや姫」とあって「媼」ではありません。流布本では、<富士の煙>の冒頭に「その後、翁・媼、血の涙を流して惑へど(完訳本文)」と見えますが、古本には「そのゝち、おきなも、ちのなみたをなかしてまとへと」とあるだけです。つまり、この物語の重要人物はやはり「竹取の翁」なのであって、こうしたあまりにもあからさまな虚言=誇張表現を簡単にしてしまう凡人として、この翁は描かれているのであって、その翁は、老人である必要はありません。物語冒頭部での翁は、<竹取のオヤヂ>ぐらいの軽い愛称程度のものではなかったのでしょうか。ですから、かぐや姫を養育し、天人から娘を守るためにのみ登場する翁の妻は、ただ「をんな」とだけあってもよいのであって、老婆たる「媼」である必要はなかったのです。
またこうした物語の手法は、たとえば、かぐや姫の発見当時の大きさの認識のずれにも指摘できます。
・それをみれは、三すんはかりなる人、いとうつくしうてゐたり、
・おきな、こはなてうことのたまふそ、竹の中より、見つけきたりしかと、なたねのおほきさおはせしを、わかたけたちならふまて、やしなひたてまつりたるわか子を、なに人か、むへにこむ、まさにゆるさむや、といひて、われこそしなめとて、なきのゝしること、いとたへかたけなり
前者が冒頭の地の文、後者が翁がかぐや姫の月への帰還を知った時の発言です。山田俊雄「『なたねの大さ』の論」山田孝雄・忠雄・俊雄『昭和校註竹取物語』(武蔵野書院・1953)によって「なたね」は今で言う「菜種」ではなく、罌粟{けし}粒程のことであり、芥子の実であると言うのだそうですが、これもまた、二十年も育てたかぐや姫じしんに去られることを翁が嘆いてこうした誇張表現となったものであり、このテクストもまた、先のテクストコードとともに、凡俗でケチな翁像を形成するのに参与しているのです。つまり、この物語は翁物語にオチはつけないものの、『竹取の翁-物語』を二度読みすることで、求婚譚をはさんで冒頭と終末部を結ぶ翁物語に「反復される矛盾の言説」二つを用意したのでした。(これは「蓬莱の玉の枝」と「優曇華の花」にも見られますが、今は置きます)
物語世界の臨界線
以下、この物語の語源譚は、三谷栄一『物語文学史論』(有精堂1952)が説くように、求婚譚は『竹取物語』の「自由区域」であり、机上の創作であって、その構成も 二話+一話+二話のいわば三幅対で括られているといわれています。つまり、不誠実にも権力に任せて、難題物を偽造する皇子に話+金力に任せて偽物を掴まされる男、+難題物探しには愚直な誠実さを示すものの、失敗して妻も家も崩壊したり、命すら失う男が描かれて、人間世界の欲望とその征服欲のありようを描いていると言うことになるのでしょう。
さらに、こうした構造を語源譚と言うことばのフレームでもって、前述の物語世界と物語る世界とを連結させているわけです。しかも、最後の石(磯)上の中納言には、「かくやひめ、すこしあはれとおほしける」とあって、物語そのもののクライマックスのかぐや姫の和歌、
「今はとてあまのはごろもきる時(流布本-をり)ぞ君をあはれとおもひ出でぬる(流布本-ける)」にまで連接されて、さらに大きな物語世界と物語る世界の大枠の物語の構造的支配が理解されるくるはずです。 つまり、どんなに卑俗で狡猾な翁であっても、かぐや姫にとっては親であり、その親や帝を愛する心を知ってしまった、このヒロインにとっては「きたなき」この地上にこそ、月の都にはない人を「あはれ」と思う心を育ててくれたのでした。物語は、結局八月十五夜には月に帰らねばならない、かぐや姫と、かぐや姫という宝物を喪失する無力な地上の人間達の絶望の言説を、哄笑とペーソスの中にそっとしのばせながら、「永遠の始まりの終わり」に向けて着々と準備を進めていたのでした。
・はちをすて又いひけるをきゝてそ、おもひなけきをは、はちをすつといひける<仏の御石の鉢 >
・としころは、たまさかなるとは、いひはしめける、<蓬莱の玉の枝>
不誠実にも権力に任せて、難題物を偽造する皇子の話
・世中の人いひけれは、これをきゝてそ、とけなき事をは、あえなしとそいひける、<火鼠の皮衣>
金力に任せて偽物を掴まされる男、
・まなこ二に、すもゝのやうなるたまを、そろへていましたると、いひけれは、あ《な-る》たへかた、といひけるよりそ、よにあらぬ事をは、あなたへかたと、いひはしめける、<龍の首の玉>
・これをきゝて、かくやひめ、すこしあはれとおほしける、それよりして、うれしきことをは、かひありといひける <燕の子安貝>
難題物探しには愚直な誠実さを示すものの、失敗して妻も家も崩壊したり、命すら失 う男
かくして、物語は「ふしの山」という最後の語源譚で締めくくられます。特に流布本では「かの山」あたりの目移りからか、「ふしの山」の「富士」の語源の説明が不完全で、本文の完全な「古本」の解釈で補われてきたことはよく知られています。
・ あふことの(流布本-も)なみたにうかむ(流布本・他の古本-うかふ)我身にはしなぬくすり もなにゝかはせむ
かのたてまつれる、ふしのくすりのつほそへて、御つかひに給はす、ちよくしつかはす、月のいはかとゝ、いふ人をめして、かのするかの国にある、山のいたゝきへ、もてとつくへきよしおほせ給ふ、みねにてすへきやうを、をしへ給、文、ふしのくすりのつほをならへて、火をつけてもやすへきよしを、おほせたまふ、そのよしを、うけ給はりて、つはものとも、あまたくしてなむ、かの山へはのほりける(流布本-あまた具して山へ登りけるよりなむ、その山を「ふじの山」とは名づけける)、そのふしのくすりを、やきてけるよりのちは、かの山の名をは、ふしの山とはなつけゝる、
いまた、そのけふり、くものなかへたちのほるとそ、いひつたへたる
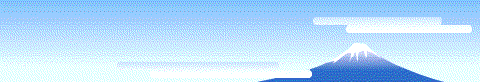
物語は、かくして、「ふじの山」で燃やされた文と不死薬の煙が、富士山の噴煙に点火リレーされて、しかも未だにその煙が立ちのぼっているという、<物語の現在>をようやく語ることで、「循環する終わりの始まり」を語っています。つまり、その頃の富士山は、煙が絶えることなど考えられてもいなかったのでしょうから、物語の現在は今に続いているのかもしれないということばの永遠性こそ、物語る世界と物語世界との臨界線なのです。しかも、この臨界線が、「古本」の解釈によってしか、<臨界>しないところに、物語世界と文献学をかろうじてつなぐ生命線が存在しているのだと考えます。
しかし、この臨界線は、あくまで鎌倉期流伝のものであって、平安時代のメッセージである保証はありません。ただし、二つの微細な本文の揺れは、この物語のメッセージを全く二つの方向に分裂させて伝える気はなく、先人の故意から生じた差異でもなくして、書写上の過失から生じたのであろうという、物語本文史の偶然にただ感謝するばかりです。しかしながら、それは僕の研究の立脚点である、微細な本文の表象の差異をどう評価するかによっては、物語の主題をつき動かすほどのものでもないのではないか、という畏怖をも喚起させてくるのです。僕のこの十年の研究史とは、何だったのでしょうか。しかし、僕は微細なものから全体を俯瞰するという文献学の持つエネルギーの、その何かに、まだその可能性が数パーセントでもあるかぎり賭け続けてみたいと思っています。敗北感や猜疑心という「絶望の言説」からは何も生まれてはこないはずです。ですから、今回のこのレポートもまた、僕の「循環する終わりの始まり」なのです。
そして、このふじの煙というコードは、西暦二〇〇一年の物研例会にさらに点火リレーされて、どこかの大学の教室で、物語への熱い議論の交わされているその中、ぼくにとつてはむさいだけの煙草の煙も、きっと変わることなくモクモクと立ちのぼっていることでしょう。 お・わ・り