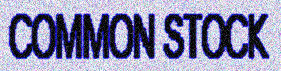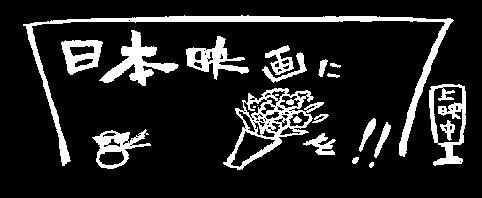
1996年10月11日開始
火だるまG
第8回:1997年5月11日
ものの本によると萩原健一、水谷豊主演のテレビドラマ『傷だらけの天使』(日本テレビ)は1974年の作品だそうだ。ショーケンが24歳、豊さんは22歳である。『傷だらけの天使』は伝説とも呼ぶべきテレビ番組で、今や中年に達した当時のテレビ小僧たちが微にいり細にいり語り尽くしているので、僕の出る幕などない。そもそも僕はテレビドラマを連続して鑑賞するという趣味が、当時も今もないので、ショーケンが死んだ豊さんを大八車(だったよね?)に載せ、泣きながら夢の島に捨てにいくシーンなど断片的に覚えていることがあるとしても、それはおそらく夕方4時からの再放送をつらつら眺めたり、いやこれは嘘だな、実は当時からドスケベ男だった僕は、ゲスト出演の女優さんたちのヌードだけを目当てにテレビの前で固唾をのんでいたのだろう。今のようにビデオなどという文明の利器のない時代、見逃せばはいそれまでよなので、かなり真剣に見ていたはずだ。今も克明に浮かぶのは、緑魔子、この人は尼さん(シスター)に扮していたな、と、当時の清純女優、志摩みゆき(名前自信なし、現状僕の資料には記載がない)の全裸である。この全裸というのがポイントで、『傷だらけの天使』はオッパイだけをちらちら見せるのではなく、オールヌードの後ろ姿を必ず見せてくれたという記憶がある。透き通るような純白の女性の肉体の後ろ姿の流線型のフォルムが僕の大脳を刺激したのだ。
さて23年ぶりの映画判にはほんの一瞬の女性の裸も出てこない。しかしこの作品は映画が映画足るための映像的シーンに満ち満ちた青春映画の傑作である。
この映画にはほとんどクローズアップがない。クローズアップはないということ自体が、これはテレビではなく映画なのですよ、ということのマニフェストなのだろう。将来この映画がビデオになりテレビの画面で見ることが可能となっても、そこにはおそらくなんにも映らないだろうと僕は思う。あなたがまれにみる遠視なら別だが。
眼技という言葉がある。表情で人間の心理を表すこと。しかし人間観や経験の裏打ちのない役者が表情で苦悩や歓びや悪意や憤りを表現しようとしても、悲しいことに、すぐ底が割れる。政治家の言葉がすべて嘘に聞こえるがごとく、中身のない役者の表情もすべて絵空事に映る。クローズアップの多様という宿命を負った現代のテレビドラマのつまらない所以である。いうまでもなくプロヂューサー、ディレクターなどのスタッフ側には中身があるという意味ではない。
それならば役者を動かそう、行動で情意を表現しようというのが、映画の方法論であり、そこにはじめて躍動感が生まれ、映画が高らかに唄いだすのである。
本作品の映画的名場面をいくつか抜き出してみよう。
豊川悦二扮するミツル(テレビ判ではショーケン)は何でも屋兼探偵。おそらく不動産関係の不良債権処理にかんする問題でマンションに立てこもる暴力団の麻薬や銃砲の違法行為のネタを調べるために深夜にある部屋に侵入する。
しかしその部屋では、今度はその暴力団内部のいざこざで居座っているはずの暴力団幹部の三浦友和自身が椅子に手錠で縛り付けられ、血液を半分抜かれた状態で死にかかっている。後でその実行グループが戻ってくれば東京湾に沈められる運命である。三浦友和は豊川悦二に背広の内側の有り金を渡して、都営アパートに住む息子を東北にいる別れた女房に送り届けるべく依頼する。そこで三浦友和は気を失うのであるが、実はそこで死んだのかもしれない、この死んだのか気を失ったのかわからないというのは、このシーンがすべてロングでとられているからである。おそらく死んだのだろう。そして豊川悦二は部屋を立ち去る前に三浦友和の手錠をはずしてやるのである。手錠をはずすという行為の危険性を豊川悦二は熟知している。なぜならしばらくすれば実行犯たちが戻ってくる。三浦自身が自力で手錠をはずせるわけもなく、それは、だれかの侵入を意味する。しかし、このシーンにはなんの説明もなくすべてロングで演じられるので、わからない人にはわからないだろう。この映画は冒頭でヒーローの自殺から物語が始まるわけである。いきなりヒーローが自殺するテレビドラマなどありようもなく、映画の映画たる所以であろう。
それでミツルは友和の息子・蛍(役名蔵井蛍、きついギャグだ)を24万のギャラで、母親の足跡を追いながら、陸前山田、八戸と連れていくのだが、幼時に母に捨てられやくざな父に育てられた蛍はスナック菓子ばかりを食べていて下痢ばかりしている。旅の途中でも何度も途中下車を余儀なくされ、医者に診てもらわねばならないこともあった。神経性の腸炎。神経性という言葉がミツルの魂を揺すぶる。途中下車した駅で、まともなものを喰わそうと少し離れた食道に向かう道で、バカみたいにたくさんの蛍の荷物を持ってやっていたミツルが、はっと気がついて、蛍の甘えを指摘し自分で持つようにいう。蛍は不承不承それをまた担ぐが、全部担がせた上で、ミツルは蛍の前にしゃがみ込んで、その蛍をおんぶしてやるのだ。このシーンもかなり遠くからのロングで撮られていた。
この間、ミツルと喧嘩して絶縁していた真木蔵人扮するヒサシ(テレビでは水谷豊)は鉄工所で仕事をし、再三のミツルによる協力要請にもシカトを決めていたのだが、あーっもうだめだ、限界だ、のため息とともに、主任有給有給と叫んで、愛車ムスタングを東北に走らせミツルに合流する。ミツルに用事をいいつけられたヒサシがミツルとほんの少し別れかけたとき、煙草を口にしたミツルの鼻先に車のウインドからにゅーっとヒサシの手が伸びて煙草に火をつける。これもロング。バックミラーに映るミツルの煙草を取り出すシーンがあるわけでもなく、しかし、いかにいつでもヒサシがミツルを見ていて、そして、ミツルと一緒にいたいと願っているかを瞬時にわからせるシーンである。
紆余曲折があり、結局蛍は牧場を経営する友和の父、菅原文太に引き取られることになった。どうしてあんたはここまでしてくれたのだという文太の問いに、ミツルは、蛍が大きくなったら一緒に酒を飲みたいからと答える。これは駅頭での感動的な蛍との別れのシーンでも、ミツルの口から蛍に繰り返し語られる祈りのような言葉である。その横ではヒサシが、俺もいつかミツルさんと切れるのかなぁ?、どうやって切れるのだろう?、と呟いている。珍しくこのシーンはアップだが、ここまでのシーンの流れから見ると、監督のテーマがここにあるのだ、ということが明確に示されているシーンでもある。この映画のテーマは愛するものとの別れの予感だろう。しかしミツルはすでに冒頭で自殺をしているのだ。彼の別れは実感であることがすごい。
そして最後にミツルは殺される。表情のアップはない。実行犯に引きずられていく手錠をはめられた左腕のクローズアップがそれをなんとなくミツルの死を指し示しているだけなのである。
現代のもっとも優れた映画監督の一人、阪本順治は、『どついたるねん』(89)でのデビュー以来、『王手』(91)、『ビリケン』(96)と、関西弁というリズミカルな言葉の特性を活かした過剰説明の映画を撮ってきたが、『傷だらけの天使』は前々作『トカレフ』(94)いらいの説明のない映画である。『トカレフ』では、自分の子供を誘拐し殺した誘拐犯と所帯を持つことに至った若い母親にとり、その子供殺しが、既定のものだったのか、つまり彼女もグルだったのか、それともグルではないにせよ、後にはその男が犯人であることを知り、それにもかかわらずその男を愛することになったのか、それとも、彼が自分の息子を殺した男であることを最後の最後まで知らないで映画は終わったのか、そこのところがどう見ても理解不能であり、また、そこの理解の仕方で映画の性格が変わってしまうキーポイントであると僕は思ったので、僕はいまいち首肯できなかったのだが。『傷だらけの天使』には賞賛を惜しまない。冒頭でのミツルの自殺も、それから延々と続く彼の厭世観および見たくもないような薄情な世間の実態(ややデフォルメはきついとしても)を見せつけられれば、すんなり納得できるものである。
これだけ刹那的で厭世的な人物をヒーローに選び、しかも冒頭でいきなり自殺の時限爆弾を仕掛けるなど、とてもとてもテレビドラマでは受け入れられるものではなく、『傷だらけの天使』が立派な映画である所以である。しかも主演は今をときめく豊川悦二だものね。
この映画は一本の映画という長い長い時間を使った、一人の人間の自殺の明確な説明であり、過去になにか似ているものがあるとすれば、ルイ・マルの『鬼火』(63)ぐらいであろう。
(この企画連載の著作権は存在します)

| headlineのページへ |