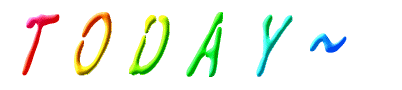 VOL.7
VOL.7 


【普賢岳を覚えていますか?】
私は、縁あって長崎県島原市に在住しています。
この10月で、まる6年になりました。
島原市の西方には、有明海が広がり、東方には山が望めます。
一歩外に出ると、大自然の懐中です。ここに住む人達は、その恩恵を十分に受け、

遠く普賢岳を望む |
田舎ながらものびのびと暮らしています。
春は、浜でアサリを掘り、野の花に手を伸ばし、
夏になると、子供達は、
樫の幹からカブトムシを取り、
小川に群れ飛ぶ蛍を見つめ、
秋には、どんぐりを拾い、
トンボを追いかけ、
冬は煌く星座に見とれて、白い息を吐きます。
とても幸せな環境・・・・です。
ここ何年かは、平穏に繰り返されている四季の移り変わり。
都会育ちの私には、この永遠に不動とも思える環境が、9年前に一変したとは、信じ難い事でした。
198年振りの普賢岳の噴火によって・・・・。
6年前、私がここに嫁いだ頃、庭の草木の葉は、白い灰で覆われていました。
初回の噴火から3年が経過していました。でも毎日毎日、灰が降り積もるのです。
島原市全土が、色を忘れてしまったかのような風景でした。
夜ともなれば、家の窓からは、真っ赤に流れる火砕流が、不気味な音とともに見て取れました。
11月17日という日は、普賢岳に噴火の予兆とも思える2本の煙が立ち昇った日です。
1990年の11月17日の事です。翌年の、6月に大火砕流が発生し、
44名もの命が消えました。
そのうち、12名は、町の消防団の方々でした。一般市民、報道関係者、焼き尽くされ、
骨さえ見つからない‥そんな壮絶な亡くなり方の人もいました。
皆さん、消防団ってご存知ですか?ボランティアの地域防災集団です。
私は、この地に来るまでは、その存在すらしりませんでした。
実は、私の義父がその消防団の団長をしています。もう、20余年になります。
その方達の慰霊碑が建つまでは・・・と義父は団長を続けてきました。
1999年、11月17日、慰霊碑の除幕式があります。土石流、火砕流が流れ着いた最後の場所、
海岸の埋立地にその碑は、花と共に建立されました。9年目にしての、鎮魂。
義父の悲願は、慰霊碑を建てて団長を退く事でした。義父は、今年で69才になります。
これで、この災害は忘れられていくのでしょうか?
普賢は、今も、私の家の西南に鎮座しています。
平成新山とおとなしい名を貰い、一億立方メートルの溶岩ドームを抱えて・・・。
今なお、直下型の地震がくれば、水無川の火山噴出物と合わせて、崩落するそうです。
そうなった時、また、どんな被害が起きるのか?
想像もできません。
最近の世界各地の、悲惨な災害のニュースを見るたび、
人の叡智の及ばない、天の力に圧倒され、驚くばかりです。だからこそ、私達は、
災害をもたらされた地域の人間は、その災害の真実を見つめないといけないと思うのです。
そして、次世代へわたせるバトンをつくっておく。
198年前の、普賢の怒りを人は忘れていました。それも被害を大きくした一因だと思います。
人は災害を他人事のように考えます。特に、天災などは、情報としてメディアに流れて行くと、
メディアを通して知った遠方の方々は、
可哀想だが、自分の所には落ちなかった「悲劇の箱」って思うのではないでしょうか?
その地域にたまたま落ちた・・ 残酷な神が落とした「悲劇の箱」って。
私も実はあの「阪神大震災」の直前まで、関西に在住していました。
関西を離れて後、あの地震が起こり、
遠い地で目にした、耳にした情報は、あまりにもショッキングな…、
しかしその悲惨さを肌では実感できない悲劇でした。
その後、偶然にも大きな災害のあったこの地に移り住み、
真実として私が知り得た事は、災害の悲劇を、天が与えた以上に大きくするのは、
「人間」そのものだという事実です。悲劇の箱の中には、必ずしも
善良な方々の悲劇のみがが詰まって入る訳ではない。利己的で営利的な人間が、
さらに悲劇を大きくしているという事なのです。
世界中の災害がそうだとは、いい切れませんが・・・
報道関係者が巻きこまれてしまったのも、報道という名を借りた、
人間の営利追求の結果…と言ったら言い過ぎでしょうか?
義父の話からは、いろんな隠蔽された事実を知る事ができます。
メディアには流れていない、(故意に流されない)
地元ゆえの知りえる真実。
しかし、それをそのまま世間に発信できないもどかしさ。
我々が暮らす世間の、悪の部分のような気がします。全ての真実を、発信できることによって、
また、それを受け、考察する事によって、
「人」は、学習できるのであろうに・・・・と考えます。
いつ落とされるかわからない「悲劇の箱」に対して、どんな対応をすれば、または、していれば
被害が最小限に食い止められるかと。

1階部分が土石流に埋まった民家 |
最近のあまりある災害情報に、
地球はどうなるのだ?という危機感を持ちながらも、
加速度を増して、増えつつあるインターネットが、
それを救う鍵を握っているような気がします。
今までのメディアとは違う発信手段。
そんな気がしてなりません。
Tamaki/s

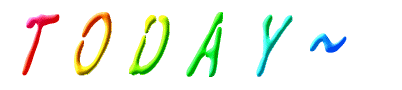 VOL.7
VOL.7 ![]()

