
2002年10月17日〜22日
8頁
10月21日(月)午後
胡同(フートン)観光
胡同とは、、、
元・明・清の三時代に渡って形づくられてきた町並み。
ガイド・ブックによると
「北京で、大通りから一本入った裏通りや、密集した民家を
縫うように走る路地のことを言う。」とのこと。
胡同は、三輪車で回る。
北海公園の北、胡同遊という辺りが出発点になる。
そこには、お客さん待ちの三輪人力車がズラリと
並んでいる。これは、その場面をちょっと撮り逃したところ。

路地を三輪車で巡りながら、
昔ながらの北京の人たちの生活ぶりを垣間見ることになる。

三輪車引きの人の中国語のガイドを
Mizuさんに訳してもらいながら回る。
「四合院」という伝統的な様式の建物の門構え

「四合院造り」を上から見たところ

絵葉書より
恭王府花園
清時代の大臣の私邸として1777年に建築されたものとのこと。

一般公開されているのは花園の部分だけ。
これが花園の正門(入場切符から)
↑美しい庭、美しい門構えもいいけれど・・・
でも、この際は、やっぱり北京路地裏模様→庶民の暮す胡同かな?
胡同も身分によって住み分けられていたそうだ。
故宮に近い胡同には、皇族、貴族など、身分の高い人が住み、
当然建物も立派。そして、少し遠くなると、庶民が暮す
質素な胡同になる。

*クリック
「あ、ネコ!」 Mizuさんの声に顔を上げると、
うーん、いい感じ。

*クリック
典型的な門と門の前の・・・
これ、何て言ったっけ? 「魔よけ」とどこかに
書いてあった気が。ガイドさんの説明?


北京市は、ここを含めて、何箇所かの胡同を
保護区に指定して残そうとはしているとのことだけれど、
一方で、全部の胡同までは、手が回らず、
その間に、胡同は、今、急ピッチで進んでいる開発のために、
どんどん消えて行く憂目なのだそうだ。
前の日、
Masaさんから、聞いたお話だ。
それにしても、
やがて、四合院が解体され、路地風景が記憶の中だけになるとしたら、、、
それは、やはり、寂しいことだ。
でも、これは、他人事ではない、お話なのだけれど。。


*クリック

*クリック



銀錠橋

胡同を一回りし終わったところ。
↓後ろに見えるのは、鼓楼

1272年元の時代に建てられたもので、
昔、時を告げた太鼓が収められているとのこと。

そろそろ、夕方のラッシュ・アワーになってくるような・・。
トルファンの干し葡萄
夕食は、
初日に苗さん宅でご一緒したIさんご夫妻や
香港からのMasaさんのお友達などと
ご一緒に上海蟹のお店でになるとのこと。
でも、
その時間までに少し余裕があるということなので、
もし、この界隈で、手に入れば、
お土産に持ち帰りたいものがあることを
Mizuさんにお話してみる。それは、トルファンの干し葡萄。
すると、Mizuさん、その干し葡萄を売っているお店を
知っているとのこと! びっくり。
これまで、「わざわざ時間を割いてまでは」と思っていたので、
敢えて口にもしていなかったコトなのに、
こんな風に機会がめぐってくるとは。
なんて、ラッキー。
それは、ちょうど読んでいた本
「ぶどう唐草幻想」(森豊著)昭和49の中に登場する。
唐草模様のルーツをシルクロードを経て探って行く、ロマン溢れる本である。
著者は、その葡萄について、こう書いている。
「いままでの黒っぽい干葡萄と違って、白緑のややくすんだ
細長い宝石の粒のような干葡萄で、馬乳葡萄といわれるもの、
甘くやわらかな香気があって、いままでの干葡萄と全く
異なった美味であった。」
ここまで、書かれたら、食べてみたくなるというものだ。
そして、Mizuさんが、つれて行って下さった市場に、
それは、確かにあった。私は、その奇遇さにワクワクして、
袋2つにざっくり干し葡萄を詰めてもらう。 ふっ、ふっ・・・。
その干し葡萄は、こちら
私には、飾り文字で表現したいほどのロマンの味だった。
トルファンに行かなくても食べられたなんて。
中国式お漬物売り
干し葡萄をリュックに詰めて外に出ると、
道路端にいきなり壷が並んでいる。何だろう?
「あ、中国のお漬物。買いましょうか?」Mizuさんが言う。
好きな壷のお漬物を選んで、ビニール袋に
入れてもらう。日本のお漬物とも似ていていいにおい。
酸っぱいもの大好きな私は、すぐ口の中がヨダレで一杯。
・・・と、Mizuさん、「食べましょう!」。ご自分も一本、
袋の中から、指でつまんで、私に袋を回してくださる。?!?
願ったり叶ったりの私だ。
私も早速、袋に手を突っ込む。
そして、二人して、お漬物をボリボリ食べながら歩く。
きゅうり、大根、あと、なんだっけ?
とにかく、交差点を渡りながらも、代わり番に次々と袋に
手をつっこんでは、食べる。
タクシーを捜しながらも食べていた。

町は、ついに、夕方、仕事帰りの人のラッシュに突入だ。
その夕暮れの混み合う四つ角付近で、
自転車やバスをかいくぐりながら・・・
お漬物の袋を持って、ポリポリ、ウロウロ、しているMizuさんと、私。
口は、お漬物味、目は、真剣に、タクシー探し。
・・・それだけのこと。でも、何ともいえず、なぁーんか、楽しい瞬間。
ホント、楽しかった。
もう少しで終わる私の北京の旅・・・ ・・・ ・・・。
タクシーがつかまる。
その運転手さんに、いきなり
ビニール袋の漬物を、勧めるMizuさん・・・!(@_@)
運転手さん、ふいを突かれて、思わず引く。(笑)
でも、それでタクシーの中は、
俄かに、なごやかムードだ^^^^。
そして、オリンピックに向けて、日本語を勉強中という運転手さんと、
日本語レッスンが始まる。
「あ・り・が・と」がうまく言えない彼のために
レストラン到着直前まで、復唱練習は、続いたのだった。
上海蟹レストラン
「漬物の袋を持ったまま」、私達は、レストランに到着する。
そして、お友達も順次、到着。
Iさんご夫婦以外の男性二人は、もちろん、私には、初めての方々だ。
どうもIさんにとってもそのお二人は、初めての方らしい。
でも、お仕事関連のお仲間の中に、
私なんかが、一人紛れ込んでいる形・・・。
「いいのかしら?」という思いが、
なきにしもあらずだった。でも、そんな心配は、即、消える。
何もかもを大きく包み込んでしまうMasaさんの人柄によるのだと思う。
そして、そういうお二人の周りには、又、いい方々が
集まるのだろう。初対面で、畑違いの私なんかが混じっても
場は、あくまでも屈託なく、楽しくて賑やかだ。
「上海蟹」がテーブルに来て、その場は、大いに盛り上がる。
楽しい時間は、すぐ過ぎて、レストランの外に出ると、
夜の北京の空気は、冷たかった。
そして、しばし、忘れていた「旅の最後の日」のコトを
思い出す。そう、今日が最後の日。
Masamizuさんのおかげで、ここでも、
素敵な出会いと知的な刺激の両方の機会も頂いたと思う。
夜、ホテルで、一日の出来事を思い出しながら
一人荷造りをする。
心もトランクも満タンだった。
心には、思い出と感動と刺激が一杯。トランクには、
そのすべての結晶のような、お土産と、刺繍が一杯だ。
何回も荷物の位置をずらして、押さえ込んで、
やっと、ふたを閉めて、荷造りを終えた。
何でも、始まりがあれば、終わりがある・・・
名残は、尽きないけれど、本当に、充実した日々を過ごさせて
頂いたと思う。これは、何回言葉を重ねても足りないと思う。
 帰国
帰国
北京訪問記TOP
「手作り館」
 |
「旅日記TOP」
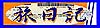 |




















