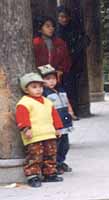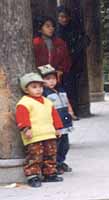2001年2月中国貴州省の旅
2月10日(金) -2-
肇興(サオシン/しょうこう)
長いデコボコ道のしんどさも、あの頂き近くの
風景の見事さで、十分補われた感があり、
皆、それぞれの充足感を味わいつつ、
あらためてバスの人になった。それから又、前述の通り、たくさんの
村落を抜け、菜の花畑を更に見ながら上り下りして、
着いたのが、このトン族の村、肇興である。
バスが、着き、私達が、鼓楼に向かうと同時に
周りには、村人も集まってきて、踊りの準備が始まっている
様子だった。
子供達も準備を見ながら待っている
代表の女性一人が、例の甲高い、
はっきりした抑揚のある中国語で、歓迎の挨拶をする。
自信を持って、代表であることがとても誇らしげだ。
そして、皆楽しげに歌い出した。
よく揃ったきれいな歌声が鼓楼の広場に響く。
嬉々とした表情に心が和む。
↑それぞれの写真をクリツクしてみて下さい。
ここの鼓楼は、細長い。そして、十三層もある。
鼓楼について、前ページに引き続き引用すると、次のようである。
なお、引用は、「月刊 しにか」2000年1月号
(特集 中国少数民族百科)から 「トン族スイ族」
筆者 麗澤大学 坂本比奈子氏から。
「・・・トン族は杉の木に宿る神を信じ、守護神として村の中心に置いたものが
鼓楼である。頂上に太鼓が置かれ、村の会議や結婚式を行う場所
として、使われる。村人の心の拠り所、村の重要なシンボルである。
鼓楼の建て替えは、百戸あまりの村人の結束を必要とする
大行事である。責任者に選ばれた大工が、指揮を取り、
村人が、木を切り出してくる。・・・・」
風雨橋についても多分、状況は同じで、どちらも
建設に際しては、村全体で、大変な労力を費やしての
ことだったと、想像できる。
若者は、頭に黒いターバンのような
布を巻いている。
ここでも歓迎式の最後で、私達も輪に加わって
一緒に踊った。
日常生活が垣間見える窓辺。
↓鼓楼の屋根と、民家の屋根
 |
*写真をクリックしてみて下さい。
鼓楼の飾りは、その建築の技術に比べると
あっさりと、素朴である。緻密な図柄であるよりは、伸びやかだ。
歓迎式の後は、この村で昼食をとる予定だ。
私達が、簡易に設定された食堂のような場所へ移動する間に
待ち構えていたらしく、刺繍を手にした十数名の
女性達が、どっと、やってきた。
手に持っているのは、製品にはなっていない形の
刺繍の布だ。「あ、見たい!」と、思うけれども、その押し寄せ方が
程陽の風雨橋より更にスゴイ。
もう少し、落ち着いて見させてくれないものか。
これでは、買う気のものも買えなくなってしまう。
おかあさんに声をかけて、
「食事が終わったら、一緒にお願いまーす。」と、
予約をする。
「よっしゃ、あんた、どれとどれが、いいか考えときィや。」
おかあさんが、答える。
押し寄せて来た女性達は、
さっき踊ったお嬢さん達が、着ていたあの光った素材の
布地に、「特徴がある刺繍」を施したものを手に手に持っていた。
刺繍をほどこしただけの布は、使い古したものから、
真新しいものまで、いろいろあった。
食事では、ここでも、女性達が、歌っては、
お酒を飲ませてくれる。
ここにも西洋人のご夫婦がいた。でも、今度は、奥さんの方が、
あまりにも堅い表情をしていて、 ここの雰囲気を
楽しんでいる風には、見えないので、
話しかけるのは止める。女の子達の
歌でのおしゃくにもニコリともせずとても不機嫌そうだ。
犬が、中に入って来ていた。くまさんは、それを見て、
すっかり自分のワンちゃんを思い出し、懐かしがる。
「うちの○○ちゃん、今頃どないしているやろ。」
その○○ちゃんについては、バスの中でくまさんが、
目覚めてから、ひとしきり聞いたのだった。
「あんた、うちの奥さん呼んでも、いっこうに来ぃしまへんが、
○○ちゃんは、呼ばなくても、ワテが、
帰ったら、喜んで迎えに来ぃよりまんねん。
そっら、かわいいでっせぇ。」。くまさんは、○○ちゃんの
話の時に、その大きなグリッとした眼をなんかい細めた事だろう。
食事が終わると、おかあさんを連れた私と、
くまさんも、早速、その刺繍の女性の群れに向かって
行った。と、言っても彼女達は、気がありそうな私達に
とにかく買ってもわらおうと
お食事所の入り口辺りに、今か今かと
たむろしていたのだったけれど。
私は、これをおみやげに出来たらいいなァと、
思っていた。あの独特の製法で作った黒光りする布の上に
特徴ある刺繍ときたら、もってこいでは、
ないか。額にいれて飾ってもよし、好きな使い方をして
もらってもいいのだ。
「よし、少しまとめて買っちゃおう。」おかあさんも、
まとめた方が値引き交渉しやすいと、言っていたし、
ところがだ。数が、多めと知ると、「相手」は、我先にと
迫ってきて、私とおかあさんの周りの肩といわず
脇といわず、あちこちから、にょきにょきと刺繍を持った手が
伸びてくる。私の手の中に自分のものを無理やりねじ込む人もいる。
もう、訳がわからない。
初め、取り敢えずいらないものをよけてはいたが、
すると、なぜこれをよけるのか、と聞いてくる(多分)
これでは、収拾のつけようがない。と、ガイドさんの声がする。
「もう、行きますヨォ!!」 時間だ。
団体行動を乱すわけにはいかない。
「だめや、誰に幾ら払ろうたらえぇか、こんなん、わからんワ。」
さしものおかあさんも、言う。
「わかりました。おかあさん、止めます。」「おじょさん、えぇのんか?」
「はい、いいです。これじゃ無理です!」
乱暴なわけではもちろんないけれど、とにかく買ってもらおうと
ぴったりくっついてくる女性達を、
私達は、振り払わざるを得なくて、彼女達をかきわけて、
それから、私達は、走った。角を回って、やっと、
ふぅー、と、一息という具合だ。
「すごいですねぇ。あれじゃ買いたいものも買えませんよね。」
おかあさんも頷く。
 |
肇興の目抜き通り。そこをあの騒動から逃れて
歩いている私とおかあさん。(頂いた写真 )
もうひとつの鼓楼
写真をクリックしてみて下さい。
肇興には、初めの鼓楼を入れて五つの鼓楼があるとのこと。
トン族は、一族につきひとつの鼓楼を持つのだそうだ。
この村は、五つの支族から成り立っているということらしい。
旅行社からの報告によると、この時、5つの鼓楼を見た
と、報告されているのだけれど、私にはその記憶がない。
多分、上記の刺繍のことで、てんやわんや
している間に皆、見学を済ませていたのだろう。
ともあれ、私がここで見た二つ目の鼓楼である。
再びトイレの話で失礼
この後、私達は、この村を後にするのだけれど、
その前に、何しろ刺繍に掛かりきっていたので、おかあさんと私、それに
何人かが、トイレを済ませなければということになる。
ガイドさんが、近くにいた村の女の子に頼んでくれ、
私達は、彼女のうちのトイレを借りることになる。
家々の間の狭い粘土質のぬかるみの道を入ったところで、
彼女が、立ち止まり、「ここです」という風に
手で教えてくれた。時間がなかったこともあったのだけれど、
結局私一人が、そのトイレを借用することになった。
他の人達は、とにかくそのまま奥へと行った。
古い板で囲われた小屋のような建物のこれも板の
扉をあけると、真中に40㎝位の高さで、横幅1m、奥行き60㎝位の
板の箱があった? これって、それ? !
閉じたドアの中で、私は、一瞬、途方に暮れた。
右のスペースには、これも結構な臭いがする干草が積まれていた。
でも、せっかく、貸していただいたのだもの、
それにドアがあるだけいいかも、私は覚悟を
決めて、服がどこにも触らないよう焦りつつ、注意深く、
その箱に登った。その箱の上には、板が数枚渡してある。
中が見えるけれど、『見ない!』
でも、そう思うと、見えないものだ。見えないことにした。
それに、足を板の間に落としても大変だ。
ああ、バッグを預かってもらえばよかった。何にも
どこにも触らないようにそして、手早く、必死だった・・・。・・・
と、
私の顔の近くで、いきなり「う゛おぉー!!」とすごい音がした。
私は、もうびっくりして、危うく、
箱の上から落ちそうになった。
ぎゃっ!私は、声にならない声を発していたと思う。
あの時落ちなくて良かったと今でも「しみじみ」思う。
どこで、どう自分を支えたのかは
記憶にないけれど、私は、辛うじて持ちこたえたのだ。
牛の大きな顔が、目の前にあった。
いろいろ必死だったので、
左側のしきりの向こうにいた牛に全く気づいて
いなかったのだ。体は、しきりのむこうだけれど、
その窓から牛が好奇心からか、大きな顔をにゅぅっと
こちらに伸ばしていた。
中で、
粘土質の濡れた土にどうにか下り立って、一息。
牛の顔に触らないように扉を開け外に出たときは、
「ふぅー、生還したぁ!」
そんな気分だった。借りトイレしながら、失礼な話だけれど、
無意識に止めていた息をした。
せめて、夏ではなくて、よかったと思う。
さあ、バスに戻ろう。
バスの周りには、さっきの刺繍の女性数人が探して
やってきていた。そのとき、買おうとおもえば買えた。
でも、まだ旅の初め。他にもある
と、思っていたので、ややこしいから、もういいやという気分だったのだ。
でも、それが大きな間違いだった。
あの刺繍は、もう他のどこでも見かける事は、なかった。
自分のだけでもせめて買っておけばよかったと、
後悔しても・・・後の祭りだった。
かくして、バスは、村から出るために
よく通れたものだという狭い坂道を上ってようよう
少し無難な前位の広さの道に出た。
三江から肇興まで110kmだった。
ここから、この日の宿泊地、榕江(ようこう)までは、
130kmある。すでに来た以上の道のりを行く事になる。
再びきれいな菜の花畑が、バスの両側に広がる。
*写真をクリックしてみてください。
トラブル発生
たくさんの村を過ぎ、山道に入り、又、ひどく曲がりくねった
カーブだらけの峠をひやひやしながら通った。
下ってきたので、もう着くのかなぁと思うと、又上った。
そうして、幾つ峠を越えたものやらわからない頃、ようやく、
道が、下りの道ばかりになってきた時、それは、起こった。
パンクだという。
トラブルなのだけれど、皆が口々に言ったのは、「あの山の上で」じゃ、
なくて良かったねぇ、ということだった。そこは、人気もそれなりにある
平地だったからだ。
結局私達は、そこで、1時間半ほど、何もすることなく、待つことになる。
でも、皆旅慣れた人達ばかりだったこともあるからか、あるいは、
前述のもっとヒドイ事態があり得たことがあったせいか
皆文句も言わずに時間を過ごした。
↓近くの煉瓦置き場のようなところにお母さんに
ついて来ていた子供達がいた。
写真をクリツクしてみてください。
この子達は、退屈している皆の格好の被写体になった。
皆、とてもあどけなくて文句なくかわいかった。子供たちのお母さんも
とてもチャーミングな人だった。
皆の撮影が、終わってから、私は、女の子に
折り紙を出して見せてみた。興味がありそうだ。
鶴、花、ピアノなどと折ってみせると、
その子は、驚いて、嬉しそうに私の顔を見あげた。
小さい折り紙で、作った小さい風船を手で
弾ませてみせると、ニコッとして真似をしてやってみて、
はにかんだ。
折り方を教えてあげようか、とジェスチャーで言うと、
ウンと、言いかけて止める。手が石炭で真っ黒だったからだ。
私は、何種類かの折り紙を集まってきた男の子と一緒に
同じ量になるよう注意して配ると、
子供達は、みんな一緒でよかったね、というように、
顔を見合わせて、エヘヘと笑う。
これで、こんなに喜んでくれるなんて、と思うようないい笑顔が
そこにあった。
私は、もうひとつ持って行ったかわいい絵のシールを思い出して、
一つ、女の子の手の甲に貼ってみる。
子供達皆が、それは、いったいなんだ、という感じで、
彼女の手に頭を寄せ合った。
あー、思い出してよかった。
一シートのシールをはさみで、幾つにも
切り分けたものを袋に入れて
持って行っていたのだった。キリンや花やかわいい絵の
シールの中から男の子の手にも一枚はると、彼は、ほっぺたにも
貼って欲しいという。貼ると今度は、おでこにも、という。
やがて、彼の顔が、シールだらけになると、他の子たちも
自分も、と言い皆の顔が、シールだらけになり、
皆で大笑いになった。シールもそれぞれの子の手に
たくさん伸せてあげる。
女の子が、男の子のポケットから、
落ちた折り紙を「あ、大変」というように、拾って、丁寧にいれ直して、
あげている。
やさしいいいお姉ちゃんなんだろうなぁ、という感じが、
その仕草一つからでも伝わってきて、ほほえましい。
子供達のお母さんが、子供達を呼ぶ。どうやら帰る時間らしい。
女の子は、お母さんのところへ走って言って、折り紙なんかの
ことを言ったらしい。お母さんが、遠くから、やさしい笑顔で軽く
会釈した。それから、手に持っている写真を嬉しそうに
ちょっと、あげて、皆にも挨拶した。Hさんが、親子を撮ってあげた
ポラロイド写真だ。
お母さんが、
肩にかけている天秤の両側の野菜のことを誰かが(中国語で)
尋ねると、前の野菜は、今夜のおかずで、後のは、家畜のエサ
とのこと。働き者のお母さんは、振りかえりながら、
家路についた。シールを顔中に貼った子供達が、その後についた。
暖かい家庭の夕餉の風景が心に浮かんだ。
子供達が、いなくなって、待ち時間が寂しくなった。
ホテルへ
結局、1時間半の遅れのために
バスは、真っ暗な山道を行く事になる(まだ山道があった! )。
バスは、遅れを少しでも取り戻したいのか、スピードをあげている。
私は、眠くなったけれど、心配で、寝ずに「番?」をしていた。
寝ている間に崖から転落なんてごめんだ、という気持ちだったのだ。
その日、ホテルへの到着は、9時を回っていた。
夕食が済むと10時近かった。皆が、やれやれと部屋に
帰ろうとしたとき、寄りによって、こんな時にこんな事を言うものか、
という声がかかる。
「添乗員はん、バスの座席な、守らないお人、おますねん。
明日から、バスの座席に全部名前、書いてちょうだいな!」
ひとりの女性だった。
それこそ、「ゲッ」という感じだ。多分、皆「う・うっ」と心で
思っていたはずだけれど、とにかくその時は、
それぞれの部屋にそそくさと、帰った。何しろ、もう時間は、遅かった。
添乗員さんは、遅れの処理や
明日の手配で、その時点でもまだ、夕食さえ済ませていなかった。
添乗員さんは、大変だ。
でもそれなのに、彼は、私のデジカメの調子を
見てくれるという。私は、多いに遠慮したけれど、
これから困るでしょうから、出来るだけのことは、と、
預かって行ってくれた。確かに、デジカメで、400枚は、撮れるつもりで
来ていたのだった。バッテリーの充電が、
万一出来ない場合を考えて、普通のカメラと、フィルムも
持っては、きていたけれど、少ない。全く困った事態だったのだ。
この日私が当たった部屋は、一階。ホテル自体は、
三江に比べるとずっと、ずっと、ホテルらしいホテルだった。
部屋の体裁もちゃんとしたホテルである。
でも、それだけに、私は、ベッドの堅さに驚いた。
こんなに硬いベッドって、初めてと言う位だった。私は、早く寝ようと焦りながら、
隣のベツドの毛布をはがすやら、枕を持って手くるなどして、
腰への負担が少しでも和らぐよう大奮闘した。
おまけに一階のせいかやはり布団が湿気っぽい。
その上、トイレの水も十分出ない。
私は、そのためにあるのかとも思われる
ホテルにあるらしくない↓金(かね)の洗面器に水を汲んで
流した。
右に見えるのが、バスタブ。立派そうに見えるけれど、
20㎝四方位、表面がはがれていた。
明日から写真、どうしよう。
そんなことなどあれこれ思いながら、口元に直接
布団が当たらないようマスクをして、ともかくも寝た。
明日からは、いよいよミャオ族の村になるのだ。