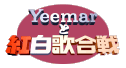
第7回
●歌が「下手」ではいけないのか●
音楽の好みが細分化した現在、「紅白歌合戦」を見ない、という人も当然います。見ない理由はいろいろでしょうが、「下手な歌手ばかり出場して、ほんとうにうまい歌手が出ていないから」ということを挙げる人も多いのではないでしょうか。
こういう意見をもつ人は、洋楽好きの人に多いです。つまり、日本の歌手は欧米の歌手に比べて下手であり、したがって「紅白」に出場する歌手にも歌の下手な人が多いというわけ。ちょっと単純化しすぎかもしれませんが、多くの人が賛成しそうな気がします。
話をポップスの歌手に限定しますと、たしかに、音程があやしく、声が出てない人はいますね。もともと音痴なのか、それとも、練習不足のために、こうなるんでしょうか。
アメリカの歌手でも、初期のナンシー・シナトラなんかのCDを聴くと、声は出てません。日本で人気があった「イチゴの片想い」(Tonight You Belong To Me)は、(下手なせいか)本国ではまったくはやらなかったそうです。僕は、この甘い歌い方がむしろ好きなのですが。
僕だけでなく、多くの人が、声の出てない、音程も怪しいポップス歌手の歌を聴いて満足しているのはどういうことでしょうか。音楽的センスが低い? いや、それだけではないはずです。ちょっと考えてみたのですが、これは日本語の特性と関係があるのではないでしょうか。
欧米の言語は、多く強弱アクセントです。強いところはびしっと強調しなければなりません。これは中学の英語で習うとおりです。強弱アクセントの言語が歌になるときは、強い音節は声を大きく出して強調しなければならないので、自然と歌手には声量が要求されることになるのでしょう。
いっぽう、日本語は高低アクセントの言語です。強弱によってアクセントを示さなくてもよく、いわばささやくように話すのですね。有気音(プハッと息を強く吐く発音)と無気音の対立もありません。こういう言語を話す国では、歌もささやくように歌ってまったく違和感がないのです。
ものの本によると、強弱アクセントの言語は英語・ドイツ語・ロシア語・イタリー語などであり、高低アクセントの言語は日本語・ヴェトナム語・タイ語・ビルマ語・中国語の呉方言・広東方言などだそうです。北京語もどちらかといえば高低アクセントでしょう。インドネシア語や朝鮮語などはアクセントをもたない言語です。
日本のポップスはアジアで比較的よく受け入れられているようですが、これはその国々の言語のアクセントと関係はないでしょうか。つまり、英語のように強弱アクセントの言語を使う国では、日本のポップスは「声が出ていない」として否定されますが、アジアの国々のように強弱アクセントでない言語を使う国では、日本のポップスも十分にエンターテインメントとして通用するということではないかと思います。やや強引でしょうか。
ただ、そうすると、高低アクセントをもつ日本語では、メロディの高低にも厳しく、音痴は許されないのではないかと思いますが、実際には音痴っぽい歌手が多いですね。ちょっと不思議です。
これはどういうことか。すべてアクセントに原因を求めるのは無茶ですが、日本語の高低アクセントはそれほど厳密ではなく、高低を違えて発音しても十分通じるような、大まかなものであるからではないでしょうか。中国語では、高低を違えると意味が通じなくなったりするので、もしかして中国人は音痴にも厳しいかもしれません(知りませんけど)。
ちょっと怪しげな説を展開してしまいました。でも、日本のポップス歌手が声が出ていないからと言って、それで即座に「下手」ということにはならない、また、そういう「下手」なら十分に許されると思うのです。
過去の「紅白」では、1987年ごろにオペラの佐藤しのぶを出演させたり、1990年ごろにはシンディ・ローパーを招いたりして、「声のよく出る歌手」を多く出演させようとしました。しかし、結局は視聴者に受け入れられず、今では「声の出ない歌手」を増やしています。それでいいんじゃないでしょうか。甘いかな。
(1998.12.28)
|