02.09.25
団七でえすわい
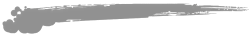
「それは僕の本です」などという「〜です」がいつごろからどのように成立したかは、まだはっきりしない部分があるようです。
辞典では、「〜でござります」が「〜でござんす」→「〜であんす」→「〜でえす」とだんだんルーズになっていって、最終的に「〜です」になったかと説明されています。しかし、研究者によっては、今の「〜です」はもっとずっと古くに成立していて、「〜です」が長くのびて「〜でえす」とか「〜でえんす」ができたと考えるほうが「真に近い」(此島正年『国語助動詞の研究』 p.82)と言う人もいます。
「〜でえす」という言い方は、一般的にはあまりなじみがありませんが、江戸時代の上方の作品には「最も普通」に出てくるようです。たとえば、湯沢幸吉郎『徳川時代言語の研究』から浄瑠璃の例を拾ってみると、
・フウ寺岡平右衛門とは、ヱヽ何でえすか
・こなんの云はんす親方筋とは、山崎の與五郎の事でえすか
・アイわしが御所柿、此村の大関でえす
などとあります。
現代のわれわれからすると、「〜です」がのびて「〜でえす」になるのは、自然な変化であるように思われます。なにしろ、かの藤井隆さんも「ナンダカンダ」(作詞・GAKU-MC)という歌で
なんだかんだ 叫んだって/やりたいこと やるべきです
の最後のところを「ベーキデース」とのばしているではありませんか。
僕の通った小学校では、発表した人の答えが合っていれば「ソーデース」、違っていれば「チガイマース」と唱和するように教育されました(おかしな習慣だったかもしれません)。
浄瑠璃などの「〜でえす」も、これと同じでようなものではいかと思っていました。「あい、わしが御所柿、この村の大関デース」というぐあいに発音しているのだろうと想像していました。
しかし、実際に発音を聞いてみて分かることもあります。
先日、めずらしく国立劇場に足をはこび、並木宗輔作の文楽『夏祭浪花鑑(なつまつりなにわかがみ)』(1745年初演)の一部を鑑賞しました。
「ヤアおのりや今日牢から出をつた」
「ヲヽ驚くまい。ヘヽヽヽ団七でゑすわい」(『文楽床本集 第一四〇回文楽公演』2002.09.07 p.15)
ここのところの発音が、太夫の語る節では「ダンシチデ、エスワイ」というふうに、区切ってありました(なお、日本古典文学大系の本文では「ヲヽ驚まいヘヽヽヽ。團七でゑすわいな」となっています)。
この発音の仕方が昔からのものだとすると、「〜でえす」は「デース」ではなく、「デ、エス」と2文節に分かれているのですね。文楽ファンには、常識のことかもしれません。
そうなると、「〜です」が単純にのびて「〜でえす」ができるという説明は、ちょっとむずかしくなりそうです。上で見たことだけに注目すれば、「〜で、えす」が縮まって「〜です」になったと考えたほうが合理的のように見受けられますが、いかがでしょうか。
|