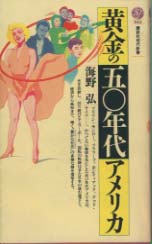
(2/24記述)
アメリカの核戦略と、その核の傘の下に保護されている国との関係は当時の映画にもなんらかの形で影響を与えています。それは一見、政治とはまったく関係ないような明るく楽しい映画のなかにも見え隠れしているようです。海野 弘 著、「黄金の50年代アメリカ」にあの懐かしい映画「ローマの休日」のことがのっています。
「ローマの休日(ROMAN HOLIDAY)」はオードリー・ヘプバーンのアメリカ映画初主演作であり、アカデミー主演女優賞をとった1953年製作の作品です。ヨーロッパの小国の王女が親善のためにローマにやってきます。堅苦しい儀式ずくめの旅行から、自由にローマの街を歩きたいために、王女は大使館を抜け出してしまいます。そこでアメリカ人新聞記者(グレゴリー・ペック)と出会い王女の冒険が始まります。ふたりでベスパに乗ってローマの街を走るシーンや「真実の口」のシーンは大変なつかしく思いだされます。監督はウィリアム・ワイラー、 脚本アイアン・マクラレン・ハンター、 撮影:フランツ・プラナー、出演はオードリー・ヘプバーン、グレゴリー・ペック、エディ・アルバード 他です。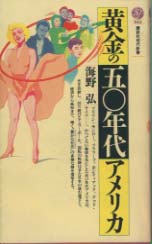
それでは
黄金の50年代アメリカ
海野 弘 著
講談社 1989年 発行
冷戦を反映する小道具(Pー183)
から引用します。
〜そういえば、「ローマの休日」のようにメルヘン風のロマンティック・コメディにさえ、当時の政治状況がまったく無縁でないのにはおどろいてしまう。王女にもどったヘップバーンが記者全見で欧州共同体について聞かれ、国と国の信頼関係が、個人と個人の間の信頼の上に築かれることを望むとのべるところがある。アメリカの新聞記者であるグレゴリー・ペックは、王女のアメリカ人への信頼は裏切られることはないだろうと答える。ここではナイト・ガウンの世界がパジャマの世界と結ばれること、ヨーロッパの王女はアメリカの新聞記者によって守られるであろうこと、つまりヨーロッパとアメリカの絆を深めたいということが語られている。これらは一見あたりまえのことのようだが、トル−マン大統領が水爆製造を指令し(1950)、スターリンがソ連の原爆実験を発表し(1951)、欧州防衛共同体条約がパリで調印され(1952)、スターリンが死んだ(1953)、というこの映画がつくられた時期を考えてみれば、米ソ間が一触即発の危機にあったわけであり、アメリカがヨーロッパとの絆を強固にしておきたいという期待がこの映画にも感じられるのである。アメリカのストライプのパジヤマに包まれて、ヨーロッパは安らかに眠れるのだという楽天的な夢を語る『ローマの休日』は、やはり五○年代でなければつくれなかった映画なのであった。ヘップバーンはあんなに美しく、グレゴリー・ペックはあんなにたのもしかったのだ。〜
ここまで考えるのは”深読み”だという人がいるかもしれませんが、当時の(そして今も)アメリカ映画の国際世界での大衆にたいする影響力を考えれば、充分、アメリカの政治宣伝がこのような洗練された形でおこなわれていたと思います。