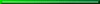
シンジはいつの間にか眠りに落ちていた。
「シンジ、これから起動実験を始める。着替えて、あれに乗れ」
「父さん・・・・・何言ってるんだよ・・・・・」
「時間がない。一度で理解しろ。あれに乗れ」
「僕は、今、着いたばかりなんだよ。何にも知らないのに、乗れるわけないじゃないか」
「説明を受けろ」
「父さんは、こんなことのために僕を呼び寄せたの」
「そうだ。必要だからだ。おまえでなければ役に立たない」
「・・・・いやだ! 絶対にいやだ!! 僕はあんなものに乗りたくて、ここに来たんじゃない!! 僕はただ・・・」
「乗るのか乗らないのか、早く決めろ。時間の無駄だ」
「・・・・じゃあ、乗らないよ!! 第二新東京へ帰るから・・・」
「そうか・・・・。おまえには失望した・・・とっとと帰れ」
その時、ドアが開いて蒼髪の少女がシンジのいるエヴァ・ケージにはいってきた。
「・・・・なんで、乗らないの?・・・・・」
「君には関係ないだろ・・・君は誰なんだよ」
「・・・・・自分の親を信じられないの?・・・・・」
「僕は父さんに捨てられたんだ。だから親なんていない、って思うようにして生きてきたのに・・・。
突然、ここに呼ばれたとき、ほんのわずかでも期待した僕が馬鹿だったよ。所詮、僕は父さんにとっては
手段、道具に過ぎないんだ。」
「・・・・なんで、そんなことが分かるの?・・・・・」
「僕はいらない子供なんだ・・・・そうでなきゃ、こんな仕打ちができるはずがない・・・・」
「・・・・自分の子供をいらないと思う親がいると思うの?・・・・」
「君は親に捨てられたことがないから、そんなことが言え」
シンジがそう呟いたとき、その少女は、それまでの無表情な顔を、きっ、と険しくして、シンジの頬を打った。
その場にいた、ミサト、リツコ、ゲンドウ、冬月、そして第一発令所でモニターでこれをみていた
マコト、シゲル、マヤ、その他の多くの職員も一様に驚愕の表情のまま押し黙った。
「レイ、あなた・・・・・」
リツコが問い掛けようとすると、レイは再び表情を消して、何事もなかったかのように、ドアから出ていった。
「シンジ君。あの子は綾波レイ。あなた同い年のもう一人のパイロットよ」
ミサトは呆然としているシンジに向かって静かに口を開いた。
「なんで、僕が会ったばかりの人に叩かれなきゃいけないんですか!?」
「あの子は、いろいろと事情があって、今、一人で暮らしているの・・・・・」
「あの子には親はいないわ。甘えたこと言わずに、たった一人で生きているのよ。あなた恥ずかしくないの?」
「リツコ!! こんなときにそんなこと言わなくてもいいじゃない!!」
「シンジ、乗らないのなら、さっさと出て行け。目障りだ」
「・・・・・・・・ 」
「シンジ君、運命から、お父さんから、逃げちゃ駄目よ。これが現実なの。現実を踏み越えない限り、未来はないわ」
「・・・・ミサトさん・・・・教えてください・・・・なぜ、僕はあれに乗らなきゃいけないんですか?」
「・・・・あなたが乗らないと、あれは動かない。そうすると、やがて破局が訪れて、みんな死ぬことになるわ」
「このNERVの人たちがですか?」
「・・・・人類・・・・すべてよ・・・」
「赤木博士、本当なんですか?」
「本当よ。この期に及んで、あなたに嘘ついても仕方ないじゃないの。」
「・・・・人類が・・・・滅ぶ・・・・・僕のせいで・・・・・」
「そう。あなたのせいで、全然関係のない、普通に暮らしている人たちまで死ぬことになるのよ」
シンジの脳裏には、さっき特別非常事態宣言が発令されたときに、
新箱根湯本駅でみた、怯えた顔の群衆の姿、そして暫く一緒に街をさまよった高橋の姿が浮かんだ。
「・・・・みんな死ぬ・・・・ぼくのせいで・・・・みんなが死ぬ・・・・・」
「時間だ。零号機の起動実験に向かう。このケージを閉鎖しろ」
ゲンドウがシンジを一瞥もせずに命じた。
(逃げちゃ駄目だ、逃げちゃ駄目だ、逃げちゃ駄目だ)
「僕が、乗ります」
シンジは苦衷の表情を浮かべて絞り出すような声で承諾した。
起動実験は失敗した。
シンジは自分の決意が成果に結びつかなかったことに、空しさと、自覚しないまま、僅かな安堵感を覚えていた。
激しい疲労のため、シンジはNERV本部の仮眠室でほどなく熟睡した。
翌日の放課後に行われた起動実験も失敗した。
シンジは再び複雑な感情に襲われていた。
(僕は一生懸命やったんだ・・・でも、だめだった・・・・どうしようもないことなんだ、これは・・・・・
やっぱり僕じゃだめなんだ・・・・役に立たないんだ・・・・それが起こっても、ぼくのせいじゃない・・・・)
「彼でも駄目なの? そうよねぇ、レイですら、7ヶ月も訓練して、未だに起動したことがないのに、
来たばっかりのシンジ君には、やっぱりオー・ナインシステムは無理だったのね・・・。で、リツコ、これからどうするわけ?」
「仕方ないわ。レイの起動実験を続けて、シンクロ率を少しずつでも上げていくしか方法はないわ。」
「・・・・・時間、あるの?・・・・」
「正直言って分からないわ。神のみぞ知るってことかしら。」
「神、か・・・・。私たちの味方なら、いいのにね・・・・」
その日の夕刻、零号機の起動実験が行われた。
「A10神経、接合」
「パルス、正常」
「シンクロ率、上昇しています」
実験施設のすべての人々が期待を込めて、零号機をみていた。
(・・・・みんな・・・みてる・・・・・
・・・・エヴァ・・・・みんなとの絆・・・・・
・・・・ヒトとの絆・・・・・・・・・・・・・
・・・・たったひとつの私の絆・・・・・・・・・・)
エントリープラグの壁面が明るくなった。
まるで壁がなくなったように外が見える。
(・・・・応えて・・・くれたのね・・・・・)
レイは実験施設の窓にへばりついて零号機を見下ろしていた多くの人々が歓声をあげて抱き合うのをみた。
(・・・・絆・・・守ったわ・・・・)
レイは、LCLの中で、ほっ、と息を吐いて少し俯いた。激しい疲労が襲っている。
もう一度、顔を上げたとき、その少年の姿が視界に入った。
(・・・・私を・・・みてる・・・・・・・・・・・・・・
・・・・険しい顔・・・・憎しみの顔・・・・・・・・・
・・・・なぜ、私を憎むの?・・・・・・・・・・・・・
・・・・あの人ですら、喜んでいるのに・・・・・
・・・・わたしの絆・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・あの子とはつながってないの?・・・・・・・・
・・・・なぜ・・・・どうして・・・・分からない・・・)
「シンクロ率が急低下しています!!」
「バルス、逆流!!」
「神経接続、解除!!」
「いけない!! 暴走するわ!!」
咆哮をあげた零号機はケージ内で暴れ始めた。
「実験中止!! パイロットの安全を確保して!!」
「エントリー・プラグ、強制射出されます!!」
「いかん!! ケージの壁に激突するぞ!!」
射出されたエントリー・プラグがケージの壁にあちこちぶつかり、床に落下する。
「レイ、大丈夫か!!」
シンジはみた。
自分の実父が、真っ先に現場に駆けつけ、手を火傷しながらも、素手でエントリー・プラグのハッチを開けて、
蒼髪の少女を助け出すのを。
「・・・・・父さん・・・なんで、僕よりあの子を大切にするんだよ?!
・・・・・やっぱり僕はいらない子供なんだ・・・・・・・・・・・・
・・・・・道具に過ぎないんだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・ちくしょう、ちくしょう、ちくしょうっ・・・・・・・・」
同日、午後8時30分、第一発令所。
「やっぱり零号機も動かないのか。どうする、碇? もう駒がないぞ・・・」
「・・・・まだ、可能性はある」
「確信はあるのか?」
冬月は、ゲンドウが唇の端だけを僅かに歪めて微笑むのを、ただみつめていた。
「新小田原沖の海上に高エネルギー反応!」
「パターン青! 使徒です!!」
発令所に絶望の沈黙が漂った・・・・・。
「いい? シンジ君。もう、あなたしかいないのよ。頼んだわね」
「でも、僕じゃ起動すらしなかったじゃないですか? ・・・無理ですよ、ミサトさん・・・・」
「やってみなければ分からないわ。確率がゼロでないことは全てやってみないと、後で後悔するから」
「そんな!! リツコさん、無責任なこと言わないで下さい!! 闘うのは僕なんですよ!!」
その時、ケージ内のモニターが第一発令所とつながった。
「初号機のデータをレイに書き換えろ」
ゲンドウの淡々とした声がケージに響く。
「レイは重傷です。無理に乗せれば、確実に・・・・」
「構わん。今、確率があるのは、この方法だけだ。手をこまねいていては、全てが終わる。
そうなれば確実にみんな死ぬ。僅かな時間、生を永らえたとしても無意味だ」
「そうね。これしかないわ・・・ミサト・・・・みんなが、人類が、生き残るためなのよ・・・・」
「・・・・・・・・・・」
ミサトは俯いた。理性は理解できている。感情が許さない。
レイが病室から連れ出されてケージに入ってきた。
息は上がり、白皙の顔は苦痛に喘いでいる。
必死に声が出ないようにこらえているが、時々、小さな悲鳴をあげてしまう。
「・・・・レイ・・・・・可哀相だけど、私たちにはもう方法がないの・・・私たちを恨んでね・・・・」
「・・・・その必要は・・・・ありません・・・・葛城一尉・・・・
・・・・それをすることが私の使命・・・・・みんなとの・・・たったひとつの絆・・・・」
「・・・・・僕が、僕が乗ります!!」
「シンジ君・・・・」
「シンジ、おまえでは駄目だ。起動しない」
「やってみなければわからないじゃないか!! 放っておいたら、みんな死んじゃうんだろ?
だったら、できる限りのことをやっておきたいんだよ!!」
「・・・・・・シンジを初号機に乗せろ・・・・。だが、起動しなかったら、直ちにレイを零号機に乗せろ」
レイは、さっき自分を憎しみの表情でみつめていた少年の顔を見上げた。
「・・・・・・君のこと、憎かった・・・でも、憎む相手が違ったよ・・・・
・・・・・・絆・・・ひとつだけじゃないよ・・・・・・・・
・・・・・・ほかの絆もみつけなきゃ・・・・・」
レイは、シンジの言葉の意味を図りかねて、ただ痛みに耐えながら彼の瞳をみつめていた。
エントリー・プラグの中で、シンジは目を瞑った。
「頼む、動いてくれ、そうじゃないと、みんな死んじゃうんだ」
初号機は微動だにしない。
「レイ、準備をしろ」
「はい・・・・」
「動け、動け、動け、今動かないと、綾波は死んじゃうんだ。頼む、動いてくれ、僕はどうなってもいい、
動いてくれ!!!」
第一発令所に歓声が沸き起こった。
零号機のように暴走もせず、起動した初号機はかなり高いシンクロ率を維持したまま、使徒との実戦に臨んだ。
が、戦いにならなかった。
一方的に攻撃を受け続けるうち、シンジは意識が薄れてきた。
「・・・・・これで・・・終わりなのか・・・・なんにもできなかった・・・・綾波・・・・ごめんね・・・・」
シンジは意識を失った。
「・・・・ラジオ体操の音だ・・・・」
「シンちゃん、起きた? 今日はシンちゃんが当番の日でしょ。」
「・・・・ここはミサトさんのマンション・・・・またみたんだ、夢・・・
・・・・まだ鮮烈に覚えているんだ・・・・僕の神経は・・・・・・」
いつもの朝が始まった。
つづく
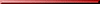
第10話に進むには、この を押してください。
を押してください。
「小説のありか」に戻るには、この  を押してください。
を押してください。
![]()
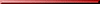
 を押してください。
を押してください。