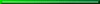
放課後。リエはリョウコと教室を出ようとした。
西日に眩ゆいばかり照らし出されている廊下に出た途端、彼女たちは後ろから呼び止められた。
「高橋さん、明石さん、ちょっといい?」
「あっ、須磨先生。どうしたんですか?」
「実はね、綾波さんに「進路相談についてのお知らせ」をまだ配っていないのよ。あの子、よく休むから・・・・」
「え? だって進路相談はもう来週からじゃないですか? あと数日しかないですよ」
「だから、あなた達に頼みたいの。高橋さんは新駒沢に住んでいるから、綾波さんのうちはすぐ傍よね」
「ええ、まあ。あの辺は殆ど行ったことはありませんけど・・・・・」
「じゃあ、今日、家に帰る途中でいいから、綾波さんのところに寄って、プリントを渡しておいてくれないかしら?」
「え!? 私がですが? 私、あんまり、あの子と話したことないから・・・・」
「それはあなたに限ったことじゃないでしょ。あなたの家が一番近いのよ。お願いね」
「はぁ・・・・。わかりました。とにかく渡せばいいんですね?」
「よろしくお願いね」
「ねえ、リエ! これってチャンスじゃない?」
「何が?」
「これで、あの子の家を正式に訪れる大義名分ができたじゃないの!!」
「でも、気が重いわ。「・・・・なにか用?・・・」とか言われたら、どう答えていいか分からなくなっちゃうよ・・・。」
「とにかく行ってみましょうよ。何かがわかるかもしれないわよ」
彼女たちは環状線の新駒沢駅に降り立った。
西日が少し傾きかける中、アスファルトの舗道の上をふたつの影が仲良く並んで揺れて行く。
「・・・・・!?・・・・・ここが・・・そうなの?」
薄汚れた外壁のアパートには、再開発工事のくい打ち機の音だけが遠く近くに響いている。
階段には、空のペットボトルや雨に打たれて皺くちゃになったチラシ、そしてたばこの吸い殻が散乱している。
「・・・・・本当に、ここなの?」
「間違いないわ。あの子、こんなところに・・・・・」
彼女たちは402号室のドアの前に立った。
「・・・・・」
リエはチャイムに手を伸ばしたが、指が触れる直前に、動きを止めた。
「ねえ・・・リョウコ、一緒に押そうよ・・・なんか、私・・・・」
「しょうがないわね・・・・」
チャイムは電池でも切れているのか、はたまた故障しているのか、音を立てなかった。
「困ったわね・・・・どうしようかしら」
「ドア、叩いてみようよ」
「うるさいけど、この際、仕方ないわね」
しかし、少し錆の浮いた鉄扉の向こうからは何の返答もなかった。
二人はドアに耳を近づけていった。
「・・・・なに・・・してるの?・・・・・・」
いきなり後ろから囁くような声をかけられた二人は、心臓が止まるほど驚いた。
「あああ、あの、せ、先生が、須磨先生が、綾波さんにプリント持っていってほしいって」
「・・・・・そう・・・・・・」
頭と腕に包帯をした松葉杖の少女は、表情を変えることなく、リエの手からプリントを、すっ、と抜き取ると、
二人の目の前をぎこちなく歩いてドアを開けた。
カギはかかっていなかった・・・・。
「あの、お節介かもしれないけど、出かけるとき、鍵かけたほうがいいよ。やっぱり物騒だから・・・・」
おずおずと声をかけたリョウコ。
レイは振り返らなかった。
「・・・・・私には・・・・なにもないから・・・・・カギ、いらない・・・・・」
「なにもないって、あなたねぇ、物取られるならいいけど、居直り強盗とかにあって、
命とられちゃったら、どうすんのよ!!」
「・・・・・・・いい・・・・・・それもひとつの終わりだから・・・・・」
「何言ってるのよ・・・・あなたはいいかもしれないけど、まわりの人が悲しむでしょうが? 」
「・・・・・・・それは・・・・ないわ・・・・」
「・・・・あなたに何かがあれば、必ず誰かが悲しむのよ・・・・カギ、絶対にかけるのよ・・分かった?」
普段、声を荒げたことのないリエの激しい口調に、レイは初めて振り返った。
「・・・・・・・・・・」
真紅の澄んだ瞳は、少し蒼ざめながらも険しい顔をして立つ少女をみつめた。
少女も視線を外さない。
レイは、ふっと視線を外すと、静かにドアを閉めた。
(・・・・・なぜ、あの人は、私に怒ったの?・・・・・・
・・・・・私・・・・怒られたことがない・・・・・・・
・・・・・ヒトと違うから・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・視線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・好奇心の対象に向けられるもの・・・・・・
・・・・・一瞬しか触れ合うことのないもの・・・・・・
・・・・・あの人も険しい顔だった・・・・・・・・・
・・・・・視線は・・・・他のひとと違った・・・・・・
・・・・・私をみつめつづけた・・・・・・・・・・・・
・・・・・ずっと触れ合っていた・・・・・・・・・・・
・・・・・なぜ・・・・なぜ・・・・・なぜ・・・・・・)
レイは錆の浮いた扉に背中をもたれさせて、そっと目を閉じた。
「リエ・・・どうしたの?・・・・・」
「・・・・あの子があんまり悲しいこと・・・言うから・・・・・」
「・・・・そうね・・・・・・・・・」
「・・・・私・・・・偽善者なのかな・・・・・」
「どうして?」
「・・・・私も、みんなと同じように、あの子のこと避けてきたもの・・・なんとなく近寄りがたかったから・・・・。
・・・・あの子にあんなこと言わせたのは、私たちのせいかもしれないのに・・・・・」
「リエ・・・・・」
「・・・・あの子の瞳、初めてみつめたわ・・・・とても澄んでいた・・・・・清らかだった・・・・。
でもね、それだけなの・・・・他には何も感じられなかったわ・・・・」
「虚無の美しさ、っこと?」
「そう・・・・。でも、それは本当の美しさじゃないような気がするの。「ヒト」は他の人と接して、傷ついたり、
悩んだり、いたわったりして、「人間」になっていくんじゃないのかしら・・・。そういう意味で、あの子の美しさは
命のない宝石のようなものなのよ・・・・人は人と一緒に生きてこそ輝くことができるのに・・・・。
今のあの子は輝いてないわ。」
「あの子、人付き合い、苦手そうだもんね・・・・」
「あの子が私たちに近寄りにくいんだったら、私たちの方から近寄っていくっていうのはどうかしら?」
「でも、さっきみたいに拒絶されるかもしれないわよ。
単なる同情とか中途半端な気持ちなら、すぐに挫折して、かえってあの子を傷付けるだけに終わるわよ」
「うん、わかってる・・・・・。すぐにはなじんでくれないかもしれないけど、辛抱強く接していくようにすれば
きっとわかってくれると思うのよ」
「リエがそこまで思ってるなら、あたしも協力してあげるわ。あたしだって、前から、あの子がぽつんと独りで
席に座っているのを見るのは、愉快じゃなかったから」
「ありがとう、リョウコ。とりあえず、どんな些細なことでも、あの子に話し掛けることから始めようよ」
リエはリョウコを新駒沢駅まで送って行くと、灯りがともり始めている商店街を抜けて、住宅街に通じる坂道を
ゆっくりとのぼり始めた。
まださほど暗くなっていない坂道を、少し涼しくなった風が吹きぬけて、道の脇の草むらを揺らす。
サイレンが鳴り始めた。
リエは、対空迎撃訓練が終わって地下からビルがゆっくりと赤い空に向かって伸びていくのを
立ち止まって眺めていた。
「私たち、これから、どうなっちゃうんだろう・・・・・。考えても仕方のないことなのに・・・・。
私たちにできることは、毎日、しっかりと生きていくことだけなんだから・・・・。
・・・・今日はいろんなことがあったわね・・・・
碇君、か・・・・・。エヴァに乗るのって大変なんだろうなぁ・・・・。
でも、この街の運命は彼に委ねられているのよね・・・・・。
がんぱってね、碇君。・・・・私たちの未来を護ってね・・・・・」
リエは、セミの声が減って、代わりにコオロギの声が聞こえ始めた坂道を登り始めた。
近道を登りおえて、住宅街にさしかかったとき、リエは後ろから車のエンジン音を聞いて振り返った。
坂道を登り終えて加速し始めた青い車が結構なスピードで走り寄ってくる。
リエは思わず、道の端によけた。
が、慌てたために、段差につまづいて転んでしまった。
「大丈夫?」
青い車から降りてきた、髪の長いタイトスカートの娘はリエに手を差し伸べた。
「あ、大丈夫です。あっ、いたたたた」
立ち上がろうとしたリエは、足の痛みに思わず声を上げた。
「あちゃー、これは足首ひねっちゃったみたいね。家はどこ? 送っていってあげるわ」
「そんな、悪いですよ。私が自分の不注意で転んだんですから・・・・」
「何言ってんのよ。子供が遠慮なんかするんじゃないの。ま、あたしはちょっち遠慮があったほうがいいって
みんなから言われてるみたいだけどねん」
そう言って、その娘は、にこっと笑った。
(あ、この人、悪い人ではなさそう。なんか元気のいいお姉さんって感じ・・・・。
やっぱり足痛いし、送ってもらおうかな)
「家は、新駒沢2丁目、このすぐ傍です。」
「何だぁ、うちのマンションのすぐ近くじゃないの。良かったわ、「うちは北海道です」とか言われたら、どうしようかと
思ってたわ」
そんな彼女の冗談にリエも思わず微笑んだ。
「あ、名乗ってなかったわね。あたし、葛城ミサト。あなたは?」
「高橋リエです。」
「リエちゃんね。よろしくね。あ、ちょっと待っててくれない。5分で買い物済ませちゃうから」
「急ぎませんから、ゆっくり買い物してきてくださいよ」
そう答えるリエに、ミサトはにっこりと笑いかけるとコンビニに入っていった。
5分後、リエは絶句していた。
「・・・・・・葛城さんちって、大家族なんですか?」
「ん? あたしとシンちゃんの二人だけよ」
「あ、ああ、お仕事忙しいんで、買いだめなさってるんですね」
「ううん。今晩、飲む分よ」
「一人で?」
「一人で!!」
(12缶・・・・このエビチュの本数は尋常じゃないわ・・・・・。この人、本当はすごい人なのかも・・・・・
ああっ、関わり合いにならない方がよかったかも・・・・)
今になって内心、後悔し始めているリエに気づきもせず、ミサトは車を走らせた。
「ちょっとマンションに寄って、この荷物を置いてくるから、ほんのちょっと待っててね。ごめんねぇ」
「あ、いいですよ。気にしないで下さいよ」
ミサトはマンションの前で車を停めると、携帯電話を取り出した。
「あ、シンちゃん。あたし。マンションの前に車停めたから、荷物とりにきて欲しいの。えっ、そ、そうよ、
エビチュよ・・・別にいいじゃないのよ・・・あーら、あたしの体のこと、心配してくれるの?
シンちゃん、やっさしー。じゃ、やさしいついでに、荷物とりにきてね、お願い」
ミサトが一方的に電話を切ってから、ほどなくエントランス・ホールから仏頂面をした少年が
「平常心」と書かれたTシャツを着て現れた。
「あっ、碇君!?」
「あら、シンちゃんのお知り会い? シンちゃんもこんなかわいい子と早くもお知り会いになっちゃうとは、
隅に置けないわね」
ニカーっと笑うミサトにシンジは赤くなって抗弁する。
「ミサトさん、そんなんじゃないですよ!! 同じクラスの子ですよ。もうっ、すぐにそんなこと言うんだから」
「碇君、葛城さんの弟さんなの? じゃ、義理のお姉さん?」
「あたしはシンちゃんの保護者なの。ちょっち、いろいろ事情があって、シンちゃん、お父さんと別居してるから・・・・
そうそう、あたしのことは、シンちゃんと同じようにミサトって呼んで。よろしくねん」
「そうなんだ・・・・。碇君、ここに住んでたんだ・・・・。えっ、ということは、このマンションは・・・・」
「ああ、ここ? ここは、コンフォート17っていうマンションよ。」
「じゃ、じゃあ、ミサトさんもNERVに・・・・」
「よく知ってるわね・・・・。この辺ではもう有名なの?」
ちょっと表情を曇らせながら、ミサトは尋ねた。
「いいえ。わたし、そこの石河不動産のおじさん達と仲いいですし、父もこの辺のことはたいてい知ってるから・・・・」
「リエちゃんのお父さんって、何してる人?」
「この第三新東京市の市会議員です。この新駒沢の一帯が選挙区なんです」
「えっ、じゃあ、この間、新箱根湯本で出会った、あの・・・・」
「父を知っているんですか? 確かに父は1週間ぐらい前、特別非常事態宣言が出た日に新箱根湯本に
行ってましたけど・・・」
「あたしとシンちゃんは、あの宣言が出たとき、偶然、あなたのお父さんと出会ったのよ。あたしが、第二新東京から
引っ越してきたシンちゃんを迎えに行ったときよ。それにしても、シンちゃん、リエちゃんと話してたんでしょ?
あの市議さんのお嬢さんだって、気がつかなかったの?」
「え、えと、その、新駒沢に住んでいるってことと、お父さんが市議やってるってことは聞いたんですけど・・・。
まさかあの時の市議さんの子供とは思わなかったんで・・・ど、どうも、すみません・・・・」
「いいのよ、別に怒ってるわけじゃないんだから。
ねっ、リエちゃん、シンちゃんってすぐこんなふうに謝るのよ。林家三平みたいでしょ。学校でも、こんな感じ?」
「いえ、学校では、いつも女の子に声をかけまくってます」
「シーンちゃーん! やっぱりあなた、女の子にちょっかい出してるのね!?」
「あっ、高橋まで、そんなこと言うの!!・・・・ひどいよぉ・・・・ミサトさんに感化されないでよぉ!!
僕は、ミサトさん一人でも、もて余しているんだから!!」
「もて余してるって何よ!! レディに向かって失礼でしょ!!」
「・・・・レディは1晩でビール12缶も空けたり、空缶やゴミの山の中で暮らしてたりはしないと思うんですけど・・・」
3人はうす暗くなったマンションの駐車場で、明るい笑い声を上げていた。
つづく
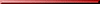
第8話に進むには、この を押してください。
を押してください。
「小説のありか」に戻るには、この  を押してください。
を押してください。
![]()
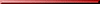
 を押してください。
を押してください。