或いはひとつの可能性 |
この小説はフィクションです。小説の中に登場する全ての人物、団体名は、実在の人物、団体等とは一切、関係はありません。
![]()
第45話・酷薄な情け |
「さっき、議会からの帰りに綾波さんに会ったよ」
高橋は背広を脱ぎながら、俯き加減で頬杖を突いてテレビを見ているリエに話し掛けた。
「あ、お帰りなさい。えっ、こんな時間に綾波さんが? 珍しいわね」
リエは少し眠そうな顔で、目をこすりながら立ち上がった。
「ああ。リエが言ってたみたいに変わった子だね。いや、変わってるっていうか、淋しそうな感じがしたな」
ネクタイを緩める手を一瞬止めて、高橋はぽつりと呟いた。
「・・・・そうなの・・・・でもね、最近は少しずつ変わってきたのよ。表情も豊かになってきたし・・・・」
リエは明るい口調で答えると、最近時折見られるようになったレイの微笑みを脳裏に描いた。
「へえ、そうかい。俺は初対面だから、ちょっと警戒されたのかな。まあ、いいや。それでね、
初瀬のコンビニの先の坂道で立ち止まって、ぼうっと夜景を眺めてたんだよ、あの子。だからね、
夜道は物騒だから、早く帰るように言って、取り敢えず葛城さんのマンションまで送ってったよ。
再開発地区まで送っていこうかとも思ったんだけど、また後でNERVから痛くも無い腹を探られるのも
いやだしね・・・・葛城さんに会うと、さらに大変そうだから、マンションの前で別れて帰ってきたけどね」
高橋は、外してしまったネクタイをだらしなく食卓の椅子の背にかけた。
「何か話したの、綾波さんと?」
リエは立ち疲れて椅子に腰掛けたが、相変わらず興味津々という瞳で父親を見つめていた。
「いや、とくに・・・・口数の極端に少ない子だったしね・・・・・」
(やっぱり、綾波さんを打ったことはリエには黙っておこう。いろいろ文句言われたらかなわないからな。
ましてや、俺のキザな台詞なんて、口が裂けても娘には言えないな・・・・)
高橋はリエに背を向けると、娘に気づかれないように僅かに苦笑した。
「ふーん・・・・そうよね。お父さんと綾波さんの間に、共通の話題なんてあるわけないもんね。
あーあ、ちょっとでも期待して損しちゃった。」
リエはつまらなそうな顔をすると、高橋に背を向けてテレビを眺め始めた。
「まあ、そういうなよ。ところで、何か食べるもの、あるかい? ちょっとごたごたがあって
晩飯食ってる暇が無かったんだ。残り物でもいいからさあ」
「ええっ、だって今日は外で食べてくるって言ってたから、何も用意してないわよ。夕食も
お蕎麦を1人前だけ作ったから、もう残りも無いし・・・・食べ物って言ったら、これぐらいしか・・・」
リエは困惑した顔で立ち上がると、戸棚からインスタントラーメンの袋を取り出した。
「ああ、これで十分だよ。俺たちセカンドインパクト世代は、こういうの慣れてるからね。
あの頃は、こういうのでもご馳走でねえ。物が食べられるっていうだけでも有り難いって時代だったんだ。
まったく、今は幸せな時代になったもんだよ、ほんと・・・・・」
高橋は、溜め息をつきながら、インスタントラーメンの袋をがさがさと振りつつ、キッチンへと向かった。
「お父さん、ちゃんとガスの元栓閉めておいてよ! 時々、閉め忘れてるから、きちんとしてね」
リエの厳しい声を背中で聞きながら、高橋はキッチンに立った。
「へいへい、わかりやした。ったく、最近、だんだん、あいつに似てきやがったな。不思議なもんだ。
物心もつかないうちに別れてしまったのにな。血は争えないってことか・・・・」
口の中でぶつぶと言いながら、高橋はふとリエの母親の姿を、ひどく懐かしく、そしてどこか胸の痛くなるような
感触とともに思い出していた。
「今日は、やけに昔のことばかり思い出すなあ。どうも辛気臭くていけねえや。こんな晩は、飯食って
早々に寝ちまうのが得策だね」
高橋が水道の蛇口に手を伸ばしながら何気なく、視線をすりガラスの窓に移したとき、何かの影がすっと音も無く、
窓ガラスの下の方をよぎって消えた。
(・・・・ふーん、ついに俺の監視もここまで強くなったか・・・・どうやら俺もVIPの仲間入りってわけか・・・
・・・・・俺も偉くなったもんだねえ・・・・・やれやれ・・・・・)
高橋は皮肉な微笑みを浮かべると、何事も無かったように水道の蛇口を捻った。
「あ、お父さん、来週、進路相談があるから、学校に父兄が来るようにって先生が言ってたよ。
ここにプリント、置いとくね。じゃ、私、そろそろ寝るから。ちゃんと戸締まりと火の元、確認しといてよ」
リエは、忙しそうに葱を切っている父親の後ろ姿に声を掛けると、廊下をとたとたと歩いて、自分の部屋に
向かった。
「ああ、分かったよ。じゃ、おやすみ・・・・さてと、湯を沸かしてって・・・・」
高橋は鍋に水を張ると、湯が沸騰するまでの間、キッチンの椅子に座った。
(・・・・橋立君の探してくれた、あの書類があれば、今回はなんとか虎口を逃れられそうだな。だけど、
これから、きっと何度もこういうような危機はやってくるだろうな・・・・向こうもようやく本気を
出してきたみたいだし・・・・・)
視線を、ちらりと窓の方に走らせながら、高橋は無意識のうちに腕組みをした。
(こちらも自衛手段を講じるしか手はないな。万田さんと近いうちに連絡を取ってみるか。それと、
橋立君の処遇についても、いよいよ真剣に考えなきゃならんな・・・・・)
ジュッと、鍋の湯が吹きこぼれる音に高橋は我に返ると、慌てて立ち上がった。
第3新東京市の夜は、いつもと変わり無く更けていった。
翌日午後1時、議会内の会議室に、第3新東京・自由改進党の議員たちが集まっていた。
昨日とは打って変わったような晴天の下、明るい陽光の差し込む室内で、議員たちは
八雲の周りに集まって晴れやかな顔で談笑しているか、あるいは松島の周りに集まって
厳しい表情で腕組みをして立ちすくんでいるか、どちらかであった。
そんな中で、高橋は足元に何かの入ったデパートの大きな紙袋を置き、眼をつむって椅子に座っていた。
「いよいよ観念したってことか」
「ああ、首を洗って待っているって姿勢だよ。年貢の納め時だね」
時折聞こえる八雲サイドの議員の声にも、高橋は動じること無く、姿勢を崩さない。
「高橋君は、大丈夫なんだろうな。こちらの票読みでは、半数近くの議員が八雲寄り、その他の議員の
2割が態度保留だからな。ここで踏ん張らないと、市議会はNERVに屈することになってしまうぞ」
幹事長代理の松島は、時折、高橋の方に視線を走らせながら、心配そうな表情で呟いた。
「彼なら、大丈夫だろう。第3新東京市議会きっての寝業師と言われた男だからな。今度も、何か
秘策があるにちがいないさ。それがあの余裕につながっているんだよ。まあ、ここは彼を信じようじゃないか。
我々にできることは、全て手を尽くしたんだからな。それで、執行部を追われるようなことになっても、
もはや致し方ないことだよ。そういうご時世だってことさ・・・・」
三笠幹事長は、日頃は吸わないタバコを背広のポケットから取り出しながら、悟り切ったような顔で
松島を見つめた。
会派代表の高千穂が入室すると、議員たちはのろのろと自分の席へ戻っていき、室内は
ぴんと張り詰めた空気が漂う中、しんと静まり返った。
「それでは、昨日の会議に引続き我が第3新東京市の抱える財政問題の抜本的解決策について
ご審議頂きたいと思います。昨日、八雲君から提議された国際連合特務機関NERVへの
財政支援要請について、ご異議のある方はご発言下さい」
高千穂の言葉が終わらないうちに、高橋はすっと手を挙げて立ち上がった。
「私も、NERVから資金を引き出すという方針には賛成です」
八雲はもちろんのこと、出席していた議員たちは、呆気に取られて高橋を見つめた。
高千穂をはじめとして、執行部の面々も血の気の引いた顔で高橋を見つめている。
「寝返ったらしいな」
「ああ、勝ち馬に乗るつもりか。今更、惨めなことをする」
議員たちの私語が広がろうとしたとき、高橋は満を持して切り出した。
「しかしながら、私はNERVに膝を屈して金を出してもらう必要など無い、と申し上げたいのです。
我々は、NERVに資金を供出させる正当な権利を有しているからであります」
「そんなこと、できるはずがない! NERVは慈善団体じゃないんだぞ!」
八雲の取り巻きから、野次が飛ばされるが、高橋は一向に気にしない。
「NERVは、確かに、今、市民の間では人気が高まりつつありますが、だからと言って、
彼らがこれまでにしてきたこと、そして、彼らがこれからしようとしているかもしれないことが
全て正当化されるわけではありません。誤りは誤りとして、正さなければなりません。
そんな大事な局面で、NERVに膝を屈して資金支援を頼むなど、路傍の物乞いと同じであり、
NERVの職務を監視する市議会としては、決して許されてはならないものであります。」
高橋は、ここでちらりと八雲に視線を移した。
八雲は、口をへの字に曲げ、明らかに頬を紅潮させて、高橋を睨み返した。
「ここに一枚の書類があります。みなさん、お読み下さい」
高橋は、党の事務員たちに目配せをすると、持ってきた紙袋の中から、書類のコピーの束を
取り出すと、彼らに渡して議員たちに配らせ始めた。
最初に手渡された執行部の議員たちの顔に、驚愕と、そして笑顔が広がっていく。
反対に、八雲はコピーを一瞥すると、顔を歪め、唇を噛み締めるとコピーを二つ折りにした。
コピーを握り締める手に力が込められているため、コピーは指のところでひしゃげている。
「これは、2005年、つまり第二次遷都計画が公表されたとき、今後のNERVへの公共サービス提供と
その適正な負担のあり方について、市とNERVが交わした覚書です。今更説明する必要もないかもしれませんが、
ここには、「固定資産税等の地方税は、国際機関に対する課税取扱いにかかる国際的慣行に則り、
これを課税しないものとする。市水道局の提供する給水事業については、受益者負担の原則に従って、
他の利用者と同等の料金体系に則った負担を、NERVは負うものとする。但し、市街地整備計画が進行し、
利用者数の規模が概ね確定し、水道料金体系が適正な水準に安定的に設定されるまでは、市はNERVに対して
水道利用量に対する費用負担を求めない」と書かれてあります。現在、市はNERVに水道料金の支払いを
求めていませんが、これは、この「但し書き」が根拠となっているんです。既に水道料金はここ2年間、
動かされておらず、利用者数も急激に変動する状況には立ち至っておりません。従って、今こそ、NERVに
水道料金の支払いを求めるべき時期と思います。私が水道局に照会したところ、NERVの
水道使用量は、ジオ・フロントで何をやっているのか知りませんが、極めて膨大なものとなっております。
私の試算では、NERVが負担すべき水道料金は、市財政を破綻から救っても、なお余りある金額です。
ゆえに私は、NERVへの水道料金請求を開始するよう提案します」
高橋は一気に話し終えると、室内をぐるりと睨み渡して、ゆっくりと席に腰を下ろした。
高橋の気迫に押されて、室内には声も無い。
ようやく我に返ったように、高千穂代表が慌てて議事を進めた。
「他にご意見はありませんか?」
さすがに、このような爆弾発言の後に、手を挙げるものは現れない。
「それでは、八雲君から提案された市債発行および国際連合特務機関への引受け要請、また高橋君から
提案された同じく特務機関NERVへの水道料金請求につき、採決をとりたいと思います。まず、
八雲君の提案に賛成の諸君の起立を求めます」
八雲は内心は焦っていたが、表情には表さず、胸を張って立ち上がった。
追随者は、極めて少数だった。
八雲は、多少驚いた様子で辺りを見回したが、賛同者がそれ以上増えないのを悟って、天を仰いだ。
「ご着席なさって結構です。それでは、高橋君の提案に賛成の諸君の起立を求めます」
これまで八雲サイドとみられていた議員たちまでも、起立していた。
(そうか・・・・ここで敢えて執行部に刃向かえば、地元への公共工事配分を減らされると判断した
わけか・・・・現執行部が勝つとみて、勝ち馬に乗ったということか・・・・・相変わらず、変わり身の
早い方々だな・・・・NERVからの歳入で潤った市財政から、おこぼれを頂戴しようっていう寸法か・・・・)
高橋は思わず苦笑すると、再び辺りを見回した。
ふと視線の合った高千穂は、にっこりと微笑むとうなづいてみせた。
「賛成多数。よって、高橋君からの提案を採択いたします」
高橋は四方に向かって深々と一礼すると、ゆっくりと椅子に座った。
「本日予定されておりました議事はすべて終了しました。これにて会議を散会します」
高千穂の声が響くと、議員たちはざわさわと立ち上がり、三々五々、部屋から出て行き始めた。
「やったな! 心配させやがって!」
高橋は、後ろから激しく肩を叩かれて、慌てて振り向いた。
松島が満面に笑みを湛えて立っていた。
「今回ばかりは、駄目かと思いましたよ、私も・・・・取り敢えず一安心ってとこですかね・・・」
高橋はすっかりリラックスした表情で、松島に笑ってみせた。
「ったく、事前に筋書きを教えておいてくれりゃあ、こんなに心配しなかったのに!」
松島は、わざと恨みがましいような顔つきをしてみせると、破顔一笑した。
「あっ、すみません。でも、こういうことは、どっから洩れるかわからないんで・・・・・
党職員の中に、NERVの息のかかったものがいないとも限りませんし・・・・」
高橋は、すまなそうな顔で松島に頭を下げると、打って変わってニヤリと笑った。
「久しぶりに、一杯どうです? 最近、行ってないじゃないですか?」
「そうだねぇ。じゃ、三笠さんなんかも誘って、ひとつぱあっと行くかな。慰労会という名目で!」
松島は一段と嬉しそうな顔になると、執行部の議員たちに向かって手招きをした。
そんな騒ぎを横目で睨みながら、八雲は僅かに肩を落として、憮然とした表情で会議室を後にした。
昨日とは一転して、付き従う者も少ないままで。
(・・・・高橋・・・・いつも、わしの前に立ちはだかる男・・・・今にまとめて礼はさせてもらうぞ・・・・
・・・・・光を浴びる者は、ただひとりしかいないのだ・・・・・)
明るい陽射しが眩しい廊下を光に包まれながら歩く八雲の右手が、強く強く握り締められた。
つづく
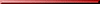
「小説のありか」に戻るには、この  を押してください。
を押してください。