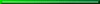
1時間目が終わると、早速、シンジの周りにはクラスメートが集まってきた。
毎週のように転校生が来るとはいえ、転校生は彼らにとって好奇心の対象なのである。
「前の学校はどこ」、「趣味は何」、「どこに住んでいるの」といった質問に、シンジは少しためらいがちに答えている。
「第2新東京市から来たんだ。趣味は・・・・これといって・・・・。あ、チェロを少し・・・その、あんまり
うまくないけど。今住んでいるところは、新駒沢」
リエは、その話の輪には加わらなかった。
(また、繰り返されるのね・・・・)
3時間目の休み時間、シンジは一人でSDATをヘッドホンで聞いていた。
昼休み。リエはリョウコと机をくっつけて自分が作ってきた弁当を食べようとしていた。
玉子焼き、から揚げといったものが中心である。新小田原の名産である、かまぼこといった練製品は、
この気候では「足が早い」ので、食中毒を防ぐため、弁当には入れないようにしている。
セカンド・インパクト以来、この国では老人と子供を中心に食中毒が増えていた。
無論、医療技術の進歩もあって、さすがに致命的なことにはなりにくいが、抗生物質に対する耐性を持った菌が
現れてきたこともあって、やはり油断はできない。
リエは、ちらっと自分の前の席の少年の背中に視線を向けた。
シンジは購買部で買ってきたパンを黙々と食べている。彼の周りには、もう、誰もいない。
「やっばり一人になっちゃったね」
「え?」
「碇君のことよ。」
「ああ、そうね。自分たちの好奇心が満たされると、みんな離れていっちゃうのよね。
結局、自分から友達を作らないと、いつのまにか一人になってしまうわね。そう、あの子のときのように・・・。」
リョウコは視線を窓の傍の席に座っている少女に向けた。
その少女は、コンビニで買ってきた小さなパンを食べている。彼女の周りにも、誰もいない。
「あのね、リョウコ。さっきから考えてたんだけど、碇君っておとなしそうでしょ。クラスになじむの、時間
かかると思うのよ。もしリョウコさえよかったら、碇君と一緒にお昼ご飯食べるようにしてあげたいんだけど・・・」
「あたしは別にいいわよ。席も近いことだし・・・。でも、珍しいね。リエがそういう行動に出るって・・・」
「誰かが孤立している姿なんて、あんまり見たくないのよ。ひとりは・・・・やっぱり寂しいもの・・・・」
リエは少し俯き加減でそう囁くと、シンジに声をかけた。
「碇君。あの、良かったら、一緒に食べない?」
「え? あの・・・僕も混ぜてくれるの?・・・・僕なんかが割り込んでもいいの?・・・なんで?・・・・
よく知らない転校生なのに・・・・ 」
(僕のことを気遣ってくれる。何で? 初めて会ったばかりなのに。縁もゆかりもない人たちなのに。誰かに
そうしろって言われたわけでもないのに・・・・)
「一人で食べるパンっておいしい?」
「そんなこと・・・ないよ。」
「じゃ、一緒に食べようよ。碇君が一人でしょんぼり食べてるから、リエが心配してるでしょ」
「ちょ、ちょっと、リョウコ!! そういうことじゃなくて、あたしは、ただ・・・・ひとりっていやなの。
あたしには学校ではリョウコがいるけど、家ではずっと・・・・。もう、やめましょ、こんな話」
「碇君がゴタク並べてさっさと加わらないから、リエが暗くなっちゃったでしょうが!!」
「あ、ごめん・・・・。あの、ひとつ・・・・聞いていいかな?・・・その、君たちの名前・・・・」
「あっ、そうね。私たちは碇君のこと知ってても、碇君はあたしたちのこと知らないもんね。
あたしは明石リョウコ。新根津の和菓子屋の看板娘よ。こっちは高橋リエちゃん。新駒沢に住んでるのよ」
「新駒沢? じゃ、僕と一緒だね。新駒沢のどの辺なの?」
「坂道を上がっていったところ。碇君は?」
「僕は、コンフォート17っていうマンションに住んでるんだ。」
「あ、それ、うちのすぐ近くよ。でも、あのマンションは・・・・・」
リエは急に声を潜めた。
「もしかして碇君も、NERVの関係者なの?」
「・・・・・なんで?」
「あのマンション、NERVが棟全体を一括借り上げしてるの。何でもセキュリティ上の必要からなんだって」
「・・・・父さんが・・・・勤めてるんだ・・・・」
(父さん・・・か。・・・向こうは、僕のことを息子だと思っているんだろうか・・・・)
「そう・・・・。あたしのこと、あんまりNERVでは話さないでね。うちのお父さん、NERVとはあんまり
仲よくないみたいなの。NERVは結構無茶なことやるし、それを秘密主義で押し通そうとするから、議会の人たちとは
必ずしもうまくいっているわけじゃないの。”超法規的権限”を盾にして、市民にいろいろ負担を強いる場合は、とくにね」
「よく、知っているんだね。」
リエは少し俯いて答えた。それが苦痛であるかのように。
「・・・父は市議なの。この第3新東京市の・・・・・。」
放課後。2年A組の生徒たちは帰り支度をはじめていた。
「いつもリョウコと途中まで一緒だけど、碇君もうちの近所だから、誘って帰ろうかな」
リエが声をかけようとした瞬間、シンジはすっと立ち上がった。そして真っ直ぐ窓際に歩いていった。
「あ、綾波も同じクラスなんだね。よろしく」
少女は、無言のまま、澄んだ紅い瞳でシンジを見つめる。
「来たばかりでわからないことが多いから、いろいろ教えてくれるかな?」
「・・・・・命令があればそうするわ・・・・」
「そ、そう・・・・・。き、今日はNERVに行くんだったよね、確か?」
「・・・・守秘義務の説明、受けなかったの?・・・・」
「あ、そ、そうだね。ごめん」
「・・・・先、行くから・・・」
綾波レイはいつもの無表情のまま、シンジをその場に残して教室を出ていった。
教室は水を打ったように静まり返っていた。
質問攻めは終わったけれど、まだ動き回るだけでも周囲の関心を呼ぶ転校生が、
よりによって、あの綾波レイと話したのだ。あの、誰とも話さない、蒼い髪の少女と。
レイの周りには誰もいなかったし、シンジもレイも声は大きくないので、クラスメートには会話の内容は聞こえない。
たちまちシンジは再びクラスメートに取り囲まれかけたが、彼は硬い表情のまま自席に戻ると、足を早めて
教室から出ていった。
45分後、リエはリョウコと新市ヶ谷のハンバーガーショップにいた。
ここは第壱中学の生徒はほとんど来ないので、彼女たちが落ち着いて話をするときによく使う場所である。
「碇君、綾波さんと知り会いだったんだね」
「うん。驚いたね。」
「ということは、綾波さんもNERV関係者ってこと?」
「そういうことになるわね。家の人がNERVに勤めているのかしら?」
「そう言えば、綾波さんってどこに住んでいるの?」
「さあ・・・。今まで気に留めたこともなかったから・・・・。家に帰って住所録を見てみるわね」
「学校も休みがちだし、たまに学校に来ても、黙って本読んでるか、外見てるだけだもんね。
いつも無表情で、必要なこと以外は全く話さないし、こっちから話し掛けても”そう”とか”じゃ、そうすれば”とか
言われちゃうと話が続かないのよね」
「あたし、この間、綾波さんの傍を通ったとき、どんな本読んでるのか、ちょっと覗いてみたの。
そしたらね、”遺伝子工学の基礎”っていう本だったの。びっくりしちゃった」
「・・・・・将来、理系の学部に進むつもりかしら?」
「さあ・・・。とにかく何にも話してくれないもの・・・」
「せっかく話し掛けてきた碇君にも、いつもみたいに仏頂面で答えていたわね」
「リョウコ、仏頂面なんて言ったら悪いわよ。もう本当に口が悪いんだから。うちのお父さんみたいよ。」
「こうして改めて考えてみると、綾波さんって、謎の多い子よね。なんか、あたし、興味が湧いてきたわ」
「いろいろ調べまわるのは、だめよ。人には誰だって知られたくない秘密はあるんだから・・・。
その秘密を守るために心の中に砦を築いているのよ。あたしたちには、そんなに大きな秘密はないから、
城壁が低くて簡単に他人と打ち解けられるけど、城壁を高くして閉じこもらざるをえない人だっているのよ・・・」
「わかってるわよ。あの子が決して悪い人じゃないってことは、あの澄んだ眼をみればわかるわ。別に陥れたり、
吹聴したりするつもりはないのよ。あたしは、ただ、事実を知りたいだけ」
「でもね、仮にあの子がNERV関係者だとすると、厄介なことに巻き込まれるかもしれないわよ・・・・」
「大丈夫だって。あんまり深入りしないから。」
いつもように眼を輝かせ、胸を張るリョウコをリエは心配そうにみつめていた。
その夜、リエは新駒沢の自宅で夕食後にぼんやりとテレビドラマ「天使の微笑み」を見ていた。
同時刻、リョウコは新根津の自宅兼店舗で、落雁をかじりながら「金沢の和菓子」という本を読んでいた。
ヒカリは、もう明日のお弁当の材料の仕込みにかかっている。知らず知らずのうちに鼻歌を口ずさんでいる。
トウジは、箪笥の引出しを開けて、明日学校に来ていくジャージを選んでいる。が、他人には全部、同じ製品にしか
みえない。「うーん、こっちのは編みがちっと荒いしな、そっちのは生地が1ミリ薄いやろ。甲乙つけがたいわい」
ケンスケは、パソコンに向かってデジカメで撮った映像を再生して眺めている。「もう少し右側から撮れば良かったな。
ここはもう少し露出を・・・。うーん、まだまだ道は遠いな・・・・」
高橋は、市議会の散会後、三笠幹事長、松島幹事長代理、八雲議員、磐手議員とともに新赤坂の活魚料理店の座敷にいる。
「いや、幹事長が眼をつけただけの店ではありますね。このアワビのステーキなんて絶品ですよ。」
魚に目がない松島は感嘆の声を上げている。一方、三笠は目をつむってイカの刺し身を堪能している。
磐手はカツオのタタキに箸を伸ばし、その傍らで、高橋は自分より年長の八雲に酌をしている。
「そういえば、高橋君。例のNERVの件だがね、どうやら奴ら、なんかでかいものをこしらえているみたいだぞ」
「でかいもの? 巨大戦車かなんかですか?」
「詳しいことはわからんのだが、出入りの業者がNERVのトイレで個室に入っていたとき、NERVの職員が外で
”E計画”とか”予算1兆5000億円”とか話しているのを聞いたそうだ。」
「八雲さんは相変わらず建設業者に太いパイプをお持ちですね。それにしても、E計画、なんか気にかかりますね」
「ああ、でも、うかつなことはできんぞ。奴ら、自前の諜報部を持っているらしいからな。内務省の万田さんが
嘆いていたよ。日本の中にもう一つの国があるみたいだ、ってね」
「国会でも、わが自由改進党が与党として国政に参画しているのに、NERVには何ら手を出せないからね。
予算委員会で取り上げようとすると、必ずどこからか横槍が入って沙汰やみになってしまうらしい」
「大方、汚職とか癒着絡みの情報をちらつかせて黙らせるんだろうな。国政レベルでは、そういった問題を
抱えていないのは一部の旧左翼政党だけだからね。だいたい、選挙は党営になったとは言え、事務所の維持費、
通信費、足代、アルバイトの人件費とか、まだ議員の個人負担となる部分が大きすぎるんだよ。とくに小選挙区はね」
突然、各家庭で放映されていたテレビ番組が中断され、緊張した面持ちのアナウンサーの顔に切り替わった。
「只今、第三新東京市全域に特別非常事態宣言が出されました。市民の皆さんは速やかにお近くのシェルターに
避難してください。繰り返します・・・・・」
つづく
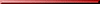
第5話に進むには、この を押してください。
を押してください。
「小説のありか」に戻るには、この  を押してください。
を押してください。
![]()
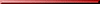
 を押してください。
を押してください。