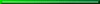
高橋はリエが笑うところを暫くみていなかったことに気がついた。
(今は第三新東京市にとって大事なときなんだ。遅延した都市計画の推進、財源問題、市の発展とともに出てきた
少年非行や治安の悪化、開発業者や市の規制を受けるさまざまな事業者と市・議会関係者の癒着、そして何よりも
難しいのはあの特務機関NERVとの関係だ・・・・。リエ、もう少し、もう少しだけ辛抱してくれ・・・)
高橋は心の中でそう呟くと、目を伏せて少しだけ俯いた。
(自分のすぐ近くにいる人も幸せにできない俺が、たくさんの市民を幸せにすることなんかできるんだろうか・・・・)
父親の変化にリエはすぐに気がついた
「お父さん、どうしたの?・・・・また、お母さんのこと?・・・・」
「いや、その、リエにもいろいろ心配かけてすまないなって・・・・・やっぱり寂しいだろ、ひとりでいるのは?」
「別に大丈夫よ。それにリョウコ達と遊んだりしてるから、寂しくなんかないよ」
「そう・・か。・・・・ああ、そうだ。リエのカードにお小遣いを入金しておいたから、友達と遊ぶときに
使うといいよ。でも、あんまり無駄使いはするなよ」
「ありがとう!! 今月、少し使いすぎちゃった。臨時収入、ありがたいわ、感謝、感謝!!」
無邪気におどけて笑ってみせるリエの顔を高橋はまっすぐに見られなかった。
(私には親らしいことはそんなことぐらいしかしてやれないから・・・)
庭に面したガラス窓を何かが引っ掻く音で、高橋は我に返った。
「こんな時間に一体なんだろう?」
「あ、ルビーがきたんだ」
「ルビー?」
「ほら、そこの不動産屋さんで飼っているシャム猫なの。時々、遊びにくるんで、煮干しとかあげてるのよ。
さっきも来たのに。ご飯のにおいを嗅ぎ付けてきたのかしら?」
リエが窓を開けると、シャム猫がゆるりと入ってきた。リエの傍にいる見慣れない人物に気づいて、じっと見つめている。
(さっきリエが話し掛けていた猫か・・・。石河不動産ではいつのまに猫を飼ったんだろう?)
高橋はルビーを撫でる娘の姿を微笑んで見つめていた。
「それじゃ、行ってくるよ。今日も遅くなるから、戸締まりに気をつけろよ」
高橋はいつものとおり議会に向かおうとしていた。
が、ふと思い出して付け加えた。
「ルビーによろしくな」
「うん、よく言っとくわ。怪しい人じゃないよって」
リエはにっこりと笑いながら、父親の後ろ姿を見送った。
いつものような一日が始まろうとしていた。
リエは戸締まりを確かめると家を出た。
新駒沢駅から第三新東京市環状線5号線に乗って、街を南下する。
市の中央部の新四谷駅で降りて市立第壱中学に向かう。
父親がいるはずの市議会はもう少し北の新代々木駅近くにある。以前、彼は自家用車で出勤していたが、最近は渋滞が
ひどいので、電車を利用している。当初は混雑した電車に乗るのはかつての役人時代を思い起こすので抵抗があったが、
電車の方が市民の本音でのいろいろな会話を耳にできるので、市政運営に役立つことに気づき始めたようだ。
リエは同じ学校の生徒たちに混じって歩いていった。
整った端正な顔立ちであるが、とくに美人というわけでもない。集団の中に紛れ込んでしまえば、友達でなければ
みつけだすのは容易ではないだろう。
「おはよう、リエ」
「あ、おはよう、ヒカリ」
同じクラスの洞木ヒカリが後ろから追いついてきて声をかけた。親友というほどでもないが、仲が悪いわけでもない。
ヒカリの父親は市役所の文教部に勤めており、リエの父親とは永年のつきあいがある。時々、数人で飲みに行ったり
しているらしい。
「今日は遅いのね。どうしたの、珍しいわね?」
「お弁当に手をかけすぎて遅れちゃったの。お父さんや妹が毎日食べるものだから、飽きがこないようにしなくちゃ
いけないのよ。結構、いろいろ大変なの。」
「でも食べてくれる人がいるのは羨ましいわ」
「お父さんがいるじゃない」
「最近、忙しくて外食ばかりなの。朝ご飯は食べていくけど、お昼も会食が殆どだし・・・」
「じゃ、リエの夕食はどうしてるの?」
「・・・・・一人で作って一人で食べてる・・・・」
「そうなの・・・・・。ねぇ、リエは和食作るの得意だったよね。治部煮って作ったことある?」
「鴨か鶏肉に小麦粉をつけてお麩と一緒に煮て、わさびを入れて食べる、あれでしょ。作ったことあるけど、とっても
手間がかかるのよ」
「そうなの? この間、デパートのお惣菜店で買ってきたんだけど、とてもおいしかったから自分でもつくってみようと
思ったのに・・・。そうだ。今度、作り方教えてくれない?」
「ええ、いいわよ」
「じゃ、来週の金曜日の放課後、リエの家に行ってもいい? その日、うちは父とお姉ちゃんと妹が外食の予定なの。
だから夕食の支度しなくても大丈夫なのよ。リエの家で、作った治部煮を食べていってもいい?」
「うん。とっても楽しみにしてるわ。」
ヒカリは、治部煮がリエの父親の好物であることも、そしてかなり時間のかかる料理であることも、ずっと以前に
自分の父親から聞いて知っていた。
リエとヒカリは一緒に2年A組の教室に入った。
「おはよう」
「おはようさん。今日もええ天気やな」
「やぁ、おはよう」
黒いジャージ姿の少年とデジタルカメラのレンズを丁寧に磨いていたメガネの少年が挨拶を返した。
「鈴原、週番でしょ。花瓶のお水替えた?」
「あっ、いかん、すっかり忘れとった」
「もうー、また相田君と馬鹿なこと話してたんでしょ? ちゃんと週番の仕事しないとだめよ!!」
「そないにポンポン言わんでも・・・。委員長にはかなわんな。あっ、こら、ケンスケ、何撮っとるんや!!」
「気にするなよ、トウジ。こういう何気ない光景が大作のヒントになるんだ。今度、高橋も撮ってあげるよ」
相田ケンスケは妖しくメガネを光らせて答えた。
「あ、あたし? ま、また今度ね」
リエは自分に矛先が向いてきたので、そそくさと話を切り上げて、その場を離れた。
(相田君も悪い人じゃないんだけどね。撮った写真、どんなふうに使うかわからないじゃない。男の子達に闇で
売ってるって噂も聞くし・・・・)
リエは、教室の前から3番目、廊下側から2列目の、自分の席につくと、1時間目の数学の教科書を鞄から出し、
朝の陽光に包まれた教室をゆっくりと見回した。
トウジとケンスケはまだ話しており、時々、トウジがのけぞったりしている。何か痛いところを指摘されたようだ。
彼らは席が隣同士なのでいつも話しているし、休み時間や放課後も行動をともにしている。二人の席はともに
教室の後ろから2番目で、ケンスケは窓側から2列目、トウジは同じく3列目。教師の目が届きにくいところである。
ヒカリの席は最も廊下に近い列の後ろから2番目。近くの席の女の子と話している。昨晩のテレビ番組のことだろうか。
リエの隣の席の主はまだ来ていない。
(また、遅刻かしら・・・。リョウコ、朝、弱いからなあ。家が近かったら、毎朝、起こしに行ってあげるのに・・・)
ゆっくりと教室を見回していたリエの視線は、最も窓側の列の後ろから2番目の少女のところで止まった。
「・・・あの子、また外を見てるのね・・・」
不意に、その少女は黒板の方を向いた。そして、自分を見ている少女に気がつくと、紅の瞳でじっと見つめた。
(怒ったのかしら? そうでもなさそうね・・・)
彼女が転校してきてから7ヶ月。その間にクラス替えも行われないまま一緒に進級したが、彼女が誰かと私語を
交わしている姿をリエは見たことがない。
光の加減で蒼くみえることもあるプラチナブロンドの髪、整った目鼻立ち、人の心の奥底まで見透すような澄んだ
紅い瞳。
最初はクラスメートの話題を一身に集めた彼女も、あまりの寡黙さゆえに今ではほとんど忘れられた存在となっていた。
「ヒトを容易に近づけない神秘的な雰囲気というか、神聖な感じがするのよね、あの子・・・」
隣席の少女の呟きに、リエは振り返った。
「リョウコ、間に合ったんだ」
「うん、なんとかね。毎朝、大変よ。学校が10時から始まるんならいいのにぃ・・・」
「それじゃ、帰りが夜になっちゃうでしょ」
「そうよねぇ。あーっ、低血圧が憎いわぁ」
リエは拳を固めて眉をひそめる親友の姿に、くすっと微笑った。
「あー、今日はですね、また転校生が入りますから、最初に紹介しておきます」と担任の数学教師が切り出した。
「また転校生が来るの? 最近、ほんとに多いわね」
「この街も来年には首都になるからね。いろんな会社が進出してきてるのよ。地方の県の出先機関も増えているみたい
だし・・・」
「さすが、市議の娘! よく把握してるぅ」
「みんな静かにして!!」
ヒカリの声がざわめき始めた教室に響く。
「では、入りなさい。あ、そこで自己紹介をしてください」
「碇・・・碇シンジ・・・です。あの・・・よろしくお願いします・・・・」
リョウコがリエの肘を突つき、小声で囁く。
「なんか気の弱そうな男の子ねぇ。色も白いし、線が細いって感じ・・・」
「リョウコ、そんなこと言っちゃだめよ。本人が気にしていることかもしれないじゃないの」
「えー、碇君の席は、そうですね、そこの前から2番目の空いている2つの席のうち、廊下側の方にしますね」
「・・・・・・・・・その頃、私は根府川に住んでいましてね。今では海の底に沈んでしまいましたが・・・」
いつものように回想モードに入ってしまった教師の話を聞きながら、リエは自分のすぐ前にある少年の背中を見つめていた。
(リョウコの言う通り、この子、ナイーブそうね。クラスになじめるかしら・・・。できるだけ親切にしてあげようっと)
つづく
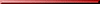
第4話に進むには、この を押してください。
を押してください。
「小説のありか」に戻るには、この  を押してください。
を押してください。
![]()
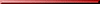
 を押してください。
を押してください。