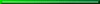
シンジは高橋の口調がやや固いものに変わったことに気がついた。
「あの・・・父を知っているんですか?」
「仕事上、関係があるんでね。好むと好まざるとにかかわらず・・・」
「仕事・・・ですか。・・・父は一体どんな仕事をしているんですか? 僕は、”人類を救うための大切な仕事”
としか教えられていないんです。・・・今度も突然、理由もいわれずに、ここに呼び付けられて・・・」
「人類を救うための大切な仕事、か・・・。何度も聞いた言葉だね。NERVの奴らは、みんなそう言うんだ。
部外者が彼らの職務について尋ねたときにはね。私は第三新東京市の市会議員をやっているが、その私ですら、
本当のところ、彼らが何をやっているのかは殆ど知らないんだよ。」
「そう・・・ですか・・・。」
彼らの話はそこでふっと途切れてしまった。人気のない新箱根湯本駅前に、ヒグラシの声だけが響く。
彼らが黙ったまま、住宅地に続く上り坂に差し掛かったとき、自動車のブレーキ音が後方で響いた。
振り返った二人の目には、青い車から降りてくる髪の長い女性の姿が映った。
「碇シンジ君、よね?」
「あ、はい。あの、もしかして、葛城さんですか?」
「ええ。非常事態宣言に巻き込まれちゃって迎えに行くのが遅れちゃったのよ。ごめんごめん」
葛城ミサトは、ぺろっと舌を出して頭をかいて笑った。
が、高橋に視線を移すと、その表情は瞬時に消えた。
「あなたは? なんでシンジ君と一緒にいるの?」
ミサトの問責するような口調を聞きながら、高橋は
「まただ」と思った。
「NERVの奴らが部外者と接する時は、いつもこうだ。怪しい者を見る目つきで、命令口調で問い掛ける・・・」
ただ、高橋は、先ほどのシンジとミサトの会話から、ミサトには悪い印象は持たなかった。
「本当は、この娘も快活な性格なんだろうな。今は、それをNERV職員の仮面で包んでいるんだ・・・」
彼は、ふと、その仮面を外してやりたいという衝動にかられた。もともと、彼は権威というものが
嫌いだった。その素質は、おそらく彼の江戸っ子としての遺伝子のなせるものかもしれない。
「私の顔をお忘れですか? NERV作戦部長、葛城一尉殿」
ミサトの表情が険しくなった。相手の心の中まで見通そうとするかのように高橋の眼をまっすぐ睨み付けている。
「私はあなたのことを知らないから、こうしてお尋ねしているんです。」
「先月、あなたのところに自治会の連中が苦情を言いに来たはずです。あなたが、ゴミ収集日の前夜にゴミを
捨てるんで、猫がゴミを漁ってあたりを汚してしまうから、やめてほしいって」
シンジは、ミサトの顔を「そんなことしてるんですか?」というかのように覗き込んだ。
「し、仕方ないのよ。当直とかあって忙しいから、ゴミを朝、捨てられないときもあるのよ」
「その連中に付き添っていたのが、市会議員の私です。連中、NERVの人を相手に文句言いに行くのはやっぱり
怖いとみえて、私に、一緒についてきてくれって頼み込んできたんですよ。」
「あぁ、あの時の市会議員さんね。覗きっていう珍しい名前だったんだ覚えているわ。」
「・・・・のぞみ、と読みます。・・・とにかく、これで、私が怪しい者じゃないことはお分かりでしょう」
「ええ・・・。でも、なぜシェルターに入らなかったんですか?」
ミサトの表情は先ほどよりは和らいでいたが、やはり目は笑っていなかった。
「やれやれ。私は、”NERV幹部の師弟に接触を図ろうとした要注意人物”、か・・・。まったく、とんでもない
奴に関わり合いになっちまったもんだ。よりによって、あいつの息子とはね・・・」
高橋は心の中で辟易しながら
「シェルターがどこにあるかわからないんですよ。それで捜し歩いていて、シンジ君と出くわしたっていうわけです。
とにかく、もうシンジ君はあなたにお任せしますよ。私は、どっかのシェルターを見つけて潜り込みますから・・・」
と言うと、駅の方に戻っていきかけた。
「あ、そうそう葛城さん。私の自宅は、あなたの、コンフォートっていうマンションのすぐ近くなんですよ。何か
困ったこととかあったら、気軽にお立ち寄りください。まあ、NERV勤めのあなたには、あまりそうした局面は
ないとは思いますがね。では、失礼しますよ」
高橋は、どことなく愛嬌があって憎めない年下の娘と気の弱そうな少年に向かって、いつもの癖で深深とお辞儀をした。
今月に入って3度目の特別非常事態宣言は3時間後に解除された。
高橋は、早雲寺の近くでやっとシェルターをみつけて潜り込んでいたが、やっと外に出てこれた。
そのまま彼は駅前に戻り、「早雲山運送」という看板がかかっているビルに入った。。
「こんちは。陸奥社長いるかい?」
「ええ。さっきシェルターから戻って、今は社長室でテレビみてますよ」
高橋は事務室を突っ切って、一番奥の社長室のドアを勢いよく開けた。
「誰だよ? ノックぐらいしろよ。ああ、高ちゃんか。驚かすなよ。どうした?」
「今日は新箱根湯本で市内の歯科医師会の会合があるんで顔を出す予定だったんだけど、さっきの騒ぎに巻き込まれ
ちまったんだ。まいったよ。あの碇の息子とも関わり合いになっちまったし・・・」
「ここんとこ、しょっちゅう宣言が発令されるね。道路が封鎖されるんで困るね。一体なんなんだよ、あれは」
「第三新東京市は国連直属の特務機関が置かれている要塞都市だぜ。そのうえ、もうすぐ遷都で日本の首都にもなる
予定だろ。近隣諸国としては、この街がどんな防空システムを持っているのか、自国の安全保障上、気になるところだよ」
「14年前みたいにならないといいがね・・・」
「ああ。もう、あんなことはたくさんだ。思い出したくもないよ。」
「お互い、あのあと、苦労したもんなぁ」
「俺よりも陸奥やんの方が苦労しただろ。俺なんか、あの時、出張先から松本市の臨時政府にすぐ合流できたからね」
「俺は宇都宮に配送に行っていたおかげで生き残っちまったよ」
「あんときは、もう世界各地で戦争が始まっていたけど、日本は非武装中立でずっとやってきたから、誰も東京に
新型爆弾が落とされるなんて思いもしなかったよな・・・。俺も陸奥やんが配送に遠出してたなんて全然知らなかった
から、しばらくして松本でばったり出会ったとき、幽霊かと思って思わず足元みちゃったよ」
「あのときは俺も驚いたよ。宇都宮からなんとかもどってきたけど、高円寺は何も残ってなかったから、近所の奴らは
みんなあの世に行っちまったと思ってたよ。それが、だよ。何とか松本まで逃げてきて、やっと運送屋を再開したとき、
届出のために交通省に行ったら、ロビーで高ちゃんに呼び止められてさ・・・」
「ああ、高円寺、何も残らなかったもんな・・・。うちの酒屋も、じーさんやおやじごとなくなっちまってたよ。」
「俺、がきの頃、高ちゃんのじーさんに可愛がってもらったよ。今でも覚えてる」
「俺には優しかったけど、おやじには結構、厳しく商売を叩き込んでたよ。”うちは権現様と一緒に三河から江戸に出て
きて以来4百年間、酒屋を続けているんだ。ご先祖さんの顔に泥塗るような商いをしちゃぁいけねえ”ってね。
そのじーさんも、いまじゃご先祖さんの仲間入りだよ」
「いやだね。昔のことを思い出すと、必ず湿っぽい話になる・・・。仕方のないことなのに・・・」
「気晴らしに、近くで晩飯でも食わないか? 今日は会合が流れたんで、晩飯がないんだよ」
「たまにはリエちゃんのところに早く帰ってやれよ。一人で飯食うのって寂しいもんだぞ。”一人で食えば鯛の刺し身でも
まずい”っていうくらいだからな」
「そうするかな。最近、忙しくてゆっくり話す時間もなかったからな・・・。じゃ、今日のところはこれで退散するよ」
高橋は新駒沢駅から暗くなりかけた道を我が家に向かった。誰もいない坂道を途中まで登ったところで、ふと立ち止まって、
振り返った彼の眼には、所々に航空機衝突防止用の赤色灯が点滅する高層ビルが幾つも映った。
「本当にあんなものが役に立つ日が来るんだろうか? その時には、ここの市民はどうなってしまうんだろうか?」
民間の高層ビルに偽装された兵装ビルの配置は、市の関係者の中でも、ごく限られた者しか知らない。
高橋は、昨年の定例議会で建設委員長を勤めたこともあって、内々、兵装ビルの配置を知っている。
しかし、自分を選出してくれた一般市民の殆どは、兵装ビルの存在すら知らない。
「それは幸せなことなんだ。」
彼はそうつぶやくと、再び坂を登り始めた。
自宅の門を入ったとき、彼は庭にシャム猫がいるのに気づいた。
猫好きな高橋は、庭に回って、猫を驚かさないようにそっと近づいていった。
「ルビー」
少女の声が聞こえた。縁側に出て猫を呼んでいるようだ。
「あなたも一人でいるのが寂しいの?」
高橋は暫くその場に立ちすくんでいた。そして、静かに玄関に戻ると、チャイムを鳴らした。
久しぶりに家で夕食を食べたい、という高橋の言葉を聞いて、リエは眼を輝かせた。
そして早速、夕食の支度を始めた。突然のことなので、材料はあまり揃っていないが、
手際よく調理を進めていく。カジキマグロのソテー、インゲンのごま和え、白和えが今日の献立だ。
もともと高橋は旧東京の下町育ちなので、味付けの濃いものや肉が好きだったが、娘が料理を作れるようになってからは、
高血圧気味の高橋の健康に配慮して、和食中心のメニューとなっている。
「俺自身も、20台の前半のように肉に執着するようなことはなくなったな。むしろ最近は、リエの作る薄味の和食が
うまく感じられるようになってきた。年取った証拠かな・・・」
「そうだとすると、ちょっと惜しかったな。セカンド・インパクトさえなかったら、若い頃にもっと肉が食えたのに・・。」
「それでね、リョウコが鈴原に言ってやったの。お風呂の中でもジャージ着てるんじゃないのって。」
食事の間も、リエはずっと喋りつづけている。
そのため食事が全然進まない。
やはり学校のクラスメートの話題が中心である。毎週のように転校生が来るらしい。
リエは何か暖かいもので胸がゆっくりと満たされていくのを感じた。
父と一緒に囲む夕食の食卓は、めったに実現しない、彼女の夢だった。
学校から帰ると黙々と夕食の用意をして、テレビをみながら一人で食事をする、という現実は、
やはり14歳の少女にはつらすぎるものだった。
「お父さんが市議なんかじゃなかったらよかったのに・・・。お母さん・・・・。」
風の強い夜や雨の日の夕方、リエはいつも呟いていた・・・。
つづく
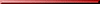
第3話に進むには、この を押してください。
を押してください。
「小説のありか」に戻るには、この  を押してください。
を押してください。
![]()
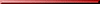
 を押してください。
を押してください。