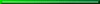
漣屋での会合が終わった後、高橋は早雲山運送に寄ってから第三新東京市に帰ることとなり、加持と橋立はしばらく
早川沿いの道を歩いて酔いを醒ますことにした。
夜もかなり更けてきた道にはせせらぎの音と蛙の声しか響いていない。
「今日は月が出ていないから、暗いですね」
「ああ、そうだな。無明暗夜という感じだな」
「こうして先輩と歩いていると学生時代を思い出しますね」
「第二新東京市での4年間か。夢のように過ぎ去ったな」
「よく一緒に飲んで、終バスがなくなったあと、こうして歩きましたね」
「ああ、あの頃は楽しかったな。明日を思い煩う必要もなかったしな・・・」
「・・・・先輩にずっと聞きたかったことがあるんです」
「どうしたい。急に改まって。なんだい、恋の相談かい?」
「・・・先輩は、なぜ、ゲヒルン、今のNERVを選んだんですか? あの時は交通通信省への内定も取っていた
じゃないですか?」
「そうだったな。あの頃は、交通省が行政改革で情報郵便省と合体したばかりで意気盛んだったからな。俺みたいな
変わり者を採って、組織活性化に使うつもりだったんだろうな。でも、よくよく考えると、俺には官僚は向いてなかった
からやめたのさ」
「先輩、もうそろそろ本当のことを教えてくれてもいいんじゃないですか? もう時効でしょう?」
「何か他に理由があるって言うのかい?」
「・・・あのとき、先輩は人事採用院の試験に合格し、交通通信省への配置が決まって非常に喜んでいました。
しかし、先輩の態度が変わったのは、葛城さんがゲヒルンに就職すると聞いたときでしたね」
「・・・そうだったかな? 近頃、年取ったせいか記憶が曖昧になってね。はははは」
「当時からゲヒルンは水面下ではいろいろな噂の飛び交っている組織でした。もしかして・・・・先輩は葛城さんを
見守るためにゲヒルンに入ったんじゃ・・・・・」
「おいおい、俺と葛城は、もうあの時点では切れてたんだぜ。それは邪推ってもんだ」
加持は立ち止まり、永大橋と書かれた石橋の欄干にもたれると、街路灯の灯りを反射して微かにきらめいてる
早川の水面にぽーん、と小石を投げた。
暗闇の中で、水面に弧が広がっていくのがみえる。
「卒業以来、会っていないんですか、葛城さんと?」
「ああ、全然な。・・・・どうやら嫌われてしまったらしい・・・ははは」
「お似合いだったのに・・・」
「ま、馬には乗ってみろ、人には添ってみろ、って言うからな。近づいてみて、よく分かったんだろうな、俺のことが。
・・・・ところで、俺も君にふたつ聞いておきたいことがあるんだ。いいかな?」
「ええ。でも、先輩に聞かれるようなことなんてあるのかなぁ」
「・・・・はっきり言おう。君はりっちゃんのことを慕っていただろ? なぜ、何も言わずにいたんだ?」
「・・・・加持先輩には隠し事はできませんね。私が赤木さんのことを、その、慕っていたのは事実です。でも・・・」
「でも?」
「赤木さんは研究一途でしたから、こういうことを切り出すのはためらわれて・・・・」
「人生にはいろいろなターニング・ポイントがある。彼女にとって、それは卒業のときだった。君が彼女にこころの
うちを伝えていれば・・・・」
「それで何かが変わった、とでもおっしゃるんですか?」
「それは俺にも断言できないよ。だが、確実に言えることは・・・・」
「・・・・・・」
「・・・・悲しまなかった・・・・だろうな・・・後になって・・・・」
「それはどういうことですか?」
「・・・俺がこれ以上語っても意味はないさ。あとは君が自分で考えることさ。ま、別に考えなくても、今の君には
何の影響もないけどな」
「・・・・考えてみます・・・力のおよぶ限り・・・・」
「ああ、そうするといい。まだ時間は残されている。・・・そんなに多くはないけどな・・・・」
「・・・・やってみます・・・・」
「もうひとつ、聞きたいことがある。君は教授に望まれて研究室に残った。それなのに、なぜ助手を間近にして
市議会事務局なんかに移ったんだ? 先生は、政府の基本政策審議会の委員だし、あのまま残っていれば、
君は経済学会で活躍できることは保証されていた・・・」
「それになんの意味があるんですか? 経済事象を分析して、したり顔で解説してみせて・・・・。それは究極的には
自己満足に過ぎないんじゃないでしょうか? 私は、問題点を知った上で、それを変えていく努力をしたかったんです」
「何かを変えていきたいのなら、役人になるという手段もあっただろう? 今は中途採用もやっているから・・・」
「今の経済問題の多くは、役人の行動原理自体が原因となっているケースも多いんです。私が役人になれば、
やはりそういうものに呑み込まれてしまいます」
「じゃあ、先生の後を継いで審議会の委員になればよかったんじゃないのかい?」
「審議会は、所詮、役人の隠れ蓑に過ぎませんよ。始めに結論ありき、で議論してますから・・・。有権者に選ばれて
いない官僚の行動をチェックすることができるのは、政治家だけです。でも、今は法的にはその力を持っていても、
スタッフが揃っていないから、十分に力を発揮できないんです。だから・・・・」
「だから・・・・自分が議員の補佐をしようと思ったのかい?」
「ええ」
「・・・・世の中はきれいごとだけでは済まない・・・・自分が堕ちたときに苦しむぜ・・・」
「覚悟してます。泥にまみれても、理想は持ち続けるつもりです・・・北極星が動かずに燦然と輝くように・・・」
「・・・・ひとつだけ教えておくよ・・・NERVと衝突するようなことがあったら、内務省を頼るんだな・・・・」
「・・・・先輩・・・・」
「俺は明日、ドイツに戻る。今度来るときには、もう会えないかもしれん。・・・・・無茶、するなよ・・・」
二人の男は黙ったまま、ただ流れ行く水を眺めていた。
高橋は早雲山運送の社長室で陸奥と差し向かいで水割りを飲んでいた。
「突然、呼び出したから、驚いたろ?」
「ああ。それで本当の理由はなんだい?」
「なんだ、わかってたのか?」
「幼なじみに嘘は通じないぜ。たとえ、あの男はうまく欺けてもな」
「そうか。それなら話は早いや。どう思った、あの男のこと?」
「ただ者ではないな。少なくとも「退屈男」ではないことは確かだな」
「やはり、おまえもそう思ったか。・・・今、NERVはてんやわんやのはずだ。そんな時期に休暇とって
のんびりしてるのはやっぱり変だよな」
「それだけじゃない。あいつには「気配」がなさ過ぎるんだよ。何考えているんだか、全くわからない」
「それにしては、いろいろとNERVの内情をしゃべっていたな」
「あいつの言ってたことは多分、みんな本当のことだよ。俺達に自分を信用させようとしているのさ」
「今回の会合なんだけどな、実は橋立が言い出したことなんだよ。あいつが俺に電話してきて、「NERVにいる
先輩が高橋さんのことを心配しているみたいだ。取り敢えず会ってみてやってほしい」って言うもんだから・・・」
「やっぱりそうか。橋立君は純朴すぎるのが欠点だな・・・ま、それが彼の長所でもあるんだけどな・・・」
「高ちゃん、気をつけろよ。NERVが動き出したのかもしれないぜ。おまえさんに限って、スキャンダルは
ないだろうな?」
「スキャンダルがあるくらいだったら、こんなに選挙資金に困ってないよ。おれんところは市民からの寄付金が頼り
だからね。女性問題も、悲しいぐらい、なんにもないからね、はははは」
「そりゃよかったな。でも、注意しろよ。相手はNERVだ。なにを仕掛けてくるか、わからないぞ」
「NERVは市民に選ばれた組織じゃないから、市民に責任を負わなくていいのさ。でも、俺は違う。
市民から未来を託された責任がある。その責任を全うするまでは、俺は死んでも死にきれないよ。
あいつらが市民を足蹴にするのなら、俺は闘わにゃならん。14年前のように市民を巻き添えにすることは許さない」
「おまえが、そこまで覚悟してるなら俺も協力するよ」
「ありがとよ。国政も巻き込んで派手に暴れてみせるけど、もしものときには・・・・」
「おう、心配するな、リエちゃんのことはまかせとけ!! 立派に育ててみせらぁな」
「・・・おい、言っておくけどな、まだ俺はくたばる気はないからな!!」
「いつ、そうなってもいいぜ。俺も娘がほしかったところだからな、あはははははは」
「ひでえやつだな、どうしても俺をくたばらせたいらしいな」
二人の男は、顔を見合わせてひとしきり笑うと、思い出したように、ぬるくなった水割りを飲み干した。
翌朝、市立第壱中学の校門は、登校する生徒でいつものように賑わっていた。
「おはよう、リョウコ!!」
「あ、リエ!! おはよう」
「ねえ、昨日の話、碇君に本当に頼むの?」
「もちろんよ。難しいことは承知の上よ。でも、もしかしたら、ってこともあるじゃない」
「うーん、碇君、困ると思うわよ」
彼女たちが教室に入ると、まだシンジは来ていなかった。
レイは、いつものように頬杖をついて窓の外を眺めている。
「おはよう、綾波さん!!」
レイに話し掛ける者は少ないので、いやでもクラス中の視線が集まる。
レイは頬杖をやめて、彼女たちの顔をみつめた。
(・・・・・高橋さんと明石さん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・私に関心を持っているヒト・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・私と視線を合わせられるヒト・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・命令も受けてないのに私を必要するヒト・・・・・・・・・・・・
・・・・・私を心配する人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・でも・・・・・エヴァ以外の絆はありえない・・・・・・・・・・
・・・・・だから・・・・これは絆じゃ・・・・・ない・・・・・・・・・・
・・・・・これは・・・何?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・絆ではないことを知って、どうするというの?・・・・・・・・・
・・・・・絆じゃなくても・・・・・いいの?・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・わからない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・でも・・・・・・・・・・応えたい・・・・・・・・・・・・・・)
暫くの間、いつもような沈黙が流れた。
予想していたことなので、リエもリョウコも別に驚かない。
やさしい微笑みを残したまま、二人は席に戻るために振り返ろうとした。
・・・レイは・・・・ほんの僅かだが、こく、と肯いた。
クラス中の物音が一瞬、途絶えた。
そして次の瞬間、大きなどよめきが広がった。
「ありがとう!! 綾波さん。応えてくれて、うれしいわ!!」
「・・・・・・挨拶・・・してくれたから・・・・」
レイは、胸の中で暖かい何かが生まれたことに当惑していた。
(・・・・・・・これは・・・何?・・・・・・不快じゃない感じ・・・・
・・・・・・・これで・・・・・・よかったの?・・・・・・・・・・・
・・・・・・・応えて・・・・・・よかったの?・・・・・・・・・・・)
「今度の日曜日の試食会、きっと来てね!! みんな待ってるから!!」
レイは、今度は、さっきより少しだけ大きく、こくん、と肯いた。
何かを確信したかのように・・・・・。
ようやく到着したシンジも、その場面を目にしていた。
「綾波が・・・応えた・・・・初めてだ・・・。僕にも、あんな反応したこと・・ないのに」
シンジは、何か自分が取り残されたような気分で、席に着いた。
(そういえば、昨日、高橋も明石も綾波にべったりだったな。・・・・僕は一人で弁当食べることになったし・・・
忘れられた存在になった・・・かな。・・・・まあ、第二新東京でもそうだったし・・・・いつもこうなるんだ・・・
でも、そのほうが楽でいいや・・・・・煩わしくないから・・・・・・)
「あ、碇君!! 待ってたのよ!!」
「え、僕のことを?」
「ねえ、お願いがあるの。ジオフロントの中、どうなってるのか見てみたいのよ。なんとかならないかしら?」
「・・・・・それは駄目だよ・・・・警備が厳しいからね・・・・」
(なんだ・・・・ジオフロントのことか・・・・・)
「やっぱりだめかぁ。残念ね」
「うーん、実に残念だ。」
「あ、相田君?」
「いや、実は僕も入ったことがないんだ。ああ、秘密要塞への侵入・探査、なんてすばらしい響きなんだ」
「・・・・相田君、相変わらずね・・・・あ、またカメラ持ってきてるの? この前、先生に没収されたばかりじゃないの」
「なんびとたりといえども、報道の自由を侵すことはできないのさ。僕のカメラは、新聞記者のペン、アナウンサーの
マイクとおなじなんだよ。いかなる弾圧にも耐えてみせるさ」
「あのねえ、弾圧って言ってるけど、学校に不要なもの持ってきちゃいけないっていうのは、校則じゃないの!!」
いつのまにか近寄ってきたヒカリが鋭く指摘する。
「あ、委員長、あの、これ、高かったんだ・・・・そのー、見逃してくれないかな・・・ね、お願い」
「もう、しょーがないわね。今度だけは目をつぶってあげるから、もう持ってきちゃだめよ」
「ははー、ありがたきしあわせ。この相田ケンスケ、一生、恩に着ます」
「おまえ、ほんまに調子いいやっちゃな」
彼らの脇を通り抜けようとしたトウジが呆れたように呟く。
が、相変わらず、シンジとは視線を合わせようとしない。
「そういえばさ、さっき、綾波が挨拶らしきことをしただろ。俺、驚いちゃったよ」
「相田君も見てたの? 別に不思議じゃないでしょ、綾波さんが挨拶したって」
「まあ、そう言われればそうだけど・・・・。でも、初めてだよな・・・・明日の朝は、その瞬間をカメラに・・・」
「だ・か・ら、カメラは駄目だって言ってるでしょ!!」
「・・・・委員長、まだいたのか・・・・・」
「え、何か言った?」
「いえ、何も・・・・・」
「碇君、さっきの話だけど、葛城さんっていう人に頼んでみてくれないかしら?」
「明石さんは、ミサトさんを知ってるの?」
「ううん。リエから聞いたのよ。すごい美人が、碇君の保護者なんだって。だめもとで、頼んでみてよ。ね、お願い」
「うーん、取り敢えず、頼むだけはね・・・・してみるけど・・・・その・・・・期待しないでね」
「やったー。ありがと。碇君。」
「あのさ、碇」
「・・・相田君・・だったよね。何?」
「すごい美人、とかいう話、本当なのか?」
「え、いや、その・・・・人によって・・・その・・・意見が違うみたいで・・・」
1時間目の授業のベルが鳴り始めた。
つづく
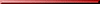
第15話に進むには、この を押してください。
を押してください。
「小説のありか」に戻るには、この  を押してください。
を押してください。
![]()
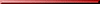
 を押してください。
を押してください。