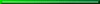
「あの・・・そんなに気を落とさないで下さいよ・・・あの子は気まぐれで人見知りが激しいから・・・」
「あ、心配させちゃったかしら? ごめんなさいね。大丈夫よ、ちょっとがっかりしただけだから・・・」
「ネコ、お好きなんですね。私も大好きなんですよ。本当はうちでも飼いたいんだけど・・・」
「マンションに住んでいるから、だめなの?」
「昼間、誰もうちにいないから・・・お父さんは毎日遅いし、私も学校に行ってるから・・・」
「お母さんは?」
「私が生まれてすぐに・・・・」
「・・・いやなこと聞いちゃってごめんないさいね・・・」
「いえ、いいんですよ。顔も知らないから、なんか実感無いんですよね」
「・・・・そう・・・・あ、すみません、突然、入ってきてこんなにお邪魔しちゃって・・・。そろそろ行かなくちゃ
いけないわ・・・・どうもお邪魔しました。また、機会があったら顔を出してもいいですか?」
「ええ。うちは構いませんよ。こんなところでよかったら、いつでも顔出してくださいよ。
あ、そうそう、おうちをお探しの際にはどうぞ当店へ、なんてね、はははは」
「おじさん、しっかり宣伝してるわね。私もあんまり遅くなるといけないから、そろそろうちに帰るわ。
あの、どちらの方面へ行かれるんですか?」
「え、私? 私は、この先のコンフォート17っていうマンションに行くんだけど・・・」
「ああ、あそこですか。うちの近所ですから、近くまで一緒に行きましょう」
「あら、そうなの。じゃ、いきましょう」
リエとその女性は石河不動産を出て、すっかり暗くなった道を並んで歩き始めた。
「あ、まだ名前、言ってませんでしたね。私、高橋リエっていいます」
「私は赤木リツコ。よろしくね、高橋さん」
「リエでいいですよ。赤木さん」
「私もリツコでいいわよ。いつもそう呼ばれてるから」
「じゃ、リツコさん。リツコさんもNERVの関係者なんですか?」
リツコは立ち止まり、表情を堅くして冷たい視線でリエを見つめた。
「・・・・・あなたが、なんでそういうことを知っているのかしら?・・・・・」
「あのマンションはNERVが一括借り上げしてるから。それに目つきの悪い人たちがよくうろついてますからね。
たぶん護衛の人でしょ? この近所の人たちは、口には出さないけど、みんな知ってることですよ」
「そうなの・・・。NERVもずいぶんと有名になったものね」
リツコは自嘲気味にそう言うと、再び表情を和らげて歩き出した。
「私、あのマンションに知り合いの人がいるんですよ」
「そう。誰かしら?」
「葛城ミサトさんと碇シンジ君です」
「まあ、ミサトとシンジ君の知り合いなの? 驚いたわね」
「ええ、碇君とは同じクラスですし、ミサトさんとは偶然知り合いになって・・・」
「ミサトはね、学生時代からの親友なのよ。今日も、ミサトの部屋にいくつもりなの。食事をごちそうしてくれるって
言うから・・・」
「そうですか。リツコさんは、NERVでは何をやっているんですか?」
「・・・・私は、主に技術面ね・・・・」
「うわあ、すごいですね。もしかして、あのロボット作ったのもリツコさんだったりして」
「・・・・もう、あれのこと、そんなに知れ渡ってしまっているのね・・・」
「みんな期待してますよ。あれがあれば、また新種生命体が出現しても、きっとこの街を護ってくれるって!!」
「そう。あれは私たち人類の切り札なのよ。あれの名前も、もう知ってるの?」
「エヴァ、でしょ? いま、私たちの間では、すごい人気ですよ。でも・・・・碇君は・・・辛いみたい・・・」
「・・・そうでしょうね・・・でも、それしか方法がないのよ、私たちには・・・・」
「あの、こんなこと、聞いちゃいけないのかもしれませんけど、なんで大人が操縦してはいけないんですか?」
「・・・・いろいろと、ね・・・・ごめんなさいね、今はこれぐらいしか答えられないのよ」
「私の方こそ、へんなこと聞いてすみませんでした。・・・・あの・・・・まわりの大人の人たちは、みんなNERVが
嫌いみたいですけど、私は信じてますから・・・・私たちの生活、そして未来を護ってくださいね」
「・・・・ありがとう・・・・でも、その言葉は、私よりも、シンジ君やミサトに言ったあげたほうがいいわよ・・・」
「なぜですか?」
「・・・・私は・・・・そういうことを言われる資格がないから・・・・」
リツコは視線を少し落として呟いた。
「未来はね、それを望む者だけに与えられるものなのよ。だから、希望を持たないまま漫然と日を送るのだけはやめなさいね」
「・・・・希望、ですか?・・・・」
(・・・・希望・・・・私は未来にどんな希望を持っているのかしら・・・・今まであまり考えたこともなかった
ような気がするわ・・・私はどのようになりたいのかしら?・・・・・私はどうあるべきなのかしら・・・・)
リエが俯いたまま黙ってしまったのをみて、リツコは優しい声で言った。
「別に急いで考える必要はないわ。まだあなたには時間があるんだから・・・でも、いつかはきちんと考えておくべき
問題なのよ。さもないと・・・・」
「さもないと?」
「・・・・大人になってから・・・・悲しいから・・・・・」
二人はいつのまにかミサトのマンションの前に着いていた。
「あなたも少し寄っていく?」
「いえ、私はうちに帰ります。そろそろご飯の支度しなきゃいけないから」
「あら、まだ若いのにしっかりしてるわね! ミサトとは大違いだわ」
「誰と大違いなんだって?」
「あら、いたの。こんな時間にどこに行くつもり?」
「シンちゃんが買い物を1つ忘れていたんで、私が代わりに買いに行ってくるっていうわけよ。
あら、リツコもリエちゃんと知り合いだったの?」
「いえ、たった今、そこの石河不動産でネコみててリツコさんと知り合ったんです」
「また、ネコぉ? リツコ、あんたネコより彼氏探しなさいよ、彼氏!! もういい歳なんだから!!」
「あら、あなたには言われたくないわね。あなたこそ、そろそろ誰かに決めたら? いろんな人から言い寄られて
いるみたいじゃないの? まぁ、夜目遠目傘のうち、って言うものね」
「なによ、それ?」
「人間、近くに寄ってよくみてみなければ、本質がわからないってこと。つまりは外見にはだまされるな、ってことね」
「あんたねぇ!!」
「あ、それじゃ、私はこれで」
リエは二人の女性の雲行きが怪しくなってきたので早々にその場を退散した。
リツコは遠ざかっていくリエの後ろ姿を眺めていた。
「高橋リエちゃんか。いい子ね・・・・わたしたちにもあんな年頃があったのね、もう昔になってしまったけど・・・」
「なに年寄りみたいなこと言ってんのよ。そうそう、あの子、レイと友達になろうとしているんだって。
シンちゃんが言ってたわ。」
「そう・・・・残酷なことね・・・・神様というものが存在するなら・・・・」
リツコは星の出ていない夜空を見上げると、マンションのエントランスホールに入っていった。
リツコとリエが出ていったあと、石河不動産では主人の石河キイチが店のシャッターを降ろしていた。
「おーい、そろそろ晩飯にしてくれないかね。しかし不思議なもんだね、あんまり客が来なくて働かなくても、
ちゃーんと腹だけは減るんだからね。客が少ないときには腹もあんまり減らないと釣り合いがとれるんだけど・・・」
「ばかなことと言ってないで、さっさと手を洗ってきてくださいよ」
「ルビーはご飯すんだのかい?」
「ええ、さっきキャットフードを出しておきましたから。あら、また残してる!! 最近、飽きてきたみたいね。
ほんと、すぐ飽きちゃうから困ったものだわ。この間、ブランド変えたばかりなのに・・・」
石河がお膳の前に胡座をかいて座ると、ルビーがとてとてと歩いてきて、胡座の間に座り込んで、石河の顔を見上げた。
「ルビーはいいよな。気に入らないものを食わないでいれば、もっと旨いものを食わせてもらえるんだから。
わたしなんか、気に入らないからって、おかず残したりすれば、もう食事つくってもらえなくなっちまうよ。
ああ、ネコが羨ましいよな。次に生まれてくるときには、ネコに生まれてこようかな・・・・」
「来世と言わず、あなたも明日からキャットフード食べますか? まだたくさん余ってますから」
石河はルビーの喉元を撫でながら、遠い目をして黙り込んだ。
「こんばんわー」
「あら、いらっしゃい。ちょうど、ご飯食べようとしていたのよ。あなたもどう?」
「ははは、それが狙いですよ、なんてね。あ、おじさん、こんばんわ」
「ああ、よく来たね。おーい、ビール出してくれよ、ビール。そう、それ、エビチュだ。」
石河は、お膳の前に座った若い男にコップを渡すと、ビールを注ぎ始めた。
「どうだい、仕事の方は? 」
「新しいプロジェクトが完成間近なんで、やたら忙しいですよ。今日は出張でこっちに来たんで、栄養補給のために
寄らさせてもらいました。一人住まいだとろくなもん食わないんで・・・。あ、電話入れる暇なくて、すみません」
「忙しいのは繁盛してる証拠だよ。ああ、そうそう、いちいち電話なんぞしなくていいよ。
ここは、あんたの家も同然なんだから」
「・・・おじさん・・・。いつもすみません・・・」
「水臭いな、礼なんぞ言うなよ。お互いたった一人の血縁じゃないか」
「ほんとにおじさんには何から何まで面倒みてもらって・・・・。今度のプロジェクトが完成すれば、7月に
特別賞与が出るんですよ。そしたら、第2新東京で何か旨いものでもご馳走しますよ」
「そんな無駄遣いしちゃいけないわよ。それはあなたの結婚資金として貯金しときなさいよ、ねぇ、あなた」
「ああ、ばーさんの言うとおりだよ。あんたが一生懸命働いた褒美だろ、あんたが自分のために使わなきゃ
意味が無いよ。その時まで郵便貯金、おっと今は東日本郵便銀行って言うんだったな、あそこに貯金しておけばいいよ」
「そんなこと言わないで下さいよ。それじゃ私の気が済みませんから。あのとき修学旅行に行っていて、一人だけ
助かった私の面倒を見てくれて、そのうえ学費まで全部出してもらったんで、私はこうして大学出て就職できたんですよ。
あのときは、私みたいになった子供たちがたくさん出たけれど、あまりにも被害が大きかったんで、奨学金制度がもはや
機能しなかったし、政府もなにもしてくれませんでしたからね。私がこうして大きくなれたのは、おじさんとおばさんの
おかげなんです。大したものはご馳走できませんけど、どうか来てくださいよ」
「そうかい。そこまで言うんなら、甘えさせてもらおうかな、なあ、ばーさん」
「ええ、そうさせてもらいましょ」
「是非、そうしてくださいよ。ここは新しくできたばっかりで、レストランや料亭はまだ少ないでしょうから」
「ところで、今、なんのプロジェクトをやってるのかい?」
「あんまり詳しくは話せないんですけど、ロボットを作っているんです。日本が独自製作する初めての大型ロボット
なんですよ。これが成功すると、わが国の産業再生の起爆剤になることができるんです。そういう意味で国運がかかった
プロジェクトなんです。」
「ああ、それでメーカー各社が予算を出しただけでなく、政府も補助金を出して技術研究組合を作ったんだね。
この間、あんたが日本重化学工業共同体に出向になったって聞いたときには、左遷かと思って心配したんだよ」
「一応、左遷じゃないみたいですよ。政府の方では、産業省の管轄下に入るみたいですけど、実際には内務省が
うちの面倒を全てみています。あ、これ、もう公然の事実ですけど、一応、他所では言わないで下さいね」
「ああ、わかってるよ。でも、つい数日前に組合ができたばかりなのに、もうプロジェクトは完成するのかい?」
「ええ、実は、内々、産業省の工業技術研究所が音頭をとって、メーカー各社の個別自主研究という形で開発を進めていた
んですけど、今回の、あの騒ぎでようやく財務省が必要性を認知して産業開発投資特別会計に計上できることに
なったんで、急いで受け皿としての組合をこしらえたんですよ。私自身は、入社以来ずっと、
あれの開発に携わってきましたから、なにも環境は変わらないんですがね」
「民生技術の開発なのに、なんで内務省が絡んでいるのかい?」
「実は民生技術じゃないんです。それに政府の手が届かない別の組織でも同じようなものをつくっていて、
競合関係にあるんですよ」
「じゃ、それは戦自の守備範囲なんじゃないのかい?」
「あそこはあそこで、つくばの技術研究所で別に開発をやっているみたいですよ。いくら行政改革やっても、所詮、役所は
たて割組織ですからね。今回の開発も、内務省・産業省連合と国防省の利権が衝突するんですよ。組合に参加している
側の企業も、従来の、いわゆる「国防ファミリー」に加わっていない中堅企業やベンチャーが中心ですからね。それに
もともと内務省と国防省は仲が悪いですからね。近親憎悪みたいなもんですよ。われわれ民間からみると、会社の中で
各部門が勝手に動いているような、ばかげた話ですよ。」
「そうなのかい。大変だね。ま、我々、一般庶民には無縁の世界だな。ところで、開発は順調なのかい?」
「ええ、極めて順調ですよ。なにしろ衰えたりと言えども、日本の産業技術の粋を集めた作品ですからね。
これが成功すれば、世界各国からも、わが国の技術水準が再評価されて、セカンドインパクト後の動乱で
下り坂になってしまったわが国の産業を再生することができるはずです」
「そうなるといいね。昔は旧東京に本社機能も研究開発機能もみんな集中していたから、あのときに日本の産業は、
壊滅的な打撃を受けたからね。ま、もっとも、その数年前から、パソコン生産では台湾、情報通信では米国、マレーシア、
シンガポール、鉄鋼・造船は中国、バイオ・航空宇宙分野では米国、EU、金融分野は米国、シンガポール、不動産開発
は香港資本に負けてしまっていて、既に凋落が始まっていたがね」
「今回の開発は、わが国のエンジニアたちの意地と誇りがかかっているんです。絶対に成功させてみせます。
自分のためだけじゃなく、この国の生き残った人たちのためにも、希望を取り戻したいんです」
若い男は、そう言うと、窓の外にそびえたつ高層ビルに視線を移した。
「そうかい。がんばってくれよ。あ、みてくれよ。この間、知り合いからネコを預かってね・・・」
「あ、ほんとだ。なかなかかわいいですね。誰から預かったんですか?」
「第二新東京からここへ越してきた人がね、一緒につれてきたんだよ。向こうでは、ネコOKのマンションだったんだけど、
ここではまだそういうの少なくてね。家賃が高いんだよ。それで、こっそり社宅で飼っていたんだけど、管理人に
ばれちゃってね。うちへネコOKのマンションを探しに来たときに、そんな話を聞いたんで、安いところの出物が
あるまでの間、うちで預かってあげることにしたんだよ。扶桑ルミさんっていう、なかなかの美人だったよ」
「そうですか。そういう人は、早めに紹介してくださいよ。なんせ、こっちは仕事漬けで、女性と知り合う機会もない
んですから。ははははは」
そのとき、電話が鳴った。
「日本重化学工業共同体の和泉と申しますが、そちらに時田さんはお帰りでしょうか?」
つづく
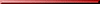
第14話に進むには、この を押してください。
を押してください。
「小説のありか」に戻るには、この  を押してください。
を押してください。
![]()
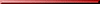
 を押してください。
を押してください。