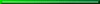
早雲山運送の陸奥社長からの電話は、高橋を驚かせた。
「きょうはどうした風の吹き回しだい? いつもは電話なんぞよこさないのに・・・・」
「ちょっとね・・・とにかく電話ではなんだから、今晩出てこいよ」
「ああ、わかった。ちょうど今晩は空いているからな。どうする? 新箱根湯本まで行った方がいいかい?」
「そうしてくれるとありがたいな。ちょっと第三新東京では話しにくいから・・・・」
「じゃ、新箱根湯本の漣<サザナミ>屋で7時に待ち合わせるか。あそこは、加賀料理がうまいからね」
「あ、ああ・・・。そうだな。そうしよう」
珍しく歯切れの悪い陸奥の言葉に、高橋は軽い違和感を覚えたものの、さして気にも留めずに電話を切った。
リエはさっきから蒼髪の少女にしきりにいろいろと話し掛けている。
「綾波さんは、どんな食べ物が好きなの?」
「・・・・・・べつに・・・・・・・」
紅い瞳の少女は、リエの方を一瞥もせずに、真っ直ぐ前をみつめたままで、素っ気なく答える。
「そ、そう・・・・。じゃ、何か、食べられないものある?」
「・・・・・・・なんで・・・そんなこと聞くの?・・・・・・・・・」
「あ、誰でも嫌いなものはひとつぐらいあるから・・・・。たとえば、私は濃い味付けのものは駄目なのよ・・・」
「・・・・・・・そう・・・・・・・・」
「・・・・・・・あ、お母さんは、どんな料理つくったりするの?」
「・・・・・・・・・・・・・・・・」
レイは何も答えないが、ほんの心持ち表情が動いたような気配がした。
(なんかまずいこと聞いちゃったかしら・・・・・・)
リエは、レイが反応を示さなくなったことに憔悴し始めていた。
(・・・・・・あーん、場がもたないよう・・・・・)
「おはよう、リエ!! あれ、綾波さんと一緒なの?」
「おはよう、リョウコ。今朝ね、新駒沢のコンビニでばったり会ったのよ。ほら、ユリコのうち。それで一緒に学校来たの」
「そうなの。おはよう、綾波さん」
レイはリュウコをみた。
静かに瞬きを2回したが、相変わらず黙っている。
(・・・・・・明石さん・・・・・・この人も私にあいさつする・・・・・・なぜ・・・・・)
「・・・・・・・どうして・・・・そういうこと言うの?・・・・・・」
リエもリョウコも一瞬たじろいだ。
レイの方から問い掛けてきたのは初めてだった。
リョウコはレイの表情が僅かながら、ほんとうにごく僅かながら曇っていることに気づいた。
「あなたは、私たちに声をかけられるのが、いや?」
「・・・・・・・そんなこと・・・・・ない・・・・・」
「わたしたちは、あなたと同じクラスにいて、この14歳という瞬間を一緒に生きてるじゃないの。
袖擦り合うも多少の縁、って言うじゃない。もし、いやじゃなかったら、一緒に話したり、ご飯食べたりしてみない?」
「そう、リョウコの言うとおりよ。私ね、今まで、あなたのこと、話し掛けづらいな、って思ってたの。でもね、
人にはいろいろ性格があって、こっちから近づかないと、決して友達になれない人もいるって気づいたの。
・・・・・・・あなた、昨日言ってたけど、確かに今のあなたにはなにもないかもしれない・・・・
でもね、これから創っていけばいいんじゃないの? 少なくとも、わたしたちは、創っていきたいと思ってるわ」
「ねえ、その怪我、どうしたの? 大丈夫? もう痛くない? 」
「わたしも、さっきから、そのこと聞いてるんだけど・・・・・綾波さん、返事してくれないのよ・・・・」
「・・・・・・・・・・どうして・・・・・私のことに関心を持つの?・・・・・・・」
「近くの人が怪我してたら、心配なのは当たり前じゃないの」
「・・・・・・・・・・心配?・・・・・・・・・・・」
「うん。心配よ。もし必要なら何かしてあげたいって思うわよ。たとえ知り合いじゃなくっても、やっぱり
大きな怪我してる人みたら心配するわよ」
「・・・・・・・・・どうして・・・・・・・自分にとって、なんの得にもならない・・・・・・」
「損得勘定で心配なんかするほど、私たちはまだ大人じゃないってこと」
「そうよ。そしてね、その人が、わたしたちの身近な人だったら、なおさら心配なのよ・・・・
私ね、リョウコが落ち込んでたら、やっぱり心配だし、リョウコが嬉しいときには、やっぱり私もうれしいもの。
別に、心配したらいいかな、とか、ここで喜んであげたらいいかな、って、いちいち考えてないのに、
自然とそういう反応になるのよ」
「・・・・・・・・・私・・・・・・身近な人・・・・・なの?・・・・・・」
「当たり前じゃない!! 確かにあなたは人付き合いが苦手みたいだけど、決して悪い奴じゃないってことは
私たち、分かってるつもりよ。急に、なんでも話せ、なんて言うつもりはないけど、少しずつでも、こんなふうに
話してみたりするのは、いいんじゃないの」
「・・・・・・・・・そう・・・・・・・かもしれない・・・・・・・・」
レイはそう呟くと、視線を舗道の敷石に移して黙ってしまった。
(・・・・・・心配・・・・・身近な人・・・・・・ヒト・・・・・・・・・・・
・・・・・・絆・・・・・・かもしれない・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・ちがうかもしれない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・わからない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・わかることが・・・・・できるの?・・・・・・私にも・・・・・・)
リエもリョウコも、いつもよりはるかに多弁なレイに驚いていた。
(・・・・・やっぱり、打てば響くものね・・・・リエ、よかったね・・・・)
リョウコは、リエのこころの一端が、レイをほんの僅かながらでも変えたことが、ちょっと嬉しかった。
「おはよう。リエ、リョウコ、・・・・ええっ、綾波さんっ??」
「おはよう、ヒカリ。今朝、リエが新駒沢駅の近くで偶然出会って、一緒に学校来たんだって」
「そうなの。これからも、ときどき、こんなことがあるかも、ね」
リエはレイの方を向いて、にっこり微笑んだ。
レイは・・・かすかにうなずいた・・・・ように見えた。
「そう。とにかく、良かったわ。・・・・なんか今日はいいこと、ありそうね」
ヒカリは、孤立していたレイに、まだ友達とはいえないまでも、話のできる少女たちが現れたことが
嬉しかった。
(委員長として、クラスメートとして、一安心ね。これで、あとは鈴原だけか・・・・・・・)
「あ、おはよう」
教室に入ってきた少女たちをみて、シンジは声をかけた。
「おはよう」
レイを除く3人のあいさつが聞こえた。
「・・・・・・碇君・・・なんで綾波さんの怪我に驚かないの?」
リエに怪訝そうに尋ねられてシンジは狼狽した。
「え、あ、ああ、そ、そうだったね、え、えっと、その昨日の晩にそんな話を聞いたから・・・」
「誰から?」
「えっと、NERVの・・・・」
「やっぱり、綾波さんもこの間の事件に関係しているの?」
「あ、いや、その、それは・・・・」
「・・・・・・碇君・・・・・守秘義務・・・・・・」
「あのね、綾波さん。守秘義務っていう言葉を言ってしまった時点で、自分がNERVに関係してるってこと、
認めたようなものだと思うんだけど・・・・・」
リョウコの指摘に、レイは沈黙してしまった。
「・・・・・・・・・・・・・・・・」
「あ、綾波は関係者だけど、そんなに深く関わっているわけじゃないんだよ」
「じゃ、少なくとも碇君みたいなパイロットじゃないってこと?」
「そ、そうだよ。確か、お父さんが勤めているんだったよね」
「・・・・・・・・・・・」
「そうなの・・・。じゃ、その怪我って、何が原因なの? 綾波さん、教えてくれないから・・・・」
「そこまでは僕も知らないよ」
「それもそうね。」
少女たちはそれぞれの席についた。
「・・・・碇君・・・・」
「あ、なに、綾波?」
「・・・・・・ちょっと・・・・・来て・・・・・」
レイが自らアクションを起こすことは初めてなので、廊下の隅へ歩いてゆきながら、いつになくシンジは緊張した。
「・・・・・エヴァのこと・・・・・話したのね・・・・・守秘義務、あるのに・・・・・」
「そのことなら、もうミサトさんには話したよ・・・・僕が言わなくても、みんな雑誌の報道で知っていたよ」
「・・・・・・私のこと、黙っていたのは、なぜ?・・・・・・・・」
「・・・・・・巻き込みたくないんだよ、綾波まで・・・・・・・・」
「・・・・・・なぜ?・・・・・・何も変わらないわ、きっと・・・・」
「NERVは必ずしもみんなから良く思われているわけじゃないよ・・・・・綾波がパイロットだって知れたら、
みんなから一層変な目でみられるんじゃないかって思って・・・・・・・」
「・・・・・・私はどんなふうにみられても、気にしない・・・・・・・」
「・・・・・・僕は、パイロットだって知られたとき、殴られたよ・・・・そんな目には遭わせたくないよ」
「・・・・・・どうして?・・・・・・」
「どうして、って、だって特別な人だからだよ」
「・・・・・・特別な人?・・・・・」
「そう。同じように、あれに乗る宿命を負った人、だから。それに・・・・・」
「・・・・・・それに?・・・・・・」
「・・・・・・友達だから・・・・・」
「・・・・・・・・・・・・・・・・」
(・・・・・なぜ・・・・・碇君まで・・・・・・・友達って・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・なぜ・・・・・みんな、私のことを・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・私のこと、気にかけても・・・・なんの見返りもないのに・・・・・・・・
・・・・・・どうして・・・・・わからない・・・・・・わからない・・・・・・・・・
・・・・・・エヴァ以外の絆・・・・・・・存在しないはずなのに・・・・・・・・
・・・・・・でも、これは・・・・・・・・やっぱり絆・・・・・・・そうなの?・・・・
・・・・・・私にとって・・・・・・・・・絆とは・・・・・・・何?・・・・・・・・
・・・・・・エヴァとは・・・・・・・・・何?・・・・・・・・・・・・・・・・)
「おはよう。碇君!!」
「あ、おはよう・・・初瀬さん、だよね・・・・」
「昨日はごめんね。私のせいで、みんなにエヴァのこと、知られちゃって。鈴原に殴られたって、ほんと?」
「あ、ああ。なんでも妹さんが怪我したらしいんだ。だから・・・・・・」
「そーんなの、碇君のせいじゃないじゃない!! よおし、あたしが鈴原に文句言ってあげるわ!!」
「あ、いや、それは、昨日、明石さんが言ってくれた・・・・」
「リョウコが? それならいいわ」
「・・・・・・あなたが・・・・碇君を窮地に立たせたの?・・・・・」
「綾波さん? 初めて声をきいたわ!!! ・・・・うん、私の不注意で・・・碇君に迷惑掛けちゃったの・・・」
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
「あ、綾波、そんなにこわい顔しなくても・・・・・どうせ、知られるの、時間の問題だったんだし・・・・」
「あの、ほんとに、悪かったって、思ってるの・・・ごめんなさい・・・・・」
ユリコもシンジも、普段は無表情なレイがいつになく厳しい顔で睨んでいるのをみて、かなり驚いていた。
だが、彼らの声を聞いたレイは再び困惑の淵に沈んだ。
(・・・・・・・・・私が・・・・・こわい顔してる?・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・そんなはず・・・・ない・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・守秘義務違反を咎めるのは・・・・私の任務じゃない・・・
・・・・・・・・・私・・・・・・・怒ってる?・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・なんのために?・・・・・・・・・・・・・・・・・・)
「トウジ、あいつ来たぜ。やっぱ謝った方がいいんじゃないかな、昨日のこと・・・・」
「なに抜かす?! わしはひとっつもまちごうたことはしておらん!! なんも謝る必要はないんじゃ!!」
「でもさ、どうみても、昨日のあれは、根拠が薄弱だよ。碇だって、わざとやったんじゃないんだし・・・・」
「わざとか、はずみか、よう知らんが、どっちにしても妹が怪我したのに変わりないやろ!!」
ケンスケはシンジの方をみていたが、ふと、シンジと目が合うと、黙って目であいさつした。
シンジも、昨日、彼がトウジを抑えようとしていたのをみていたから、ケンスケに向かって、軽くうなづいた。
トウジはシンジがいる方向にすら、顔を向けようとしなかった。
レイは、休み時間は、本を読むか、頬杖をついて窓の外をみるだけだったが、今日はいつになく忙しかった。
休み時間になるたびに、二人の少女が近くの席に移ってきて、なんやかやと話し掛けてくるためである。
そして昼休みを迎えた。
リエとリョウコは、やはりレイの隣と前の席に移ってきて、自分たちの弁当を広げ始めた。
「ごめんね、綾波さん。きょうは、本読む時間を取ってしまって・・・・・・」
「・・・・・・いい。・・・・・別に・・・・とても読みたいと思っているわけじゃないから・・・・」
「なんか、くだらない話ばっかりでごめんね」
「・・・・・・そんなこと・・・・ないわ・・・・・」
(・・・・・・・・衣服、テレビ番組、食事・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・今まで知らなかったこと・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・知る必要がなかったこと・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・この人たちは・・・・・楽しそうに話す・・・・・
・・・・・・・・内容・・・・・・ぜんぶは分からない・・・・・・
・・・・・・・・あまり・・・・・関心は・・・・持てない・・・・
・・・・・・・・でも・・・・・・嫌じゃない・・・・・・・・・・
・・・・・・・・この場にとどまること・・・不快じゃない・・・・
・・・・・・・・なぜ・・・・・・私は、この場にいるの?・・・・・・)
レイは、鞄から初瀬のコンビニで買ったパンを取り出した。
そして2つのパンを机の上に並べると、じっと見詰めた。
(綾波さん、初瀬のおじさんからもらったパン、食べるかしら・・・・・・
初瀬のおじさん、口下手だから、綾波さんに気持ちがちゃんと伝わっているか、心配だな・・・・)
リエは、思わず箸を止めて、レイの手許を見つめていた。
レイは、まだとまどっているようにも、あるいは考え込んでいるようにみえた。
そして・・・・・レイはくるみパンの封を破り、パンを小さくちぎると、
ゆっくりと口に入れた・・・・自分の買ったクロワッサンには手をつけずに・・・・
(ああ、通じたんだわ、気持ち・・・・よかった・・・・・)
リエは、ほっと安堵のため息を洩らした。
それに気づいたレイは、パンを呑み込むと、リエの顔をみつめ、囁くような声で
「・・・・・・・くるみパン・・・・・・・嫌いじゃないわ・・・・・」
と呟いた。
(あ、綾波さんの表情、ほんのちょっとだけ動いたみたい・・・・・・・
でも・・・・・・私の気のせいかもしれない・・・・・・・・・・・・
今は、気のせいでもいいわ。いつか、きっと、この子も、にっこり笑う日が来るはず・・・・・)
祈るような気持ちで、リエは、少女の白皙の頬を眺めていた。
その傍らで、リョウコは、いろいろな思いを巡らせていた。
(今朝、電車で出会った人、やさしそうだったわ。あんな人がお姉さんだったら、いいのにな・・・。
ほんとうに、週末にお店に来てくれるかしら? 来てくれたら、どんなお菓子を勧めようかな?
そうだわ、店のお菓子のほかに、自分で作ったお菓子も試作品として食べてもらおうかしら・・・・
さっそく、今日から準備を始めようっと!!)
リョウコは思惟にけりをつけると、レイに向かって話し掛けた。
「綾波さんは、お菓子って好き?」
「・・・・・・お菓子?・・・・・・・」
「まさか、食べたことないんじゃ・・・・」
レイは小さくうなづいた。
「・・・・・・・・必要な栄養は・・・・十分にとっているから・・・・」
「おうちの人は食べないの?」
「・・・・・・・・・・・・・・・」
リエは、自分の問いに対するレイの沈黙が、ちょっとだけ寂しかった。
(やっぱり、自分のことは話してくれないのね、綾波さんは・・・・でも、まだ仕方ないのかしら・・・)
リエが顔を上げると、リョウコの心配そうな顔がみえた。
リエが「大丈夫よ」というように小さく微笑んでうなづくと、リョウコは、ほっとしたような表情になった。
「じゃ、今度、暇なときに、うちの店においでよ。お菓子ご馳走するから!!
うちのお菓子、そんじょそこらのコンビニと比べ物にならないほど、おいしいのよ!!」
「あーら、そんじょそこらのコンピニで悪かったわね。うちの扱っているお菓子は大手の製菓会社の売れ筋新製品
ばっかりよ。リョウコんちのお菓子に負けないもん!!」
通りがかりのユリコがぷうっと頬を膨らまして、リョウコの脇に立ちはだかった。
「なに言ってんのよ!! こっちは手作り和菓子よ!! ユリコのところのは、洋菓子やスナック菓子じゃないの。
比較の対象にならないわ!!」
(困ったわね・・・・二人とも一旦言い出したら聞かない性格だし・・・・)
リエはとんでもない方向に話が進んでしまって焦っていた。
ユリコもリョウコも、下町育ちで性格が似ているため、普段は仲が良く、
「ねえねえ、昨日の夜の、「天使の微笑み」見た? あたし、感動しちゃったわよ!!」
「あ、あたしも!! 最近のテレビ第3新東京、なかなかセンスいいわよねぇ!!」
などと話しているが、一旦、それぞれの扱っている商品の話になると、
やはり父親とふたりで店を切り盛りしてるため、メンツがあるせいか、絶対に一歩も引かず、険悪な雰囲気が漂う。
リョウコはコンビニが和菓子を洗剤など他の商品と一緒に扱うのを敵視しているし、
ユリコは米屋を廃業してコンビニを開業するという、いわば背水の陣を敷いているだけに、
意地でも個人商店には負けられないと思っている。
そのため、彼女たちの前で、商品、とくに菓子の話をすることは、2年A組ではタブーとなっていた。
ユリコとリョウコがにらみ合う姿を、レイはただじっとみつめていた。
(・・・・・・・あるときは対立し、べつのときは笑い合う・・・・・・・・・・
・・・・・・・敵であれば・・・・なぜ完全に殲滅しようとしないの?・・・・
・・・・・・・笑い合っていたのに・・・なぜ対立するの?・・・・・・・・・
・・・・・・・わからない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・)
リエはレイが二人の姿を紅い瞳でみつめていることに気づいて慌てた。
(まずいわ。綾波さんがみてるわ。なんとかしなきゃ・・・・・)
「あ、えーと、そうだわ。じゃ、今度、その、試食して比べてみるのは・・・どう・・・・かしらね・・・」
こう言ってしまったあと、リエは「苦し紛れに最悪の選択をしちゃったかも・・・・」と後悔していた。
「そうね。この際、しっかりと決着をつけておかないとね」
「望むところよ」
「じゃ、今度の日曜日の午後3時なんか、どう? うちはお父さんがレジ担当だから大丈夫よ」
「コンビニは職人が必要ないからいいわよね。あたしは週末は店から離れられないのよ」
「じゃ、あんたの家に集まったらいいじゃない」
「そうね。いいわよ。リエ、それから綾波さん!! あなたたちも来るのよ!!」
「え、リョウコ、わたしたちも?」
「審判がいなきゃ勝負がつかないじゃない!! とくに綾波さんはお菓子食べたことないって言うから、
変な先入観がなくて、審判にはうってつけよ。絶対に来てね!!」
「・・・・・・・私・・・行くの?・・・・・・」
「そうよ!! あなたに来てもらわないと困るの!! 必要なのよ!!」
レイは少しの間、黙って、リョウコ、ユリコ、リエの顔をゆっくりと見回していた。
「・・・・・・・必要なの・・・・・私?・・・・・・・・」
「・・・・・・・お願いよ・・・・・絶対来てね!!・・・」
「・・・・・・・日曜日の午後3時・・・・明石さんのうち・・・・・了解・・・・したわ・・・・・・」
レイは無表情のままだったが、内心はかなり動揺していた。
彼女の答えを聞いた瞬間、3人の少女の顔がぱっと輝いたから・・・・・・・・・。
(・・・・・・・この人たちにとって・・・・・私はどのような存在・・・・・・・・
・・・・・・・この感覚・・・・・・・決していやじゃない・・・・・・・・・・・
・・・・・・・むしろ・・・・・・・・その反対のような気がする・・・・・・・・
・・・・・・・この人たちは・・・・・私とは・・・・違うのに・・・・・・・・・
・・・・・・・でも・・・・・・どうして・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・この感覚・・・・・・・前にも感じことがある・・・・・・・・・
・・・・・・・これは・・・・・何・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・)
下校時、リエはレイがいないことに気づいた。
「一緒に帰ろうと思ってたのに・・・・・」
「綾波さん、少し疲れたんじゃないかしら?」
「・・・・そうかもしれないわね。急に世界が広がったみたいだから・・・・・」
「あの子、今まで、鍵穴から部屋の中をみていたような感じだったはずよ。それが突然、ドア開けられて
さあ、入れ、って言われたら、やっぱり戸惑うよ。でも、決して悪いことじゃないと思うわ」
「そうね。・・・・私もなんか疲れちゃった・・・・リョウコ、なんか食べて帰らない?」
「いいわよ。こっちも、いろいろと話したいことあるし」
リエはリョウコの瞳が以前のように好奇心で輝いているのをみた。
(あ、すっかり元気になってる!! よかった・・・)
二人の少女は、セミ時雨が降る道をゆっくりと新四谷駅の方に向かって歩き始めた。
「そうそう、さっきの試食会の話、リエが切り出したの、絶妙のタイミングだったわよ。やるわね!!」
「あーあれ、苦し紛れに言っちゃったのよ。でも、よくユリコもOKしたわね?」
「あ、知らないの? ユリコも、あの子がいつも独りでぽつんとしていること、気にしてたのよ」
「えっ、そうなの? 全然気がつかなかったわ。」
「ああいう性格だから、人前ではそんなことめったに言わないけどね。この前、たまたま学校に来るとき、電車で
一緒になったの。そしたらね、ユリコ、「綾波さんは寂しくないのかしら」って、ぽつりと言ったのよ」
「そうだったの・・・・・。リョウコも、そういう話はすぐに私にしてくれればいいのにぃ。」
「あのあと、いろんなことがあったから忘れちゃってたのよ。」
「それじゃ、あの話の後半は・・・・・」
「うふふふふ。そうよ、あたしとユリコの連携プレー!! 一瞬のうちに視線で打ち合わせちゃったのよ。
どう? うまくいったでしょ? だてに喧嘩してるんじゃないわよ、あたしたちは!!」
「あなたたちって・・・もうっ!!・・・・・」
ちょっと膨れたあと、リエは相好を崩した。
二人の少女の涼やかな笑い声は、暑さで融けかかったアスファルトの上に、しばらくの間、響いていた。
夕闇のとばりが降りた頃、高橋は新箱根湯本駅の改札を出た。
そして表通りの市街地を抜けると、早川の流れに沿ってしばらく歩き、旅館街に差し掛かった。
傍らの河原からは、蛙の鳴く声が聞こえてくる。
(最近、増えてきたな、蛙・・・・・)
高橋は、ぼんやりと、そんなことを考えながら、「割烹旅館・漣屋」と書かれた暖簾をくぐった。
「あ、7時に予約入れてる高橋だけどね」
「これはこれは、お待ちしておりました。おつれさまは、もうお着きです」
「電話で言っといたけど・・・・席は・・・・・」
「ご指示どおり、離れの「五箇山」をおとりしておきました」
「いつもすまないね。助かるよ」
「いえいえ、今後もごひいきに・・・・」
高橋は、母屋から泉水のうえに架けてある廊下橋を渡ると、池に面した離れに向かった。
襖の前まで来たとき、部屋の中から、幼なじみのだみ声が聞こえた。
「誰か、連れてきたのかな?」
ふたつの、かなり若そうな声が続いて聞こえた。
つづく
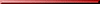
第12話に進むには、この を押してください。
を押してください。
「小説のありか」に戻るには、この  を押してください。
を押してください。
![]()
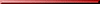
 を押してください。
を押してください。