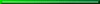
「じゃあ、行ってくるよ。あ、今日は遅くなるから夕食は外で済ませてくる」
「お父さん、今、忙しいの? そろそろ進路相談が始まるって先生が言ってたけど・・・」
「ああ、市街地整備計画の最終段階にさしかかっているからね・・・。でも、進路相談は行けるから心配しなくていい」
彼はそう言うと自宅から歩み出た。
まだ5月の初めだというのにかなり暑い。最近増えてきたセミの声が暑さを一段と感じさせる。
彼はまだ比較的新しい建築物の並ぶ道を南に向かってやや早足で歩いていった。
彼の自宅はやや高台にある。
9年前にこの都市の建設が始まったとき、最初に市街地が建設されたところであるため、どの家も少し外壁が
くすみ始めており、新興住宅地という印象ではなくなっている。
駅に着くと、彼はいつもように立ち食い蕎麦を食べる。
いつもは時間ぎりぎりなので、早く食べられるかけそばしかとらない。
「今日はいつもより少し早いから、天ぷらそばでも食べるか・・・」
彼は食券販売機にカードを差し込み、ボタンを押しながら、ぼんやりと
「あれから14年。こうして立ち食いそば屋でも、天ぷらそばが食べられるようになったんだなぁ・・・」
と思った。
彼は通勤快速で目的地の駅に着くと、また早足で大きな建物に向かったが、5分も歩かないうちに声をかけられた。
「おはようございます。今日も暑いですね」
「まったく。昔は今ごろの季節はまだそんなに暑くはなかったんだけどね。こう毎日暑くっちゃ仕事になんないよ」
「そうですね。私も、あの時はもう13歳になっていましたから、初夏の記憶はあります。いい季節でしたね・・・」
「ああ。それはさておき、橋立君、仕事には慣れたかい? ここはある意味、特殊だから大変だろ?」
「ええ、もう1ヶ月経ちましたから。やりがいのある仕事ですよ」
彼は、橋立というその青年と大きな建物のエントランスホールで別れ、彼の職場に向かった。
「おはよう。今日は早いね」
「ええ。今日は質問に当たっているんで、余裕をもって早めに出たんですよ。幹事長も相変わらずお早いですね」
「年寄りは朝が早くって困るよ。その代わり夜も早く寝てしまうがね。はっはっは」
「あ、そうそう、昨夜、新駒沢駅前の商店街から私の自宅まで陳情に来ましてね。何でも騒音問題だそうです」
「ああ、聞いているよ。戦自の装甲車が夜に東富士演習場に移動するとき、あそこらを通るからね」
「戦自相手では難しいですね。やはり、あれから10年も経つと、いろいろと不満も表面化してきますね」
「人間っていうものは贅沢な生き物だよ。つい10年前までは、それこそ生きていくだけで精一杯だったのにな」
「ええ。私も今朝、立ち食いで天ぷらそばを食べたとき、そう思いましたよ。あの頃は天ぷらなんかとても
食べられような状態じゃなかったですからね。私なんか、かけそば一杯でも食えりゃ嬉し涙が出たもんです」
「高橋君はあの時、いくつだったね?」
「24歳でした。まだ東京の交通省で係長心得をやってました。運良く、あのときは出張で福井に行ってました」
「私は横浜の市議をやっていたよ。あの時は定例議会が9月24日から始まるんで、忙しくなる前に、と
思って家族で伊豆に旅行に行っていたよ」
白髪の老人がそこまで話したとき、机上の電話が鳴った。
「三笠幹事長、そろそろ幹事長・書記長会議が始まります。議会事務局の第2会議室までお越しください」
「おお! 橋立君か。今行くよ」
三笠幹事長が去った後、高橋は質問内容を書いた原稿を静かに読み始めた。
「・・・・・・時間がまいりましたので、これで質問を終わります」
「続きまして、自由改進党高橋覗君からの質問を始めます」
「高橋でございます。本日、私が質問したいことの第一点は、2016年度予算案のうち市債発行計画についてです。
財政部長にお聞きしたい。このように多額の債券を発行するとの計画ですが、セカンド・インパクトからの復興が
漸く終わりつつあるとは言え、国民の貯蓄水準は大きく低下したままなのはご承知だと思います。一体、誰がこの
第三新東京市債を消化するのですか? 私はそもそもこんなに多額の起債は無理なのではないかと思います」
「委員長」
「厳島財政部長」
「財政部としては、市の公金出納機関の新陽銀行による縁故引受のほか、国際機関による購入も想定しております」
「国際機関とは、一体どのよう先を考えておられるのか」
「国際連合が加盟国から納付された分担金を一時的に運用する対象として市債を購入したい旨申し出てきております」
「例のNERVが購入することはないのでしょうね?」
「只今の高橋議員の発言は適当ではないと思われるので、委員長職権により発言の撤回ならびに議事録からの削除を
命じます」
「口が滑りました。発言を撤回します」
「高橋君、今日の質問、なかなか切れ味良かったぞ。でもな、NERVのことはあんまり突つけないな。なにしろ
この街はNERVでもっているところがあるからな。」
「いくら市の行政運営を実質上、彼らのスーパーコンピューターが行っているとはいえ、行政を監督するのが
われわれ議員の役目じゃないですか。それも制限されるなんて、やりきれませんね。そう思いませんか、幹事長?」
「9月には選挙がある。今、彼らの逆鱗に触れるようなことは避けた方がいい。今は臆病者といわれてもそうした方
がいいよ。この困難な時代、君のような有能な議員がずっと市政に携わっていてくれないと困るよ」
「幹事長を困らせるつもりはないですよ。正論を声高に主張するには、私は汚れすぎています・・・」
「汚れているのはみんな同じさ。あの頃はみんな生きるのに必死だった。大質量隕石の落下、津波、地軸の移動、
戦争、そして飢餓・・・。21世紀に対して、私たちが抱いていた夢や希望は一瞬にして打ち砕かれた・・・」
「・・・・・」
「あの時、人類に残されたのは、希望の残骸だけだった。それをかき集めて、漸く今の繁栄を取り戻していったのさ」
「そうですね。生き残った我々ががんばって、子供たちには明るい未来を見せてやらないといけませんね」
「わかってくれたか・・・。ところで、質問も終わったことだし、この後、一杯どうかい?」
「すまみせん。今日は午後3時から新箱根湯本で会合があるんですよ」
「そうかい。じゃ、明日の晩はどう? 新赤坂に活魚料理の店ができたんだよ。もう行きたくてたまらなくてね」
「また、幹事長の魚狂いが始まりましたね。いいでしょ、いきましょう。」
高橋は第三新東京市庁を出ると新代々木駅に向かった。
事前の予想通り、彼の後に質問に立った野党議員が建設部長の収賄疑惑を追及、議会は空転し、今日は質疑は打ち切り
となっていた。
高橋は新代々木駅から第三新東京市環状線に乗り、新箱根湯本駅に着いた。
その時、駅構内のスピーカーが一斉に放送を始めた。
「只今、東海地方全域に特別非常事態宣言が発令されました。速やかにお近くのシェルターに避難してください。
繰り返します。・・・・・」
「またかよ。今度は、どこの国の偵察機が飛んでやがるんだ? 空から見たって、何もわからないぜ。兵装ビルは
みんな偽装されてるし、やばいもんはみんなジオフロントの中だからな」
高橋はじろりと天を一瞥すると、群集の後をゆっくりと歩き始めた。
「みんな、あのときのことを覚えているんだ。だから、宣言が出ただけで、こんなに素直に粛々と従うんだ」
彼はしばらく歩いた後、背広を電車内に置き忘れたことに気がついた。
「やれやれ、取りに戻るか。どうせ偵察機は爆撃なんぞしねぇから大丈夫だな」
彼は引き返して背広をとると、人気のなくなった改札を抜けて駅前に出た。
「まいったね、こりゃ・・・。シェルターはどこだっけ? 第三新東京市内なら全部頭に叩き込んであるんだが・・・」
彼は取り敢えず駅前を山の方に向かって歩き出した。
と、その時、駅前の公衆電話コーナーで人影が動くのが目に入った。
「ちょうどよかった。ここらへんのシェルターって、どこにあるんですか?」
「あの、その、実は僕も知らないんです。ずっと第2新東京に住んでて、初めてこの街に来たんです。」
まだあどけなさを残す、気弱そうな色白の少年は困惑した声でそう答えた。
「迎えが来るはずだったんですけど、まだ来てないみたいだし・・・・。やっぱり来るんじゃなかった・・・」
「おいおい、そんなこと言ってる場合じゃないでしょう。とにかくさがしてみましょう」
彼らは人気のない道を歩き始めた。シェルターの入り口は巧妙に偽装されているので、部外者にはよくわからない。
「迎えって、誰が来る予定なの?」
「あ、父の勤務先の女の人です」
「取り敢えず、その人のことを探してみた方がいいみたいだね。なんか手がかりあるかい?」
「ええ、写真が送られてきました。これです」
少年が差し出した写真には20代後半と思われる女性が写っており、胸の谷間にはペンで「ココに注目!」などと
書いてある。
「この人かい? よく知ってる人?」
「いいえ。面識はありません」
「・・・・・」
彼は写真をもう一度見た。そして、被写体が彼の知っている女性と似ていることに気がついた。
「まさか・・・」
「この人の名前は?」
「えと、葛城さんです」
「もしかしてNERVの?」
「はい」
「君もNERVの関係者なのか?」
「父が司令をやっています。」
「碇・・・さんか?」
「そうです。僕は・・・息子で、シンジといいます。」
高橋は平静を装うとしたが、顔が強張るのを押さえ切れなかった。
「あの碇の息子か。似てないな。」
彼は自分にとっては快くない、あの組織の最高責任者の髭面を思い出していた。
つづく。
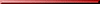
第2話に進むには、この を押してください。
を押してください。
「小説のありか」に戻るには、この  を押してください。
を押してください。
![]()
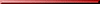
 を押してください。
を押してください。