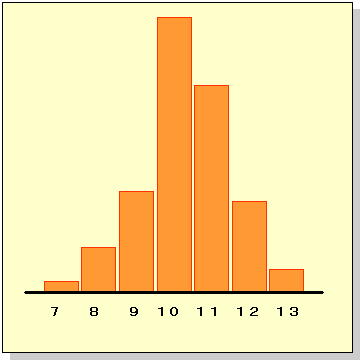素朴な疑問について調べてみよう
〜ミカンの房はいくつある?〜
対象年齢:小学校低学年以上。
統計学にこだわれば,中学生以上の研究課題にもなります。
毎年,冬になると,何気なく食べているミカン。
皮をむいて,房をちぎって,口に放り込んでいたとき,ふと思いついた疑問。
「ミカンの房って,何個?」
ミカンの花は,花びらが5枚。おしべはもっと多かったっけ……
ミカンの実の,私達が食べている部分って,子房の外側の「毛」みたいな部分に,果汁がたまって膨れたものらしいけど,その房の数は,どうやって決まっているのだろう?
なんとなく10個ぐらいあるような気もする……
あれこれ考えていても,結論は出ません。
調べてみましょう。
【用意するもの】
・みかん ……正確にデータを取るために,なるべく大きさにばらつきが無いように選びましょう。M玉とかS玉とか,調べるミカンのサイズ決めておくと良いでしょう。
・メモ ……ひたすらメモを取ります。あらかじめ表を作っておいて,数字だけ書き込むようにすると便利。
【観察しよう】
ひたすら,ミカンを食べたときに,房の数を数えて記録してゆきます。
家族の人達に協力をお願いすれば,より多くのデータが集まります。
…で,実際に調べてみました。
調査期間は2007年11月から2008年3月。
うんしゅうみかんのS玉について,房の数を数えました。
調べた数は66個。
房の数の最低は7個,最高は13個。
平均値は10.3個。
度数分布グラフを作ってみます。
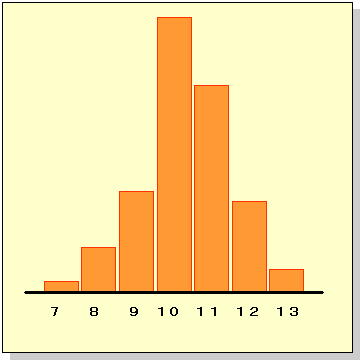
お,きれいに正規分布しているようです。
グラフを見ただけでも,10より少し多いかな,と言うのが見えると思います。
注)これを丸々コピーして自由研究や「しらべ学習」に使うことの無いよう,グラフの縦軸は,あえて省略しています。
自分で調べるのが「しらべ学習」です。手抜きしちゃダメですよ。
高校生以上なら,統計を学んでいるはずですから,もっと詳しい解析ができると思います。
ミカンに限らず,いろんな数字を調べてみると,面白いですよ。
【もう少し観察してみよう】
「統計」をもっと身近に感じて遊んでみましょう。
学校で学ぶ確率論や統計学は,「サイコロの目」だったり,赤い玉と白い玉の混ざって入っている袋から玉を取り出すときに,どっちの色が何割の確率で出るか,みたいな話を例題にしているのが多いのですが,少なくとも私は,ちっとも面白くなかった。
自然界の中で起こる現象を観察,測定して,統計によって,それがどんな意味を持つのか考えてみる。
自然を知るための道具として,統計学は有力な武器になるのです。
ミカンに限ったことではありません。いろいろなことを調べて,統計を取ってみましょう。
自然観察では,こんなテーマはどうですか?
・セミのたくさん鳴く時刻はいつ?セミの種類によっても違う?
・クビキリギスの鳴く夜と気温の関係は?
・アサガオやオシロイバナの花の開く時刻と,日の出,日の入りの時刻の関係は?
……
さまざまなことが,観察と統計でわかってきます。
→「身近な自然で遊ぼう」目次へ
→Home