・とにかく,鳥のいる場所に出かけましょう!
・鳥の図鑑(ずかん)や,羽を入れるふくろを用意しましょう。
【観察しよう】
ちかくの公園におちていた羽。長さは3cmぐらい。
大きさや色やかたちから,どんな鳥の,どこの部分の羽か,考えてみましょう。
……これは,スズメの羽。
じゃ,スズメのからだのどこにあった羽?
そのヒントは,羽のかたちにあります。
羽をひろおう!
対象年齢:小学生未満からOK!
鳥の羽って,ときどきおちていますよね。羽1枚だって,「自然からのメッセージ」。鳥の羽だけでも,いろんな観察ができます。冬に,カモのあつまる池に行けば,きっと,たくさん羽がおちていると思います。羽をあつめて,じっくり観察してみましょう。
【用意するもの】
・とにかく,鳥のいる場所に出かけましょう!
・鳥の図鑑(ずかん)や,羽を入れるふくろを用意しましょう。
【観察しよう】
ちかくの公園におちていた羽。長さは3cmぐらい。
大きさや色やかたちから,どんな鳥の,どこの部分の羽か,考えてみましょう。
……これは,スズメの羽。
じゃ,スズメのからだのどこにあった羽?
そのヒントは,羽のかたちにあります。
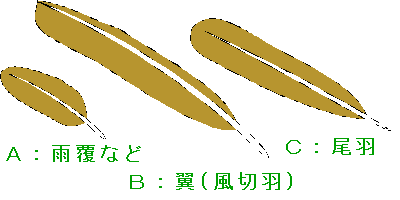 |
| 注) 雨覆(あまおおい)とは,翼(つばさ)をたたんだときに,翼の上にくる羽 |
Aのタイプの羽は,やわらかいものが多くて,短いものが多い。
Bのタイプの羽は,羽の軸(じく)が,かたよっていて,ふとい。ちょっとアーチ型にまがっている。
Cのタイプは,ほとんどまっすぐ。軸はしっかりしているけれど,Bのような「かたより」はない。
……つまり,鳥の羽は,はえている場所や目的によって,ぜんぜん,かたちがちがうのです。
もちろん,鳥の種類によっても,羽のかたちは,すこしずつ,ちがいます。
上から,ドバト,ヒヨドリ,オナガガモの尾羽…つまり,「しっぽ」の羽です。
ちがうようにみえますか?にていると思いますか?
でも,まっすぐで,軸が真ん中をとおっている,というデザインは,いっしょですね。
…さて,冬になると,町の中の公園の池にも,カモが冬ごしにやってきます。
ほとんどのカモのオスは,冬のはじめに日本にやってきてから,羽がはえかわっています。
(翼の羽や尾羽は変わりませんが…)
ですから,冬,カモのいる池に行くと,いろいろな羽がひろえるチャンスがあります。
キミも名探偵になって,ひろった羽から,誰の落としものか,推理(すいり)してみよう。
公園でひろったオナガガモの羽。こんなところから落ちたらしい。
それではもうひとつ,羽のやくわりをかんたんに見わけるテクニックを教えましょう。
……それは,羽を投げてみること!
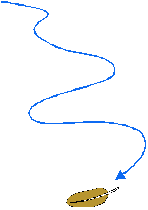 |
鳥の飛行にあんまり関係ない羽 ……胸やおなかの羽などは, 投げてもフラフラ落っこちるだけ。 |
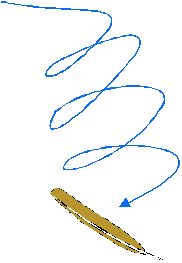 |
翼の羽は,クルクルよく回りながら, 落ちてゆく。 |
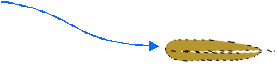 |
尾羽は,紙ひこうきのように飛ばすと, うまく,ス〜っと飛んでくれる。 |
胸やおなかの羽は,からだを冷やさないため,水をはじくためのジャケットだから,風を切るデザインではありません。
翼の羽は,はばたいたときに空気を羽のうしろのほうに押し出すようになっています。これに風をあてると,空気を押し出す力を出す部分が,しっかりと風をうけとめるので,プロペラのようにまわってしまいます。
尾羽=しっぽの羽は,飛行機のうしろについている「尾翼(びよく)」とおなじように,空気のながれをまっすぐにととのえるやくめがあります。ですから,尾羽を投げると,風を切って,ス〜っと前へ飛んでゆきます。
【もう少し観察してみよう】(ちょっとくわしい説明)
ふだんは手で触ることの出来ない野鳥。
その中でも,羽は,いちばん気軽に触れることの出来る,野鳥のパーツです。
特に小さいお子さんは,遠くから望遠鏡や双眼鏡で見るだけの観察では,飽きてしまうことも多いのですが,そんなときの「お助けアイテム」として,私はよく「拾い物」の観察を始めます。水鳥のたくさんいる公園なら,羽もたくさん拾えます。子供達に袋を持たせて,羽を集めて,「これは誰が落とした羽かな?」とクイズで迫ったり,たくさん羽が拾えたときは,両面テープを持ち出し,誰か1人に「鳥モデル」になってもらって,どの辺にくっついていた羽なのか,想像しながら,腕や背中に拾った羽をペタペタ貼ってゆきます。翼の,いちばん大きな羽(初列風切)が,人間で言えば指先のほうについていたんだ,とか,ちょっとした「比較解剖学」にもなっているんです。こんな演出で,実際に泳いでいる水鳥への興味が広がったり,図鑑をていねいに読むようになったり,知らず知らずのうちに,観察する力がついてゆくように感じます。
鳥の羽が拾いやすいのは,冬の水鳥だけではありません。
多くの場合,繁殖期が終わった頃に,野鳥は「換羽(かんう)」に入ります。1年間使ってきた羽を着替えるのです。
8〜9月頃のバードウォッチングの観察ネタに,「羽拾い」をしてみては,いかがでしょう?この時期だと,セミの翅などもあるので,けっこう,拾い物だけで,いろいろな観察が出来ますよ。
これはオオタカの羽。都区内で拾ったものです。
こういうものにめぐり会えるから,羽拾いは楽しいのかも…。