「ノルウェー王の率いる、ヴァイキングの大船団3百隻が、ノーザンブ
リア東海岸を南進中」
との情報が、ロンドン滞在中のハロルド王の許に届いたのは、9月
19日であった。
丁度、フルフォード街道の大激戦が火蓋を切る直前であった。
知謀優れた軍略家でもあったハロルド王は、
「南下するヴァイキング軍団が第一の攻撃目標とする処はヨーク市
であろう」
と、判断した。
そこで、彼は南部の海岸に配置していた精鋭の家臣団を、直ちにロ
ンドンに招集した。
ハロルド軍団の中堅を占める家中戦士(ハウス・カール)や、幹部の
小領主(セイン)らは騎乗していた。だが、大部分の兵は歩兵であっ
た。
ハロルド王は、ロンドンに集結した歩兵軍団約1万名を閲兵し、訓示
を与えた。
「皆の者、よく聞け!
我々の国イングランドは、今、ノルウェー・ヴァイキングのハードラダ
苛烈王に侵略されんとしている。ヨークを守るモルカール伯は、危機
に面している。
余は、国王として、このヴァイキング共を放逐せんと決断した。
今からヨークに進軍する。一刻を争う国家一大事である。全軍駈足で
余に続け!」
と、号令した。目的地は、ヨーク市である。
王妃アルドギーサの兄モルカール伯を支援するというよりも、北方か
らの侵略者を駆逐することが王としての北進の名分であった。
ハロルド軍団は、その昔ローマ軍団が建設した、イングランドの主要
都市を直線で結ぶ軍用道路(通称ローマン・ロード)を、ヨーク市目指
して急ぎに急いだ。
全軍、ひた走りに走った。
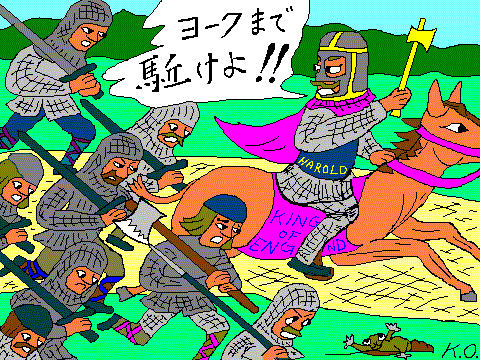
しかし、彼らがヨーク市に到着した時には、フルフォード街道の戦は
既に終っていた。
だが、ノルウェー王の軍勢が、人質を受取るためにスタンフォード橋
に待っているとの報告を受けて、ハロルド王はニンマリと微笑んだ。
「ヴァイキング共は、よもや余がヨーク迄進軍して来るとは思っては
いまい。
油断しているに相違ない。リッコール村の上陸地点から、随分離れ
ているスタンフォード橋で人質を受取るとはな。兵力は二分されてい
る筈だ。
皆の者。直ちにスタンフォード橋を急襲するぞ!」
息つく間もない厳しい命令であった。
ハロルド王の戦略は、まづ大軍団を迅速に移動させ、敵の意表をつ
いて出現し、相手の兵士の気勢を削ぐことを狙いとしていた。この電
撃作戦は完全に成功した。
風林火山――名将武田信玄が「軍を動かすに際しては、疾きこと風
の如く」と実行したように、ハロルド王の軍事行動もよく似ていた。
ノルウェー王ハラルド・ハードラダは、ダーウェント川の両岸に散開し、
思い思いの恰好で休息をとっている配下の兵を、急いで東岸に集め
るように隊長達に命じた。
水浴中の兵は真裸であった。牛や羊を追って遠くに出掛けた兵士達
は、非常呼集の法螺貝(ほらがい)の音を聞いた。が、駈けつけるに
は遠かった。
東の丘を越え、更に東の丘陵地へと観光見物に出掛けて、木蔭で昼
寝をしていた兵もいた。甲冑を着ける間もなかった。武装も不十分な
ままに、陣形を立てねばならなかった。
緊急作戦会議が開かれた。
「ハードラダ王、一旦リッコール村に退いてはどうであろうか。我が軍
は、此の地では全軍揃っていない。人数も軍備も劣っている。
ハロルド王配下の家中戦士には、平地での戦では苦戦はまぬがれ
まい。船に帰れば、いかにハロルド王といえども、簡単に攻撃を仕掛
けてくることは難しかろう」
と、トスティ卿はハードラダ王に進言した。
「いや、敵に背を見せて逃げれば、リッコール村に辿り着く前に、あの
騎乗武者どもの餌食になるのが落ちだろうよ。今となっては、此処で
一戦交えて、雌雄を決するほかに道はなかろう」
と、ハードラダ王は決戦の覚悟を語った。
リッコール村の本陣に残っている軍勢を呼ぶ間はなかったが、とも角
伝令を走らせた。
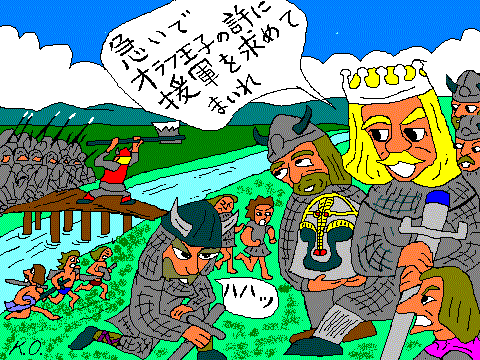
スタンフォード橋は、人が3、4人やっと通れる位の、幅の狭い木橋で
ある。川の西岸にいた兵士達が、一気に渡れる幅はなかった。
ハロルド王の軍団は、西岸沿いに攻めて来たので、結果としてヴァイ
キングの勢力を更に二分した形となった。
東岸の本陣で、ハードラダ王とトスティ卿が懸命に防衛陣を作ってい
る間、西岸のヴァイキング達は、不十分な武装のまま1万余名のアン
グロサクソン歩兵軍団と渡り合わねばならなくなった。甲冑も着けず
に、殆ど裸に近い姿で腰の短剣を抜いて戦った。
いかに戦いなれているとはいえ、相手は十分に武装している精鋭の
ハロルド軍団である。家中戦士達の攻撃には、ひとたまりもなかった。
それでも、ヴァイキング達は勇敢に橋を守り、主君ハードラダ王が陣
形を立て直す時を稼いだ。
ヴァイキングの中に、「赤雷鳥」(レッド・サンダーバード)と呼ばれる、
頭が良く、武芸の心得もある若者がいた。
その名はエリック・ウルフサン。大斧の使い手としてノルウェーでは高
名であった。
彼も、家畜を追って西岸に渡っていた。が、いざという揚合に備えて、
鎖帷子(くさりかたびら)を脱がずに、大斧を携えていた。
橋の西岸を必死に守るヴァイキング達が、一人また一人と斃されてい
った中にあって、若武者エリックは阿修羅のごとく奮戦したが、遂に西
岸を守る最後の一人となった。
彼は、狭い橋の中央に、両足を踏んばって、立ちはだかった。
「さあ、アングロサクソンの農民兵共よ。勇気ある者は突込んでみよ。
この大斧が、喜んでお相手しよう」
と、得意の大斧を、あたかも水車のように振り回した。
彼は、次々と突撃して来るアングロサクソン兵40数名を倒した。
ハロルド軍団の先鋒は、橋の真中で大斧を振り回すこの若武者に手
を焼いた。
「見よ!敵ながら天晴れな武者振りよのう」
「だが、何としてもこの橋を突破しなければ、敵の陣立てが出来てしま
う」
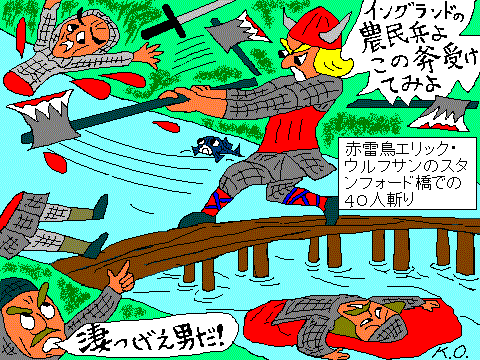
一計を案じたアングロサクソンの部隊長は、部下に命じて近くの岸辺
に小舟がないかと、丹念に捜させた。
ようやく、葦の間に乗り棄てられていた小舟を見付けた。舟といっても
盥舟(コラクル)である。人がやっと二人乗れるほどの小舟である。
部隊長は、槍武者を乗船させて、そっと橋の下に近付けるよう命じた。
丸太を粗く並べた田舎の橋である。いくつもの隙間があった。
橋の上では、ヴァイキングの若者「赤雷鳥」エリック・ウルフサンが、相
変らず勇気凛々として大斧を振り回していたが、その足許に盥舟が近
付いているとは気がつかなかった。
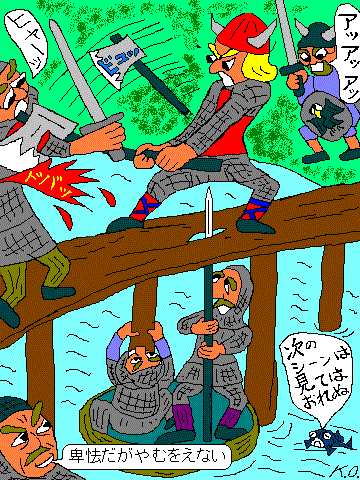
アングロサクソンの槍武者が、狙いを定めて、橋桁の下から突き上げ
た槍の穂先に、さしもの豪勇を誇ったエリックも串刺しになった。
「卑怯なり!無念なり!」
絶叫を残して、彼は血を吐き、息を止めた。
スタンフォード橋の緒戦は、奇襲したハロルド王指揮下のアングロサ
クソン軍団の勝利で始まった。
東岸の丘の上では,ハラルド・ハードラダ王が、気忙しく陣立てを進め
ていた。
王は、楯を持っている兵士を二列横隊に並ばせ、槍を持たせた。
次に、その両端を折り曲げるような形で後退させた。背後の方で、右
端と左端の兵が隣り合った。
見事な楯の円陣ができた。楯の二重壁である。その円陣の中に僅か
の弓隊を入れた。
武装不十分の兵も這入った。
円陣の中央に床机を据えたハードラダ王は、橋を渡って来るハロルド
軍団を睨んでいた。
「前列の兵、片膝つき中腰!」
「槍を大地に斜めに立てよ!」
「後列の兵!前列の兵の楯の隙間に、槍を構え、敵が攻め来れば、
水平に突き出せ!」
と、号令した。
特長のある原色の飾り文様をつけたヴァイキングの円い楯は、上下
二段に、あたかも魚鱗のように重なり合っていた。鱗の隙間から突き
出た槍は、「針千本」と呼ばれる
全身に鋭い辣のあるハリフグのようであった。
固い槍衾(やりぶすま)ができた。
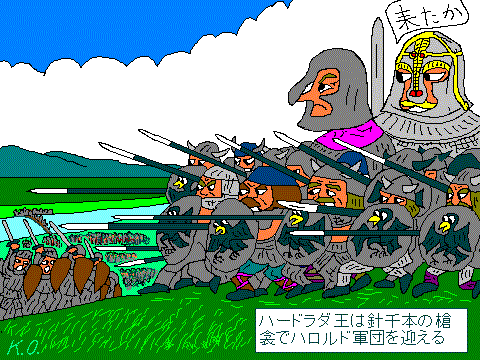
その間にも、ハロルド軍団は、橋を渡り、なだらかな丘の下手に陣を
取った。
両軍は動きを停止した。
ノルウェー軍団には、つい先刻までの、のんびりとした底抜けの明る
さはなかった。
不意打を食った。十分な武具を準備していなかった。更には兵力で
も劣っていたことなどから、陣内には一転して厳しく悲愴の気配が流
れた。
嘘のような沈黙の睨み合いが続いた。
この張りつめた雰囲気を破るかのように、アングロサクソン軍ハロルド
王の中央戦列から、軍使の旗を押し立てて、20騎の華やかな装束の
騎士が現われた。
彼らは、一列横隊に馬首を揃え、足並みを合わせて乗り出して来た。
ヴァイキング達は、騎士の動きに見惚れた。
20騎が停った。
その真中から、赤い楯に黄金の手斧を持った一騎が、数歩前へ進み
出た。
「トスティ卿は、いずこにおわすやぁ――。兄君ハロルド王には、殿下
を殺すに忍びずとのお考えなり。
降伏すれば――命を助けた上、再びノーザンブリアの一部を頒ち与
えようとの申出なり。如何なりやぁ。すみやかに決め候え!」
と、大音声で叫んだ。
「トスティは此処にあり!申出の条件はしかと承知したぁ。
しかし、ノルウェー王、ハラルド・ハードラダ殿には――何を引出物と
される所存なりやぁ」
と、この騎士に質ねた。
「イングランドの大地7フィートだぁ。
もっとも――ハードラダ王は特大の男なればぁ、もう少し余計に墓地
が要るかもしれぬがぁ」
と、この騎士は音吐朗々と答えた。
トスティ卿は、
「男子一旦ノルウェー王と盟約を結んだからにはぁ、ノルウェー王ハラ
ルド・ハードラダ殿と運命を共にしてぇ、最後まで戦う決心である――。
降伏する位ならあ、我は死を選ぶ!」
と、黄金の手斧を持つ騎士に叫んだ。
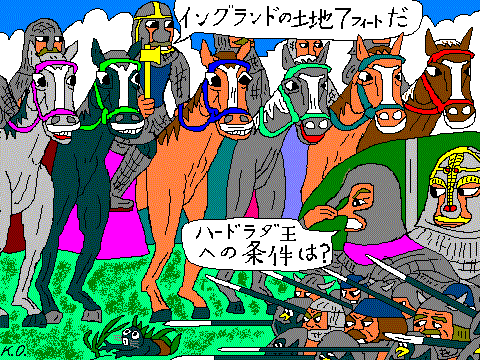
軍使一行が引き返した後に、トステイ卿は、ノルウェー王に、
「何を隠そう、実は今の軍使は、わが兄ハロルド王自身であった」
と、打ち開けた。
今にも血生臭い嵐の吹かんとする戦場で、敵味方に別れた肉親の兄
弟が、心を通わせた一瞬であった。
もしトスティ卿が「軍使はハロルド王その人だ!」と叫べば、ノルウェー
軍の最前線の兵は、軍使の旗を無視して、一斉に矢を射、襲いかかっ
ていたかもしれない。
軍使の一行が、踵を返して自軍に帰り着いた時に、戦の火蓋は切ら
れた。
ハロルド王の黄金の手斧が一振りされるや、アングロサクソン歩兵軍
団が、槍をしごいて丘の斜面を登って来た。
その後には半弓隊が続いていた。
弓の一斉射撃に続いて、歩兵の攻撃が始まった。
5日前、フルフォード街道の戦で勝利を得たとはいっても、ノルウェー、
フランダース連合軍は、相当の死傷者を出していた。この丘の陣営に
も、軽傷者は沢山いた。
武器の携帯も十分ではなかった。固い楯の陣を構え、防戦に努める
ほかなかった。
ノルウェー軍の弓隊は、矢筒に残っている僅かばかりの矢を慎重に
射って、善戦した。
ハロルド軍は、楯の間から突き出される槍に苦戦した。
ハロルド王は、第一線の指揮官を集めた。
「よいか、総攻撃を仕掛け、揉合いの後に、号令一下、見せかけの敗
走をする」
と、打合せた。
激しい攻撃が仕掛けられた。その真最中に、アングロサクソン全軍に
退却命令が出た。
円陣の中で、うずうずと防戦一方に回っていたヴァイキング達が、ドッ
と喜んだ。
ノルウェー軍の固い楯の陣が、あちこちで開かれ、腕白慢のヴァイキ
ング達が打って出た。
「待て!追うな!」
陥穽(かんせい)と読み取っていたハラルド・ハードラダ王は懸命に声
をかけたが、勢に乗ったヴァイキング達の耳に届かなかった。
待伏せしていたハロルド王の遊軍が、バラバラのヴァイキング達を取
り囲み、混戦模様の肉弾戦になった。
こうなっては、ハロルド王の軍に有利であった。
金髪の巨人、苛烈王と呼ばれた豪勇のハラルド・ハードラダは、巨大
な剣を振りかざし、先頭に立ってハロルド王に肉薄したが、今一歩の
ところで矢を咽喉に受けて、遂に落命した。
すかさず、トステイ卿が、王に代って、本営の軍旗の下に立ち、全軍
を指揮した。
血を分けた兄弟の、文字通り骨肉の争いであった。激戦が続いた。
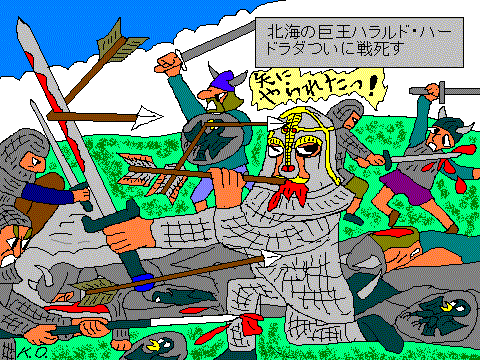
イングランド王ハロルドは、再び停戦を命じた。
ノルウェー王が戦死した今、いかにノルウェー軍と同盟を結んでいる
とはいえ、実弟トスティ卿まで殺すには、肉親の情としてしのびなか
った。
白旗を高々と掲げた、停戦交渉の軍使が出された。
だが、トスティ卿は、兄ハロルド王の折角の申出を再び拒絶した。
彼としては、実兄ハロルド王に、一矢を報いるための挙兵であった。
いかに血を分けているとはいえ、否、血を分けていればこそ、憎悪も
深かったのである。
「余は、血の一滴が無くなる最後の最後まで戦ぅぞ!たとえ此の地で
討死しようとも、わが魂魄(こんぱく)は必ず兄に復讐するぞ!」
と、トスティ卿は軍使に答えた。
「我々もだ!エイッエイッ、オウッ!」
傷ついたヴァイキングやフランダースの兵は一斉に叫んだ。
再び肉弾戦が続けられた。
アングロサクソン軍の弓隊が前に出て、一斉射撃を行なった。
さしものトステイ卿も、数本の矢を身体に受けて戦死した。
ヴァイキングの敗色は歴然としていた。
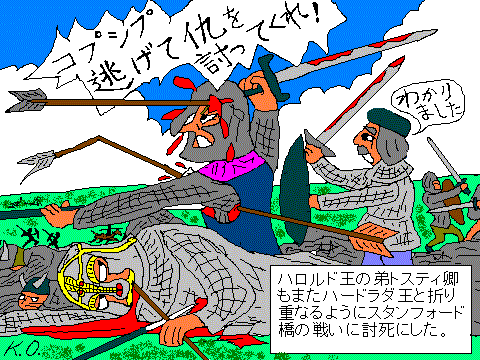
リッコール村の軍船に残っていた3千名のヴアイキング達は、伝令の
知らせを受けて驚いた。オラフ王子を応援隊長として、直ちに甲冑に
身を固め、駈けつけた。
しかし、9月とは思えぬ酷熱の太陽に、まだ癒えぬ手傷は痛み、重た
い甲冑のために疲れていた。いかに勇猛なヴァイキングとはいえ、人
であった。士気は高かったが、駈けに駈けた肉体の疲れはひどかっ
た。
ようやくスタンフォード橋に到着したものの、敗勢の仲間を盛り立てる
カとならずに、彼らもまた次々と討死していった。
祖先の時代から、長い間ヴァイキングに苦しめられて来たアングロサ
クソンの農民兵達は、勝に乗じて、ヴァイキングを嬲(なぶり)り殺しに
していた。
遂に、ノルウェー王子オラフは、ハロルド王に降伏を申出た。
ハロルド王は、黄金色の手斧を高々と上げて、全軍に停戦を命じた。
部将の中には、
「王子オラフを斬り、ヴァイキング全員を死刑とし、軍船を焼き棄つべ
し」
との強硬論を吐く者もいた。
しかし、ハロルド王は、これ以上の殺傷は不要と判断した。
彼は、オラフ王子の命を助け、臣従を誓わせた。そして、ハラルド・ハ
ードラダ王の遺体を、リッコール村に繋留している旗艦「ドラゴン」号に
運ばせた。
オラフ王子と、生き残った僅かの部下は、ハロルド王の温情溢れる騎
士道精神の一端をはじめて理解した。
彼らは、陽に焼けた髭だらけの顔を、くしゃくしゃにして、滂沱(ぼうだ)
の涙を流しながら、ハンバー河を北海へと漕ぎ去って行った。
何世紀もの間イングランドの海岸部を、我物顔に荒らし回ったヴァイキ
ングが、カにおいても、精神においても、完膚なきまでに敗れ去ったの
である。
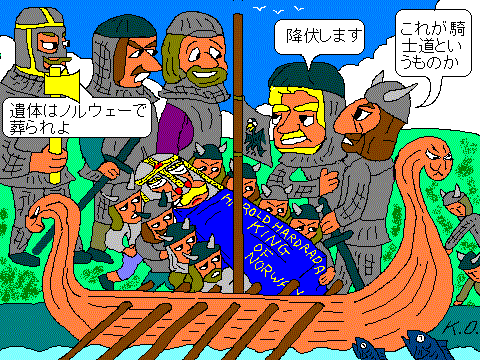
弟トスティ卿も手厚く葬られた。
しかし、ハロルド王配下の精鋭軍団も、精根疲れ果てていた。
イングランド南部ウェセックスやケントの海岸警備からロンドンに戻り、
更にヨークまで、3百マイルを駈けに駈け、走りに走った。その上、一
日中戦った疲れがドッと出たのであった。
兵士達は勝鬨(かちどき)をあげるや、ゴロリと大地に横になって、貪
るように深い眠りについた。
その夜ハロルドは眠れなかった。弟トスティのことを想い、胸中そくそ
くとしていた。
何気なく満天の星空を見上げた彼は、中天から南の地平へ向って、
大きな流れ星が落ちるのを見た。
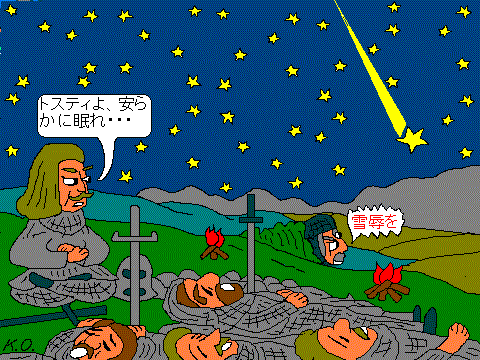
偶然であろうか。この大きな流れ星を、ヒースの薮陰に寝ころんで見
た男がいた。
トスティ卿の家老コプシプである。彼の目尻には、涙がうっすらと流れ
ていた。
主君のトスティ卿が戦死したのを見て、彼は、その恨みを晴らさんと再
起の決意を固めた。手勢の部下数名と命からがら戦線を離脱して来
たのである。
夕闇と、丘を覆うヒースの薮が、彼等の逃走を助けた。
家臣達は、いずれも刀槍の傷を負ってはいたが、ハロルド王の包囲
網を突破し、追手をたじろがせた強者達であった。彼等は、コプシプ
の傍に高鼾(いびき)をかいて横になっていた。
風が、ヒースの荒野に吹き走った。コプシプは、目を閉じた。
翌朝、太陽が昇った時には、もはやその薮陰に人影はなかった。
第17章 ノルマン軍団の上陸
いざないと目次へ戻る
「見よ、あの彗星を」Do You Know NORMAN?へ戻る
ホームページへ戻る