第17章 ノルマン軍団の上陸
サン・バレリー港に立ち、キッと双眸を海峡に向けているノルマンディ
公ウィリアム。1027年生まれ彼は、男として脂の乗りきった39歳で
ある。
機智に富み、本能的に危険と安全を嗅ぎ分ける動物的感覚に秀で
ていた。
集団を指導し、統率する力では、抜群の才があった。
ハロルド王とウィリアム公は、残るべくして残り、戦うべくして戦う宿命
を担った英仏両国の誇りとする英傑であった。
そのウィリアム公は、じつくりと満を持していた。風を待っていた。まだ
北の風であった。その風待ちのため士気に弛みが出た。
彼は、従軍牧師を呼んだ。
「エドモンド聖人の聖骨を、サン・バレリーの教会から海岸へ運び出せ。
海岸に祭壇を設け、ローマ教皇から下賜された聖ぺテロの旗幟を立
てよ。そこで、汝等は風向きを変える祈祷をせよ」
牧師達は驚いた。
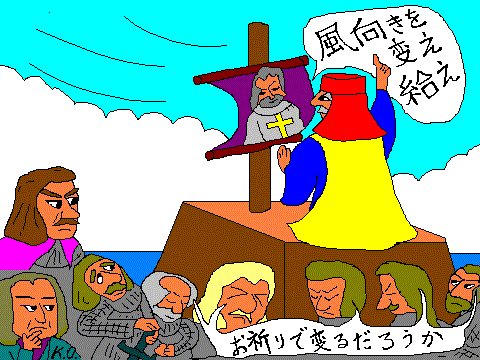
祈祷で風向きを変えることなどどうしてできようか。自分たちの祈祷が、
どれほど利いているのか利いていないのか、内心よく承知しているの
は牧師自身であった。口に出せば、折角の地位を免職させられるば
かりか、斬首されることにもなりかねない。
「わかりました。すぐにお祈りいたします」
見晴らしのよい海岸に、祈祷の祭壇が準備され、街中の聖職者達が
招集された。
翌日、早朝から祈祷が開始された。その祈祷の最中に、風ははたと
止まった。そして、次に吹いて来た風は南西の方向からだった。
「風向きが変わったぞ!」
「南西からの風だ!」
「すぐに南の風になろう」
「お祈りの甲斐があった」
「神は、我々に味方されているぞ――」
どよめきが、祭壇の周囲から街中にと、潮のごとく伝わり、歓声が溢
れた。
最も吃驚したのは、内心困惑しながら祈祷していた牧師達であった。
実は、巧智に長けたウィリアム公は、諜者の元締めとして重用してい
る側臣ウォルターに、気象情報の入手を命じていた。
サン・バレリーに碇泊している間に、ウォルターは、天文学者や漁師
や、老練な船乗りなどに、ひそかに手を回して、そろそろ風向きが変
るという情報を得ていたのである。
祈祷は、いや祈祷という演出は成功した。ノルマン兵はもとより、金が
目当の外人傭兵までもが、〈聖ペテロの旗幟を掲げるウィリアム公に
は神が味方している〉という自己暗示に、完全にかかっていた。再び
士気が統一された。むしろ、神がかりのような雰囲気が高まってきた。
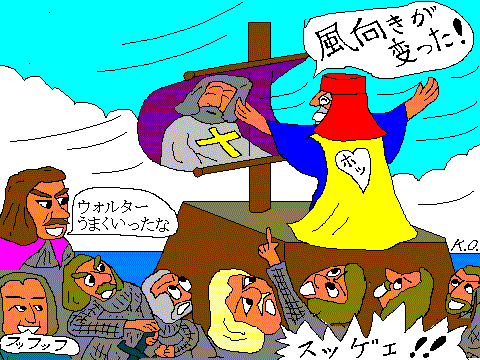
9月23日――
イングランド海峡を渡って、新しい情報がも斎された。
「ハロルド王は、ノルウエー王との決戦のために、大規模な歩兵軍団
を率いて、ヨーク市へ進発しました。ウェセックスの海岸は、今はガラ
空きです」
「本当か?」
と、ウィリアム公は身を乗り出した。
ウィリアム公にとって、今回の敵前上陸作戦を成功させる鍵となるの
は、何千頭もの乗馬の輸送問題である。
人間ならば、多少の風浪を我慢できよう。だが、船には慣れていない
馬の輸送は
やっかいである。できるだけ短い時間で渡航を終了させたい。また馬
の陸揚げの時に、敵に襲われたくなかった。水際での交戦はできるだ
け避けたかった。
風も時機も、まさにウィリアム公の願う通りとなった。
まさに、ツキにツイている男であった。
9月26日――
「乗船準備!全軍海岸待機!」
伝令が、各部隊の間を走り廻った。
9月27日――
「乗船!」
夕刻、全員乗船完了。
直ちにサン・バレリー港を出航した。
上陸作戦を日中に展開するには、夜行せねばならぬ、と計算された
からである。
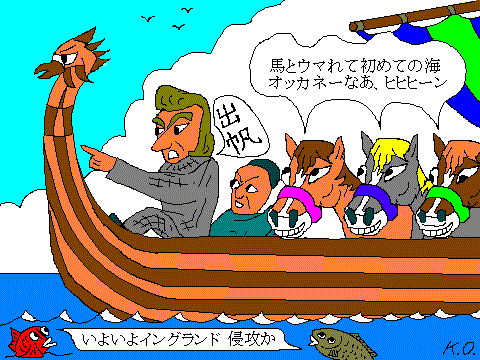
全船のマストに、目印のランプが灯された。船と船との連絡のために
赤い信号灯が、絶えず海面に振られた。
海面は、まさに光の洪水であった。
光の洪水から離れぬ限り、船団から落伍することはない。
騎士達は、去りゆくサン・バレリーの町の灯火を、感慨深げに眺めて
いた。
ノルマンディの山野を駈けめぐり、幾度かの修羅場を潜り抜けて来た
猛者揃いではあったが、夜の輸送船は苦手であった。彼等は、胴の
間に降りると、戦勝の景気づけにと酒杯を傾け、蛮声を張り上げて、
民謡や、卑猥な歌を大合唱した。
ウイリアム公の乗船した旗艦には、「モラ」という船名がつけられてい
た。「モラ」とは、ラテン語で「遅延」という意味である。ところが、実際
にはこの船が船団の中で最も快速であった。
この機智に富んだ命名者は、誰あろう、留守居の公妃マチルダである。
「モラ」号は、快調な船足であった。常に先へ先へと船団をリードして
行った。
全船、順風を帆一杯に受けて、綱も切れんはかりに脹み、舳先は波
を蹴立てて、
南インクランドの海岸を目指して、まっしぐらに進んで行った。
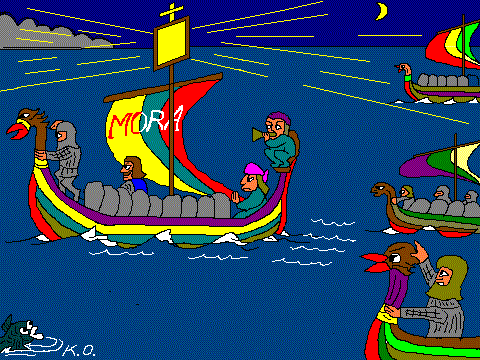
「少し速すぎましませぬか。後続の船団の汀が、だんだん遠去かりま
すが――」
と、船長が不安気に尋ねた。
「なーに構わぬ、構わぬ。最高速度で進め」
ワインを飲みながら、ウイリアム公は船長になおも突進を命じた。
遂に灯は全く見えなくなった。
夜の海に旗艦のみが白波を蹴立てていた。
船内の酔吟も止んでいた。
「ウワッハッハッ、皆の者少し酔がさめたと見えるな。心配することは
ない。オイッ、船長、船を止めよ。一寸酒盛りをやり直してりゃあ、の
ろま共が追いついてくるだろう」
と、彼は停船を命じた。
「お前達、そう心配せんでも大丈夫だ。それ酒を飲め、歌を歌え」
と、ウィリアム公は平然としていた。
暫くたって、水夫が叫んだ。
「お味方の船団が追いついて参りました!」
「ウォッ」
と船内は、再び活気が溢れ賑やかになった。
「それにしても、殿の胆の据わっていることよのう」
「御大将は流石に豪の者よ」
と、家臣達はウィリアム公を頼もし気に仰ぎ見た。
9月28日――
日がさした。遥か故郷のノルマンディより昇る旭光を背に船は水を切
って進んだ。
天気晴朗こして波浪高からず。快調な船足こ、人馬ともども上気嫌で
あった。
騎士や従卒たちは、愛馬の鬣(たてがみ)を撫でながら、こみ上げてく
る興奮を抑えようとしていた。行手には、すでにイングランドの陸地が
見えていた。
大船団は、熱気を孕んで接近していった。遂にサセックスのペペンジ
ー湾に入港したのである。点呼をとってみると、僅か2隻が行方不明
になっていただけである。夜の渡航としては大成功であった。
何事にも慎重なウィリアム公は、ウォルター輩下の間諜組織を駆使し
て、事前に上陸地点の調査を終了していた。
ペペンジー湾は、イングランド海峡に対して東南に弓状に展けており、
ノルマンディから乗り入れると、真直に懐に飛び込むような位置にあ
る。しかも、一面の砂浜地帯である。大軍団が一斉に上陸するには、
絶好の条件を備えていた。
かつて、ローマ帝国がブリテン島を支配していた紀元前300年から
250年頃にかけては、彼らもペペンジーを上陸地点とし、広大な城
壁を回らした軍団基地を設けていた。海峡を渡って来たローマ軍の
巨船は、直接この基地の城門に乗り入れられたと伝えられている。
だが、海岸線は長年に亘って、次第に変化し、ローマ時代の城は内
陸奥深く取り残されて、軍事上重要視されなくなり、廃虚となって、荒
れるにまかせていた。
ローマ軍団と同様に、ウィリアム公もこの砂浜地帯を上陸地点に選
んだ。海岸にはハロルド王の軍勢は全く見当らなかった。
ハロルド王は、地方の郷土達に、昼となく夜となく、海岸を見廻るよう
に命令していた。郷土達は、春先以来、忠実に警戒を怠らなかった
が、夏が過ても船影一つ現われないため、ついつい気が緩み油断
をしていた。
突如、海面を埋めるように現れた大船団を見て、村人達は慌てふた
めいて、森へ逃げこんだ。
早速、上陸が開始された。文字通り無血上陸である。
最後に、総司令官ウィリアム公が上陸した時、ちょつとした騒ぎがあ
った。
彼が船から飛び下りた際に、砂浜に足をとられ、ヨロヨロッと前へつ
んのめって、顔中砂だらけになってしまった。
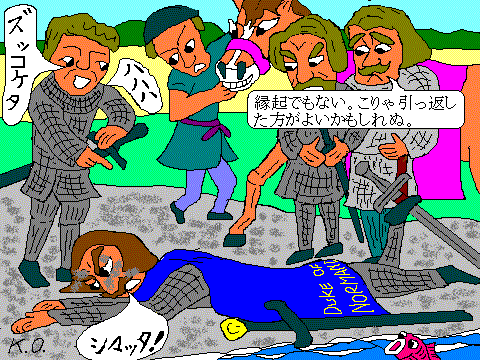
ドッと軽蔑の笑い声とざわめきが、将兵の間に起こった。
「縁起でもない。総大将が上陸の時にひっくり返るなんて!」
「そうだ。これはひっくり返した方がいい」
「そんな洒落をいっている場合じやない。本当にノルマンディに引き
返した方がいいかもしれないな」
一瞬のうちに、全軍の空気を察したウィリアム公は、すっくと立上ると、
両手を高々と掲げ、あらん限りの大音声で叫んだ。
「見よ!皆の者!余はすでに、イングランドの地を、誰よりも先に、こ
の両手にしっかりと握ったぞ!」
彼の掌には、砂が一杯握り込まれていた。
騎士達は、単純な気性の持主であった。
このウィリアム公の機智に、ドッと拍手を送った。
これを見て、フイッツ・オズバーン卿はサッと皆の前に出、間髪を入
れずに、
「いざや!我らも続かん!エイッ、エイッ、オウッ!」
と、気勢をあげた。
「エイッ、エイッ、オウッ!」
全員が、無事敵地に立った安堵と興奮の交錯した感情で、これに和
した。
機転の利くウィリアム公と、彼を援けるオズバーン親衛隊長のコンビ
の面目躍如たるものがあった。
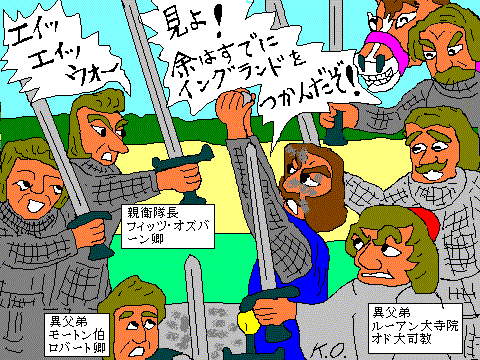
兵士も、馬も武器も、必要な物は何一つ損傷することなく、全部陸揚
げされた。
上陸作戦は、完全に成功した。兵士・軍属・水夫合計1万2千名の
大軍であった。
ウィリアム公と重臣達は、直ちに会議を開いた。
側臣ウォルターが地図を展げた。彼の部下が調べ上げていた詳細な
サセックスの地図であった。
オド大司教、ロバート卿、フイッツ・オズバーン卿、ユーステス伯等の
面々が、ウィリアム公の手許を窺き込んだ。
「此処は上陸地としてはよいが、守りに不向きだ。今から東へ向かう。
目的地はへイスティングズである。へイスティングズには小高い丘が
ある。この丘を当分の間、露営地とする」
「了解!」
装備を着け、隊伍を整えた各部隊は、10マイル余り東の、へイスティ
ングズ目指して次々と出発した。
古くから五大港の一つとして、商業や漁業で賑わっているへイスティ
ングズの町には、海峡を見下す小高い丘がある。海に面した方は、
切り立った崖になっている。
この崖下の港に軍船を繋留しておけば、少人数の警備兵で十分管
理ができる。丘の上からは、北に向かって緩やかに下り傾斜した丘
陵地帯が一望の下に見渡せる。
ウィリアム公は、この丘に急造の砦を構築した。いや、正確には組み
立てたというべきであろう。
ペペンジー湾から回航された輸送船から、兵士の兵糧や葡萄酒の
樽とともに、木材や板戸が陸揚げされた。それらの木材や厚板には
すでに切り込みがされており、記号が書き込まれてあった。
ウォルター輩下の城大工が、兵士達を指導して、これらの木材や厚
板を組立てていくと、アッという間に、厚板張りの砦と、雨露をしのぐ
兵舎が建ち上った。
何と物見櫓さえ組立てられたではないか。
丘の上に出来上った砦は、板張りではあったが、ノルマン軍団の兵
士達に、何にも勝る安堵感を与えた。
彼等は、喚声をあげて、砦の完成を喜んだ。ウィリアム公は、このへ
イスティングズに2週間滞在して、ひそかにハロルド王の動静を探っ
た。
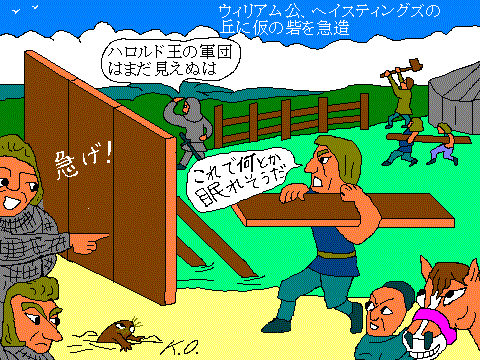
第18章 項垂れし聖像へ
いざないと目次へ戻る
「見よ、あの彗星を」Do You Know NORMAN?へ戻る
ホームページへ戻る